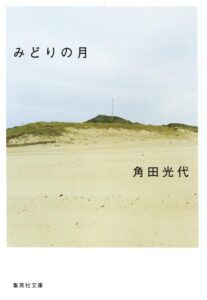 小説「みどりの月」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんが描く、どこか息苦しく、それでいて目が離せない世界へ、少しだけ足を踏み入れてみませんか。
小説「みどりの月」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんが描く、どこか息苦しく、それでいて目が離せない世界へ、少しだけ足を踏み入れてみませんか。
この物語は、日常に潜む奇妙さや、逃れられない人間関係のもどかしさを巧みに描き出しています。読んでいる間、主人公たちの行動に「なぜ?」と問いかけたくなるかもしれません。共感できる部分もあれば、全く理解できない部分もあるでしょう。
読み進めるうちに、もしかしたらあなた自身の心の奥底にある、言葉にならない感情や矛盾に気づかされるかもしれません。それは心地よい体験ではないかもしれませんが、深く記憶に残る読書になるはずです。
この記事では、「みどりの月」がどのような物語なのか、そして私がこの作品を読んで何を感じ、考えたのかを、ネタバレも避けずに詳しくお話ししていきたいと思います。少し長い道のりになりますが、お付き合いいただけると嬉しいです。
小説「みどりの月」のあらすじ
物語は、主人公である南が、恋人のキタザワのアパートへ転がり込むところから始まります。会社を辞め、行くあてもなかった南にとって、それは一時的な避難場所のはずでした。しかし、そのアパートには奇妙な先住者がいました。キタザワの「妹」だと名乗るマリコと、その恋人だというサトシです。
キタザワは特に説明もせず、南はその不可解な四人での共同生活を受け入れざるを得なくなります。マリコとサトシはほとんど働かず、家事もしません。部屋は散らかり放題で、生活のリズムもバラバラ。南は一人、苛立ちを感じながらも、甲斐甲斐しく掃除や料理をこなす日々を送ります。
キタザワは優しいけれど、どこか掴みどころがなく、現状を変えようとはしません。「めんどくさい」が口癖で、南の不満にも真剣に向き合おうとしません。マリコは時折、不可解な言動で南を惑わせ、サトシは影が薄く、何を考えているのか分かりません。
南は何度もこの歪な関係から抜け出そうと考えますが、キタザワへの情や、行くあてのない不安から、結局その場に留まり続けてしまいます。次第に、南自身もこの怠惰で無気力な空気に染まっていくような感覚に襲われます。掃除をする気力も失せ、散らかった部屋で彼らと同じように過ごす時間が増えていきます。
この作品集にはもう一編、「かかとのしたの空」が収録されています。こちらは、仕事を辞めた夫・克彦とともに、すべてを捨てて東南アジアへ旅に出た女性・多佳子が主人公です。彼らは自由を求めて旅を続けますが、行く先々で不気味な日本人女性につきまとわれるようになります。
その女性は、かつて自分を捨てた男を探していると言い、多佳子たちの行く先に必ず現れるのです。彼女の存在は、自由であるはずの旅に不穏な影を落とし、多佳子の心を掻き乱します。逃げても逃げても追ってくる存在から、彼らは解放されるのでしょうか。二つの物語は、逃避しようとしても絡みついてくる現実や人間関係の不気味さを描いています。
小説「みどりの月」の長文感想(ネタバレあり)
角田光代さんの「みどりの月」、読み終えた後のこの何とも言えない、ざわざわとした感覚は一体何なのでしょうか。正直に申し上げると、読んでいる間、ずっと居心地が悪かったのです。表題作「みどりの月」の主人公・南にも、「かかとのしたの空」の主人公・多佳子にも、なかなか感情移入することができませんでした。むしろ、彼女たちの行動や心理に、苛立ちや戸惑いを覚えることの方が多かったように思います。
「みどりの月」の南。恋人キタザワの部屋に転がり込んだら、そこには彼の「妹」マリコとその恋人サトシが同居していた。しかも、その関係性は非常に曖昧で、生活は怠惰そのもの。普通の感覚なら、すぐにでも「おかしい」「ここにはいられない」と感じるはずです。南も最初はそう感じ、一人で家事をこなし、苛立ちを募らせます。でも、なぜか彼女はその奇妙な共同生活から抜け出さない。それどころか、最後にはその淀んだ空気に飲み込まれていくようにさえ見えるのです。キタザワへの愛情なのか、それとも行く場所がないという諦めなのか。読みながら「早く逃げて!」と何度心の中で叫んだことか分かりません。
キタザワという男性も、掴みどころがありません。優しそうに見えて、その実、あらゆることから目を背け、「めんどくさい」の一言で片付けようとする。マリコやサトシとの関係も、南との関係も、すべてが曖昧で無責任。でも、南はそんなキタザワを拒絶しきれない。この「拒絶しきれない」という部分に、男女関係の不可解さや、ある種の依存のようなものが描かれているのかもしれません。解説にあった「共犯」という言葉が、妙に腑に落ちる感覚がありました。南もまた、この奇妙な生活の維持に、無意識のうちに加担してしまっていたのではないか、と。
そして、マリコ。彼女の存在はこの物語に、底知れない不気味さを与えています。自称「妹」でありながら、その言動は予測不能で、時に南を翻弄します。彼女は一体何者なのか、何を考えているのか。最後まで明確には語られません。サトシに至っては、さらに影が薄い。彼らの存在は、キタザワと南の関係性を映し出す鏡のようでもあり、同時に、日常に潜む不条理さや不可解さの象徴のようにも感じられました。彼らのいる空間は、まるで現実から切り離された、時間の流れが違う場所のようです。
南が抱える苛立ちは、読んでいるこちらにも伝染してきます。散らかった部屋、無気力な同居人たち、真剣に向き合おうとしない恋人。この状況は、私たちの日常にある些細なストレスや不満が増幅されたもののようにも思えます。だからこそ、南が最終的に抵抗を諦め、その空気に染まっていく様子には、一種の諦観とともに、妙なリアリティを感じてしまうのかもしれません。完璧な解決や脱出ではなく、現状を受け入れ、順応していく…それもまた、人が生きていくための一つの選択なのかもしれない、と考えさせられました。
一方、「かかとのしたの空」は、また違った形の「逃避」と「つきまとうもの」を描いています。夫・克彦とともにすべてを捨ててアジアを旅する多佳子。一見、自由で開放的な旅のように思えますが、そこには常に、あの不気味な日本人女性の影がつきまといます。この女性は、「みどりの月」のマリコを彷彿とさせます。小柄で、どこか常識が通じないような雰囲気を持ち、執拗に多佳子たちに関わろうとしてくる。
この女性の存在は、物理的な恐怖というよりも、心理的な圧迫感をもたらします。逃げても逃げても現れる彼女は、まるで多佳子自身の心の奥底にある不安や、過去から逃れられないという現実を突きつけてくるかのようです。「ユートピア」を求めて旅に出たはずなのに、結局はどこまでも「自分」という存在からは逃れられない。旅先でさえ、気づけば日本の日常と同じような心配事をし、小さな「枠」を作ってしまう。この描写には、逃避という行為そのものの虚しさや限界が示されているように感じました。
克彦もまた、仕事を辞めて旅に出たものの、どこか目的意識が希薄で、流されるままに生きているように見えます。「みどりの月」のキタザワと重なる部分もあります。彼ら男性陣は、現状を変える力強さを持つというよりは、むしろ状況に流され、責任から逃れようとする側面が強調されているように感じます。そして、女性たちはそんな彼らとの関係性の中で、もがき、悩み、時に諦め、時に順応していく。
二つの物語に共通して流れているのは、一種の閉塞感と、そこから抜け出そうとする試みの困難さです。そして、その試み自体が、新たな閉塞感を生み出してしまうという皮肉。角田光代さんは、人間の心の複雑さや矛盾、ままならない現実を、非常に巧みに、そして容赦なく描き出していると感じます。読後感がすっきりしない、モヤモヤするといった感想が多いのも、この容赦のない描写ゆえかもしれません。
正直、読んでいて楽しい物語ではありません。登場人物たちの行動原理は理解しがたく、共感よりも反発を覚えることの方が多いでしょう。特に、マリコや謎の女のような、常識や理屈が通じない存在は、生理的な嫌悪感や恐怖すら感じさせます。ある読者の方が「駄作」「時間返して欲しい」と感じたというのも、無理はないかもしれません。それほどまでに、この作品は読者の心を掻き乱し、不快な感情を引き起こす力を持っているのです。
しかし、その不快さや居心地の悪さこそが、この作品の持つ深さなのではないか、とも思うのです。私たちは普段、分かりやすい物語や、共感できる登場人物に安心感を覚えます。でも、現実の人生は、そんなに単純ではありません。理解できない他者、ままならない状況、自分の中にある矛盾した感情。そういったものと向き合わざるを得ない瞬間が、誰にでもあるはずです。
「みどりの月」は、そうした現実の複雑さや不確かさを、デフォルメされた形で突きつけてくる作品なのかもしれません。「いろんな気持ちが本当の気持ちだ」という言葉が作中にあったように、南や多佳子が抱える葛藤や揺らぎは、決して他人事ではない、普遍的な人間の姿を映し出しているのではないでしょうか。
逃げることは悪いことなのか? どこまで行けば本当に自由になれるのか? 他者との関係の中で、自分はどう折り合いをつけていけばいいのか? この物語は、明確な答えを与えてはくれません。ただ、読者一人ひとりに、重く、そして深く、問いを投げかけてきます。だからこそ、読み終えた後も、登場人物たちのことや、物語が問いかけてきたことを、ずっと考えてしまうのです。
もしかしたら、キタザワや克彦のように「めんどくさい」と目を背ける生き方にも、マリコや謎の女のように常識から外れた場所を漂う生き方にも、私たちが知らないだけで、何らかの理由や切実さがあるのかもしれない。そう考えると、単純に彼らを断罪することもできなくなってきます。この作品を読むことは、自分の価値観や常識を揺さぶられる体験でもありました。
好き嫌いははっきりと分かれるでしょうし、万人におすすめできる作品とは言えないかもしれません。しかし、人間の心の奥底にある混沌や、日常に潜む不穏な空気、そして「逃避」というテーマに興味がある方にとっては、忘れられない一冊になる可能性を秘めていると思います。心地悪さの先に、何かを見つけられるかもしれない。そんな期待を抱かせる、不思議な力を持った作品でした。
まとめ
角田光代さんの小説「みどりの月」は、読む人によって大きく評価が分かれる作品かもしれません。表題作「みどりの月」では、恋人の部屋で始まった奇妙な四人暮らしの中で、主人公・南が感じる苛立ちと、次第にその状況に順応していく様子が描かれます。怠惰な同居人たちと掴みどころのない恋人との生活は、息苦しさを感じさせます。
もう一編の「かかとのしたの空」では、すべてを捨ててアジアを旅する夫婦が、行く先々で不気味な女性につきまとわれるという、これまた不穏な物語が展開されます。自由を求めたはずの逃避行が、逃れられない現実や他者の存在によって脅かされていく様は、読んでいて心がざわつきます。
これらの物語は、日常からの「逃避」とその限界、人間関係の不可解さや曖昧さ、そして心の奥底に潜む混沌とした感情を、角田光代さんならではの鋭い視点で描き出しています。共感しにくい登場人物や、理解しがたい展開に戸惑うかもしれませんが、それこそがこの作品の持つ力なのかもしれません。
読後感は決して爽やかなものではなく、むしろモヤモヤとしたものが残るでしょう。しかし、そのモヤモヤこそが、私たち自身の日常や心のありようについて、深く考えさせてくれるきっかけになるのではないでしょうか。心地よい読書体験を求める方には向きませんが、人間の複雑さや人生のままならなさに触れたい方には、強く印象に残る一冊となるはずです。

























































