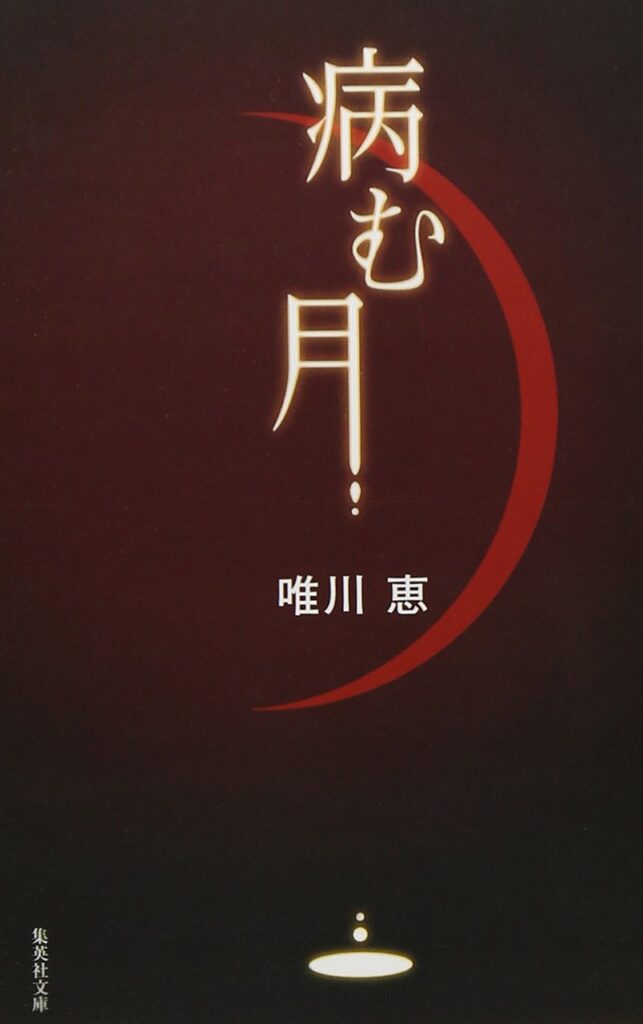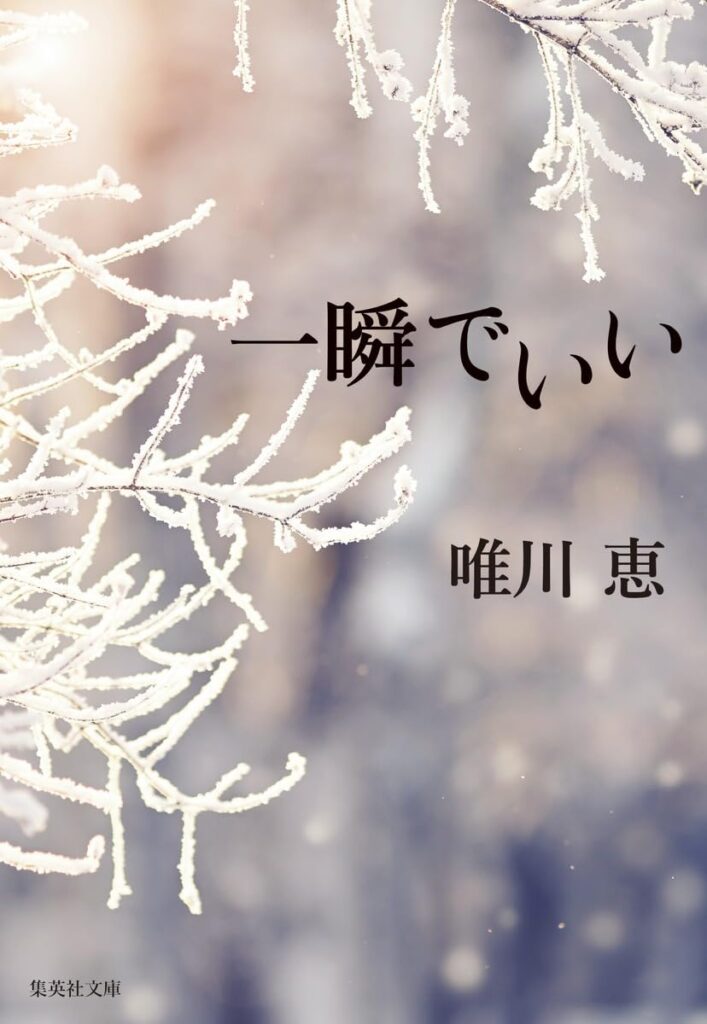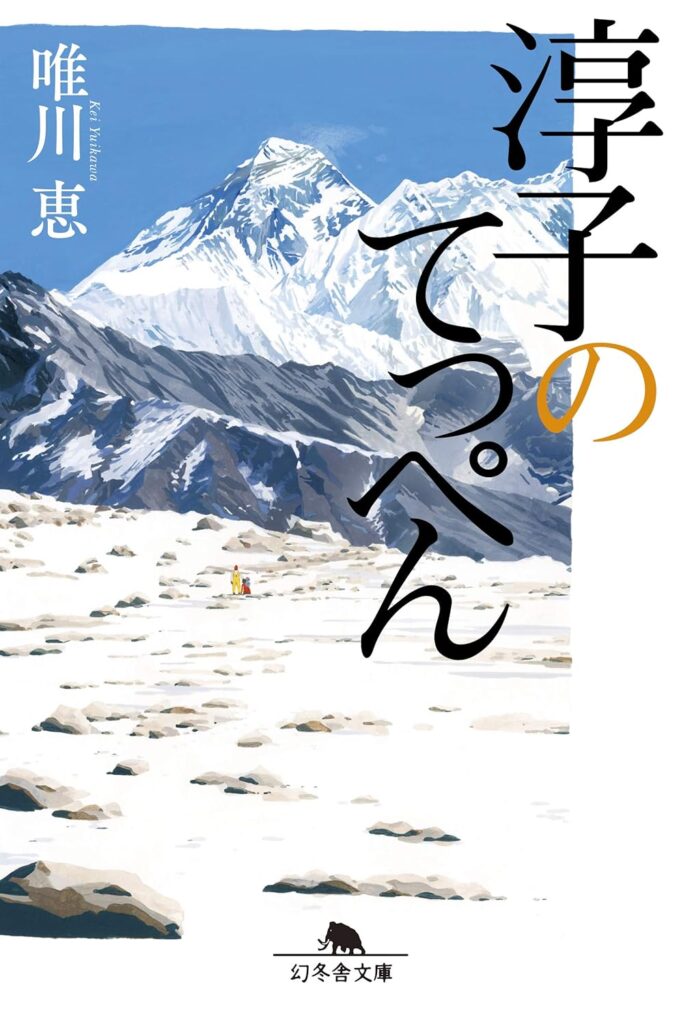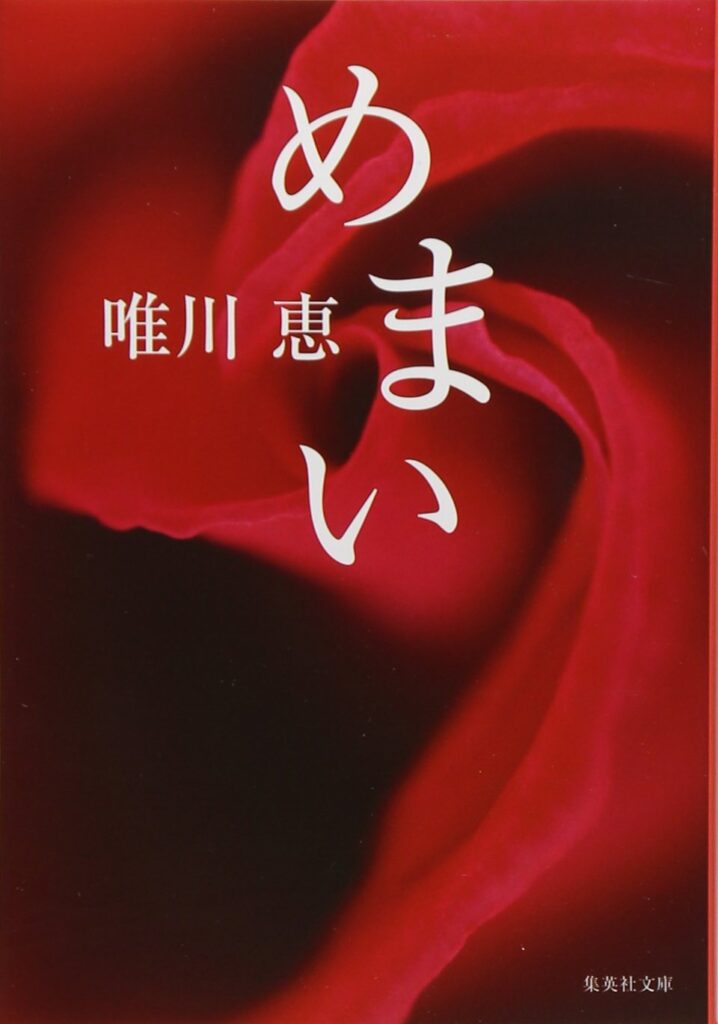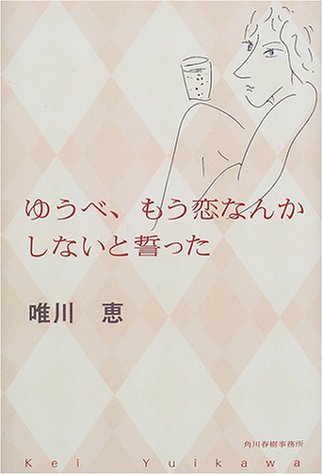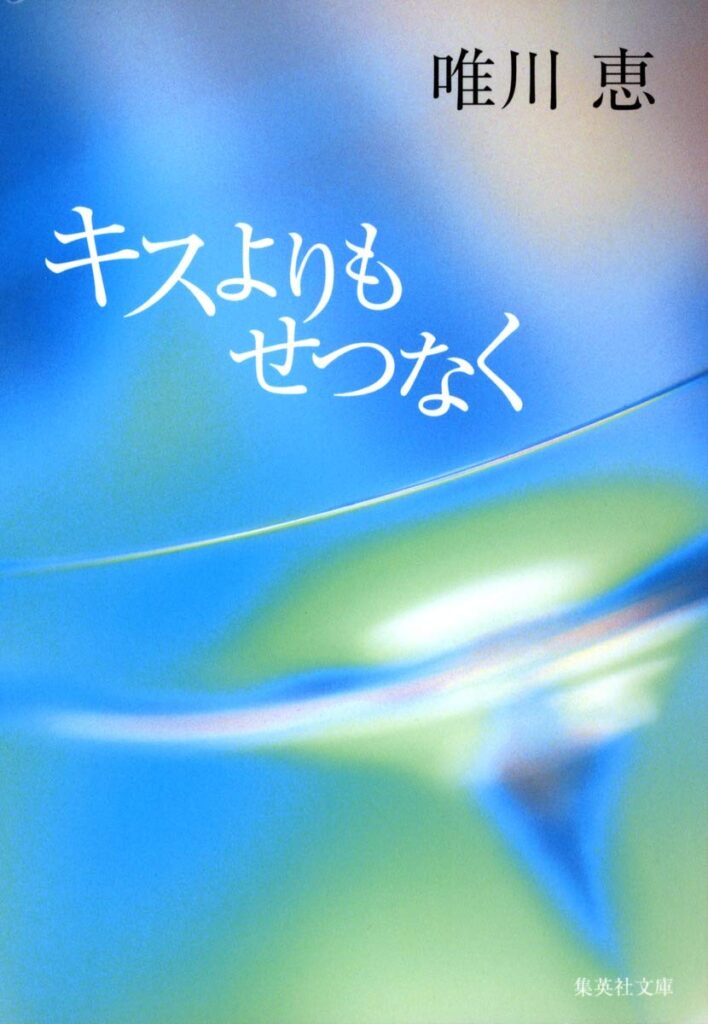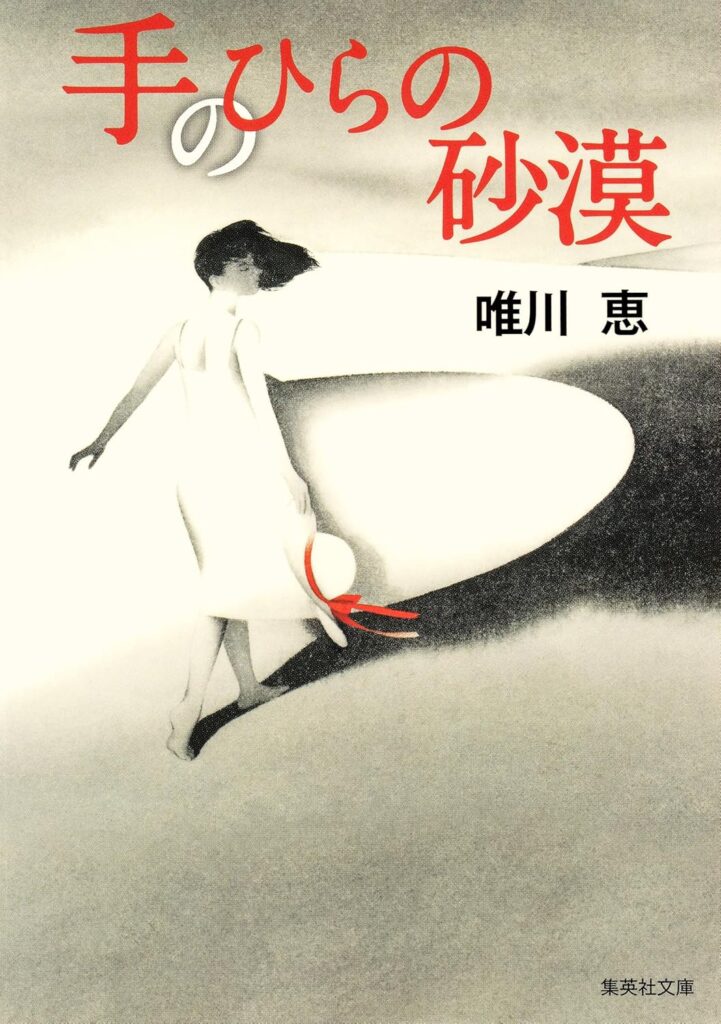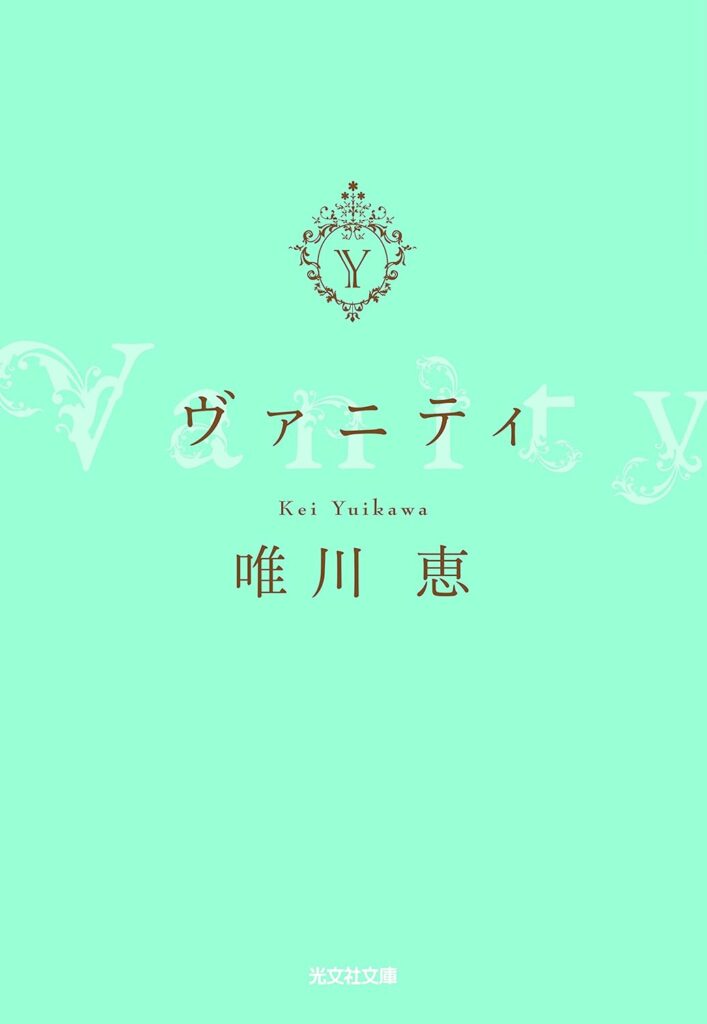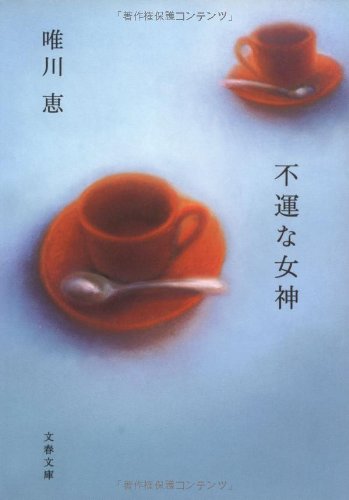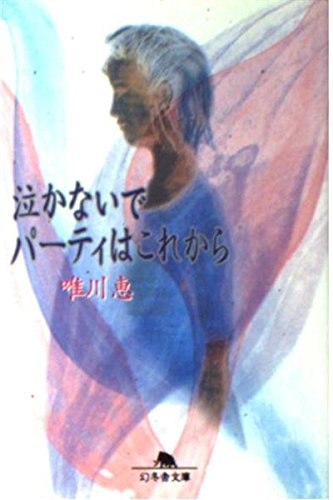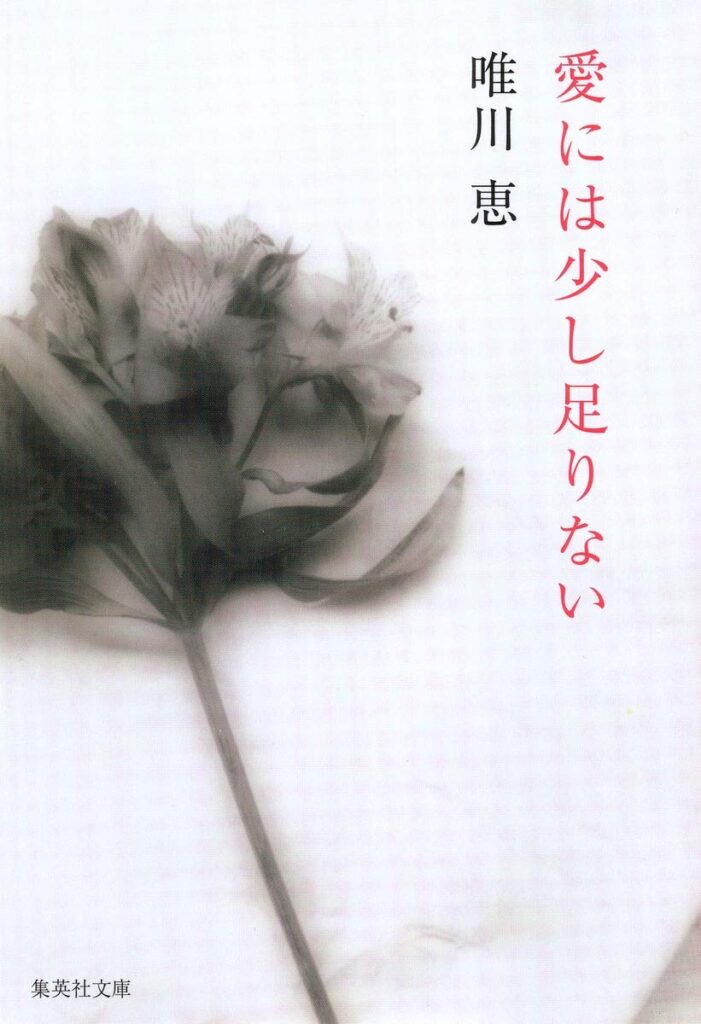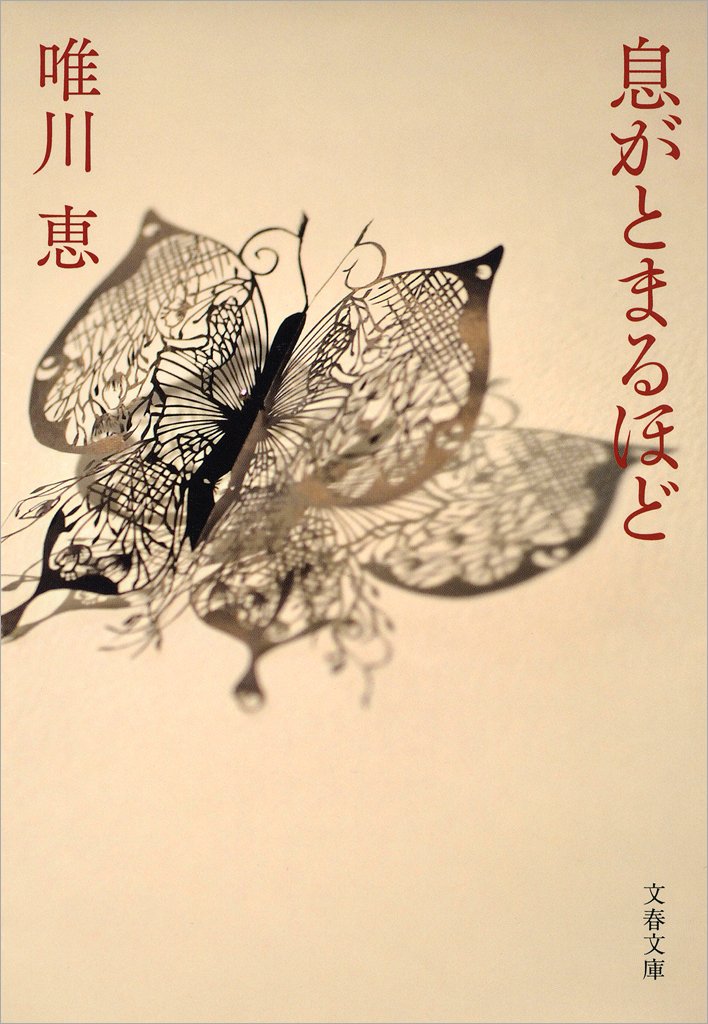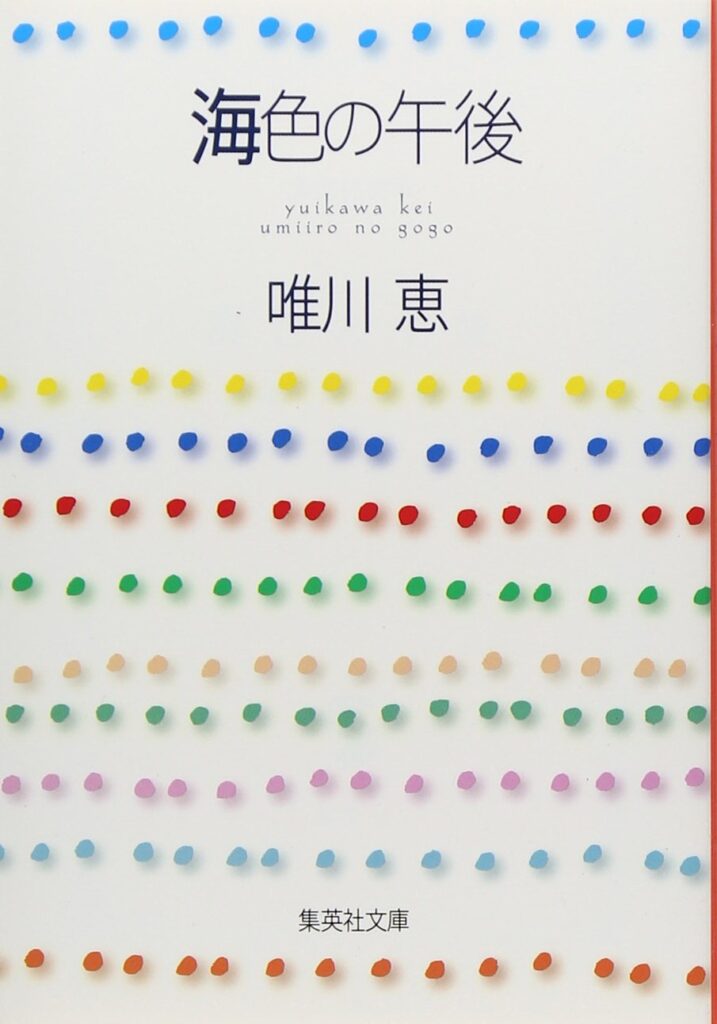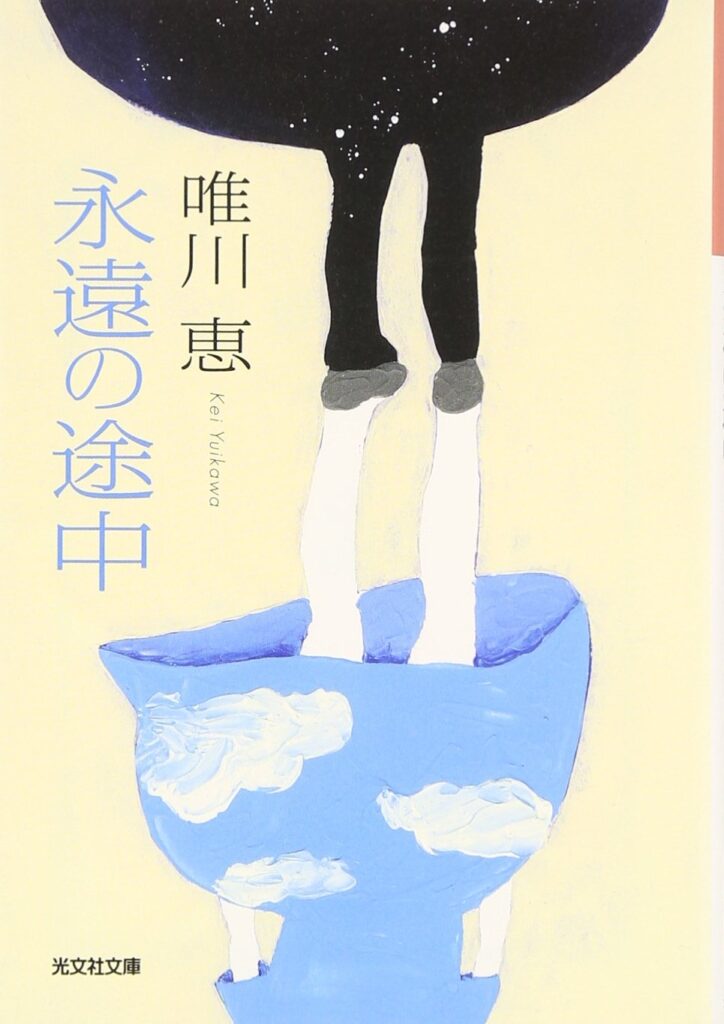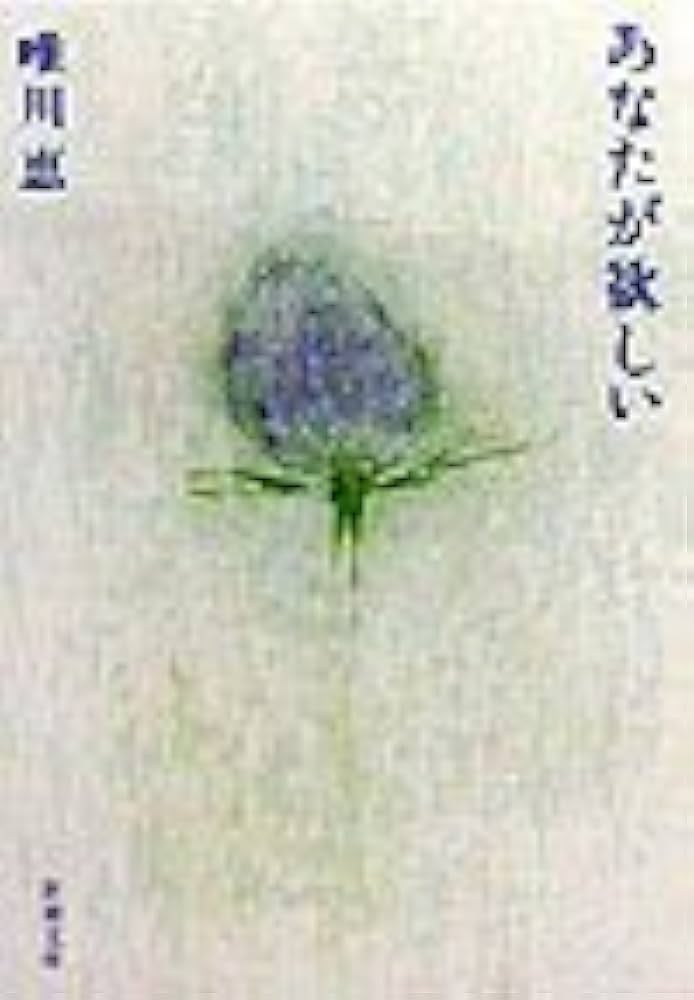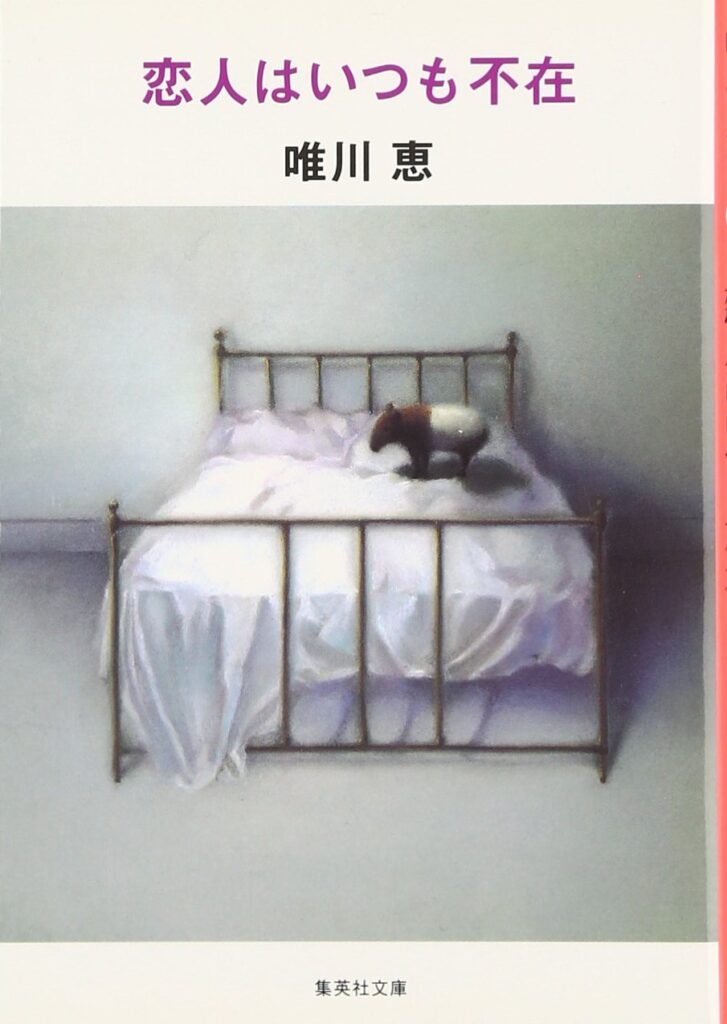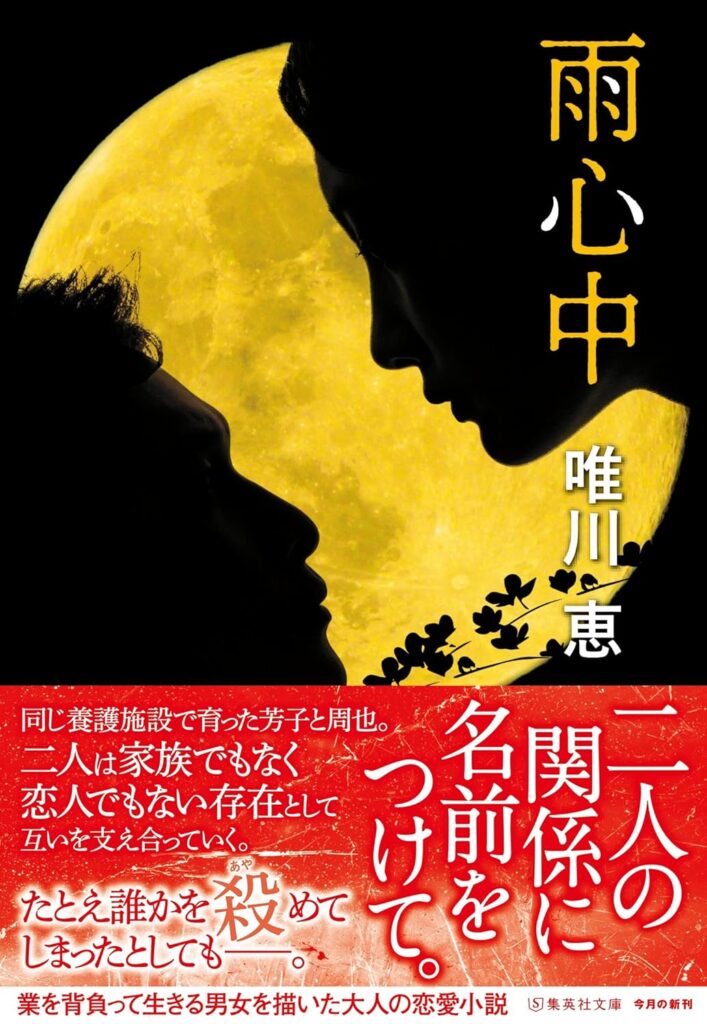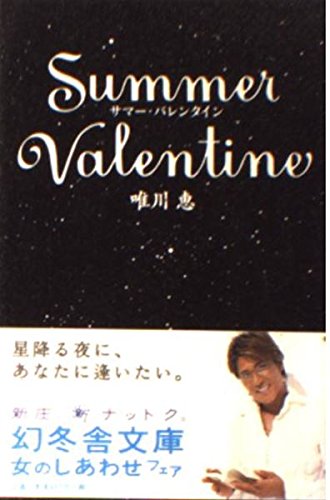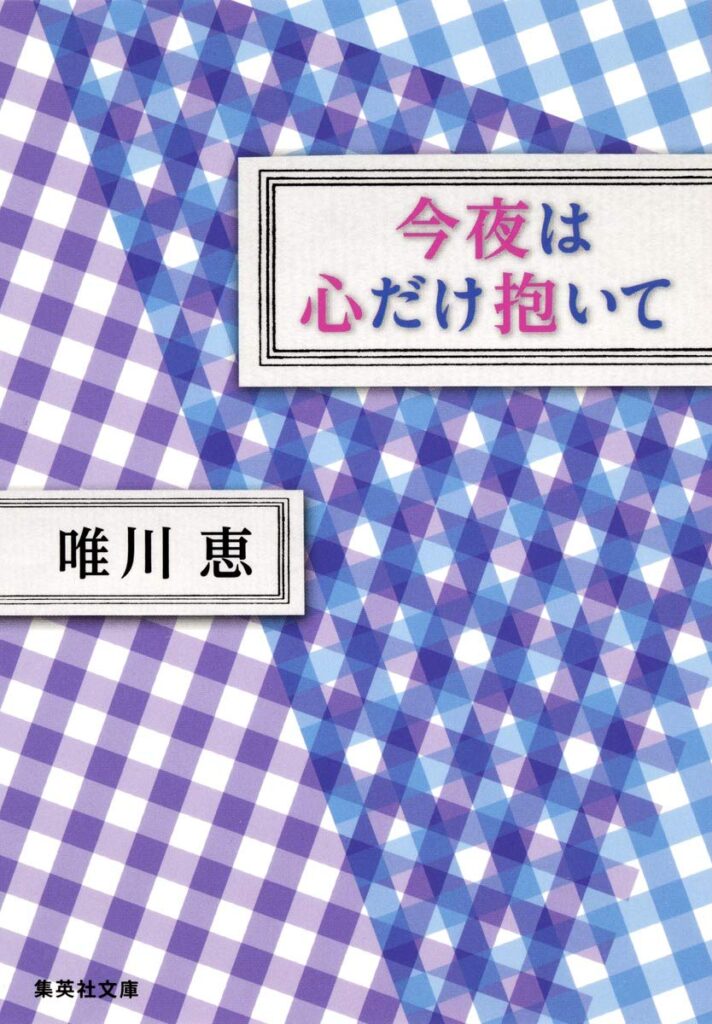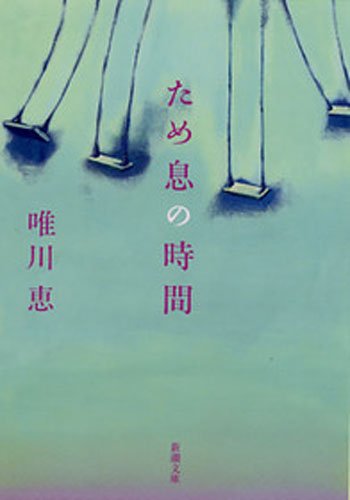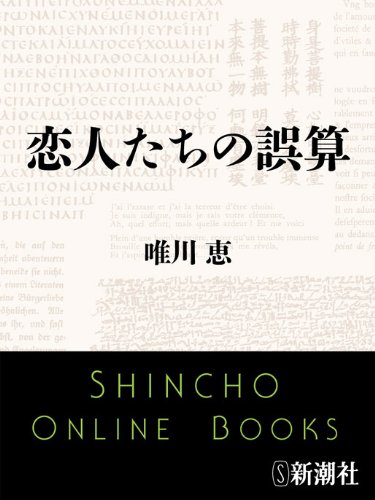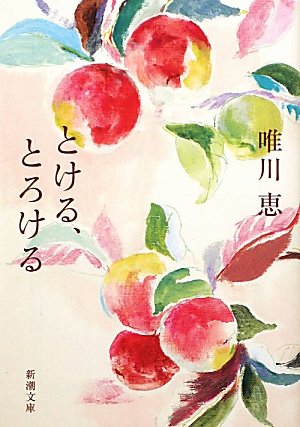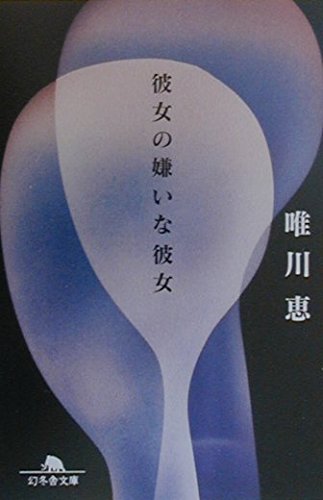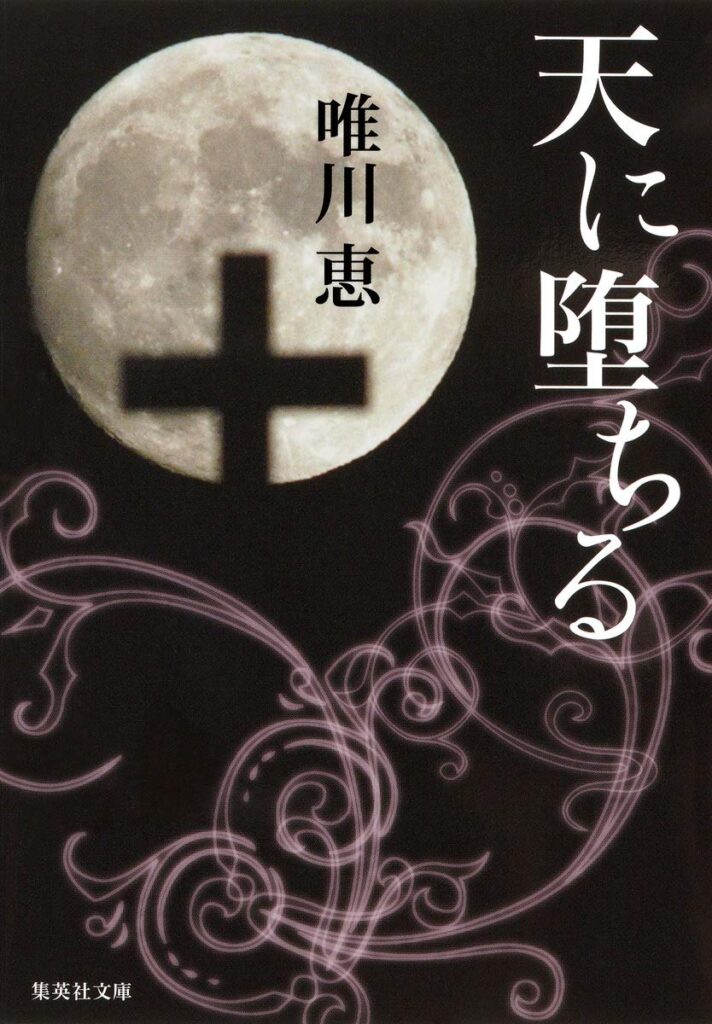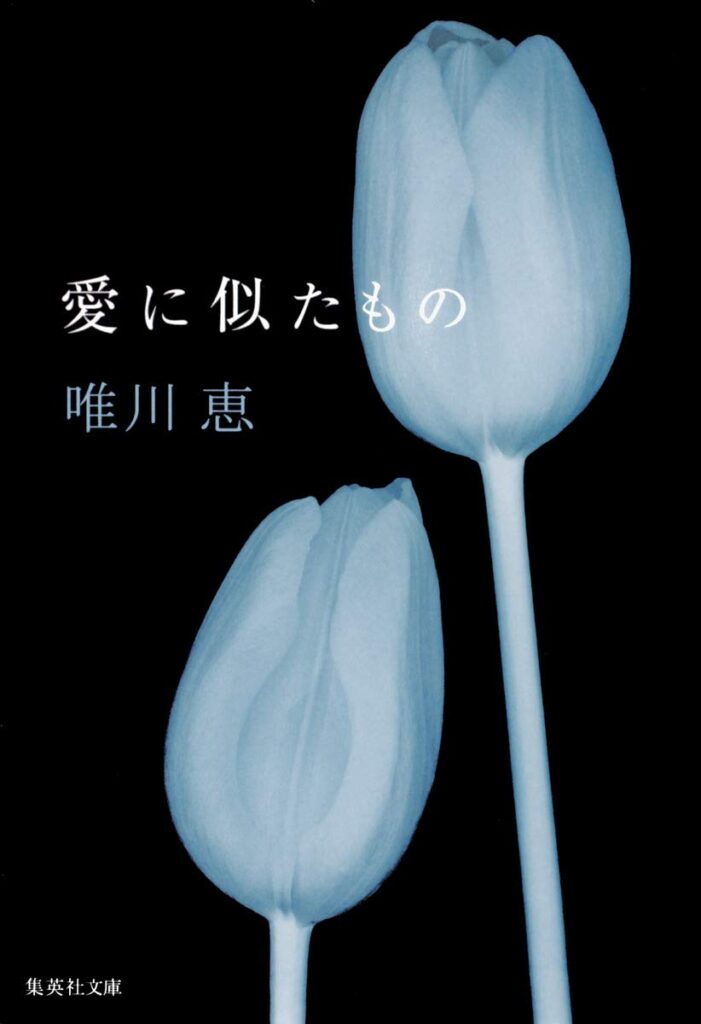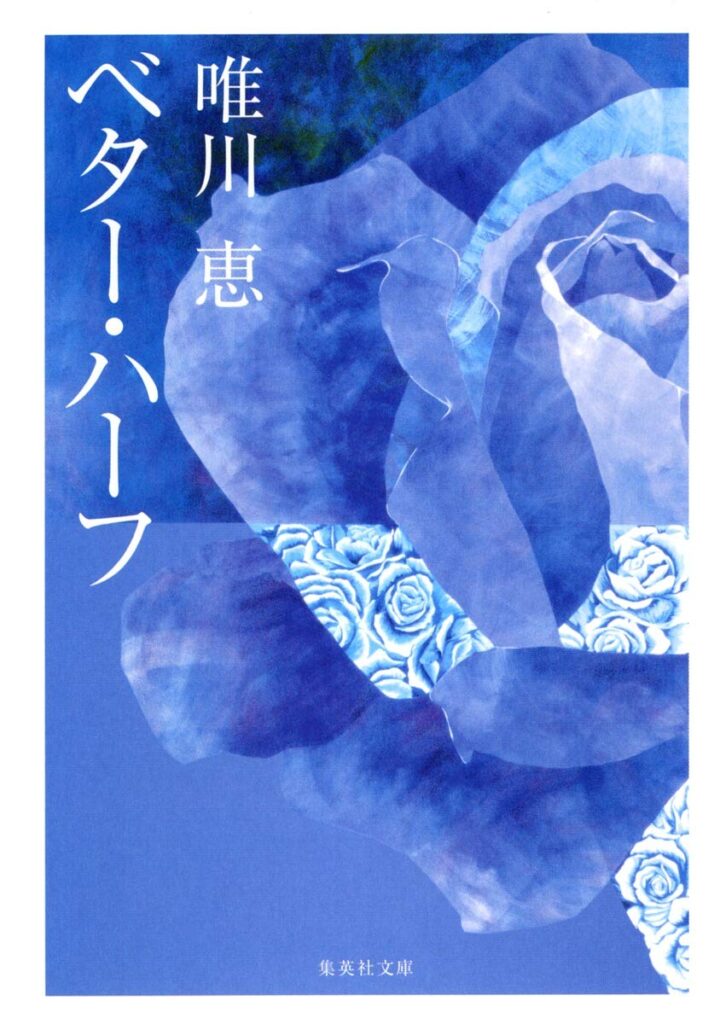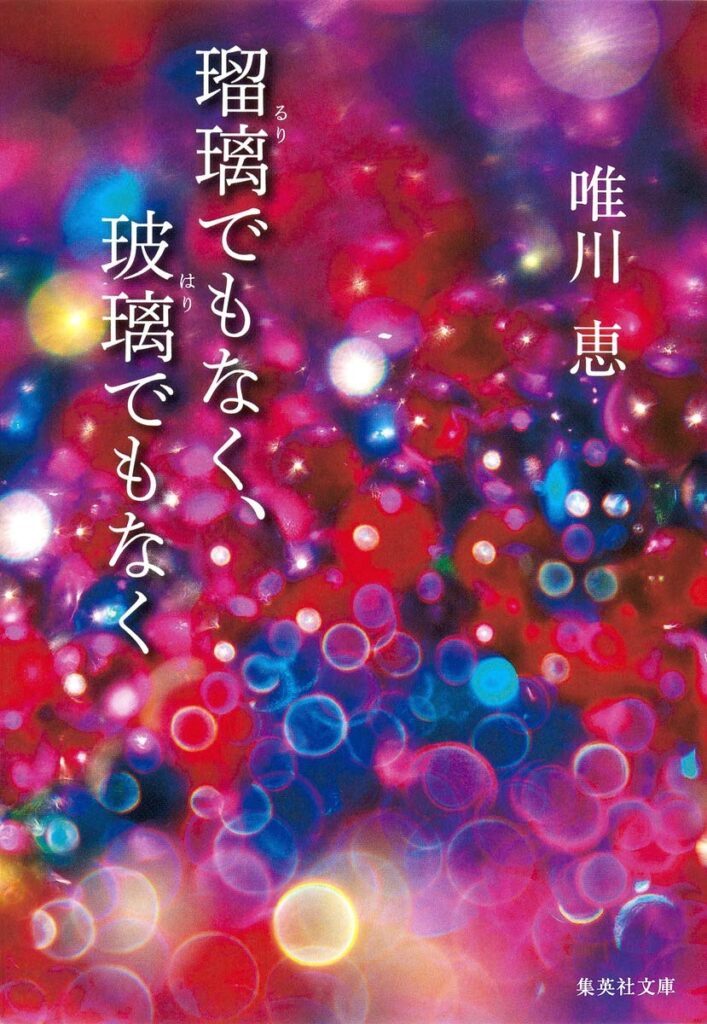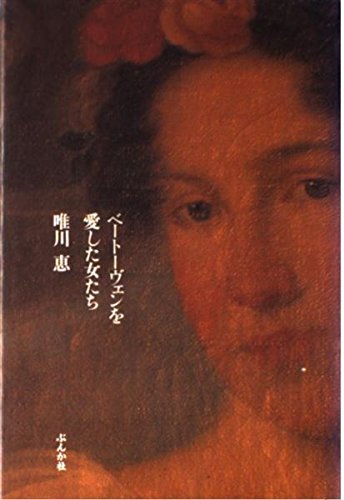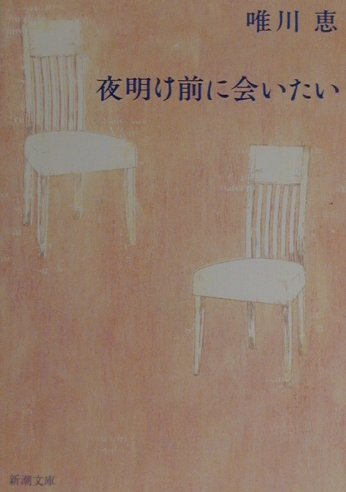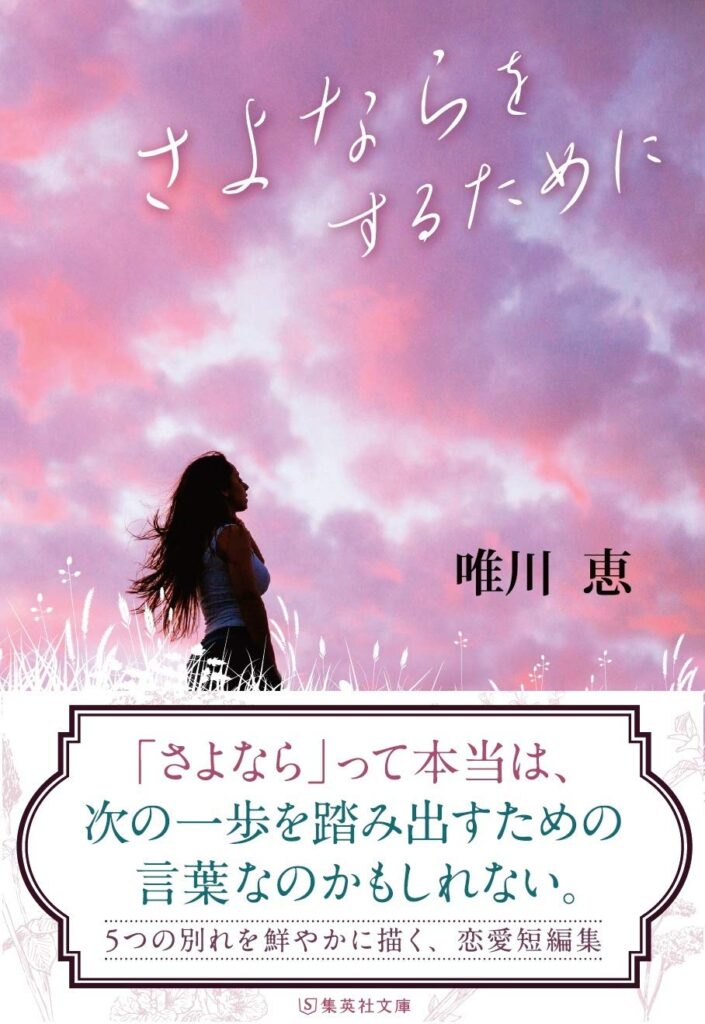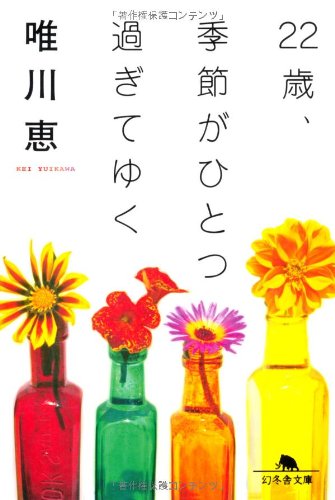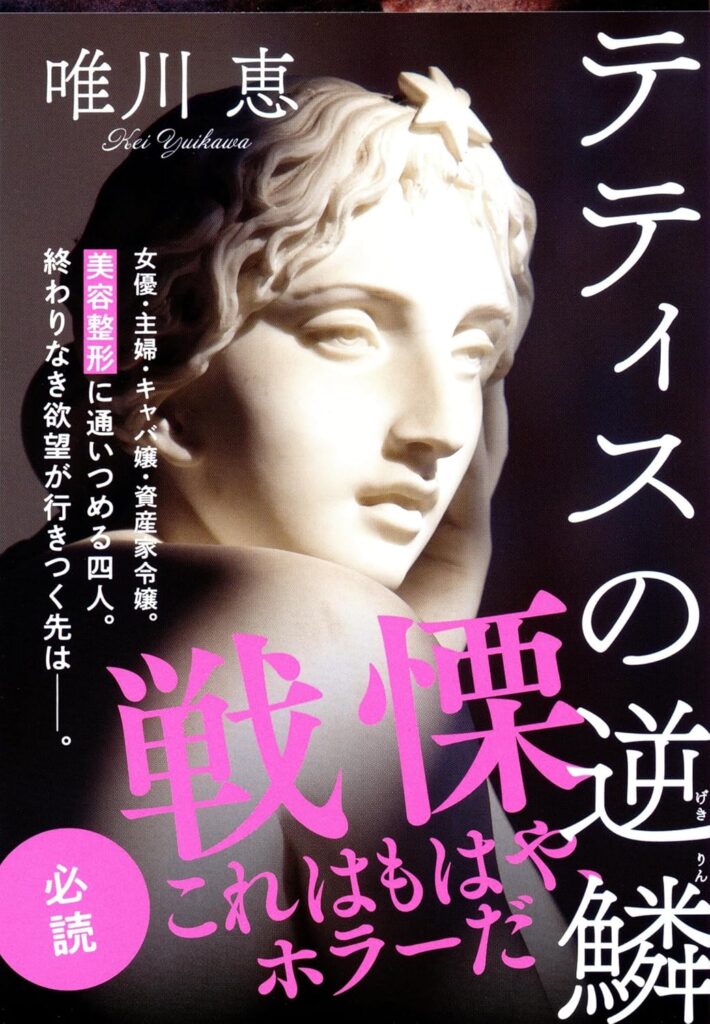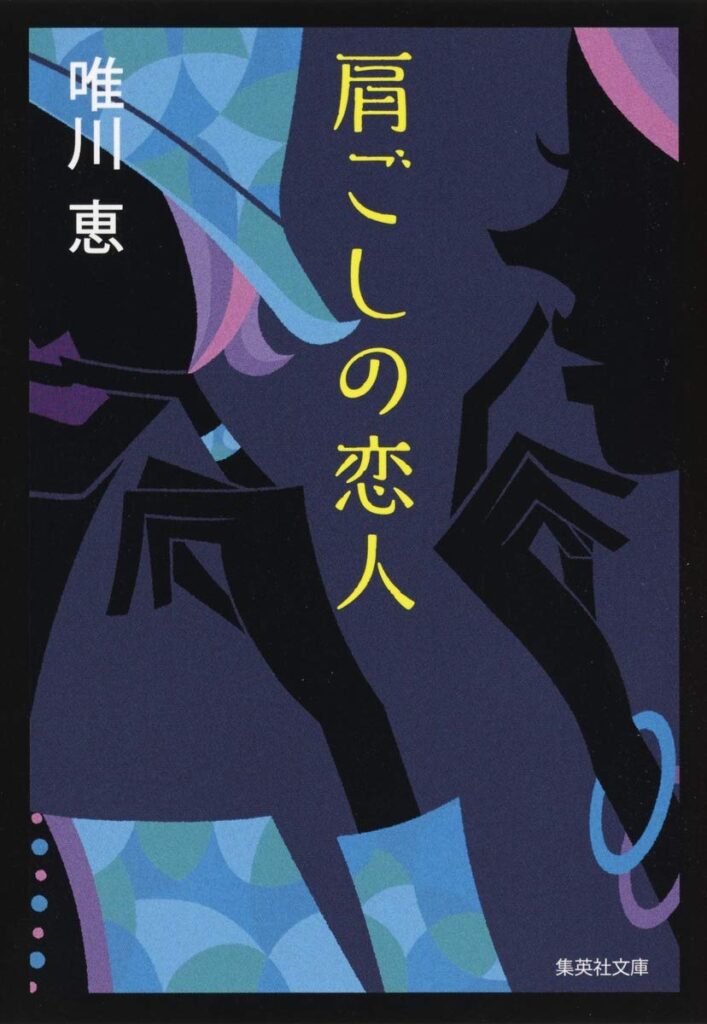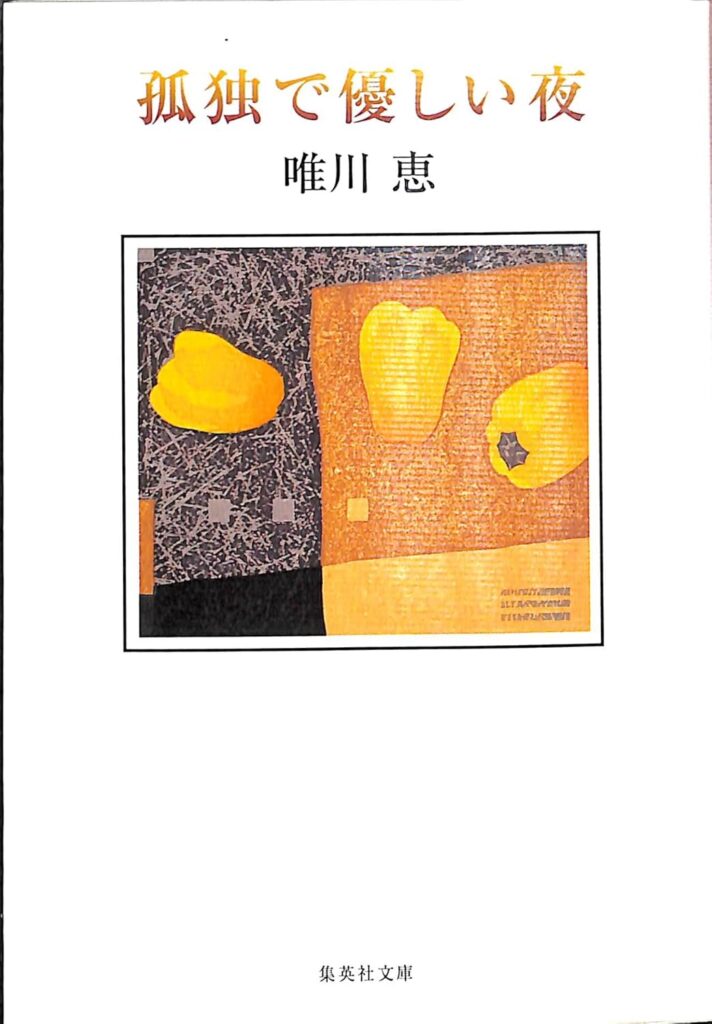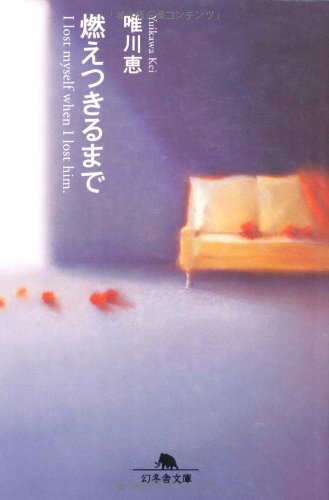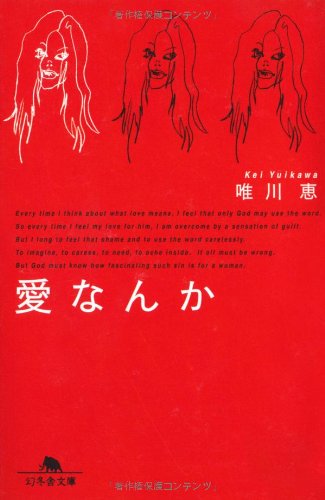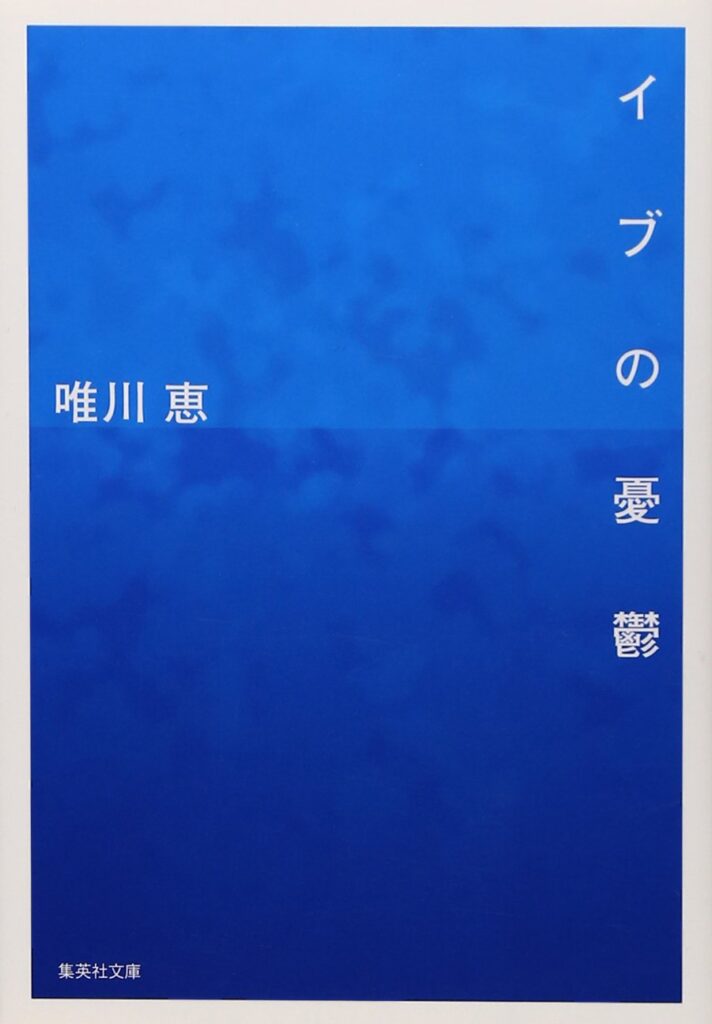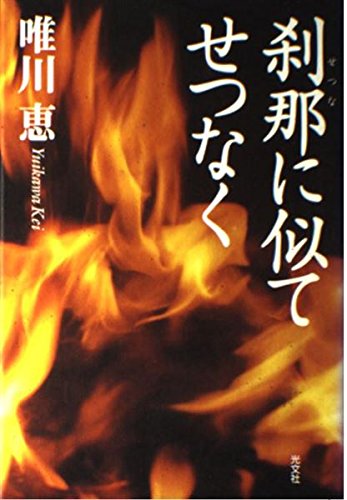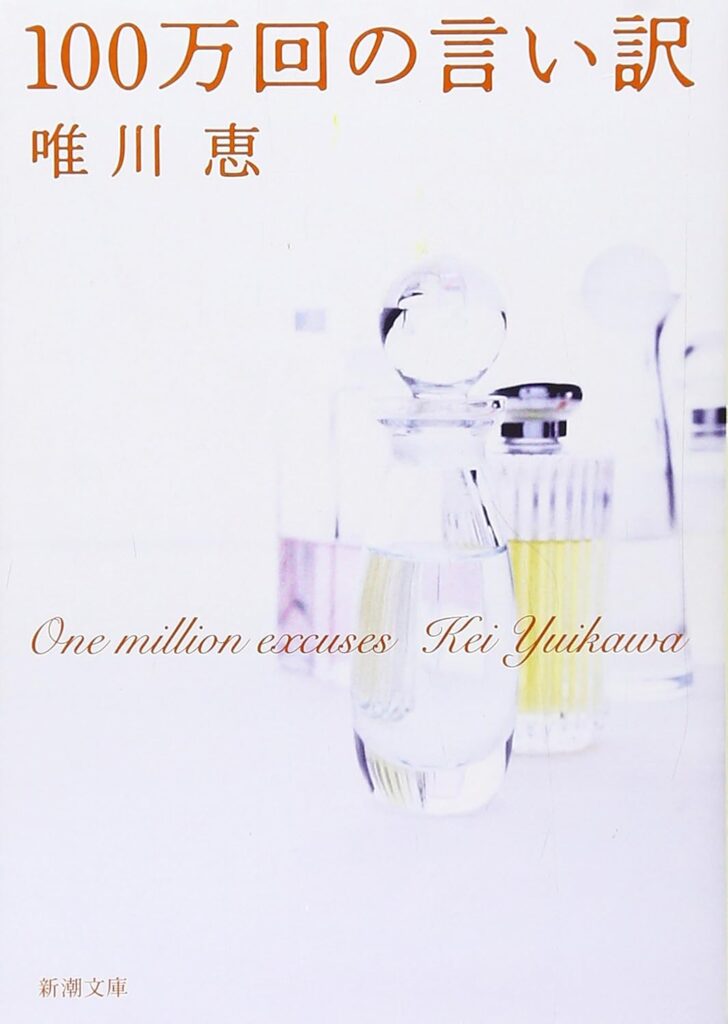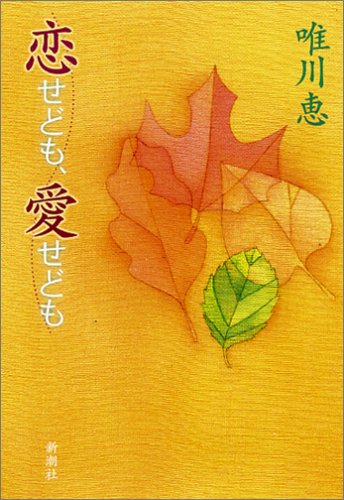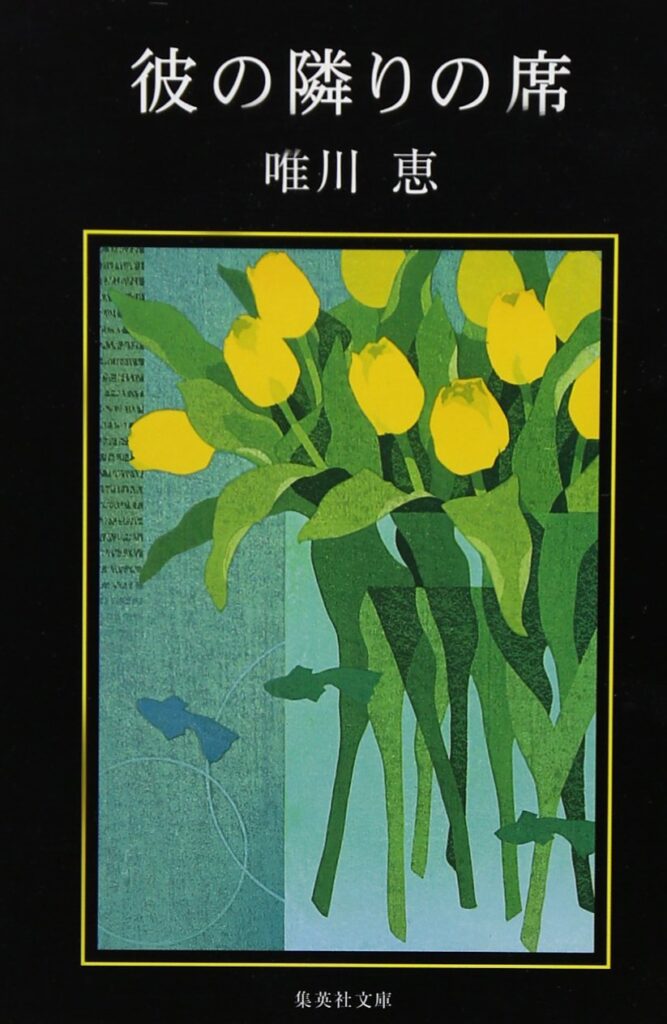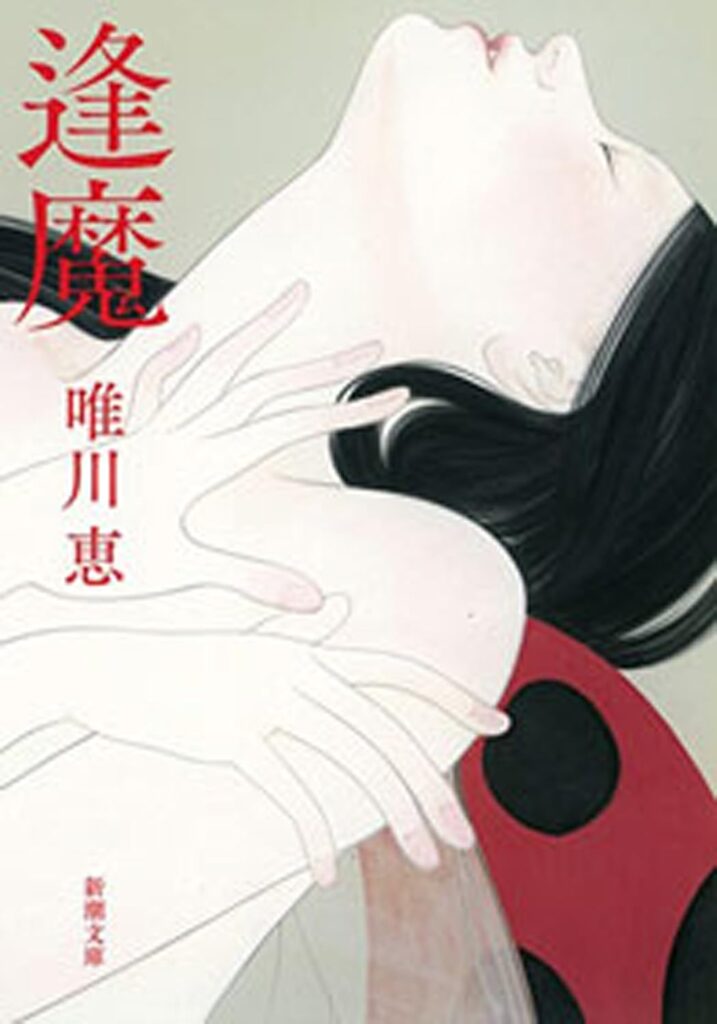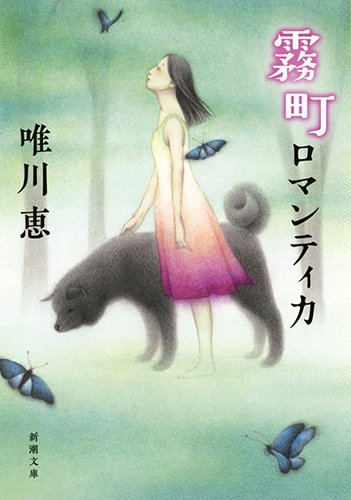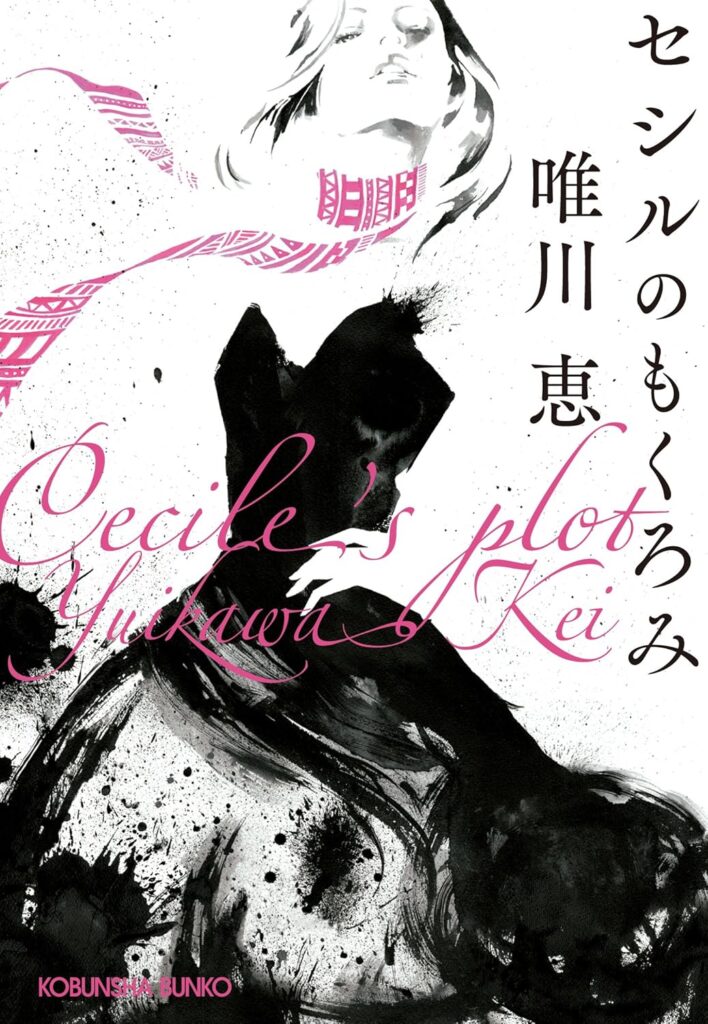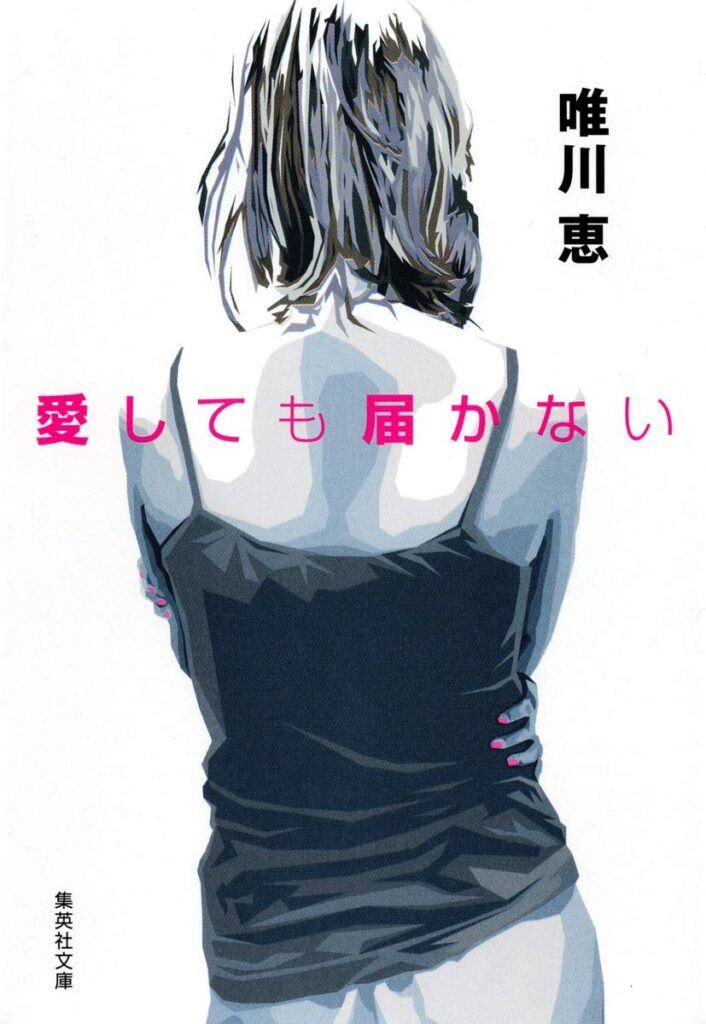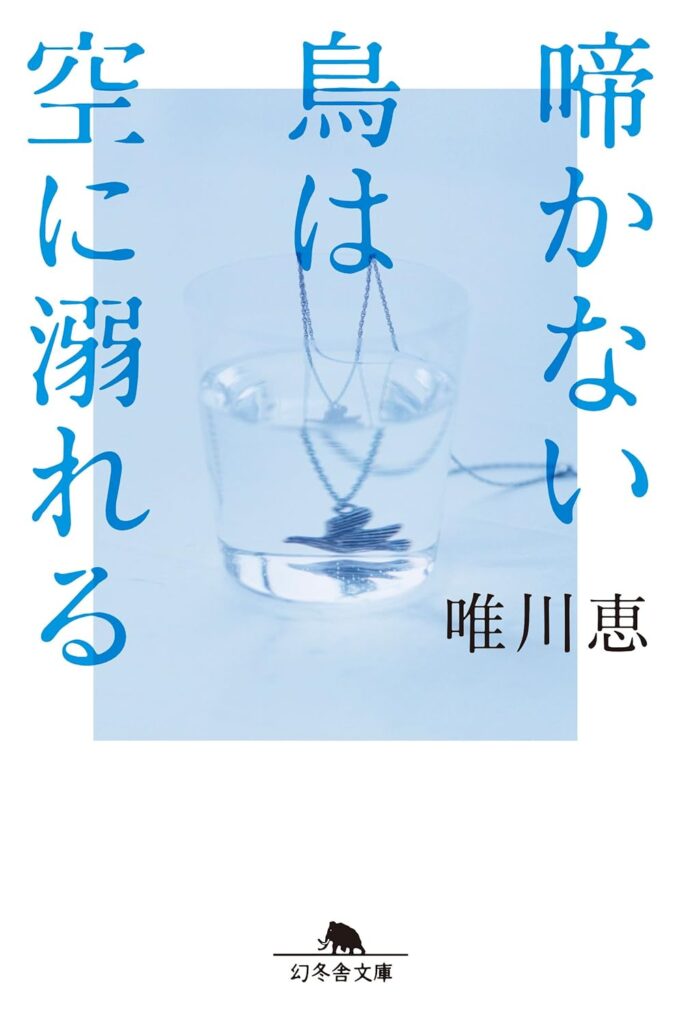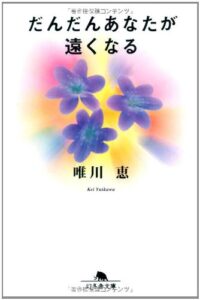 小説「だんだんあなたが遠くなる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。唯川恵さんが紡ぎ出す、胸を締め付けられるような、それでいてどこか私たちの日常にもありふれた人間関係の物語に、心を深く揺さぶられたという方もきっと多いことでしょう。
小説「だんだんあなたが遠くなる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。唯川恵さんが紡ぎ出す、胸を締め付けられるような、それでいてどこか私たちの日常にもありふれた人間関係の物語に、心を深く揺さぶられたという方もきっと多いことでしょう。
この物語は、過去の恋愛によって心に傷を負い、都会の喧騒を離れて新たな一歩を踏み出した主人公・萩(はぎ)の視点から語られていきます。彼女が園芸店で見つけたささやかな安らぎと、そこで出会った恋人・要司(ようじ)との間に芽生えた穏やかな時間。しかし、その平穏は、萩の古い友人である、いづみの突然の訪問によって静かに波紋を広げ始めるのです。
いづみがその身に抱える、誰にも打ち明けられない秘密。そして、その秘密を共有し、彼女を支えようとすることで、萩と要司の関係性は少しずつ、しかし確実に変容していくことになります。愛する人が、自分ではない誰かに心を寄せていくのではないか。そんな予感とめまぐるしく変わる現実に、萩の心は静かに、けれど深くかき乱されていく様子が描かれます。
本記事では、そんな「だんだんあなたが遠くなる」の物語の核心部分に触れつつ、登場する人物たちの心の細やかな動き、そして読み終えた後も長く心に残り続ける、この作品ならではの魅力について、じっくりと語り明かしていきたいと考えています。唯川恵さん特有の、等身大の女性が抱える感情の描写にも、ぜひご注目ください。
小説「だんだんあなたが遠くなる」のあらすじ
物語は、主人公である萩が、心に深い傷を残した過去の恋愛と会社員生活に区切りをつけ、新しい自分を求めて園芸店で働き始めるところから静かに幕を開けます。緑に囲まれた場所で、彼女は予備校講師の要司と出会い、二人は自然な成り行きで恋人同士となります。ようやく手に入れた穏やかで満ち足りた新しい日々が、このまま続いていくかのように思われました。
そんな萩のもとへ、ある日、大学時代からの親しい友人である、いづみが何の連絡もなく突然訪ねてきます。いづみは萩の故郷、長野で暮らしていたはずの友人でした。しかし、久しぶりに再会した彼女の表情にはどこか暗い影が落ち、以前の快活さは見られません。彼女は、妻子ある男性との許されない関係の末に妊娠し、相手からは冷たく別れを告げられたという、重く苦しい現実を一人で抱え込んでいたのです。
萩と恋人の要司は、身重でありながら誰にも頼れず行き場を失ったいづみを見過ごせませんでした。特に要司は、いづみが置かれた困難な状況に深く同情し、親身になって彼女の相談に乗り、精神的な支えになろうとします。こうして、萩と要司、そしていづみという、どこかぎこちなくも温かい、三人の共同生活が始まることになったのです。
しかし、三人で同じ屋根の下で過ごす時間が増えるにつれて、萩は、恋人である要司の心が、少しずついづみの方へと傾いていくのを敏感に感じ取ってしまいます。要司がふとした瞬間にいづみに向ける優しさや眼差しが、単なる同情や友情を超えた、特別な感情のように萩の目には映ってしまうのでした。萩の心の中には、言葉にできない不安と、どうしようもない寂しさが静かに募っていきます。
萩が抱いていたその予感は、悲しいことながら、やがて否定しようのない確信へと変わっていきます。要司といづみの間には、いつしか萩が踏み込むことのできない、二人だけの親密な空気が流れ始めていたのです。愛する人の心が、静かに自分から離れていこうとしている。その抗えない事実を、萩は心のどこかで静かに受け止め始めていました。そして、深い苦悩と葛藤の末に、彼女はひとつの大きな決断を下すことになります。
萩は、要司といづみ二人のこれからの幸せを心から願い、自ら身を引くという道を選びます。「大好きだから、ふってあげる」。彼女はそう心の中で静かに呟きながら、愛した人たちの元を黙って去り、再び一人きりで新たな道を歩き出すことを決意するのでした。それは、愛する人を手放すという、あまりにも切なく、そして痛みを伴う選択だったのです。
小説「だんだんあなたが遠くなる」の長文感想(ネタバレあり)
読み終えた後、胸の内に広がるのは、言葉では簡単に表現し尽くせない、切なさにも似た感情の波でした。「だんだんあなたが遠くなる」という作品は、単に恋愛が終わりを迎える物語というだけではなく、愛とは何か、友情とは何か、そして何よりも、自分自身とどう向き合い、どう生きていくのかという、私たち誰もが抱える普遍的な問いを、静かに、しかし深く投げかけてくるように感じられます。その問いは、読者の心に長く残り、ふとした瞬間に思い出されては、自らの経験と重ね合わせてしまうような、不思議な力を持っているのです。登場人物たちの息遣いがすぐそこに感じられるようなリアリティと、物語の結末が示すほろ苦い真実が、いつまでも心から離れません。
作者である唯川恵さんは、かつて銀行にお勤めだったというご経歴をお持ちで、その経験が作品世界に独特の深みを与えているように思います。特に、働く女性が日常で感じる細やかな感情の揺れや、人間関係の中で抱えることになる複雑な思いを捉える筆致は、多くの読者から共感を得ています。「だんだんあなたが遠くなる」においても、主人公・萩の心の動き、言葉にはできない不安や、諦めに似た感情のグラデーションが、まるで自分のことのように生々しく伝わってきます。誰しもが一度は経験したことがあるかもしれない心の機微を、巧みな情景描写とセリフ回しで鮮やかに描き出すその作風が、この物語でも遺憾なく発揮されていると言えるでしょう。
物語の始まり、主人公の萩は、過去の恋愛で深く傷つき、また、目的を見失いかけていた会社員としての生活にも別れを告げ、心機一転、新しい自分として歩み出そうとしています。裏切られた恋の痛みも、日々の繰り返しに感じていた空虚さも、すべてを洗い流すかのように選んだ園芸店での仕事。そして、そこで出会った要司という存在は、彼女にとってまさに暗闇に差し込む一筋の光であり、未来へのささやかな希望だったはずです。しかし、古くからの友人であるいづみの予期せぬ出現によって、その築き上げたばかりの新しい生活がいかに繊細で、脆い基盤の上に成り立っていたのかが、容赦なく露呈してしまうのです。再生への淡い願いが、過去からやってきた親友の影によっていともたやすく揺らぶられる。この、希望と、それを打ち砕くかのような現実とのコントラストが、物語全体の切なさをより一層際立たせているように私には感じられました。
親友であるいづみを助けたいという純粋な思いやりと、彼女の存在が自分の大切なものを奪ってしまうかもしれないという、拭い去ることのできない恐れ。萩の心の中では、この二つの相反する感情が、絶えず激しく渦巻いていたことでしょう。表面上は彼女を心配し、できる限りの気遣いを見せながらも、その実、内心では恋人である要司がいづみに向ける優しさや親密な態度の一つ一つに、鋭い嫉妬の感情を抱き、そして、そんな風にしか感じられない自分自身に対して、深い自己嫌悪を覚えていたのではないでしょうか。実際にこの作品を読んだ方々の中にも、こうした萩のどうしようもなく人間的な葛藤や心の揺れ動きに対して、「痛いほど気持ちがわかる」「自分も同じような経験をしたことがある」といった共感の声が多く見受けられます。この生々しさこそが、読者を引き込む大きな力となっているのです。
物語のクライマックスで萩が下す決断、そして彼女の心の中で静かに呟かれる「大好きだから、ふってあげる」という言葉は、この物語の核心を突くものであり、読者に深い印象を残します。この言葉だけを捉えれば、彼女は要司への深い愛情ゆえに、自らの気持ちを抑え、身を引くことを選んだのだと解釈できます。自分が身を引くことによって、結果的に要司といづみが結ばれ、二人が幸せになることを心から願う、ある種の自己犠牲に基づいた崇高な愛の形と言えるかもしれません。愛する人の幸福を何よりも最優先する、その選択はあまりにも切なく、胸を打ちます。
しかしながら、この萩の決断は、本当にそれだけの意味しか持たないのでしょうか。少し視点を変えて深く掘り下げてみると、これは、これ以上自分が傷つくことから巧みに身を守り、刻一刻と変化していく関係性の中で、自分自身の尊厳を保つための、非常に能動的な選択だったのではないか、とも考えられるのです。要司の心が自分から離れていくのを日々感じながら、ずるずると曖昧な関係を続けることの苦痛に耐えるよりも、自らの意志で関係に終止符を打つことによって、「自分自身を好きでい続けるため」の道を選んだとも言えるのではないでしょうか。つまり、愛する人を失うという計り知れない痛みを受け入れてでも、自分自身を大切にし、守り抜こうとした、静かながらも強い意志の表れだったと解釈することもできるのです。
この、一見すると自己犠牲的な愛と、その裏に隠された自己肯定への渇望という二つの側面。これこそが、萩という登場人物が持つ人間的な深みであり、この物語が読者に対して多様な解釈の可能性を提示し、長く考えさせる要因となっているのではないでしょうか。彼女は、物語にありがちな単なる「どこまでも優しい聖女」でもなければ、「一方的に傷つけられる哀れな被害者」でもありません。非常に複雑で、時には矛盾するような感情をその胸に抱えながらも、最終的には自分自身の確固たる意志に基づいて未来への道を選択していく、一人の等身大の人間として、鮮やかに描かれているのです。その姿に、私たちは自分自身を重ね合わせずにはいられないのかもしれません。
一方で、物語の中で重要な役割を担う男性キャラクター、要司という存在はどのように読み解けるでしょうか。彼は、困難な状況に陥っているいづみを決して見捨てることができない、心優しい人物として序盤では描かれます。妊娠し、誰にも頼ることができずに途方に暮れているいづみに対して、彼は親身になって相談に乗り、精神的な支えとなろうと努めます。その姿は、一見すると、多くの女性が理想とするような、包容力のある誠実な男性にも映るかもしれません。彼の行動は、人として正しいことをしているように見えます。
しかし、彼のその「優しさ」は、物語が進むにつれて、結果的に萩の心を深く、そして静かに傷つけていくことになります。萩といづみという二人の女性の間で揺れ動く彼の態度は、どこか煮え切らず、はっきりとした意思表示を避けているかのように見えます。実際に、この作品を読んだ方々の中からは、彼のその優しさに対して「結局は自分の感情に正直なだけで、エゴイスティックに見える」「別れを自分から切り出す勇気がなく、萩にその役目を押し付けているようでずるい」といった、かなり手厳しい意見も少なからず寄せられています。彼自身は、意図的に萩を傷つけようとしたわけではないのかもしれません。しかし、その受動的とも言える態度や、はっきりと言葉にしない曖昧な気持ちが、事態をより複雑化させ、最終的に萩に対して、あの辛く、重い決断を強いる一因となった側面は、決して否定できないでしょう。
要司というキャラクターは、物語全体に、一筋縄ではいかない「ままならなさ」や、白黒はっきりとは割り切れない複雑な感情(いわゆる「モヤモヤ」とした感覚)を巧みにもたらしています。そして同時に、「本当に優しい男性とは、一体どのような存在なのだろうか」という、古くて新しい問いを、私たち読者に静かに投げかけているようにも感じられます。彼のその曖昧模糊とした存在感が、結果として、萩が下した決断の重みや切実さを、より一層際立たせる効果を生んでいるとも言えるのかもしれません。彼の存在なくして、この物語の深みは生まれなかったでしょう。
そして、物語のもう一人の重要な登場人物、いづみ。許されない恋の果てに妊娠し、相手の男性からは無情にも捨てられてしまった彼女は、物語の序盤においては確かに被害者であり、読者の同情を強く誘う存在として描かれています。萩と要司に助けを求め、彼らの家に身を寄せることになる彼女の姿は、痛々しくも儚げです。しかし、物語が進むにつれて明らかになるのは、彼女の役割が、単なる「悲劇のヒロイン」という枠には到底収まらないということです。彼女の存在そのものが、萩と要司という二人の間にこれまで築かれていた関係性を根底から揺るがし、変容させていく、いわば「触媒」としての極めて重要な役割を果たしているのです。彼女が萩たちの前に姿を現したことによって、それまで表面的には安定しているかに見えていた二人の関係の内に潜んでいた、見えない亀裂や問題点が、否応なく表面化していくことになります。
萩、要司、そして、いづみ。この三人の登場人物が織りなす関係性は、まるで細い糸でかろうじて繋ぎ止められているかのような、非常に繊細で危ういバランスの上に成り立っています。この物語の巧みなところは、誰か一人だけが絶対的に「悪い」というような、単純な構図で描かれていない点でしょう。それぞれのキャラクターが持つ立場や、抱える個人的な感情、人間的な弱さや、時として矛盾する優しさといったものが、複雑に、そして有機的に絡み合い、結果として、関係性が必然的に変化していく様子が克明に描かれています。この、どうすることもできない「どうしようもなさ」、人生の「ままならなさ」こそが、「だんだんあなたが遠くなる」が持つ強烈なリアリティを支え、読者の心を掴んで離さないのではないでしょうか。読者は、ある時は萩の視点に深く感情移移入しながらも、またある時は要司やいづみの行動や心情にも一定の理解を示してしまう。だからこそ、単純な善悪の二元論では到底割り切ることのできない、深く、そして長く続く余韻が心に残るのかもしれません。
この物語は、読者の感情を激しく揺さぶるような派手な口論のシーンや、次から次へと劇的な事件が起こるような展開を見せるわけではありません。むしろ、園芸店での日々の仕事の風景や、三人で囲む食卓といった、ごくありふれた日常の場面の中で、登場人物たちの内面の変化が、静かに、しかし非常に丁寧に、そして丹念に描出されていくのが特徴です。これこそが唯川恵さんならではの、登場人物たちの感情の微細な動きを的確に捉える、繊細な筆致が最も光る部分と言えるでしょう。言葉には決してならないけれども、そこには確かに存在している空気の変化、ふとした瞬間に交錯する視線、あるいは、意味深長な沈黙。そうした細やかで巧みな描写が幾重にも積み重ねられることによって、登場人物たちの心の奥底にある本当の気持ちや、言葉にならない想いが、じわじわと読者に伝わってくるのです。この静謐とも言える描写のスタイルが、かえって主人公である萩が内面に抱えることになる深い孤独感や、胸を締め付けるような痛み、そして諦観にも似た複雑な感情を際立たせ、読者の心に深く、そして静かに染み入るような効果を生み出しているように、私には感じられました。派手さはないけれど、静かに、しかし確実に心に刻まれる。それが「だんだんあなたが遠くなる」という作品の持つ、抗いがたい大きな魅力の一つなのです。
作品のタイトルでもある「だんだんあなたが遠くなる」というフレーズが示す通り、この物語においては、単に物理的な距離が離れていくということだけでなく、人と人との間にある「心の距離」の変化が、極めて重要なテーマとして扱われています。かつては深く愛し合い、誰よりも近くにいたはずの相手が、時の流れや環境の変化、そして新たな人間関係の発生によって、少しずつ、しかし確実に自分から離れていってしまう。その予感、そしてそれが現実のものとなっていく過程の描写は、読む者の胸を締め付けます。近づきたいと願うのに近づくことができず、必死に繋ぎ止めようとすればするほど、するりと手からこぼれ落ちていってしまう。そんな、恋愛において誰もが一度は経験するかもしれない、普遍的でありながらも抗うことのできない感情の動きが、読者一人ひとりの心の琴線に触れ、深い共感を呼び起こすのでしょう。
この物語を読んだ方の中には、主人公・萩が最終的に下した決断に対して、「潔い選択だ」「彼女は強い女性だ」と感じ、深い共感を覚える人もいることでしょう。その一方で、「なぜもっとお互いに正直に話し合おうとしなかったのか」「それは単なる勝手な思い込みで、早まった別れを選んでしまったのではないか」といった、どこか歯がゆさを感じたり、もどかしさを覚えたりする人もいるかもしれません。このように、読者によって様々な反応や解釈が生まれ、議論を呼ぶという点もまた、この「だんだんあなたが遠くなる」という作品が、長年にわたって多くの人々に読まれ、そして語り継がれていく理由の一つと言えるのではないでしょうか。作者は、物語の中で明確な答えや、あるべき姿といった教訓を提示するのではなく、むしろ読者一人ひとりに、登場人物たちの行動や選択を通して、深く考えるための余地を残してくれているのです。その余白こそが、この物語を何度でも読み返したくなる魅力に繋がっているのかもしれません。
恋愛における一方的な依存や、過去への執着といったものから最終的に解き放たれ、自分自身の足でしっかりと大地を踏みしめて生きていくことを選んだ萩の姿は、変化の激しい現代社会を生きる私たち、特に多くの女性たちにとって、自分らしい生き方とは何か、幸せとは何かを考える上で、一つの大切な在り方を示唆してくれているようにも思えます。愛する人を失うという、人生における大きな痛みを経験しながらも、決して自分自身を見失うことなく、自らの価値観と信念に基づいて未来への一歩を踏み出していく。その凛とした姿は、切なさを伴いながらも、どこか清々しく、そして確かな強さを感じさせます。彼女の選択は、悲しい結末ではなく、新たな始まりの予感すら漂わせているのです。
「だんだんあなたが遠くなる」は、おそらく、読む人の年齢や、その時々の自身の恋愛経験、あるいは人生経験によって、感じ方や共感するポイントが大きく変わってくる作品かもしれません。若い頃に初めて読んだ時と、様々な経験を積み重ねて人生の機微を理解できるようになった後に再読した時とでは、登場人物たちへの見方や、物語から受け取るメッセージもまた、少なからず変化していくことでしょう。しかしながら、これまでに誰かを心の底から深く愛したことのある人、大切な友情と恋愛感情の間で心が揺れ動いた経験のある人、あるいは、人間関係におけるどうしようもない複雑さや、ままならなさを痛感したことのある人にとって、この物語はきっと、いつまでも忘れられない特別な一冊となる可能性を秘めていると感じます。静かで、しかし力強い感動を私たちに与えてくれる、珠玉の物語であることは間違いありません。
まとめ
唯川恵さんの手による「だんだんあなたが遠くなる」は、読み終えた後もなお、登場人物たちが下した選択や、彼らが抱えていた複雑な感情が、静かな波紋のように心に広がり続ける、そんな深い余韻を残す物語でありました。特に、主人公である萩が、苦悩の末に下した決断の背景にある重みと切なさが、いつまでも胸に残ります。
愛情、友情、同情、そして自己肯定感。これらの感情が複雑に絡み合い、少しずつ変化していく人間関係の様相が、非常に丁寧に描き出されていました。誰が正しくて誰が間違っているという単純な話ではなく、それぞれの立場や想いが痛いほど伝わってきます。そのリアルさが、この物語の大きな魅力と言えるでしょう。
「大好きだから、ふってあげる」。この言葉に集約される萩の選択は、切なく、そして強い意志を感じさせずにはいられません。愛するがゆえの別れ、そして自分自身を守るための決断。この物語は、愛の多様な形や、自分らしく生きることの難しさと尊さについて、改めて静かに問いかけてくれるきっかけを与えてくれたように感じます。
もしあなたが、人間関係の機微や、ままならない恋愛の現実に触れる物語を求めているなら、この「だんだんあなたが遠くなる」は、きっと心に響く一冊になるはずです。静かな感動と、人生について考えるヒントを与えてくれる作品として、おすすめしたいです。