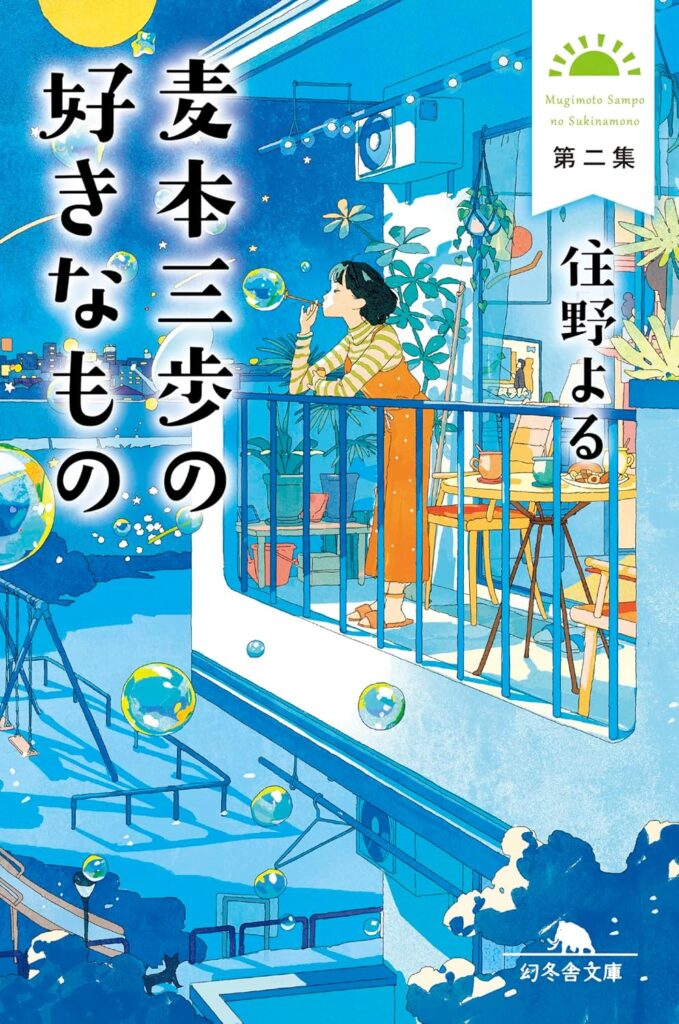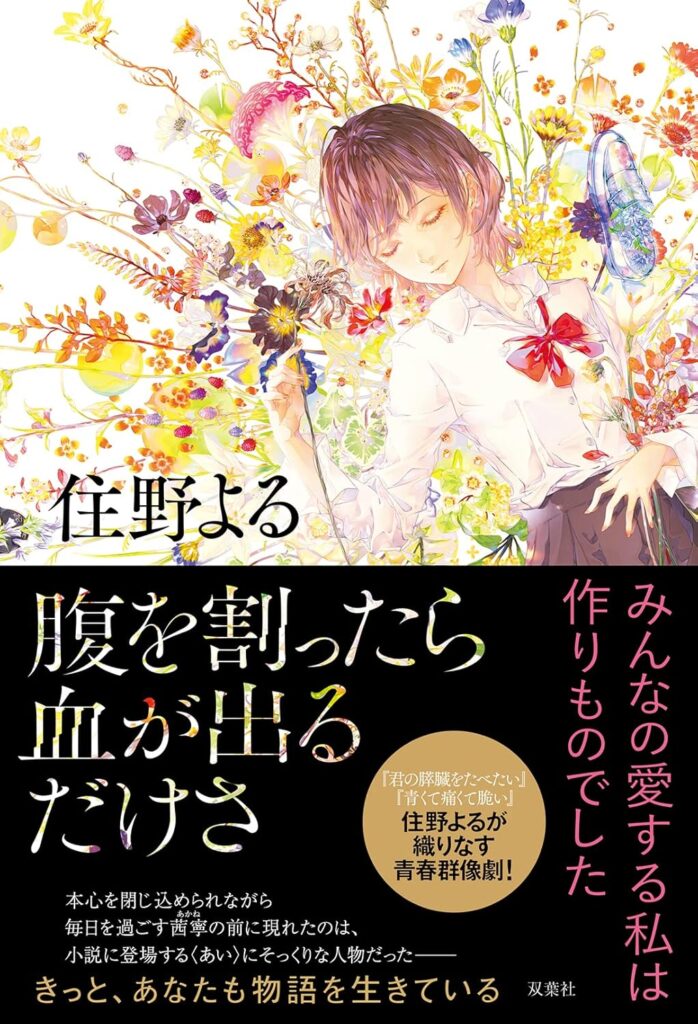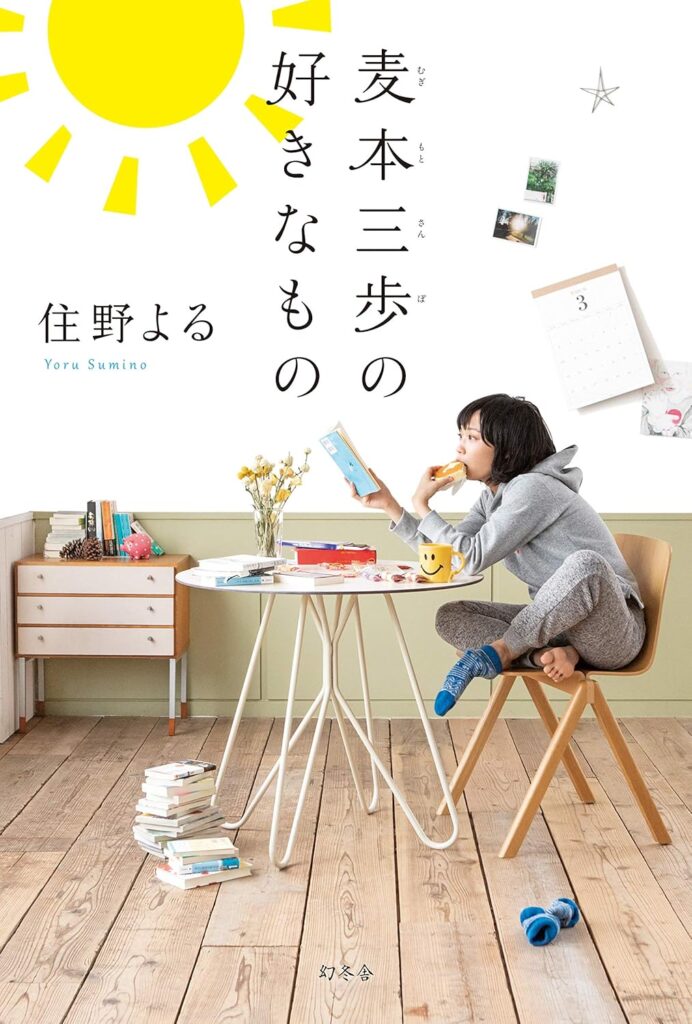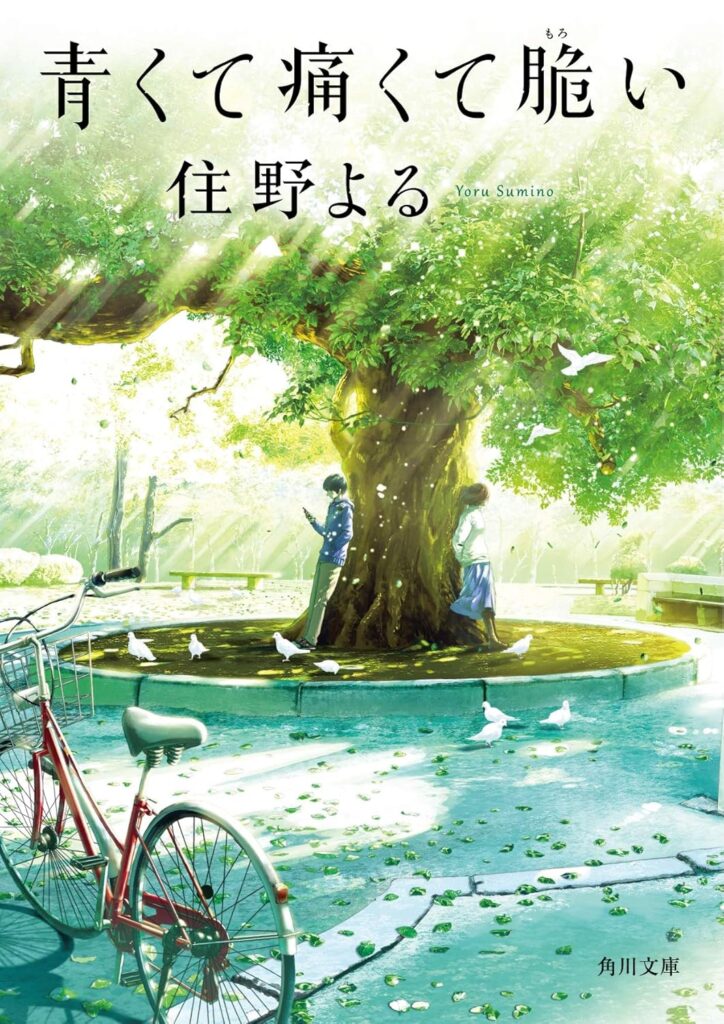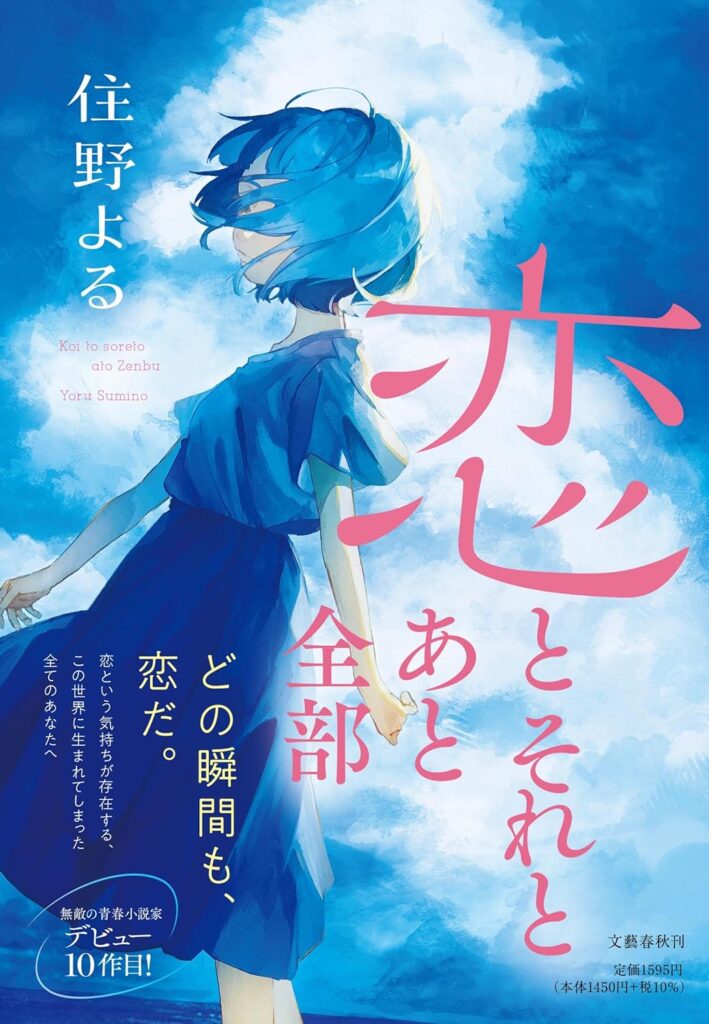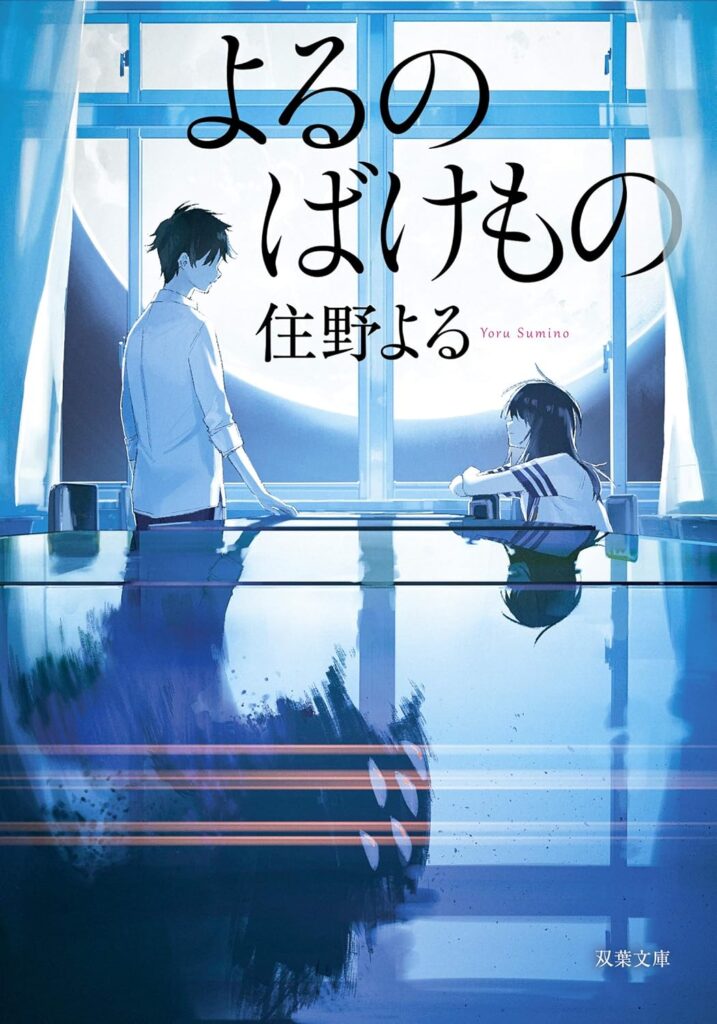小説「この気持ちもいつか忘れる」のあらすじを物語の核心に触れる部分も含めて紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「この気持ちもいつか忘れる」のあらすじを物語の核心に触れる部分も含めて紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
住野よるさんが描く、初の恋愛長編と銘打たれたこの作品。しかし、ただの恋愛物語ではありません。異世界との不思議な出会い、巧みに張り巡らされた伏線、そして「記憶」と「感情」をめぐる深い問いかけが、読む人の心を強く揺さぶります。
この記事では、まず物語の概要、どのようなお話なのかを掴んでいただけるように記述します。その上で、物語の核心、特に驚きの仕掛けや伏線について、私自身の解釈を交えながら詳しく語っていきたいと思います。物語を読み終えた方はもちろん、これから読む方も、作品の持つ奥深さを少しでも感じていただけたら嬉しいです。
読み進めるうちに、きっとあなたもこの物語の虜になるはずです。そして、読み終わった後には、もう一度ページをめくりたくなる、そんな魅力に満ちた一冊について、これからじっくりとお話しさせてください。
小説「この気持ちもいつか忘れる」のあらすじ
物語の主人公は、カヤという名の男子高校生。彼は、どこか世の中を冷めた目で見ており、退屈な毎日を送っています。学校生活にも特に楽しみを見いだせず、クラスメイトたちのことも「田中」や「斎藤」といった記号的な名前で呼び、人間関係にも深く関わろうとしません。彼にとって唯一の心の拠り所は、放課後に一人で行うランニングでした。
そんなある日、カヤはランニングの休憩場所として使っていた廃バス停で、不思議な存在と出会います。彼女の名前はチカ。瞳と爪だけがぼんやりと光って見える彼女は、カヤとは違う世界に住んでいるようでした。最初は戸惑いながらも、二人は言葉を交わし始めます。
異なる世界に住む二人ですが、奇妙なシンクロニシティが存在することに気づきます。カヤの世界で起こった出来事が、形を変えてチカの世界にも影響を与えることがあるのです。二人は様々な試みを通じて、お互いの世界の繋がりを探り、少しずつ心を通わせていきます。退屈だったカヤの世界は、チカとの出会いによって色づき始め、彼は次第に彼女に強く惹かれていきます。
しかし、その特別な時間は長くは続きませんでした。ある日突然、チカとの繋がりは断ち切られてしまいます。理由もわからぬまま訪れた別れは、カヤの心に深い喪失感と、決して忘れられない強い感情を残しました。チカとの出会いは、彼にとって唯一無二の、かけがえのない体験となったのです。
月日は流れ、高校卒業から十数年後。カヤは大人になりましたが、心の中ではまだ高校時代のチカとの出会いを引きずっていました。まるで余生を生きているかのように、感情の起伏の少ない日々を送っていました。あの特別な時間は、彼の中で風化することなく、むしろ神聖化され、彼を過去に縛り付けているようでした。
そんな彼の前に、転機が訪れます。それは、高校時代の同級生、カヤが「斎藤」と呼んでいた女性、須能紗苗との再会でした。彼女との再会が、止まっていたカヤの時間を再び動かし始めることになるのです。過去の記憶と現在の現実が交錯する中で、カヤはチカとの出会いが自分にとって何だったのか、そしてこれからどう生きていくのかを見つめ直していくことになります。
小説「この気持ちもいつか忘れる」の長文感想(ネタバレあり)
住野よるさんの「この気持ちもいつか忘れる」、読み終えた後の衝撃と感動は、今でも鮮明に心に残っています。単なる青春小説や恋愛小説という枠には到底収まらない、幾重にも仕掛けられた構造と、人間の記憶や感情の本質に迫るテーマ性に、すっかり心を奪われてしまいました。物語の核心、特に驚かされた仕掛けや伏線について、感じたことを詳しくお話しさせてください。
まず、多くの読者が度肝を抜かれたであろう、クラスメイトの呼称に関する仕掛けです。物語の後半、316ページに至るまで、私たちはカヤの視点を通して、彼のクラスメイトを「田中」や「斎藤」として認識しています。特に「斎藤」は、カヤにとって少し特別な存在として描かれ、読者も自然と彼女に感情移入していきます。しかし、終盤で明かされる真実。「うちのクラスに、田中って人、いたっけ?」「いや、いない」。この斎藤(須能紗苗)との会話は、頭を殴られたような衝撃でした。
カヤは、自分にとってその他大勢、つまり「特別ではない」クラスメイトをすべて「田中」という普遍的な名前で分類し、その中でも少しだけ異なる行動をとる須能紗苗を「斎藤」と呼んでいたのです。私たちが「田中」だと思っていた人物たちには、それぞれ固有の名前があり、人生がありました。例えば、アルミの飼い主だった「前の席の田中」は会沢志穂梨という名前でした。この事実に気づいた時、物語全体がまったく異なる様相を呈して見えました。
この仕掛けの巧妙さは、初読ではほとんど気づかない伏線が、作中に自然に散りばめられている点にあります。例えば、「あの田中」「飼い主の田中」「横の席の田中」といった、まるで固有名詞ではないかのような修飾語付きの「田中」の呼び方。読み返してみると、確かに不自然なのですが、初読ではカヤの独特な言い回し程度にしか感じませんでした。さらに、「鈴木くん」と呼ぶ田中と「鈴木」と呼ぶ田中が別々に登場する箇所(37ページと56ページ)。これも、読み返して初めて「別人だったのか!」と気づかされる仕掛けです。
極めつけは、38ページにある「田中はもう使われているし」というカヤのモノローグ。これは、チカに名前を付ける際に、自分の中で「特別ではない人々」を示す記号として「田中」という名前を既に”使っている”から、チカには使えない、という意味だったのです。こんな序盤に、これほど重大な伏線が隠されていたとは…住野よるさんの構成力には、ただただ脱帽するばかりです。この事実に気づいた瞬間、全身に鳥肌が立ちました。カヤがクラスメイトたち、ひいては世界に対してどれほど心を閉ざし、自分だけの壁を作っていたのかが痛いほど伝わってきました。
次に、異世界の少女チカの存在についてです。彼女は本当に実在したのか、それともカヤの妄想だったのか。物語は最後まで明確な答えを示しません。カヤの世界とチカの世界がリンクする不思議な現象、瞳と爪しか見えないという異質な存在感、そして突然の別れ。これらは、カヤが生み出した「都合の良い」妄想の産物と解釈することも可能です。特に、兄が廃バス停に現れた瞬間にチカの存在が消えたことは、それがカヤの内的世界だけの出来事だった可能性を示唆しているようにも思えます。
しかし、私は個人的に、チカは「奇跡」として実在したのだと信じたい気持ちが強いです。退屈な日々に絶望していたカヤが、チカと出会い、心からの笑顔を見せる場面。あの輝きは、単なる妄想が生み出せるものではないように感じられるのです。カヤにとってチカは、人生を根底から揺るがすほどの「突風」であり、かけがえのない「特別」な存在でした。たとえその記憶が薄れていこうとも、その体験がカヤの人生に与えた影響は計り知れません。
チカの発言にも、多くの違和感と伏線が隠されていました。例えば、172ページのアクセサリーのくだり。カヤはチカにとって唯一の特別な存在でありたいと願いますが、複数の人間と繋がっていることを喜ぶチカとの間には、恋愛観や繋がりに対する価値観の根本的な違いが見えます。また、222ページの「ここではカヤにしか会えないから」というセリフ。「ここでは」という限定的な言い方に、初読では気づけませんでした。他にも、犬や制服についてカヤが説明したはずのないことを知っていたりする描写。これら全てが、チカがカヤ以外の人間とも交流していることを示唆する伏線だったのです。そして、242ページの「初めに」というたった一言。これで、チカがカヤ以外の人間とも繋がっていることが確定的に示されます。この一言が持つ破壊力、物語が一気に反転する感覚は、まさに住野よる作品の真骨頂だと感じました。
作中で繰り返される「見つからないように」という別れの挨拶。これも当初は、異世界に関わる神秘的な意味があるのではないかと深読みしていました。しかし、物語の終盤で明かされたのは、その土地に逃げてきた人々が先住民から隠れるために使っていた言葉が、挨拶として残ったという歴史的な背景でした。ファンタジーではなく、現実的な理由があったことに、ある種の肩透かしと、同時にリアルな手触りを感じました。秘密めいた言葉の裏にあった意外な真実も、この物語の魅力の一つです。
そして、十数年の時を経て再会した斎藤、須能紗苗の存在が非常に重要です。彼女は、カヤが「田中」と「斎藤」というフィルターを通してしか世界を見ていなかったことを指摘し、彼を過去の呪縛から解放するきっかけを与えます。カヤが高校時代、斎藤(紗苗)の本名すらまともに認識していなかったこと、卒業後に名刺を渡されてもピンとこなかったこと。これも、カヤがいかに他者に無関心であったかを示す伏線でした。紗苗は、カヤとは対照的に、過去の出来事(例えばライブハウスでの体験)の「気持ち」はいつか忘れるかもしれないけれど、その「事実」や経験は大切にしながら、未来に向かって歩んでいます。彼女の存在が、カヤに過去の「気持ち」とどう向き合い、現在を生きていくべきかを気づかせるのです。
この物語は、THE BACK HORNというバンドとのコラボレーションから生まれたという点も特筆すべきでしょう。作中にも音楽に関する描写が登場し、特に紗苗が音楽によって救われた経験を語る場面は印象的です。小説と音楽が互いに共鳴し合うことで、物語の世界はより深く、豊かになっていると感じられます。付属のCDを聴きながら読むことで、カヤやチカ、紗苗の感情が、より立体的に伝わってくるかもしれません。(限定版についていたCDを聴きながら読む体験は、また格別だったのだろうと想像します。)
「この気持ちもいつか忘れる」というタイトル。これは、チカとの出会いという強烈な体験によって生まれた感情も、時とともに薄れていくという切ない真実を示唆しています。しかし、同時に、その感情を抱いた「事実」は消えないし、その経験が自分自身を形作っているのだ、というメッセージも込められているように感じます。紗苗が言うように、大切なのは、過去の感情に縛られ続けることではなく、その経験を糧にして今を生きることなのかもしれません。
住野よるさんの作品は、「君の膵臓をたべたい」をはじめ、どれも読者の心を掴んで離さない魅力がありますが、「この気持ちもいつか忘れる」は、特にその構成の巧みさとテーマの深さにおいて、際立った作品だと感じます。伏線に気づいた上で再読すると、初読とは全く違う景色が見えてきます。カヤのモノローグの一つ一つ、登場人物たちの何気ない会話の裏に隠された意味を発見するたびに、改めて作者の筆力に驚かされます。
この物語は、読む人によって様々な解釈が可能な、懐の深い作品です。チカは本当にいたのか?カヤは過去から解放されたのか?明確な答えは示されません。だからこそ、読者は自分自身の経験や価値観と照らし合わせながら、物語について考え続けることになるのでしょう。切なくて、少し不思議で、そして読み終わった後には、自分の心の中にある「忘れられない気持ち」について、そっと想いを馳せてしまう。そんな特別な読書体験を与えてくれる一冊でした。
まとめ
住野よるさんの「この気持ちもいつか忘れる」は、退屈な日常を送る高校生カヤと、異世界の少女チカとの不思議な出会い、そして十数年後の再会を描いた物語です。単なる恋愛小説に留まらず、巧みな伏線と驚きの仕掛けが満載で、読む者を飽きさせません。
特に、カヤがクラスメイトを「田中」「斎藤」と呼んでいたことの真相が明かされる場面は衝撃的でした。この仕掛けによって、カヤの孤独や世界との向き合い方が浮き彫りになり、物語は一層深みを増します。読み返すごとに新たな発見があり、作者の構成力に感嘆させられます。
チカの存在が現実だったのか、それともカヤの妄想だったのかは、読者の解釈に委ねられています。しかし、どちらであっても、その出会いがカヤの人生にとってかけがえのないものであったことは間違いありません。過去の記憶や感情とどう向き合い、現在を生きていくかという普遍的なテーマが、心に深く響きます。
「この気持ちもいつか忘れる」というタイトルが示すように、強い感情もいつかは薄れていくかもしれません。それでも、その経験が自分を形作っているという事実は変わらない。切なくも温かい読後感を残す、忘れられない一冊となるでしょう。ぜひ、この不思議で心揺さぶられる物語を体験してみてください。