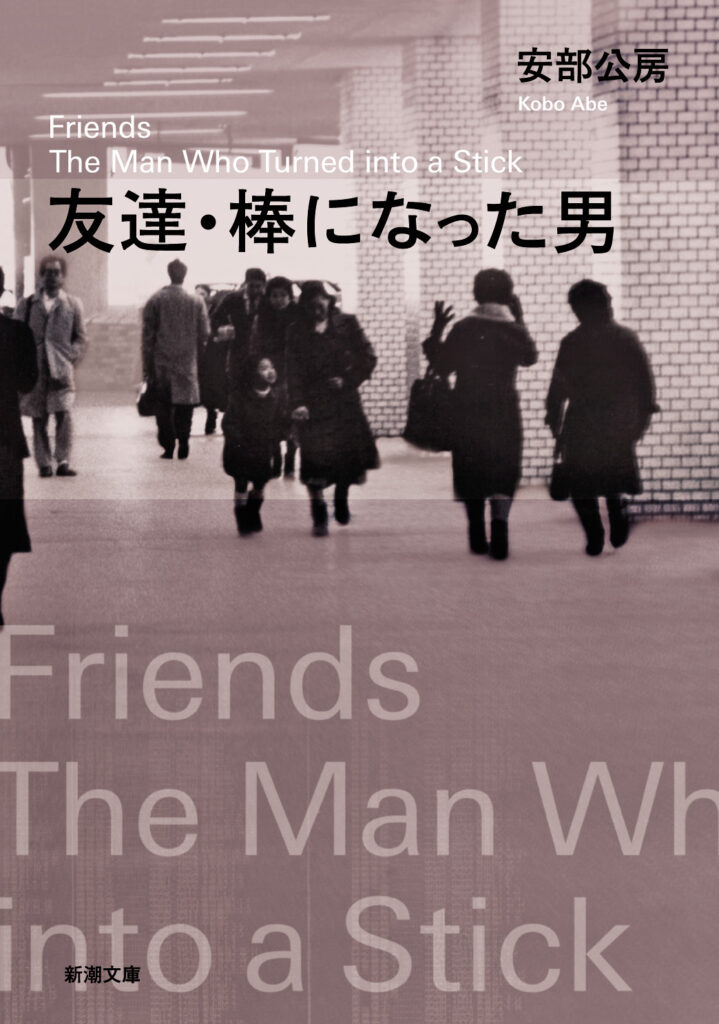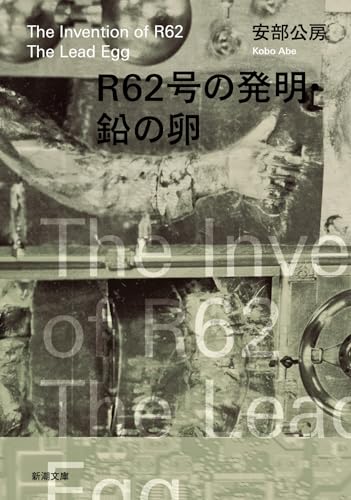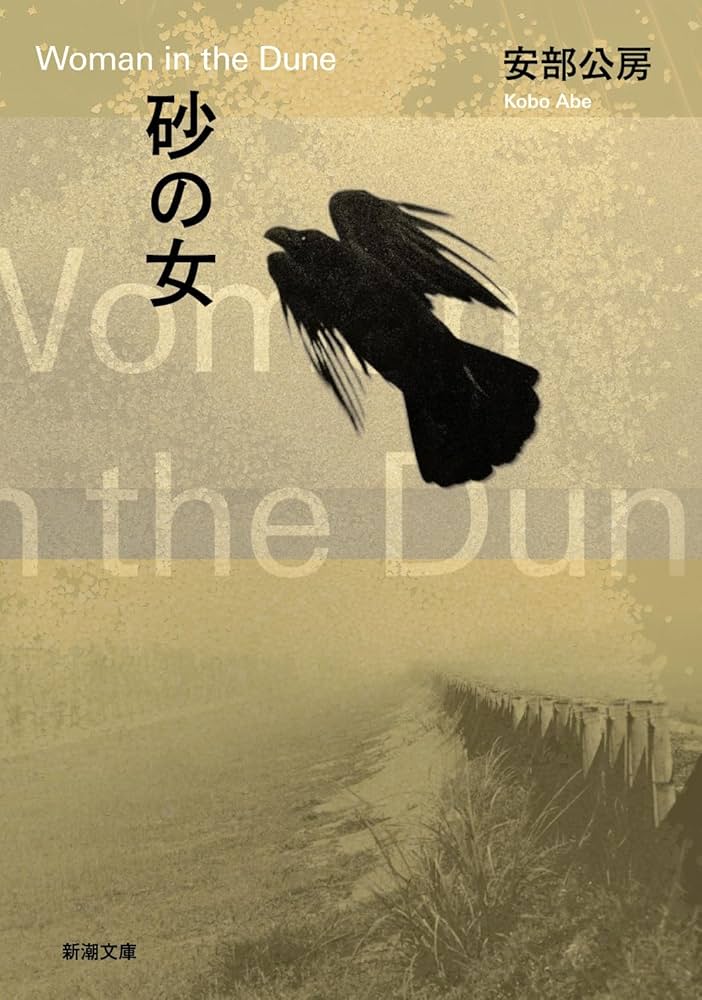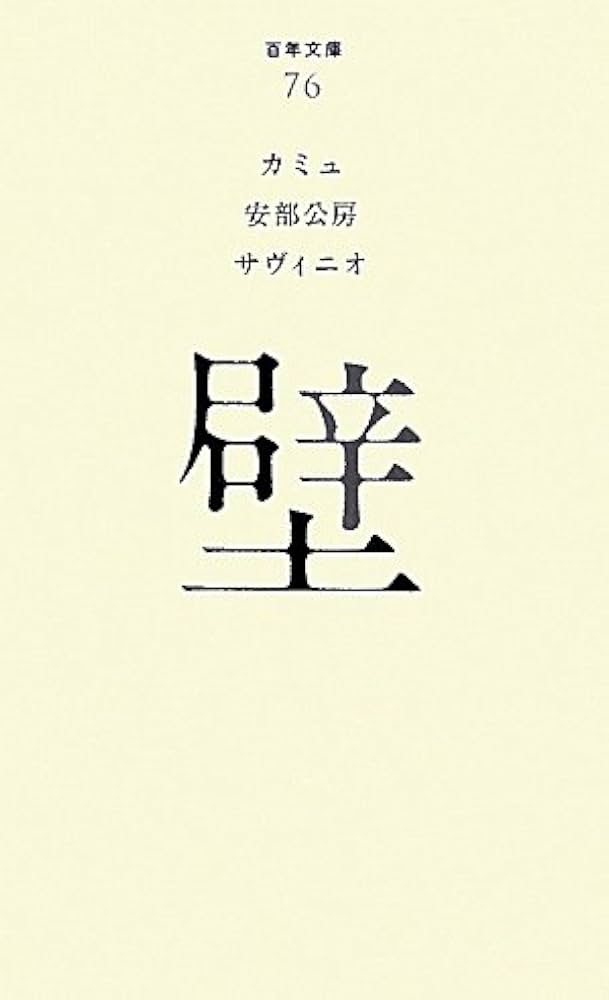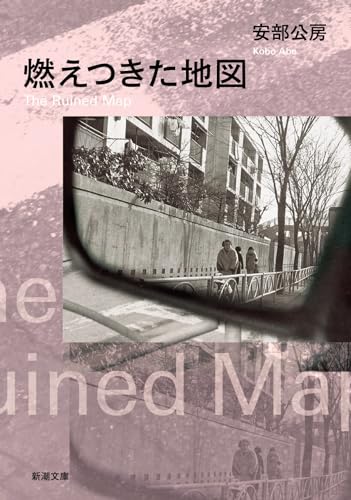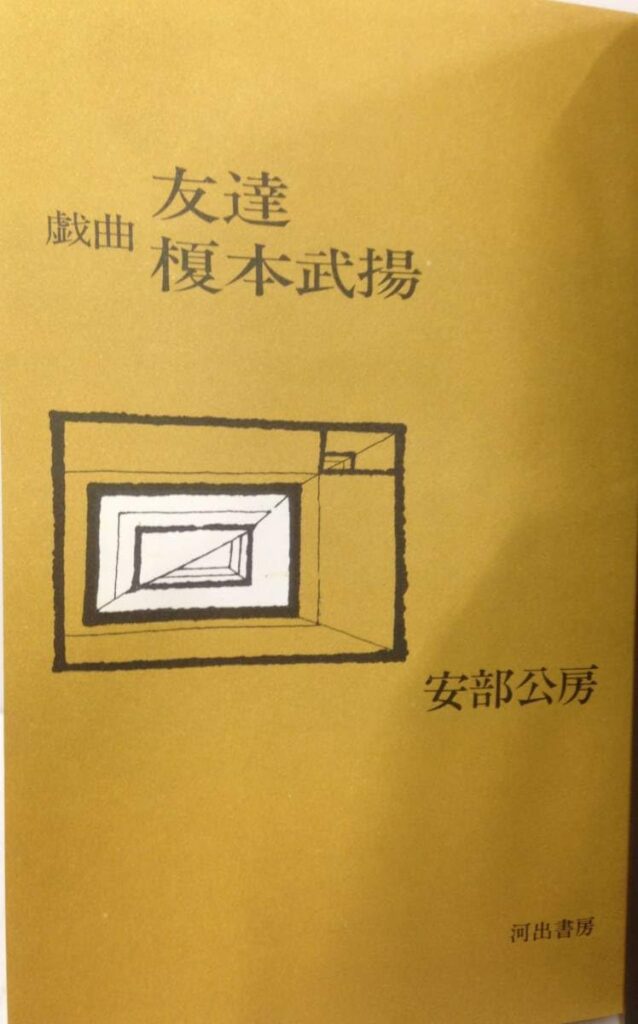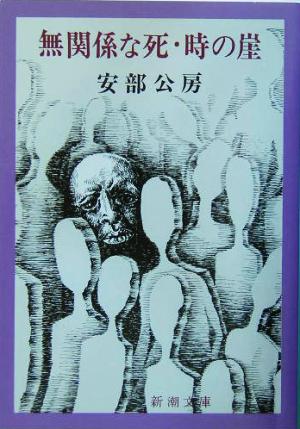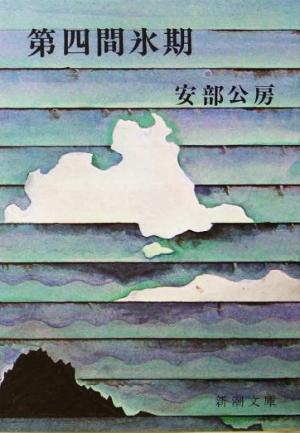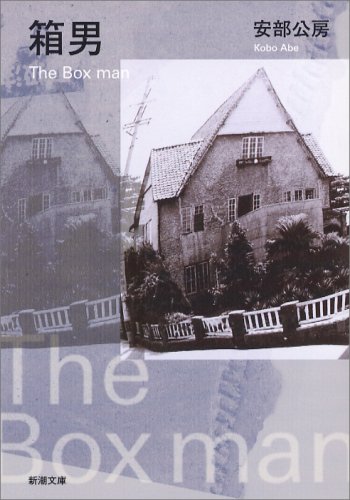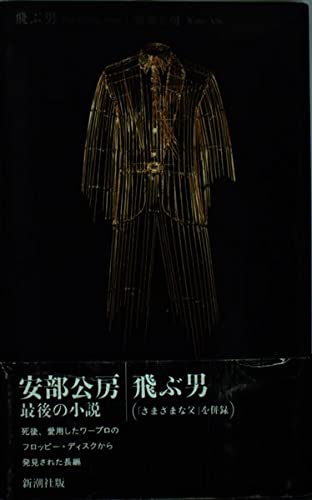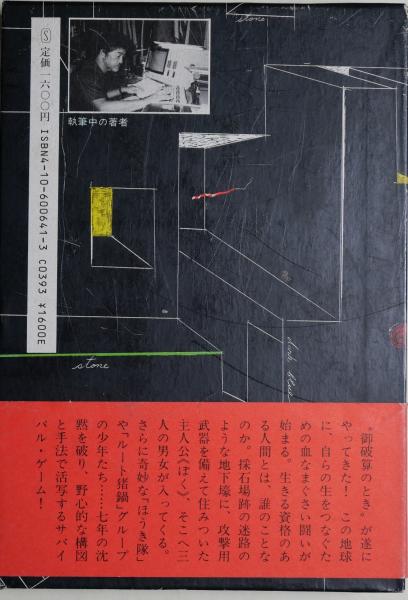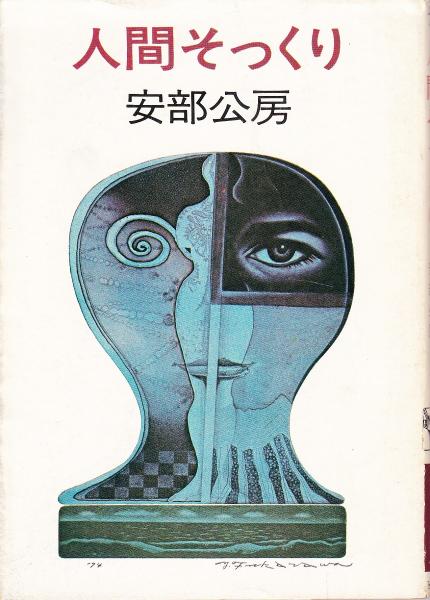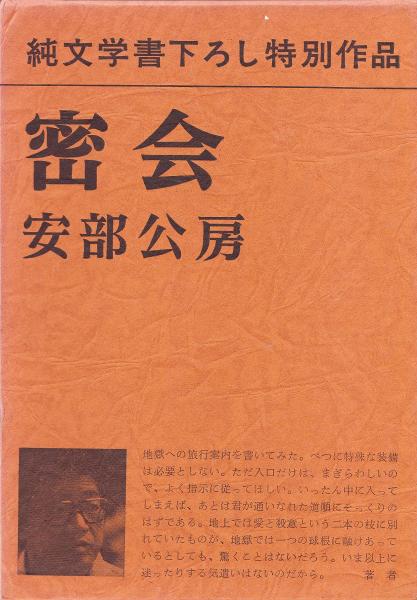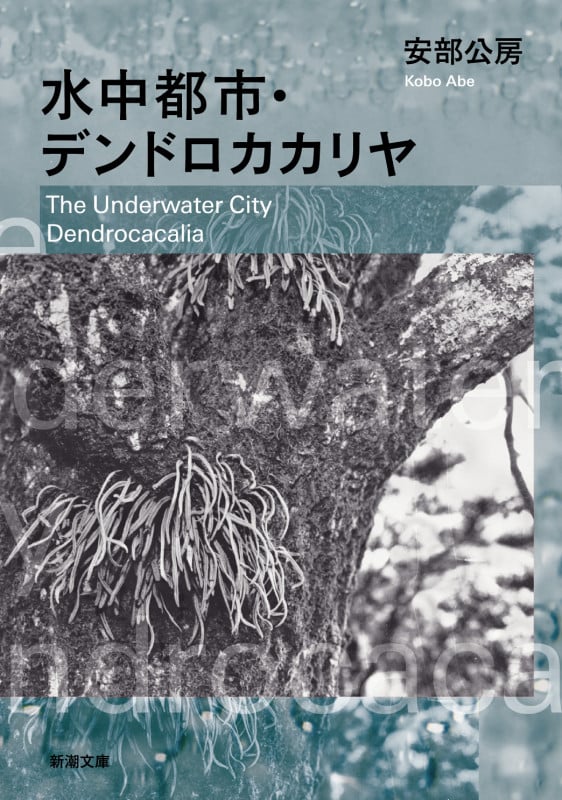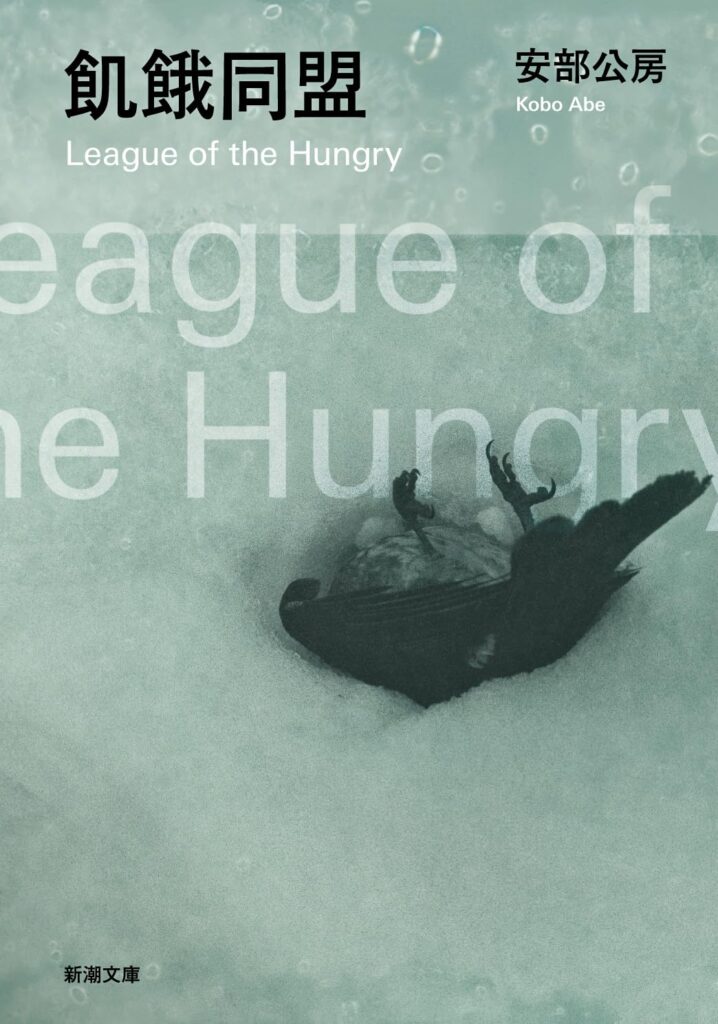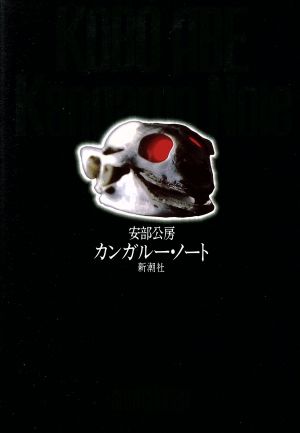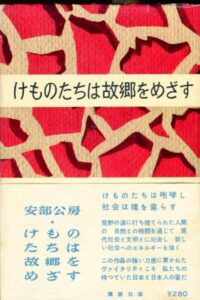 小説「けものたちは故郷をめざす」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「けものたちは故郷をめざす」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、単なる冒険小説やサバイバル記として片付けることのできない、非常に重く、そして深い問いを私たちに投げかけてきます。一度読んだら忘れられない、強烈な読書体験を約束してくれる一冊と言えるでしょう。
舞台は第二次世界大戦終結直後の旧満州。あらゆる秩序が崩壊し、混沌が支配する荒野です。主人公の青年は、一度も踏んだことのない土地である「日本」という故郷を目指して、絶望的な旅に出ます。その道程は、私たちの想像を絶するほど過酷なものです。
この記事では、まず物語の骨子となる部分を紹介し、その後で結末を含む重大なネタバレと共に、この作品がなぜこれほどまでに心を揺さぶるのか、その魅力とテーマについて、じっくりと語っていきたいと思います。安部公房が描く「故郷」とは何なのか、そして人間が「けもの」に変わる瞬間とは。
これから「けものたちは故郷をめざす」を読もうと思っている方、あるいはすでに読了し、その衝撃に打ちのめされている方、どちらにとっても読み応えのある内容を目指しました。この壮絶な物語の世界に、一緒に分け入っていきましょう。
「けものたちは故郷をめざす」のあらすじ
物語は、敗戦後の旧満州の架空の町・巴哈林(パハリン)から始まります。主人公は、満州で生まれ育った日本人青年、久木久三(くき・きゅうぞう)。戦争で両親を失い、引き揚げにも乗り遅れた彼は、ソ連軍兵士の下男として働くことで、かろうじて生き延びていました。しかし、その生活もある種の隷属であり、彼が心に抱き続けるのは、見たこともない「故郷」日本への帰還という切なる願いでした。
ある日、彼を庇護していたソ連兵たちが部隊ごと移動するという知らせが、彼の運命を大きく動かします。このままでは見捨てられ、混沌の中に放り出されることを悟った久三は、ついに逃亡を決意。最後の晩餐の席でウォッカを酌み交わしながら、地図やナイフを盗み出し、猛吹雪の闇の中へと姿を消します。彼は、保証された安定を捨て、死が待ち受けるかもしれない荒野へと自ら飛び込んでいくのです。
孤独な逃避行のさなか、久三は高石塔(こう・せきとう)と名乗る、日中混血を自称する謎めいた男と出会います。人を惹きつける不思議な魅力と、底知れない胡散臭さを併せ持つ高。二人は生き延びるため、互いを利用し合う形で、脆弱な協力関係を結びます。友情や信頼ではなく、ただ生きるという共通の目的だけで結ばれた二人の旅が始まります。
彼らが目指すのは、日本の密航船が出ているという南の大都市・瀋陽。しかし、その道のりは飢えと寒さ、そして人間同士の裏切りに満ちた、まさに地獄のような苦行でした。人間性を剥ぎ取られ、生存本能だけの「けもの」へと変わっていく二人。はたして彼らは、無事に目的地へたどり着き、久三は焦がれ続けた故郷の土を踏むことができるのでしょうか。このあらすじの先には、衝撃的な展開が待っています。
「けものたちは故郷をめざす」の長文感想(ネタバレあり)
「けものたちは故郷をめざす」を読み終えたとき、心に残るのは感動や爽快感ではなく、ずっしりと重い沈黙と、底なしの虚無感かもしれません。この物語は、安部公房自身の「故郷喪失者」としての体験を色濃く反映させながら、単なる私的な物語を超えて、人間存在の根源的な不安や不条理を鋭くえぐり出しています。
安部公房は満州で育ち、自らを故郷を持たない人間だと考えていました。その意識が、この作品の根底に流れています。これは彼の体験そのものを描いた自伝的なものではありません。むしろ、自身のパーソナルな問いを、フィクションという装置を使って普遍的なレベルにまで高めた、壮大な思考実験と言えるでしょう。
物語の冒頭、主人公の久木久三は、ソ連兵の下男という屈辱的ではありながらも、食住が保証された環境にいます。しかし、彼はその安定を自ら蹴って、死と隣り合わせの荒野へと逃亡します。この選択こそが、この物語が単なる生存闘争ではないことを示しているように感じます。彼にとって、誰かの道具として生きることは、肉体的な死にも等しい精神的な死だったのではないでしょうか。
彼の逃亡は、主体性を取り戻すための、あまりにも無謀な賭けでした。たとえそれが、人間であることをやめ、「けもの」になることを意味するとしても。私たちは、この久三の決断に、極限状況における人間の尊厳とは何かを考えさせられます。
そして、久三は高石塔という男と出会います。この高という人物が、物語に強烈な厚みと不穏さを与えています。彼はカリスマ的でありながら、その言動の端々からは嘘と自己中心的な匂いが立ち上ります。久三の「日本へ帰りたい」という純粋な願いは、高にとっては自分の目的を達成するための都合のよい道具に過ぎないように見えます。
二人の間に生まれるのは、友情などという生易しいものではありません。それは、互いが互いの生存に必要だという、極めて機能的な、脆い共生関係です。高は久三の目的地「日本」を隠れ蓑に利用し、久三は高のサバイバル知識を必要とする。この関係は、社会というものが崩壊した世界での、人間関係の究極の姿を映し出しているかのようです。
高の真の目的は、故郷への帰還などではなく、アヘンを密輸して金と権力を手にすることでした。このアヘンへの執着こそが、彼を突き動かす唯一のエネルギーなのです。理想や理念ではなく、即物的な欲望だけが人間を動かす原動力となる。この冷徹な現実は、読み進めるうちに読者の心にも突き刺さってきます。
この小説の白眉は、何と言っても瀋陽を目指す南への旅の描写の凄まじさにあるでしょう。安部公房の筆は、凍傷で腐っていく指先の感覚や、飢えで意識が朦朧とする様を、執拗なまでに克明に描き出します。読んでいるこちらまで、満州の凍てつく風を感じ、飢えの苦しみが伝わってくるようです。
肉体的な苦痛は、彼らから人間らしい感情や思考を奪い去っていきます。イデオロギーや国家、社会性といったものは、生きる上での「重荷」でしかなくなり、ただ「生きる」という純粋な本能だけが残ります。まさしく、タイトルが示す通りの「けもの」へと、彼らは変貌していくのです。
道中で発見される、日本人のものらしき五体のミイラ。彼らが遺した「ムネン ミチ ナカバニシテ…」という言葉は、久三たちの旅が常に死と隣り合わせであることを、そして彼らを待ち受けるかもしれない運命を、静かに、しかし冷酷に予言しているかのようです。
この旅を通して、人間を人間たらしめているものは何か、という問いが浮かび上がります。あらゆる社会的記号が剥ぎ取られ、肉体の苦痛という絶対的な現実だけが残ったとき、そこに「人間」は存在するのでしょうか。安部公房は、観念的な思索よりも、生々しい身体感覚こそが世界の真実であるとでも言うように、その苦痛を描き続けます。
さて、この過酷な旅を支える唯一の光が、久三の心の中にある「故郷・日本」のイメージです。彼にとって日本は、記憶の中にある場所ではありません。教科書で読んだだけの、完全に観念として構築された、自由と安らぎが約束された楽園、神話的な聖域なのです。この理想化された故郷のイメージこそが、彼に絶望的な苦行を耐えさせ、前へ進む力を与える唯一の精神的な支えとなっています。
この小説のタイトルが『けものたちは“日本”をめざす』ではなく、『けものたちは“故郷”をめざす』であることは、非常に示唆に富んでいます。彼らの旅は、特定の地理的な場所を目指す理性的な行為ではなく、起源へ回帰しようとする、理性を介さない本能的な衝動、まさに「けもの」の衝動であることを物語っているのではないでしょうか。
しかし、安部公房は、その「故郷」という概念そのものに鋭いメスを入れます。久三が盲目的に信じる「故郷」という神話は、彼の苦しみを正当化し、彼を生かし続ける力となります。しかし、その一方で、作者は「故郷」というものが、いかに曖昧で、時には危険な虚構であるかを暴き出そうとしているように思えます。久三の旅は、彼の想像の中にしか存在しない聖地への、悲劇的な巡礼なのです。
ここからは、物語の結末に関する重大なネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。
想像を絶する旅の果てに、久三と高はついに瀋陽に到着し、日本へ向かう密輸船に乗り込むことに成功します。久三の長年の夢が、ついに叶う瞬間が目前に迫ります。しかし、読者の淡い期待は、ここから始まる裏切りと絶望によって、完膚なきまでに打ち砕かれることになります。
船の上で、高の真の目的がアヘンの密輸であったことが確定し、力関係は完全に逆転します。そして、この物語における最も残酷な行為が行われます。高は、久三の存在そのものを消し去るかのように、彼のアイデンティティを奪い、「俺が久木久三だ」と名乗り始めるのです。旅の過程で家族も国籍も人間性も失い、最後に残った「名前」という自己同一性の最後の砦までもが、彼から奪い去られます。
やがて船は、日本の沿岸にたどり着きます。甲板からは、久三が命を懸けて目指した故郷の灯りが見えます。しかし、名前を奪われ、密輸団の陰謀に巻き込まれた彼は、船倉に監禁され、その渇望した土地に足を踏みおろすことが許されません。物語は、久三がこの絶対的な不条理の中に閉じ込められたまま、突然幕を閉じます。
この結末には、いかなる救いもカタルシスもありません。旅は終わったのに、目的地は永遠に手の届かない場所にある。目標を達成したかに見えたその瞬間に、より根源的で脱出不可能な絶望が訪れる。これこそが、安部公房が描き出す世界の不条理さの真骨頂でしょう。久三の悲劇は、日本にたどり着けなかったことではありません。たどり着いた結果、救済の地としての「日本」など初めから存在しなかったと知らしめられたこと、そして彼自身の存在が完全に無に帰してしまったことにあるのです。彼は、文字通り「何者でもない者」として、故郷の岸辺を永遠に眺め続ける、生ける亡霊となったのです。
まとめ
「けものたちは故郷をめざす」は、私たちに「故郷とは何か」「自分とは何か」という根源的な問いを突きつける、恐るべき傑作です。物語の筋書きだけを追えば、それは満州からの壮絶な脱出劇に見えるかもしれません。しかし、その奥深くには、人間存在の不確かさや、アイデンティティの脆さといった、普遍的なテーマが横たわっています。
主人公・久三が体験する肉体的、精神的な苦痛は、読者自身の心をも深くえぐります。そして、たどり着いた先にある衝撃的な結末は、私たちに安易な救いや希望を与えてはくれません。むしろ、圧倒的な虚無と不条理の中に、私たちを置き去りにします。この読後感の重さこそが、この作品が持つ比類なき力と言えるでしょう。
この物語は、決して気軽に楽しめるエンターテインメントではないかもしれません。しかし、文学が持つ本来の力、つまり、私たちの価値観を揺さぶり、世界の見方を変えてしまうほどの力に満ちています。安部公房が仕掛けたこの存在論的な問いに、打ちのめされる覚悟で向き合ってみてはいかがでしょうか。
人間が「けもの」になるとき、そしてその「けもの」が目指した故郷の正体とは。この絶望的な旅路の果てに何を見たのか、ぜひご自身の目で確かめてみてください。きっと、あなたの心に消えない傷跡を残す、忘れがたい一冊となるはずです。