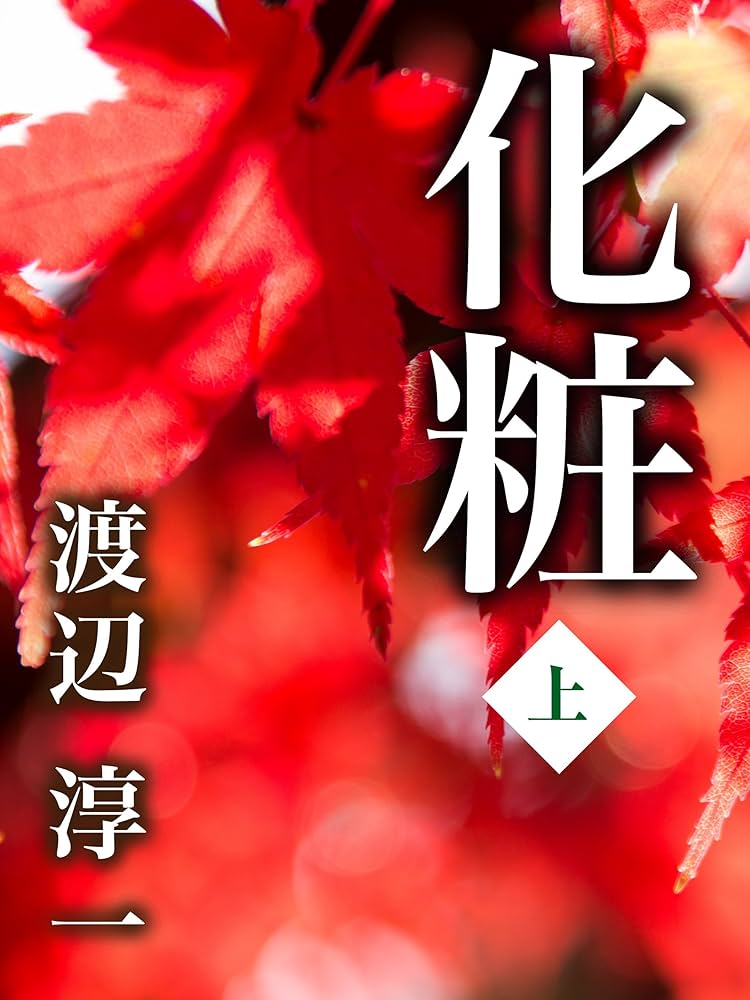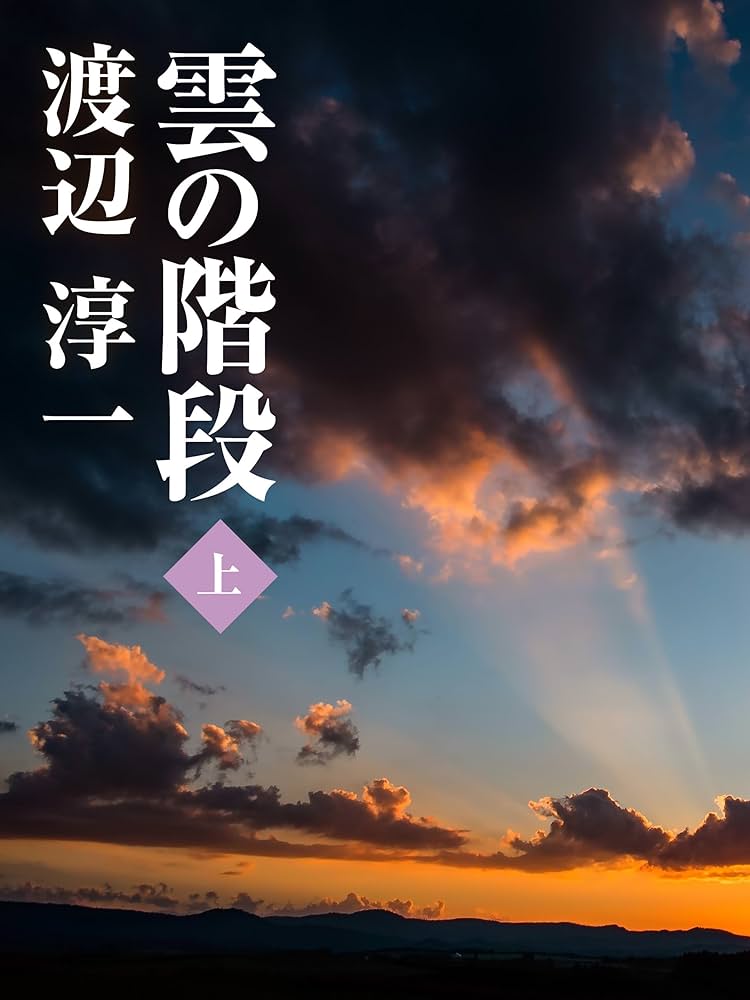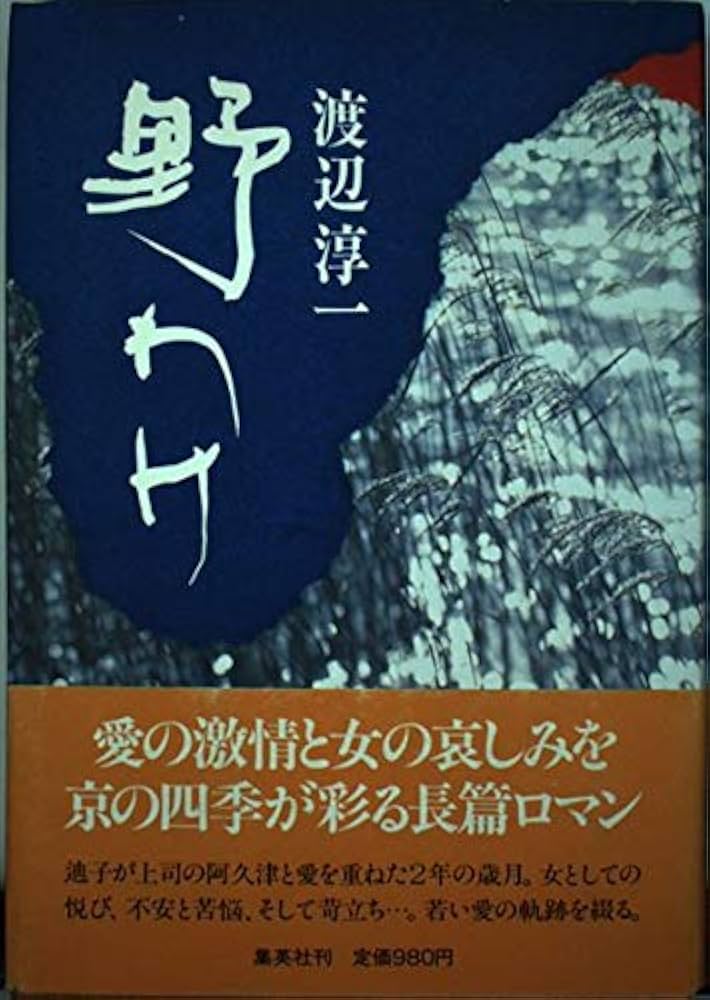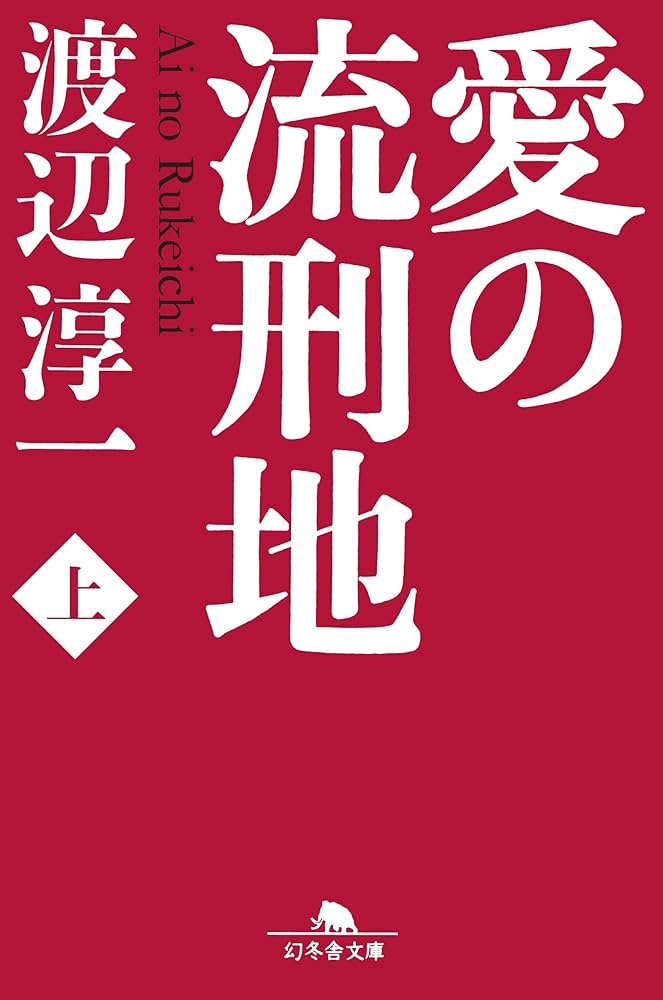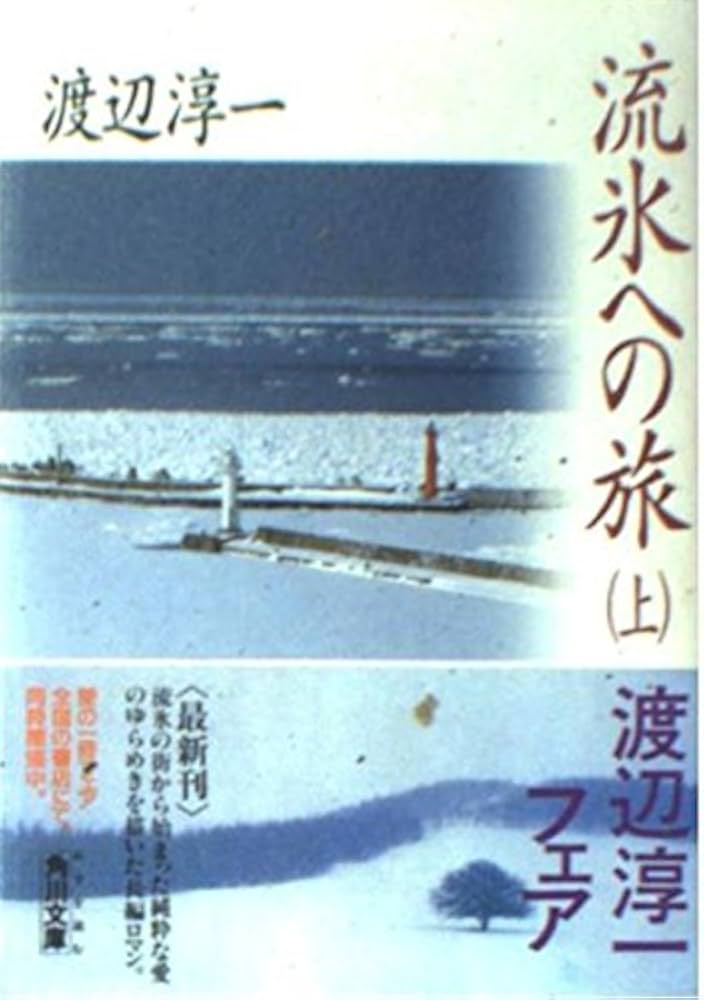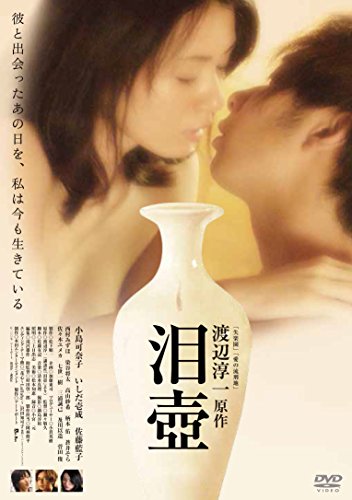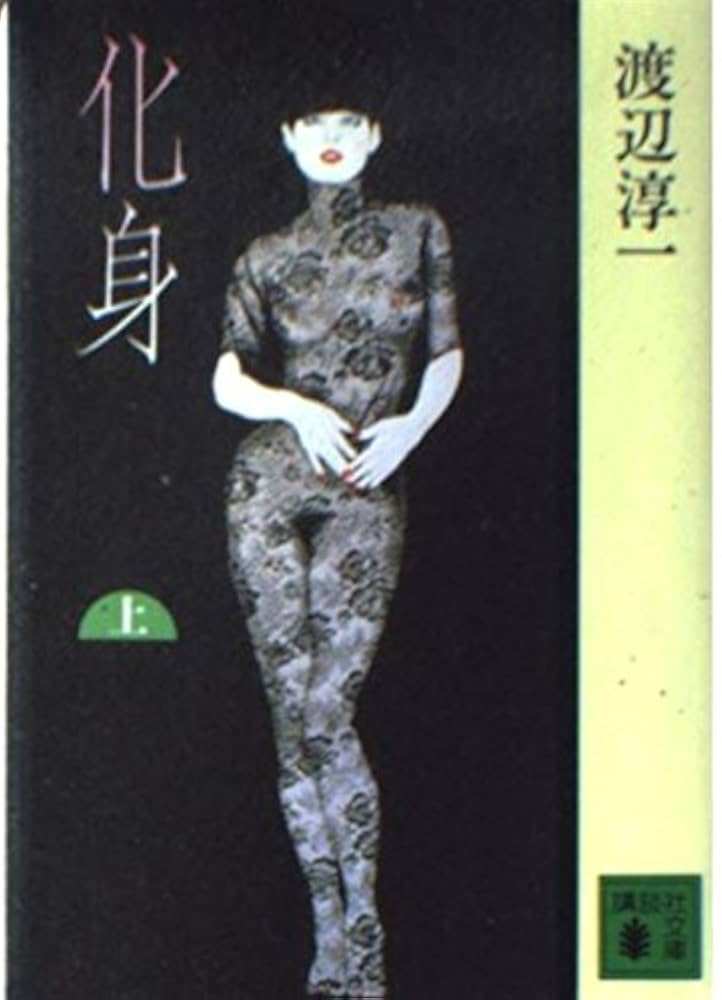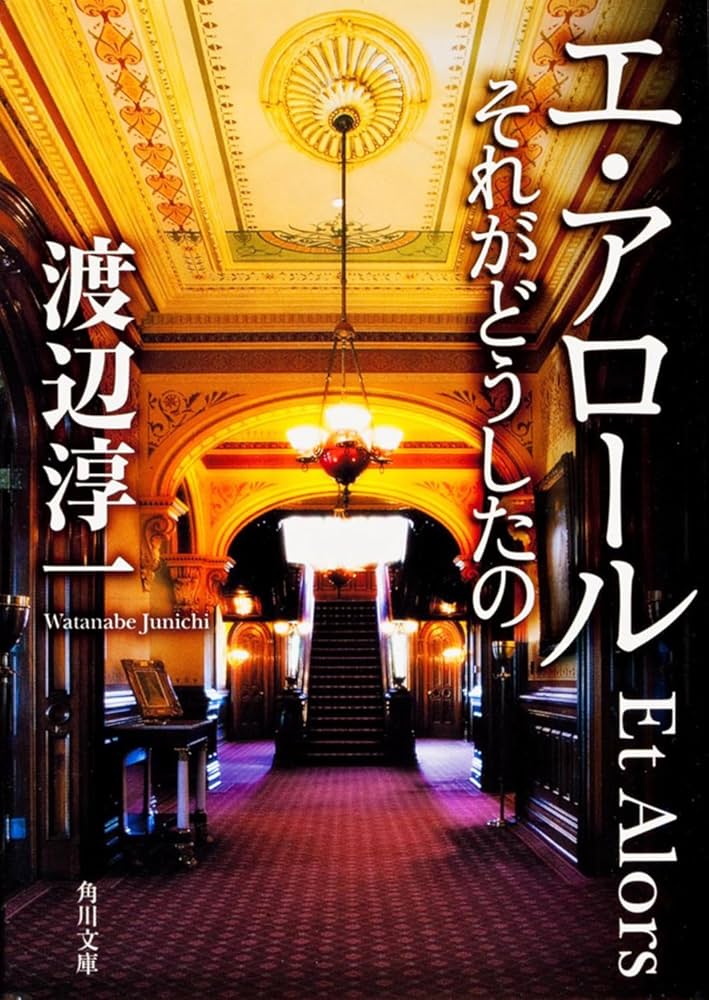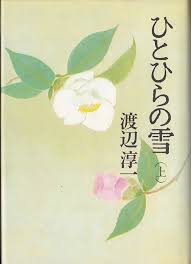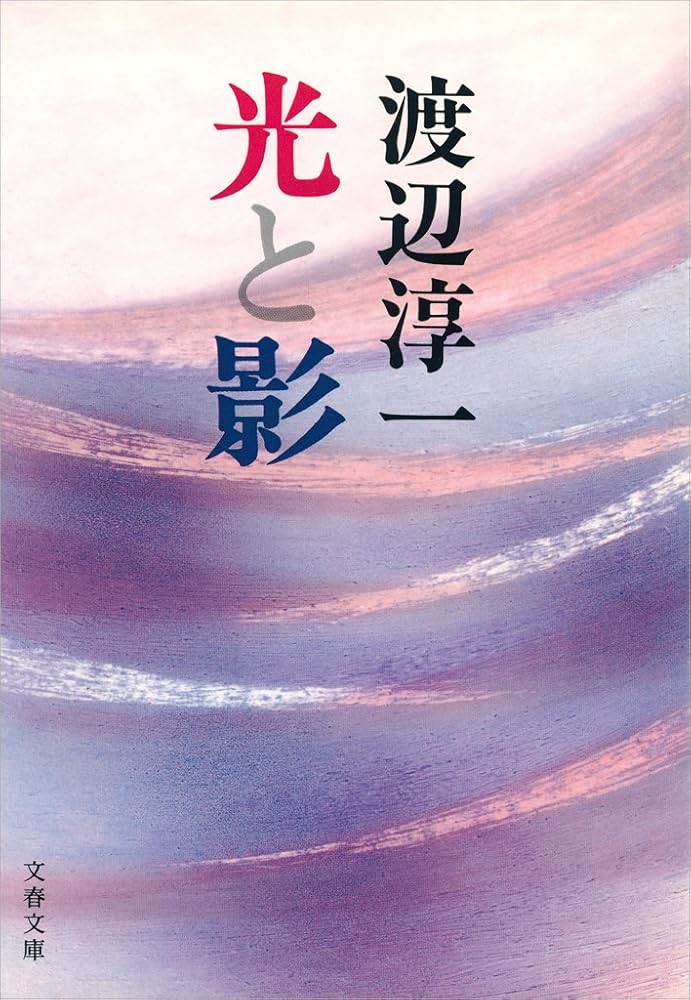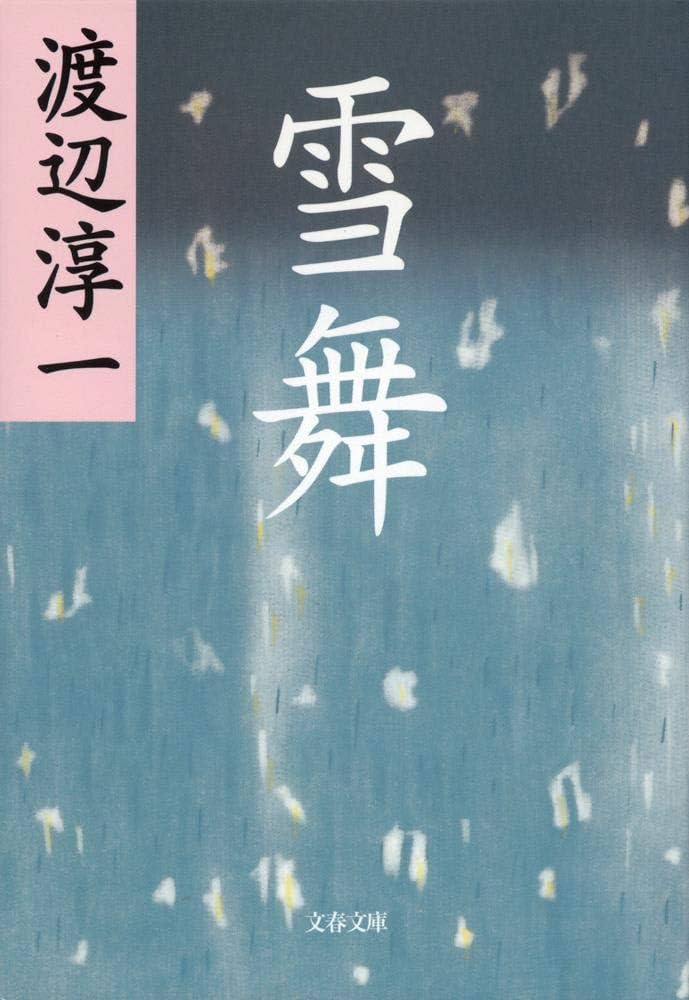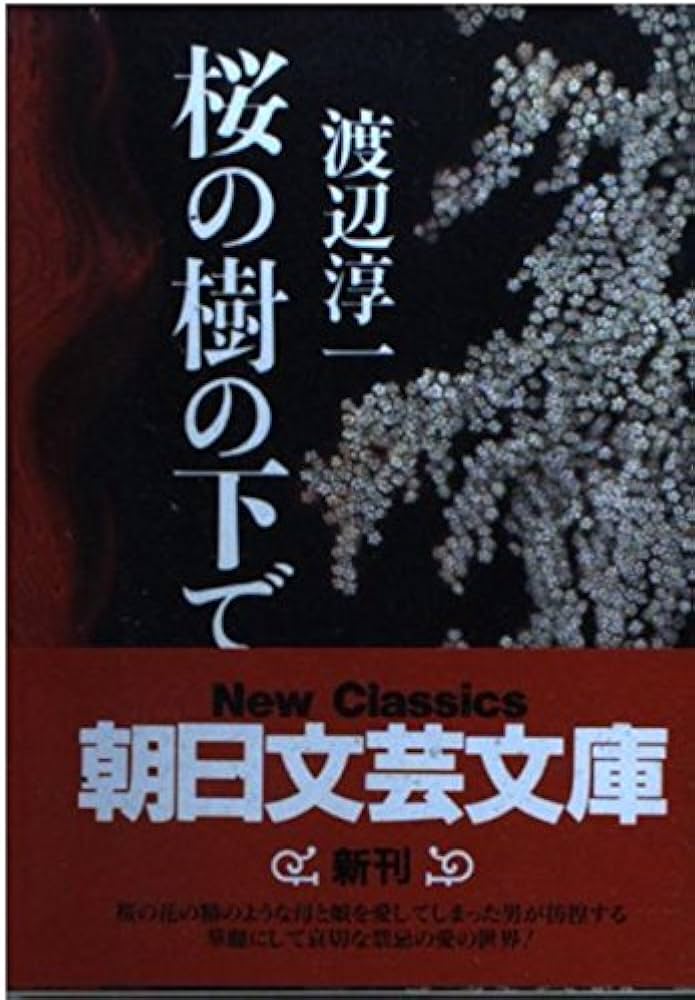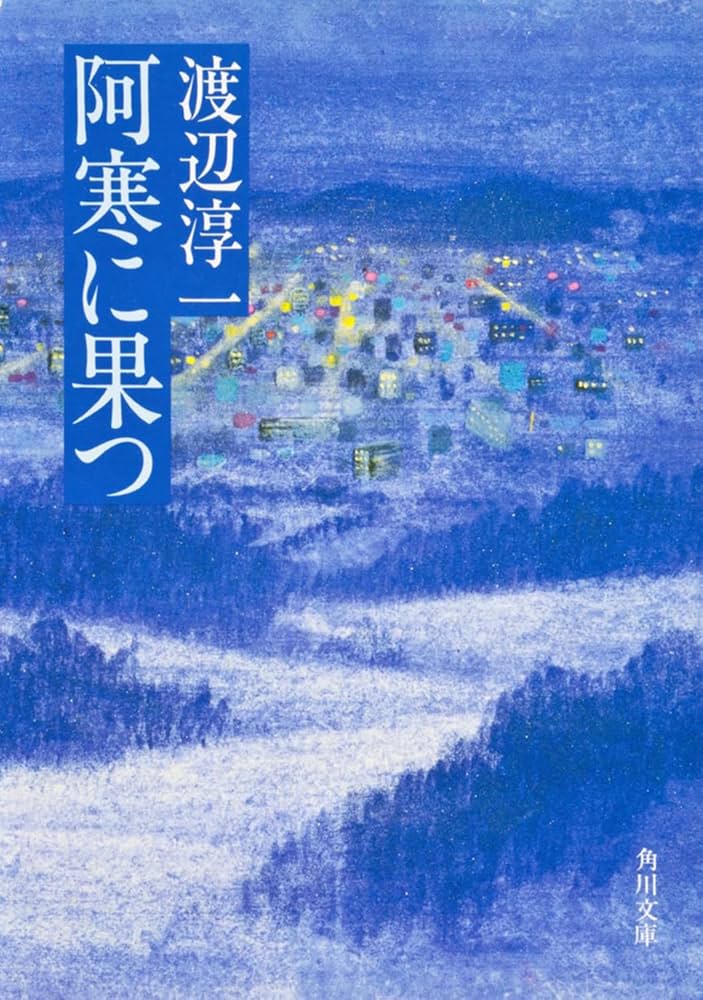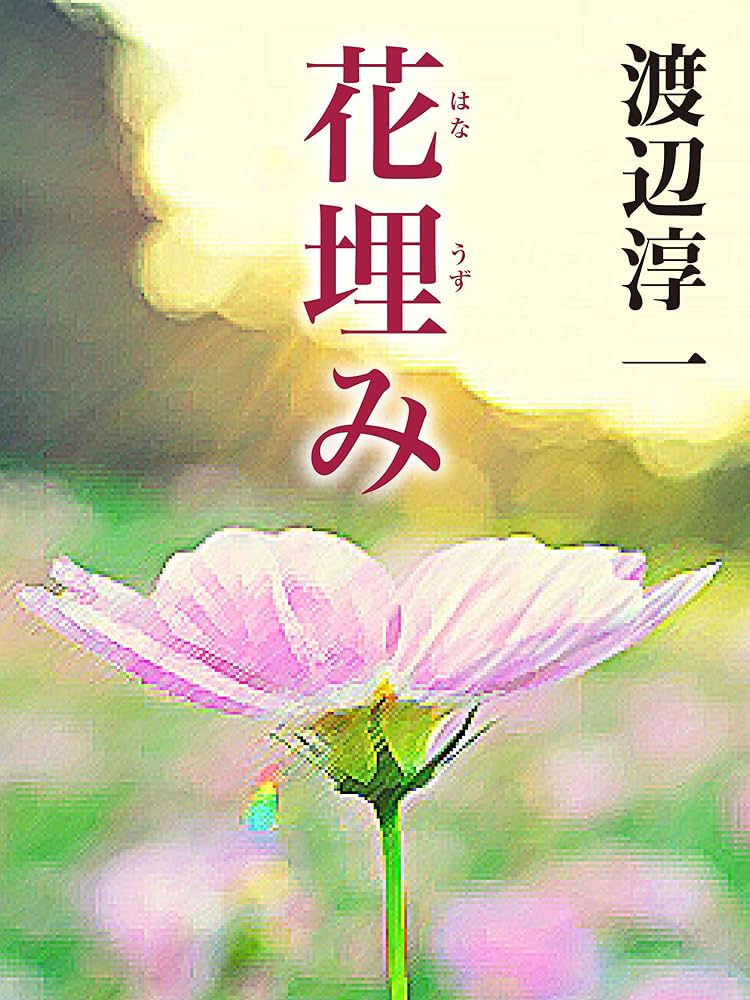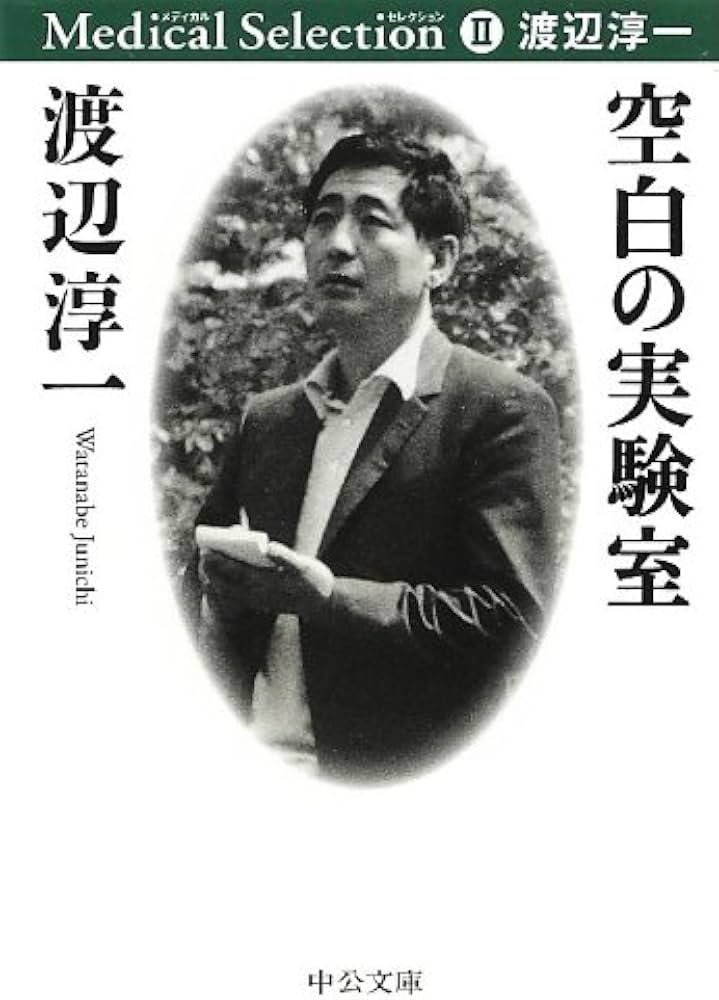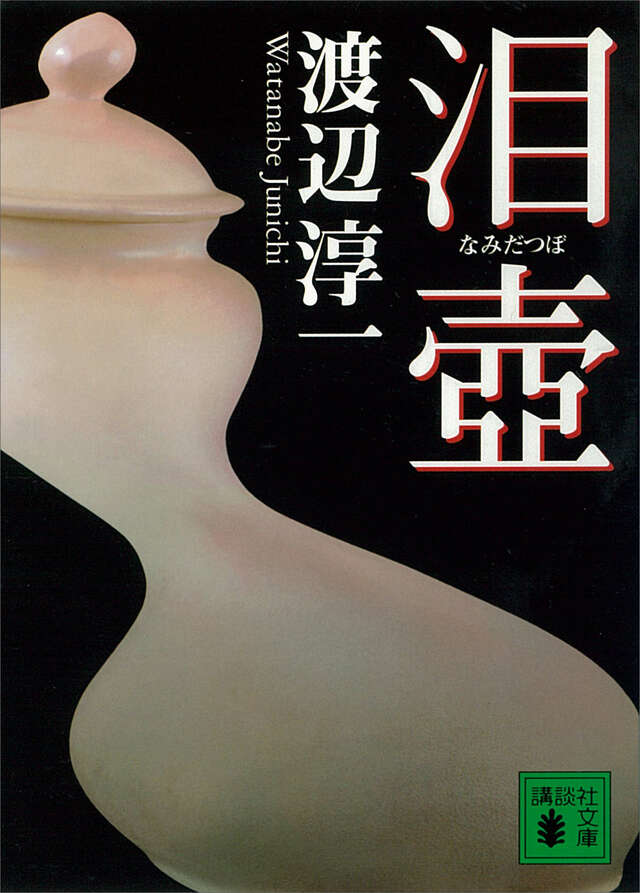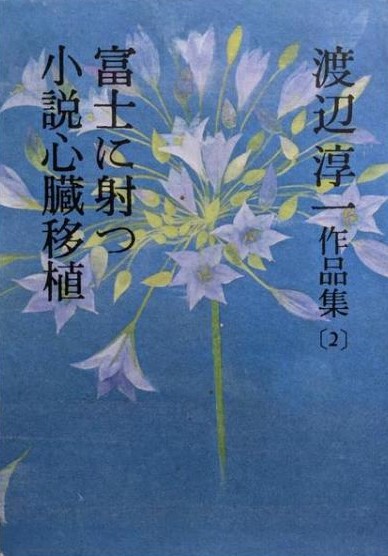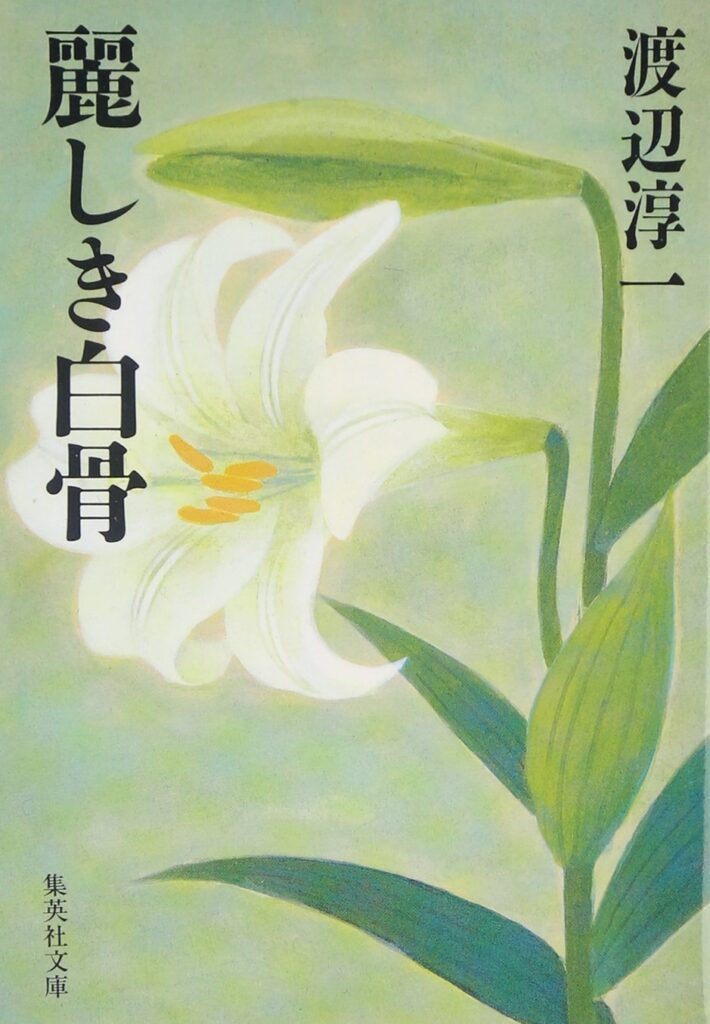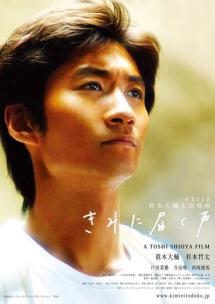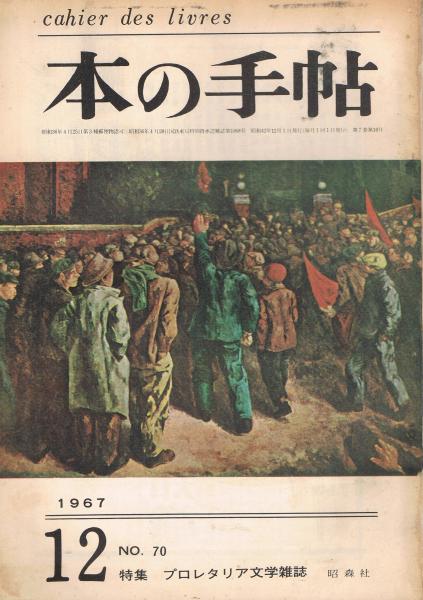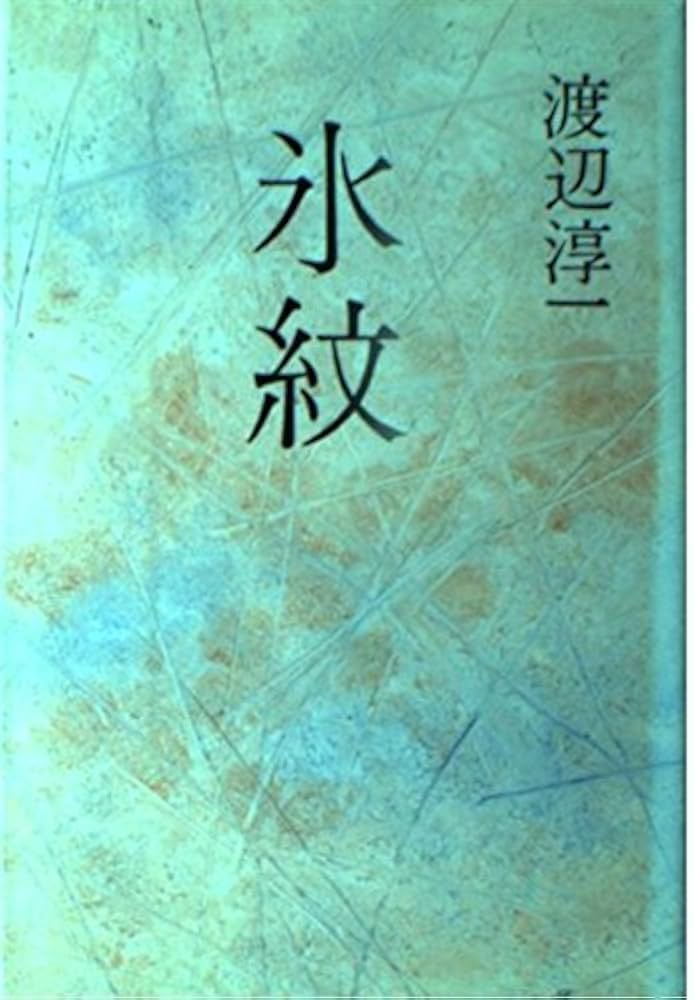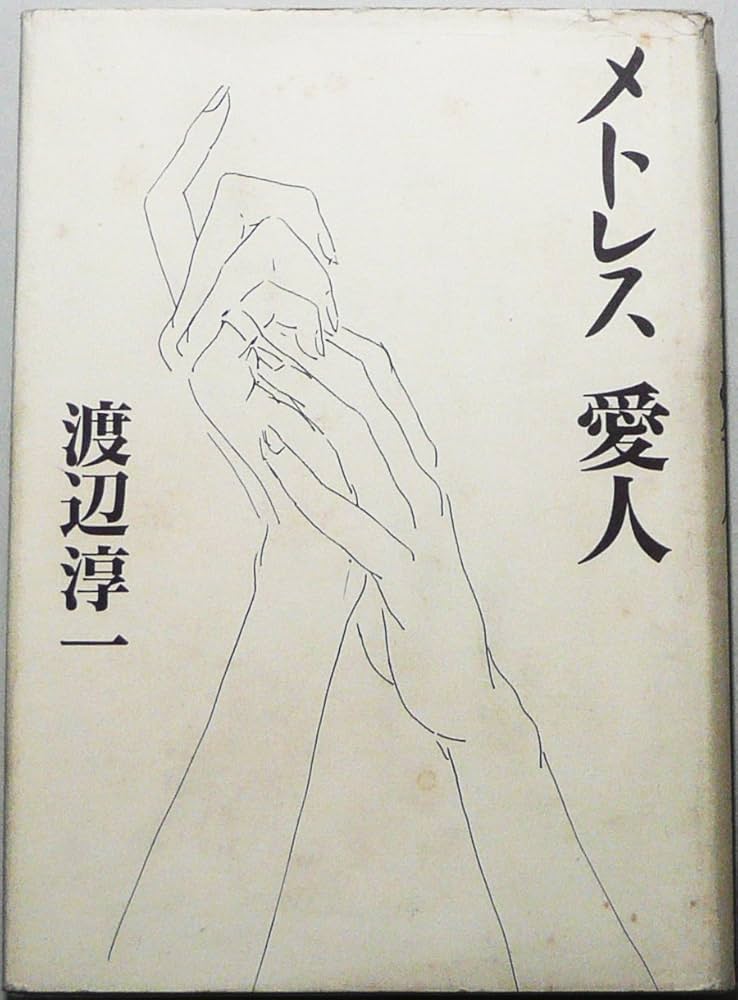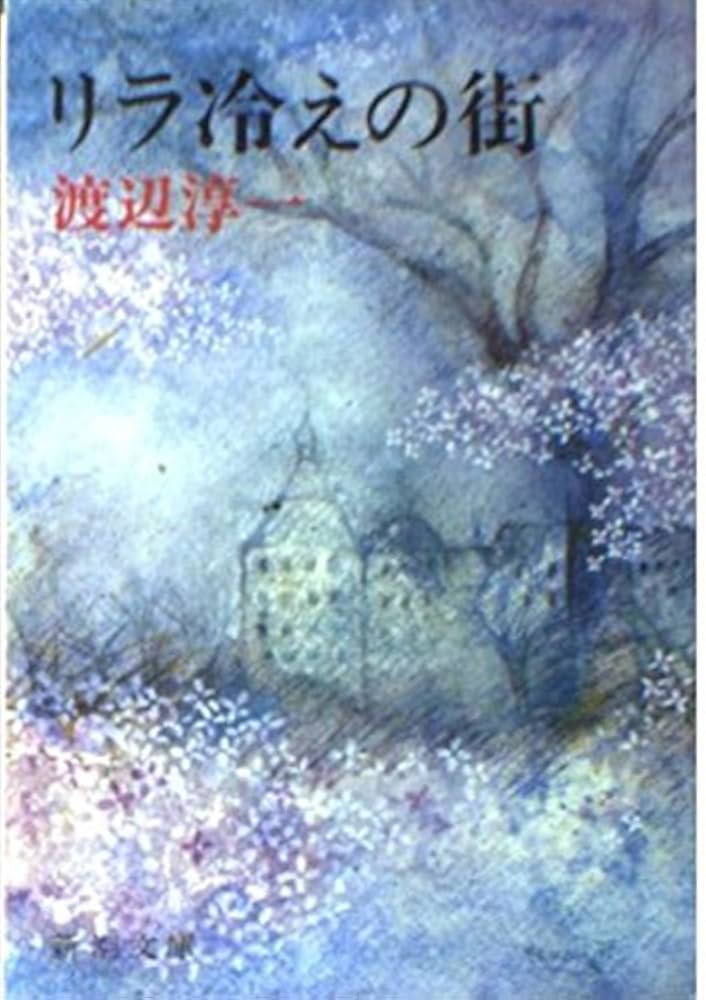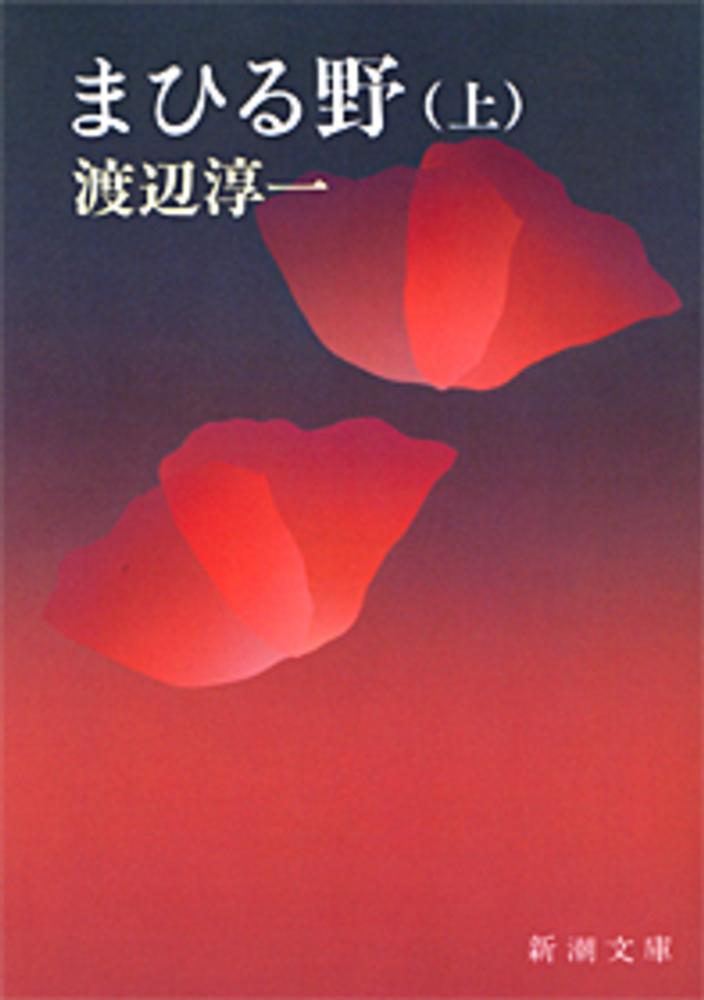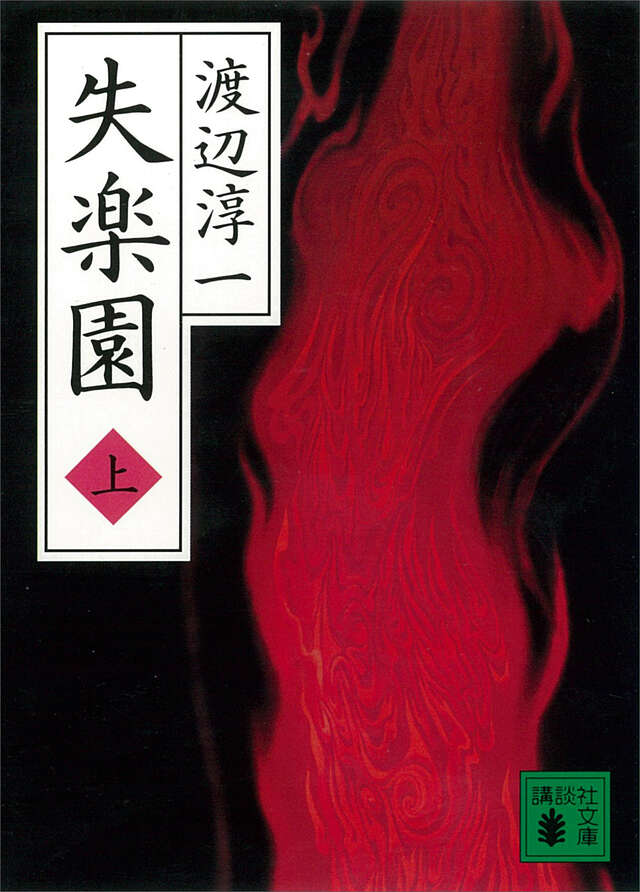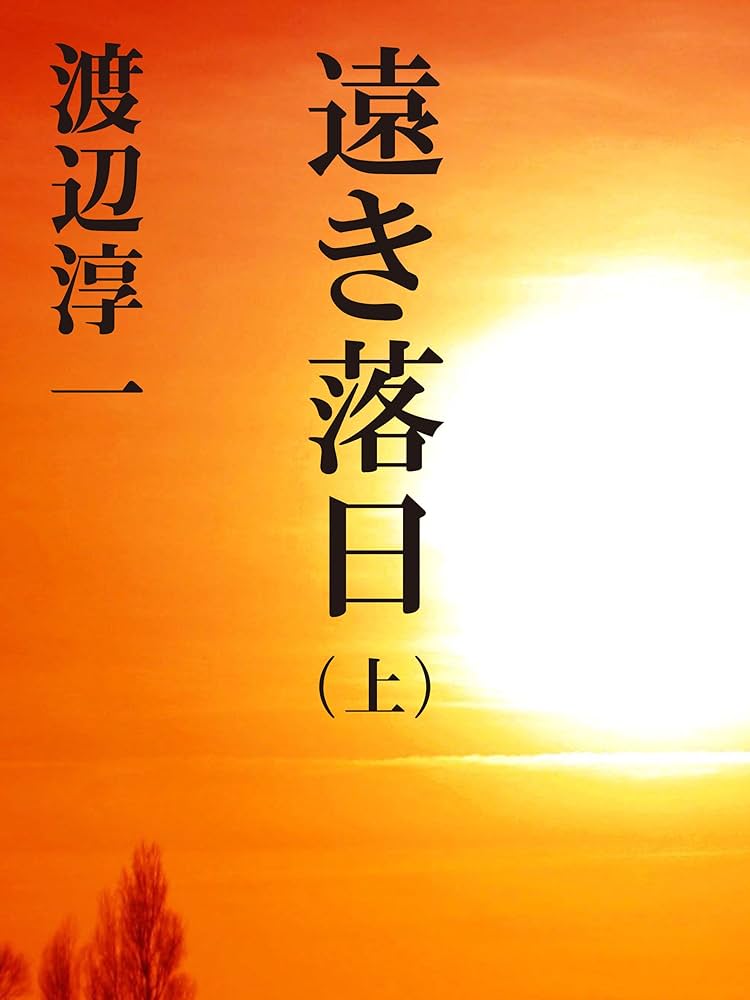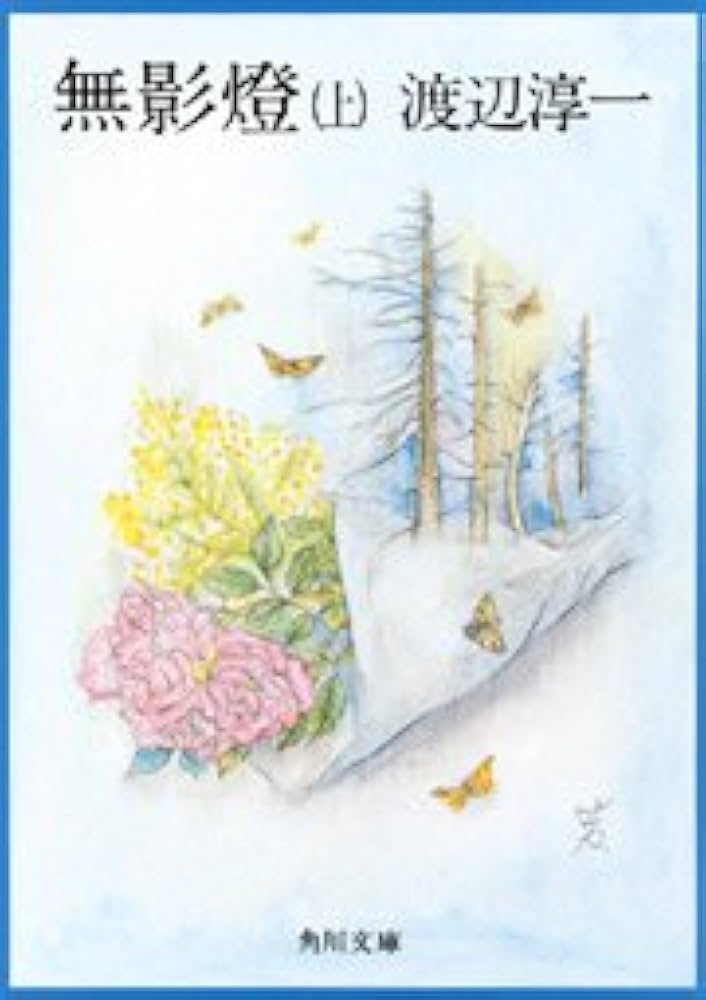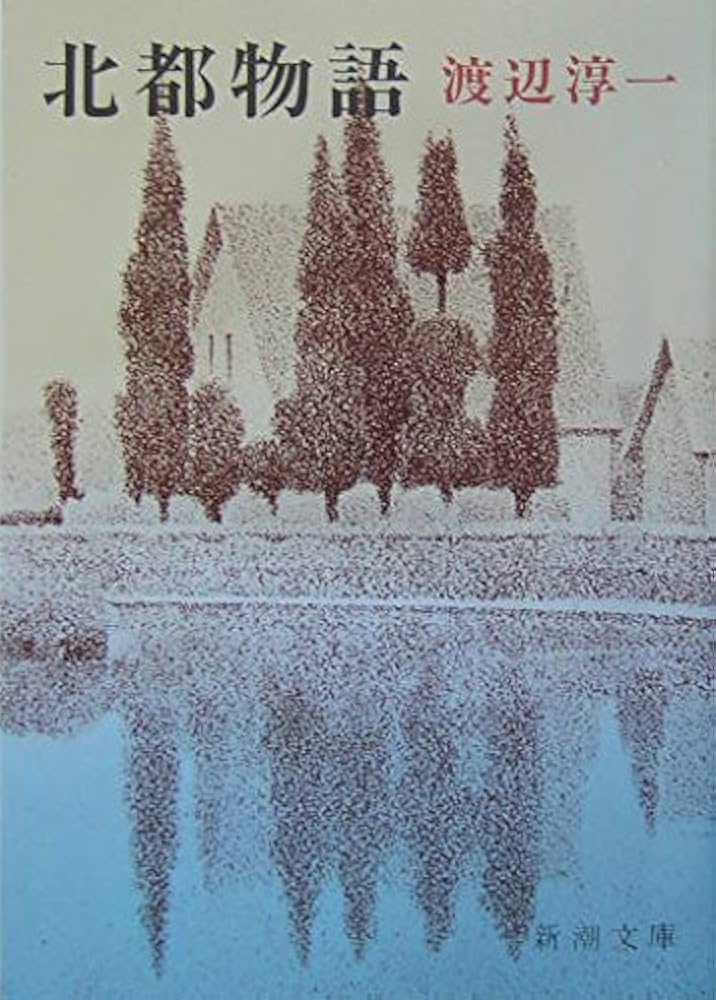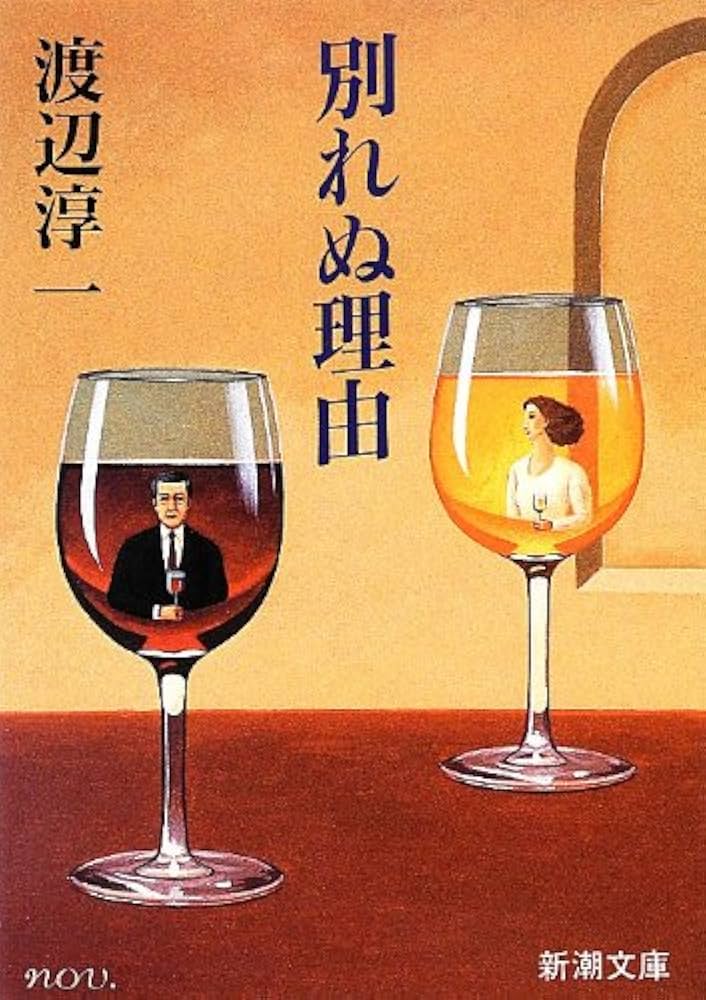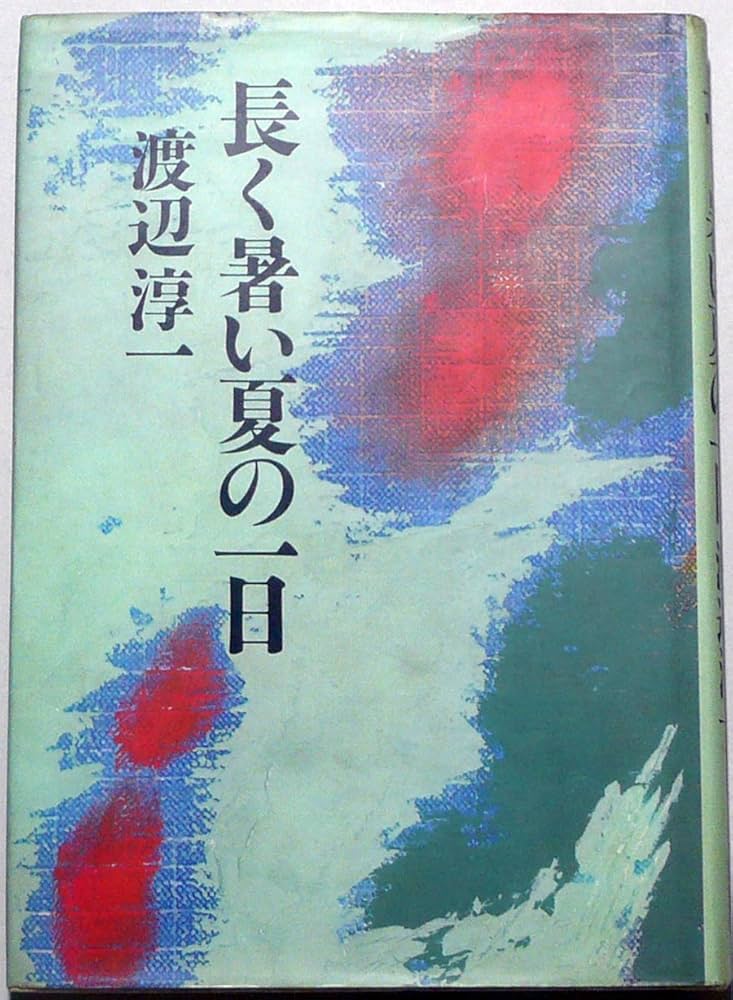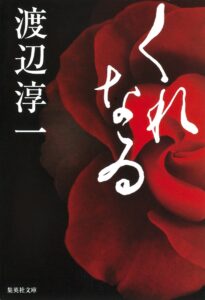 小説「くれなゐ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「くれなゐ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
渡辺淳一氏が描く、愛と性の深淵。その中でも、特に鮮烈な印象を残す一作がこの『くれなゐ』ではないでしょうか。発表されたのは1970年代半ばですが、現代を生きる私たちが読んでも、その問いかけの鋭さにはっとさせられます。女性の身体と心、そしてアイデンティティという、非常にデリケートで根源的なテーマを、作者は医師であった経験から得た冷徹なまでの視線で描ききっています。
物語の中心にあるのは、「子宮を失った女は、女でいられるのか」という、胸に突き刺さるような問いです。この一つの出来事をきっかけに、主人公の人生は大きく揺らぎ始めます。彼女がたどる魂の遍歴は、時に痛々しく、目を背けたくなるかもしれません。しかし、その先に彼女が見出す光景は、私たちに生きることそのものの意味を問いかけてくるようです。
この記事では、まず物語の骨子となる部分をご紹介し、その後で、物語の結末にも触れながら、私がこの作品から何を感じ、何を考えたのかを、少し長くなりますが詳しく語っていきたいと思います。この物語が持つ力、そしてその危うさも含めて、深く味わっていただければ幸いです。
「くれなゐ」のあらすじ
物語の主人公は、木之内冬子。28歳にして原宿に自身の帽子店を構える、才能あふれるデザイナーです。彼女は自立した現代女性であり、私生活では著名な建築家で妻子ある貴志祐一郎と、情熱的な恋愛関係にありました。仕事も恋も順調で、彼女の世界は完璧に見えたかもしれません。しかし、その輝かしい日々に、ある日突然、暗い影が差し込みます。
体に感じた異変から婦人科を受診した冬子は、子宮筋腫と診断されます。手術を受ければ問題ない、当初はそう考えられていました。筋腫だけを取り除く「核出術」を受けるはずだったのです。ところが、麻酔から覚めた彼女に告げられたのは、子宮をすべて摘出したという、あまりにも過酷な事実でした。彼女の同意のない、一方的な判断による手術でした。
この瞬間から、冬子の心は深く傷つき、「自分はもう女ではない」という強迫観念に取り憑かれてしまいます。愛する貴志に抱かれても、以前のように喜びを感じることができない。彼の優しささえも、自分を「欠陥品」として扱っているように感じてしまうのです。かつてあれほど満ち足りていたはずの二人の関係は、彼女が「不感」になったことで、徐々にその形を失っていきました。
愛する人との間にさえ、埋めようのない溝を感じ始めた冬子。アイデンティティの拠り所を失い、深い孤独と絶望の淵に立たされた彼女は、失われた自分自身を取り戻すため、あてのない、危険な魂の旅へと足を踏み入れていくことになるのです。
「くれなゐ」の長文感想(ネタバレあり)
この『くれなゐ』という物語を読み終えたとき、私はしばらくの間、言葉を失いました。それは単に感動したとか、面白かったという感情では片付けられない、もっと複雑で重い何かを受け取ってしまったような感覚でした。
物語が投げかける「子宮を失った女は、女でいられなくなるのか」という問い。これほどまでに直接的で、残酷な問いを、私は他に知りません。主人公・冬子の苦悩は、まさにこの一点から始まります。
彼女は、手術によって物理的に子宮を失っただけではありませんでした。それ以上に、彼女が失ったのは「女である自分」という、それまで疑いもしなかった自己認識そのものだったのです。これは、彼女の存在の根幹を揺るがす、あまりにも大きな喪失だったといえるでしょう。
その喪失感を埋めようとするかのように、恋人である貴志は、懸命に彼女を支えようとします。彼は、自分の愛があれば彼女を再び「目覚めさせる」ことができるはずだと信じていました。しかし、その試みはことごとく失敗に終わります。
彼の努力が深まれば深まるほど、二人の間の性愛は、かつての情熱的な交歓から、まるで臨床実験のような無機質な行為へと変わっていきました。冬子にとって、それは愛の確認ではなく、自分が「女ではない」という事実を繰り返し突きつけられる、苦痛な儀式でしかありませんでした。この過程で、二人の関係が修復不可能なほどに壊れていく様は、読んでいて本当に胸が痛みました。
貴志との異性愛の枠組みの中では救いを見いだせないと悟った冬子は、やがて新たな関係性へと足を踏み入れます。相手は、彼女の店の顧客である、洗練された年上の女性、中山麻子でした。この同性との関係は、冬子にとって一つの避難所だったのかもしれません。
そこには、自身の「欠落」を意識させられる男性器の存在がありません。ただ、純粋な感覚のやりとりがあるだけです。麻子の腕の中で、冬子はこれまでとは違う種類の官能と安らぎを見出します。評価されることのない、ただ受け入れられる身体。このサフィックな関係は、彼女に一時的な休息を与え、傷ついた自己を回復させるための重要なステップだったように感じられます。
しかし、それもまた、永続的な魂の救済にはなり得ませんでした。彼女の心の空洞は、それほどまでに深かったのです。そして、物語は最も衝撃的で、倫理的に大きな問題をはらんだ展開へと進んでいきます。
冬子が、レイプの被害に遭うのです。この暴力的な出来事が、皮肉なことに、彼女の閉ざされた感覚の扉をこじ開けるきっかけとなってしまいます。性的不感症だった彼女が、この暴力によって再び「感じる」体を取り戻す。この展開には、正直、強い嫌悪感と戸惑いを覚えました。
「なぜ、こんな形でしか彼女は救われなかったのか」。そう思わずにはいられませんでした。性的暴力を、個人の再生のための触媒として描くことの危うさ。現代の視点から見れば、これは極めて危険な発想であり、決して肯定できるものではありません。多くの読者がこの部分に強い抵抗を感じるのも当然でしょう。
この描写は、おそらく渡辺淳一という作家が持つ、一種の生命主義の表れなのかもしれません。極限のショックや暴力的な体験が、停滞した生を揺り動かし、変化をもたらすというテーマは、彼の他の作品にも通底するものです。しかし、その手法の残酷さ、倫理的な問題点から目をそらすことはできません。
この物語には、もう一つの重要な柱があります。それは、冬子の同意なく子宮を摘出した執刀医に対する、医療過誤をめぐる戦いです。冬子に代わって、恋人である貴志が法的手段に訴えようと動き出します。
しかし、彼の前に立ちはだかったのは、医療界という巨大な権力の壁でした。執刀医の父親は医師会の大物であり、その権力によって貴志は社会的に追い詰められ、仕事を失うという報復まで受けてしまいます。この展開は、個人の正義がいかに巨大な組織力の前で無力であるかを、容赦なく描き出しています。
この医療訴訟のサブプロットは、物語の中で巧みな役割を果たしていると感じました。男性の庇護者(貴志)も、社会の正義(法)も、結局は彼女を救うことができない。外部からの救済という道がすべて断ち切られることで、冬子は完全な孤立状態に追い込まれます。
そして、この絶対的な孤独こそが、彼女が最終的に誰にも頼らず、自分自身の力で再生を遂げるための、必要不可欠な条件となるのです。物語は、彼女を救済のない荒野へと突き放すことで、内なる力の発露を促しているようにも見えます。
あらゆる救いの可能性を失い、絶望の淵をさまよった冬子。彼女の魂の遍歴は、ある静かな、しかしあまりにも鮮烈な光景によって、劇的な終着点を迎えます。その鍵となるのが、作品の題名でもある「くれなゐ」です。
ある日、彼女が目にしたのは、燃えるように咲き誇る葉鶏頭(はげいとう)の群生でした。その、命の色そのものであるかのような、圧倒的なまでの「くれなゐ」。その色を見つめるうち、冬子は自分自身の内にも、同じように燃え盛る生命の力があることを感じ取るのです。
それは、子宮があるからとか、男性に愛されるからといった、条件付きの「女」としての自己ではありません。ただ、ここに生きている一つの生命体としての、根源的な自己肯定感でした。この瞬間、彼女は他者の評価から完全に解放され、自分自身の足で生きていくことへの、揺るぎない自信を取り戻したのです。
このクライマックスの美しさは、筆舌に尽くしがたいものがあります。それまでの凄惨な遍歴があったからこそ、この静かな内面的な解放の瞬間が、より一層輝いて見えるのです。最終的に彼女を救ったのは、社会的な正義の実現でも、誰かとの関係性の修復でもなく、自然の中に脈打つ生命の力との交感という、極めて個人的で審美的な体験でした。
この『くれなゐ』は、渡辺淳一文学の真骨頂ともいえる作品です。医師としての冷静な観察眼と、恋愛小説家としての情熱的な筆致が見事に融合しています。しかし同時に、1970年代という時代の価値観が色濃く反映されており、現代の私たちが読むと、その「偏った女性像」や、時に感じられる男尊女卑的な視点に、違和感を覚えることも確かです。
それでもなお、この物語が持つ力は色褪せません。女性の身体と心、そして性が、これほどまでに率直に、赤裸々に描かれた作品は稀有でしょう。冬子の旅は、社会や他者によって作られた「女」という役割をすべて剥ぎ取られ、剥き出しの生命として、生きることの根源に流れる「くれなゐ」の力に再び触れるまでの、壮絶な記録です。その手法はあまりにも残酷で、その哲学には議論の余地があります。しかし、だからこそ、この物語は読む者の心を激しく揺さぶり、忘れがたい印象を残すのだと思います。
まとめ
渡辺淳一氏の小説『くれなゐ』は、女性の身体とアイデンティティをめぐる、痛切で衝撃的な物語です。主人公・冬子が子宮摘出という過酷な現実を突きつけられ、自己を見失いながらも、もがき苦しんだ末に魂の再生を遂げるまでを、克明に描き出しています。
物語の展開には、現代の倫理観からは受け入れがたい部分も含まれており、読む人によっては強い抵抗を感じるかもしれません。特に、性的暴力を再生のきっかけとして描く手法は、大きな議論を呼ぶ点でしょう。しかし、それらの要素も含めて、本作が人間の「生」の本質に深く迫ろうとした、力強い作品であることは間違いありません。
愛憎、裏切り、そして社会の不条理に翻弄され、絶対的な孤独の中で冬子が見出した「くれなゐ」の光景。その内なる解放の瞬間は、私たち読者に、生きることの根源的な意味と、自己を肯定することの尊さを教えてくれます。
この物語は、単なる恋愛小説の枠を超え、一人の人間の尊厳をめぐる壮絶な闘いの記録として、これからも多くの人々の心を揺さぶり続けるでしょう。重厚で、時に読むのが辛い作品ではありますが、それだけの価値がある一作です。