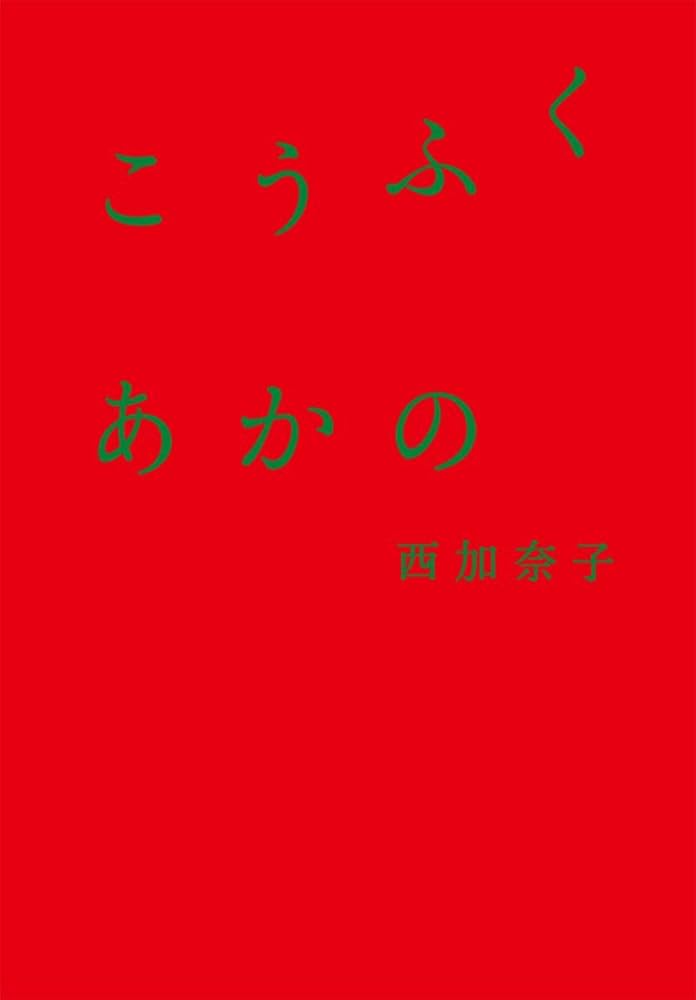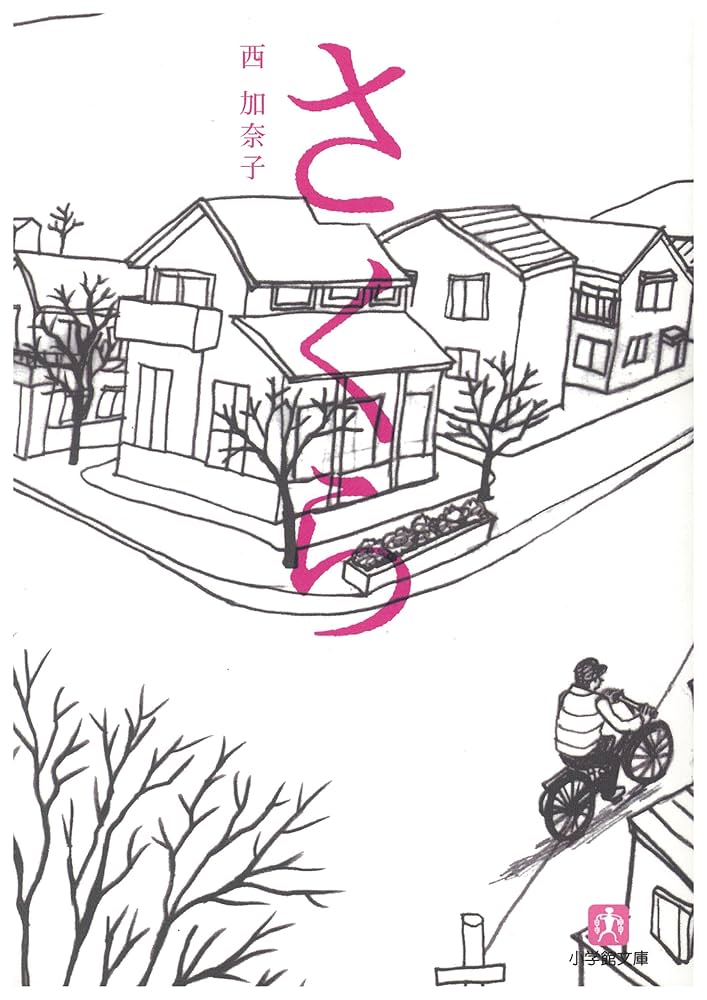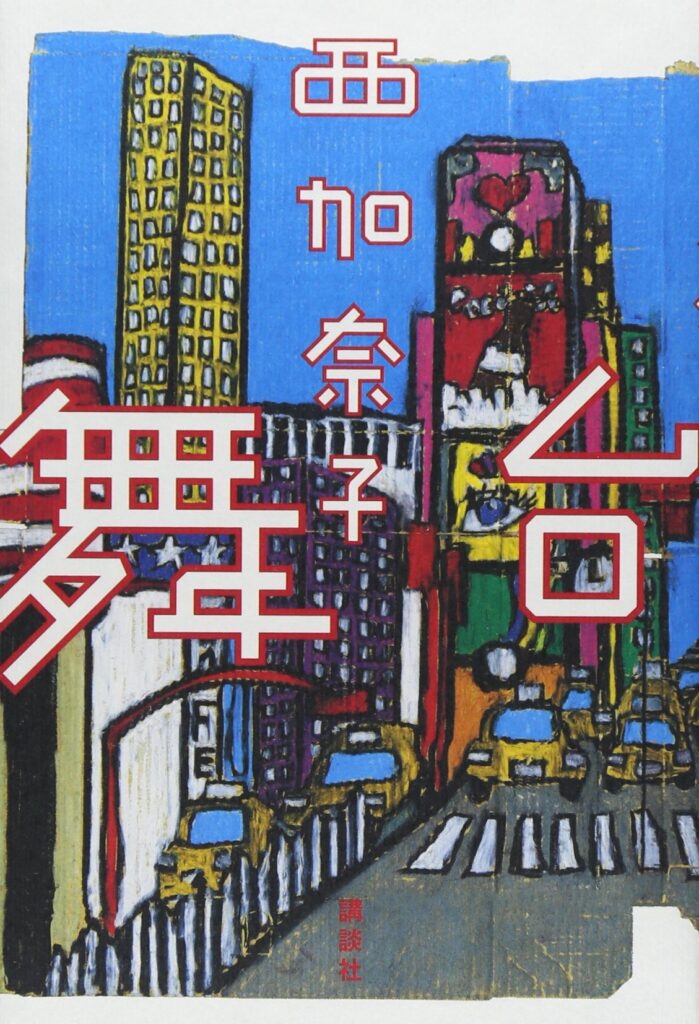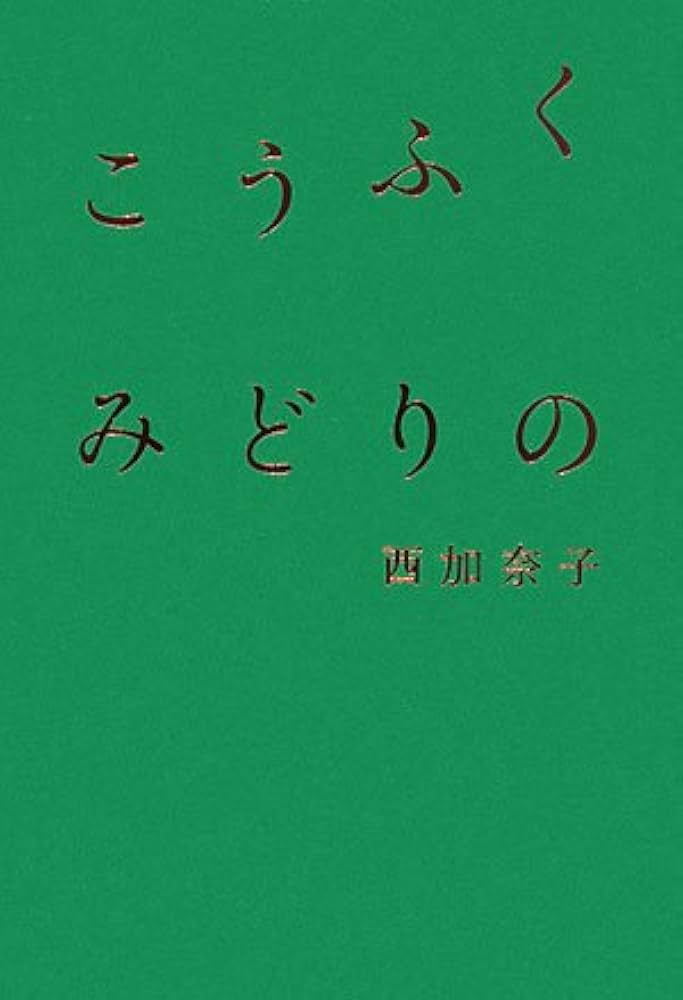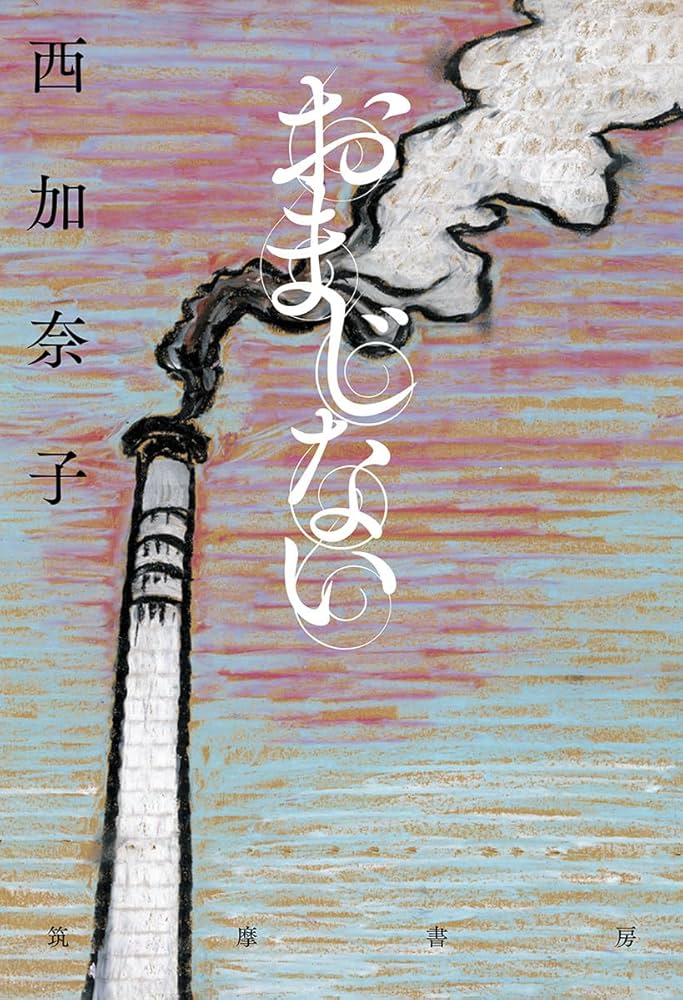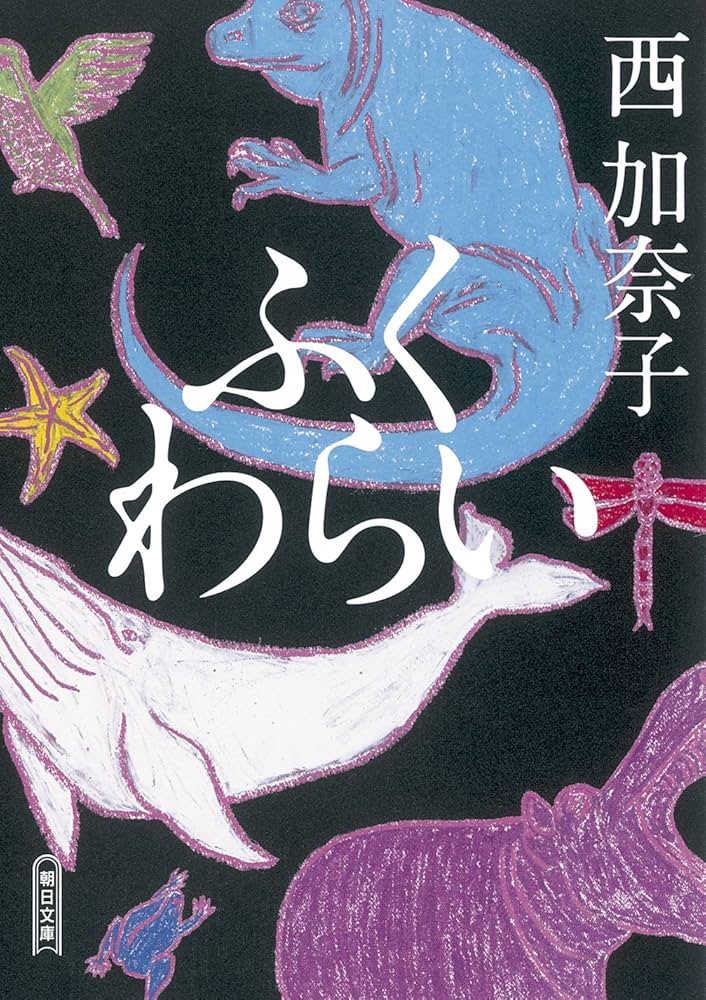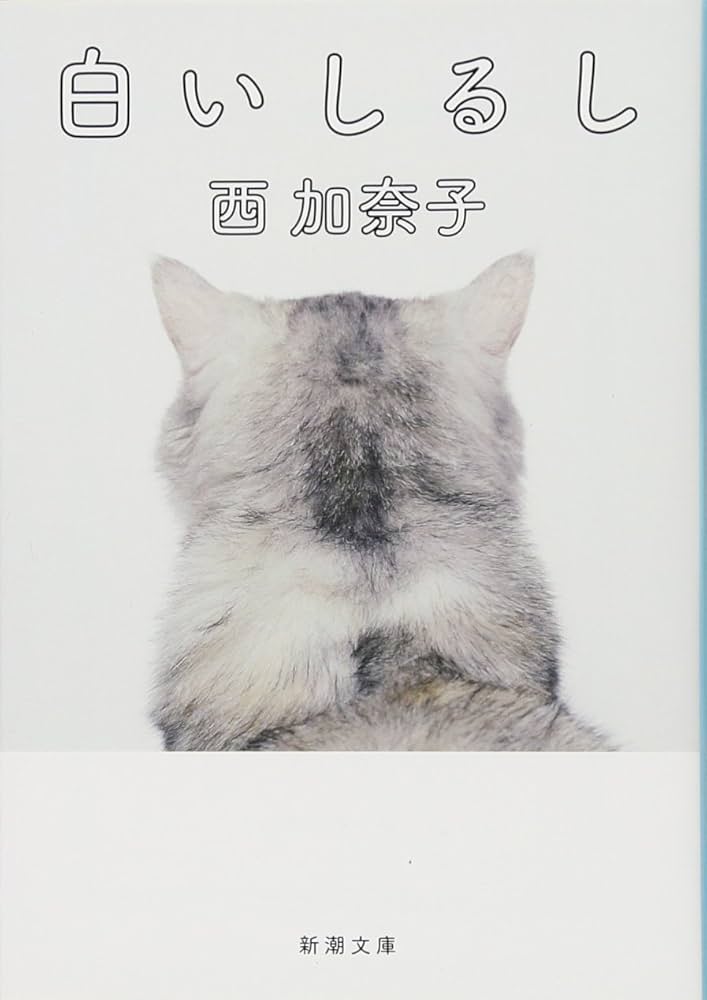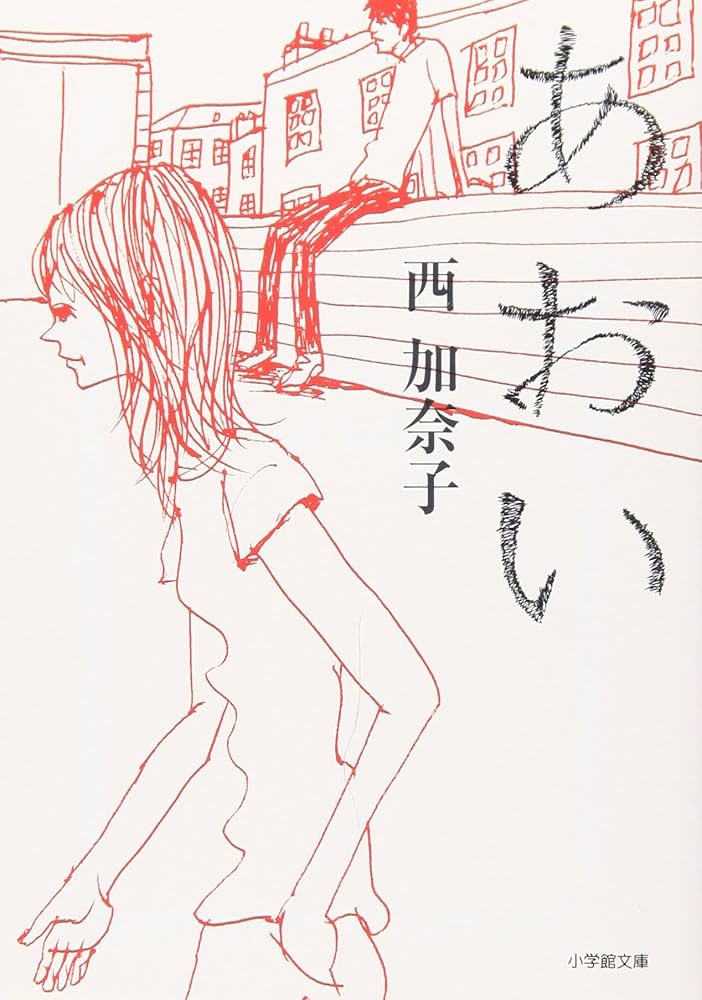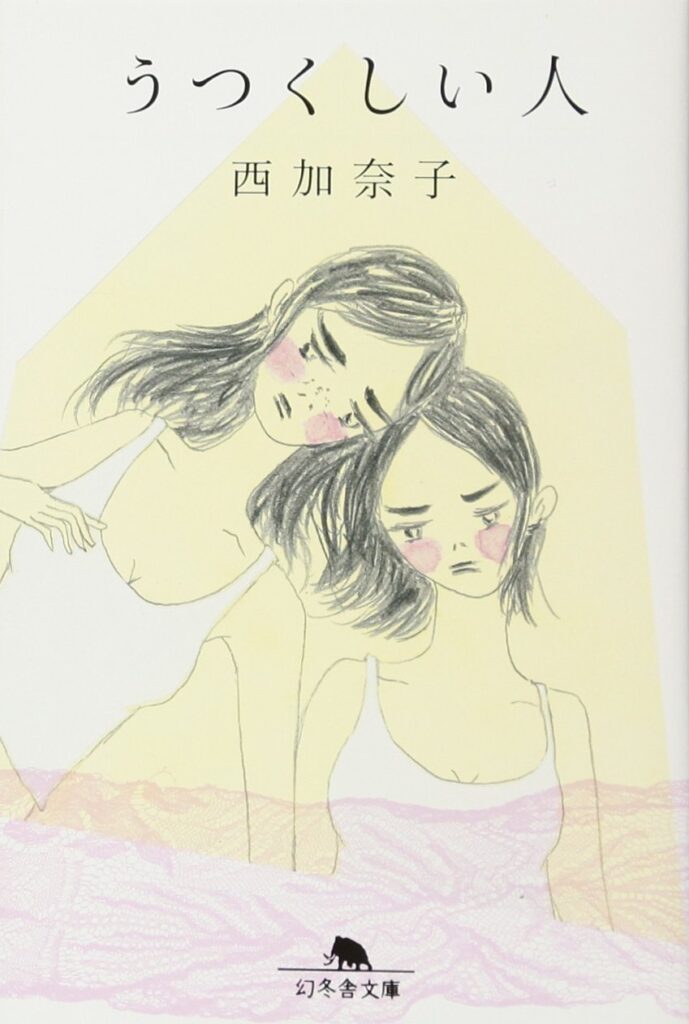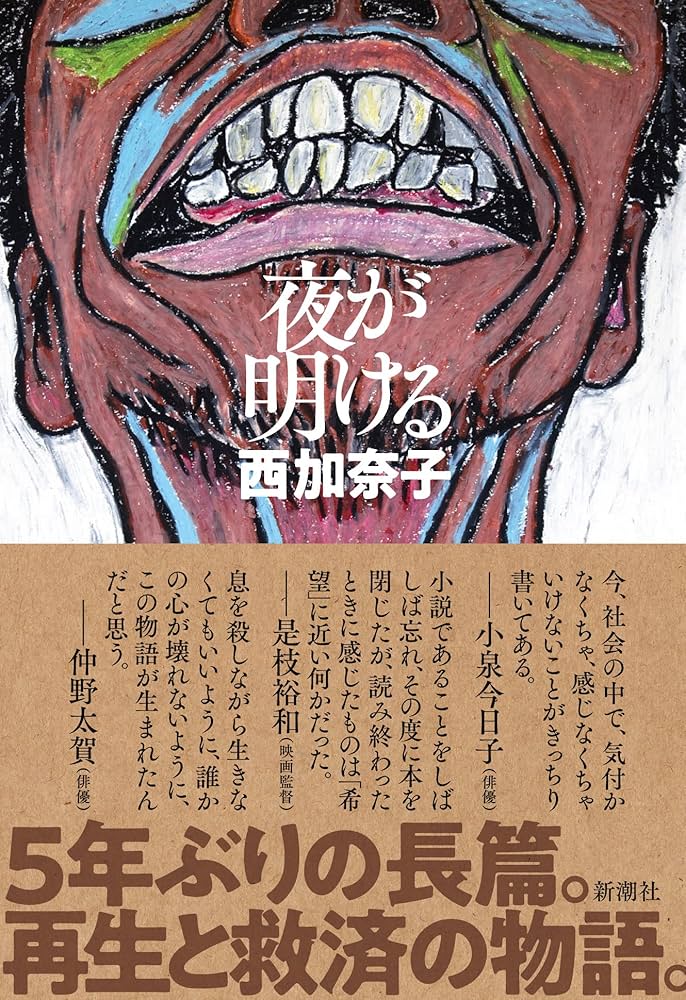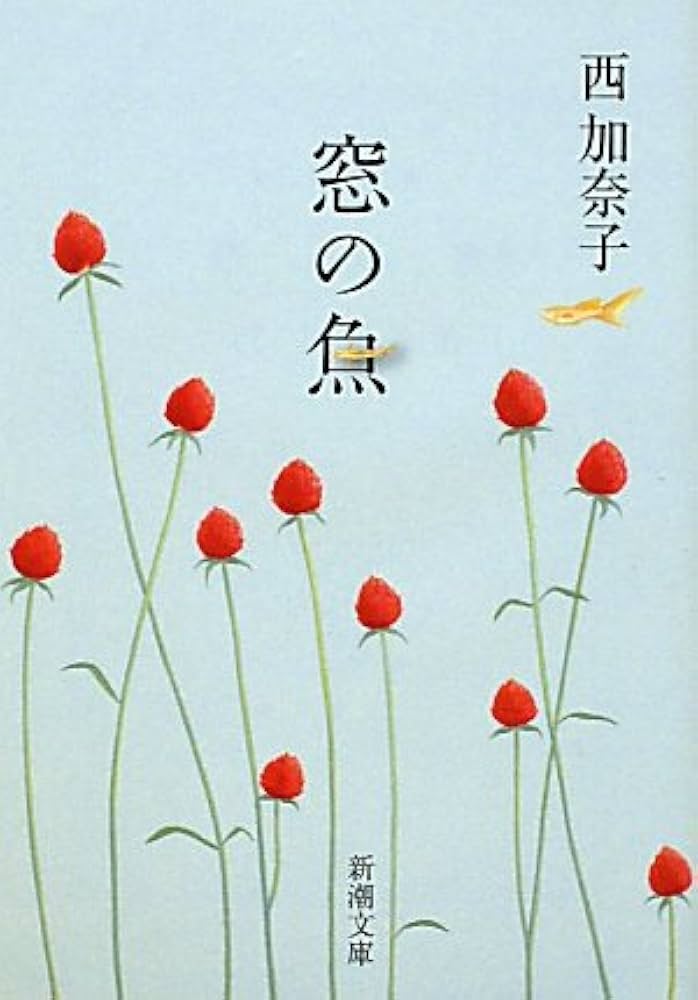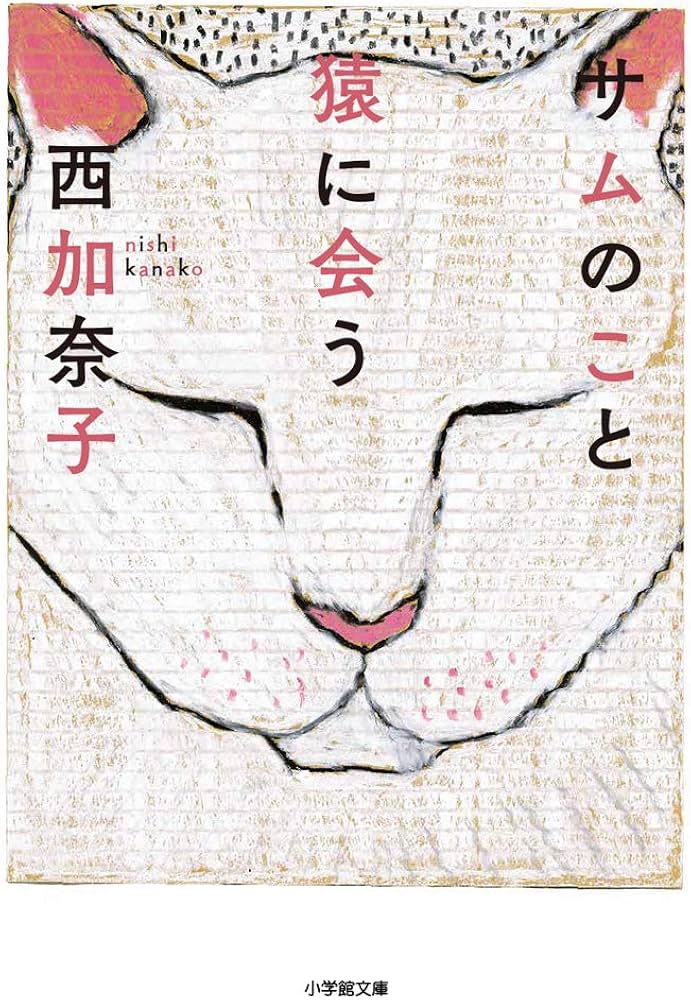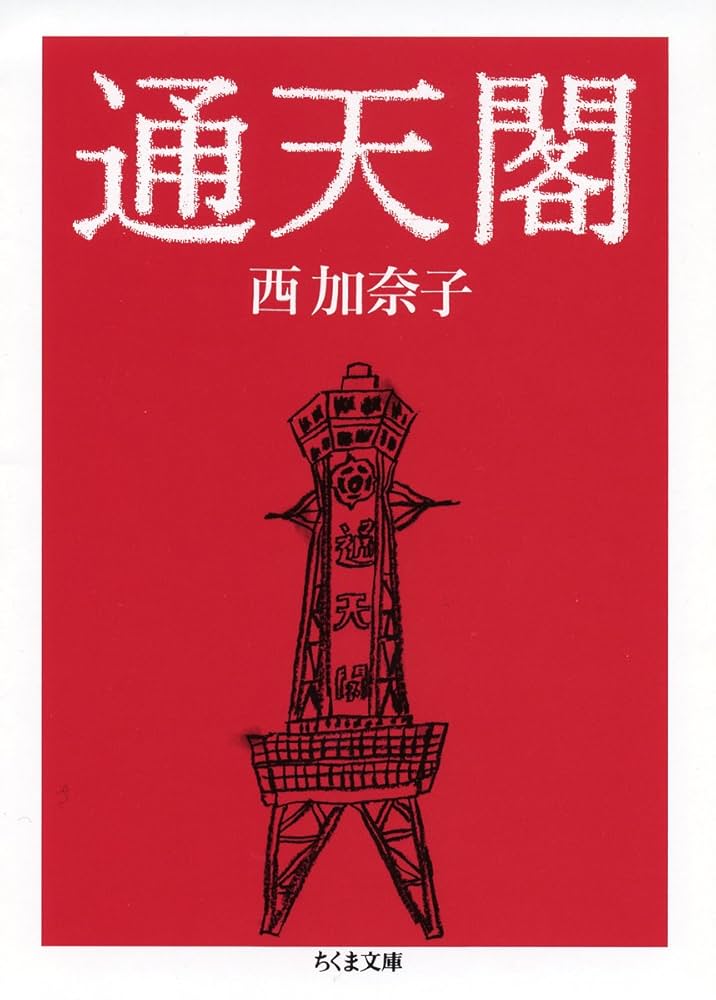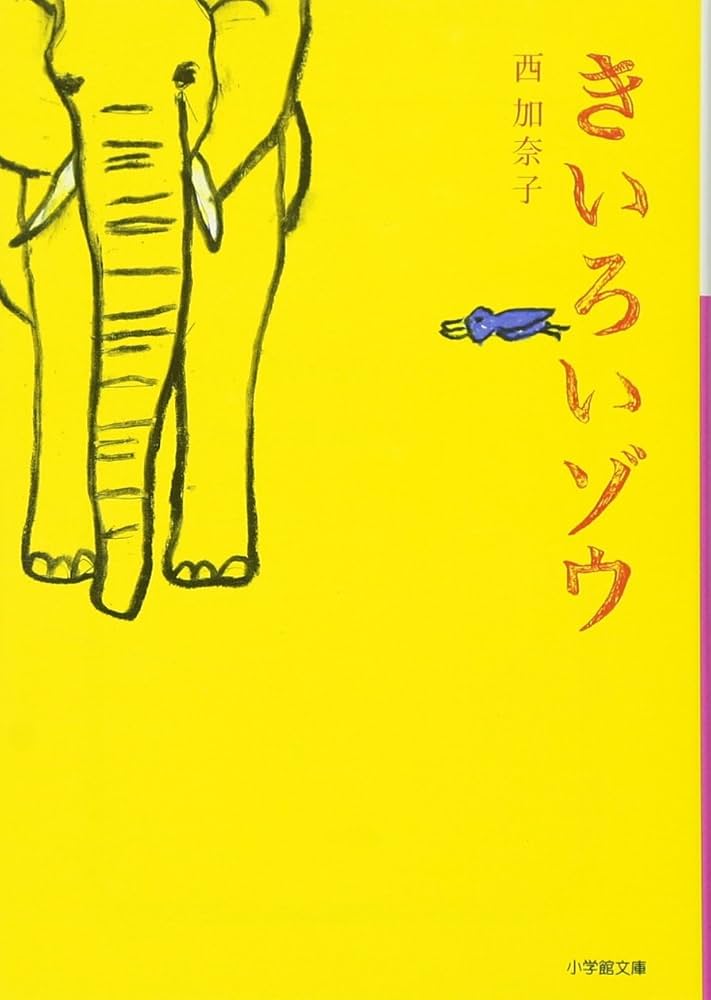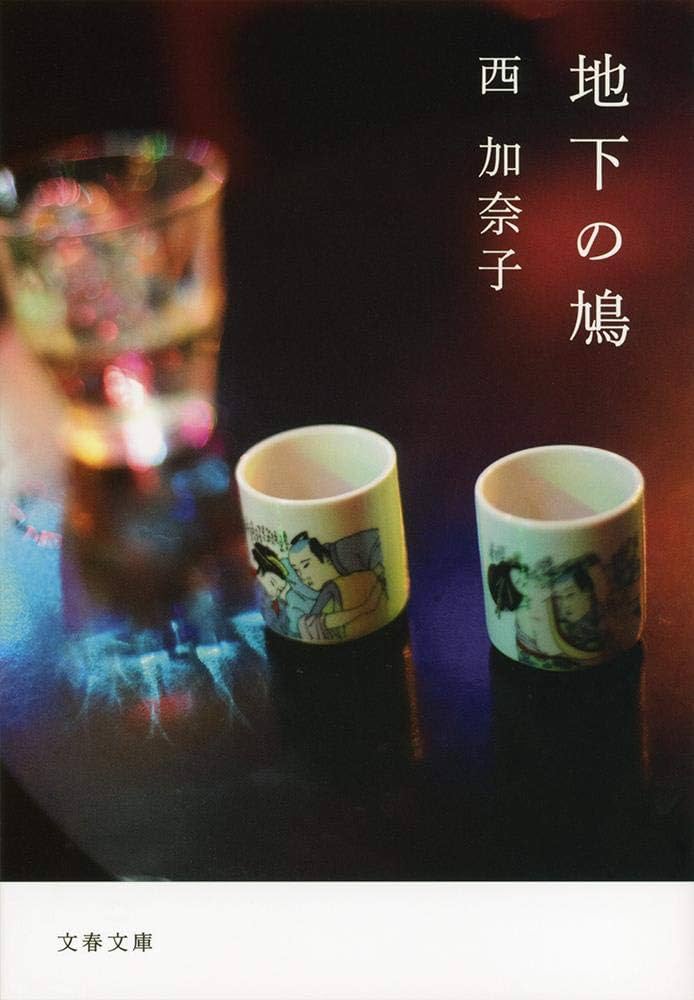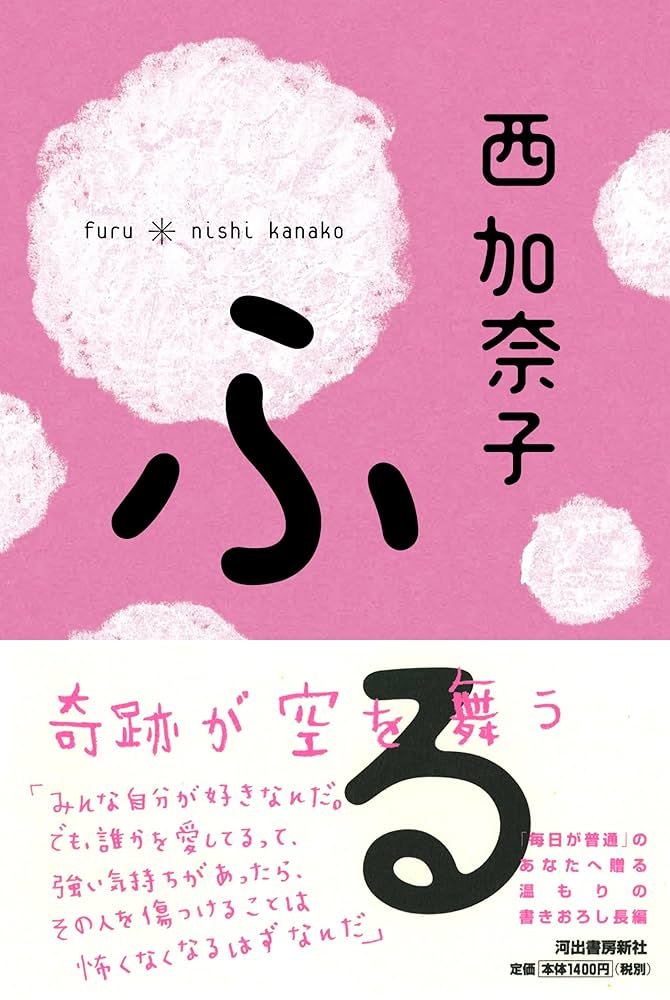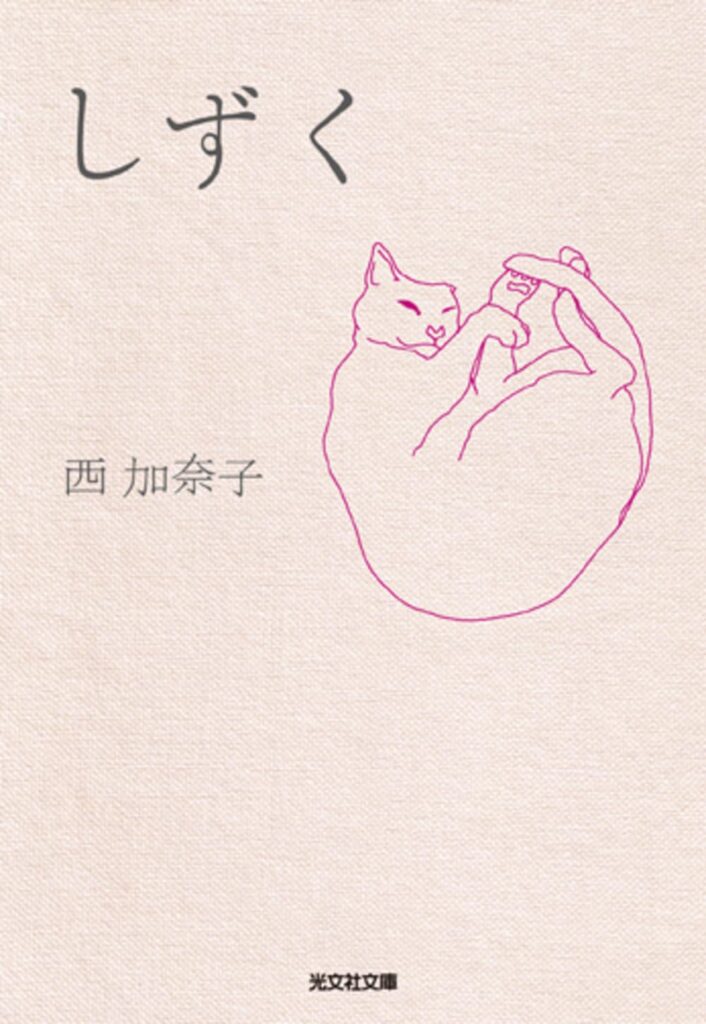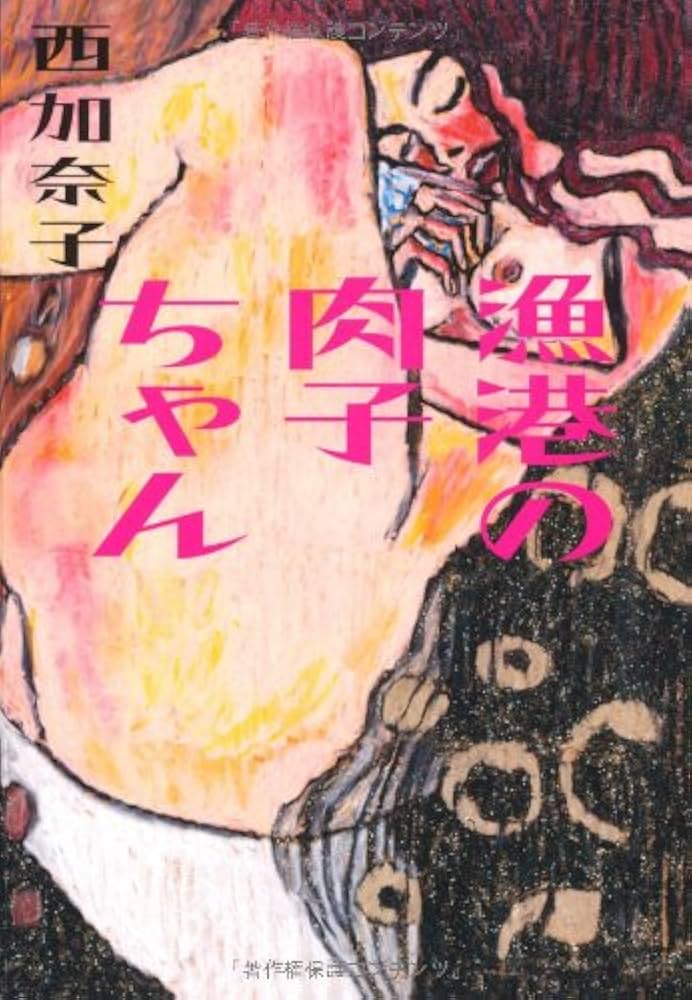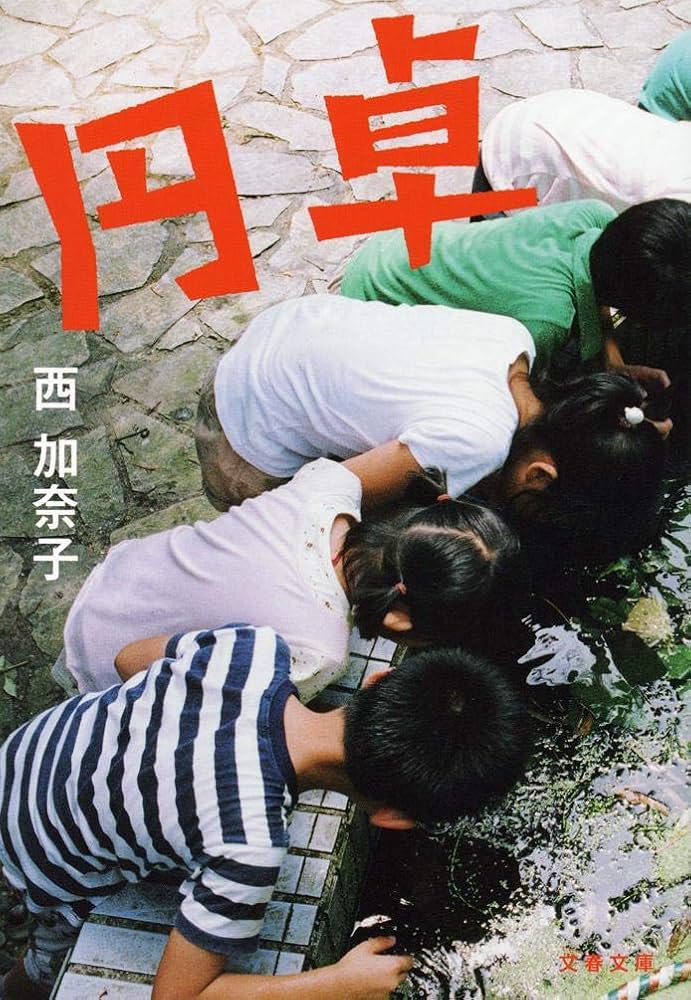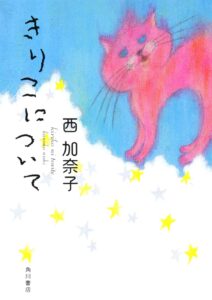 小説「きりこについて」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「きりこについて」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
西加奈子さんの長編「きりこについて」は、「きりこは、ぶすである。」という、あまりにも衝撃的な一文から幕を開けます。この冒頭は、美醜という普遍的なテーマを真正面から問いかける西さんの強い意志を感じさせます。美人な「まぁま」とハンサムな「ぱぁぱ」の間に生まれたにもかかわらず、「紛う事なきぶす」と描写される主人公きりこが、社会の美醜の基準に翻弄されながらも、真の自己受容に至るまでの軌跡を描いた作品です。
きりこは両親の無償の愛情に包まれ、「世界一可愛い女の子」と信じて疑わずに育ちます。しかし、小学5年生の時に「ぶす」という残酷な言葉を突きつけられたことをきっかけに、彼女の世界は一変します。引きこもり、葛藤する中で、彼女は賢い黒猫ラムセス2世と出会い、その超然とした視点から人間社会の価値観を相対的に見つめ直すようになります。
本作は、外見という「容れ物」と、内面という「中身」の間に揺れる人間の普遍的な苦悩を深く掘り下げます。特に現代社会に蔓延するルッキズムや、SNSによる他者評価のプレッシャーに苦しむ人々にとって、この物語は自己肯定感を取り戻すための大きなヒントを与えてくれるでしょう。西加奈子さん独自のユーモラスで時に容赦ない表現は、読者の心に深く突き刺さりながらも、温かい肯定感で包み込んでくれます。
彼女の成長物語は、単なる美醜の問題に留まらず、多様な人間関係や社会の不条理、そして何よりも「自分を愛すること」の重要性を私たちに教えてくれます。これは、誰もが抱える「生きづらさ」に対する、西加奈子さんからの力強いエールだと私は思います。
「きりこについて」のあらすじ
物語の主人公きりこは、誰もが認める美男美女の両親の間に生まれました。しかし、その容姿は「紛う事なきぶす」と周囲から見られ、彼女自身も成長するにつれてその事実を突きつけられていきます。それでも、きりこは両親から惜しみない愛情を注がれ、「世界一可愛い女の子」だと信じて疑わず、幼少期は揺るぎない自信と持ち前のリーダーシップで周囲を従える「皇女のような少女時代」を送ります。
しかし、小学5年生になったきりこに転機が訪れます。初めて恋をした男の子、こうた君に勇気を出してラブレターを送ったところ、面と向かって「ぶす」と言い放たれてしまうのです。この一言は、きりこの内なる世界を音を立てて崩壊させ、彼女は深いショックから引きこもるようになります。これまで築き上げてきた自己肯定感が崩れ去り、社会の「ぶす」という認識に直面したきりこは、深い絶望の中にいました。
そんなきりこの引きこもり生活の中で、彼女の人生に深く関わることになるのが、小学校の体育館裏で拾った黒猫、ラムセス2世です。ラムセス2世は驚くほど賢く、やがて人間の言葉を理解するようになります。きりこの唯一無二の親友となり、精神的な支えとなるラムセス2世は、きりこが大切にしていた白玉を落としたことがきっかけで出会い、その存在が彼女の人生に大きな変化をもたらすことになります。
ラムセス2世の視点から描かれる人間社会は、きりこが苦しむ「美醜」や「社会的評価」といった価値観が、いかに些細なことであるかを浮き彫りにします。猫の超然とした視点は、きりこの内なる葛藤に寄り添いながら、彼女が再び外の世界に目を向け、自己を見つめ直すきっかけを与えていくのです。きりこは、このかけがえのない存在とともに、自己受容への道を歩み始めます。
「きりこについて」の長文感想(ネタバレあり)
「きりこは、ぶすである。」
西加奈子さんの「きりこについて」を初めて手に取ったとき、この冒頭の一文には、まさに痺れました。川端康成の「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」と並び称されるほど、この短いフレーズは、物語の全てを凝縮し、読者の心に深く問いかけます。それは単なる導入ではなく、私たち読者が無意識に抱いている「美醜」という固定観念や、現代社会に深く根ざしたルッキズム(外見至上主義)に、冒頭から揺さぶりをかける挑発的なメッセージだと私は感じました。この「容赦なさ」こそが、作品全体で展開される「容れ物」と「中身」という主要なテーマへの導入として機能し、私たちに自己反省を促す効果があるのでしょう。
物語は、誰もが認める美人な「まぁま」とハンサムな「ぱぁぱ」の間に生まれながらも、「紛う事なきぶす」と描写される主人公きりこの成長と自己発見の軌跡を描いていきます。両親から「可愛い、可愛い」と惜しみない愛情を注がれ育ったきりこは、自身を「世界一可愛い女の子」と信じて疑わず、持ち前のリーダーシップで周囲を従え、「皇女のような少女時代」を過ごします。この幼少期の描写は、きりこが社会の評価とは無関係に、いかに純粋な自己認識と自信に満ちた存在であったかを読者に提示し、その後の人生における大きな落差を際立たせる基盤となります。きりこの幼少期は、両親の無条件の愛と、子供たちの「酔い」とも表現される判断の甘さによって、自分が「ぶす」であることに全く気づかずに「可愛い子」として振る舞うことができたのです。これは、子供時代の純粋さや無知が、同時に社会の残酷さ、つまり他者の評価に敏感になる時期に直面するまでの一時的な猶予期間であったことを示唆しているように思えます。
しかし、小学5年生の時に好きな男の子から「ぶす」と面と向かって言われたことを転機に、きりこは社会の厳しい現実に直面し、自身の外見と内面の関係性、そして自己受容の道を模索していくことになります。この一言は、きりこにとって計り知れない衝撃となり、それまで両親の愛情と自身の揺るぎない自信によって築き上げられていた「世界一可愛い女の子」という内なる世界が、音を立てて崩壊する瞬間でした。この出来事により、きりこは自身が「ぶす」であるという社会的な認識に直面し、深いショックから引きこもる日々を送るようになります。この転換点は、単なる個人的なショックではなく、社会化の過程で避けられない「自己認識の強制」であり、その過程で多くの人が経験する「自己肯定感の揺らぎ」を象徴していると言えるでしょう。
本作の大きな特徴は、きりこが小学校の体育館裏で拾った賢い黒猫「ラムセス2世」の視点を通して物語が語られる点です。ラムセス2世は人間の言葉を理解し、きりこの親友となる存在であり、その超絶俯瞰的な視点は「神様」のようだと評されます。この猫の視点は、人間社会の「可愛い」「美人」といった凝り固まった価値観を相対化し、読者に「自分は自分」という境地に達するための新たな視点を提供するのです。自己受容や外見と内面のテーマは文学において普遍的ですが、本作では「ぶす」という極端な設定と、人の言葉を理解する猫という要素を組み合わせることで、現代社会のルッキズムやSNSによる他者評価のプレッシャーといった、現代的な文脈でテーマが深く再解釈されています。ラムセス2世との出会いは、きりこがこよなく愛していた好物「白玉」を落としてしまったことがきっかけでした。きりこは給食に出た白玉を「口に含み、噛まずに、舌の下や奥歯と頬の間で慈しみ、五限目が始まる頃まで置いておくことが、きりこにとって至上の喜びであった」と描写されるほど執着していました。しかし、白玉を落としたきりこが体育館裏で悲しみに打ちひしがれている時にラムセス2世と出会い、その衝撃から愛してやまない白玉を「ぽいっと、地面に投げ捨てた」のです。この白玉への異常な執着と、ラムセス2世との出会いによる突然の「投げ捨て」は、単なるコミカルな描写に留まりません。白玉はきりこの幼少期の純粋な喜びと、自己中心的な「女王様」ぶりを象徴しています。それを「投げ捨てる」行為は、ラムセス2世との出会い、すなわち新たな自己認識と成長の始まりが、過去の自己(無自覚な「可愛い」自分)との決別と、より広い世界への目覚めを意味していることを示唆する、象徴的なシーンだと私は解釈しました。これは、自己成長には時に過去の執着やアイデンティティの一部を手放す必要があるという、普遍的なテーマを象徴的に描いているのです。
ラムセス2世が「神様」のようだと評されるのは、単に賢い猫だからではありません。猫の視点から人間社会の「美醜」や「社会的評価」といった価値観が「まじでどうでもいい」ものとして描かれることで、人間の愚かさや、いかに些細なことに囚われているかが浮き彫りにされます。これは、読者に対し、より本質的な「生きる意味」や「自己の尊厳」について深く考えさせるための、強力なメタファーとして機能しています。ラムセス2世は、きりこの苦悩に寄り添い、彼女が再び外の世界に出る決心をするきっかけを与える、かけがえのない存在となります。猫の無条件の愛は、きりこの両親の愛と並行し、自己肯定感の基盤となる「無償の愛」の重要性を強調しているように感じられます。
引きこもりから脱し、新たな一歩を踏み出したきりこは、近所に住む「ちせちゃん」との出会いを通して、さらなる成長を遂げます。ちせちゃんは、きりことは異なる価値観を持ち、特に性的なテーマにも深く関わるキャラクターとして描かれます。ちせちゃんの経験、例えば「セックス好きであっても同意のないセックスはレイプであるという性交渉の同意について示唆」といった描写は、きりこが自身の「容れ物」に囚われていたことに気づき、「自分らしく生きればいい」というメッセージを受け取る上で重要な要素となります。きりこは、ちせちゃんのために大人たちに毅然と立ち向かうなど、自己を確立し、他者を支える強さを身につけていきます。この交流は、きりこの内面的な成長を加速させるだけでなく、読者にも現代社会におけるデリケートな問題について深く考える機会を提供してくれます。
「きりこについて」は、きりこの少女時代から20代半ばまでの人生を描き出します。彼女は、自己肯定感を育み、最終的には「容れ物(外見)だけでなく、中身が大事」という一般的な結論に留まらず、「容れ物も、中身も込みで、うち、なんやな」と、外見も含めた自分自身全体を肯定する境地に至ります。この自己受容の深化は、きりこが社会の評価に左右されない、揺るぎない自己を構築したことを示しているのです。物語の終盤には、きりこが予知夢を見るようになるなど、やや特殊な展開も含まれます。しかし、これは物語にファンタジー要素を加えるだけでなく、きりこの内面的な強さや、困難を乗り越えて「生きる力」を強調する象徴的な要素として機能していると私は感じました。
「ぶす」という言葉は、作中で太字で繰り返し使用されます。この表現は、その言葉が持つ侮蔑性や、個人に与える精神的ショックを極めて強調しているように感じられました。きりこが「ぶす」と認識された後の周囲の態度の変化は、社会が外見によって人を判断し、差別する現実をリアルに描き出しています。この容赦ない描写は、単なるキャラクター描写を超え、読者自身の内面にルッキズムがどれほど深く根付いているかを問いかけ、強い不快感や自己反省の感情を呼び起こす意図的な心理的アプローチです。これにより、作品のメッセージがより深く刻み込まれることになります。
西加奈子さんの作品全体に共通する重要なテーマとして、「容れ物にとらわれないで生きる」というメッセージが強く込められています。この「容れ物」は、単に身体的な外見に留まらず、社会的役割、経済力、ジェンダー規範など、個人を規定するあらゆる外部的要素を包括するメタファーとして機能します。作品は、これらの「容れ物」に囚われることの苦しさと、そこからの解放を描くことで、現代社会の多様な抑圧構造に光を当てているのです。きりこは当初、「人間には『中身』しかない」と考えていましたが、物語の終盤で「容れ物も、中身も込みで、うち、なんやな」と、外見も含めた自己全体を受け入れる境地に至ります。これは、外見と内面が不可分であり、外見もまたその人の中身の一部であるという、より深い自己認識を示していると言えるでしょう。
きりこの自己認識の旅は、幼少期の無自覚な「可愛い」という自己像から、社会からの「ぶす」というレッテルによる自己認識の崩壊、そして深い引きこもりを経て、最終的に自己を肯定するまでの複雑な心の動きとして詳細に描かれています。この過程は、多くの人が経験する「人と自分を比較するところから生まれる苦しみ」からの解放の道筋を具体的に示しています。きりこの葛藤とそれを乗り越える姿は、読者自身の内省を促し、自己受容へのヒントを与えてくれます。作品が伝える最も重要なメッセージの一つは、「自分への判断を、他人に委ねてはいけない」という強い主張と、「誰もがみな、唯一無二である」という普遍的な肯定です。きりこは、他者の評価に翻弄されることなく、「自分のしたいことを叶えてあげるんは、自分しかおらん」という真理に気づき、自分自身をありのままに受け入れる強さを獲得します。このメッセージは、現代社会において他者の目や評価に過度に囚われがちな人々に、自己の尊厳と主体性を取り戻すことの重要性を力強く訴えかけています。
きりこの両親の底抜けに深い愛情と、ラムセス2世の無条件の受容は、きりこの自己肯定感を育む上で不可欠な要素として描かれています。彼らの存在は、社会の評価に揺らがないきりこの土台を形成したと言えるでしょう。自己肯定感は単に内面的な努力だけでなく、他者からの無条件の受容という外部的な要因によっても深く育まれることを示唆しています。特に、猫の視点からの愛は、人間社会の条件付きの愛とは異なる、より純粋で普遍的な愛の形を提示し、読者に「生まれてきただけで美しい」というメッセージを伝えているように感じられます。
物語が猫のラムセス2世の視点で語られることで、人間社会でしか通用しない「可愛い」「美人」といった価値観が相対化されます。猫から見れば、人間の外見への執着は「まじでどうでもいい」ことであると描写され、人間がいかに些細なことに囚われているかが浮き彫りにされます。ラムセス2世の「神様」のようだと評される視点は、単に賢い猫だからではありません。猫の視点から人間社会の「美醜」や「社会的評価」といった価値観が「どうでもいい」ものとして描かれることで、人間の愚かさや、いかに些細なことに囚われているかが浮き彫りにされるのです。これは、読者に対し、より本質的な「生きる意味」や「自己の尊厳」について深く考えさせるための、強力なメタファーとして機能していると言えるでしょう。
ラムセス2世の存在は、「世界は、肉球よりも、まるい」という象徴的な言葉に集約されるように、より広く、多様で、本質的な世界のあり方を提示します。これは、読者が固定観念から解放され、ありのままの自分を受け入れるための新たな視点を提供するのです。猫の視点との対比は、人間の愚かさや、いかに狭い「定規」で自分を測り、苦しんでいるかを浮き彫りにしています。
西加奈子さんの文章は、テンポが良く、ポップさがあり、特に今作では関西弁を多用することで、その特徴が際立っています。この軽快な語り口が、時に「ヘヴィな内容」や露骨な描写を読者に受け入れやすくしています。関西弁を多用した文章は、単なる地域色ではなく、作品の「容赦なさ」を際立たせる効果を持つように思えます。関西弁の持つストレートで時にユーモラスな響きは、きりこの「ぶす」描写や社会批判の鋭さを和らげつつも、その本質的なメッセージをより直接的に読者に届ける役割を果たしています。この言語的選択は、作品のシリアスさとコミカルさの絶妙なバランスを保つ上で不可欠な表現技法だと感じました。
「容赦ないぶす描写」は、きりこの外見を読者に強く印象づける一方で、その「ぶすさ」がもはや架空の生き物のような異質さを帯びることで、彼女の特別な存在感を際立たせています。例えば、「輪郭がブヨブヨ」「鼻はアフリカ大陸をひっくり返した」といった具体的かつ想像を絶する表現が用いられ、読者の想像力を掻き立てます。
登場人物の心情や周囲の環境描写は的確でリアルであり、「あー分かるー」「こういうことあったあった」と読者の共感を呼びます。特に、子供たちの「酔い」の状態や、思春期における自己認識の変化の描写は秀逸であり、読者が自身の過去と重ね合わせて感情移入することを可能にしています。
西加奈子さんの作品には、「容れ物にとらわれないで生きる」や「自己肯定感」が共通のテーマとして頻繁に登場します。「きりこについて」は、この「容れ物」と「中身」のテーマを、外見の「ぶす」という極端な設定を通じて深く掘り下げ、自己受容の重要性を訴える点で、西加奈子作品群の中でも象徴的な位置を占めています。
西加奈子さんの創作原動力は「好きなものを書く」という姿勢にあり、読者を想定せず、自身が感じたことを全力で表現する「エゴイスティックなもの」と語っています。この姿勢は、一見すると独りよがりに見えるかもしれませんが、彼女自身の内面的な気づきや社会への問いかけを、妥協なく「原色のままに描ききる」ことを可能にしています。結果として、個人的な感情や問いが、普遍的な人間の葛藤や自己肯定のテーマへと昇華され、多くの読者に共感を呼ぶ力となっているのです。これは、真に個人的な表現が、時に最も普遍的な響きを持つという文学の特性を示していると言えるでしょう。
西加奈子作品の「容赦なさ」と「肯定感」は、一見矛盾する特性に見えますが、実は密接に結びついています。「きりこについて」における容赦ない「ぶす」描写や、ちせちゃんのシビアな性的描写は、目を背けたくなるような現実を直視させることで、その後のきりこの自己受容や、登場人物たちの「完璧じゃない自分」を肯定するメッセージをより力強く、説得力のあるものにしています。つまり、「容赦なさ」は「肯定感」を際立たせるための、西加奈子さん独自の表現戦略だと私は強く感じました。
「きりこについて」は、読者から多岐にわたる反響を呼んでいます。多くの読者からは「サクサク読めるわ面白いわで良い本でした」、「面白かった」「素晴らしい」「考えさせられる内容」といった肯定的な評価が寄せられています。特に、自己肯定感の低さに悩む読者からは、「自己肯定力が下がったときに読むと爆上がりする!!」といった熱烈な支持を得ており、作品が読者の精神的な支えとなり得ることを示唆しています。
一方で、作品の持つ「容赦のない残酷なぶす表現にだんだん気持ちが滅入ってきて、しんどくなって読むのを断念!」という声や、「生々しい表現も多く電車で読むのに躊躇する事があった」という意見もあり、読者によって受け止め方は多様です。この多様な反応こそが、作品が扱うテーマの深さと、それが読者の内面に強く作用する性質を示していると言えるでしょう。
きりこの幼なじみであるちせちゃんがAV女優になる設定や、性交渉の同意に関する示唆など、性に関して「あけすけな言葉遣い」や「シビアな話」が含まれることが指摘されています。これらの描写は、一部の読者には苦手意識を抱かせる側面があるかもしれません。しかし、これらの描写は単なる露骨な表現に留まらず、身体を「容れ物」として捉え、自己の尊厳や性的同意といった現代的なテーマを深く掘り下げる上で不可欠な要素として機能していると私は考えます。性描写が一部の読者に「苦手」「躊躇する」といった不快感を与える一方で、それが「繊細に描かれている」と評価され、特に「性交渉の同意」という現代社会の重要な論点に触れている点は、作品の意図を深く読み解く鍵となります。この「不快感」は、作品が扱うテーマ(身体の尊厳、自己の所有権)が、読者の既成概念やタブーに挑戦している証拠であり、その「必要性」を浮き彫りにしています。西加奈子さんの「容赦なさ」が、このデリケートなテーマを避けることなく描くことを可能にし、作品のメッセージに深みを与えているのです。
この作品は「中学生、高校生に読んでほしい作品」として推奨されています。これは、若年層が直面する自己認識や他者との比較といった悩みに寄り添い、自己肯定感を育む上で有益な示唆を与えるためでしょう。作品が提供する自己受容のメッセージは、現代社会に生きる多くの人々の「生きづらさ」に対する具体的な解決の糸口や、精神的な強さを与える力を持っていると私は確信しています。この点は、文学が単なる娯楽ではなく、人生の指針となり得る可能性を示していると言えるでしょう。「容れ物にとらわれないで生きる」という西加奈子さんの頻繁なテーマを体現する本作は、現代社会におけるルッキズムや多様性の問題を考える上で、重要な文学的意義を持っています。読者からの継続的な支持や推薦の声が、作品の社会的影響を示唆しています。
まとめ
西加奈子さんの「きりこについて」は、「ぶす」という極端な外見を持つ主人公きりこの成長を通して、「美」と「醜」の相対性、自己受容、そして社会のルッキズムという、普遍的かつ現代的なテーマを深く掘り下げた作品です。賢い黒猫ラムセス2世というユニークな視点を導入することで、人間社会の価値観の狭さや愚かさを浮き彫りにし、私たち読者に「容れ物」に囚われず、ありのままの自分を肯定する強さの重要性を問いかけます。
本作は、外見だけでなく、社会的役割や他者の評価といったあらゆる「容れ物」に縛られがちな現代人に対し、「自分のしたいことを叶えてあげるんは、自分しかおらん」という力強いメッセージを投げかけます。きりこの葛藤と成長の軌跡は、多くの読者に自己肯定感の育み方や、他者との比較から生まれる苦しみからの解放のヒントを与えてくれるでしょう。
西加奈子さん独自の「容赦なさ」と「肯定感」が融合した作風は、時に読者に強い衝撃を与えつつも、最終的には温かい光を差し伸べます。性描写や「ぶす」という直接的な表現も、単なる刺激に留まらず、自己の尊厳や身体の所有権といったデリケートなテーマを深く考察するために不可欠な要素として機能しています。
「きりこについて」は、自己肯定感の低さに悩む方、他者の評価に囚われがちな方、そして「自分らしく生きる」ことの意味を模索しているすべての人に、ぜひ読んでいただきたい一冊です。この作品が、あなたの心に新たな光を灯し、自分自身の「容れ物」と「中身」を丸ごと肯定する勇気を与えてくれることを願っています。