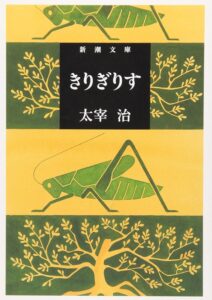 小説「きりぎりす」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治が描くこの物語は、芸術家の成功とその裏で起こる人間関係の変化、特に夫婦の関係がどのように移り変わっていくのかを、妻の視点から鮮やかに描き出しています。
小説「きりぎりす」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治が描くこの物語は、芸術家の成功とその裏で起こる人間関係の変化、特に夫婦の関係がどのように移り変わっていくのかを、妻の視点から鮮やかに描き出しています。
物語は、純粋な情熱で結ばれたはずの夫婦が、夫の社会的成功によって徐々にすれ違っていく様子を追います。かつて貧しさの中に喜びを見出していた妻は、名声と富を得て俗物化していく夫に幻滅し、静かに別れを決意するのです。彼女の独白を通して、読者は愛の形、成功の意味、そして失われたものへの哀切を感じ取ることでしょう。
この記事では、まず物語の結末までを含む詳細なあらすじをご紹介します。そして、その後に、妻の心理描写や夫の変化、作品のテーマ性について、私なりの深い読み解きを感想として綴っていきます。なぜ二人の関係は変わってしまったのか、そして妻が最後に聞いた「きりぎりす」の声は何を意味するのか、一緒に考えていきませんか。
太宰治の巧みな筆致によって描かれる人間の心の機微、そして社会で生きることの複雑さ。この「きりぎりす」という作品が持つ深い味わいを、この記事を通して少しでもお伝えできれば幸いです。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。
小説「きりぎりす」のあらすじ
二十四歳になる「私」は、夫である「あなた」との別れを決意しています。物語は、彼女が夫へ宛てた手紙、あるいは独白のような形で進んでいきます。
「私」が「あなた」と出会ったのは十九歳の春。父の会社に出入りしていた骨董屋の但馬さんが、「あなた」の描いた一枚の画を持ってきたのがきっかけでした。但馬さんは、この無名の画家は将来必ず大家になると言い、「私」との見合いを強く勧めます。周囲は半ば呆れていましたが、「私」はその画を一目見て、「この画は、私でなければ、わからない」「あなたのところへ、お嫁に行かなければ」と強い衝撃を受け、心が震えるのを感じました。親戚からは素行の悪さや左翼思想の噂などを聞かされ反対されますが、「私」の決意は固く、ほとんど身一つで画家の元へ嫁いだのです。
結婚後、淀橋のアパートで過ごした二年間は、貧しいながらも「私」にとってこの上なく幸福な日々でした。夫は世間の評価や大家の名声などには一切関心を持たず、ただひたすらに自分の描きたい画を描き続けていました。生活は苦しく、時折訪れる但馬さんが画を数枚持っていき、代わりに置いていくお金が頼りでしたが、「私」はその貧しさを「自分のありったけの力を試す」機会と捉え、むしろ楽しんでいました。夫はお金には全く無頓着で、但馬さんにお金の入った封筒を渡されても中身を見ようともしませんでした。
しかし、結婚して二年目の秋、但馬さんが個展の話を持ち込んだ頃から、夫は少しずつ変わり始めます。個展は大成功を収め、出品した画はすべて売れ、新聞や雑誌で絶賛され、有名な大家からも手紙が届くようになりました。夫は但馬さんに連れられて毎晩のように挨拶回りに明け暮れ、朝帰りすることも増えました。そして、後ろめたさを隠すかのように饒舌になり、貧しいアパートを恥じるようになり、やがて世間体を気にして三鷹の大きな家に引っ越します。
引っ越し後、夫の変化はさらに加速します。以前は無口だった彼が、他人の受け売りのような美術論を得意げに語るようになり、お金に執着するようになります。かつての純粋で反骨精神に満ちた面影は消え、「私」は夫を「嘘つきでわがままな楽天家」と感じるようになります。夫が、普段は悪口を言っていたような人々を集めて「新浪漫派」という団体を設立するに至っては、「世間の成功者とは、みんな、あなたのような事をして暮らしているものなのでしょうか」と、その俗物ぶりに強い嫌悪感と疑問を抱くのでした。
決定的な出来事は、正月に夫の熱心な支持者である大家、岡井先生の家を訪れた時のことでした。「私」は岡井先生の「孤高な眼」に、初めて夫の画を見た時と同じような震えを感じます。しかし、その帰り道、あれほど先生の前でぺこぺこしていた夫が、急に「ちえっ!女には甘くていやがら」と陰口を叩くのを聞き、「私」は完全に夫との別れを決意しました。先日、ラジオから流れてきた夫の声は「不潔に濁った声」に聞こえ、「私の、こんにち在るは」などと語る夫の姿に、ただ「いやな、お人だ」と感じ、スイッチを切りました。その夜、床に就くと、縁の下でこおろぎが鳴いています。その声がまるで自分の背骨の中で小さな「きりぎりす」が鳴いているように感じられ、「私」は、この小さくかすかな声を、一生忘れずに背骨にしまって生きていこう、と心に誓うのでした。
小説「きりぎりす」の長文感想(ネタバレあり)
太宰治の「きりぎりす」は、読むたびに心の深いところに響いてくる作品です。妻である「私」の一人称で語られるこの物語は、一見すると、純粋だった芸術家の夫が成功と共に俗物化し、それに幻滅した妻が別れを決意するという、ある種分かりやすい構図を持っているように思えます。しかし、読み進めるうちに、語り手である「私」自身の心の複雑さ、そして「成功」や「純粋さ」とは何かという問いが、重層的に立ち上がってくるのを感じます。今回は、その結末にも触れながら、この作品が持つ多面的な魅力について、じっくりと考えてみたいと思います。
まず、「私」が夫と結婚を決意する場面。彼女は夫の画を見て「この画は、私でなければ、わからない」「あなたのところへ、お嫁に行かなければ」と直感します。これは純粋な芸術への共感、魂の触れ合いのようにも読めますが、同時に「この世界中に自分でなければ、お嫁に行けないような人」を探していた彼女の、ある種の自己陶酔や、困難な状況にある相手を「支える私」という役割への渇望が見え隠れするようにも感じられます。夫の人となりよりも先に、その「世間から認められていない才能」に惹かれたのではないか、という疑念です。
その疑念は、貧しい結婚生活を「楽しんでいた」という彼女の言葉からも補強されます。「貧乏になればなるほど、私はぞくぞく、へんに嬉しくて」という感覚。これは、清貧を尊ぶ心とも取れますが、見方を変えれば、夫が世俗的な成功から遠い場所にいる限り、彼女の「支える」という役割、そして「私だけが彼の価値を理解している」という優越感が保証されるからではないでしょうか。夫がお金に無頓着であること、但馬さんが持ってくるお金の中身すら確認しない様子を、彼女はどこか誇らしげに語りますが、それは夫の純粋さへの賛美であると同時に、自分がその生活をコントロールできている(少なくともそう感じている)ことへの満足感の表れだったのかもしれません。
夫の才能に対する彼女の確信についても、少し立ち止まって考える必要があります。「私でなければ、わからない」と感じたその直感は、本当に芸術的な審美眼に基づいていたのでしょうか。それとも、周囲の無理解の中で輝く才能(と彼女が信じたもの)に、自分自身を重ね合わせ、運命的な結びつきを感じただけだったのでしょうか。物語の中で、彼女が具体的に夫の画のどこに惹かれたのかは語られません。ただ、強い衝撃と使命感だけが強調されるのです。
変化の兆しは、個展の成功から現れます。夫が身なりに気を使い始め、饒舌になり、世間体を気にするようになる。これは、成功した人間が社会に適応していく過程として自然なこととも言えますが、「私」にとっては、自分だけが知っていたはずの夫が、手の届かない、理解できない存在へと変わっていく始まりでした。骨董屋の但馬さんの存在も重要です。彼は夫の才能を見出し、世に出すきっかけを作りましたが、同時に夫を社交の場へと引き込み、変化を加速させた人物とも言えます。
「私」が感じる「私が、謂いわゆる成金の、いやな奥様のようになってしまったような気がして」という不安は、単なる自己嫌悪でしょうか。それとも、夫の変化によって、かつて自分が拠り所にしていた「貧しい芸術家を支える清らかな妻」という自己イメージが崩壊していくことへの恐れだったのではないでしょうか。夫が俗物化していくことへの幻滅と、自身の存在意義が揺らぐことへの不安が、彼女の中で複雑に絡み合っていたように思えます。
夫の言葉の変化は、その内面の変容を象徴的に示しています。「他人から借りてきた言葉ばかりを使って」お客と談笑する姿。自分の内から湧き出る言葉ではなく、世間に受け入れられるための空疎な言葉を弄するようになった夫に、「私」は耐え難い「恥ずかしさ」を感じます。それは、かつて信じていた夫の独自性や純粋さが失われたことへの悲しみであり、借り物の言葉で塗り固められた夫の姿が、まるで自分自身の虚飾を映し出しているかのように感じられたからかもしれません。
そして、金銭への執着。これが「私」にとって、夫の「清貧」という、最も価値を置いていたであろう美徳が完全に失われたことを示す決定的な証拠となります。芸術よりもお金、内面的な価値よりも世間的な成功。この価値観の転倒は、彼女が夫と結びついた根幹を揺るがすものでした。夫を「嘘つきでわがままな楽天家」と断じる彼女の言葉には、裏切られたという激しい感情が滲んでいます。
普段は悪口を言っていた相手と「新浪漫派」なる団体を作るという夫の行動は、芸術的信念よりも処世術を優先する姿を露呈させます。「世間の成功者とは、みんな、あなたのような事をして暮しているものなのでしょうか」という彼女の問いかけは、単なる夫への批判に留まらず、当時の文壇や社会全体に対する痛烈な皮肉としても響きます。太宰自身も、成功や名声と、自身の文学的信念との間で葛藤した作家でしたから、この部分には作者自身の経験や苦悩が投影されているのかもしれません。
そんな幻滅の中で出会った岡井先生の存在は、非常に重要です。「孤高な眼」を持ち、「単純なことをこだわりなく話す」その姿に、「私」は再び魂が震えるような感覚を覚えます。それは、夫の中に失われてしまった(あるいは元々なかったのかもしれない)と感じる、真の芸術家の姿、あるいは「私」が理想として追い求めていた純粋さの体現のように見えたのでしょう。岡井先生は、俗物化した夫との対比を際立たせ、彼女が自身の価値観の正しさを再確認するきっかけを与えます。
だからこそ、その直後の夫の陰口「ちえっ!女には甘くていやがら」は、決定的な一撃となります。尊敬すべき大家に対してすら、裏ではそのような卑俗な言葉を吐く夫の姿に、「私」の中で何かが完全に断ち切られます。それは、わずかに残っていたかもしれない期待や幻想の完全な終焉であり、別れを決意させるに十分な出来事でした。夫の本質が(少なくとも「私」にとっては)完全に露呈した瞬間と言えるでしょう。
ラジオから流れる夫の声が「不潔に濁った声」に聞こえ、「私の、こんにち在るは」という自己満足に満ちた言葉に嫌悪感を抱く場面は、彼女の夫に対する評価が最終的に定まったことを示します。かつてあれほど惹かれた芸術家は、もはや「ただのお人」であり、その成功も「くだらない」ものとして切り捨てられるのです。スイッチを切るという行為は、夫との関係を物理的にも精神的にも遮断するという、彼女の決意の象徴です。
そして、物語はあの印象的な結末を迎えます。縁の下で鳴く「こおろぎ」の声が、自分の「背骨の中で小さいきりぎりす」が鳴いているように聞こえる。この不思議な感覚は何を意味するのでしょうか。参考情報にある山田氏の考察のように、こおろぎの古い呼び名がきりぎりすであり、夫への未練を抱えた過去の自分(こおろぎ)を、成長した現在の自分(きりぎりす)として捉え直し、それを「背骨にしまう」ことで過去と決別し、未来へ進もうとする意志の表れと解釈することも可能でしょう。
しかし、別の解釈も成り立つように思います。「きりぎりす」の鳴き声は、一般的にか細く、儚いイメージがあります。それは、夫の成功によって失われてしまった純粋さ、貧しいながらも確かに存在した(と彼女が信じている)かつての輝き、あるいは芸術そのものへの消え去りがたい憧憬の象徴なのかもしれません。夫はそれを捨て去り、「不潔に濁った声」で世間的な成功を語る存在になりましたが、「私」はそのか細い、しかし純粋な響きを、自分自身の中心である「背骨」にしまい込み、それを支えとして生きていこうと決意したのではないでしょうか。それは過去との決別というよりは、失われた理想を決して忘れず、自分の中に大切に持ち続けるという、ある種の抵抗のようにも感じられます。
この「背骨にしまう」という表現もまた、示唆に富んでいます。背骨は体を支える中心であり、人間の根幹をなす部分です。そこに「きりぎりす」の声をしまうということは、それが彼女にとって、これからの人生を支える上で最も重要で、本質的なものであることを示唆しています。それは、夫への未練という感傷的なものではなく、たとえ世間的な成功とは無縁であっても、自分が信じる価値観(純粋さ、清らかさ)を貫いて生きていくという、静かですが、非常に強い意志の表明ではないでしょうか。
最後に、この物語全体を通して考えさせられるのは、語り手である「私」の視点の信頼性です。彼女の語りは、夫の変貌に対する純粋な被害者の嘆きなのでしょうか。それとも、参考情報の考察にもあるように、彼女自身の強い自己愛や、「貧しい芸術家を支える私」という役割への固執が、夫の変化を一方的に断罪させている側面はないのでしょうか。彼女が本当に愛していたのは夫自身だったのか、それとも「私が支えるべき存在」としての夫だったのか。この問いに対する答えは、読者一人ひとりに委ねられているように思います。「きりぎりす」は、成功とは何か、純粋さとは何か、そして愛とは何かという普遍的なテーマを、一人の女性の視点を通して深く問いかけてくる、読み応えのある作品なのです。太宰治の描く人間の心の複雑さと、社会の中で生きることの難しさが、短い物語の中に凝縮されています。
まとめ
この記事では、太宰治の短編小説「きりぎりす」について、結末までの詳しいあらすじと、私なりの長文の感想・考察をお届けしました。物語は、純粋な芸術への情熱で結ばれたはずの画家とその妻が、夫の社会的成功によって心が離れていく様を、妻の視点から描いています。
あらすじでは、無名の画家との結婚、貧しいながらも幸福だった日々、そして個展の成功を機に夫が名声や富に執着し、俗物化していく過程、そして妻が別れを決意するまでの流れを追いました。特に、岡井先生との出会いやラジオ放送のエピソードが、彼女の決意を固める重要な転換点となったことが分かります。
感想の部分では、妻の心理の複雑さに焦点を当てました。彼女が夫に惹かれた理由、貧乏生活を楽しんだ背景にある自己愛や役割意識、夫の変化に対する幻滅の根源、そして結末で「きりぎりす」の声を「背骨にしまう」ことの意味について、複数の解釈の可能性を探りました。単なる夫への批判だけでなく、成功とは何か、純粋さを保つことの難しさといった普遍的なテーマが内包されていることを論じました。
「きりぎりす」は、人間の心の移ろいやすさ、社会と個人の関係、芸術と俗世間の葛藤などを、女性の繊細な語り口を通して鋭く描き出した名作です。読後には、登場人物たちの誰に感情移入するか、あるいは誰の視点にも完全には立てないと感じるか、様々な思いが交錯するかもしれません。この記事が、作品をより深く味わうための一助となれば幸いです。




























































