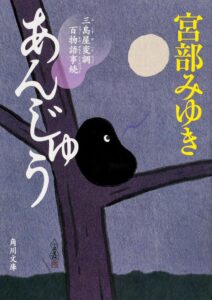
小説「あんじゅう」の物語の概要を、結末に触れる内容も含めてご紹介します。読み終えての個人的な思いも長めに書いていますので、どうぞお付き合いください。本作は、宮部みゆきさんが描く江戸時代の百物語集め、三島屋変調百物語シリーズの第二弾にあたります。前作『おそろし』でその世界に魅了された方も多いのではないでしょうか。私もその一人です。
今作『あんじゅう』では、前作とは少し趣が異なり、子供たちが関わる話や、その土地に伝わる言い伝えのような、少し不思議で、時に切ない物語が多く収められています。怪談としての怖さは少し控えめかもしれませんが、その分、登場人物たちの心情や、人と人ならざるものとの間に生まれる絆のようなものが、より深く、丁寧に描かれているように感じました。
この記事では、まず『あんじゅう』に収められた四つの物語の簡単な流れをご紹介し、その後で、各話について、物語の結末に触れながら、私が感じたことや考えたことを詳しくお話ししていきたいと思います。特に表題作でもある「暗獣」は、心揺さぶられる、忘れられない物語でした。それでは、しばし『あんじゅう』の世界にお付き合いいただければ幸いです。
小説「あんじゅう」のあらすじ
江戸は神田にある袋物屋の三島屋には、少し変わった慣わしがあります。主人の伊兵衛の姪であるおちかが、訪れる客から不思議な話、奇妙な話を聞き集めているのです。それは百物語のように、一つ一つ語られては忘れられていく約束。おちか自身も、過去に心に深い傷を負っており、人々の語る物語に耳を傾けることで、少しずつ癒しを得ているかのようです。本作『あんじゅう』は、そんな三島屋を舞台にした連作短編集の第二弾となります。
収録されているのは四つの物語。「逃げ水」では、ある出来事をきっかけに奇妙な現象に見舞われるようになった少年の話が語られます。少年が近づくと水が避けていくという不思議。しかし、その裏には少年と山のヌシとの純粋な交流がありました。「藪から千本」は、不吉とされた双子姉妹の数奇な運命を描きます。迷信に翻弄されながらも、家族の強い思いが起こした、少し変わった奇跡の物語です。
そして、表題作でもある「暗獣」。これは、子供たちに読み書きを教えている浪人、青野利一郎がおちかに語った物語です。利一郎の師である老夫婦が、かつて「紫陽花屋敷」と呼ばれる家で出会った、この世ならざるもの「くろすけ」との交流譚。無邪気で愛らしいけれど、どこか影を持つ「くろすけ」と老夫婦の間に紡がれた、温かくも悲しい、忘れがたい日々が描かれます。なぜ「くろすけ」は現れたのか、そして彼らが迎えた結末とは。
最後の「吼える仏」では、偽坊主を名乗る男が、山奥の隠れ里で見たという恐ろしい出来事を語ります。古いしきたりを守ろうとする里と、外の世界を知り変化を望む若者との間に起こった悲劇。人間の持つ業や怨念が生み出す怪異譚でありながら、共同体のあり方や変化について深く考えさせられる物語となっています。これらの物語を通して、おちかは様々な人々の人生や想いに触れ、自身も少しずつ前へと歩みを進めていくのです。
小説「あんじゅう」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは『あんじゅう』に収録されている四つの物語について、物語の結末にも触れながら、私が感じたことを詳しくお話ししていきたいと思います。前作『おそろし』が、ぞくりとするような「怖さ」に重点が置かれていたとすれば、今作『あんじゅう』は、人々の心の機微や、切なさ、温かさといった情緒的な側面に光を当てているように感じました。もちろん、宮部さんらしい、ぞっとするような描写や、人間の心の闇を描く鋭さは健在ですが、読後感としては、どこか物悲しくも、優しい気持ちになれる物語が多かったように思います。
まず最初の物語「逃げ水」。このお話の主人公は、周りから水が逃げていく、という不思議な力を持ってしまった少年、市太郎です。原因はある事件で、彼が山のヌシさまの怒りに触れてしまったこと。でも、物語を読み進めていくと、それは単なる呪いのようなものではなく、市太郎の持つ純粋さ、素直さが引き起こした、ある種の奇跡だったことがわかってきます。市太郎は、山のヌシさまを怖れるどころか、友達のように心を通わせ、その孤独に寄り添おうとします。その穢れのない心が、本来なら人を寄せ付けないはずのヌシさまの心を動かしたのでしょう。
特に印象的だったのは、市太郎が三島屋の奉公人である少年、新太と友情を育む場面です。境遇は違えど、子供同士の純粋な気持ちで結びつき、互いを思いやる姿は、読んでいて心が洗われるようでした。大人の世界の複雑なしがらみや損得勘定とは無縁な、彼らのまっすぐな関係性が、とても眩しく感じられます。山のヌシさまが市太郎を守ろうとする姿も、単なる異類への同情ではなく、市太郎の純粋さに心打たれたからこそ生まれた、深い愛情のように思えました。人間と、人間ではない存在。その垣根を越えて通じ合う心の温かさが、この物語の核となっています。読み終えたとき、子供時代の、あのキラキラとした、けれどもう戻れない感覚を思い出して、少しだけ切なくなりました。子供って、本当にすごい力を持っているのかもしれませんね。
二番目の「藪から千本」。これは、題名からして興味をそそられます。「藪から棒」ならぬ「藪から千本」。その名の通り、突然、どこからともなく無数の針が現れる、という奇妙な出来事を描いた物語です。舞台は針問屋。かつて、この家には双子の姉妹が生まれましたが、当時は双子が不吉とされていたため、妹のほうは分家に養子に出されます。しかし、本家に残った姉が病で亡くなってしまう。悲しみにくれた両親は、亡き姉そっくりの人形を作り、生きている妹と同じように扱い始めます。食べ物も、着る物も、習い事も、すべて同じように。もし少しでも差をつければ、人形に無数の針が突き刺さり、同時に生きている妹の体にも原因不明の湿疹が現れるというのです。
この物語は、一見すると死んだ姉の怨念や呪いのように思えます。しかし、読み進めていくと、その真相はもっと複雑で、切ないものでした。実は、この奇妙な現象は、亡き姉を想う親心と、生きている妹を愛しく思う親心、その二つの強い愛情が、ある種の「奇跡」として形になったものだったのです。親たちは、亡くなった娘を忘れることができず、かといって生きている娘をないがしろにすることもできない。その板挟みの苦しみが生み出した、歪んでいながらも、どこか必死な愛情表現だったのかもしれません。
最終的に、この「不思議」は、家族がある大胆な作戦を実行することで終わりを迎えます。それは、亡き姉の人形にも花嫁衣装を着せ、嫁いでいく妹を見送らせる、というものでした。この結末には、本当に救われた気持ちになりました。親たちの行き過ぎた愛情は、結果的に家業を傾かせることになりましたが、それでも、生きている娘の幸せと、亡くなった娘の魂の安寧を願う気持ちが、何よりも優先されたのです。死者と生者が、形は違えど、同じように祝福され、送り出される。そこに、家族の深い愛を感じずにはいられませんでした。迷信やしきたりに縛られながらも、最後は人間の「情」が勝る。そんな希望を感じさせてくれる物語でした。また、作中で触れられる「痘痕(あばた)」に関する俗信なども興味深く、当時の人々の価値観を知る上でも面白かったです。
そして、三番目にして表題作の「暗獣」。この物語は、私が『あんじゅう』の中で最も心を揺さぶられた作品です。語り手は、おちかの知り合いである浪人、青野利一郎。彼が師事する加登新左衛門とその妻、初音がある屋敷で出会った不思議な生き物「くろすけ」との思い出を語ります。この「くろすけ」、最初は得体の知れない存在として描かれますが、次第にその無邪気で愛らしい姿が明らかになっていきます。真っ黒で、動物のようでもあり、子供のようでもある。言葉は話せないけれど、簡単な受け答えをしたり、教えられた歌を歌ったり、感情表現も豊か。新左衛門夫婦は、子供のいない寂しさもあってか、この「くろすけ」に深い愛情を注ぎ、まるで我が子のように育てます。
物語の前半は、新左衛門夫婦とくろすけの、穏やかで温かい日常が描かれます。そこには、種族を超えた確かな絆と、深い愛情がありました。しかし、幸せな時間は長くは続きません。くろすけの正体は、実はこの世ならざる「暗獣」であり、人の「気」を吸って生きる存在だったのです。くろすけが成長するにつれて、新左衛門夫婦は衰弱していきます。彼らは、くろすけを愛しているからこそ、このまま一緒にいては、自分たちが命を落としてしまう、そしてくろすけ自身も生きていけない、という残酷な現実に直面します。
一緒にいたい。けれど、一緒にいてはいけない。愛しているからこそ、離れなければならない。この究極の選択は、読んでいて本当に胸が締め付けられました。特に、別れの場面。すべてを悟ったかのように、自ら夫婦の前から姿を消そうとするくろすけの姿は、涙なしには読めませんでした。**くろすけの存在は、闇夜に灯る小さな蝋燭の火のようでした。**温かく、心を照らしてくれるけれど、いつかは消えてしまう運命にある、儚い光。その光を失う悲しみと、それでもその光が存在したことへの感謝。新左衛門夫婦の、そしておそらくはくろすけ自身の、複雑な感情が痛いほど伝わってきました。
利一郎がこの話をなぜおちかに語ったのか、その背景には彼自身の抱える事情も絡んでくるのですが、物語の本筋である新左衛門夫婦とくろすけのエピソードは、それだけで独立した、非常に完成度の高い悲話だと思います。怖さよりも、切なさ、愛しさ、そしてやるせなさが胸に深く残りました。思い出を共有し、心を通わせた相手と、生きる世界が違うというだけで、永遠に別れなければならない。その理不尽さと悲しみが、強く心に響きました。読み終えた後も、くろすけの健気な姿が瞼に焼き付いて離れませんでした。もし、彼らが違う形で出会っていたら、と願わずにはいられません。この物語だけでも、多くの人に読んでほしいと感じる、珠玉の一編です。
最後の物語は「吼える仏」。これは、他の三編とは少し毛色が違い、人間の業や怨念が引き起こす、より土俗的で、後味の悪い恐怖を感じさせる物語でした。語り手は、訳ありの偽坊主、行念坊。彼が迷い込んだ山奥の隠れ里には、外部との交流を断ち、独自の神仏と古いしきたりを守って暮らす人々がいました。しかし、里の若者たちの中には、外の世界への憧れや、古い因習への反発を募らせる者も現れます。
この対立が、やがて悲劇的な結末を迎えます。里の秘仏であるはずの仏像が、まるで獣のように吼え、若者たちを襲い始めるのです。行念坊が目撃したのは、変化を拒む古い世代の狂信と、未来を求める若い世代の焦りがぶつかり合い、憎しみと恐怖が渦巻く地獄絵図でした。この物語が問いかけるのは、伝統やしきたりを守ることの是非、そして変化を求めることの是非です。どちらが正しく、どちらが間違っているとは一概には言えません。里を守ろうとする人々の思いも、新しい世界を夢見る若者の思いも、どちらも理解できる部分があるからです。
しかし、その思いが過剰になり、他者を排除しようとしたとき、それは恐ろしい「呪い」と化す。仏が吼えるという怪異は、実は里の人々の凝り固まった心、憎しみや恐怖といった負の感情が生み出した幻影だったのかもしれません。この物語は、閉鎖的な共同体の中で、異質なものを排除しようとする人間の恐ろしさや、凝り固まった信仰の危うさを鋭く描いています。
読み終えて、現代社会にも通じるような、重いテーマを突きつけられた気がしました。古いものを守り続けることが停滞を生む一方で、変化だけを追い求めても大切なものが失われてしまう。そのバランスの難しさを考えさせられました。行念坊が語る悲劇は、おちかと利一郎の関係にも、どこか影を落とすような、不穏な余韻を残します。三島屋の物語が、ただの怪談集めではなく、人々の生き様や、時代の変化をも映し出す鏡であることを、改めて感じさせられた物語でした。宮部さんは、こうした重いテーマを、エンターテイメントの中に巧みに織り込み、読者に深く考えさせる力を持っていると、改めて感嘆しました。
全体を通して、『あんじゅう』は前作以上に、語り手たちの個人的なドラマや、おちか自身の心の成長に焦点が当てられているように感じました。特に、利一郎という新たな登場人物がおちかの世界に加わったことで、物語に新しい風が吹き込まれたように思います。彼がおちかに語る「暗獣」の物語は、二人の関係性を深める重要なきっかけとなりますが、同時に、彼自身の過去や、今後の展開を予感させる要素も含まれており、シリーズ全体の奥行きを増しています。
おちかは、人々の語る不思議な話、悲しい話、恐ろしい話に耳を傾ける中で、自身の過去の傷と向き合い、少しずつですが、確実に前を向いて歩き始めているように見えます。他者の痛みに共感し、寄り添うことで、自分自身の心もまた、癒されていく。そんな静かな変化が、物語の底流には流れているように感じました。百物語はまだ始まったばかり。この先、おちかはどんな物語と出会い、どのように成長していくのか。そして、利一郎との関係はどうなるのか。次なる物語への期待が膨らむ、そんな読後感でした。
まとめ
宮部みゆきさんの三島屋変調百物語シリーズ第二弾『あんじゅう』は、前作『おそろし』とはまた違った魅力に満ちた作品でした。怪談としての側面も持ちつつ、今回は特に、子供たちの純粋さや、人と人ならざるものとの切ない交流、そして家族の複雑な愛情といった、情緒に訴えかける物語が多く描かれていたように思います。四つの物語はどれも個性的で、読者の心を様々な形で揺さぶります。
「逃げ水」では子供の世界の清らかさに、「藪から千本」では少し歪んだ、しかし深い親心に、「暗獣」では種族を超えた愛とその別れの悲しみに、そして「吼える仏」では人間の業と共同体のあり方に、それぞれ深く考えさせられました。特に表題作「暗獣」の、くろすけと老夫婦の物語は、その愛らしさと切なさで、忘れられない印象を残します。涙なしには読めない、感動的な一編でした。
物語の聞き手であるおちかの成長や、新たな登場人物である利一郎との関係性も、今後のシリーズ展開を期待させる重要な要素となっています。人々の語る「変調」な物語に耳を傾けることを通して、おちか自身が癒され、変化していく過程が丁寧に描かれており、単なる怪談集ではない、深い人間ドラマとしての側面も本作の大きな魅力です。怖さだけでなく、温かさや切なさ、そして深い感動を味わいたい方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。































































