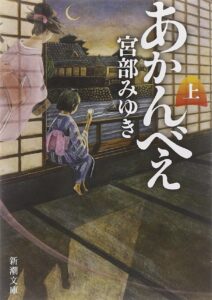
小説「あかんべえ」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品は数多く読んできましたが、この「あかんべえ」は、江戸情緒あふれる中に、切なくも温かい不思議な物語が織り込まれていて、心に残る一冊となりました。時代小説でありながら、お化けが出てくるファンタジー要素もあり、さらに謎解きミステリーの側面も持っている、とても読み応えのある作品です。
物語の中心となるのは、料理屋「ふね屋」の一人娘おりんと、その店に住み着く訳ありの亡霊たち。おりんはある出来事をきっかけに、普通の人には見えないはずの彼らの姿が見えるようになります。なぜ彼らは成仏できずにいるのか? そして、おりんだけが彼ら全員を見ることができる理由とは? 読み進めるうちに、過去に起きた忌まわしい事件の真相が少しずつ明らかになっていきます。
この記事では、まず「あかんべえ」の物語の筋道を追いかけ、その後、物語の核心に触れながら、私が感じたこと、考えたことを詳しくお伝えしていきます。まだ読んでいない方、あるいは読み終えて誰かと語り合いたいと思っている方にとって、このお話の魅力を再発見するきっかけになれば嬉しいです。
小説「あかんべえ」のあらすじ
江戸は深川。主人公のおりんは、両親(太一郎と多恵)が新たに開いた料理屋「ふね屋」で暮らす十二歳の女の子です。実はこの「ふね屋」がある場所は、以前は曰く付きの土地でした。おりんは春先に重い熱病にかかり、生死の境をさまよった後、不思議なことに、普通の人には見えないものが見えるようになっていました。そう、お化けです。
ふね屋には、どうやら五人のお化けが住み着いているようなのです。飄々とした若侍の玄之介、口をきかない少女のお梅、粋な姐さん風のおみつ、按摩の笑い坊、そして何やら恐ろしい過去を背負っていそうな、おどろ髪。彼らは皆、成仏できずにこの場所に留まっていますが、なぜ留まっているのか、その理由は自分たちでもよく分かっていません。そして、これまで五人全員の姿を見ることができた人間は、おりんが初めてだというのです。
ふね屋の開店祝いの日、最初の宴席がおどろ髪の仕業で台無しになるという騒動が起こります。この一件で、ふね屋は「お化け屋敷」として知れ渡ってしまいますが、おりんの祖父であり、大店の賄い屋「高田屋」の主である七兵衛は、逆にお化けを売りにすることを思いつきます。そんな中、おりんは玄之介たちに助けられながら、彼らが成仏できない理由、そしてこの土地に隠された過去を探り始めます。どうやら、三十年前に向かいにあった興願寺という寺で起きた、住職によるおぞましい事件が関係しているらしいのです。
おりんは差配人の孫兵衛や、その下で働くヒネ勝(勝治郎)、隣の武家屋敷に住む旗本・長坂主水助など、周囲の人々の助けも借りながら、少しずつ真相に近づいていきます。お化けが見えるという他の人々(偽者も現れますが)との出会いや、彼らとの関わりの中で、「お化けが見える人には、見えるお化けと同じ心のしこりがある」という法則も見えてきます。果たして、おりんは興願寺の事件の真相を突き止め、亡霊たちを安らかに眠らせてあげることができるのでしょうか。
小説「あかんべえ」の長文感想(ネタバレあり)
宮部みゆきさんの描く物語は、いつも私たちをその世界にぐっと引き込んでくれますね。「あかんべえ」も、まさにそんな作品でした。読み始めると、江戸の町の空気感、ふね屋の活気、そしてそこに漂う少し不思議な気配に、あっという間に心を掴まれてしまいました。
この物語の魅力は、たくさんあります。まず、主人公のおりん。十二歳という若さで、突然お化けが見えるようになるという、とんでもない経験をするわけですが、彼女は決して怯えてばかりいるわけではありません。もちろん最初は戸惑い、怖がりもしますが、持ち前の優しさと思いやりで、目の前にいる亡霊たちのことを理解しようと努めます。彼らがなぜ成仏できないのか、その理由を探ろうと、健気に奔走する姿には、本当に胸を打たれます。特に、亡霊たちと心を通わせ、彼らの過去の悲しみや苦しみに寄り添おうとする姿は、読んでいて何度も目頭が熱くなりました。おりんは、ただ優しいだけでなく、物事の核心を見抜く洞察力や、困難に立ち向かう強さも持っています。物語を通して、彼女が少しずつ成長していく様子は、まるで固い蕾がゆっくりと開いていくようで、見守っていてとても頼もしく感じました。
そして、ふね屋に住み着く五人の亡霊たち。彼らもまた、非常に個性的で魅力的です。半分透けていても美男子で、どこか掴みどころのない玄之介。彼が抱える過去の秘密と、終盤で明らかになる長坂主水助との関係には、ぐっとくるものがありました。無口で影のある少女、お梅。彼女の過去は壮絶極まりなく、読んでいるだけで胸が締め付けられます。しかし、だからこそ、彼女が最後に見せる強さと、おりんに向けて叫ぶ言葉は、深く心に響きます。「みほとけはおわします」という彼女の言葉は、絶望の中に射す一条の光のように感じられました。粋で面倒見の良い姐さんのおみつ、人の良い按摩の笑い坊、そして恐ろしい姿ながらも悲しい過去を持つおどろ髪。彼ら一人ひとりの背景が丁寧に描かれていて、最初は「お化け」として見ていた彼らが、次第に愛すべき存在に変わっていきました。彼らが抱える「心のしこり」が、おりんや他の登場人物たちの心の闇と共鳴していく様も、物語の重要なポイントですね。
脇を固める登場人物たちも、生き生きとしています。おりんを温かく見守る両親の太一郎と多恵。どっしりと構え、時に厳しく、時にユーモラスに皆を導く祖父の七兵衛。ひねくれているけれど根は優しいヒネ勝。怪しげな雰囲気を持つ差配人の孫兵衛。そして、事件の鍵を握る人物たち…おつたやおゆう、島次、そして狂気の住職。彼らは決して単純な「善人」や「悪人」として描かれているわけではありません。
特に印象的なのは、「悪」とされる側の人々の描き方です。夫を殺してしまった妻、妾腹という出自から心を歪ませた娘、同じ境遇から人殺しとなった侍の亡霊(おどろ髪)、同僚の夫に思いを寄せ、二人を引き裂こうとした女中、そして仏の存在を確かめたいという歪んだ探求心から無差別に人を殺し続けた住職。彼らが犯した罪は許されるものではありません。しかし、宮部さんは、彼らがなぜそのような道を選んでしまったのか、その背景にある苦悩や孤独、切なさをも丁寧に描き出しています。だからこそ、私たちは彼らを一方的に断罪するのではなく、どこかで哀れみを感じてしまう。人間の心の複雑さ、善と悪の境界の曖昧さを見事に描き出している点も、この物語の深みだと思います。おつたやおゆうが、完全な悪人になりきれなかったところに、わずかな救いを感じました。
物語の構成も実に見事です。三十年前の興願寺の事件という大きな謎を軸に、お化けが見える理由、それぞれの亡霊の過去、登場人物たちの秘密などが、少しずつ明かされていきます。散りばめられた伏線が、終盤に向けて一気に回収され、事件の全貌が明らかになるクライマックスは圧巻でした。ミステリーとしての面白さと、オカルト的な要素、そして人情味あふれる時代劇の要素が、実に巧みに融合されています。まさに宮部みゆきさんならではの、「ストーリーテラー」としての手腕が光る作品と言えるでしょう。
忘れてはならないのが、料理の描写です。舞台が料理屋「ふね屋」ということもあり、作中には様々な江戸料理が登場します。その描写がまた、とても丁寧で美味しそうなのです。読んでいるとお腹が空いてくるほどで、当時の人々の食生活や文化が垣間見えるのも、この物語の楽しみの一つです。参考書籍として紹介されていた「宮部みゆきの江戸レシピ」も併せて読むと、より一層楽しめるかもしれませんね。
怖さ、切なさ、そして温かさ。様々な感情が呼び起こされる物語でした。特にお梅の最後の場面は、鳥肌が立つほどの衝撃と感動がありました。彼女が経験した苦しみを思うと涙が止まりませんでしたが、それでも最後に希望を見出すことができたのは、おりんとの出会いがあったからでしょう。そして、お梅の行動があったからこそ、他の亡霊たちもようやく安らぎを得て、次の場所へと旅立つことができたのだと思います。玄之介と甥の主水助との再会、ヒネ勝のささやかな幸せ、孫兵衛とおりんの不思議な交流など、心温まるエピソードもたくさん散りばめられていました。
全体を通して、「あかんべえ」は、人間の心の光と闇、生と死、罪と赦しといった普遍的なテーマを、江戸という時代を舞台にした魅力的な物語の中に織り込んでいます。読後には、登場人物たちのそれぞれの人生に思いを馳せ、深い余韻に浸ることができました。おりんの健気さ、亡霊たちの悲しみ、そして悪役たちの切なさ。すべてが心に染み入る、忘れられない一作です。
まとめ
宮部みゆきさんの「あかんべえ」は、江戸時代の料理屋を舞台にした、不思議で、切なく、そして心温まる物語でした。お化けが見えるようになってしまった少女おりんが、店に住み着く五人の亡霊たちと共に、過去に起きた忌まわしい事件の謎を解き明かしていく過程が描かれています。
ミステリーとしての謎解きの面白さはもちろん、個性豊かな登場人物たちの魅力、特に健気で心優しい主人公おりんの成長ぶりや、悲しい過去を抱えながらもどこか憎めない亡霊たちの姿が印象的です。また、悪役とされる人物たちにも複雑な背景があり、人間の心の奥深さを考えさせられます。
時代小説の情緒、ファンタジーの不思議さ、ホラーの緊張感、そして人情噺の温かさが見事に融合した、宮部みゆきさんならではの世界が広がっています。読後には、きっと登場人物たちの誰かに深く共感し、物語の余韻に長く浸ることになるでしょう。まだ読まれていない方には、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。































































