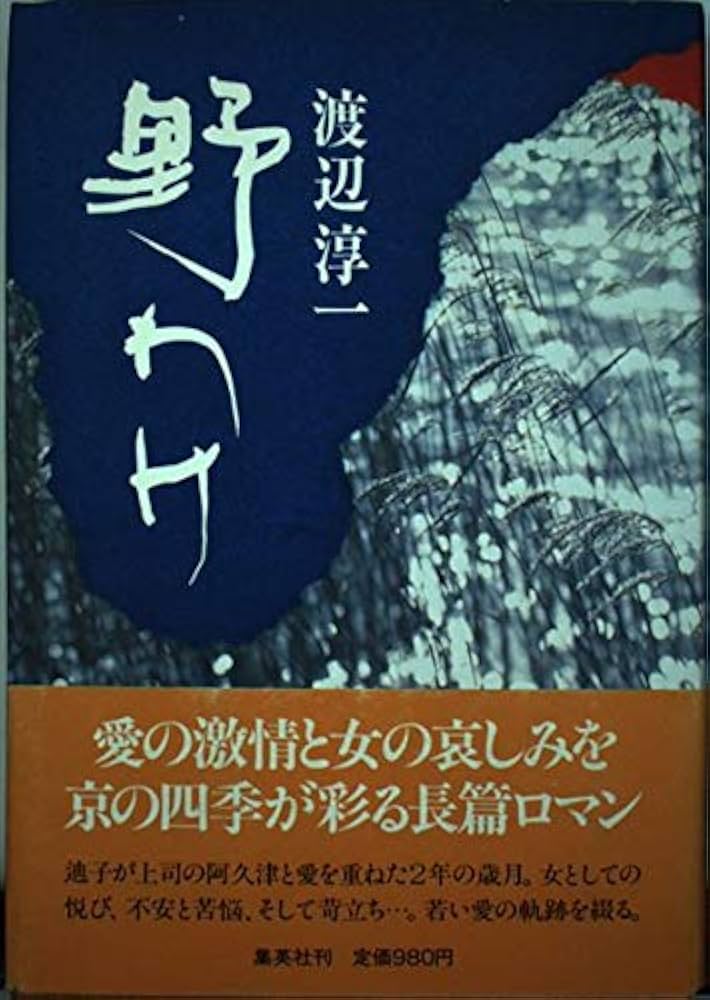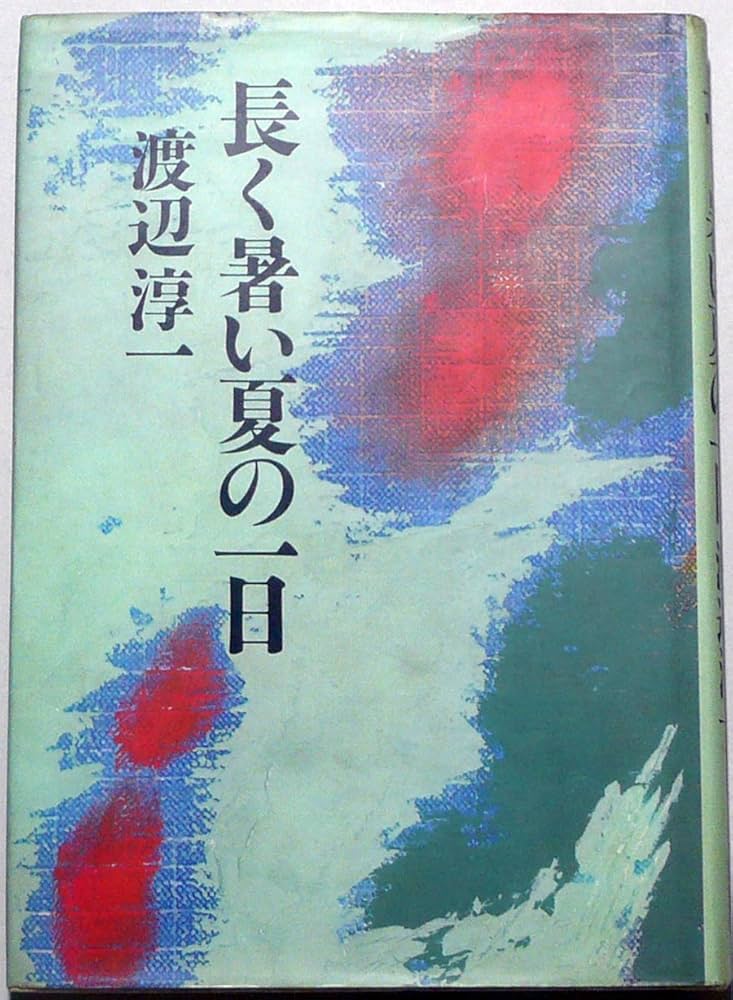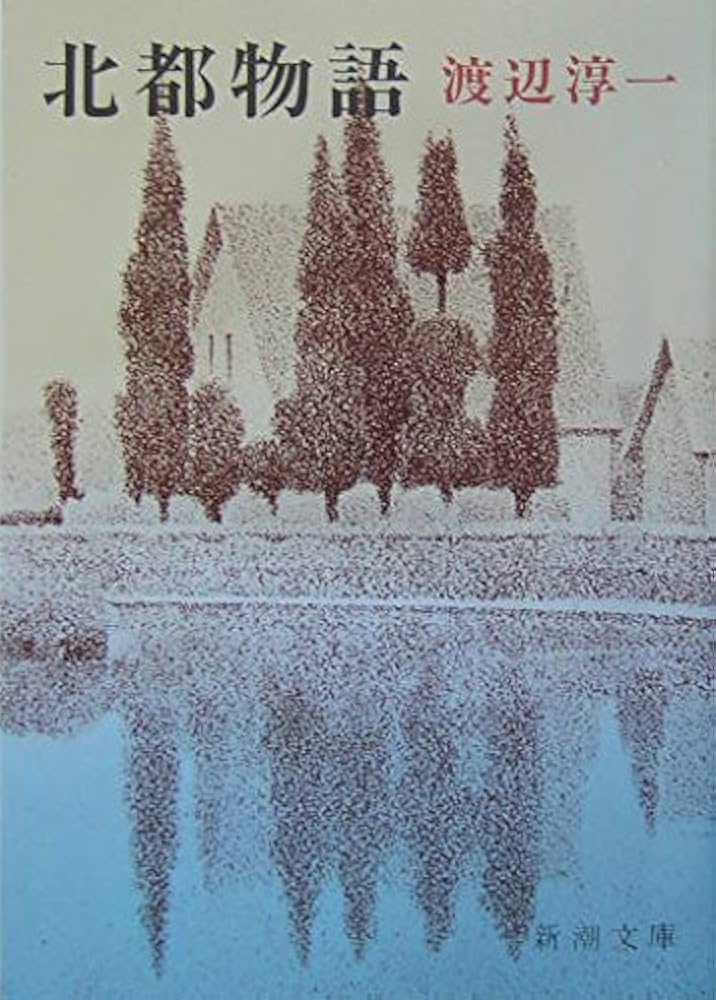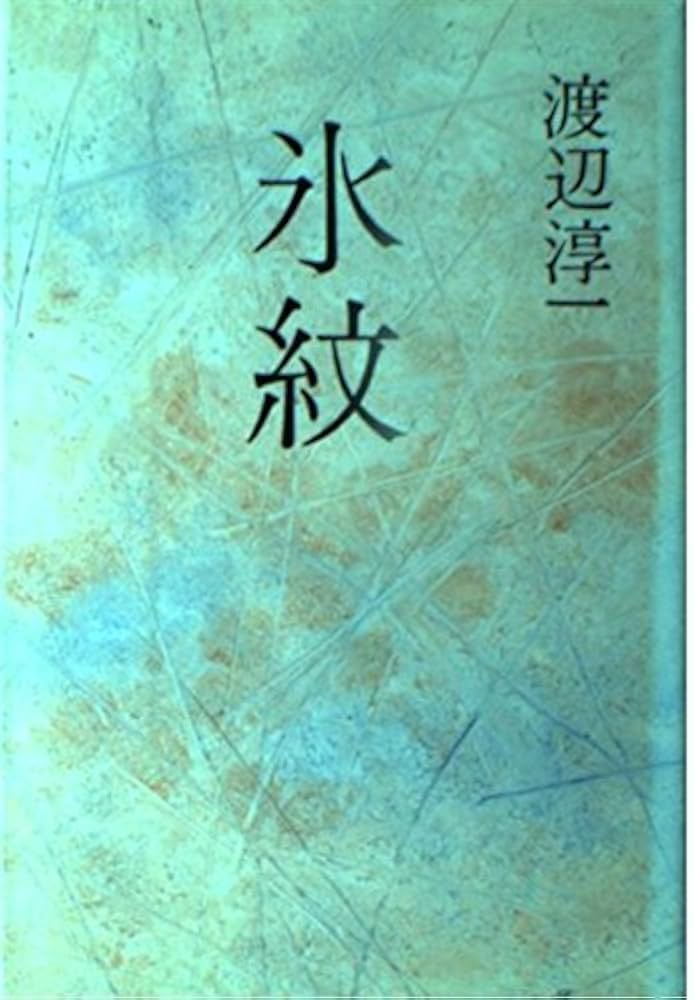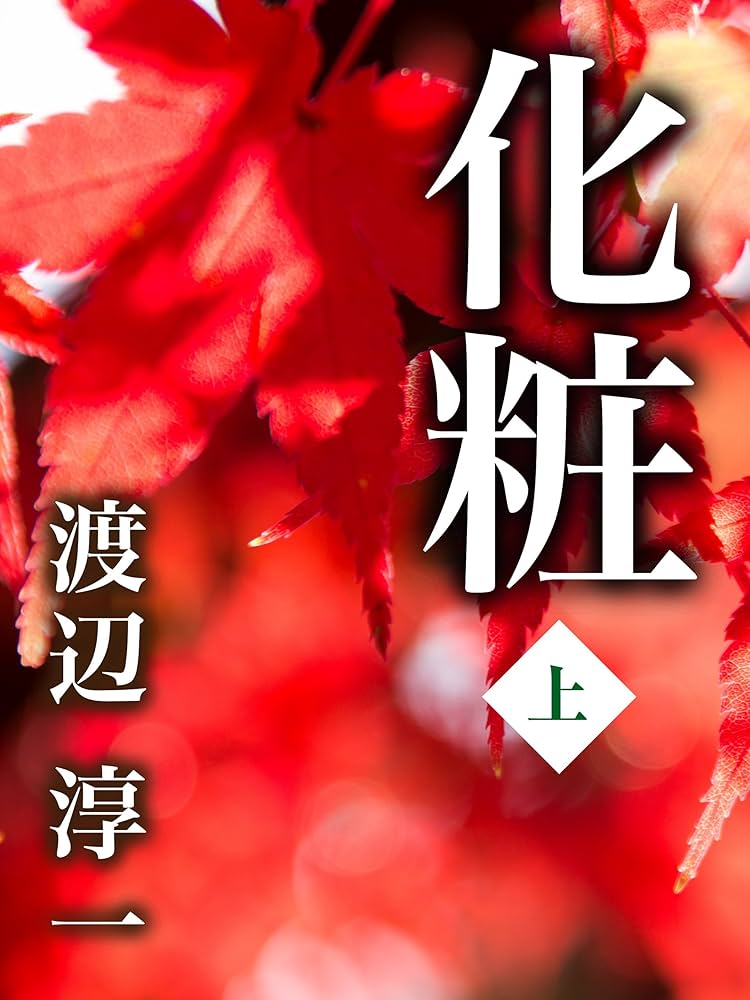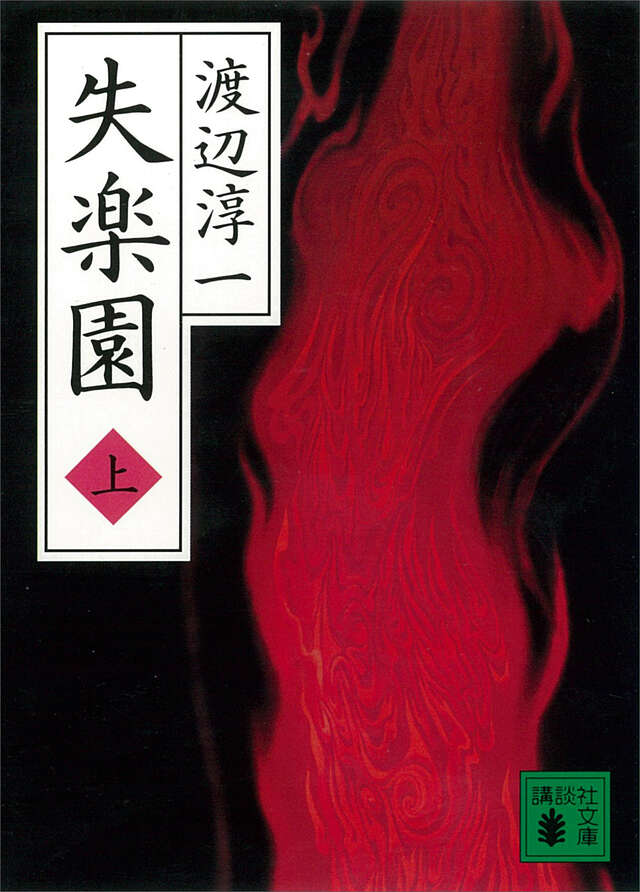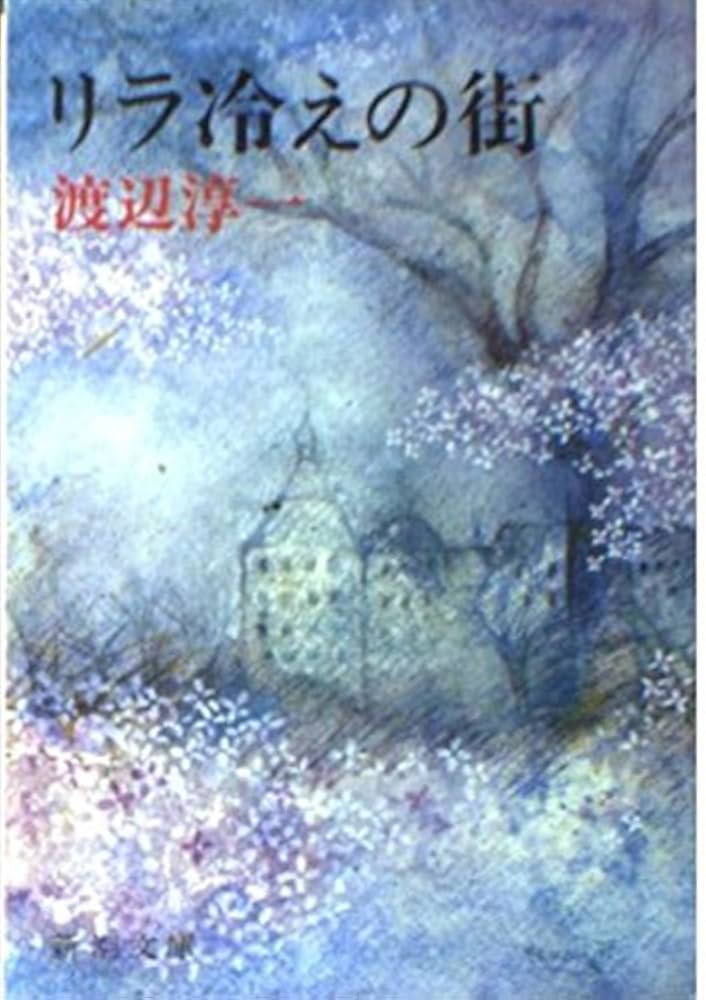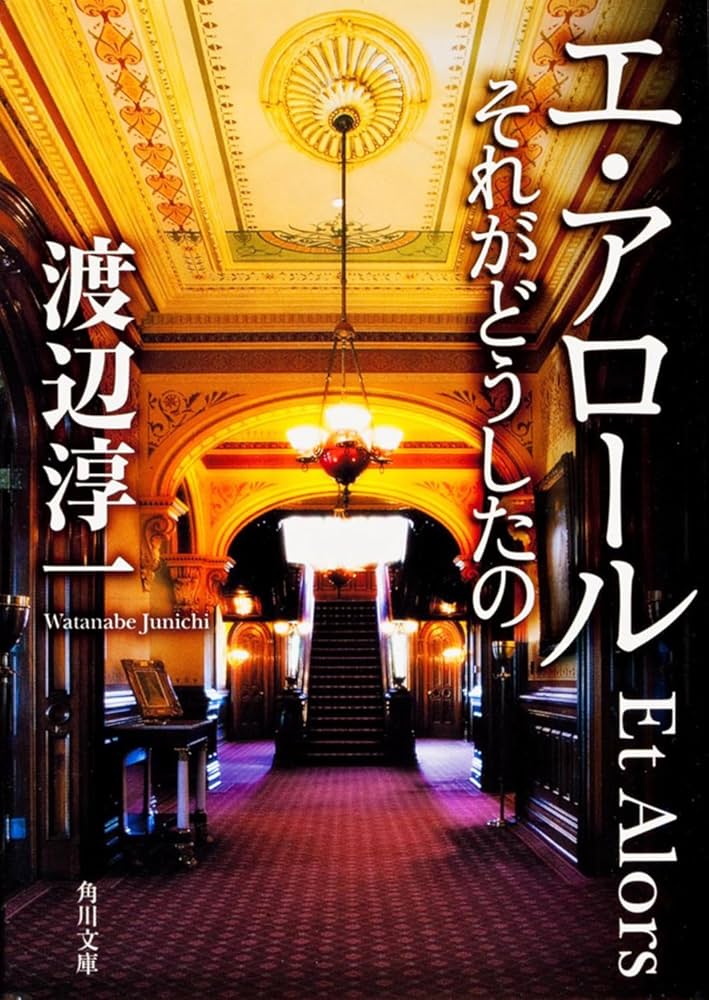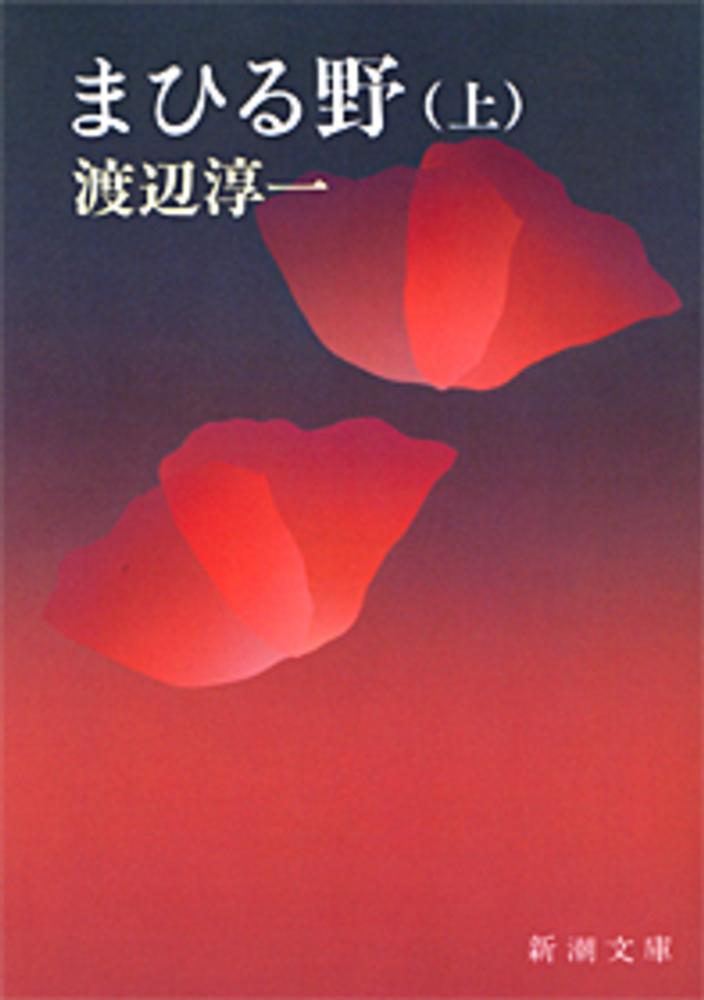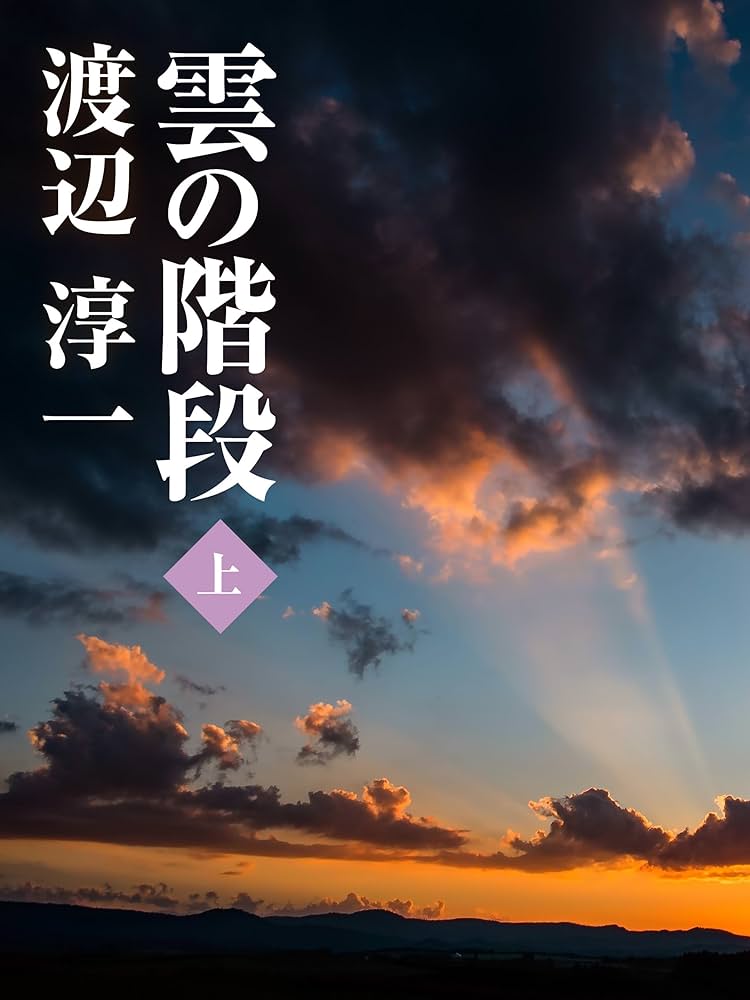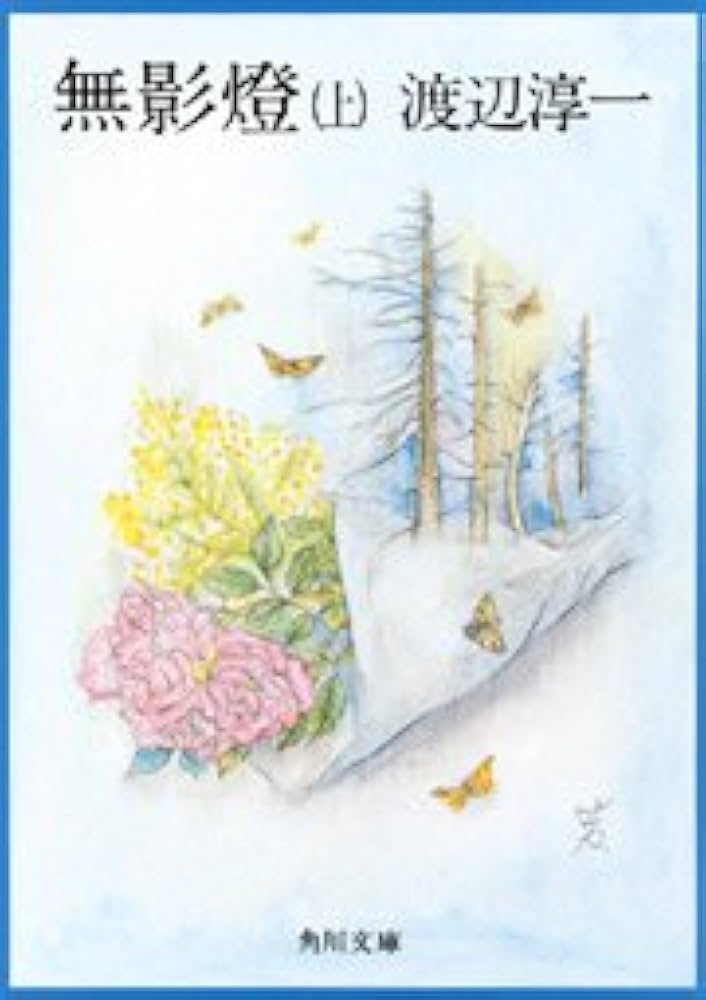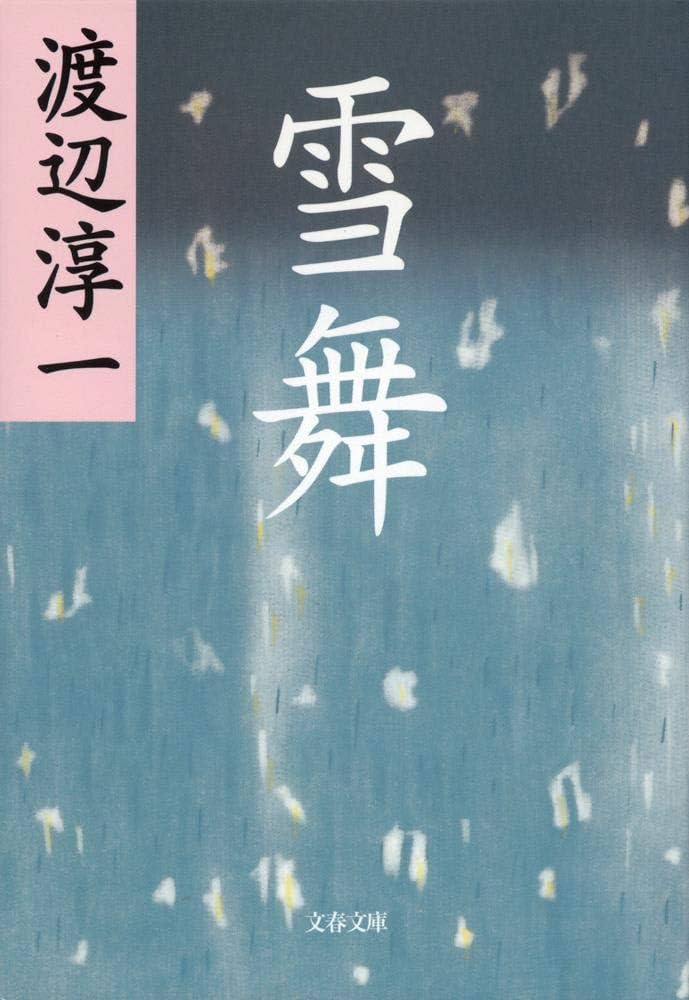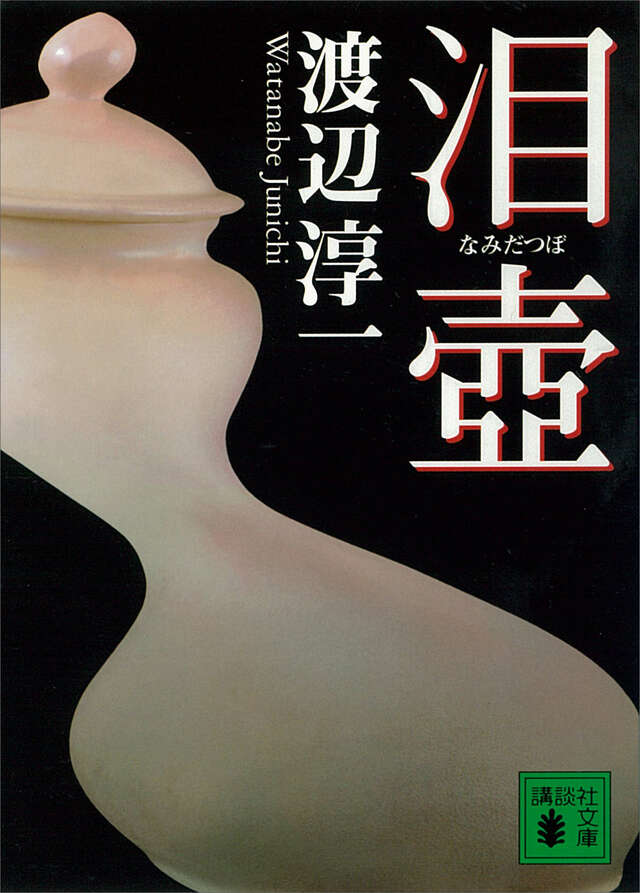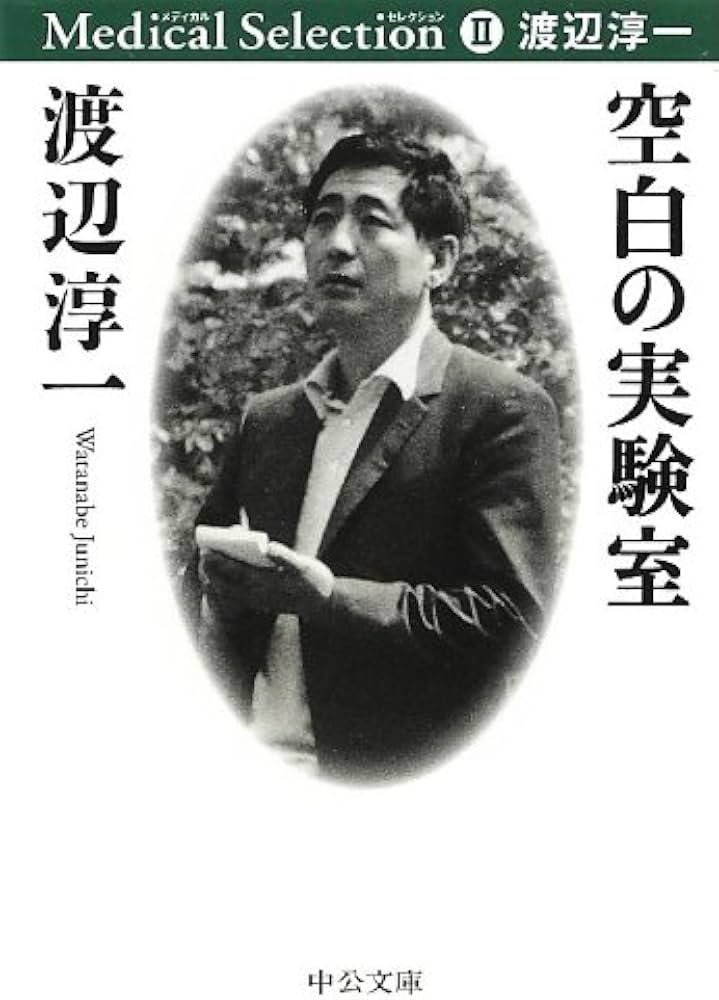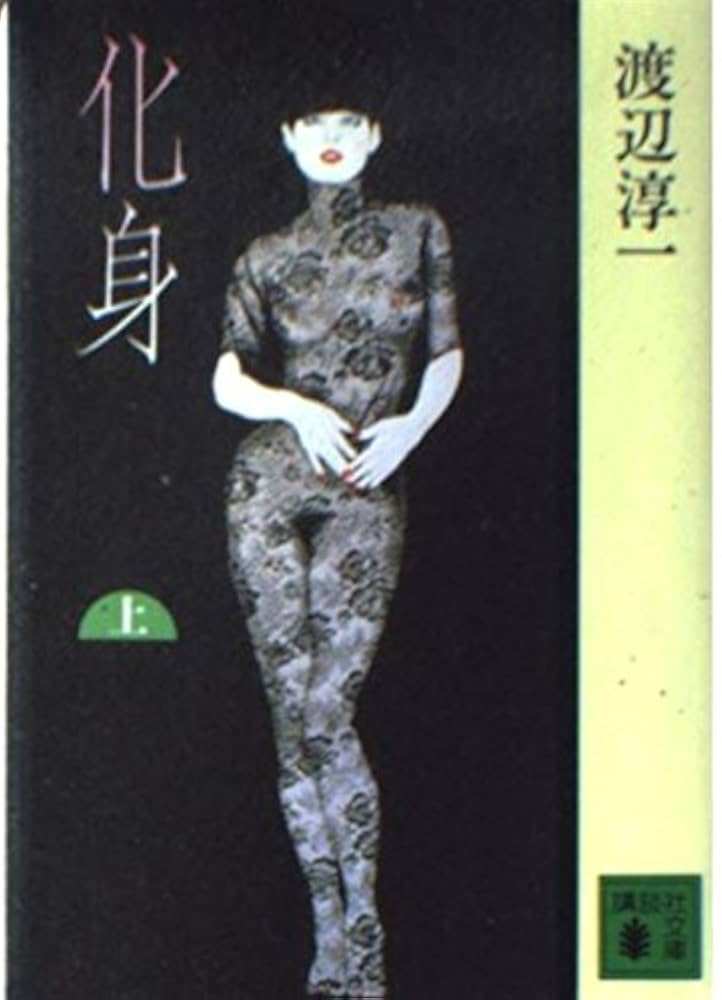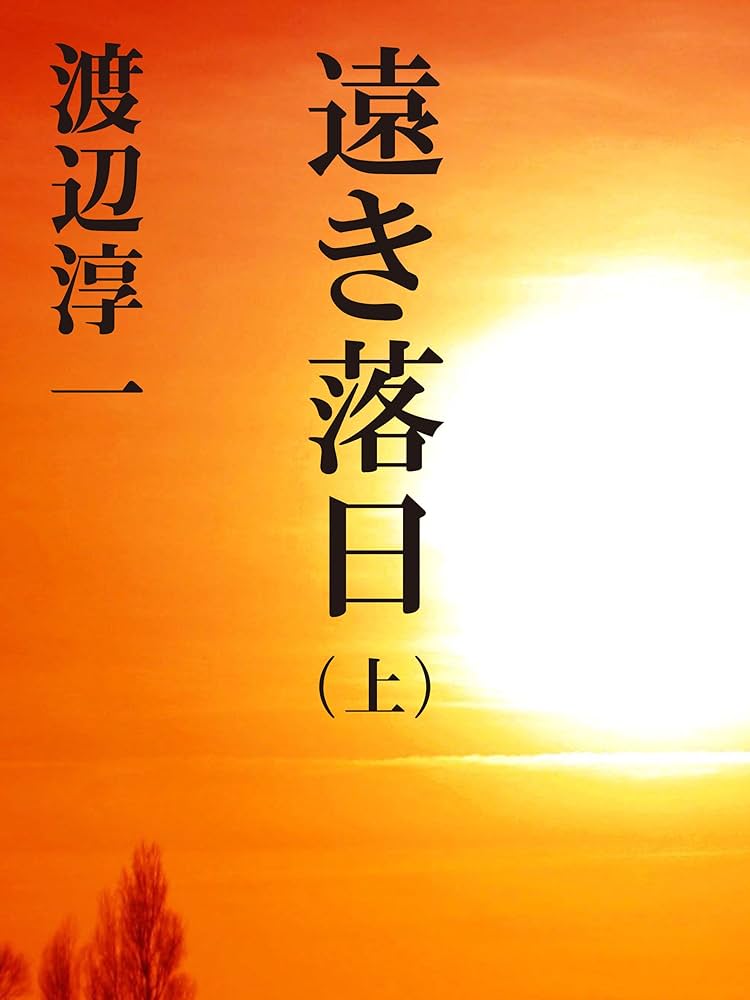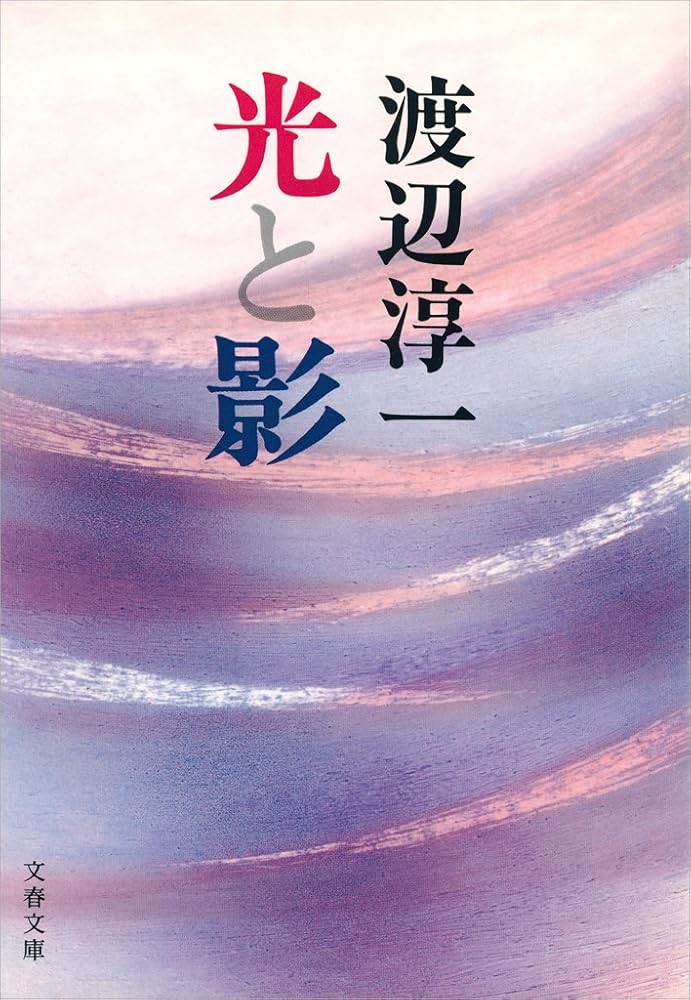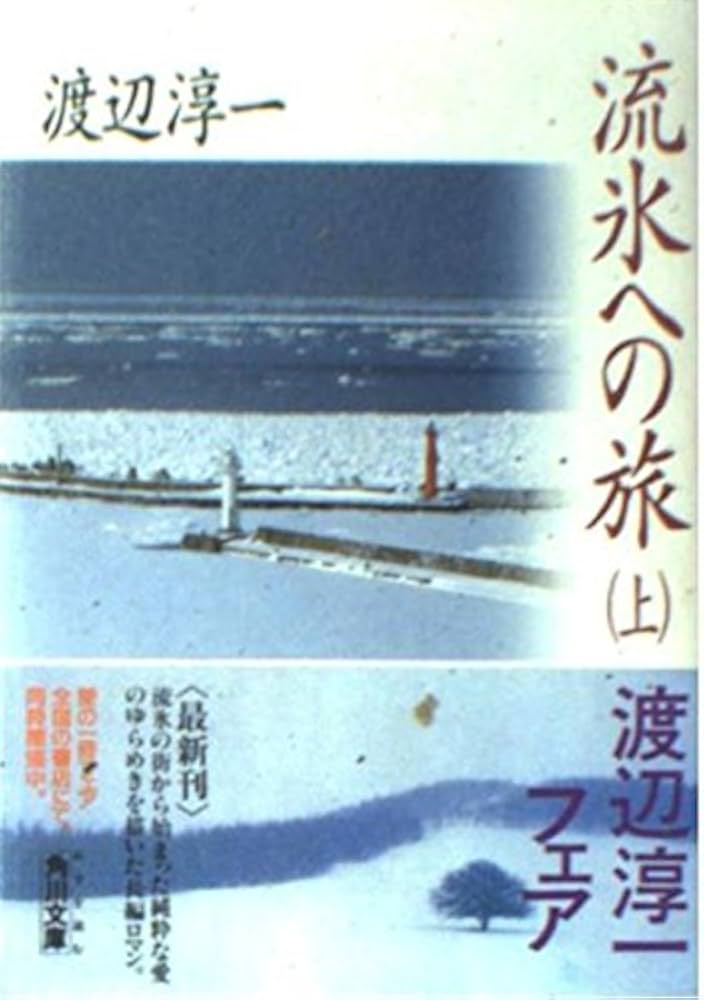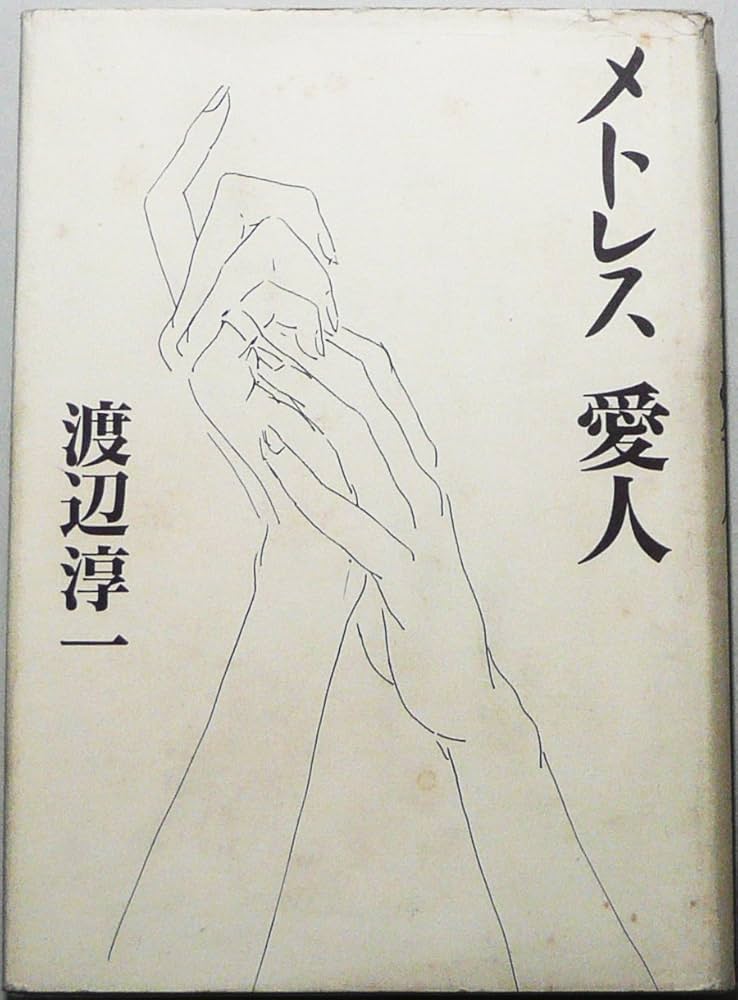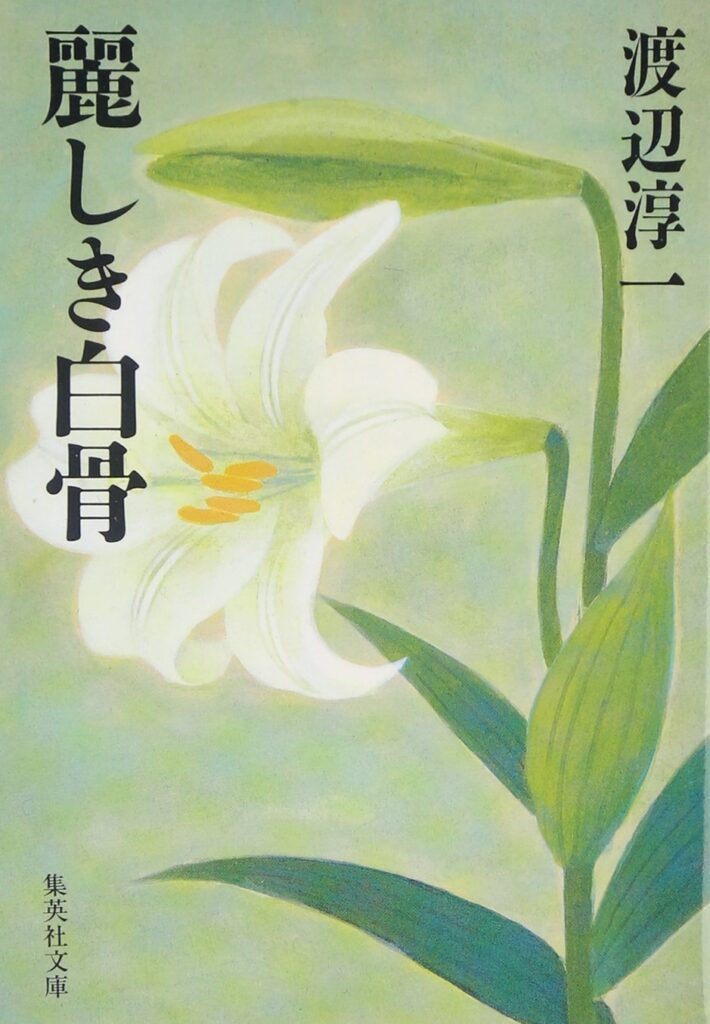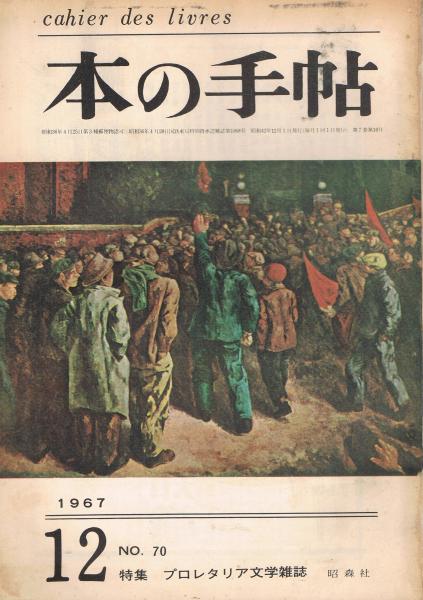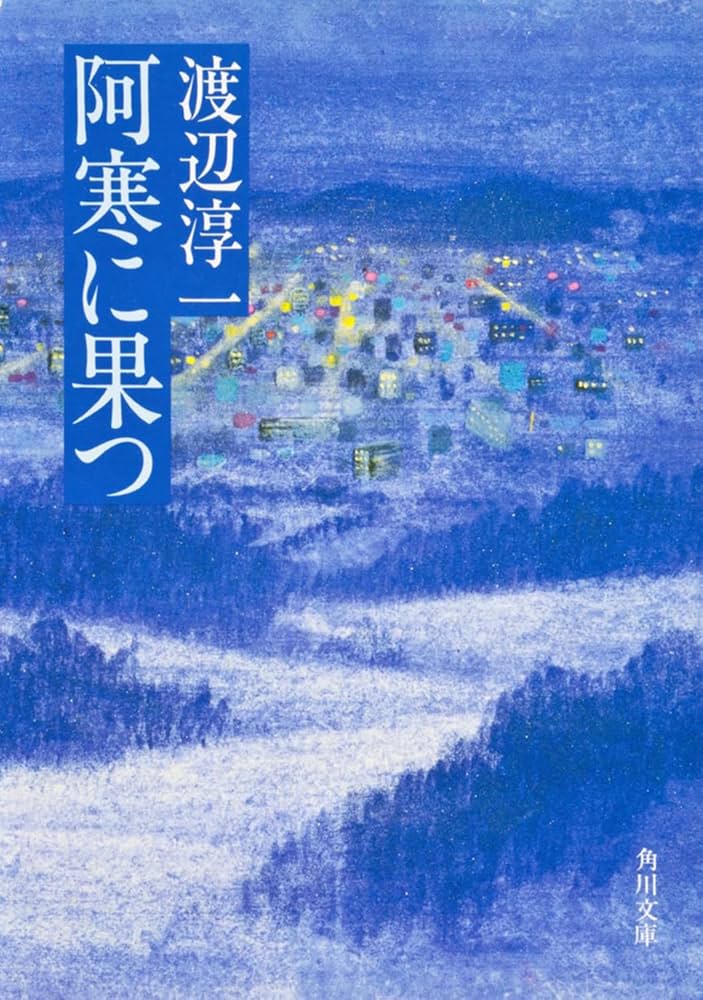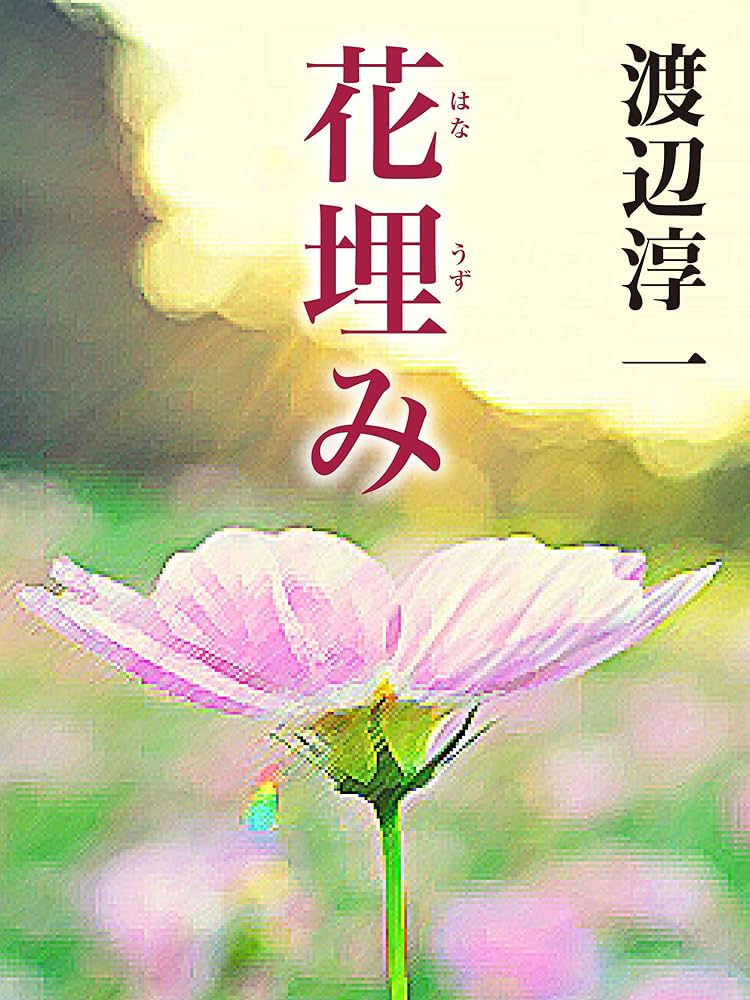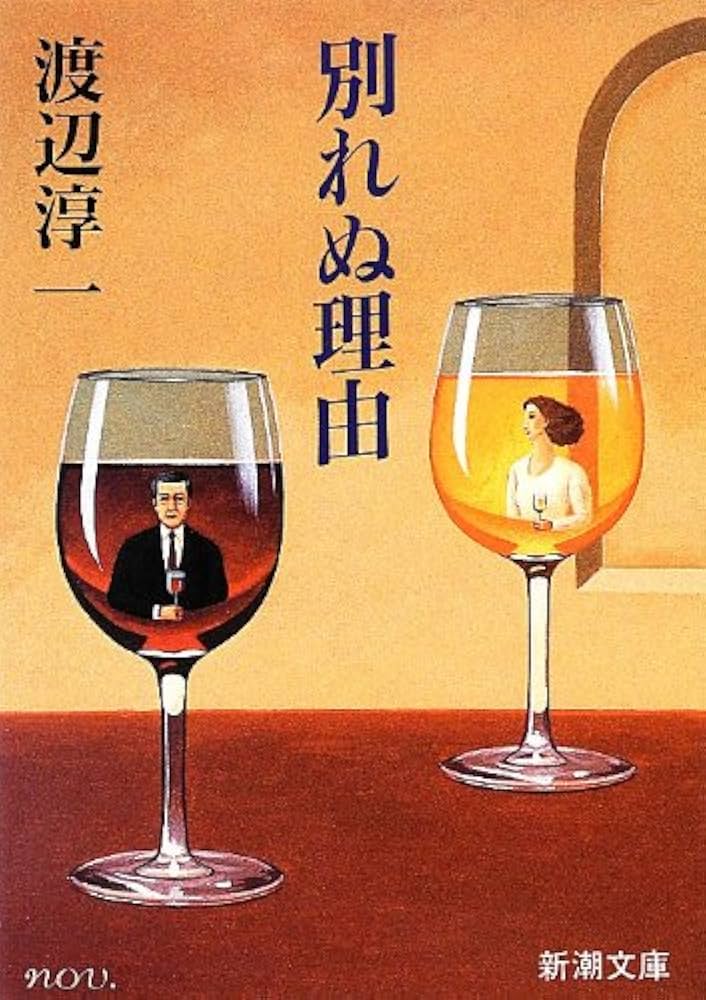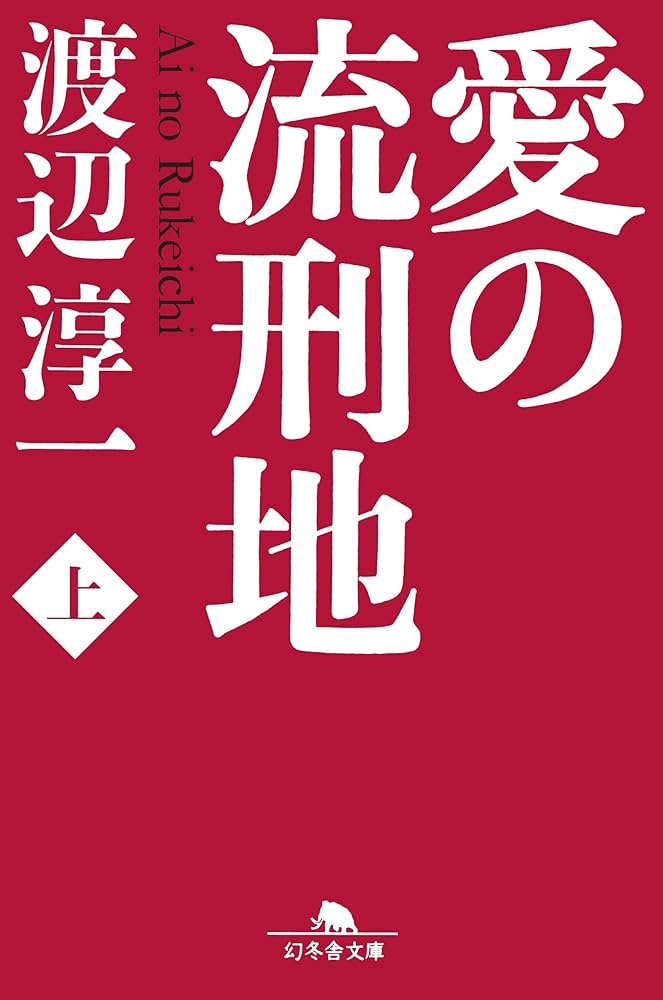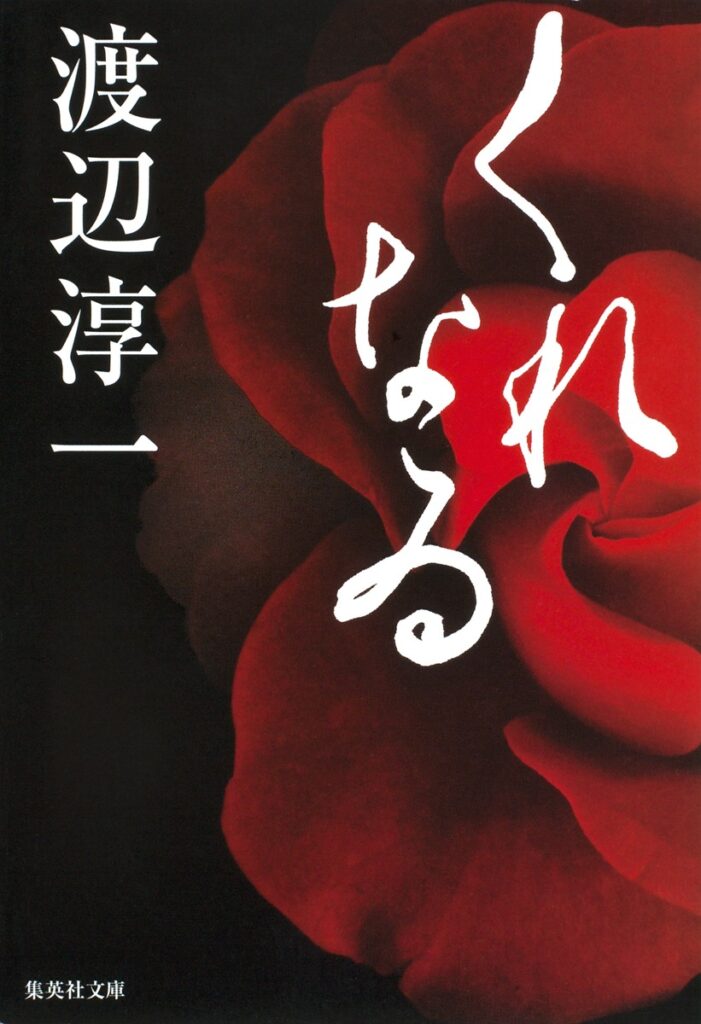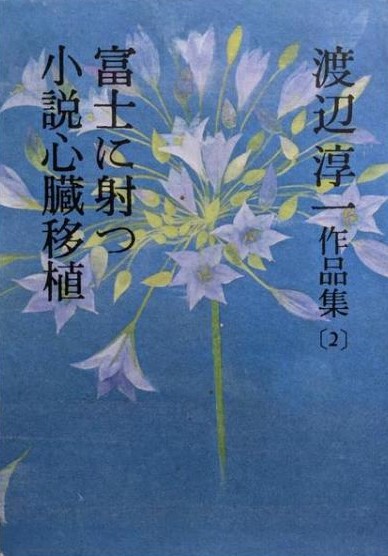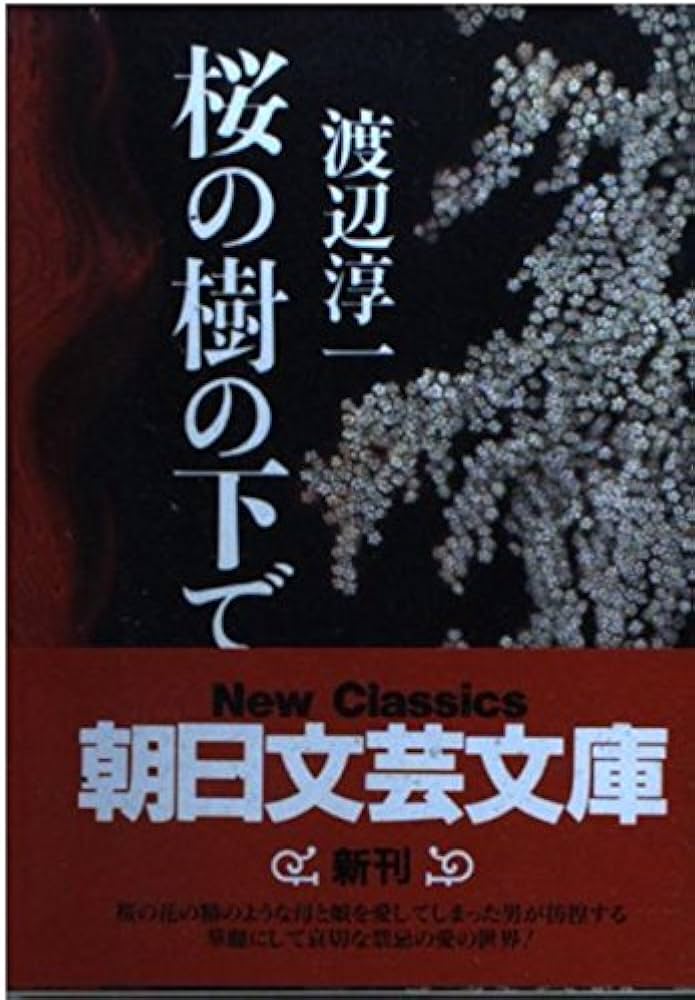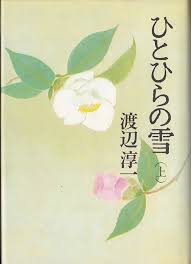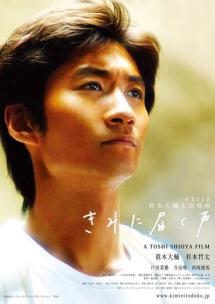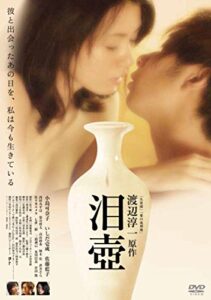 小説「泪壺」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「泪壺」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
渡辺淳一作品といえば、男女の燃え上がるような恋愛を描いたものが数多くあります。しかし、この「泪壺」という物語は、単なる恋愛小説という言葉では到底括ることのできない、人間の愛と執着の最も深い、そして最も恐ろしい淵を覗き込むような作品です。一度読んだら忘れられない、強烈な印象を心に刻みつけます。
物語の始まりは、あまりにも衝撃的です。亡くなった最愛の妻の遺骨を使い、ひとつの壺を作り上げる。この常軌を逸した行為から、物語は静かに、しかし確実に狂気を帯びていきます。その壺は、単なる思い出の品ではありませんでした。やがてそれは、生きている人間を排除し、夫の愛を独占しようとするかのような存在感を示し始めるのです。
この記事では、まず物語の導入から中盤までの流れをご紹介し、その後に核心部分の展開にも触れながら、この物語がなぜこれほどまでに人の心を揺さぶり、そして凍てつかせるのか、その魅力と恐怖の源泉をじっくりと語っていきたいと思います。この世の涯てにあるような、究極の愛の形に触れてみてください。
「泪壺」のあらすじ
主人公である新津雄介は、乳癌によって36歳という若さで世を去った妻・愁子のことが忘れられずにいました。彼女は死の間際に、「わたしを壺にして、側に置いてほしい」という奇妙な遺言を残します。それは、自らの骨を砕き、その骨灰を混ぜ込んだ土でボーンチャイナの壺を焼いてほしいという、具体的で鬼気迫る願いでした。
愁子の死後、雄介はその遺言を果たすため、陶芸家の友人に懇願します。友人はその異常な依頼に慄きながらも、雄介の執念に押されて制作を引き受けます。そして完成した壺は、一点の曇りもない純白の磁器でありながら、その表面にまるで血の涙が流れたかのような「淡い朱の一筋」が浮かび上がっていました。雄介はそれを「泪壺」と名付け、愁子の魂が宿る証として、何よりも大切に愛し始めます。
雄介の生活は、この「泪壺」を中心に回り始めます。愁子の死から時が経ち、新しい女性と親しくなっても、彼女たちが泪壺を目にした途端に言い知れぬ嫌悪感を抱き、関係は終わりを告げます。まるで壺が、雄介の新たな愛を拒絶しているかのようでした。やがて雄介は、お見合いで物静かな女性・朋代と出会い、再婚を果たします。
穏やかに始まったかに見えた新しい結婚生活。しかし、朋代は次第に、夫の愛情が自分ではなく、リビングに置かれた美しい壺へと注がれていることに気づいてしまいます。彼女の中で、壺は亡き先妻の形見から、夫を奪い合う「恋敵」へと変わっていきました。日増しに募る嫉妬と憎しみは、やがて朋代をある大胆な行動へと駆り立てるのでした。
「泪壺」の長文感想(ネタバレあり)
この「泪壺」という物語を読み終えたとき、心に残るのは感動や悲しみといった単純な感情ではありません。それは、人間の心の奥底に潜む、愛という名の底なしの執着を見せつけられたことによる、一種の畏怖と戦慄です。これは、愛の物語であると同時に、愛がその純粋さを保ったまま狂気へと至る、世にも恐ろしい物語なのだと感じずにはいられませんでした。
物語の核心は、主人公・雄介が亡き妻・愁子の遺言を実行する、その一点に凝縮されています。愛する人の骨で壺を作る。この行為を、私たちはどう受け止めればいいのでしょうか。単に「異常だ」と切り捨てるのは簡単です。しかし、渡辺淳一の筆致は、雄介の行動を単なる狂人の奇行としてではなく、あまりにも深く、純粋な愛情の究極的な表現として描いていきます。だからこそ、読者は戸惑い、心を揺さぶられるのです。
雄介は自らの手で、妻の骨を乳鉢で擂り潰します。その描写は淡々と、しかし克明です。生々しい行為であるはずなのに、そこには悲壮なまでの愛情が満ちています。彼は、腐敗し消えゆく肉体という運命に抗い、妻という存在を永遠に自分の側に留めておきたいと願った。その願いが、ボーンチャイナという、最も高貴で純粋な白磁へと結実するのです。
そして完成した壺に浮かび上がった「淡い朱が一筋」。雄介はこれを、愁子が流した血の涙であり、彼女の魂が宿った証だと確信します。読者もまた、この超自然的な現象を、物語の中の「真実」として受け入れざるを得ない空気に包まれていきます。この瞬間から、壺は単なるモノではなく、愁子そのものとして、物語の中で息づき始めるのです。
雄介がこの「泪壺」に注ぐ愛情は、もはや追憶の念ではありません。それは、生きている人間に対するものと同等、いや、それ以上の熱量を持った献身です。彼は壺に話しかけ、優しく撫で、その存在を何よりも優先します。この倒錯した関係性は、物語が進むにつれて、より明確に、そしてより恐ろしい形で現れてきます。
その最初の犠牲者となるのが、雄介の新しい恋人・麻子です。彼女は、雄介の自宅で泪壺を目にした瞬間、生理的な嫌悪感を覚えて逃げ出してしまいます。この場面は、物語が単なる心理劇から、超自然的なホラーへと踏み込む重要な転換点です。麻子の反応は、壺が生きている人間、特に雄介の愛を奪おうとする「女」を本能的に拒絶し、追い払う力を持っていることを示唆しています。
それは雄介の深層心理が麻子を拒んだのか、それとも愁子の魂が宿る壺が能動的に彼女を排除したのか。その境界線は曖昧に描かれています。しかし、どちらにせよ、死せる愁子の存在が、生ける麻子の存在を打ち負かしたという事実は揺るぎません。この時から、雄介の世界では、死者が生者に対して明確な優位性を持つようになるのです。
そして、物語は後妻・朋代の登場によって、決定的な悲劇へと向かっていきます。朋代は、何も知らずに雄介と結婚した、ごく普通の女性です。彼女の視点は、私たち読者の視点と最も近いと言えるでしょう。夫が自分よりも美しい壺を溺愛している。その壺が、亡き先妻の骨から作られているなどとは夢にも思わず、彼女はただ純粋な嫉妬心から、その壺を「恋敵」として憎むようになります。
朋代の感情は、あまりにも人間的で、共感を誘います。「あなたは、わたしよりこの壺のほうが大切なのよ」。そう言って、壺の表面を爪で激しく引っ掻く彼女の姿は、愛する人の心を取り戻そうともがく、痛々しくも必死な抵抗です。しかし、彼女のこの行為は、眠れる獅子を起こすような、あまりにも無謀な挑戦でした。
この抵抗からわずか三日後、朋代は唐突な交通事故で命を落とします。その死は、あまりにもあっけなく、原因も状況も一切語られません。この描写の欠如こそが、この上ない恐怖を生み出します。まるで、神聖な領域を侵した者に対する、冷徹で容赦のない天罰が下ったかのように。朋代の死は、泪壺の意志による報復だったのか。読者の想像力は、その不気味な可能性へと導かれていきます。
そして物語は、戦慄のラストシーンで締めくくられます。再び一人になった雄介が、泪壺を優しく撫でながら囁く、最後の言葉。「やっぱり、お前だけを守っていくよ…」。この一言が、この物語のすべてを物語っています。彼は、生きている妻・朋代の死を悲しむのではなく、死してモノとなった妻・愁子との愛の成就を誓うのです。朋代の死は、彼らの愛を邪魔する最後の障害が取り除かれたことを意味していました。
ここにきて、私たちは悟るのです。これは悲劇の物語ではなく、雄介と愁子にとっては、究極のハッピーエンドなのだと。常識や倫理観を根底から覆す、倒錯した愛の完成。そのおぞましいほどの純粋さに、私は言葉を失いました。愛とは、時にこれほどまでに排他的で、残酷なものになり得るのかと。
ここで、2008年に公開された映画版にも少し触れておきたいと思います。映画版は、この原作の持つ冷たい恐怖とは全く異なるアプローチで「泪壺」を描きました。最大の違いは、後妻の朋代が、亡き妻・愁子の「姉」として設定されている点です。この変更によって、物語は大きくその姿を変えます。
映画版の朋代は、妹の結婚前から雄介に想いを寄せていた、悲劇のヒロインとして描かれます。彼女にとって泪壺は、亡き妹の象徴であり、雄介への愛を阻む罪悪感の塊です。物語の葛藤は、「人間 vs 壺(死者)」から、「朋代の心の中の葛藤」へと移行し、より共感を呼びやすい、切ない恋愛ドラマとして再構築されているのです。
原作の持つ、理屈を超えた超自然的な恐怖を好むか、映画版の持つ、人間的な感情に寄り添った悲恋の物語を好むか。それは個人の好みによるでしょう。しかし、渡辺淳一が最初に描こうとした、人間の「理でないリアリティー」を抉り出すような、文学の持つ鋭利な刃物のような切れ味は、やはり原作の短編にこそ宿っていると私は感じます。
渡辺淳一は元医師という経歴を持つ作家です。その視点は、常に人間を「肉体」という物質的な存在として冷徹に捉えています。精神や魂も、結局はこの肉体に宿り、肉体が滅べば消えていく。だからこそ、雄介は妻の「骨」という物質に執着したのかもしれません。精神的な愛という不確かなものではなく、手に触れられる「モノ」として、妻を永遠に所有しようとしたのです。
この物語が書かれた1980年代後半の日本は、バブル経済の絶頂期でした。誰もが物質的な豊かさを追い求めていた時代に、雄介は社会に背を向け、死者の骨という、究極に私的なモノとの関係に閉じこもっていきます。その姿は、時代の熱狂に対する強烈なアンチテーゼのようにも見えます。
「泪壺」は、私たちに問いかけます。愛とは何か、と。それは、温かく、他者と分かち合うものなのか。それとも、冷たく、排他的で、自分だけの世界で完結するものなのか。この物語が提示する愛の形は、あまりにも極端で、恐ろしいものです。しかし、その恐ろしさの中に、否定しきれない純粋な輝きを見出してしまうからこそ、この物語は私たちの心を捕らえて離さないのでしょう。
まとめ
渡辺淳一の小説「泪壺」は、亡き妻の遺骨で焼いた壺を溺愛する男の物語という、一度聞いたら忘れられない設定を持っています。それは、愛と執着が常軌を逸し、やがて生きている人間をも脅かす存在へと変貌していく様を、静かな筆致で描き出した傑作です。
本記事では、物語の結末に至るまでの流れを追いながら、その核心に秘められた恐怖と、倒錯した愛の形について深く掘り下げてみました。主人公・雄介が選んだ究極の選択は、読む者の倫理観を激しく揺さぶります。これは単なる悲しい物語ではなく、ある種の愛の成就を描いた、戦慄の物語でもあります。
また、後妻・朋代を亡き妻の姉として設定し、悲恋の物語として再構築した映画版との比較も行いました。原作の持つ冷徹な恐怖か、映画版の切ない人間ドラマか、どちらの「泪壺」に惹かれるかは、人それぞれかもしれません。
この記事を通して、「泪壺」という作品が持つ、底知れない魅力の一端でもお伝えできていれば幸いです。美しいだけではない、愛という感情が内包する狂気と純粋さの深淵を、ぜひご自身の目で確かめてみてください。