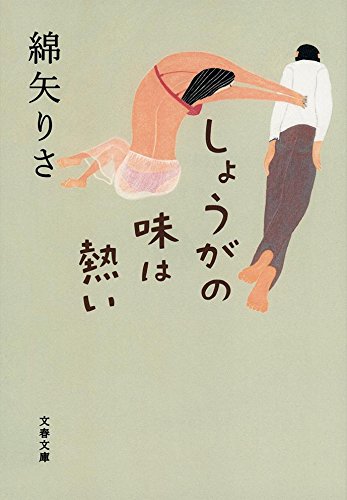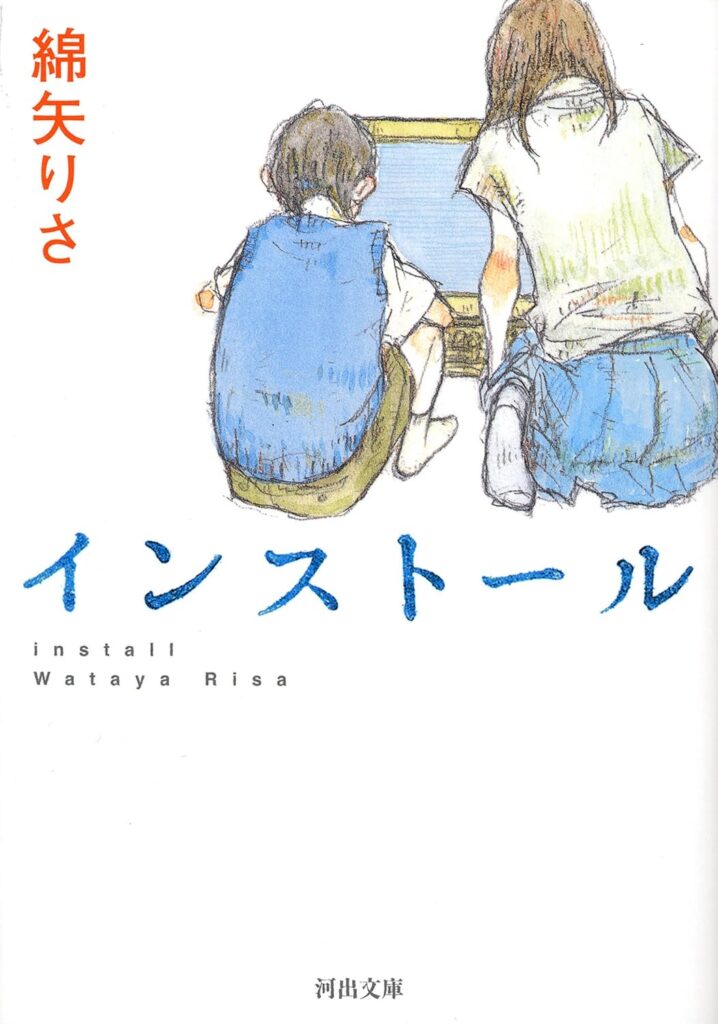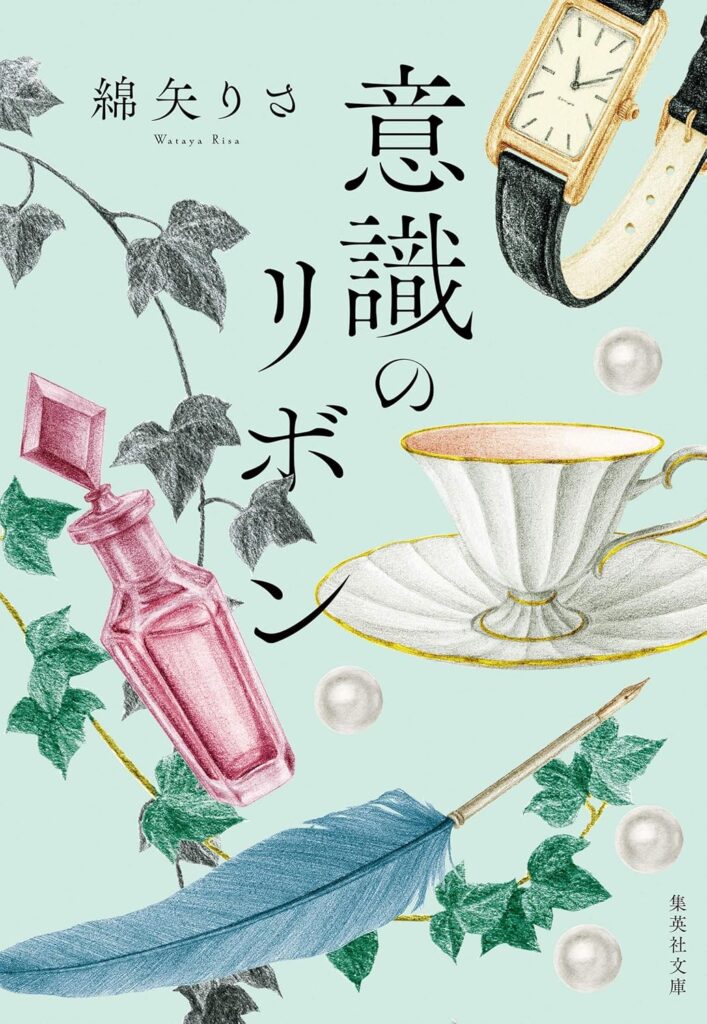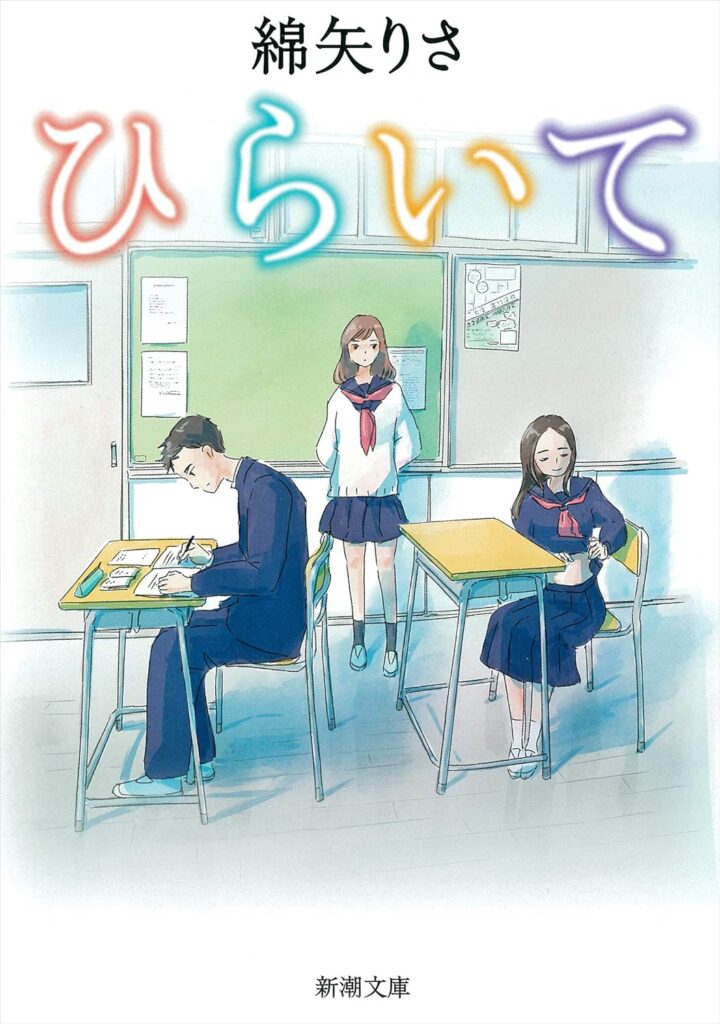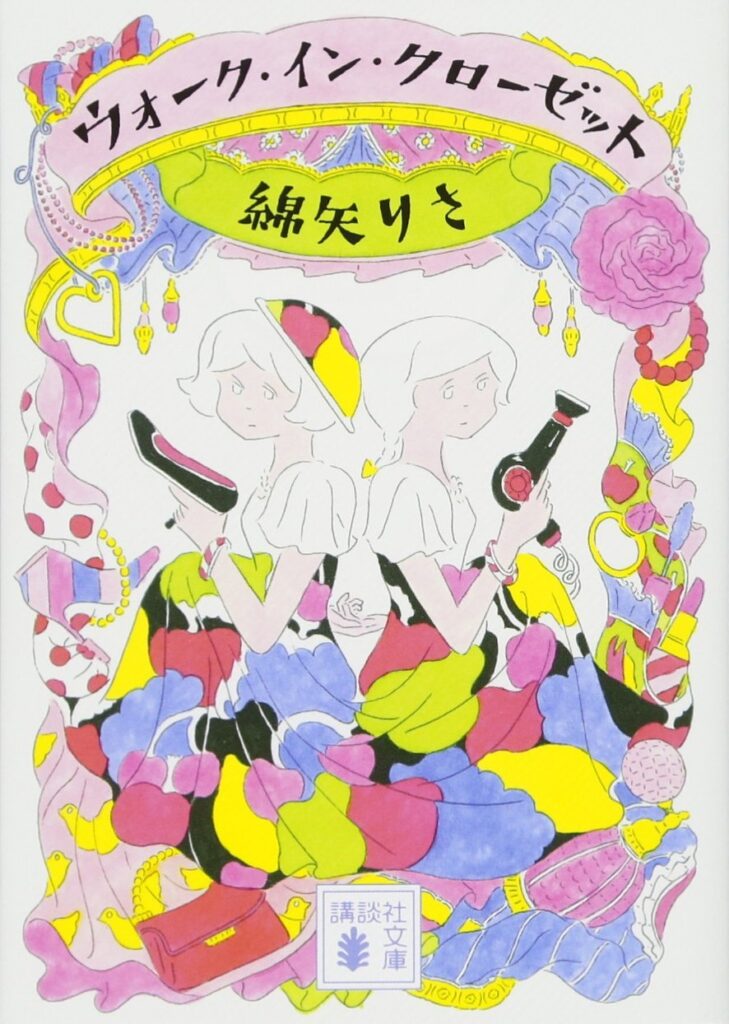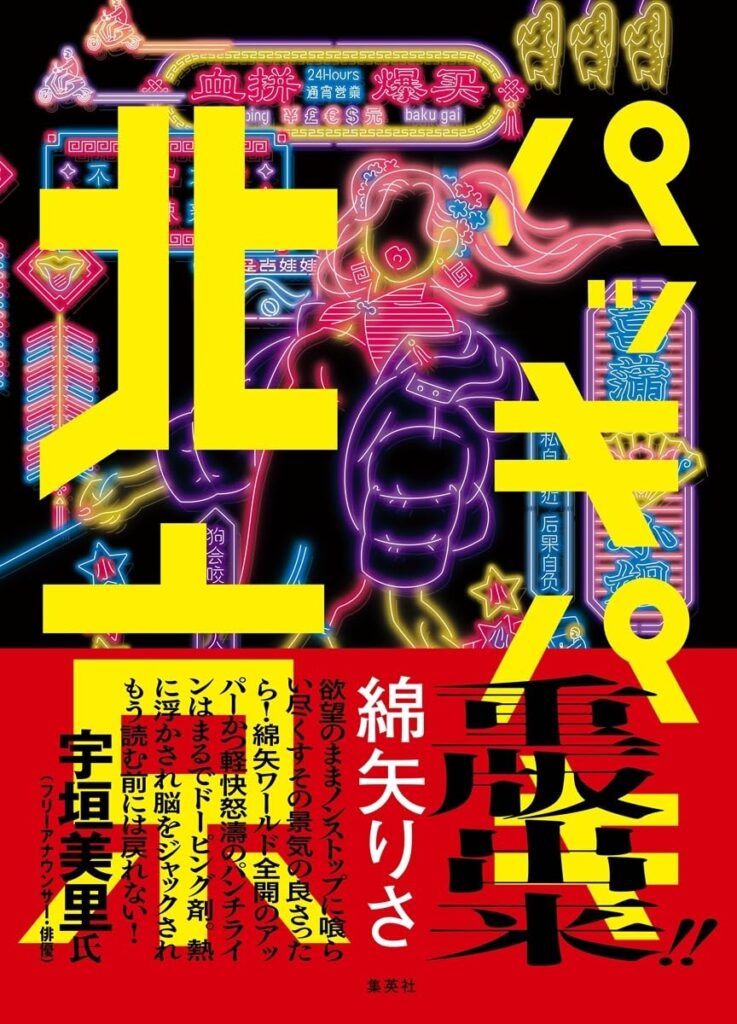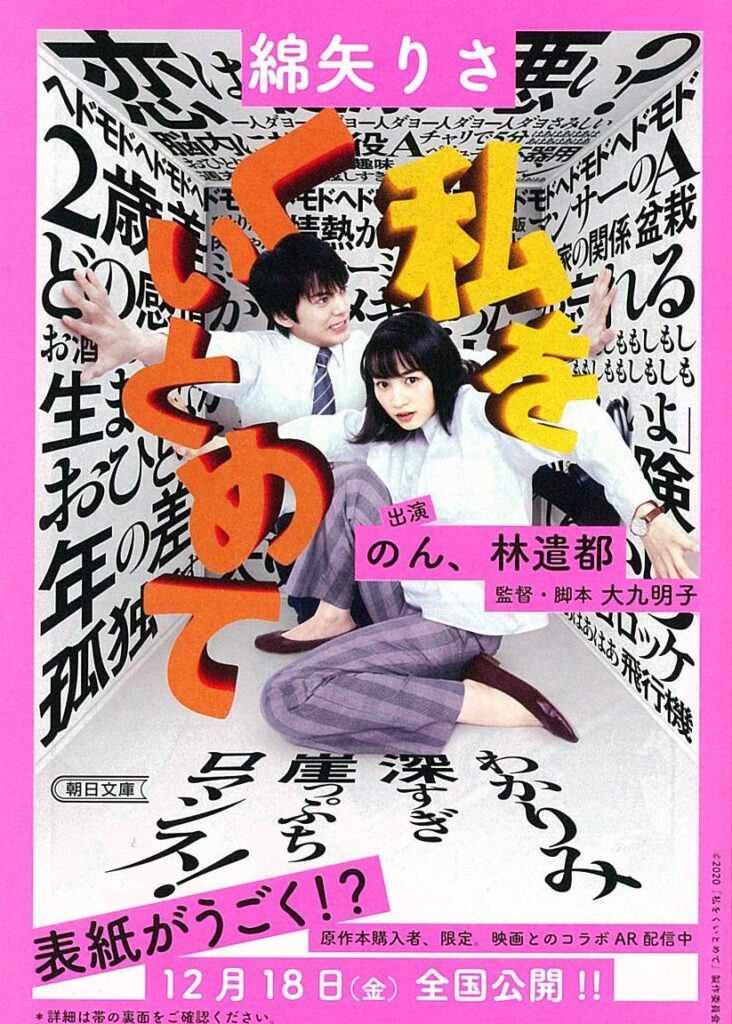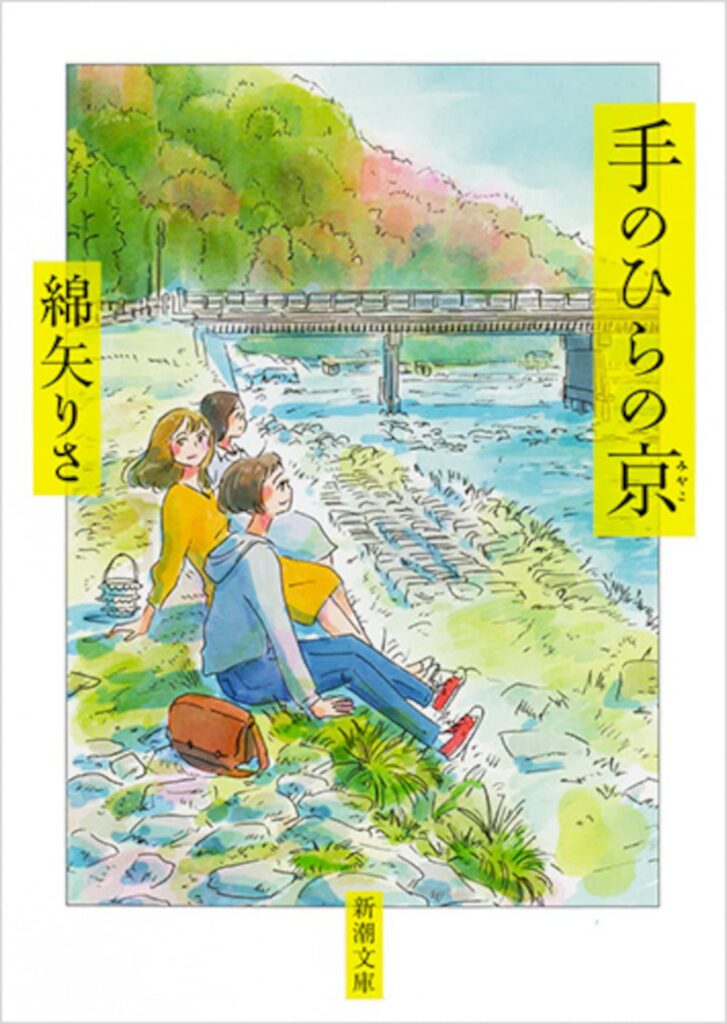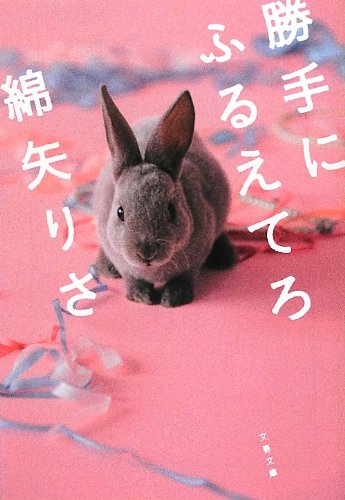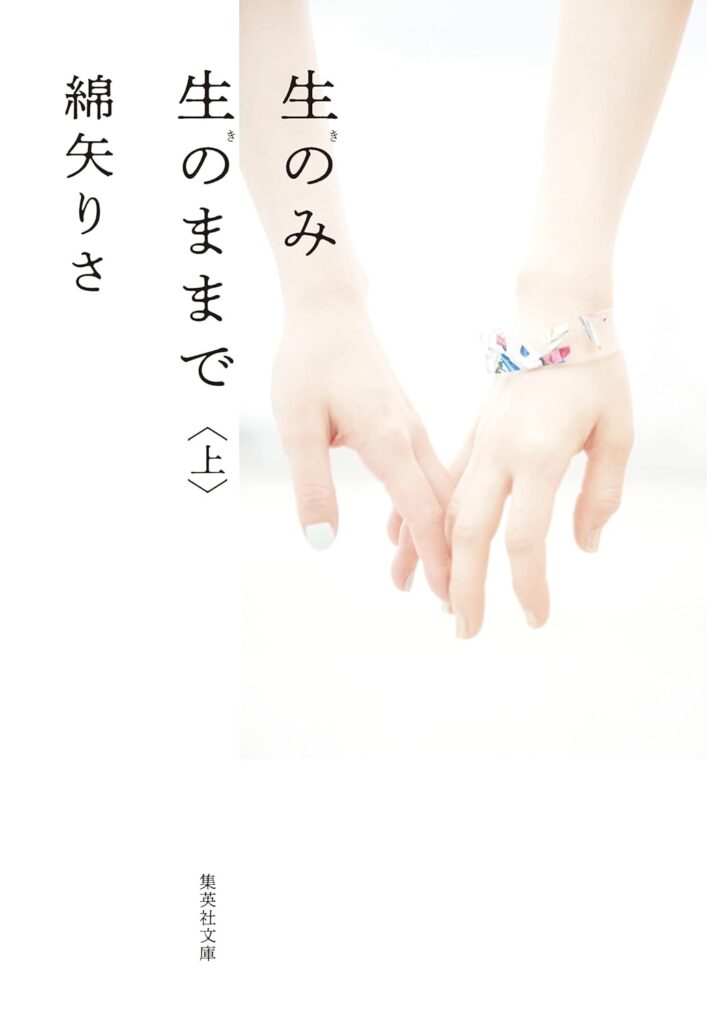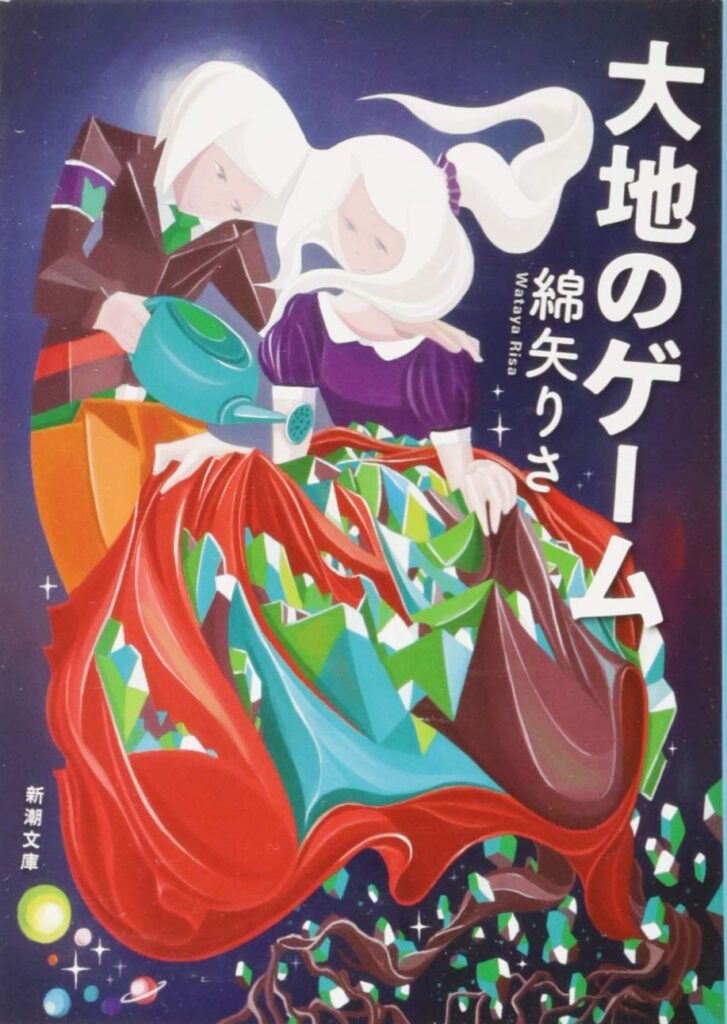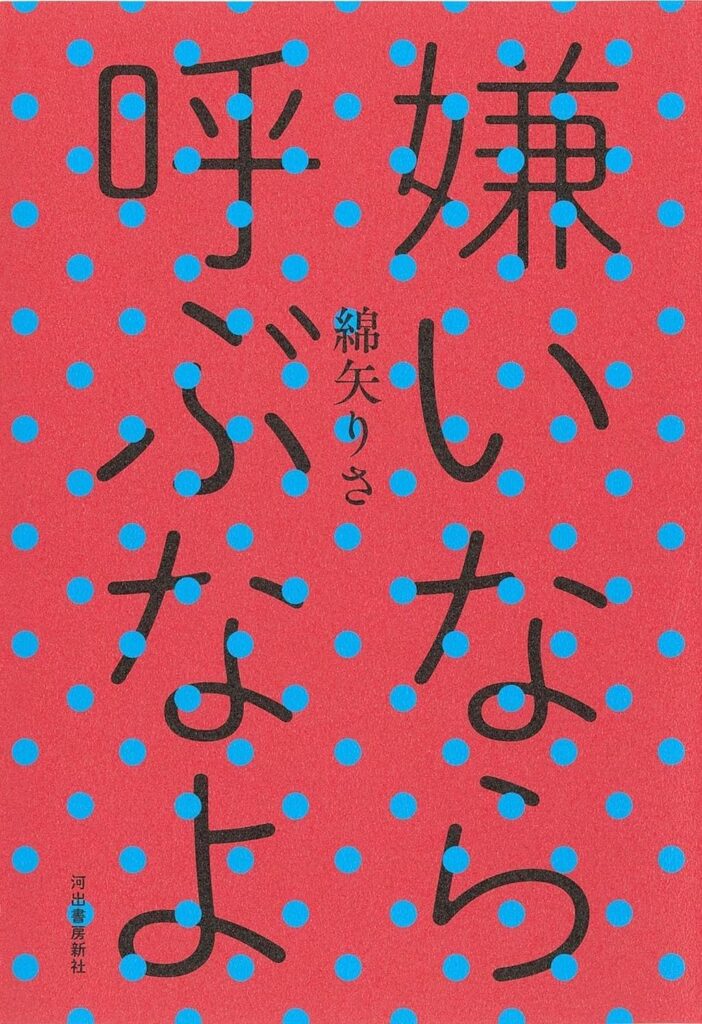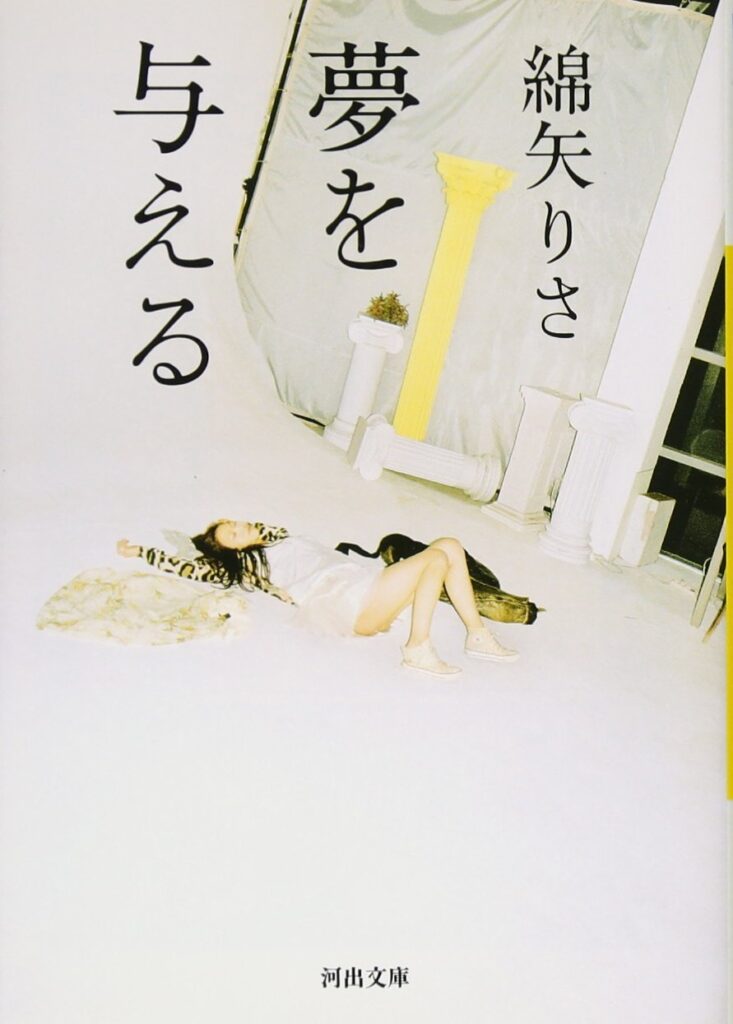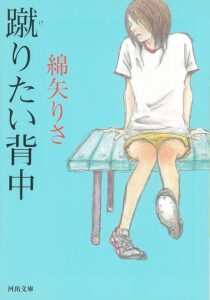 小説「蹴りたい背中」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「蹴りたい背中」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
綿矢りささんの「蹴りたい背中」は、2003年に発表され、第130回芥川賞を受賞した作品ですね。当時、作者の綿矢さんが19歳という若さで受賞されたことは、本当に大きな話題となりました。この記録は今も破られていないそうで、文学史に残る出来事だったと言えるでしょう。
この物語は、高校という閉じた世界のなかで、うまく周囲に馴染めずにいる二人の男女、ハツとにな川の関係性を軸に描かれています。思春期特有の孤独感や、言葉にならないもどかしさ、そしてタイトルにもなっている「蹴りたい」という衝動。読んでいて、自分の学生時代を思い出したり、ヒリヒリするような感覚を覚えたりする方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな「蹴りたい背中」の物語の筋道を、結末の内容にも触れながら詳しくお伝えしていきます。さらに、作品を読んで私が感じたこと、考えたことを、少し長くなりますが丁寧に書き綴ってみました。作品の魅力を深く味わう一助となれば嬉しいです。
小説「蹴りたい背中」のあらすじ
物語の主人公は、高校一年生の長谷川初実、通称ハツ。彼女は、クラスの中で特定のグループに属さず、どこか冷めた視線で周囲を観察しながら、孤独な学校生活を送っています。中学時代からの友人である絹代は、高校に入ると新しい友人たちと群れることに一生懸命で、ハツとの間には少し距離ができていました。ハツは、そんな友人に対しても、どこか醒めた気持ちを抱いています。
ある日の理科の実験の時間、ハツは自分と同じようにクラスで浮いている男子生徒、にな川智の存在を意識します。実験に参加しようとせず、彼は膝の上で女性向けのファッション雑誌を熱心に読んでいました。ハツが何気なく声をかけても、にな川はほとんど反応を示しません。しかし、雑誌に載っているモデル、オリちゃんこと佐々木オリビアを指してハツが「この人に会ったことある」と口にすると、にな川は意外な反応を見せます。
これがきっかけとなり、ハツはにな川の家に招かれます。古びた平屋の離れにある彼の部屋は、独特の空気が漂っていました。そこでハツは、にな川がオリちゃんの熱狂的なファンであり、彼女に関する雑誌の切り抜きや、グッズ、さらには女性ものの服まで収集していることを知ります。「死ぬほど好き」だと語るにな川の異様さに、ハツは少なからず衝撃を受けます。
ハツがオリちゃんに会ったのは、中学一年生の夏。駅前の無印良品で試食のコーンフレークを食べていた時でした。美しいオリちゃんと、彼女を撮影していたカメラマン。彼らがふざけてコーンフレークを食べさせ合う姿を見て、ハツはそれまで無自覚だった「試食で食事を済ませる」ことへの羞恥心を覚えたのでした。この出来事は、ハツが周囲との距離を意識し、高校で孤立を選ぶようになる遠因とも言えます。
にな川との交流は続きます。彼の部屋で、イヤホンでオリちゃんのラジオを聴き、彼女の世界に没入するにな川。その無防備な背中を見ているうちに、ハツは説明のつかない衝動に駆られます。「蹴りたい」。気づけば、彼女の足はにな川の背中に触れていました。謝るハツですが、この出来事は二人の関係に奇妙な影を落とします。
やがて、にな川はオリちゃんのライブチケットを手に入れ、ハツと、そして絹代も誘って三人でライブ会場へ足を運びます。ライブの熱狂の中で、ハツは再び疎外感を感じます。帰り道、終バスを逃した三人は、にな川の家に泊まることになります。深夜、眠れずにベランダに出たハツは、そこで一人うずくまるにな川を見つけます。明け方の空を眺めながら、二人は言葉少なに対峙します。そして、ハツの中で再び「あの気持ち」が湧き上がり、彼女はつま先を、にな川の背中にそっと押し当てるのでした。
小説「蹴りたい背中」の長文感想(ネタバレあり)
綿矢りささんの「蹴りたい背中」、この作品を読むたびに、高校時代のあの独特な空気感、息苦しさみたいなものを思い出して、胸がざわざわしますね。主人公ハツの、周囲に対する斜に構えた態度や、内面に抱えるプライドの高さ、そして孤独。それは、多かれ少なかれ、誰もが思春期に経験する感情なのかもしれません。
ハツは、クラスメイトたちが作るグループの輪に入ろうとしません。中学時代の友人・絹代が、必死で「友達」という集団に所属しようとする姿を、どこか冷ややかに見ています。理科の実験で顕微鏡を覗きに行くことすらためらう彼女の姿には、「声をかけて輪に入れてもらう」ことへの抵抗、あるいは「自分から行くなんて負けだ」というような、いびつな自尊心が見え隠れするように感じます。
彼女の孤独は、単なる「ひとりぼっち」という状態ではなく、自ら選んだ壁のようなものなのかもしれません。「あんな人たちと無理して付き合う必要はない」「自分は違う」と考えることで、かろうじて自己を保っている。そうした態度は、知らず知らずのうちに他者を見下す視線につながっていくのかもしれません。
そんなハツの前に現れたのが、にな川という存在です。彼もまた、クラスの中で孤立しています。しかし、ハツの孤立が能動的な選択であるのに対し、にな川のそれは、もっと受け身で、不器用さからくるもののように見えます。授業中に女子向けファッション誌を読みふけり、モデルのオリちゃんに異常なまでの執着を見せる。彼の部屋に集められたオリちゃんグッズや女性ものの服は、彼の現実からの逃避願望と、満たされない何かを表しているように思えます。
ハツは、にな川に対して複雑な感情を抱きます。最初は、自分と同じ「余り者」としての仲間意識のようなものがあったかもしれません。しかし、彼のオリちゃんへの偏執的なまでの想いや、部屋の異様な様子を知るにつれて、そこには軽蔑や憐れみ、そしてある種の嫌悪感のようなものが混じり始めます。それでも、彼から完全に離れることはしない。それは、にな川が自分と同じく「普通」の輪からはみ出した存在であり、どこか理解できる部分、あるいは自分を映す鏡のような部分を感じていたからかもしれません。
そして、この物語の核心とも言える「蹴りたい」という衝動。ハツがにな川の無防備な背中を見て抱くこの感情は、一体何なのでしょうか。単なる暴力衝動、サディズムというだけでは片付けられない、もっと複雑なものが絡み合っているように感じます。それは、言葉にならない苛立ちや、コミュニケーション不全の表れなのかもしれません。
にな川の、オリちゃんへの歪んだ愛情表現(例えば、参考資料にあったアイコラの話など、作品内の描写を思い出します)に対する嫌悪感や、彼の弱さ、不気味さに対する拒絶反応。あるいは、自分の中にもある、うまく言語化できないドロドロとした感情を、一番手近で、自分よりも弱い(と彼女が認識している)存在であるにな川にぶつけてしまいたいという欲求。様々な解釈ができると思います。
興味深いのは、ハツがにな川を蹴るのは一度だけではないということです。最初は彼の部屋で、そして物語の最後、ライブの後にな川の家に泊まった明け方、ベランダで。二度目の「蹴る」行為は、一度目よりもっと静かで、確信犯的な印象を受けます。「痛い」と言うにな川に、「ベランダの窓枠じゃない?」と嘘をつくハツ。この行為は、単なる衝動の発露というよりも、二人の間のいびつな関係性を象徴し、ある種のコミュニケーションとして機能しているようにも見えます。言葉では繋がれない、触れることでしか確かめられない存在。そんな危うさが、この場面には漂っています。
オリちゃんの存在も、この物語において非常に重要ですね。彼女は、ハツとにな川という、本来交わるはずのなかった二人を結びつける共通項として機能します。しかし、それだけではありません。ハツにとってオリちゃんは、中学時代に「社会」や「他者の視線」を意識させ、それまでの無邪気な世界からの脱却を促した存在でもあります。無印良品での出来事は、ハツが「個」として生きることを意識し、高校で集団から距離を置く選択をするきっかけの一つになったのかもしれません。
一方で、にな川にとってのオリちゃんは、現実逃避の対象であり、崇拝の対象です。ライブ会場で本物のオリちゃんを目の当たりにしたにな川は、しかし、「今までで一番彼女を遠くに感じた」と言います。手の届かない偶像であることを痛感させられた瞬間です。この経験は、彼にとってどのような意味を持ったのでしょうか。彼のオリちゃんへの想いは、この後どう変化していくのか、あるいはしないのか。読者の想像に委ねられています。
作品全体を覆うのは、思春期特有の閉塞感と、ヒリヒリするような感覚です。教室の中の目に見えないカースト、友人関係の微妙なパワーバランス、異性に対する意識、大人たちの世界への反発と、そこはかとない諦め。綿矢さんの文体は、そうした少年少女の心理の機微を、非常に繊細かつシャープに捉えています。決して感傷的になりすぎず、かといって突き放すだけでもない。その絶妙な距離感が、読者を引き込みます。
この作品が芥川賞を受賞した当時、19歳という作者の年齢が大きな注目を集めましたが、それ以上に、この作品が描き出した現代的な(当時としても、そして今読んでも古びない)孤独やコミュニケーションのあり方が、多くの読者の共感を呼んだのだと思います。SNSが発達した現代において、ハツやにな川のような孤独感や、他者との繋がりを求めながらも壁を作ってしまうような感覚は、むしろより身近なものになっているのかもしれません。
読み終えた後、爽快感があるわけではありません。むしろ、少し重たいものが心に残ります。ハツやにな川が、この後どうなっていくのか。彼らの関係は続くのか、それとも終わるのか。明確な答えは示されません。それでも、あの明け方のベランダのシーン、同じ景色を見ながら全く違うことを考えている二人、そしてそっと背中に触れる足の感触。その光景が、強く印象に残ります。
それは、完全な理解や共感には至らなくても、あるいは歪んだ形であっても、他者と関わろうとすること、その存在を確かめようとすることの、一つの形なのかもしれません。痛みを伴うとしても、そこに微かな繋がりや、人間関係の複雑なリアリティが描かれているように感じました。青春のきらめきだけでなく、その影にある痛みや苦さをも描き切った、「蹴りたい背中」は、何度読んでも考えさせられる深い作品だと思います。
まとめ
綿矢りささんの「蹴りたい背中」は、高校生のハツとにな川という、クラスに馴染めない二人の関係性を軸に、思春期の複雑な感情を描き出した物語です。芥川賞を史上最年少で受賞したことでも知られるこの作品は、発表から時間が経った今でも、多くの読者の心を捉えています。
物語は、孤独を選び取るハツと、モデルのオリちゃんに熱狂するにな川という、対照的なようでいて、どこか通じ合う部分を持つ二人の出会いから始まります。彼らの交流は、友情とも恋愛ともつかない、危うく、そして奇妙な共犯関係のような様相を呈していきます。そして、ハツが抱く「蹴りたい」という衝動は、言葉にならない感情やコミュニケーション不全の象徴として、強く印象に残ります。
この記事では、物語の結末に触れながら、その筋道を詳しく追いました。また、ハツやにな川の人物像、オリちゃんの役割、そして「蹴る」という行為に込められた意味などについて、私なりの解釈や感じたことを詳細に述べさせていただきました。ネタバレを含む内容となっていますので、その点はご留意ください。
「蹴りたい背中」は、読者に自身の経験を重ね合わせたり、人間関係の難しさや思春期の息苦しさについて考えさせたりする力を持っています。まだ読んだことのない方はもちろん、再読を考えている方にも、この記事が作品をより深く味わうための一つの視点となれば幸いです。