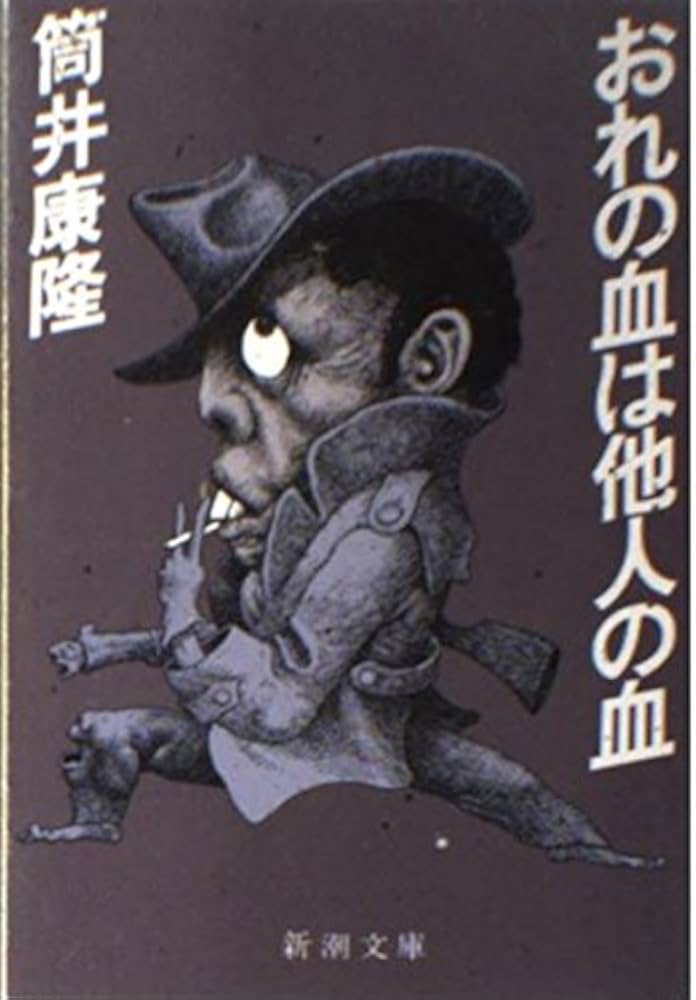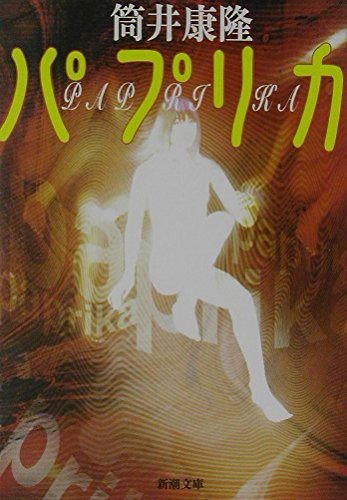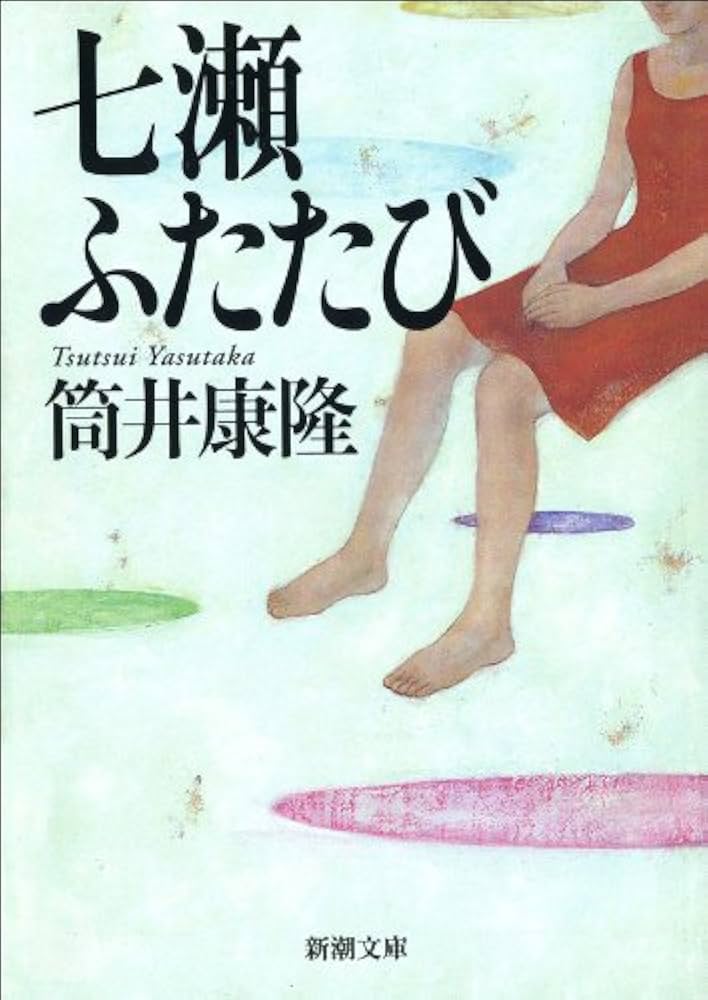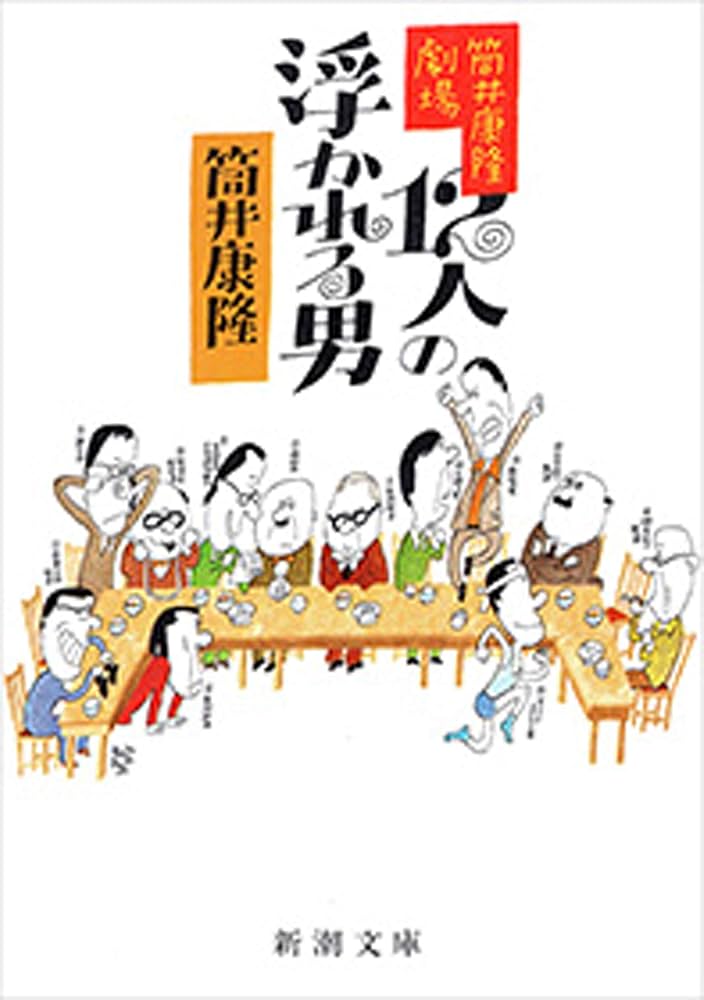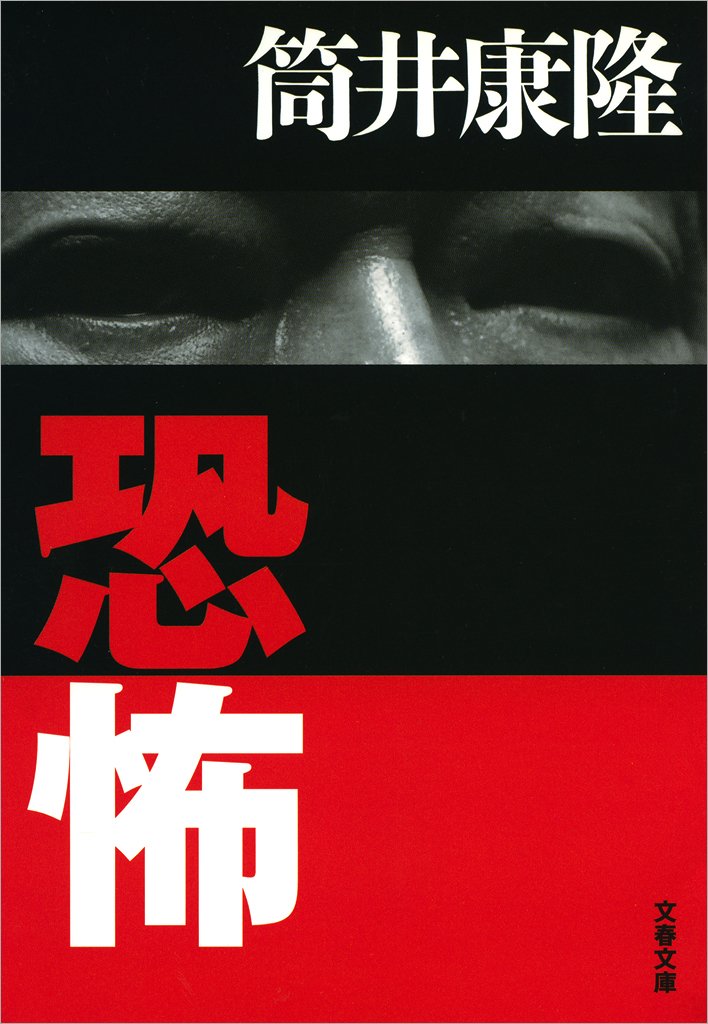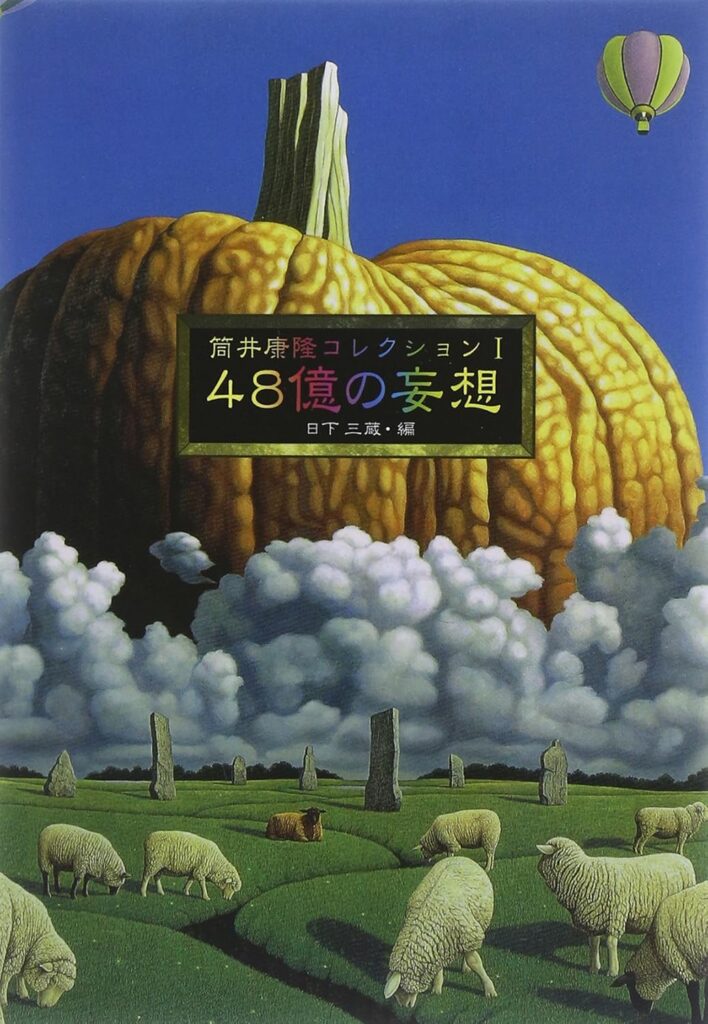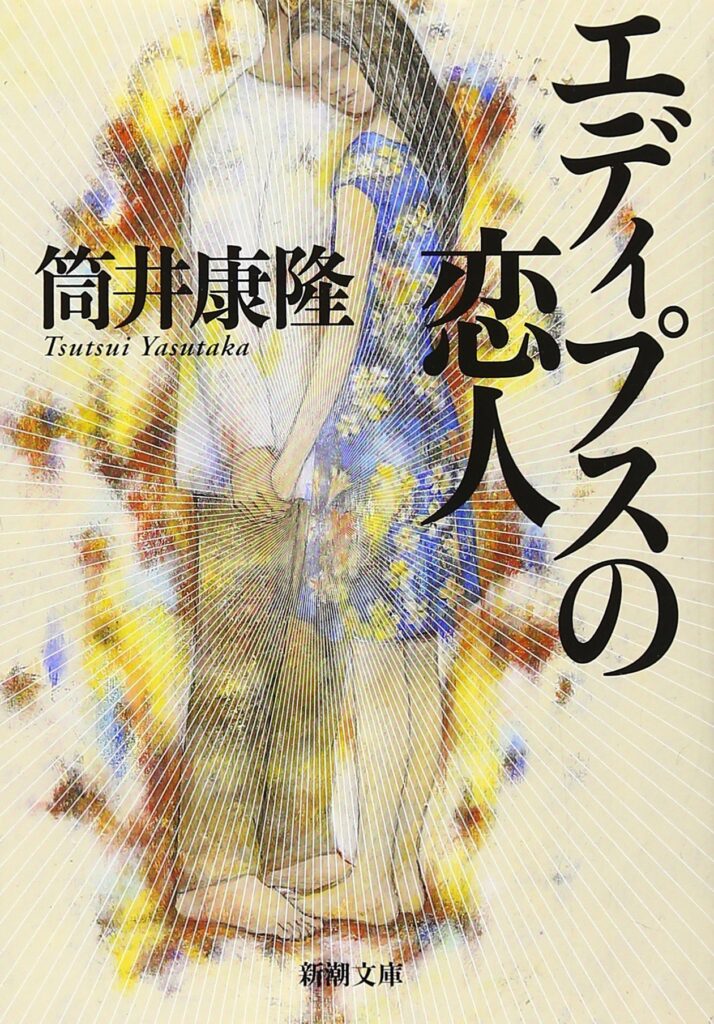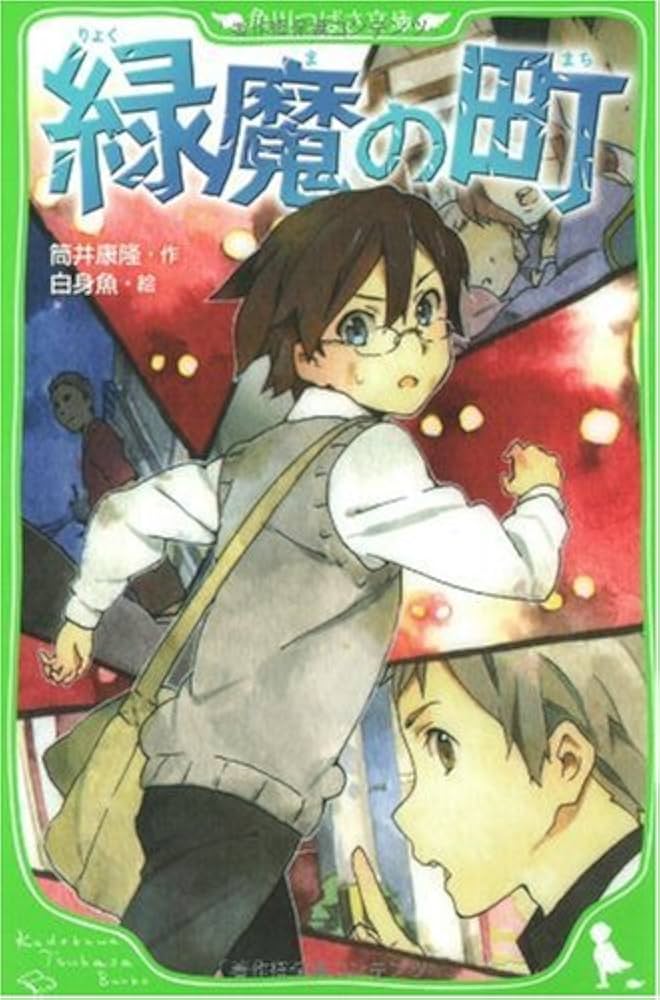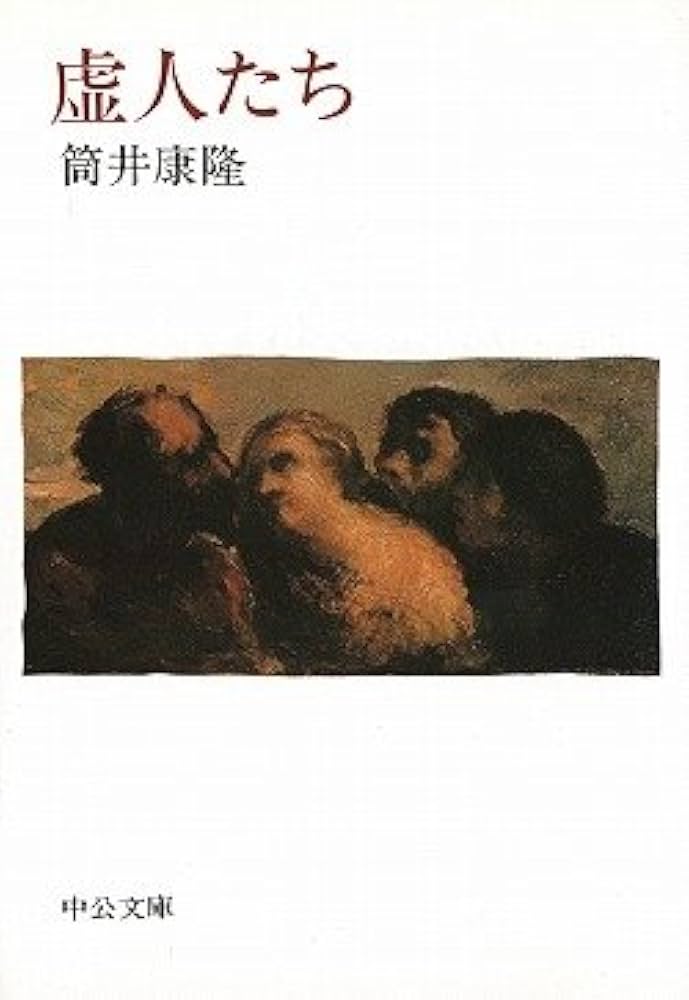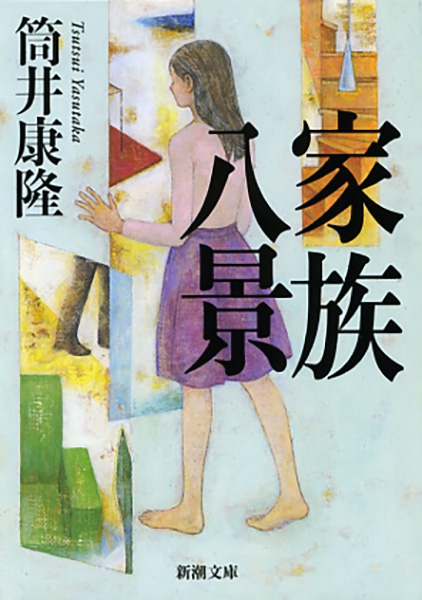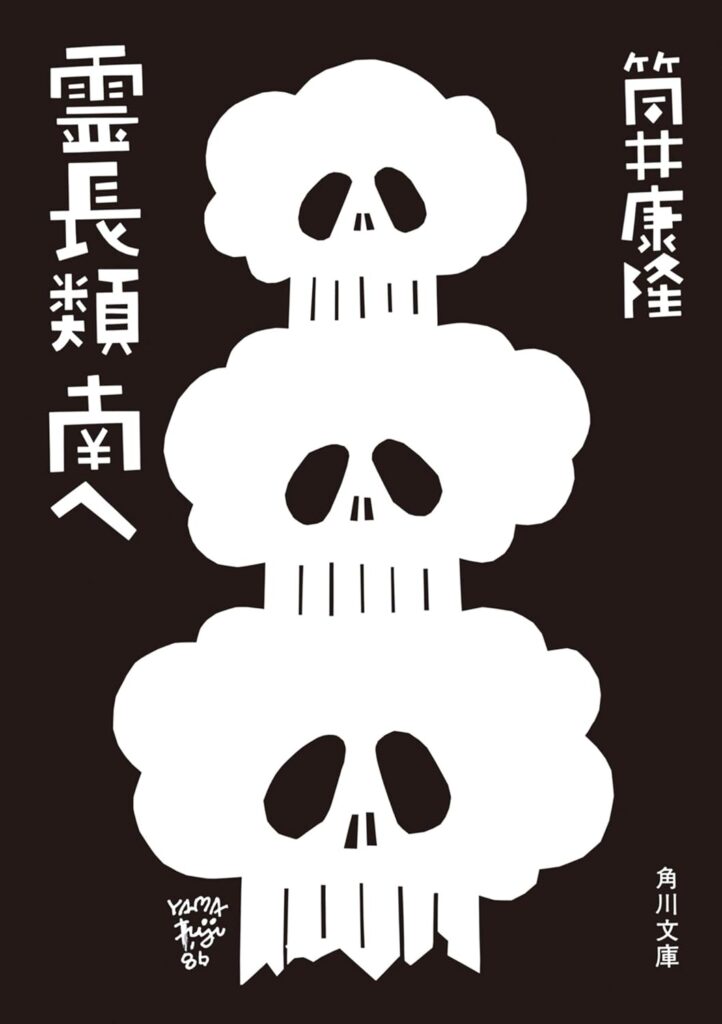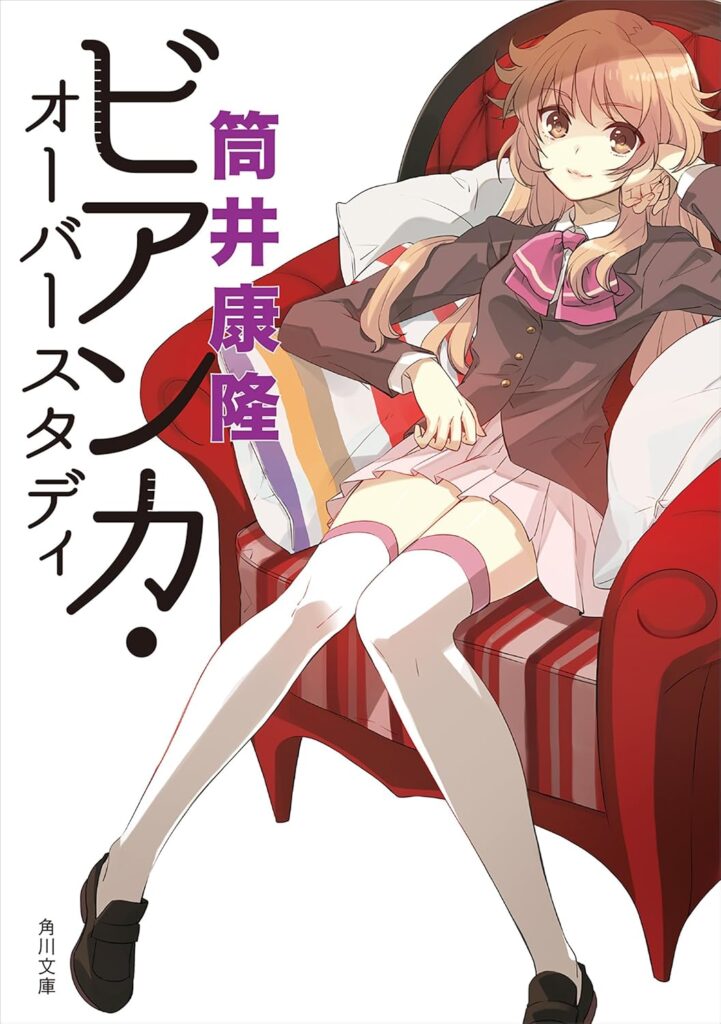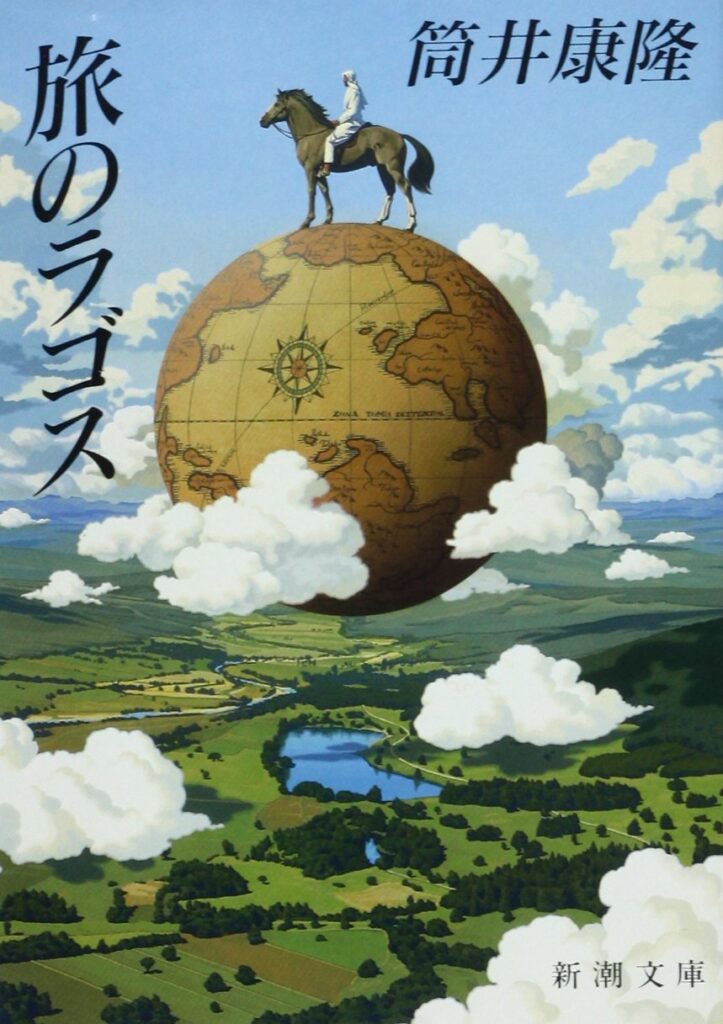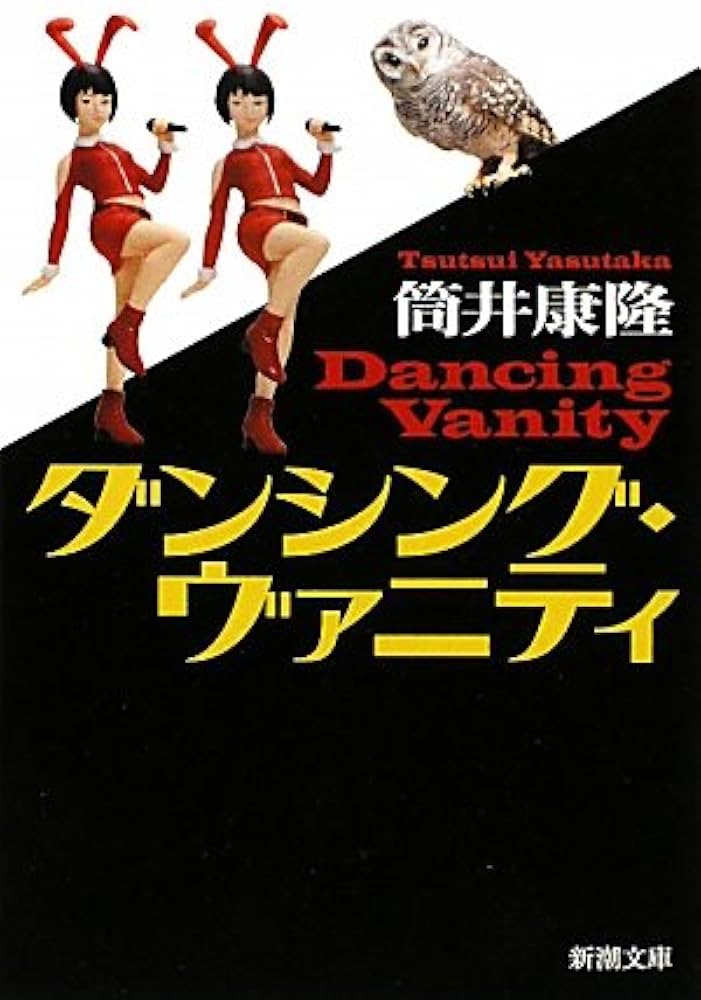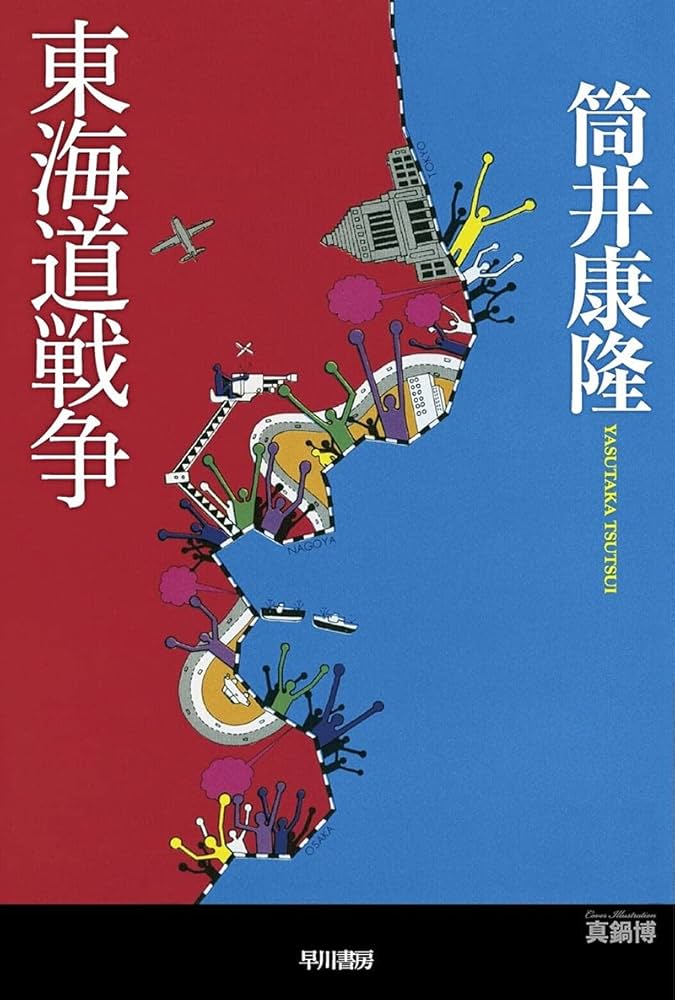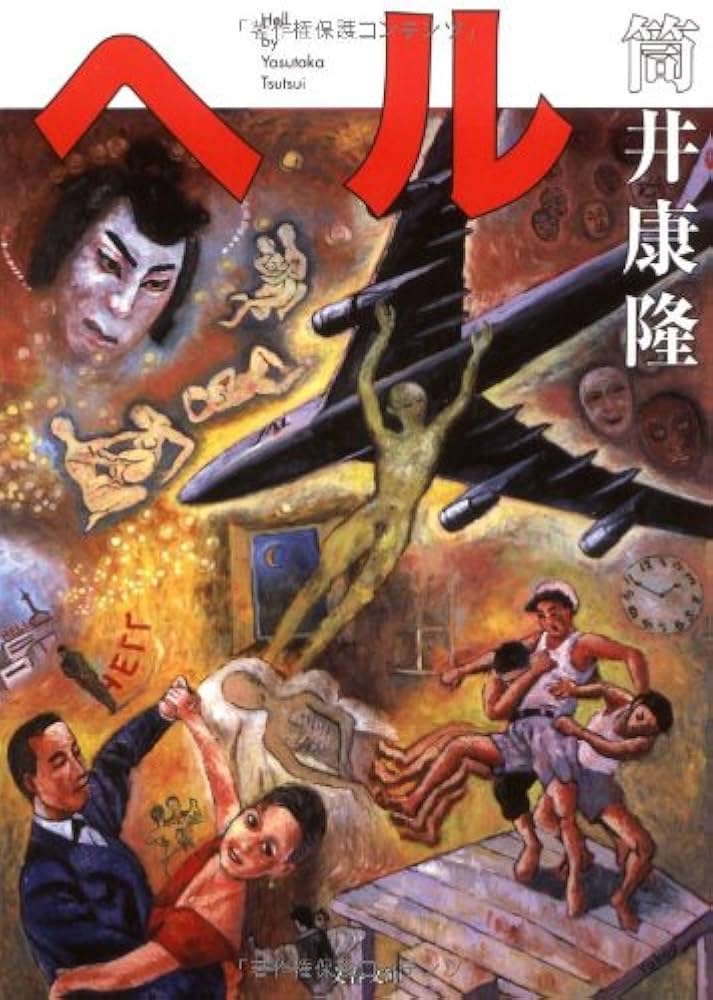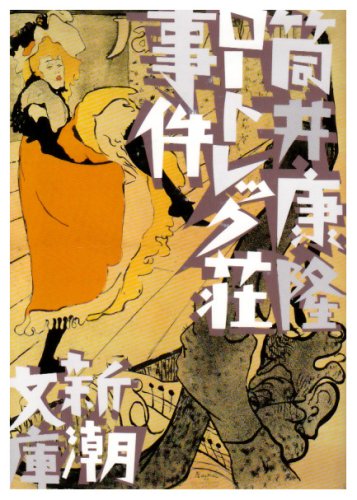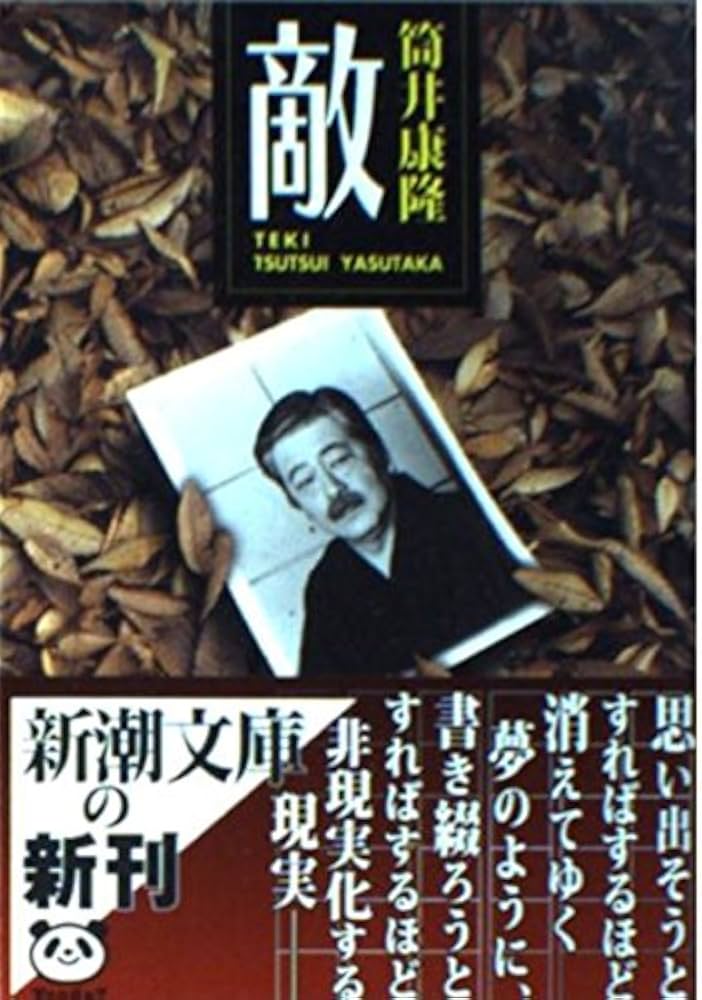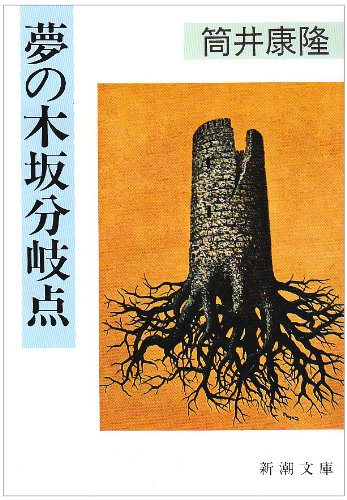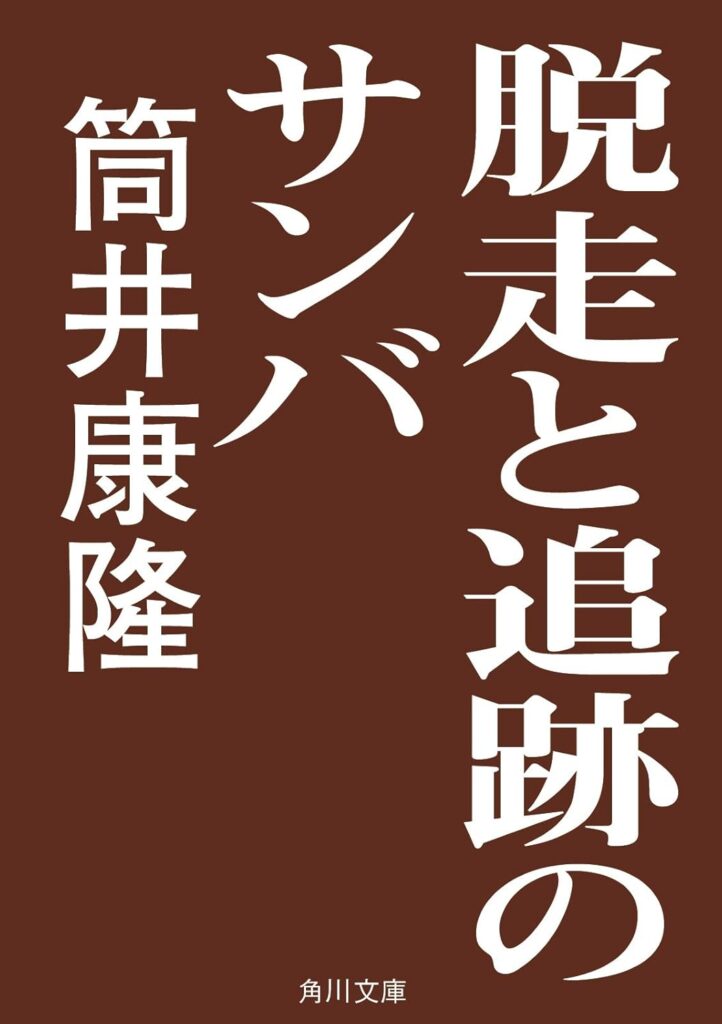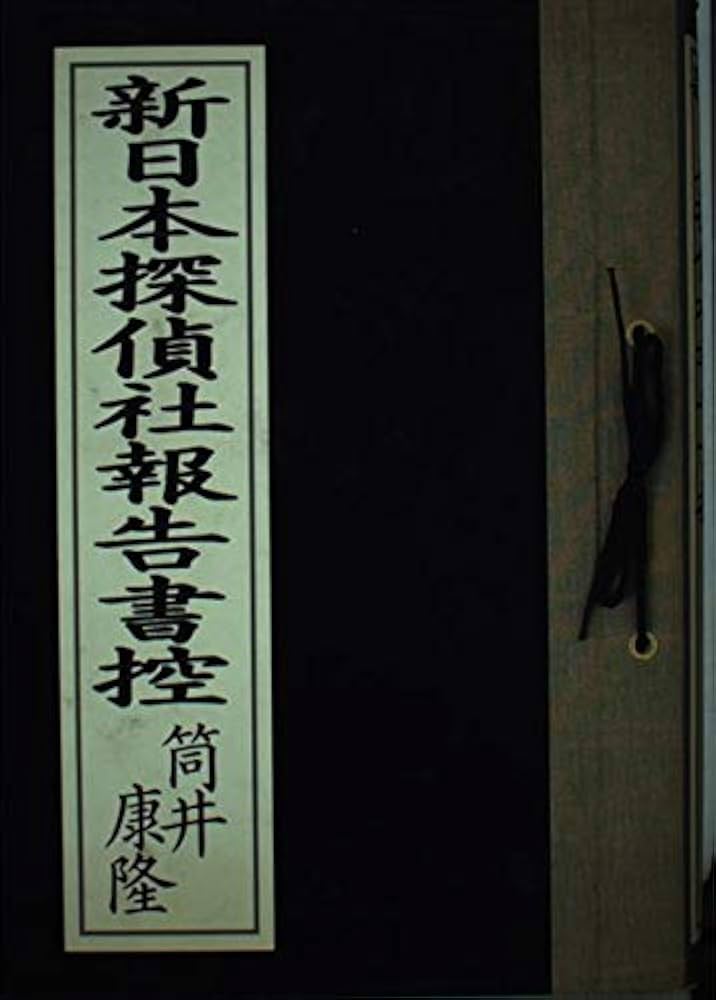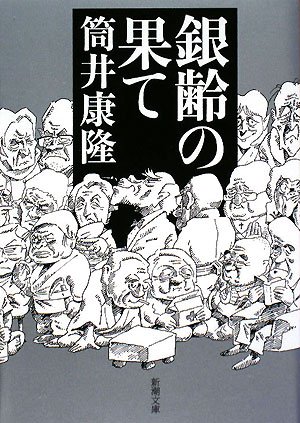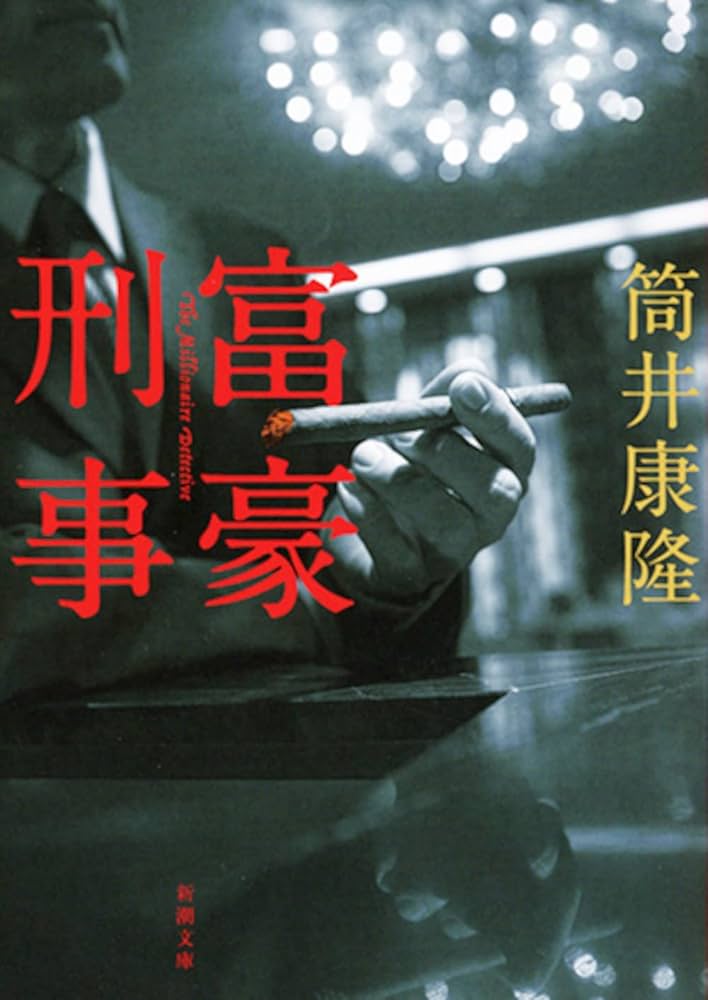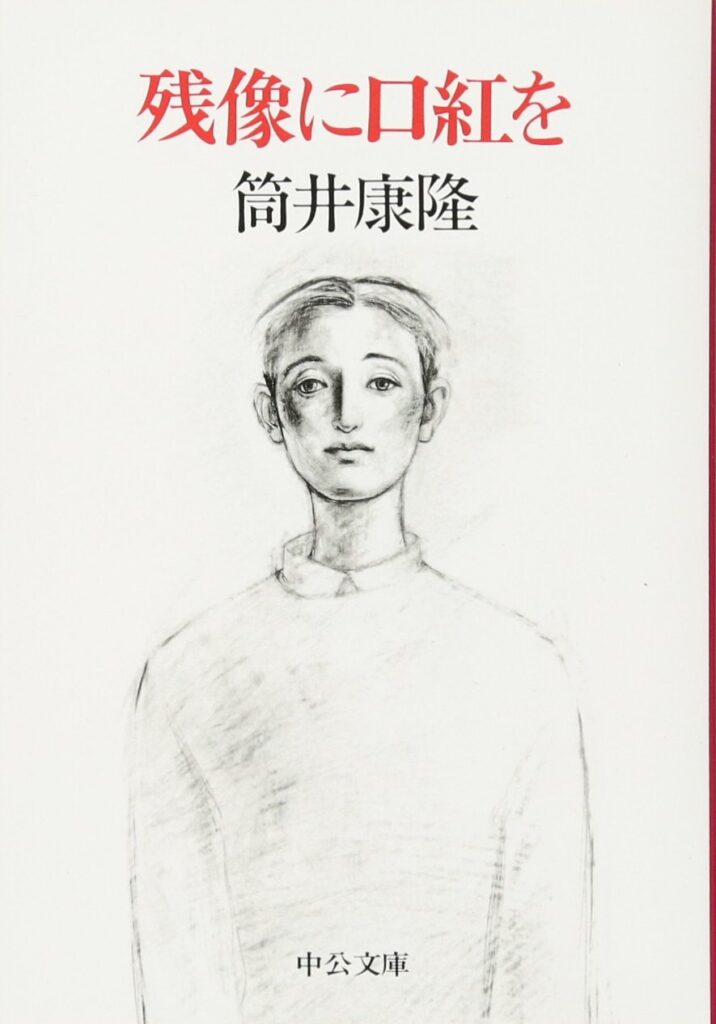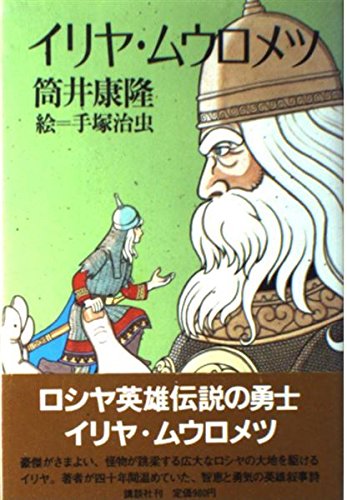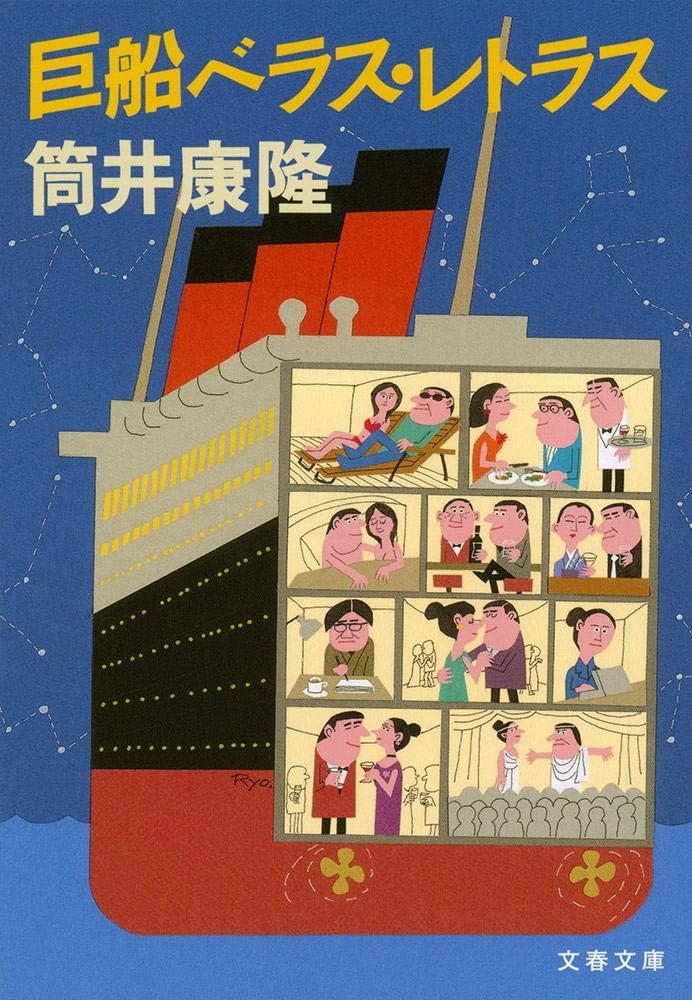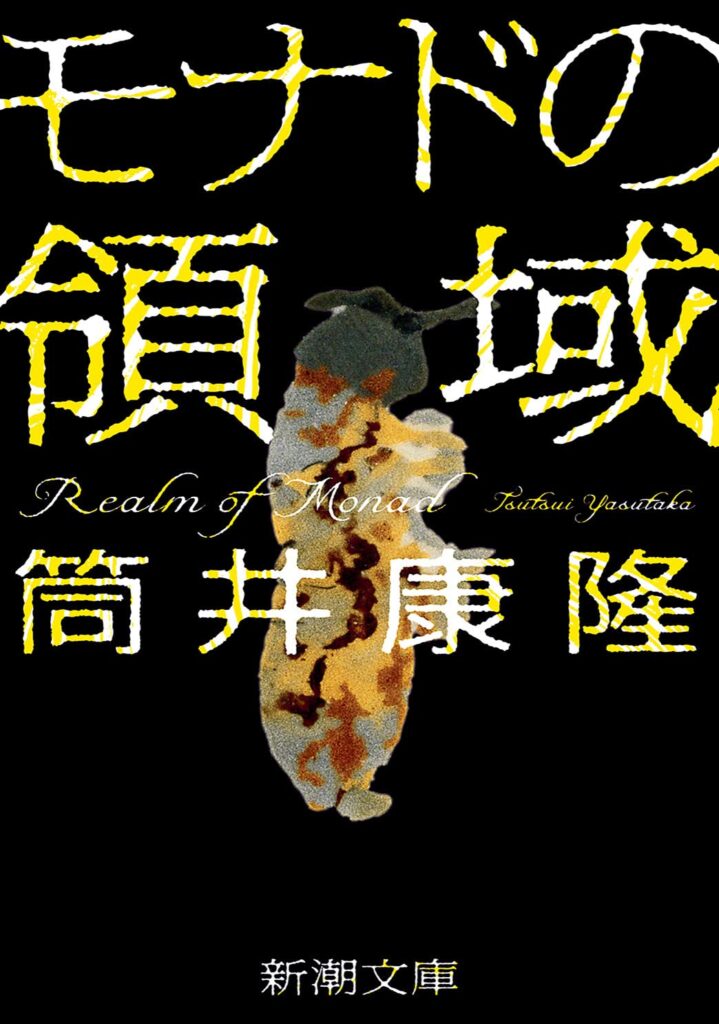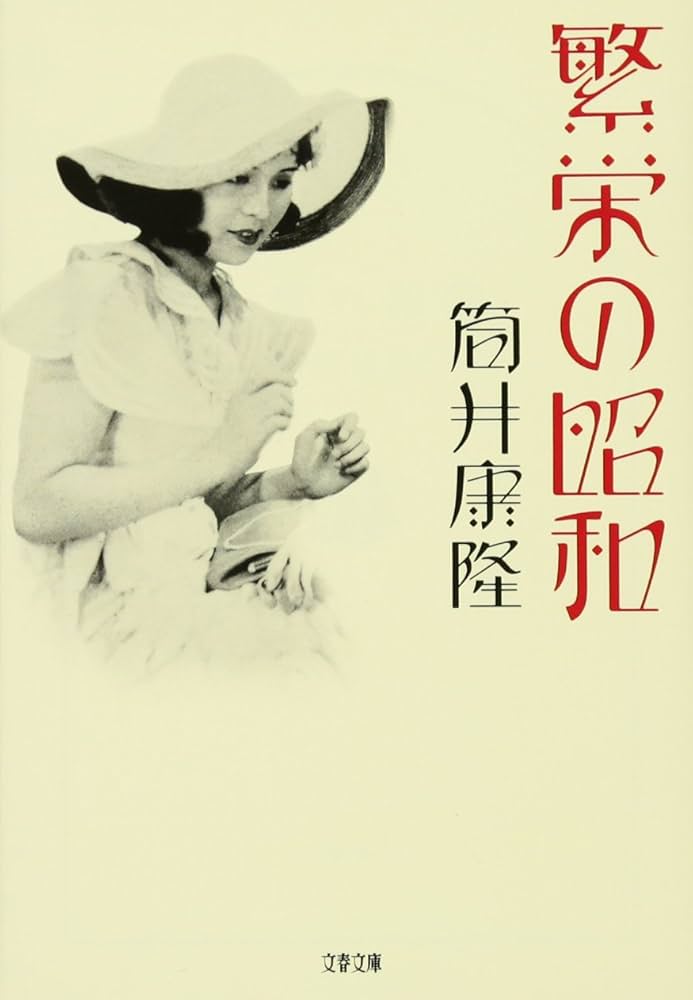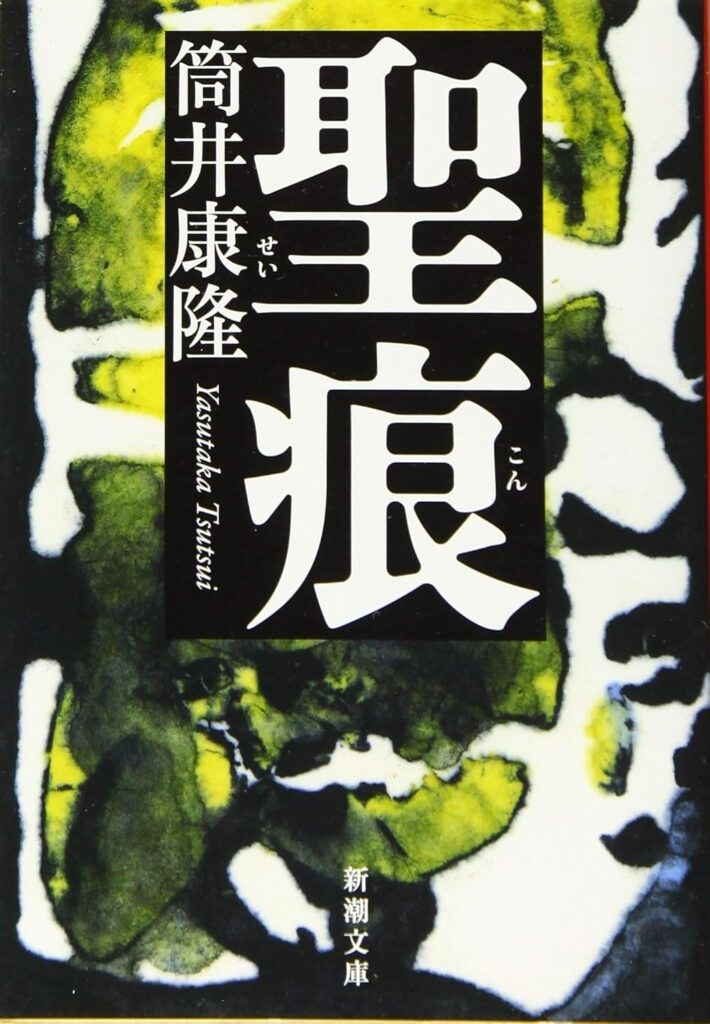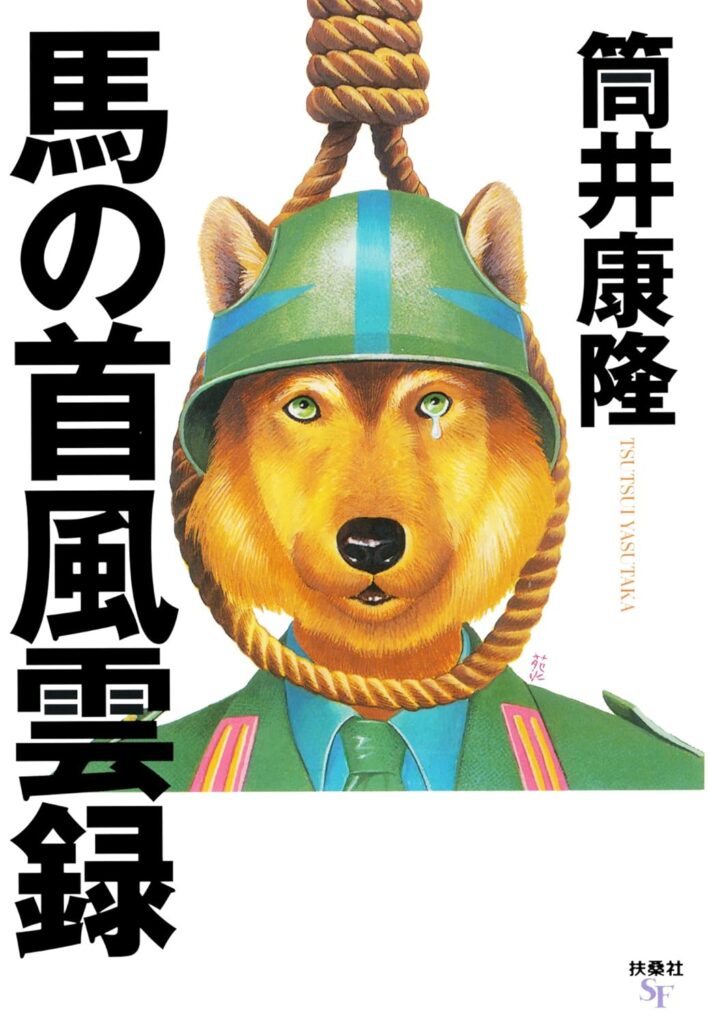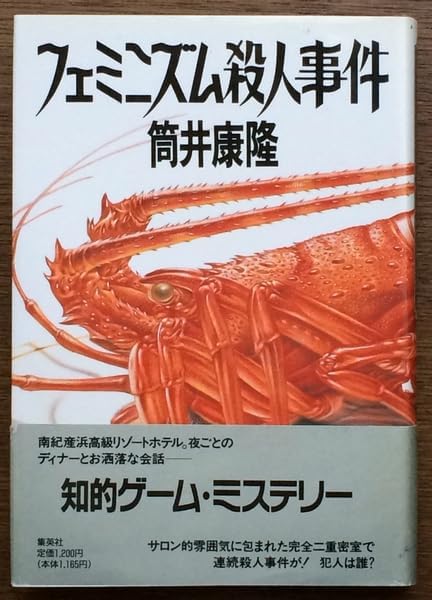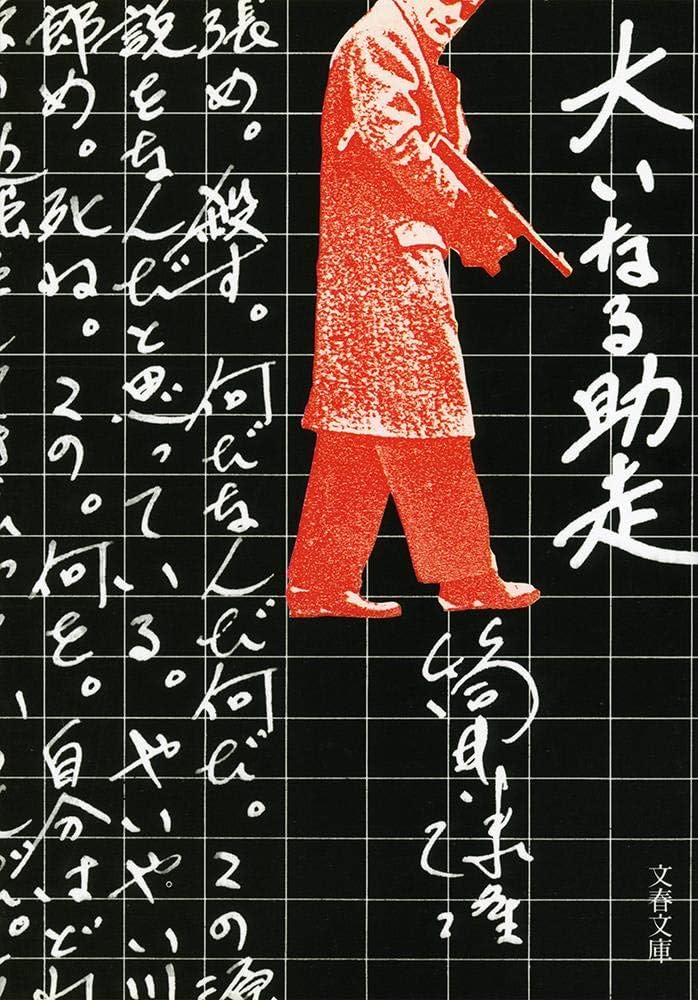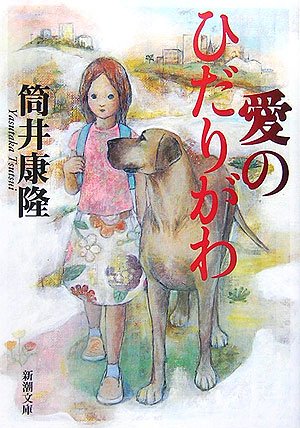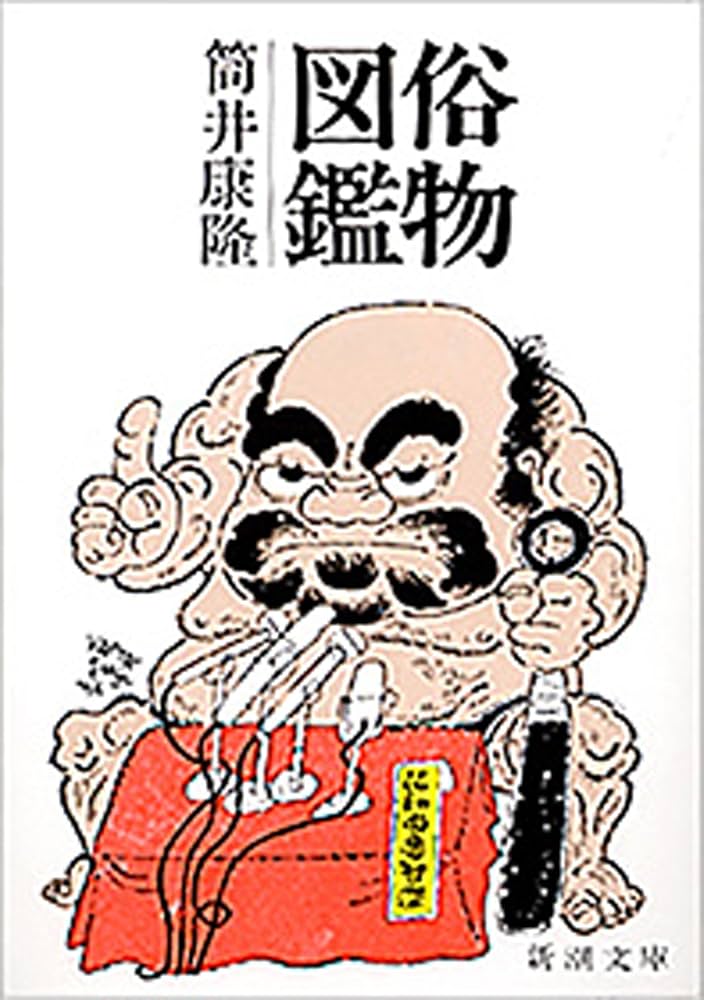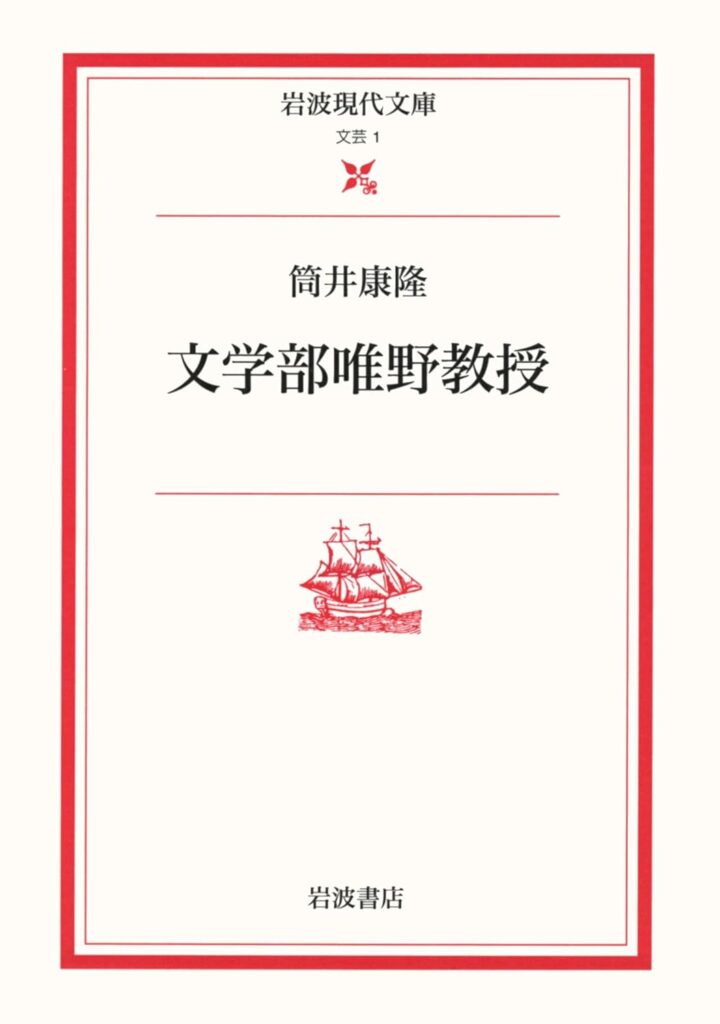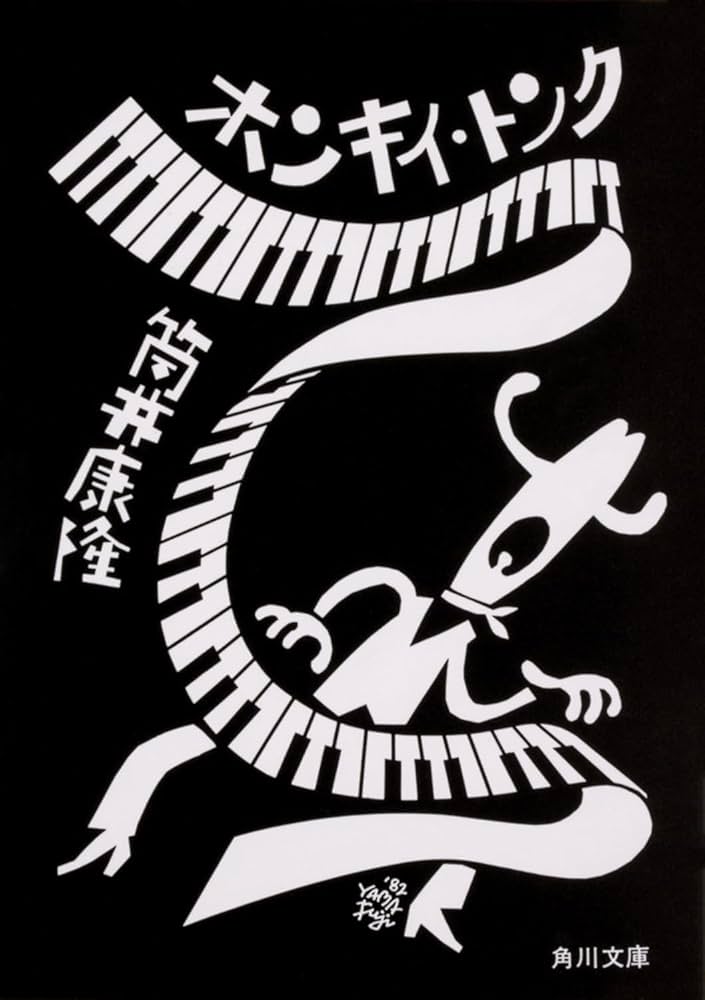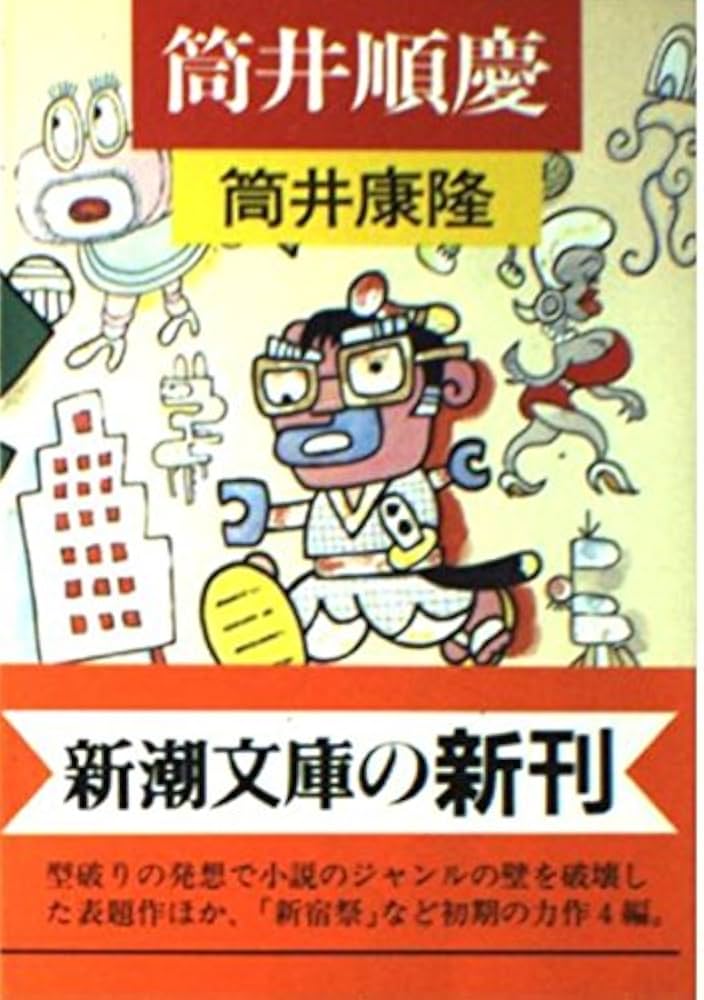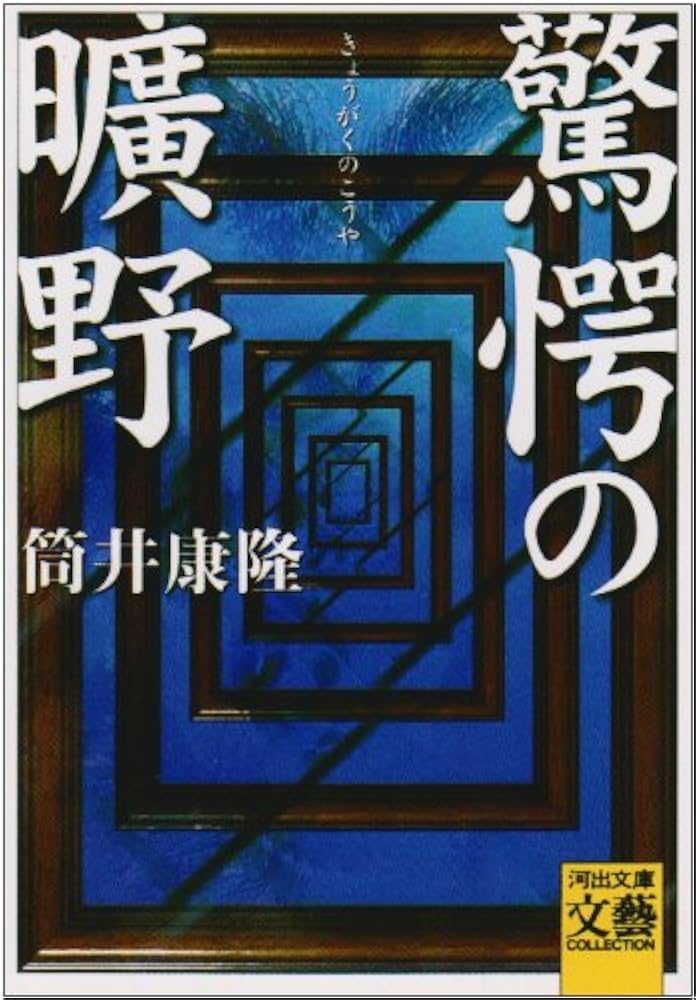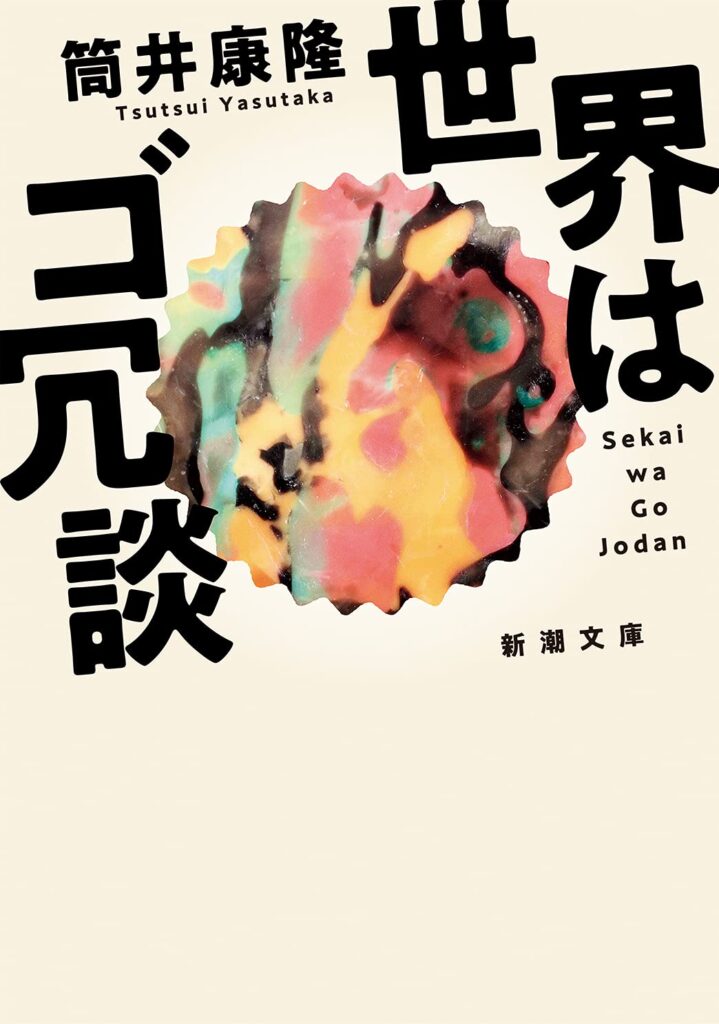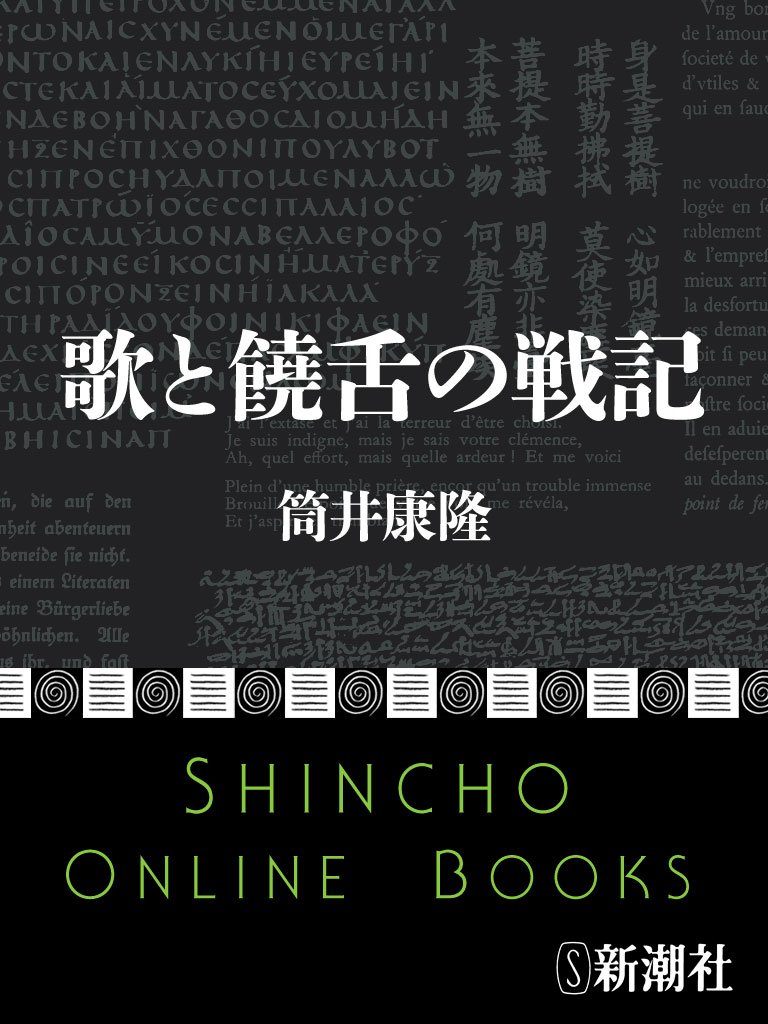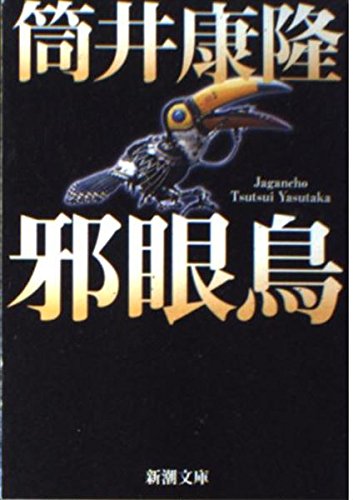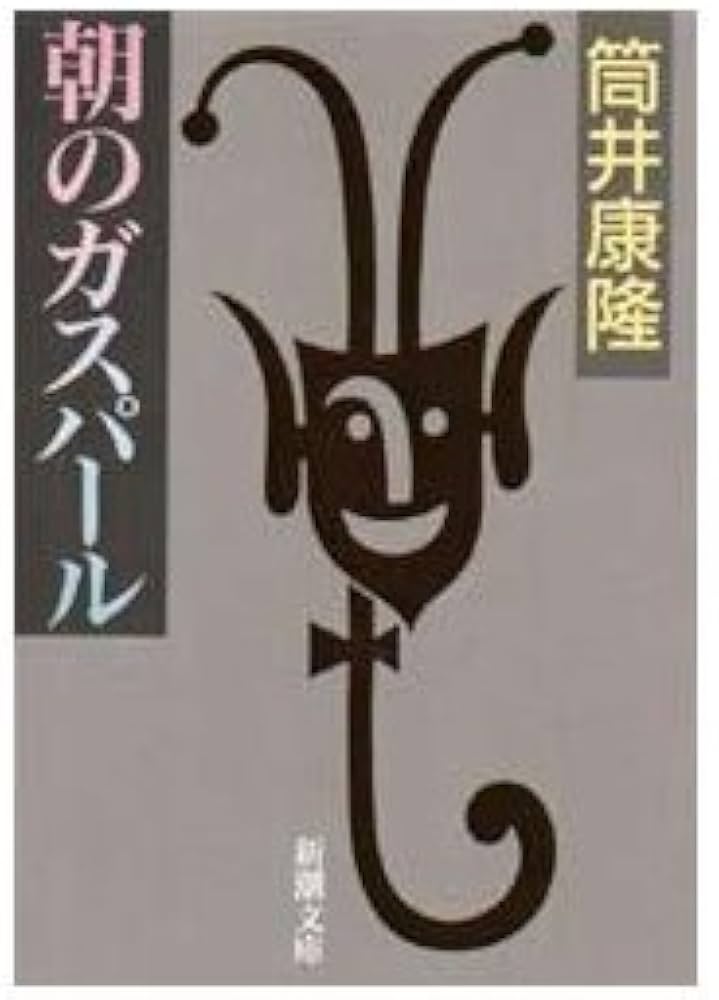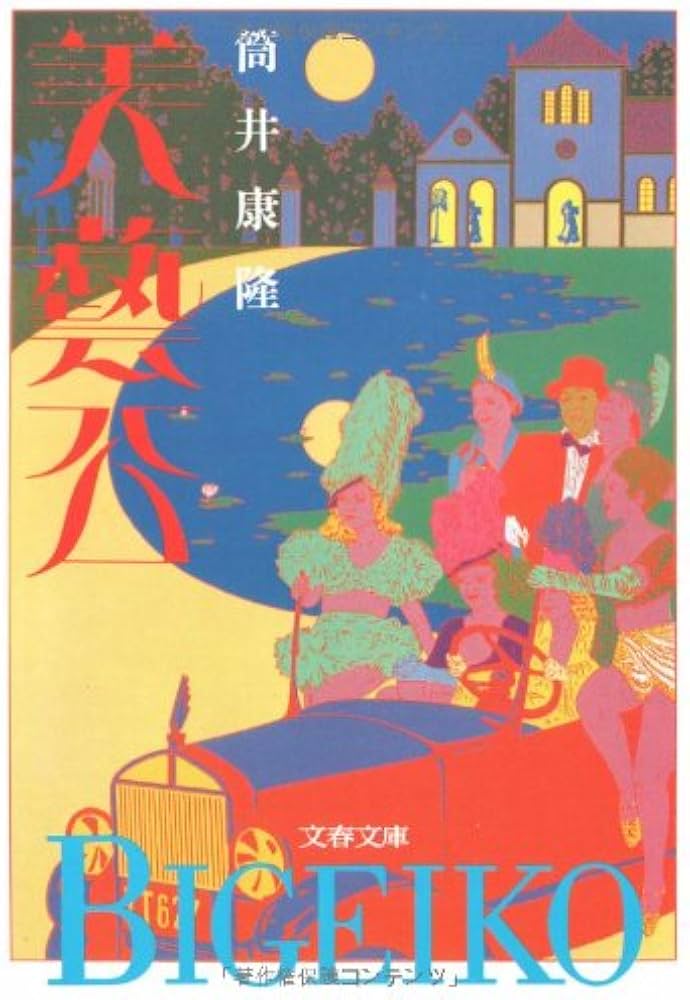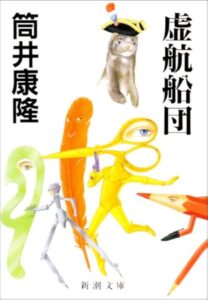 小説「虚航船団」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「虚航船団」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この作品は、日本文学における一つの巨大な事件であり、読む者を選ぶ「奇書」として知られています。一度足を踏み入れたら、その異常な世界観と実験的な仕掛けの数々に、良くも悪くも精神を揺さぶられることは間違いありません。
物語は大きく三つの章から構成されています。それぞれが全く異なる文体と視点で描かれており、読み進めるうちに何度も突き放され、そして引きずり込まれるような、不思議な感覚に陥ります。第一章では狂った文房具たちの閉鎖空間でのドラマが、第二章ではある動物たちの壮大な歴史が、そして第三章ではそれら全てが衝突し、物語そのものが崩壊していく様が描かれます。
この記事では、そんな『虚航船団』の世界を、物語の核心に触れながら、できる限り詳しく、そして私の抱いた想いを込めて語っていきたいと思います。この小説がなぜこれほどまでに人々を惹きつけ、また戸惑わせるのか。その魅力と恐ろしさの一端でもお伝えできれば幸いです。
これから語るのは、単なる物語の紹介ではありません。この途方もない航海を追体験し、その果てに何が見えるのかを探る試みです。準備はよろしいでしょうか。それでは、前人未到の文学の宇宙へ、一緒に出発しましょう。
小説「虚航船団」のあらすじ
物語の幕は、巨大な宇宙船の一室で開きます。しかし、その乗組員は人間ではありません。コンパス、消しゴム、ホチキス、糊といった、擬人化された文房具たちなのです。彼らはどこへ向かうのかも知らされず、終わりの見えない航海を続けています。その閉鎖された環境の中で、乗組員たちの精神はすり減り、ほとんどの者が何かしらの形で狂気に陥っていました。
船内では、自意識過剰で苦悩するコンパス、自分を天皇だと信じ込む消しゴム、ひたすら他者に攻撃を仕掛けるホチキスなど、個性豊かすぎる文房具たちが、それぞれの狂気を抱えながら日々を送っています。彼らの間では、些細なことから衝突が絶えず、時には殺伐とした事件にまで発展します。船というミクロコスモスの中で、秩序は崩壊寸前の状態にありました。
そんなある日、司令艦から絶対的な命令が下されます。それは、イタチ族が流刑されている惑星「クォール」を襲撃し、その住民を一人残らず殲滅せよ、というものでした。これまで目的もなく漂流していた彼らにとって、この殲滅命令は初めて与えられた「目的」となります。しかし、その目的はあまりにも暴力的で、破壊的なものでした。
狂気に満ちた文房具たちを乗せた船団は、命令に従い、惑星クォールへと進路を取ります。彼らは、これから始まるであろう殺戮の任務に、ある者は絶望し、ある者は歪んだ使命感に燃えながら、運命の星へと向かっていくのでした。この常軌を逸した遠征が、やがて宇宙と物語そのものを揺るがす大事件へと繋がっていくことになります。
小説「虚航船団」の長文感想(ネタバレあり)
『虚航船団』を読了したときの感覚を、どう表現すればよいのでしょう。それは感動や興奮といった単純な言葉では収まりきらない、もっと混沌とした、脳がぐちゃぐちゃにかき混ぜられるような体験でした。これは単なる小説ではなく、読書という行為そのものへの挑戦状であり、文学という形式を限界まで拡張しようとする、恐るべき試みであると感じました。
この作品が発表された当時、賛否両論を巻き起こしたというのも頷けます。作者自身が「読者を選ぶ」と公言しているように、物語の展開だけを追いたい読者や、感情移入しやすい主人公を求める読者は、間違いなく振り落とされてしまうでしょう。しかし、その挑発に乗り、最後まで食らいついていった者だけが見ることのできる景色が、この小説には確かに存在するのです。
まず度肝を抜かれるのが、第一章「文房具」の世界です。冒頭の「まずコンパスが登場する。彼は気がくるしていた。」という一文から、もう尋常ではありません。舞台は宇宙船、乗組員は文房具。しかも、そのほとんどが「気がくるっている」。この設定だけでも、普通の物語でないことは明らかです。
彼らの狂気は、実に多種多様です。ナルシシズムに陥る下敷き、ゲシュタルト崩壊を起こし続ける輪ゴム、性欲の塊である糊。これらの文房具たちは、私たち人間の社会にいる「ちょっと変わった人たち」のカリカチュアのようでもあります。彼らが持つ本来の「用途」が、歪んだ形で彼らの行動原理となっているのが、非常に巧みだと感じました。
この第一章で描かれるのは、閉塞した空間における人間の(この場合は文房具の)精神の崩壊です。目的も与えられず、ただ存在するだけの毎日。その虚無感が、彼らを狂気へと追いやります。これは、現代社会に生きる私たちが抱える不安や孤独感と、どこか地続きになっているように思えてなりませんでした。
そして、彼らに「イタチ族の殲滅」という命令が下される場面は、物語の大きな転換点です。目的のない虚無から、突如として与えられた破壊という目的。この皮肉な展開に、私は人間の愚かさや戦争の本質について考えさせられました。大義名分さえ与えられれば、狂気は正当化され、暴走を始める。その恐ろしさが、この荒唐無稽な設定の中から鋭く浮かび上がってくるのです。
第一章の濃密な狂気に眩暈を覚えながらページをめくると、読者は第二章「鼬族十種」で、再び大きな衝撃を受けることになります。文体が一変し、それまでの心理描写中心の物語から、まるで歴史の教科書のような無機質な文体で、惑星クォールに住むイタチ族の千年にわたる年代記が淡々と語られ始めるのです。
この唐突な転換は、多くの読者を戸惑わせたことでしょう。私も最初は「これは一体何なんだ?」と混乱しました。しかし、読み進めるうちに、このイタチ族の歴史が、私たち人類の歴史の壮大なパロディであることに気づかされます。王朝の興亡、宗教戦争、革命、そして偉大な指導者の出現。そこには、私たちが学んできた世界史の出来事が、イタチというフィルターを通して、滑稽かつ残酷に再現されていました。
特に「クズレオン・ポナクズリ」という、ナポレオンを彷彿とさせる英雄の登場には、思わず唸ってしまいました。このような遊び心の中に、歴史は繰り返すという冷徹な視線が感じられます。イタチ族は、天然の毛皮を持つために織物業が発展せず、結果として産業革命を経験しないという設定も秀逸です。
しかし、技術的な道筋が違えども、彼らが最終的に行き着くのは、核兵器による自滅的な戦争でした。この結末は、文明の進歩とは何か、そして知的生命体に内在する自己破壊衝動について、重い問いを投げかけます。どんなに文化が発展し、歴史を積み重ねても、結局は同じ過ちを繰り返してしまうのか。そのやるせない思いが胸に迫りました。
そして第三章「神話」。ここに至って、物語は制御不能の領域へと突入します。文房具船団と、核戦争で既に壊滅状態にあったイタチ族の生き残りとの間で、混沌とした戦争が始まります。この章の凄まじさは、その内容もさることながら、文章表現そのものにあります。
句読点が消え、段落の区切りもなくなり、紙面を埋め尽くす言葉の洪水。視点はめまぐるしく入れ替わり、時間軸もバラバラになります。これはまさに、戦争の混乱と狂気を、読者に追体験させるための仕掛けなのでしょう。私は文字を目で追いながら、本当に戦場に放り込まれたかのような疲労感と眩暈を感じました。
この実験的な文章は、単なる奇をてらったものではありません。物語の秩序が崩壊していく様を、文章の構造そのもので表現しているのです。もはや、客観的な視点から物語を眺めることは許されません。読者はこの混沌の中に叩き込まれ、物語と共に崩壊していくしかないのです。
さらに驚くべきことに、この最終章では、作者である筒井康隆氏自身が物語に介入してきます。執筆中の出来事や自身の愚痴などが、作中の戦争の描写とシームレスに混ざり合っていくのです。フィクションと現実の境界線が溶解し、何が物語で何が現実なのか、全く分からなくなってしまいます。
これは、メタフィクションという手法の極致と言えるでしょう。「書く」という行為そのものが、物語の最終的なテーマとして立ち現れてきます。消しゴムというキャラクターが、読者が読んでいる文章を消してしまうという描写に至っては、もはや笑うしかありません。私たちは、作者の手の上で転がされているだけでなく、その創作の現場にまで立ち会わされているのです。
物語の登場人物たちは、この混沌の果てに、次々と無残な最期を遂げていきます。あれだけ個性的だった文房具たちも、戦争という巨大な暴力の前では為すすべもなく消えていく。その様は、まさに「殺戮者たちの末路ははかなない」という言葉通りであり、虚しさが募ります。
しかし、この物語は完全な絶望では終わりません。全てが破壊され尽くしたかに思われた灰の中から、一つの奇跡が生まれます。それは、文房具であるコンパスと、イタチ族の生き残りとの間に生まれた、混血の子供です。このありえない生命の誕生は、暗闇の中に灯る、本当に小さな希望の光のように感じられました。
そして、物語は、その子供が呟く「これから夢を見る」という一言で幕を閉じるのです。この最後の言葉が、私の心に深く、そして長く響き渡りました。この「夢」とは一体何なのでしょうか。それは、新たな物語の始まりを意味するのか。それとも、この絶望的な世界を解釈し、意味づけるという、生命の根源的な営みを指すのでしょうか。
この『虚航船団』という小説は、物語を読むという行為の意味を根底から問い直す作品でした。あらすじをなぞるだけでは、この作品の価値は決して理解できません。狂った文房具たちに眩暈を覚え、イタチの歴史に呆れ、言葉の洪水に溺れそうになりながら、この航海を最後までやり遂げたとき、初めて見えてくるものがあります。それは、文学の持つ無限の可能性と、虚構を紡ぎ出すことの業の深さ、そしてその尊さなのかもしれません。万人には決してお勧めできませんが、もしあなたが文学の最果てを見てみたいと願うなら、この船に乗り込む価値は十分にあります。
まとめ
この記事では、筒井康隆氏の傑作にして問題作、『虚航船団』の核心に迫るべく、その物語の筋道と私なりの解釈を綴ってきました。この作品は、単に物語を楽しむというより、その特異な構造と文体を「体験」することにこそ真の価値がある、類い稀な小説だと言えるでしょう。
第一章の狂った文房具たちの閉鎖空間、第二章の壮大にして皮肉なイタチ族の歴史、そして第三章の物語自体の崩壊と作者の介入。これらの目まぐるしい展開は、読者を絶えず揺さぶり、安易な理解を拒絶します。しかし、その挑発的な仕掛けの数々こそが、本作を唯一無二の存在たらしめているのです。
ネタバレを読んで物語の結末を知ったとしても、この小説の衝撃が色褪せることはありません。なぜなら、この作品の本当の面白さは、その混沌とした世界を自らの精神で渡り歩き、言葉の迷宮に迷い込み、そしてそこから何かを見つけ出すという、読書体験そのものにあるからです。
もしあなたが、これまでの読書体験を覆すような、強烈な一冊を求めているのであれば、『虚航船団』はまさにうってつけの作品です。覚悟を持ってページを開いてみてください。その先には、あなたの文学観を根底から揺るがすような、忘れがたい航海が待っているはずです。