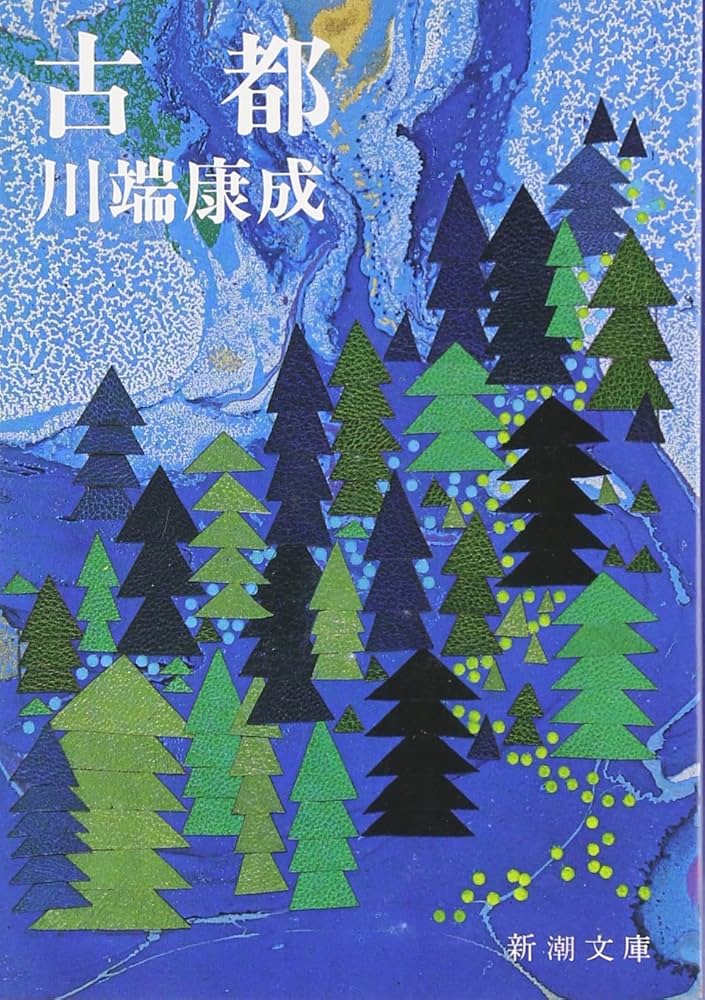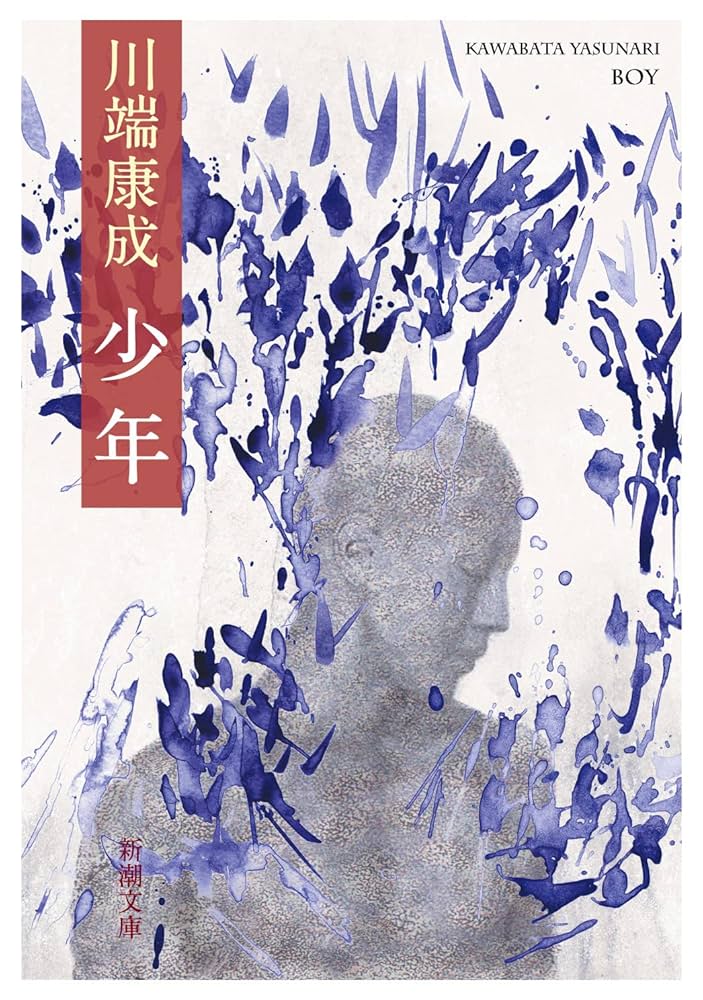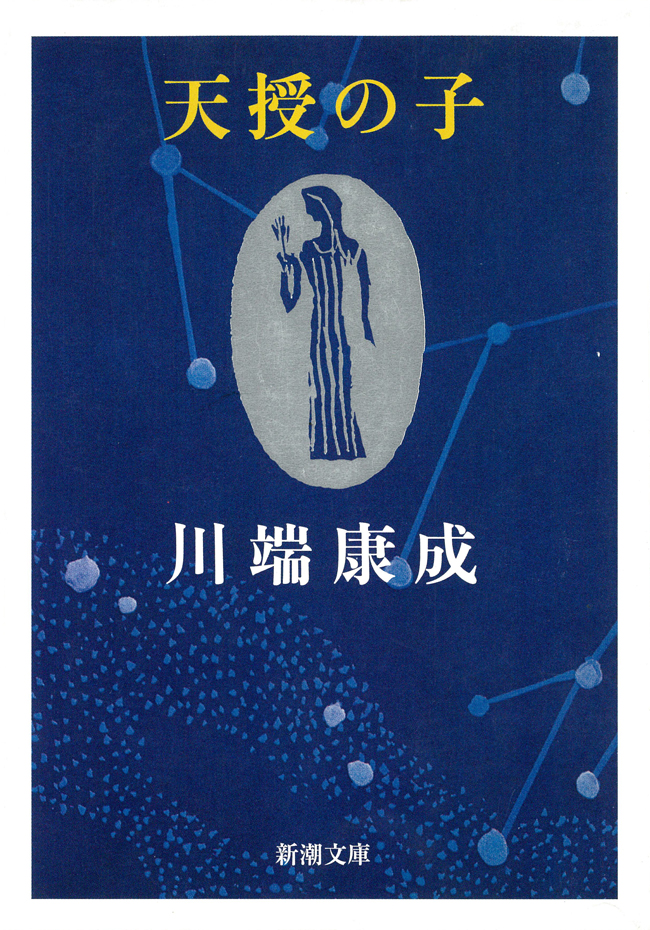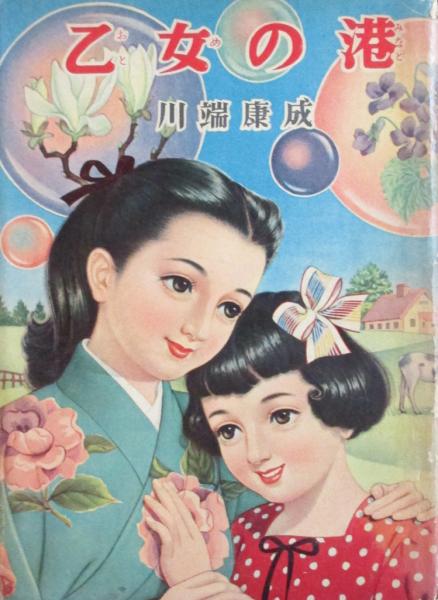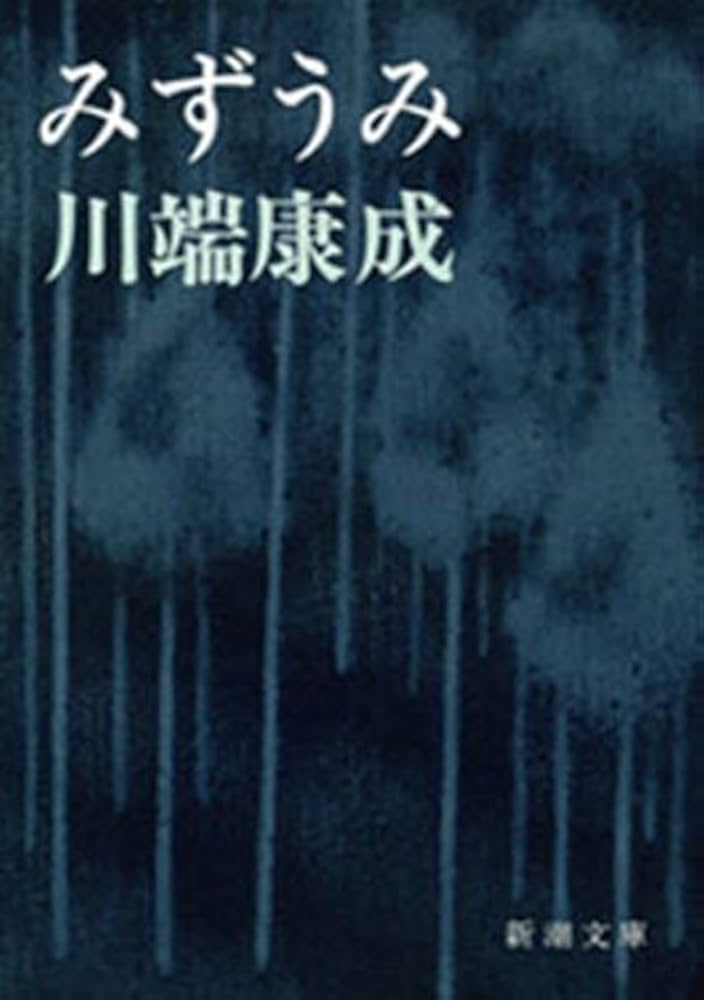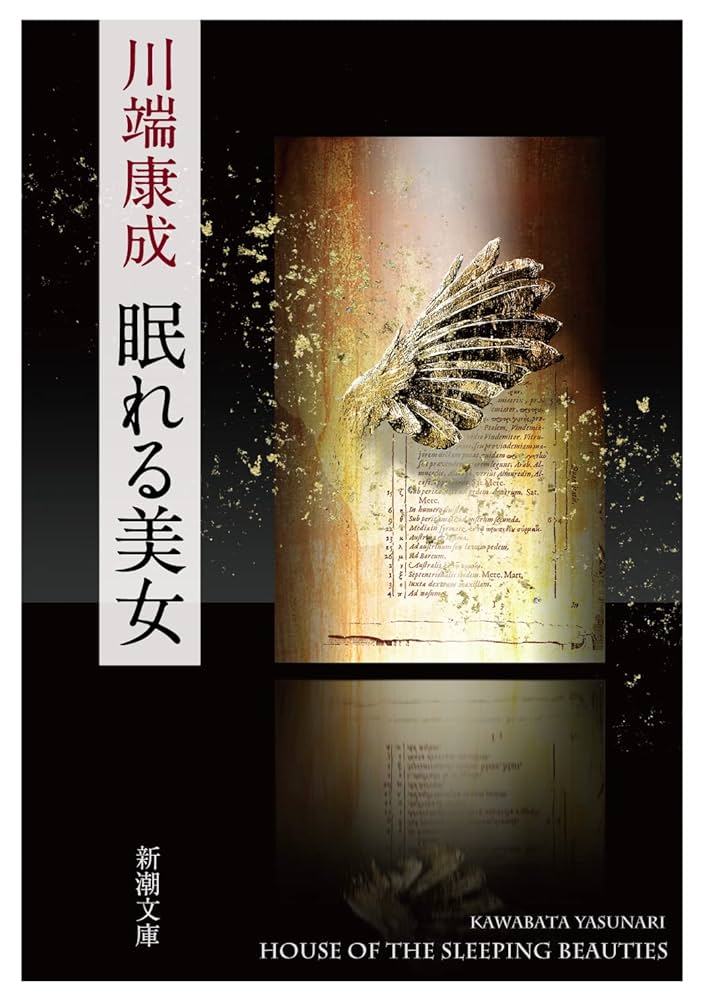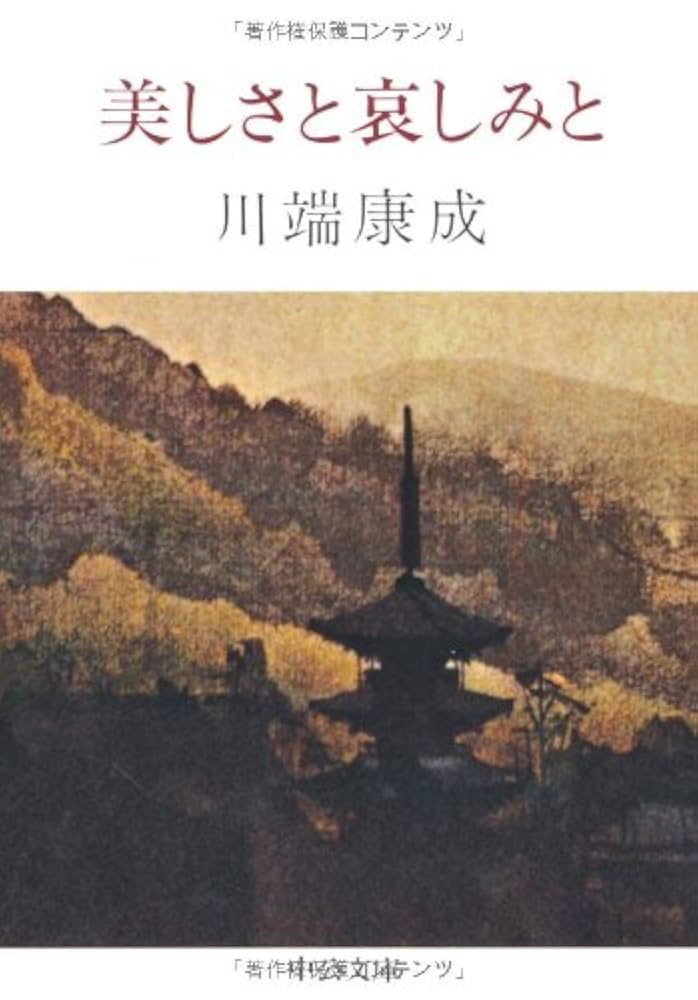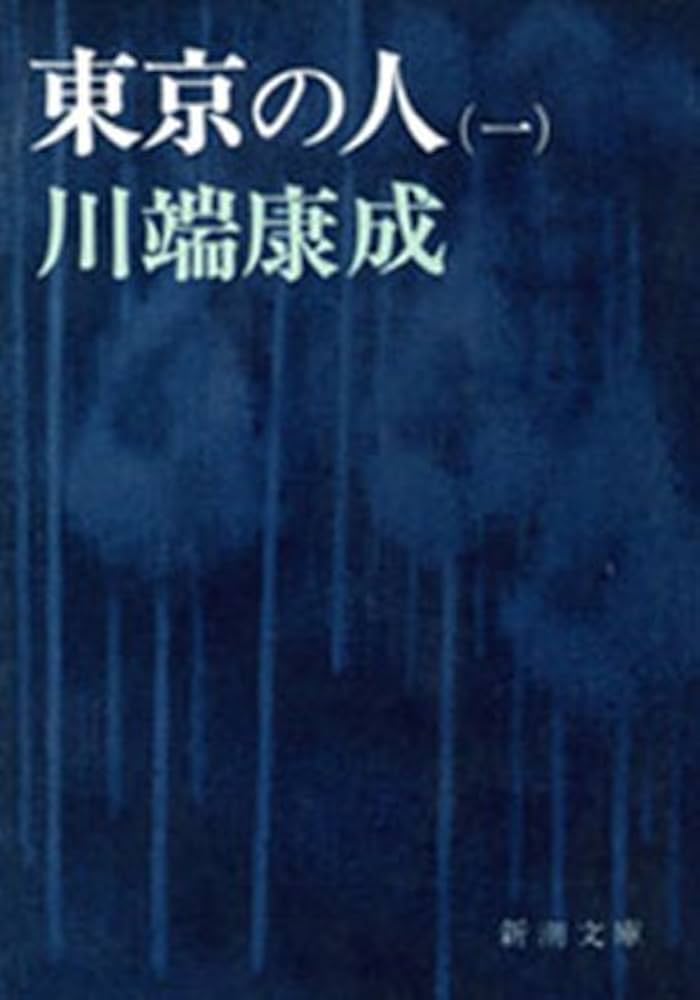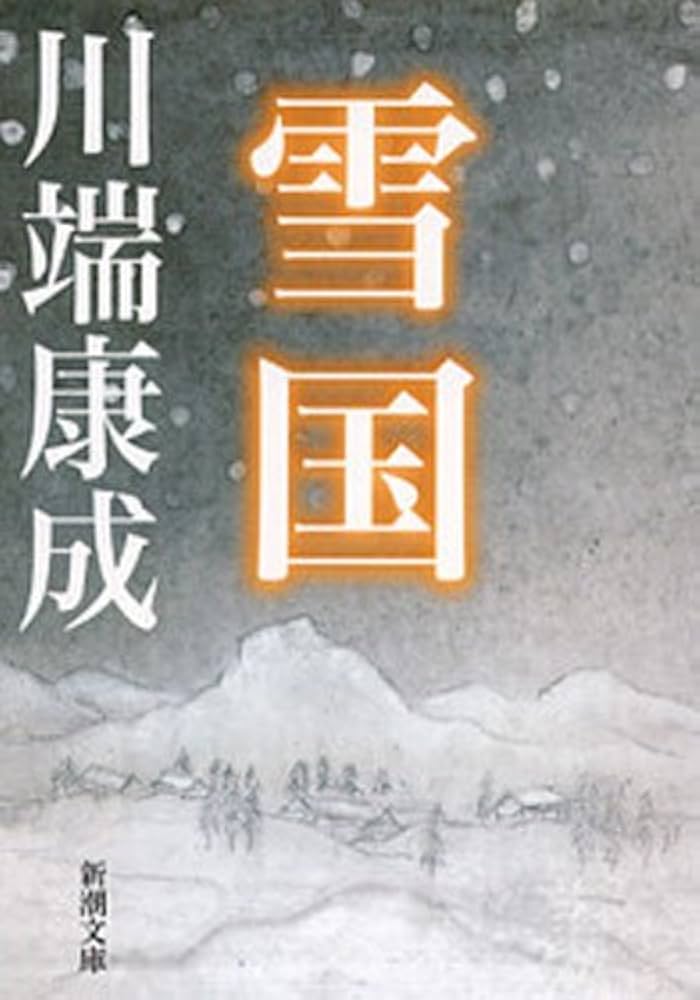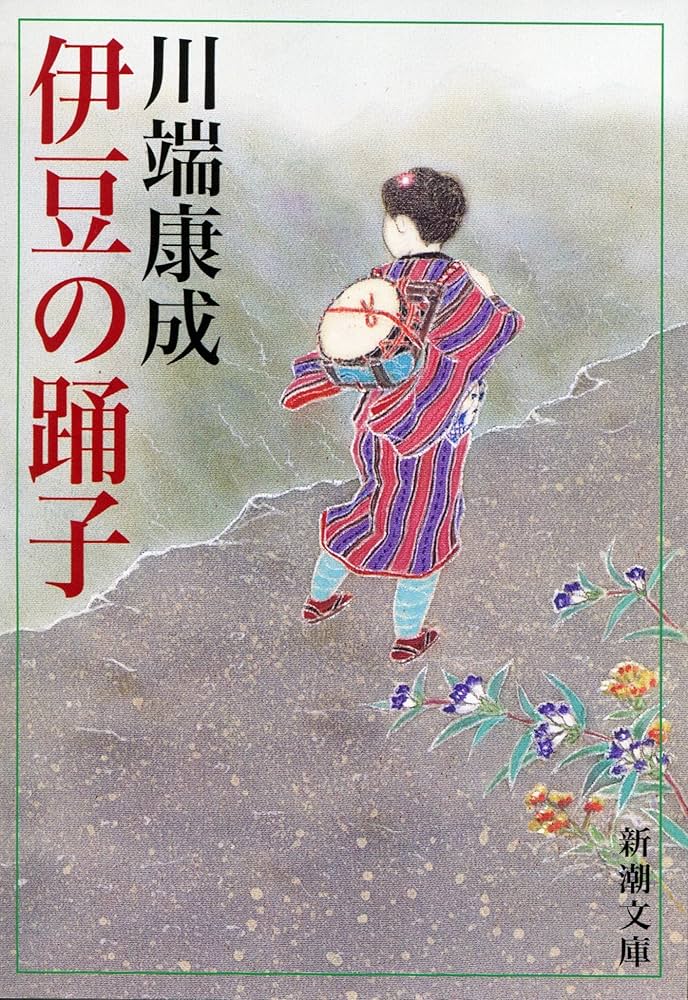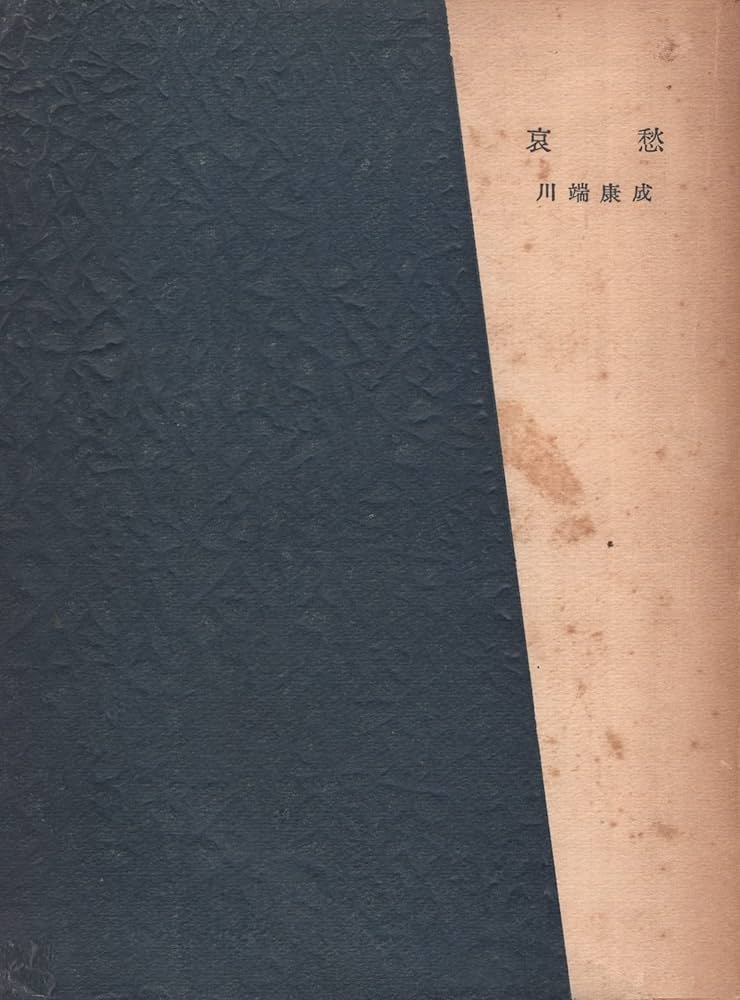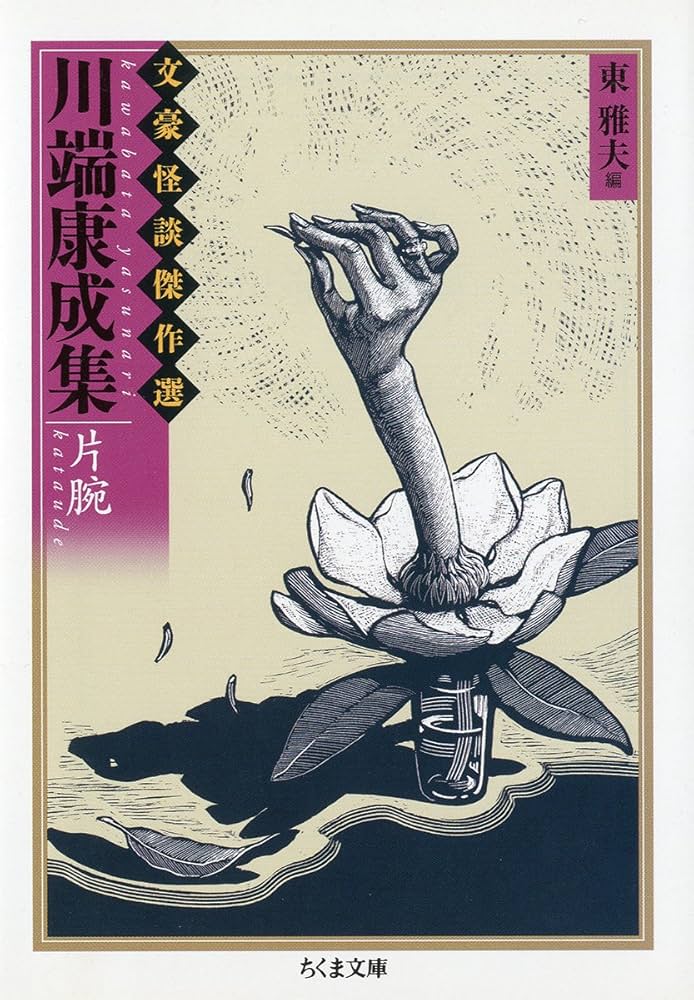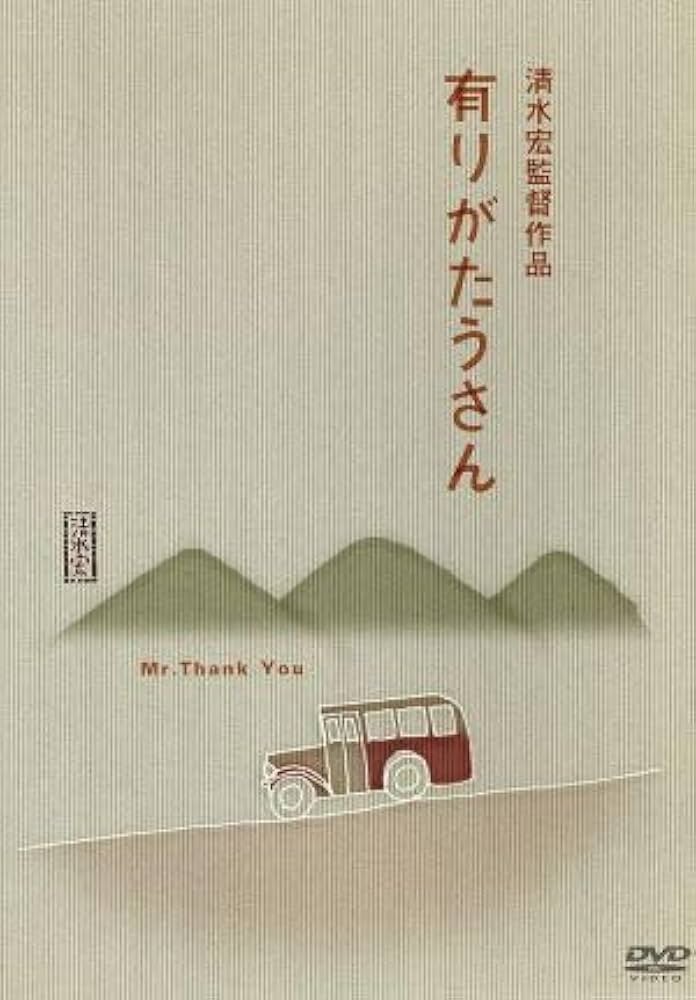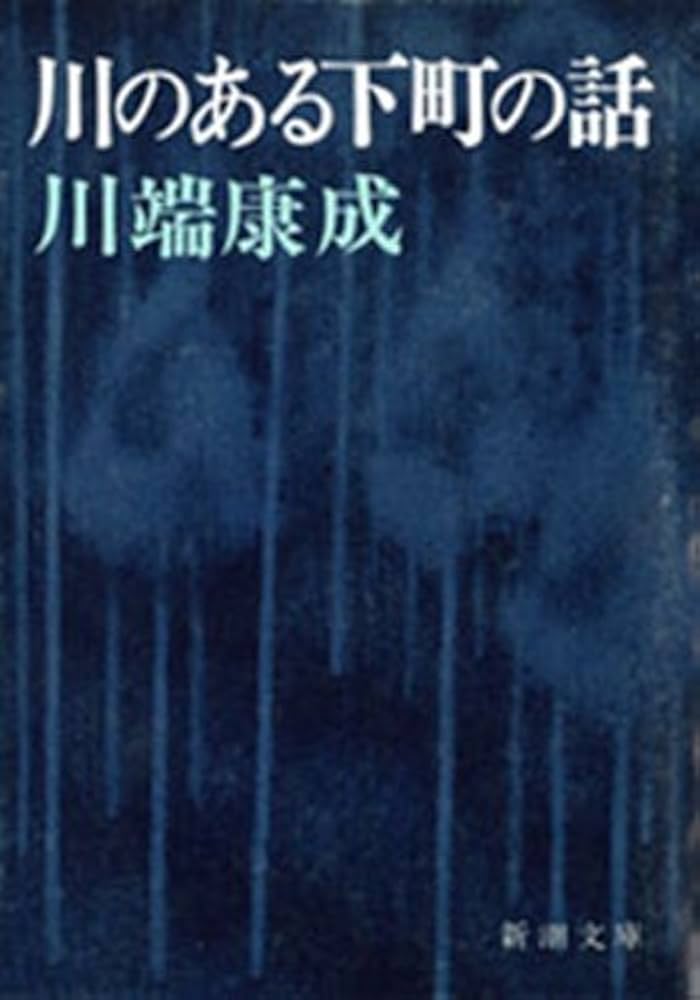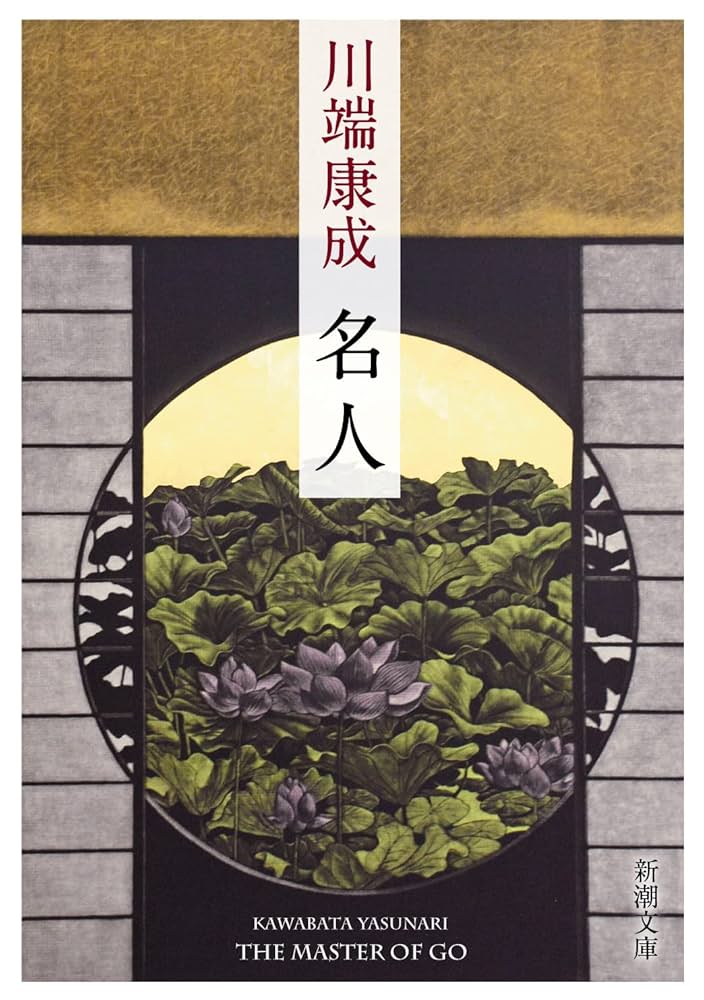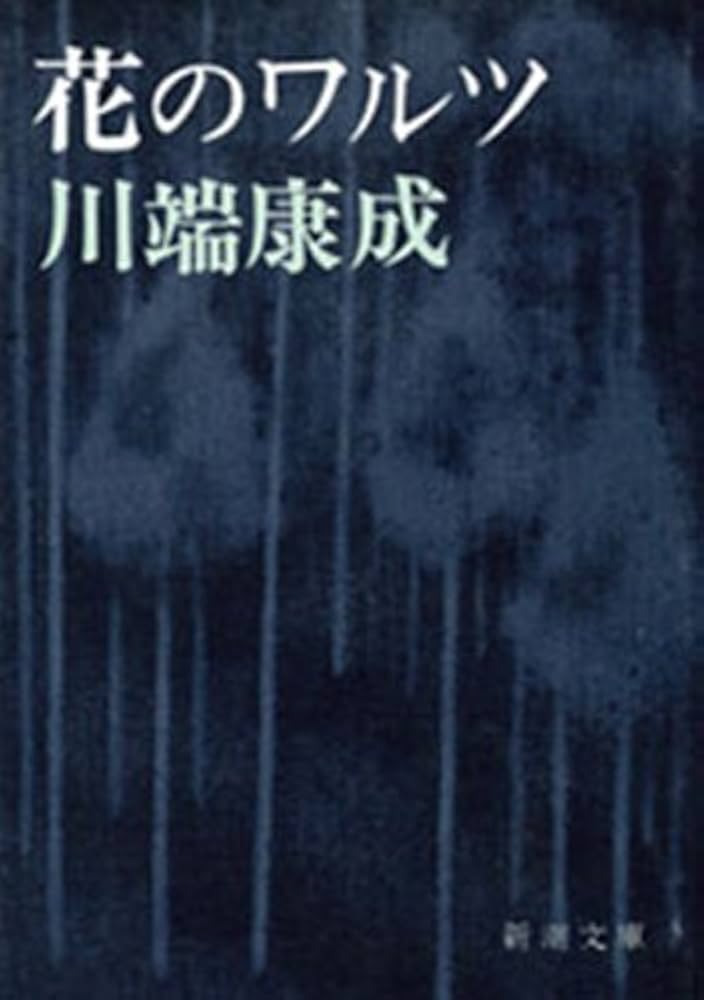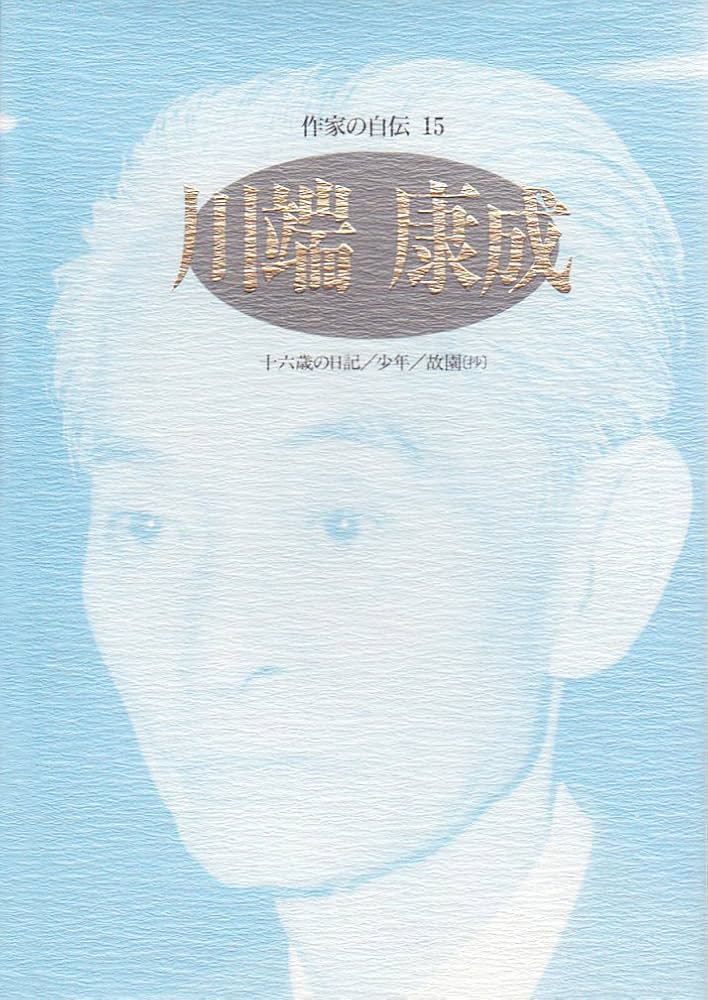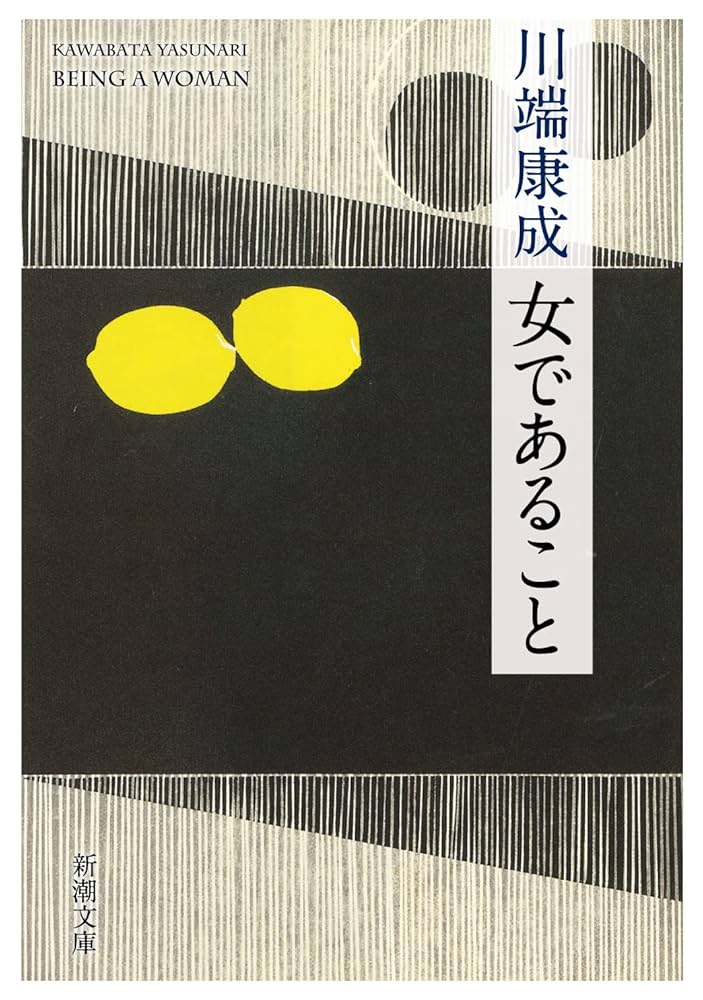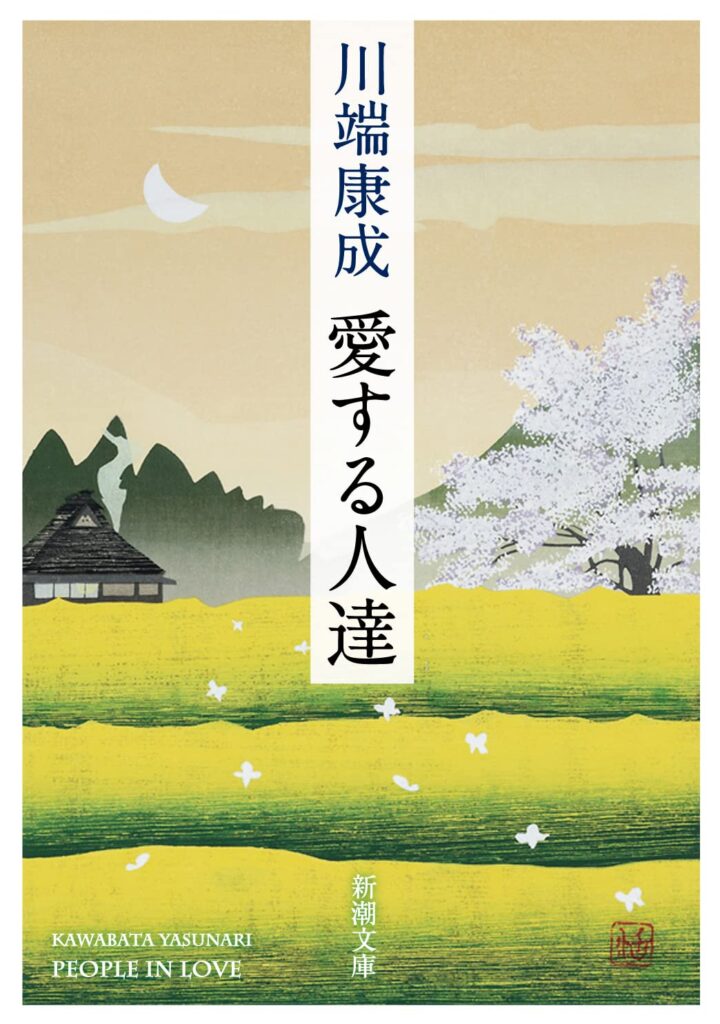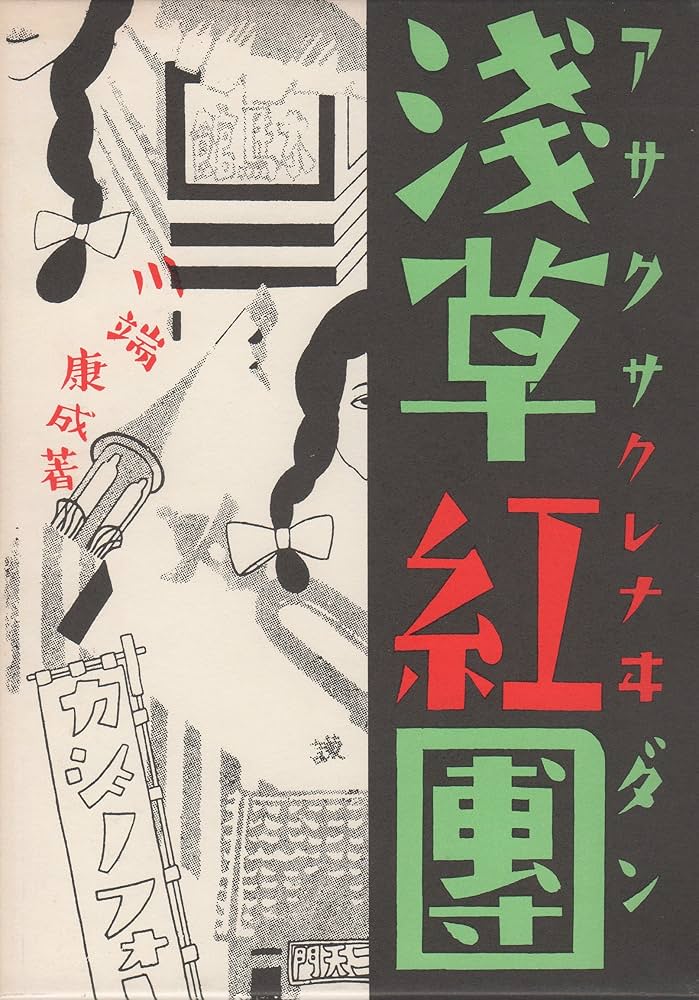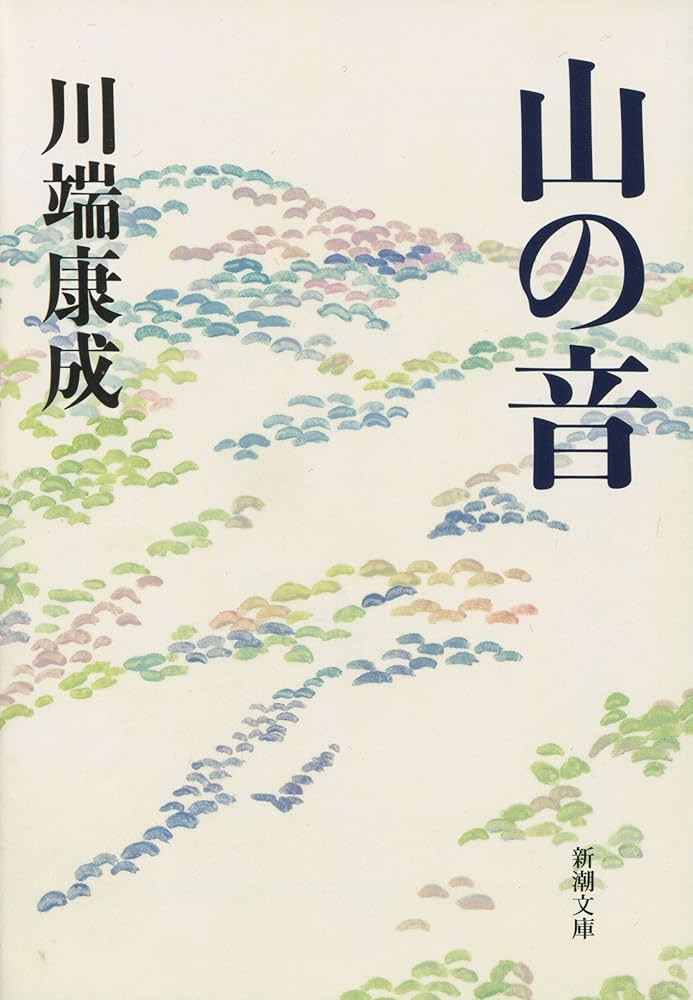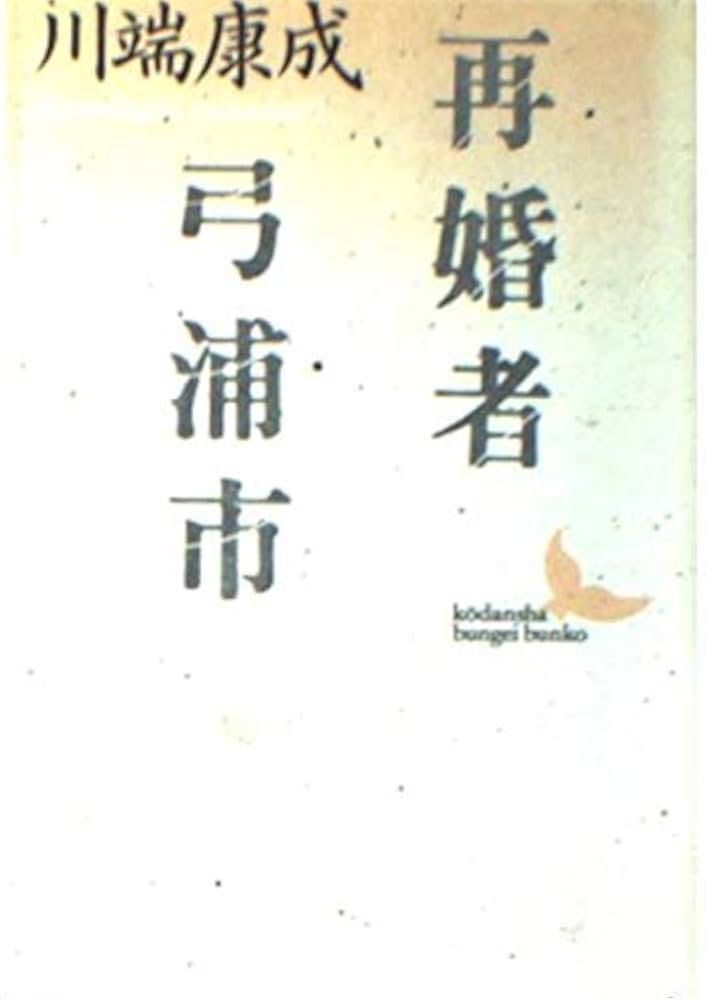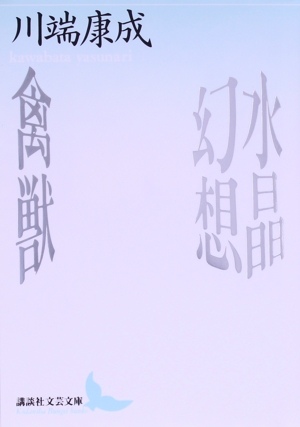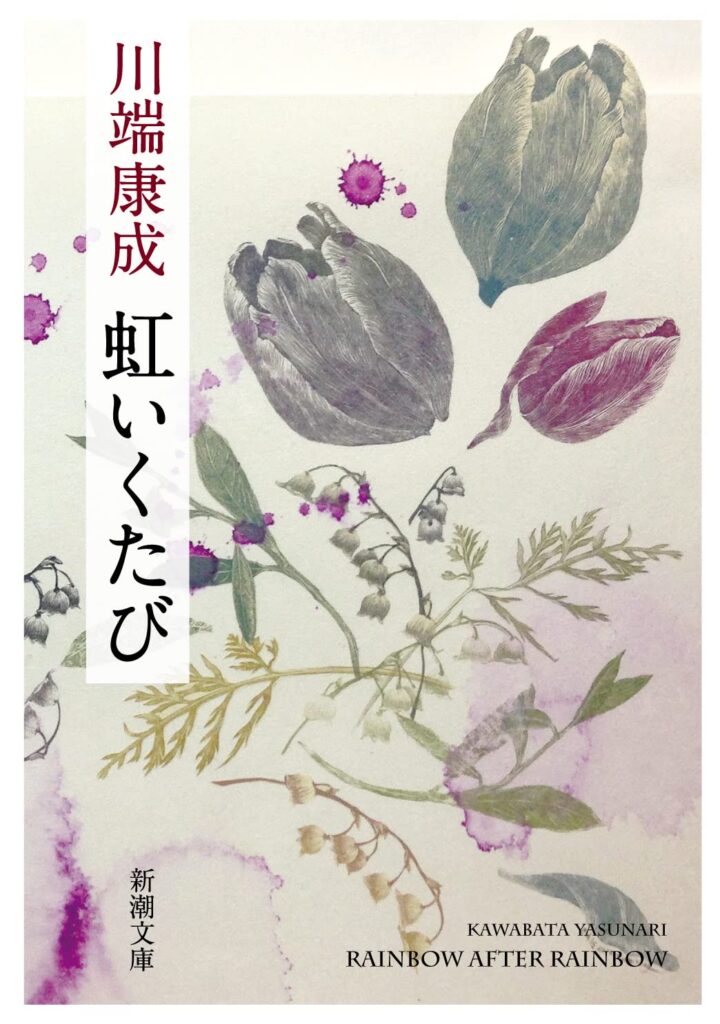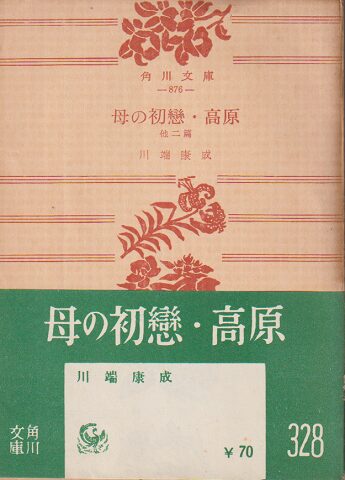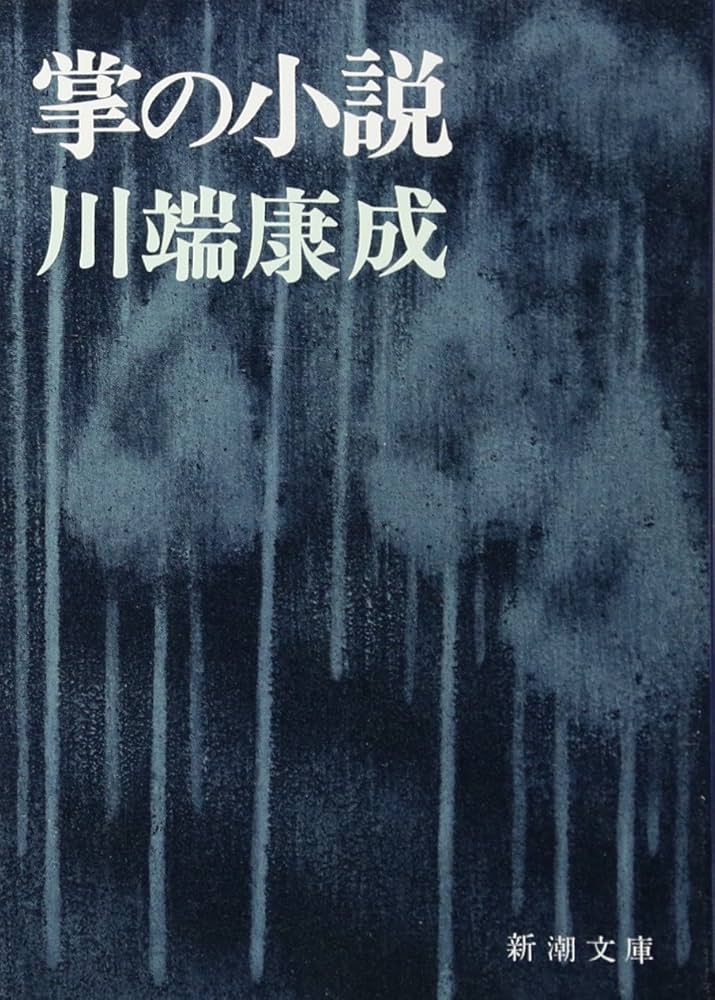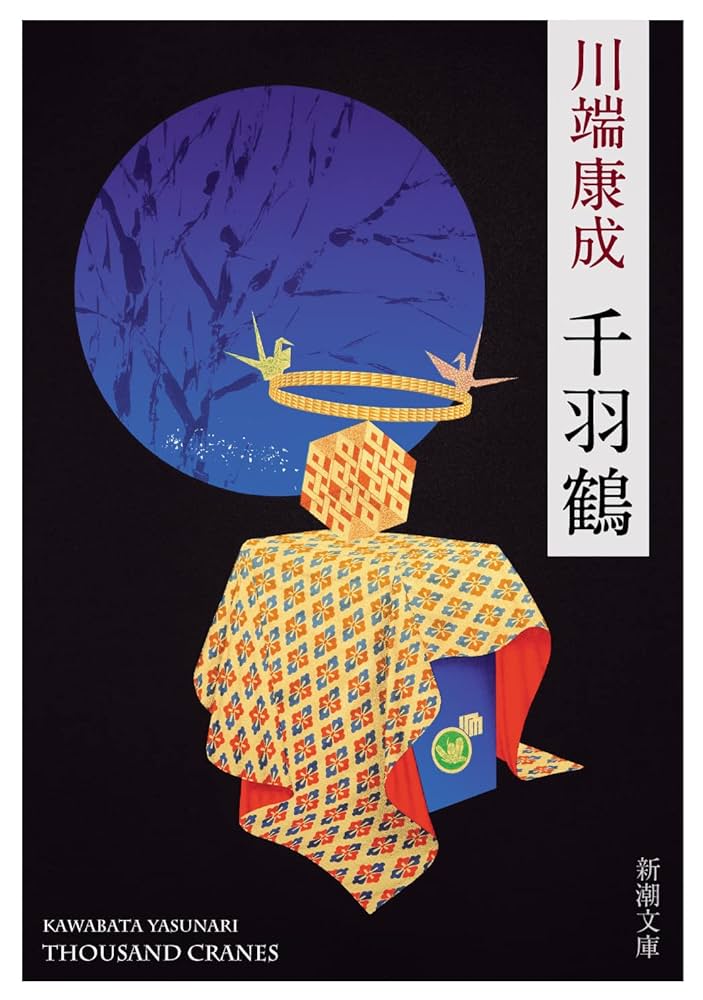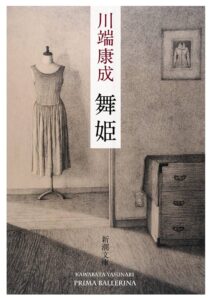 小説「舞姫」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「舞姫」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
川端康成と聞くと、『伊豆の踊子』の甘酸っぱい旅情や、『雪国』の透き通るような情景を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、今回お話しする『舞姫』は、そうした清らかなイメージとは少し趣の異なる、人間の内面に渦巻く澱(おり)のような感情を冷徹なまでに描き出した作品です。戦後の日本を舞台に、一つの家族が静かに、しかし確実に崩壊していく様は、読む者の心を強く揺さぶります。
物語の中心は、バレエという華やかな芸術に人生を捧げた母娘と、その家庭を内側から蝕んでいく知的な父。彼らの織りなす心理的な駆け引きは、息が詰まるほどの緊張感をはらんでいます。この記事では、まず物語の骨子となる部分をご紹介し、その後で、結末を含む重大なネタバレに触れながら、この物語が持つ深い意味について、私なりの解釈を交えてじっくりと語っていきたいと思います。
一見すると複雑な人間関係も、それぞれの登場人物が抱える孤独や渇望を知ることで、その輪郭がはっきりと見えてきます。なぜ彼らはすれ違い、傷つけ合わなければならなかったのか。そして、川端康成が「魔界」という言葉に託した、この物語の核心とは何だったのでしょうか。読み終えた後、きっとあなたもこの矢木家という名の舞台で演じられた、悲しくも美しい悲劇の虜になっているはずです。
「舞姫」のあらすじ
物語の舞台は、第二次世界大戦の傷跡がまだ生々しい1950年代の日本。北鎌倉に居を構える矢木家は、一見すると裕福で文化的な家庭に見えます。主である矢木元男は国文学者、その妻の波子は元プリマ・バレリーナで、現在はバレエ教室を主宰しています。彼らの間には、母と同じくバレリーナを目指す娘の品子と、大学生の息子の高男がいます。
しかし、その内実は冷え切った関係と、互いへの不信感で満ちていました。波子は、かつての恋人であり、今は実業家として成功している竹原と密会を重ねています。家庭では夫の元男から絶えず経済的な圧迫を受け、その陰湿な支配に苦しめられていました。波子にとって、竹原との時間は、息の詰まる家庭から逃れるための唯一の慰めだったのです。
一方、父の元男は、穏やかな学者の仮面の下に、家族を支配しようとする冷酷なエゴを隠し持っていました。彼は妻の財産に寄生しながら、その行動を監視し、じわじわと精神的に追い詰めていきます。そんな中、息子の高男が、母である波子と竹原が二人でいるところを目撃してしまい、それを父に報告したことから、家族の水面下にあった亀裂は、決定的なものとなっていくのです。
才能ある娘の品子は、この息苦しい家庭の中で、母の味方をしながらも、静かにすべてを観察していました。父の欺瞞、母の苦悩、そして自分自身の夢。すべてが絡み合い、矢木家という名の舞台は、静かに、そして確実に崩壊の最終幕へと向かって動き出します。物語は、この家庭に隠された秘密が次々と暴かれていく過程を克明に描いていきます。
「舞姫」の長文感想(ネタバレあり)
この『舞姫』という作品を読み解く上で、まず心に留めておきたいのは、物語全体を覆う息が詰まるような閉塞感です。それは単に仲の悪い家族の話、というだけではありません。敗戦という大きな歴史の転換点の中で、古い価値観(家制度)が崩れ去り、新しい価値観をまだ見出せずにいる、戦後日本の精神的な宙吊り状態が、矢木家という一つの家庭に凝縮されているように感じられます。
舞台となる北鎌倉の立派な家も、もはや家族の安らぎの場ではありません。かつての豊かさの残骸であり、登場人物たちを縛り付ける檻(おり)のような存在です。物語の冒頭から、彼らの間には愛情ではなく、不信と無関心、そして言葉にならない不満が澱のように溜まっています。この家庭は、すでに見えない形で崩壊しているのです。
そして、何よりも皮肉なのが『舞姫』という題名です。バレエという西洋の華やかな芸術が題材でありながら、この物語の中心人物である母・波子と娘・品子は、真の意味で舞台の上で輝くことがありません。波子は過去の栄光にすがる元プリマであり、品子の才能はまだ開花する前。彼女たちの「舞踏」は、決して踊られることがないのです。
この「踊られない舞踏」は、彼らが生きることを渇望しながらも、心理的な鎖によって身動きが取れなくなっている人生そのものを象徴しているように思えてなりません。華やかなバレエへの期待と、登場人物たちが舞台に立てない現実。このギャップこそが、物語の核心に繋がっていきます。それは、ただ感傷に浸るのではなく、困難な現実と向き合い、真に生きることを意味する「魔界」というテーマへと続いていくのです。
この物語を動かす登場人物たちは、誰もが心に乾きと孤独を抱えています。まず、母である矢木波子。元プリマ・バレリーナという過去の栄光と、満たされない現在の間で揺れ動く女性です。彼女は夫を愛しておらず、かつての恋人・竹原との密会に心の逃げ場を求めますが、その関係は決して一線を超えません。
波子のこの決断力のなさが、彼女の悲劇性を際立たせています。家庭から逃げ出したいと願いながら、決定的な行動を起こす勇気がない。夫からの精神的・肉体的な支配に屈辱を感じながらも、ただ耐えるだけ。彼女の姿は、皇居の堀でじっと動かない一匹の白い鯉に重なります。美しく、しかし完全に孤立し、停滞した存在なのです。
その波子を内側から支配するのが、夫の矢木元男です。彼は貧しい書生から、波子の裕福な実家と縁組することで国文学者の地位を得た、いわば知的寄生者です。表面上は温厚な紳士を装っていますが、その内面は自己中心的で、家族を言葉と心理操作で支配する「観察の悪魔」とでも言うべき存在です。
現代の言葉で言えば、彼の振る舞いはまさしくモラルハラスメント。あからさまな暴力ではなく、知性を武器に相手の人格をじわじわと否定し、精神的に追い詰めていくのです。妻の不貞に気づきながらも、それを直接問いただすことはしません。むしろ、それを材料に、より残酷なやり方で妻を支配するのです。彼のこの冷酷さは、人間的な共感を一切欠いた、不毛な知性の恐ろしさを感じさせます。
元男の書斎には「魔界入り難し」という掛け軸が掲げられています。これは、困難で真実の生を志すことの難しさを示す禅の言葉ですが、彼がこれを掲げることこそ、最大の偽善であり皮肉です。彼は「魔界」の対極、つまり安全地帯から他者を観察し、裁くだけの人生に安住しているのですから。この一点だけでも、彼の人物像の空虚さが浮き彫りになります。
そんな絶望的な家庭の中で、唯一の希望として描かれるのが、娘の品子です。彼女は母の夢を一身に背負い、バレリーナとしての才能を秘めています。物静かで観察力が鋭く、家庭内の力学を冷静に見つめています。父の金銭的な欺瞞や、家族を見捨てようとする計画に最初に気づき、母に告げるのも彼女でした。
品子の内面には、他の登場人物にはない「芯の強さ」が秘められています。姉弟の高男は、彼女の表情に興福寺の沙羯羅(さがら)像の面影を見ます。可憐な童子の姿をした竜王。このイメージは、彼女の繊細な外見の下に、力強く、ほとばしるような生命力が眠っていることを暗示しているかのようです。彼女こそが、この停滞した家から飛び立つ可能性を秘めた存在なのです。
脇を固める息子の高男と、波子の恋人である竹原もまた、この物語の停滞を象徴する人物たちです。高男は当初尊敬していた父の本性を知り、幻滅します。そして家族や社会に対して無関心で冷笑的な態度をとるようになります。彼の態度は、何を信じていいか分からなくなった戦後の若者たちの姿そのものです。一方の竹原は、波子を愛しながらも、夫と対決する勇気はなく、「友人」という立場に留まり続けます。彼もまた、決断できずに「魔界」の周りをうろつくだけの、無力な男なのです。
物語のネタバレになりますが、この淀んだ家族関係は、息子の高男が母と竹原の密会を目撃したことで、一気に崩壊へと向かいます。元男はこの報告を絶好の武器とし、子供たちの前で波子を徹底的に詰問します。この場面は、まるで一つの演劇のクライマックスのようです。計算され尽くした言葉の暴力で、妻の人格を粉々に砕いていく元男の姿は、悪魔的ですらあります。それは、戦後日本の「家」という制度が、完全にその機能を失い、崩壊する瞬間を象’徴しているようでした。
この「公開処刑」ともいえる夜、波子は結婚生活で初めて、夫の肉体的な要求を拒絶します。これは、彼女にとって初めての、そして決定的な反逆の行動でした。精神的な浮気に留まっていた彼女が、初めて具体的な「否」を突きつけたのです。この行為によって、二人の間の最後の絆は断ち切られ、彼女は精神的な隷属から、ささやかながらも確かな一歩を踏み出します。
そして、元男の欺瞞のすべてが明らかになります。ネタバレの核心ですが、彼が朝鮮戦争の勃発を恐れ、妻と娘を日本に置き去りにして、自分だけアメリカへ逃亡する計画を立てていたことが発覚するのです。彼の平和主義も、学者としての権威も、すべては自己保身のための卑劣な嘘だったことが暴かれます。彼の人間性の完全な破綻が示される瞬間です。
物語の結末は、あまりにも唐突に、しかし鮮烈な印象を残して訪れます。すべての欺瞞が明らかになり、家庭が完全に崩壊した中、品子は衝動的に家を飛び出し、伊豆へ向かう電車に乗り込みます。彼女は、かつてバレエを教わった師である香山が伊豆にいるという、不確かな噂だけを頼りに、一人、未知の未来へと旅立っていくのです。
この品子の「飛翔」こそ、この重苦しい物語における唯一の救いであり、希望の光です。波子や竹原が決断できずに停滞し、元男が不毛な観察に閉じこもる中、品子だけが、自らの意志で物理的にその場を離れ、新しい世界へと一歩を踏み出します。彼女のこの行動こそが、この小説におけるたった一度の、真の「魔界」への挑戦なのです。
「仏界易入 魔界難入」(仏界に入るは易く、魔界に入るは難し)。安易な慰めや感傷(仏界)に逃げるのは簡単だが、情熱や苦悩といった人間の業(ごう)を正面から受け止め、真に生き抜くこと(魔界)は難しい。この物語の登場人物たちは、品子を除いて、誰もがこの「魔界」に入ることができませんでした。彼らは皆、その入り口でためらい、挫折した人々だったのです。
ですから、この物語は「魔界」に入れなかった人々の悲劇を描いた物語であると言えます。しかし、最後に品子が見せた絶望的なまでの跳躍は、読む者に強烈な印象を残します。彼女の未来は不確かで、決して楽な道ではないでしょう。しかし、停滞した家から自力で抜け出した彼女の勇気ある行動は、真に「生きる」ことの尊さと可能性を示唆してくれます。彼女の旅は、彼女自身の「舞踏」の、まさに第一歩なのです。
まとめ
川端康成の小説『舞姫』は、戦後の日本を舞台に、一つの家族が静かに崩壊していく様を描いた、息の詰まるような心理劇です。元バレリーナの母、知性で家族を支配する父、そして未来へと飛び出す娘。彼らの間で交わされる言葉や視線の一つ一つが、物語に深い緊張感を与えています。
この記事では、まず物語の導入となるあらすじを紹介し、家庭内に渦巻く不和の根源を探りました。そして、ネタバレを含む長文の感想パートでは、登場人物たちの心理を深く掘り下げ、彼らがなぜすれ違い、傷つけ合わなければならなかったのかを考察しました。
特に重要なのが「魔界」という考え方です。それは、困難な現実から逃げずに真に生きようとする、険しい道のことです。多くの登場人物がその道へ踏み出せずに停滞する中、娘の品子だけが最後に家を飛び出し、不確かな未来へと旅立ちます。この結末は、物語に一筋の光を投げかけています。
家族とは何か、真に生きるとはどういうことか。『舞姫』は、そんな普遍的な問いを私たちに突きつけてくる、深く、そして忘れがたい作品です。この記事が、あなたがこの物語の世界へ足を踏み入れるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。