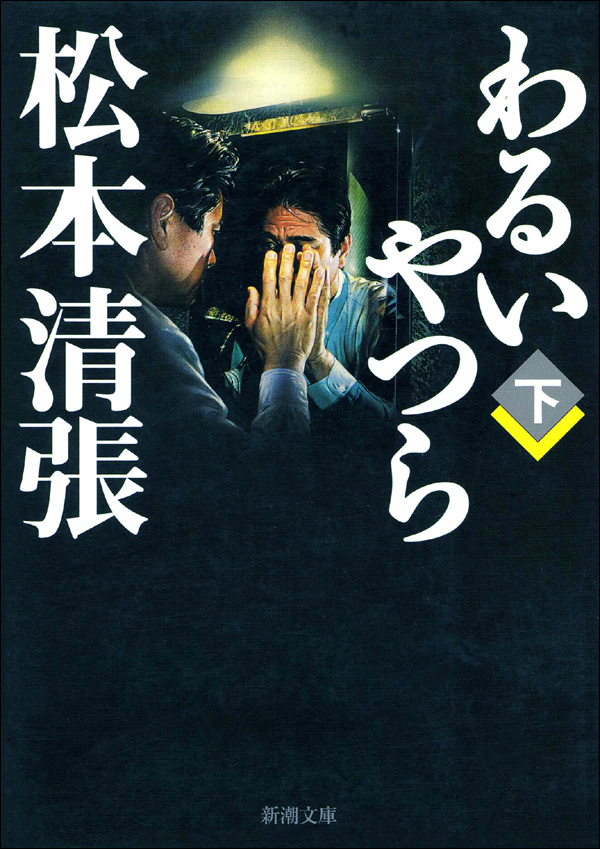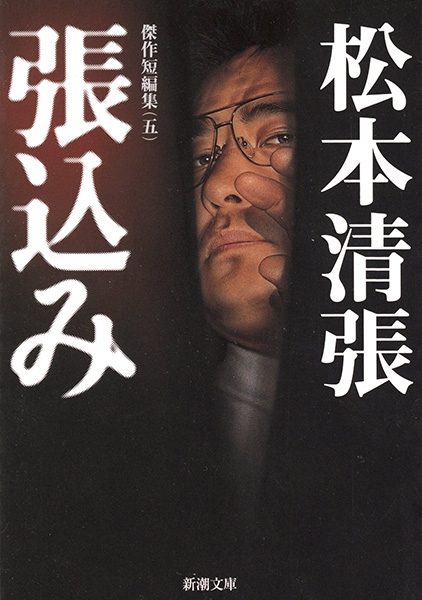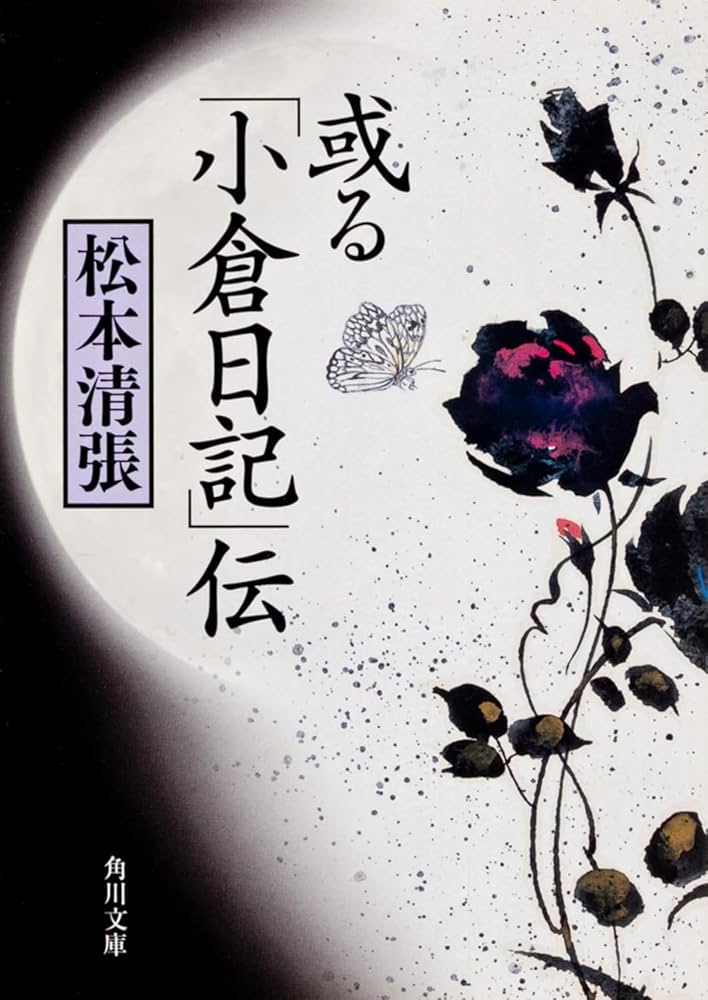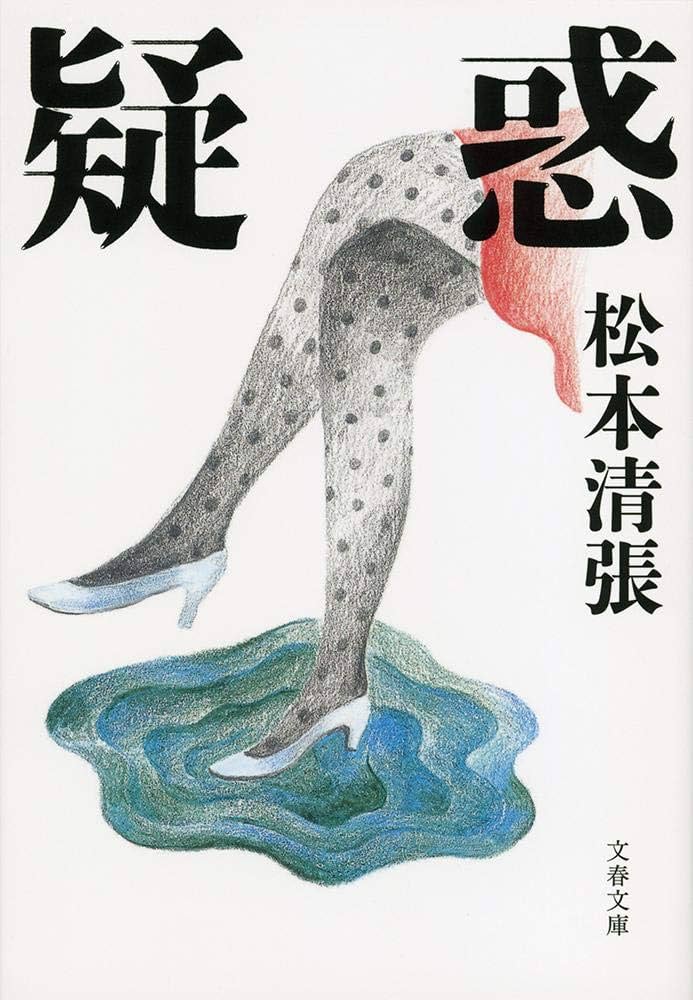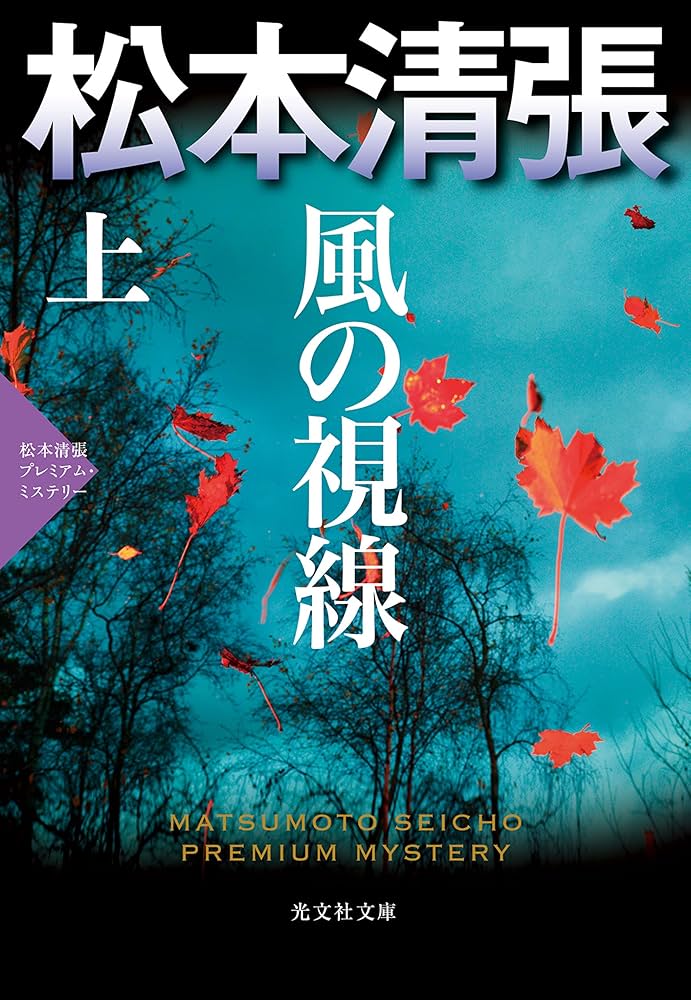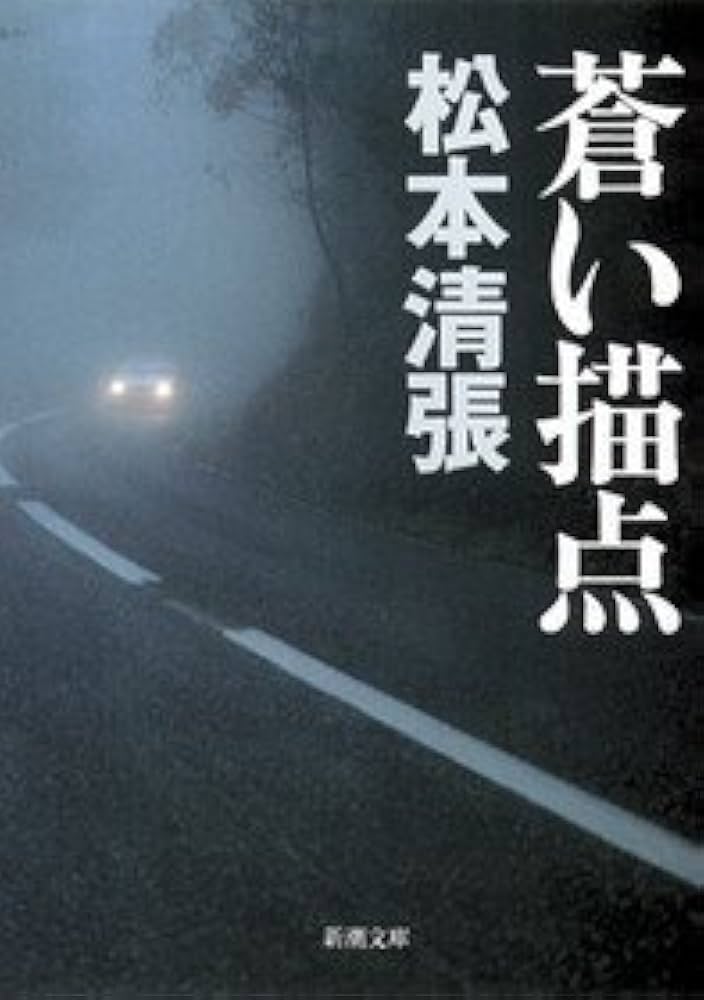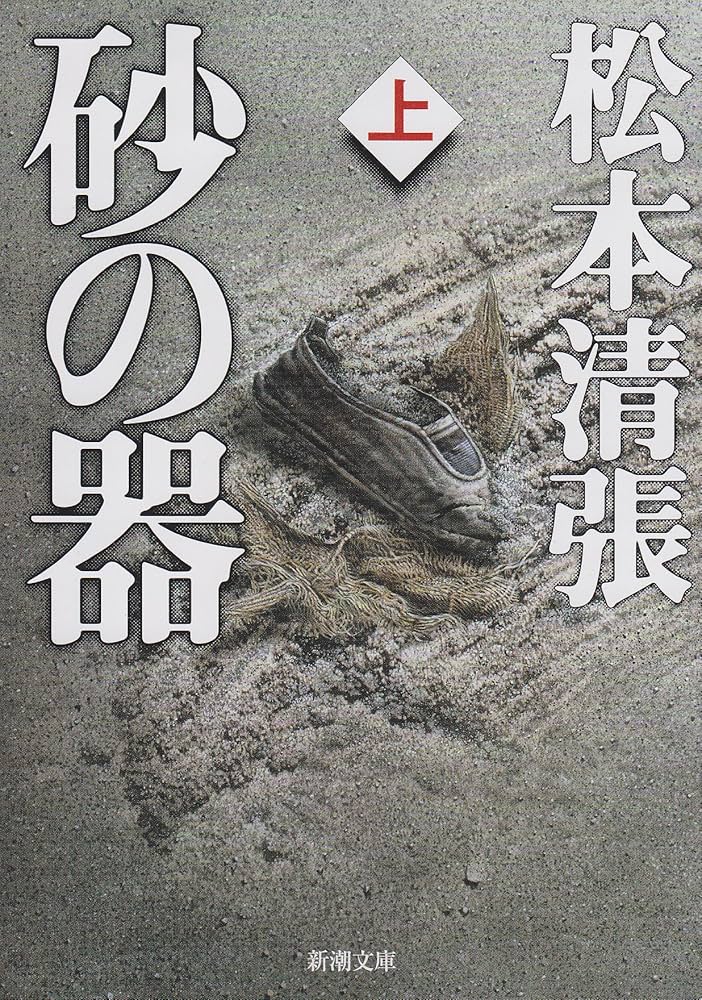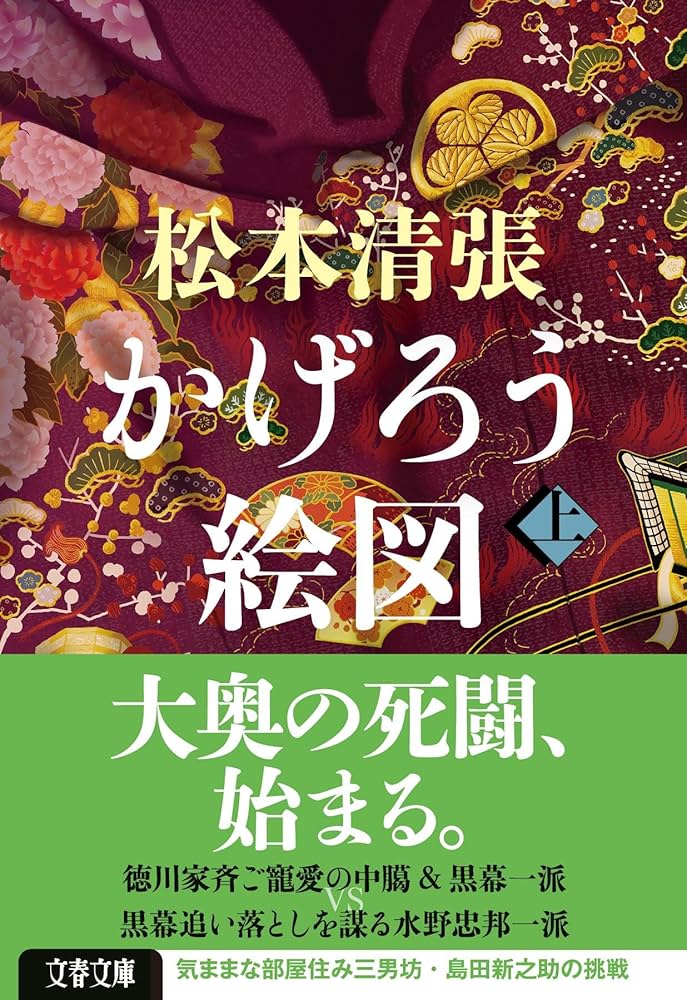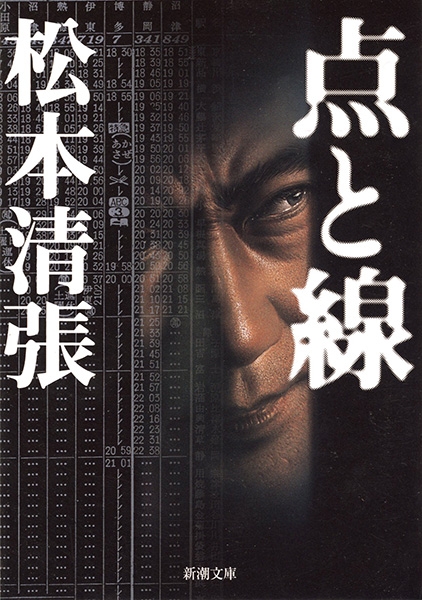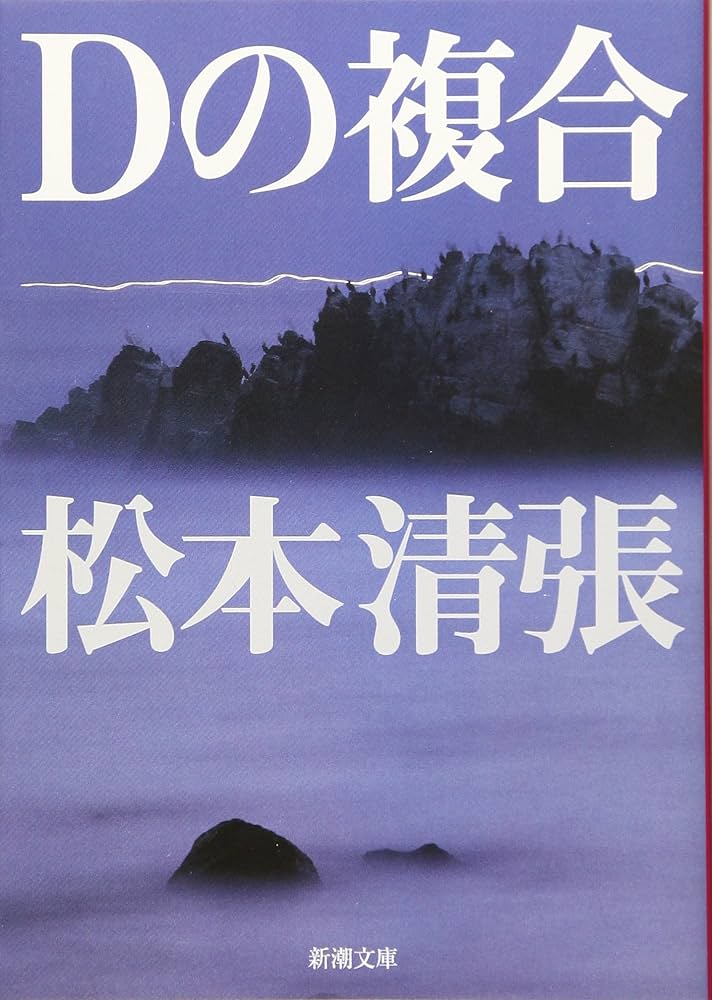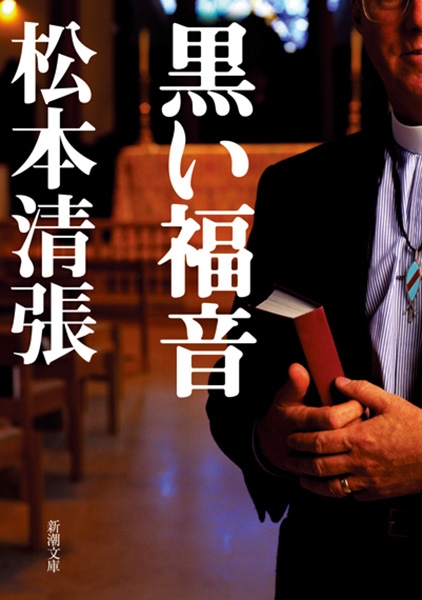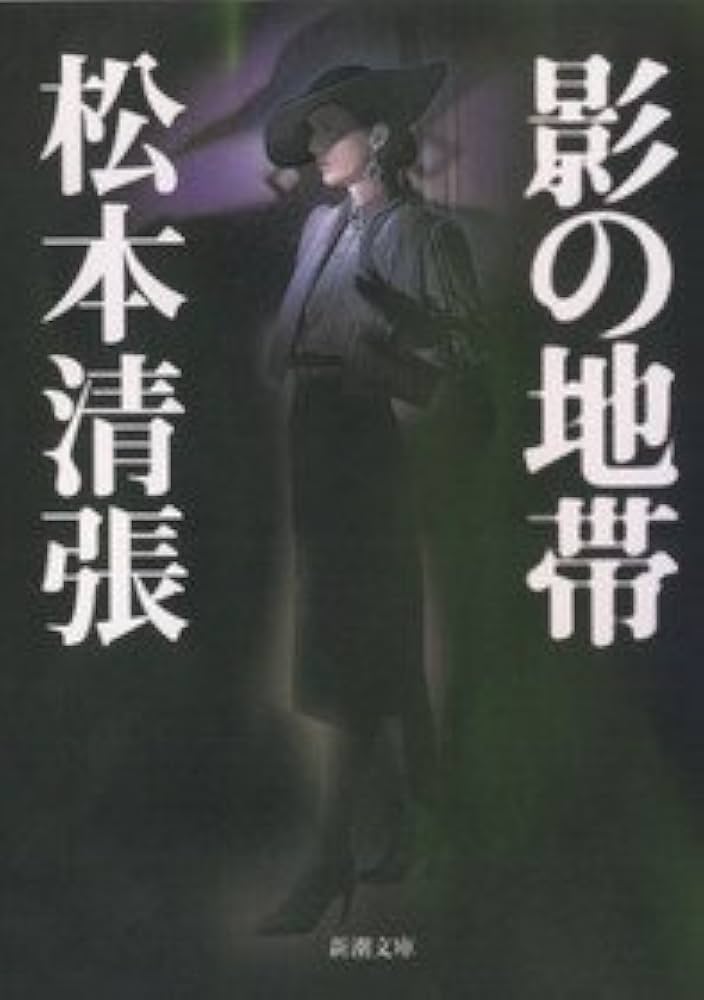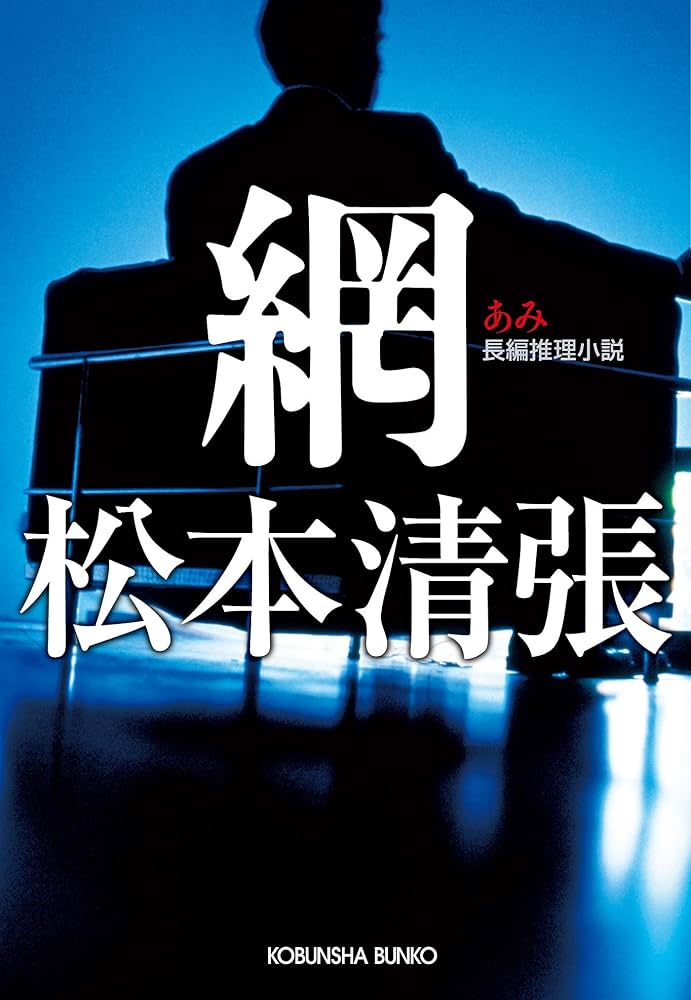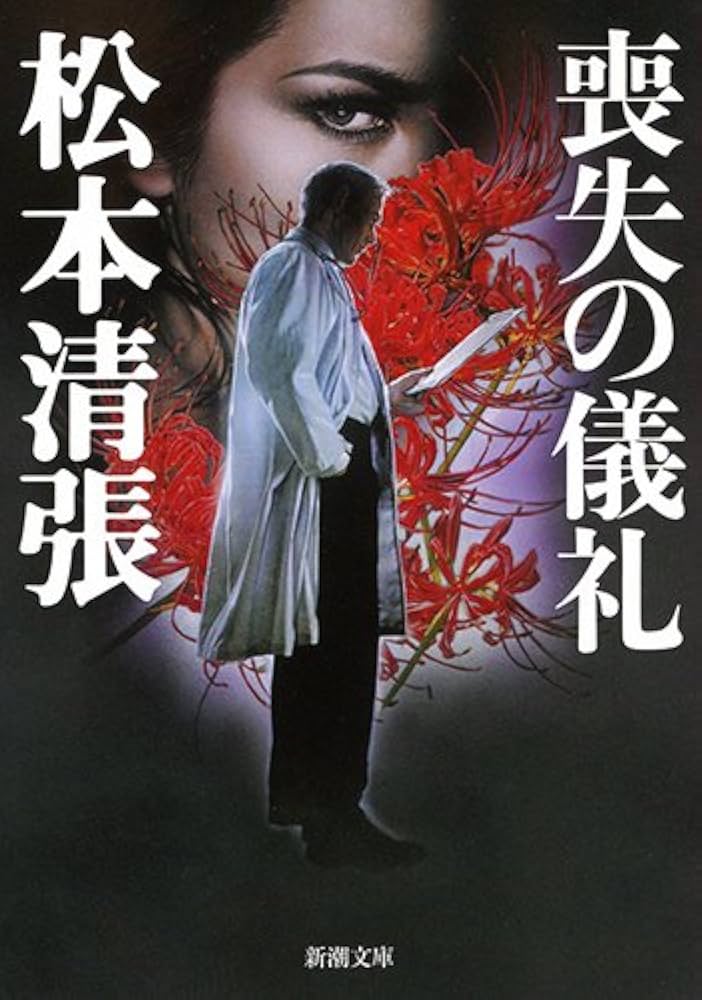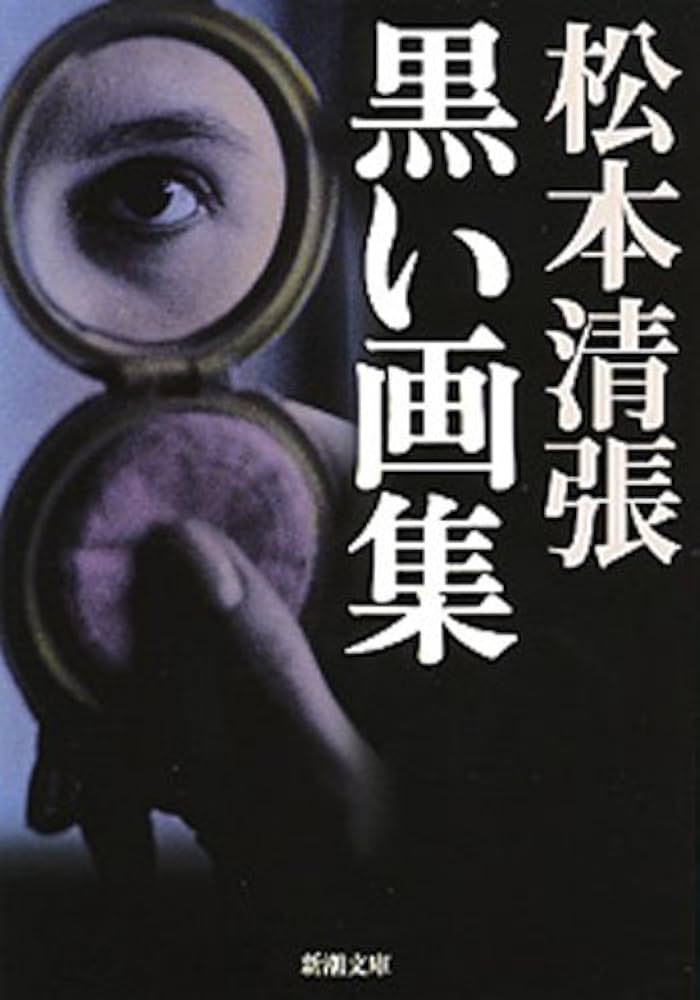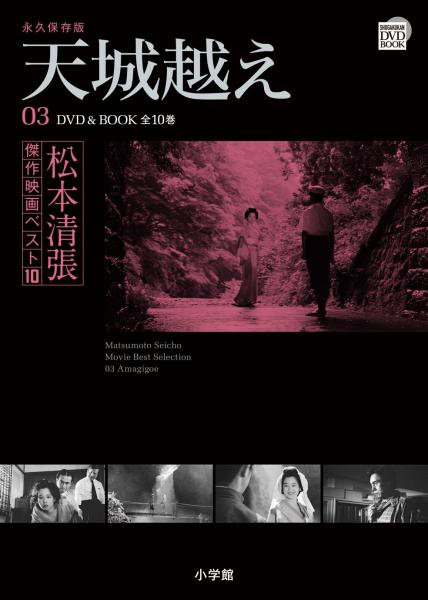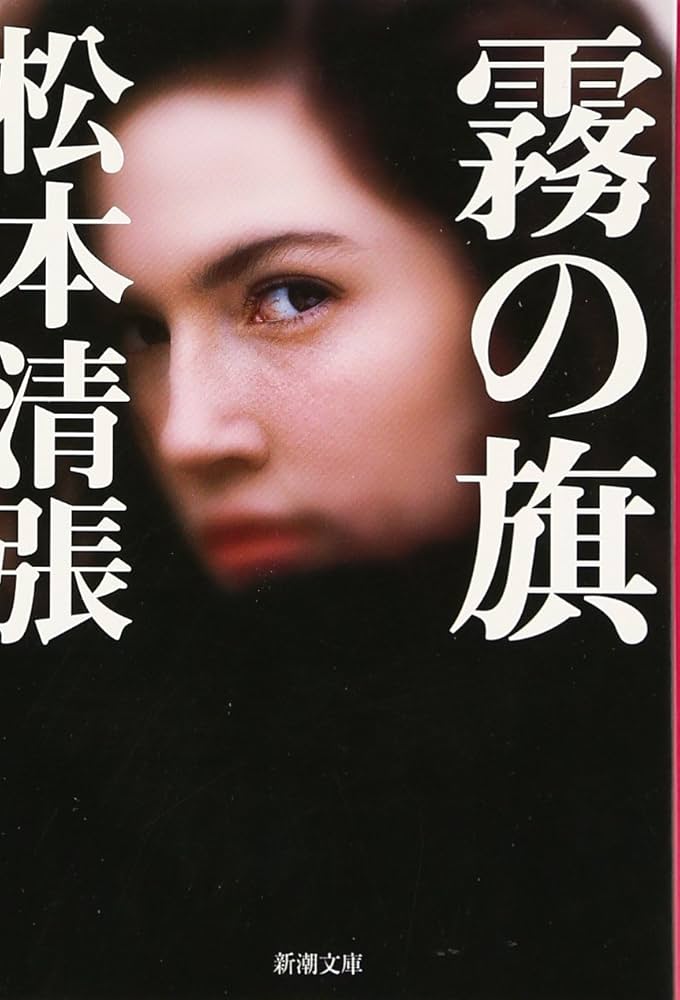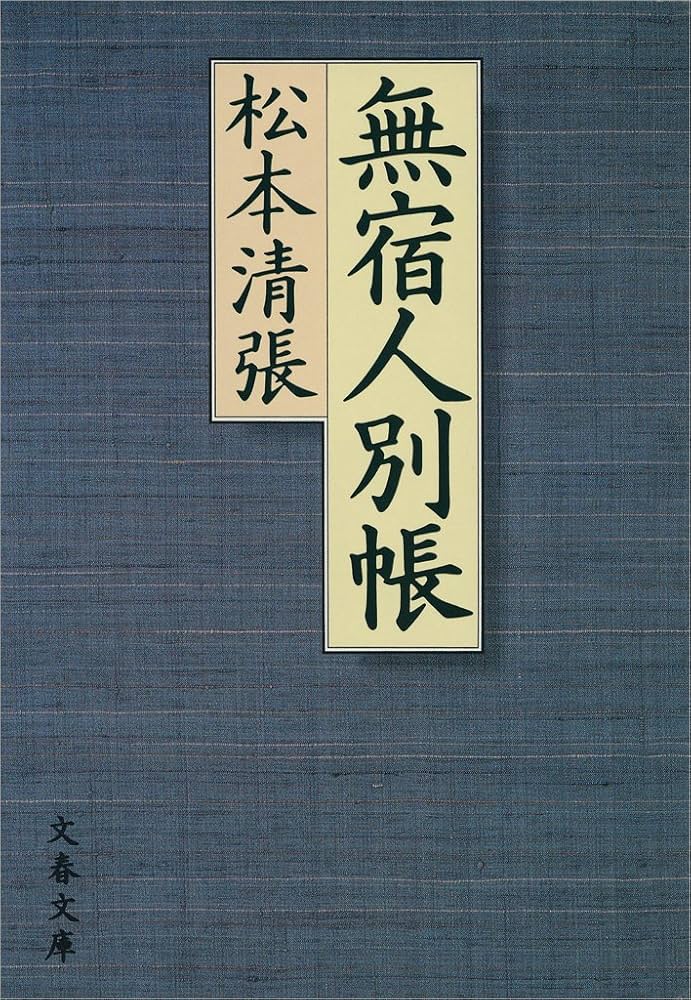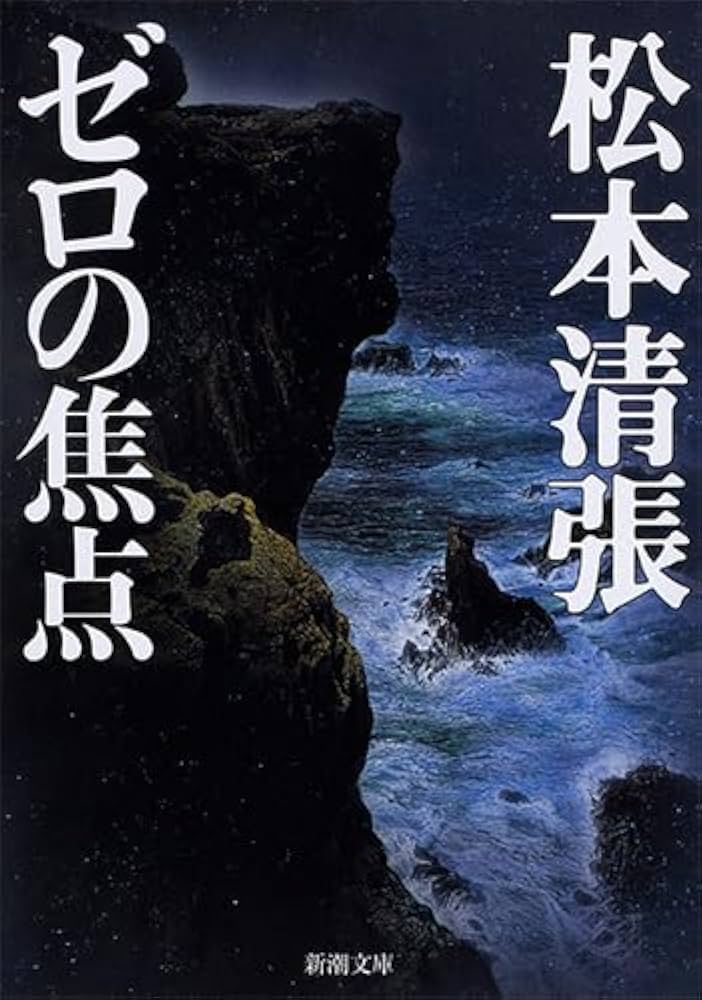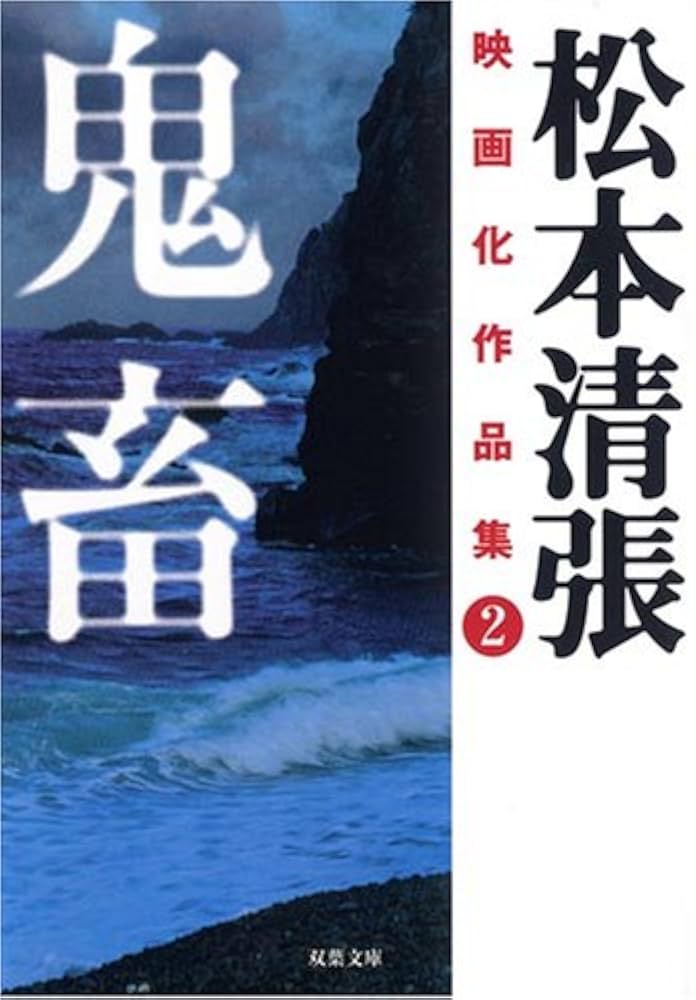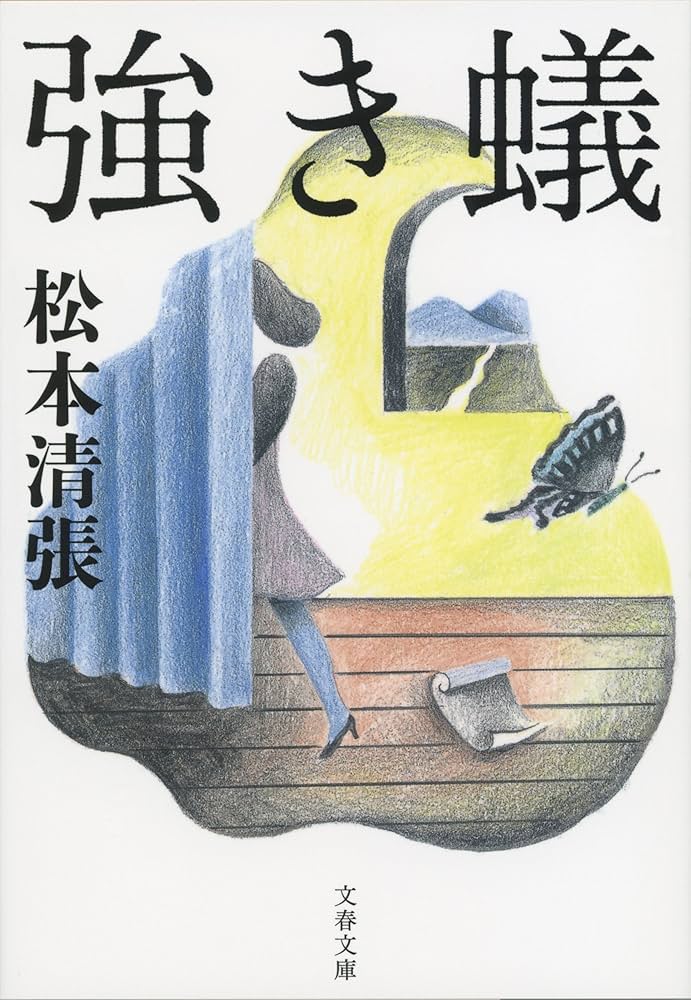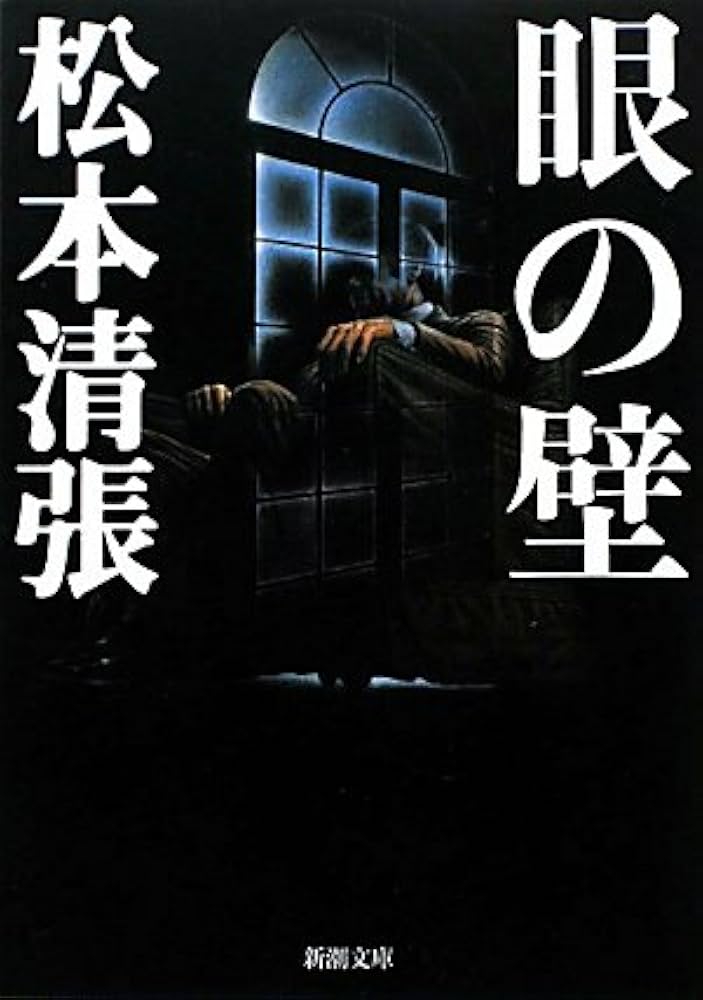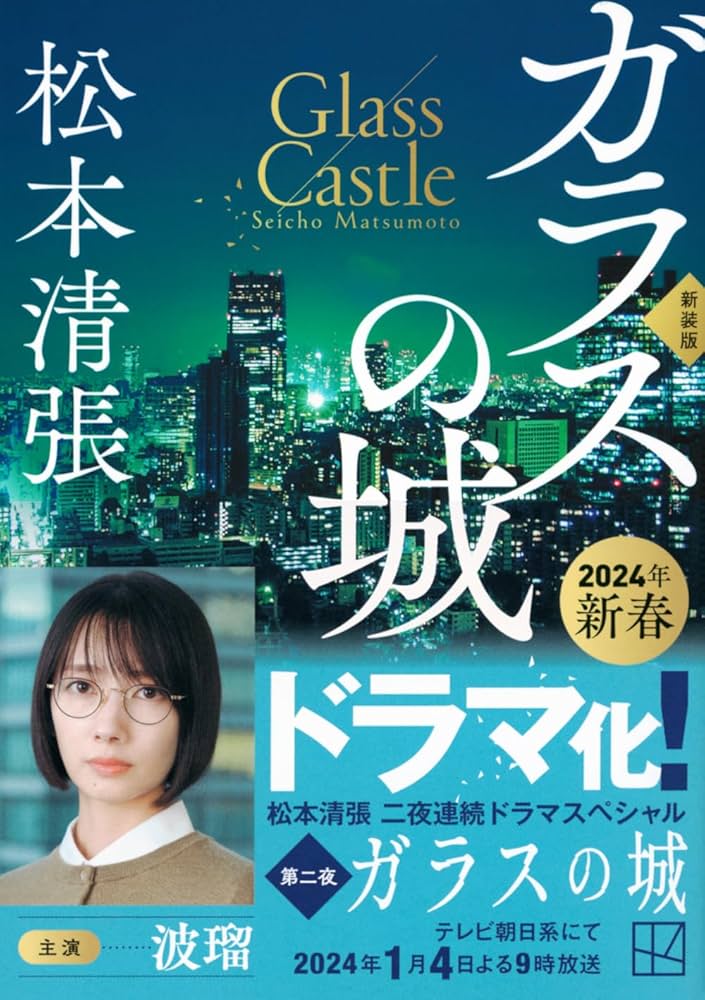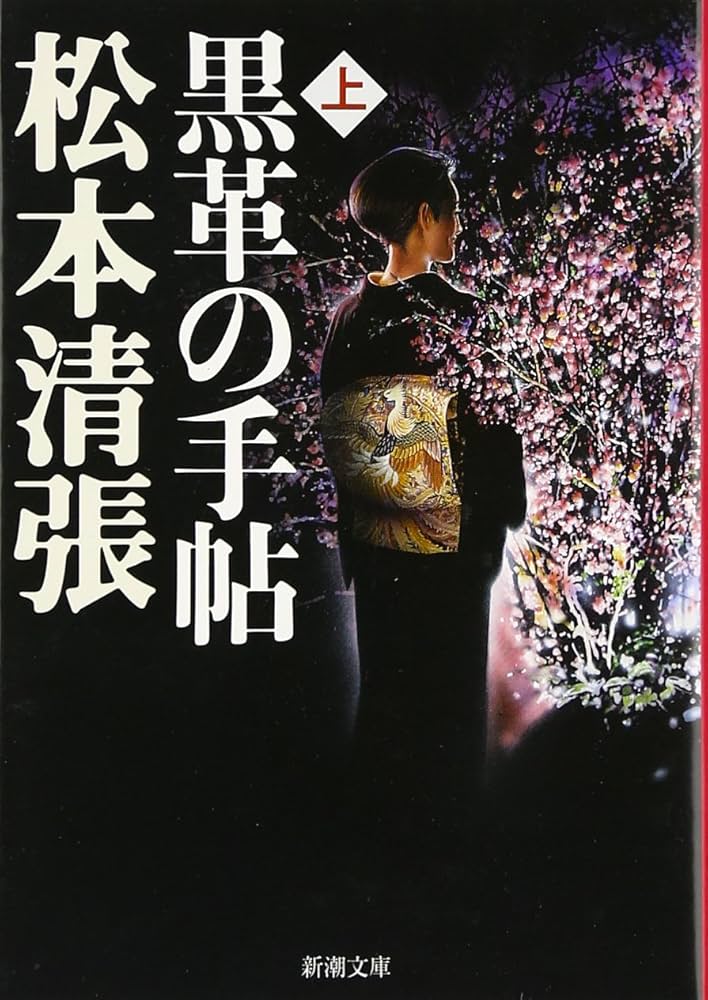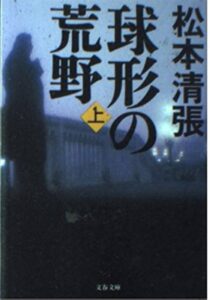 小説「球形の荒野」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「球形の荒野」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
松本清張作品の中でも、特に悲しく、そして美しい物語として多くの読者の心に刻まれているのが、この「球形の荒野」ではないでしょうか。単なる推理小説という枠には到底収まりきらない、壮大なスケールで描かれる歴史の悲劇と、その中で翻弄される人々の切ない運命。一度読み始めれば、その世界に引き込まれてしまうこと間違いありません。
物語は、戦争の傷跡がまだ生々しく残る時代を背景に、ひとつのささやかな疑問から始まります。しかしその疑問は、やがて国家を揺るがした歴史の闇へと繋がり、登場人物たちを巨大な陰謀の渦へと巻き込んでいくのです。この記事では、そんな「球形の荒野」の物語の骨子となる部分と、核心に触れるネタバレを含む深い思いを綴っていきます。
戦争とは何か、国を愛するとはどういうことか、そして家族の絆とは。この物語は、私たちに多くのことを問いかけてきます。まだ読んだことのない方はもちろん、かつて読んだことのある方も、この記事をきっかけに再びこの名作の世界に触れていただければ幸いです。それでは、物語の深淵へとご案内しましょう。
「球形の荒野」のあらすじ
物語の幕は、古都・奈良の唐招提寺で開かれます。主人公の一人、芦村節子は、芳名帳に見覚えのある筆跡を発見します。それは、第二次世界大戦末期にスイスで客死したと伝えられる叔父、元外交官・野上顕一郎のものと酷似していました。17年前に亡くなったはずの叔父が、なぜ今ここに。このささやかな疑問が、全ての始まりでした。
節子から話を聞いた夫の亮一や、野上の娘である従妹の久美子たちは、初めは半信半疑でした。しかし、久美子の婚約者で新聞記者の添田彰一がこの謎に興味を抱いたことから、事態は大きく動き出します。添田が調査に乗り出すと、芳名帳の該当ページが破り取られるという事件が発生。何者かが、野上の生存の痕跡を消そうとしていることは明らかでした。
添田の取材が進むにつれ、戦時中に野上と関わりのあった元外交官や元軍人たちの不審な動きが次々と浮かび上がります。彼らは一様に口を閉ざし、添田や久美子たちの周辺には、得体の知れない監視の影がちらつき始めます。やがて、関係者の一人が謎の死を遂げたことで、この事件は単なる過去の謎ではなく、現在進行形の危険な陰謀であることを登場人物たちは思い知らされます。
なぜ野上は死んだことにされなければならなかったのか。そして、もし本当に生きているのなら、なぜ今になって日本に姿を現したのか。添田と久美子は、日本の戦後史の深い闇に隠された、あまりにも悲しい「終戦工作」の真実に迫っていくことになります。その先には、誰も予想しなかった衝撃の結末が待っているのでした。
「球形の荒野」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心に触れるネタバレ情報を含みますので、未読の方はご注意ください。この物語がなぜこれほどまでに心を揺さぶるのか、その理由をじっくりと語らせていただきたく思います。
まず、物語の発端となる奈良の唐招提寺、芳名帳に記された一つの署名。これが全てのはじまりです。亡くなったはずの叔父、野上顕一郎の筆跡。単なる思い過ごしで終わってもおかしくないこの小さな波紋が、やがて大きなうねりとなっていく構成は見事としか言いようがありません。この「筆跡」という、個人の魂の証のようなものが物語の鍵となることで、歴史の闇に葬られたはずの一個人の存在が、抗いがたい力をもって現代に浮かび上がってくる様を象徴しているように感じました。
この発見に対する家族の反応も実にリアルです。特に、野上の実の娘である久美子の母、孝子の「もうそっとしておいてあげて」という態度は、長年、夫の死を受け入れ、その上で平穏を築いてきた女性の偽らざる心境でしょう。死んだはずの人間が生きていたかもしれない、という事実は、残された家族にとっては喜びであると同時に、これまで積み重ねてきた時間の全てを揺るがす劇薬でもあるのです。
その平穏を打ち破るのが、新聞記者・添田彰一の存在です。彼のジャーナリストとしての鋭い嗅覚と執念がなければ、この物語は家族の中のささやかな謎のまま終わっていたかもしれません。芳名帳のページが破り取られていたことが判明した瞬間、物語は静かな謎解きから、明確な「敵」のいるサスペンスへと移行します。誰かが、野上の存在を積極的に消し去ろうとしている。この事実が、読者の心を一気に掴んで離しません。
物語が中盤に差しかかると、不穏な空気はさらに濃密になります。野上のかつての同僚たちが、歌舞伎座に一堂に会する場面は、本作屈指の緊張感あふれる名シーンだと思います。言葉は交わされず、視線だけが交錯する。誰もが腹に一物を抱え、互いの出方を探り合っている。この静かなる攻防戦は、これから始まるであろう悲劇を予感させ、息を飲むほどの迫力がありました。
そして、ついに最初の犠牲者が出てしまいます。久美子のモデルとなった画家・笹島の死。彼は、野上が娘の姿を一目見るためだけに利用された、いわば善意の第三者でした。彼の死と、現場から消えた久美子のデッサン画は、この事件の背後にいる者たちの冷酷さを浮き彫りにします。彼らは、目的のためなら無関係な人間の命さえためらいなく奪う。この瞬間、物語はロマンの香りをまとったミステリーから、血の匂いがする冷徹なスリラーへとその姿を変えるのです。
この冷酷な陰謀を操っていたのが、「国威復権会」という右翼団体の存在です。戦前の軍国主義の亡霊ともいえる彼らにとって、野上が進めようとしていた「和平工作」は、国家に対する許しがたい裏切りでした。彼らの信じる「愛国」が、いかに独善的で破壊的なものであるか。松本清張は、この組織を通して、戦争が終わってもなお社会の深層に巣食う、危険な思想の根深さを鋭く告発しています。
舞台は京都、奈良へと移り、事態はさらに緊迫の度合いを増します。野上のかつての協力者であった村尾が狙撃され、野上の忠実な部下であった門田が殺害される。特に、品川の旅館の主人として身を潜めていた門田の最期は、涙なくしては読めませんでした。かつての上官であり、敬愛する野上を守るため、彼は最後まで口を割らず、命を落とすのです。彼の忠義心と悲劇的な結末は、戦争という巨大なうねりが、いかに多くの名もなき人々の人生を狂わせたかを物語っています。
ここで物語の核心である、ネタバレの核心部分に触れなければなりません。野上顕一郎が進めていた「終戦工作」の真相です。大戦末期、本土決戦や一億玉砕という破滅的な未来を回避するため、彼は国や軍上層部の意に反し、独断で連合国側との和平交渉の道を探っていました。それは何百万人もの命を救うための、崇高な行為でした。しかし、軍の強硬派にとってそれは「売国行為」以外の何物でもなかったのです。
この野上の行動は、実際にあったとされる「ダレス工作」などの歴史的事実が下敷きになっており、物語に圧倒的なリアリティを与えています。彼の同僚たちは、暗殺の危機から彼を守り、和平工作を続けさせるために、彼がスイスで病死したという偽の情報を流し、その存在を公の記録から抹消したのでした。国を救うための行動が、国賊としての汚名を着せられ、歴史から消される。このあまりにも理不尽で皮肉な運命に、胸が締め付けられる思いがします。
17年の時を経て、死期を悟った野上が日本へ帰ってきた理由。それは、決して自らの名誉を回復するためではありませんでした。ただ、望郷の念に駆られ、そして、一度も会うことのなかった娘・久美子の成長した姿を一目見たいという、純粋で人間的な愛情によるものでした。この個人的な願いが、期せずして「国威復権会」という眠れる獅子を起こしてしまったのです。野上の悲劇は、彼の「裏切り」が実は最高の愛国心であり、敵対する者たちの「愛国心」こそが独善的な狂信であるという、強烈なパラドックスを私たちに突きつけます。
そして、物語は全ての真相が明らかになった後、感動的なクライマックスを迎えます。観音崎の海岸で、ついに野上と久美子が邂逅するシーン。しかし、そこには涙の再会も、感動的な抱擁もありません。交わされるのは、ごくありふれた短い会話だけ。けれど、久美子は直感で、目の前にいる白髪の紳士が誰であるかを悟るのです。「全身で“父”の存在を感じていた」という一文に、この場面の全てが凝縮されています。
言葉はいらない。理屈もいらない。血の繋がりが、魂が、17年という歳月と偽りの歴史を超えて、互いを認識する。これほど静かで、これほど切なく、そしてこれほどまでに美しい再会シーンが他にあるでしょうか。父に会えた喜びと、その父を二度と会えない存在として永遠に失う悲しみを、久美子は同時に味わうのです。この言葉にならない感情の深淵を描き切った松本清張の筆力は、まさに圧巻です。
最後に、この「球形の荒野」というタイトルについて。故郷を追われ、国籍すら捨て、愛する家族に名乗ることさえできない野上にとって、もはや安住の地は地球上のどこにもありません。彼にとって、この地球という「球形」の惑星そのものが、ただただ広がる孤独な「荒野」と化したのです。このタイトルは、野上顕一郎という一人の男の悲劇的な運命そのものを、見事に表現しています。
この物語は、単なるミステリーではありません。戦争が個人の運命に残した、決して癒えることのない深い傷跡を描いた一大叙事詩であり、歴史の波間に消された人々への鎮魂歌(レクイエム)でもあります。読後、心に残るのは謎が解けた爽快感ではなく、むしろ胸を締め付けるような切なさと、歴史の非情さに対するやり場のない怒り、そして、それでも確かに存在した父と娘の魂の絆に対する、静かな感動なのです。
「球形の荒野」は、時代を超えて読み継がれるべき、日本の文学が誇る金字塔の一つであると、私は確信しています。戦争の記憶が風化しつつある現代だからこそ、この物語が持つ重みとメッセージは、より一層私たちの心に響くのではないでしょうか。
まとめ
松本清張の「球形の荒野」は、戦争という巨大な歴史の波に翻弄された、一人の男とその家族の悲劇を描いた不朽の名作です。物語は、死んだはずの人物の筆跡という小さな謎から始まりますが、やがて日本の戦後史に隠された壮大な「終戦工作」の真実へと繋がっていきます。ネタバレになりますが、国を憂い、多くの命を救おうとした男が、なぜ歴史から抹殺されなければならなかったのか。その理不尽さが胸を打ちます。
スリリングなサスペンスと、歴史の闇を暴く知的な興奮、そして何よりも登場人物たちの切ない心情が、読む者の心を強く揺さぶります。特に、物語のクライマックスである観音崎での父と娘の無言の邂逅シーンは、日本文学史に残る名場面と言えるでしょう。言葉を超えた魂の交流が、涙を誘います。
この小説の魅力は、複雑なプロットだけでなく、登場人物一人ひとりの心の機微を丁寧に描き出している点にあります。平穏を願う家族、真実を追う新聞記者、過去の亡霊に憑りつかれた者たち。それぞれの立場や想いが交錯し、重層的な人間ドラマを織りなしているのです。
「球形の荒野」は、ミステリーファンはもちろん、深い感動を呼ぶ人間ドラマや、歴史の裏側に興味がある方にも、ぜひ読んでいただきたい一冊です。読後、タイトルの意味を噛みしめたとき、きっとあなたの心にも忘れられない余韻が残るはずです。