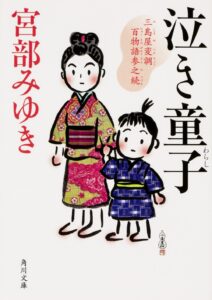 小説「泣き童子 三島屋変調百物語参之続」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが紡ぐ、江戸の袋物屋・三島屋を舞台にした、少し不思議で、時にぞくりとする物語のシリーズ第三弾ですね。おちかという娘が、訪れる人々の怪異譚に耳を傾ける「変わり百物語」。その聞き役も、すっかり板についてきたように感じます。
小説「泣き童子 三島屋変調百物語参之続」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが紡ぐ、江戸の袋物屋・三島屋を舞台にした、少し不思議で、時にぞくりとする物語のシリーズ第三弾ですね。おちかという娘が、訪れる人々の怪異譚に耳を傾ける「変わり百物語」。その聞き役も、すっかり板についてきたように感じます。
この「泣き童子 三島屋変調百物語参之続」では、さらに深みを増した物語が六編、収められています。人の心の奥底に潜む情念や、説明のつかない出来事が、江戸の情景とともにしっとりと描かれています。怖いだけではなく、切なさや温かさも感じられるのが、このシリーズの素敵なところ。おちか自身の心の変化や成長も、物語の縦糸としてしっかりと織り込まれています。
この記事では、「泣き童子 三島屋変調百物語参之続」の各話の物語の筋立てを追いかけつつ、物語の核心にも触れていきます。そして、読み終えて私の心に残ったあれこれを、たっぷりと語っていきたいと思います。これから読もうと思っている方、すでに読まれた方、どちらにも楽しんでいただけたら嬉しいです。
小説「泣き童子 三島屋変調百物語参之続」のあらすじ
江戸は神田にある袋物屋の三島屋には、少し変わった決まり事があります。主人の伊兵衛の姪であるおちかが、訪れる客人の不思議な話、怖い話、奇妙な話をただひたすらに聞く、「変わり百物語」。語られた話は聞き捨て、胸のうちにしまい込むのが習わしです。過去に心に深い傷を負ったおちかが、人々の話を聞くことで少しずつ心を解きほぐしていく…というのが、この物語の始まりでした。
「泣き童子 三島屋変調百物語参之続」では、おちかが聞き手となって一年が過ぎ、彼女の心にも変化が見られます。そんな折、三島屋には様々な事情を抱えた人々が訪れます。「魂取の池」では、ある池にまつわる祟りの話が語られます。命は奪わないけれど、大切な何かを奪っていくという陰湿な怪異。語り手の女性が池に向かった理由とは…。続く「くりから御殿」は、大火に見舞われた屋敷の跡地で起こる不思議な出来事と、生き残った者の悲しみ、そして亡き友との絆を描いた切ない物語です。
表題作でもある「泣き童子」は、ひときわ異様な雰囲気をまとった話です。ある人物の前でだけ、赤ん坊の姿をした何かが泣き続ける…。その泣き声は人の罪を責め立て、聞く者を狂わせていくと言います。骸骨のように痩せ衰えた男が語るその話には、恐ろしい秘密が隠されていました。また、「小雪舞う日の怪談語り」では、おちかが初めて三島屋の外へ出て、怪談語りの会に参加します。そこで語られる四つの話と、道中で起こる奇妙な出来事が描かれます。
後半の「まぐる笛」は、山に出没するという恐ろしい存在「まぐる」と、それを鎮める笛使いの物語。生命の原始的な恐怖を感じさせる、シリーズ中でも特に凄惨な描写が含まれる一編です。語り手の女性とその母の勇敢な姿が印象的です。最後の「節気顔」では、亡くなった人にそっくりな顔を持つ者が現れるという不思議な現象が語られます。そこには、過去の因縁と、思いがけない人情の機微が関わっていました。そして、この話には、シリーズの今後に関わってきそうな謎めいた人物も登場します。
小説「泣き童子 三島屋変調百物語参之続」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは「泣き童子 三島屋変調百物語参之続」を読み終えた私の、熱のこもった語りにお付き合いください。物語の核心、結末にも触れていきますので、未読の方はご注意くださいね。
全体を通して感じたのは、前二作にも増して、物語の幅が広がったなということです。怖い話はもちろんですが、悲しい話、温かい話、そして少し考えさせられるような話まで、実に多彩な味わいがありました。おちかが聞き手としてだけでなく、時には外の世界へ出て物語に関わっていく様子も描かれ、彼女自身の成長がよりはっきりと感じられたのも嬉しい点でした。
『第一話 魂取の池』
タイトルからして、もっと直接的に命を奪うような恐ろしい池を想像していたのですが、そうではありませんでしたね。「魂」というよりは、その人にとって「かけがえのない何か」を奪っていく、というところが陰湿で、かえって現実味のある怖さを感じました。語り手の女性が、夫との縁を切りたいがために、わざと祟りに遭いに行くという動機。その執念というか、思い詰めた気持ちが生々しいです。そして、池が奪ったものが、彼女が内心で一番失いたくなかったであろうものだった、という結末が皮肉であり、また物悲しくもありました。人の欲や執着が怪異を引き寄せる、というのは怪談の王道ですが、その描き方が巧みだなと感じ入りました。都市伝説のような、現代にも通じるような怖さがありましたね。
『第二話 くりから御殿』
これは、六編の中でも特に胸に沁みたお話でした。大火で多くの命が失われた屋敷跡。そこで聞こえるはずのない声、見えるはずのない姿…。生き残った語り手の男性が抱える罪悪感と、亡くなった友人たちの想いが交錯します。災害や事故で遺された人々の心情は、現代に生きる私たちにも痛いほど伝わってきます。「行方不明のままよりは、亡骸が見つかった方が…」という考えと、「亡骸を突きつけられる方が辛い」という考え、どちらも真実なのだろうと思います。
特に印象的だったのは、病床で生死の境をさまよった語り手が聞いた、亡き友人たちの「いっぺんお帰り」という言葉の意味。最初は自分も死の世界へ誘われているのかと恐れた彼が、その言葉に込められた本当の意図――「一度、現世に帰って、生きろ」という友人たちの励まし――に気づく場面は、涙なしには読めませんでした。悲しい出来事の中にも、確かな友情と優しさが描かれていて、読後感がとても温かい物語でした。
『第三話 泣き童子』
表題作だけあって、これは不気味さが際立っていましたね。特定の人物の前でだけ泣き続ける赤ん坊の姿をした存在、「泣き童子」。その正体は、人が犯した罪そのもの、あるいは罪悪感を具現化させたようなものなのでしょうか。泣き声によって絶えず罪を責められ続けるというのは、想像するだけで精神的に追い詰められます。語り手の男が、なぜ「泣き童子」に取り憑かれることになったのか、その経緯と童子の正体が明かされるにつれて、ぞくりとする感覚が増していきます。
そして、この話が特に印象深いのは、語り終えた後の三島屋の場面です。男が「人を呼んでほしい」と言い残し、おちかが人を呼びに行っている間に事切れていた…という結末もさることながら、その後の描写が何とも言えず物々しい。何か不穏な気配が漂っているような、まだ終わっていないような感覚。怪異そのものだけでなく、それがもたらす「場の空気」まで描き出す筆致に、宮部さんの凄みを感じました。物語自体も怖いですが、読後感がひときわざわざわする一編でした。
『第四話 小雪舞う日の怪談語り』
この話は構成が面白いですね。おちかが三島屋を出て、よそのお屋敷で開かれる怪談語りの会に参加するという趣向。そこで語られる四つの短い怪談も、それぞれに味わいがありました。母子の情愛を感じさせる話、少しぞっとする話、不思議な力を持つ人の話など、バラエティに富んでいます。
しかし、この話の真骨頂は、怪談語りの会そのものよりも、おちかが屋敷へ向かう道中と帰りに経験する奇妙な出来事にあるように思います。雪の日に現れた不思議な駕籠屋。その正体は、読み進めるうちに「もしや…?」と思いましたが、結末で明かされた事実は、私の予想を超えて、とても温かいものでした。多くの怪異譚を聞き、人の心の機微に触れてきたおちかだからこそ、この出来事を正しく、温かいものとして受け止められたのだろうな、と感じます。私だったら、ただただ怖がって、その裏にある優しさや思いやりに気づけなかったかもしれません。怪異に慣れ、心が少しずつ開いてきたおちかの成長を実感できる、素敵なエピソードでした。験担ぎの話に出てきた「四は死に通じるから嫌うが、九は苦に通じても、浮き世には苦があるのが当たり前だからいい」という親父さんの言葉も、妙に心に残りました。
『第五話 まぐる笛』
これは……正直、一番怖かったです! 油断していました。これまでの話が、怖さの中にも切なさや温かさがあったので、ここまで直接的で原始的な恐怖が描かれるとは思っていませんでした。山に潜む「まぐる」という存在。それは、単なる幽霊や妖怪というより、もっと実体を持った、人を襲い喰らう「怪獣」のようなもの。その描写が、本当に生々しくて容赦がないんです。特に、まぐるが人を襲う場面や、笛の音によって操られ、自らを喰らう場面などは、目を背けたくなるほどでした。『まぐる笛』の恐怖は、まるで足元から這い上がってくるような、じっとりとしたものでした。
しかし、ただ怖いだけではありません。この話の語り手である女性と、その母である笛使いの生き様が、また壮絶で、胸を打ちます。特に、まぐるが現れた際に、我が子を守るために毅然と立ち向かう母親の姿は、神々しさすら感じました。目に見える脅威である「まぐる」と、目に見えず正体もわからない災厄、どちらがより恐ろしいのか。そして、災厄に遭わないことと、遭っても乗り越える力を持つこと、どちらが幸せなのか。そんな問いかけも、深く考えさせられました。おちかが自身の心の中にも「まぐる」がいるのかもしれない、と感じる場面は、このシリーズ全体のテーマにも通じるものがあるように思いました。怖かったけれど、非常に読み応えのある、濃密な一編でした。
『第六話 節気顔』
最後のこの話は、少し物騒な過去も描かれますが、読後感はとても温かく、希望を感じさせるものでした。「節気顔」とは、季節の変わり目などに、亡くなった人にそっくりな顔の者が現れる、という不思議な現象。語り手の男性が、かつて悪事を働いていたものの、改心して穏やかに暮らす老人と出会い、その老人がまさに、過去に因縁のあった人物の「節気顔」だった…という筋立てです。
この話で注目すべきは、やはり「おそろし」のラストにも登場した、謎めいた商人風の男の再登場でしょう。「あなたのその顔をお借りします」という台詞、何とも妖しい響きですが、彼がしていることは、必ずしも悪意だけではないように思えます。死者の顔を借りて現世に現れ、何かを成し遂げる、あるいは伝える。それは、遺された者にとっても、そして死者自身にとっても、ある種の救いになっているのかもしれません。この謎の男が、今後シリーズでどのような役割を果たしていくのか、非常に気になりますね。
そして、悪事を重ねてきた老人が、最期は人に恨まれることなく、穏やかに弟のもとで人生を終えることができた、という結末には、素直に感動しました。人は過ちを犯すけれど、やり直すこともできる。そして、思いがけない形で、誰かの助けになることもある。そんな、人の持つ複雑さと温かさを感じさせてくれる、シリーズの締めくくりにふさわしい物語でした。
宮部さんの筆致はますます円熟味を増しているように感じます。江戸の町の空気感、人々の息づかい、そして目に見えないものの気配。それらが、独特の言い回しや表現(参考資料にあった「しおしおと消える」「ふくふくとした笑い方」「ぞわりぞわりと身動きしている」など、本当に豊かですよね!)によって、実に鮮やかに描き出されています。怖い話のはずなのに、読んでいると心が洗われるような、浄化されるような感覚になる瞬間があるのは、やはり宮部作品ならではの魅力だと思います。おちかの成長とともに、三島屋の物語も、まだまだ深まっていきそうですね。次作への期待がますます高まりました。
まとめ
宮部みゆきさんの人気シリーズ第三弾、「泣き童子 三島屋変調百物語参之続」。今回も、江戸の袋物屋・三島屋を舞台に、聞き手のおちかが人々の語る不思議な話、怖い話、そして切ない話に耳を傾けます。六つの物語は、それぞれに趣が異なり、読者を飽きさせません。
収録されているのは、人の執着が生む怪異譚「魂取の池」、大火の記憶と友への想いが胸を打つ「くりから御殿」、罪悪感が生み出す異形の存在を描く表題作「泣き童子」、おちかが外の世界で怪談に触れる「小雪舞う日の怪談語り」、原始的な恐怖と母子の絆を描いた「まぐる笛」、そして、不思議な縁と人情が交差する「節気顔」。どの話も、ただ怖いだけでなく、人間の心の深淵や、温かな感情を描き出しています。
特に「まぐる笛」の凄惨な描写や、「くりから御殿」の切なさ、「節気顔」に登場する謎の人物など、印象に残る場面が多くありました。おちかの心の成長も丁寧に描かれており、シリーズを通しての楽しみも増しています。怖い話が苦手な方でも、きっと心惹かれる物語が見つかるはず。江戸の情緒と怪異譚が好きな方、そして何より、人の心の機微に触れる物語を読みたい方におすすめしたい一冊です。































































