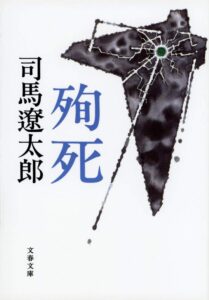 小説「殉死」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。司馬遼太郎さんが描く、日露戦争の英雄でありながら、その生涯を自ら閉じた陸軍大将・乃木希典。彼の人生は、まさに光と影、栄光と苦悩が交錯するものでした。
小説「殉死」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。司馬遼太郎さんが描く、日露戦争の英雄でありながら、その生涯を自ら閉じた陸軍大将・乃木希典。彼の人生は、まさに光と影、栄光と苦悩が交錯するものでした。
本作「殉死」は、単なる英雄譚ではありません。むしろ、その内面に深く切り込み、一人の人間としての乃木希典の姿を浮き彫りにしていきます。軍人としての評価、明治天皇への忠誠、そして妻・静子との最期。司馬さんの鋭い視点が、歴史の裏側に隠された真実を照らし出そうと試みています。
この記事では、まず物語の筋道を追いながら、乃木希典がどのように生きたのか、そしてなぜ殉死という道を選んだのか、その背景にある出来事や心情を詳しく見ていきます。物語の核心に触れる部分もありますので、その点はご承知おきください。
そして、後半では、私がこの「殉死」を読んで何を感じ、何を考えたのか、率直な気持ちを詳しくお話ししたいと思います。乃木希典という人物、そして彼が生きた時代について、一緒に深く考えてみませんか。
小説「殉死」のあらすじ
物語は、明治の軍人、乃木希典の生涯を追います。彼は長州藩の出身で、縁あって若くして陸軍少佐となります。吉田松陰門下の系譜にも連なり、藩閥の恩恵もあって順調に歩みを進めるかに見えました。しかし、西南戦争での熊本鎮台赴任中、薩摩軍との戦いで敗走し、軍旗を奪われるという痛恨の失敗を経験します。
この軍旗喪失事件は、乃木希典の心に深い傷を残し、彼のその後の人生観、特に精神主義的な側面を形作っていく大きな要因となります。自責の念に駆られ、死をも願うほどの苦悩を抱えながらも、彼は軍人としての道を歩み続けます。この事件は、皮肉にも彼の名を世に知らしめ、軍内部でのある種の評価にも繋がっていきました。
その後、東京での連隊長勤務を経て、乃木希典はドイツへ留学する機会を得ます。この留学は、彼の生活様式や考え方に大きな変化をもたらし、まるで別人のようになって帰国したと言われています。しかし、軍事的な才能という点では、同行した川上操六や、後にライバルとも目される児玉源太郎のような評価は得られませんでした。
日露戦争が勃発すると、乃木希典は当初、第一線から外れていましたが、旅順要塞攻略という困難な任務を担う第三軍司令官に任命されます。近代的な要塞に対する知識や経験が乏しい日本陸軍にとって、この攻略戦は熾烈を極めました。乃木希典自身も、当初の楽観的な見通しが誤りであったことを痛感させられます。
参謀長・伊地知幸介との連携も円滑とは言えず、正面からの強行突破に固執した結果、膨大な数の将兵が犠牲となりました。海軍からの二〇三高地攻略の要請もなかなか受け入れられず、戦況は泥沼化します。この間、乃木は長男・勝典の戦死という悲報にも接しますが、それを表に出すことはありませんでした。
ついに状況を打開するため、満州軍総参謀長であった児玉源太郎が現地に乗り込み、事実上、指揮権を掌握します。児玉の指揮のもと、二〇三高地は陥落し、旅順要塞攻略の道筋が見えました。この劇的な展開の後、乃木希典は降伏したロシア軍司令官ステッセルとの「水師営の会見」に臨み、その紳士的な態度は世界中から称賛され、「武士道の鑑」として名を高めることになります。しかし、その裏には、多くの犠牲と、司令官としての苦い経験がありました。
小説「殉死」の長文感想(ネタバレあり)
司馬遼太郎さんの「殉死」を読むと、いつも複雑な気持ちになりますね。乃木希典という人物は、日露戦争の英雄として、また明治天皇に殉じた忠臣として、非常に有名な存在です。しかし、司馬さんは、彼を手放しで称賛するのではなく、むしろ軍事指揮官としては「ほとんど無能にちかかった」とまで断じています。この厳しい評価が、作品全体に流れる基調となっています。
「坂の上の雲」でもそうでしたが、司馬さんの乃木希典に対する視線は一貫して冷徹です。ただ、それは単なる批判や非難とは少し違うように感じます。むしろ、なぜそのような人物が「軍神」として祭り上げられ、多くの人々から敬愛されたのか、その構造自体に深く切り込もうとしているのではないでしょうか。乃木希典個人の資質の問題だけでなく、彼を取り巻く時代や社会、そして日本陸軍という組織が抱えていた問題を、彼の生涯を通して描き出そうとしているように思えるのです。
西南戦争での軍旗喪失事件。これは乃木にとって生涯忘れられない汚点であり、同時に彼の精神性を決定づけた出来事でした。軍旗を神聖視する風潮は、この事件以降、帝国陸軍内でより強まったと司馬さんは指摘します。責任感の強さ、潔癖さ、そしてある種の自己演出。乃木の中にあったこれらの要素が、失敗を経験することで、さらに純化され、硬直化していったのかもしれません。
ドイツ留学を経て「別人になった」という記述も興味深いです。規律正しさや質素倹約を徹底する姿は、ある意味で模範的な軍人の姿かもしれません。しかし、それが戦術眼や柔軟な思考に結びつかなかったところに、彼の限界があったのでしょうか。司馬さんは、乃木が軍事技術よりも「自分美の求道者」であったと評しています。戦場にあっても詩を詠み、自らの不運に感動する。その姿は、美しくもあるけれど、同時に危うさも感じさせます。
そして、日露戦争、旅順攻囲戦です。近代要塞に対する認識の甘さ、参謀・伊地知幸介の無能さ(司馬さんはかなり手厳しいですね)、そして正面攻撃への固執。多くの犠牲者を出したこの戦いは、乃木希典の指揮官としての評価を決定づけるものとなりました。海軍が早期から指摘していた二〇三高地の重要性をなかなか認めなかった判断は、戦略眼の欠如と言わざるを得ません。
ここで対比的に描かれるのが、児玉源太郎です。同じ長州出身でありながら、藩閥の恩恵に頼らず実力で道を切り拓き、卓越した戦術眼を持っていたとされる児玉。彼が颯爽と現れ、膠着した戦況を打開する場面は、乃木の限界を際立たせる効果を持っています。児玉が乃木を長年庇ってきたという関係性も、物語に深みを与えていますね。結果的に、児玉の介入によって旅順は陥落しますが、その功績は乃木のものとして語られる部分も大きい。このあたりの歴史の皮肉も、司馬さんは逃しません。
しかし、水師営の会見で見せた乃木の態度は、世界中から称賛されました。敗者に対する寛容さ、武士道精神の体現者としての姿。ここに、乃木希典という人間の持つもう一つの側面、つまり「人格者」としての魅力が現れます。軍事的な能力とは別に、彼の持つ清廉さや誠実さ、そしてある種の悲劇性が、人々を引きつけたのではないでしょうか。司馬さんも、軍人としては厳しく評価しつつも、その人間的な美徳を完全に否定しているわけではないように感じます。
「殉死」の後半は、明治天皇との関係と、その最期に焦点が当てられます。乃木は、西南戦争での失敗にもかかわらず、明治天皇から深い信頼を得ていました。天皇は、乃木の持つ古武士的な愚直さ、誠実さに惹かれたのかもしれません。乃木もまた、天皇に絶対的な忠誠を誓い、仕えることに喜びを見出していました。学習院院長としての乃木は、皇族や華族の子弟教育に情熱を注ぎますが、その厳格すぎる教育方針は、時に反発も招いたようです。
そして、明治天皇の崩御。乃木にとって、それは自らの存在理由が失われるほどの衝撃だったのでしょう。大喪の日に、妻・静子とともに自刃するという選択。この殉死は、当時の社会に大きな衝撃を与え、森鴎外の「興津弥五右衛門の遺書」や夏目漱石の「こころ」にも影響を与えたと言われています。司馬さんは、その最期の様子を、警察の検死調書なども参考にしながら、克明に、しかしどこか抑制された筆致で描いています。
妻・静子の最期については、多くの謎が残ります。薩摩出身の彼女は、長州出身の夫とは違う気質を持っていたかもしれません。二人の息子を戦争で失い、夫が殉死を決意した時、彼女は何を思ったのでしょうか。司馬さんは、当初、乃木に静子を道連れにする意思はなかった可能性を示唆しつつ、最終的に二人が共に死を選んだ経緯を推察しています。そこには、夫婦としての深い絆があったのか、あるいは時代の空気や武家の妻としての覚悟があったのか。想像するしかありませんが、その壮絶な場面は胸に迫ります。
司馬さんは、乃木の殉死を、単なる忠誠心の表れとしてだけではなく、彼の「自己美学の完成」という側面からも捉えています。「棺が三つそろうまでは葬式を出すな」という言葉に象徴されるような、自分自身への演出。それは、ナルシシズムと紙一重かもしれませんが、彼にとっては譲れない生き方、死に方だったのかもしれません。現代の価値観からすれば、理解しがたい部分も多いですが、その行動の裏にある精神性を否定するだけでは、何も見えてこない気がします。
この「殉死」という作品を通して、司馬さんが問いかけているのは、単に乃木希典という個人の評価だけではないでしょう。明治という時代、近代化を急ぐ中で日本人が何を獲得し、何を失ったのか。そして、その後の昭和、特に太平洋戦争へと続く日本の歩みに、乃木的な精神主義がどのような影響を与えたのか。司馬さんは、乃木希典という存在を、昭和の日本陸軍が持つ欠陥の象徴として捉え、その思想的な源流を探ろうとした、という見方もできるかもしれません。
読み終えると、英雄か、愚将か、という単純な二元論では割り切れない、乃木希典という人間の複雑な肖像が浮かび上がってきます。そして、彼が生きた時代、彼が下した決断について、深く考えさせられます。司馬さんの、歴史を見る複眼的な視点、そして人間に対する深い洞察力が、この短い作品の中に凝縮されているように感じます。私たち現代人が、過去の歴史とどう向き合うべきか、そのヒントを与えてくれる一冊だと言えるでしょう。
まとめ
司馬遼太郎さんの「殉死」は、日露戦争の英雄でありながら、明治天皇に殉じて自ら命を絶った陸軍大将・乃木希典の生涯を描いた作品です。しかし、単なる伝記ではなく、司馬さん独自の鋭い視点から、乃木希典という人物の内面と、彼が生きた時代に深く切り込んでいます。
物語は、西南戦争での失敗から、ドイツ留学、そして日露戦争における旅順攻囲戦での苦闘と膨大な犠牲、児玉源太郎による事態収拾、水師営の会見での名声、そして明治天皇崩御に伴う殉死へと続きます。司馬さんは、乃木を軍事指揮官としては厳しく評価しつつも、その清廉さや誠実さといった人間的な側面にも光を当てています。
この作品を読むことで、私たちは乃木希典という一人の人間の複雑な肖像に触れることができます。英雄か愚将かという単純な評価ではなく、彼の行動の背景にある精神性、自己美学、そして彼を取り巻く明治という時代の空気を感じ取ることができます。妻・静子との壮絶な最期は、読む者に強い印象を残します。
「殉死」は、乃木希典個人の物語であると同時に、近代日本の歩み、特にその後の昭和史へと繋がる精神構造について深く考えさせられる作品です。歴史上の人物や出来事を多角的に捉え、現代に生きる私たちに問いを投げかける、司馬文学の真髄に触れることができる一冊と言えるでしょう。






































