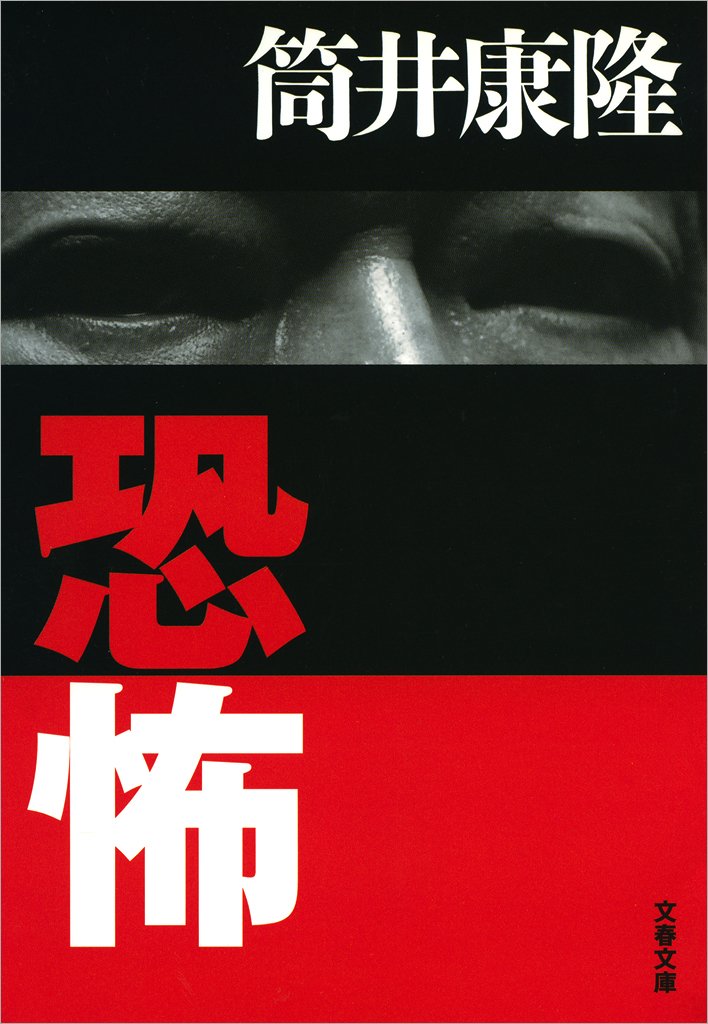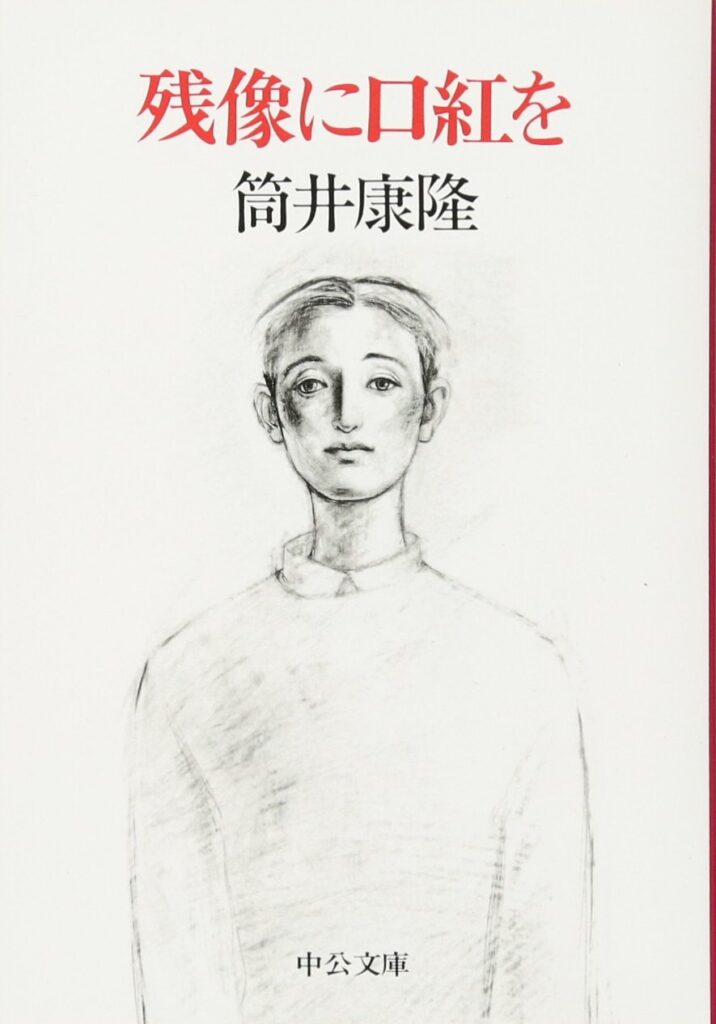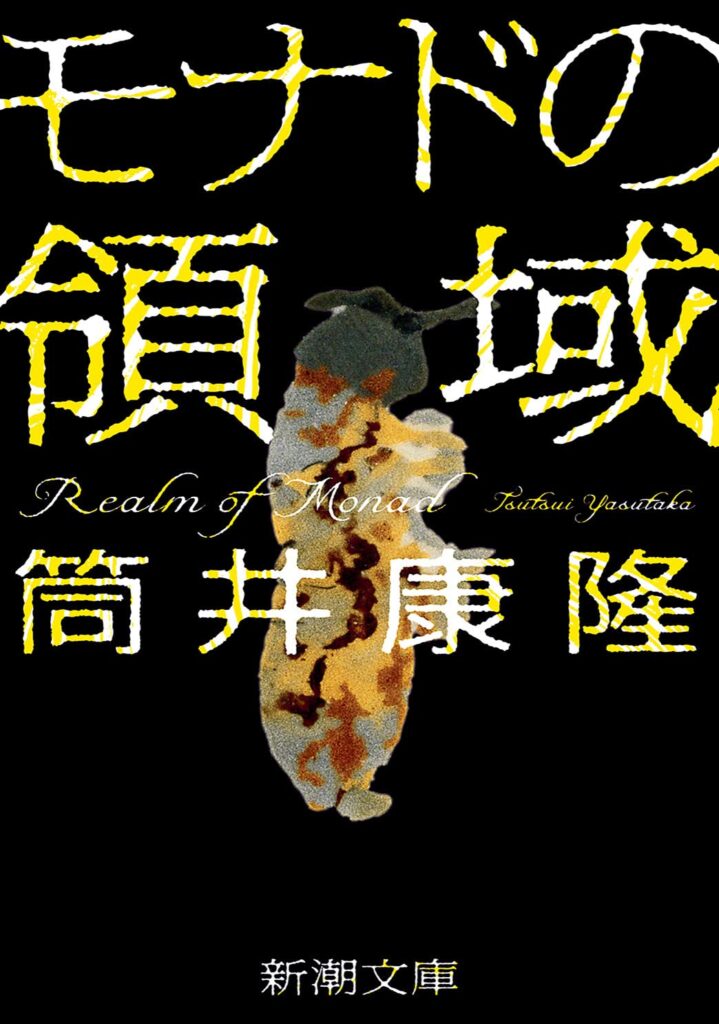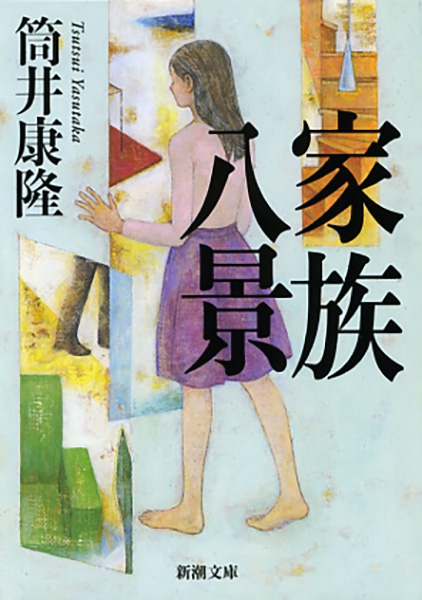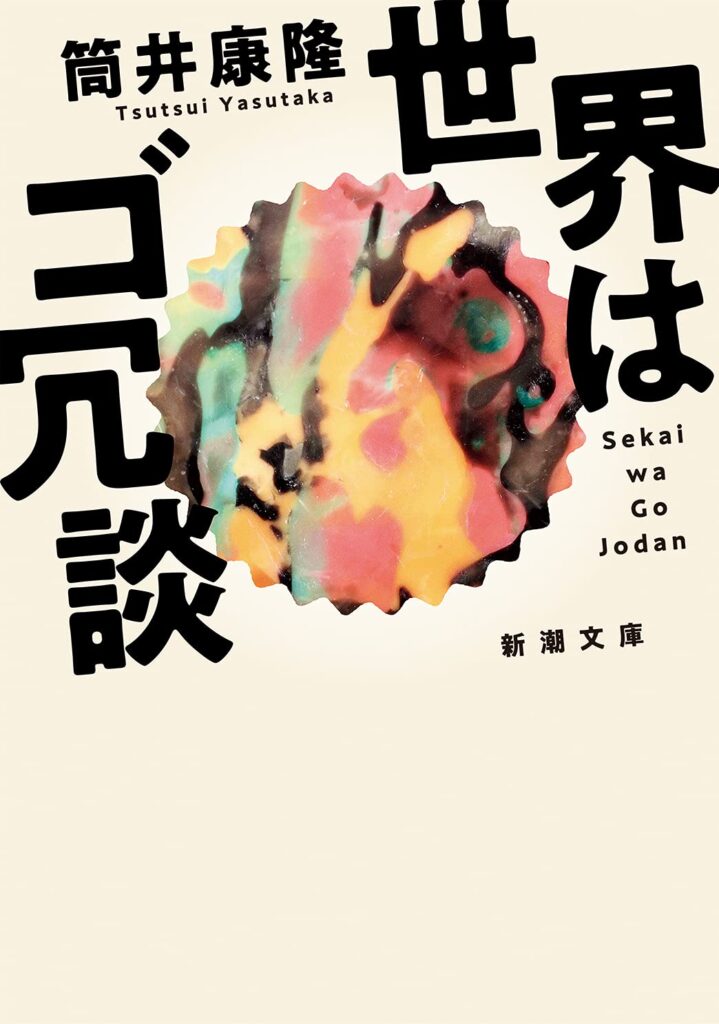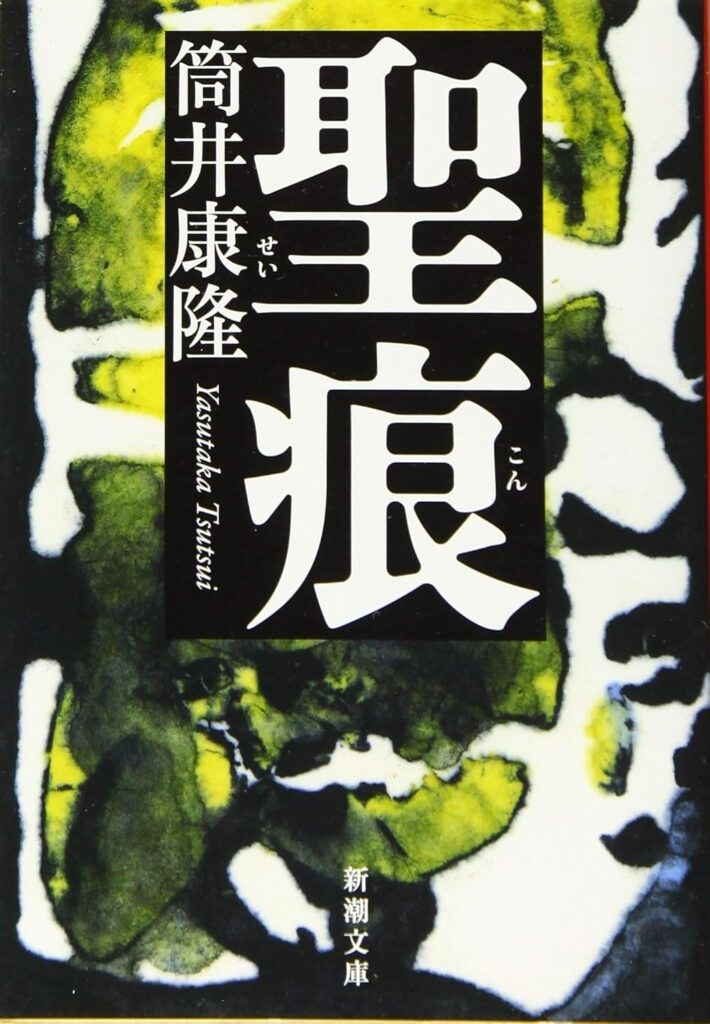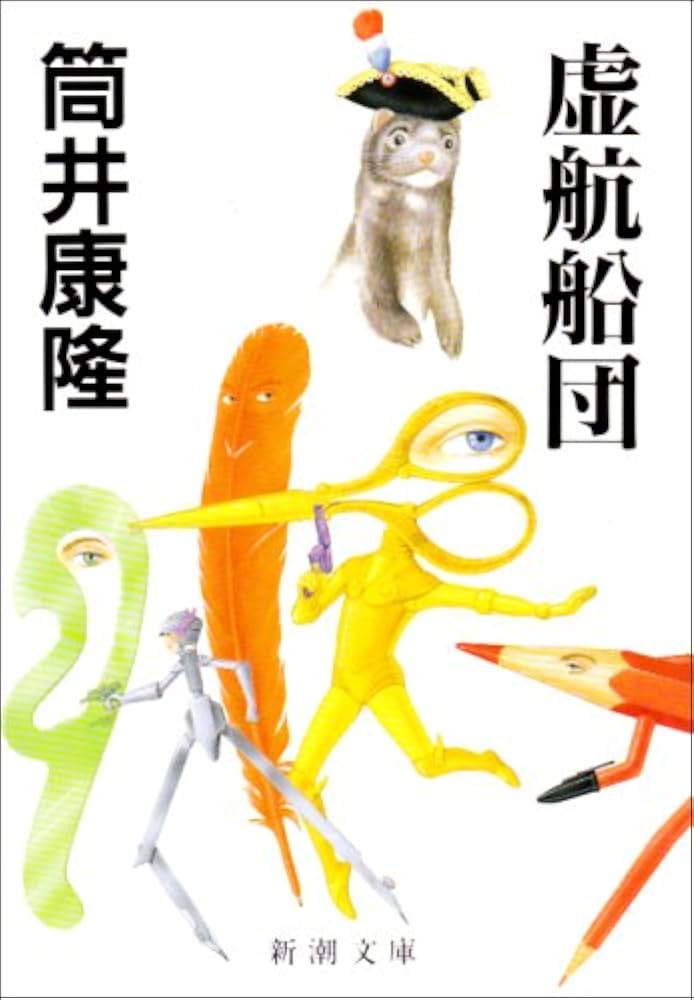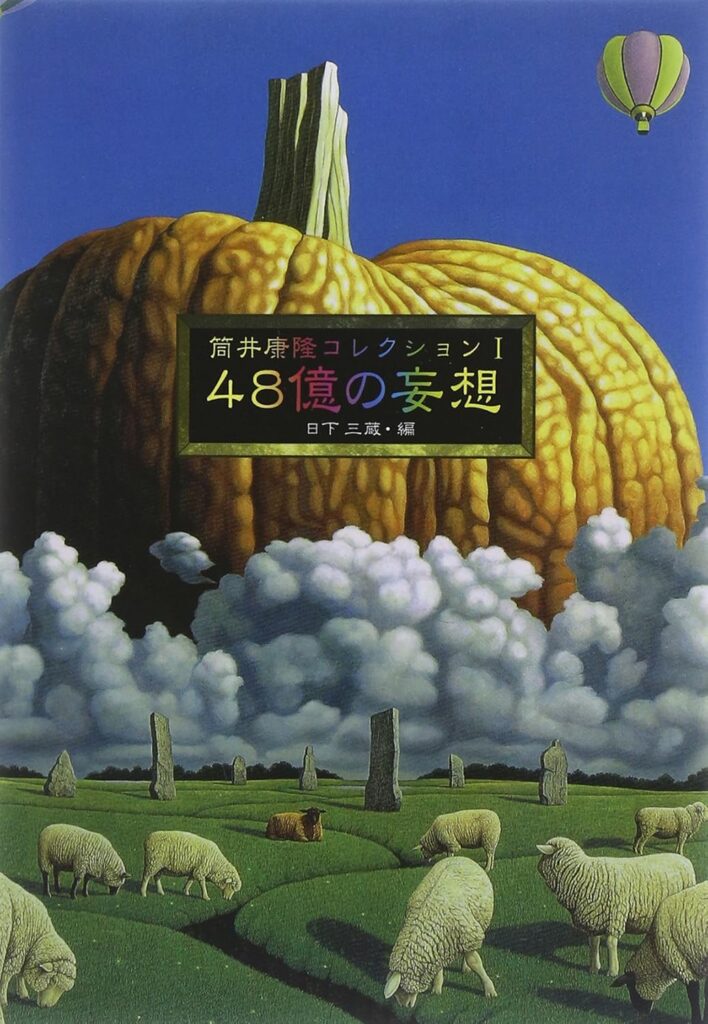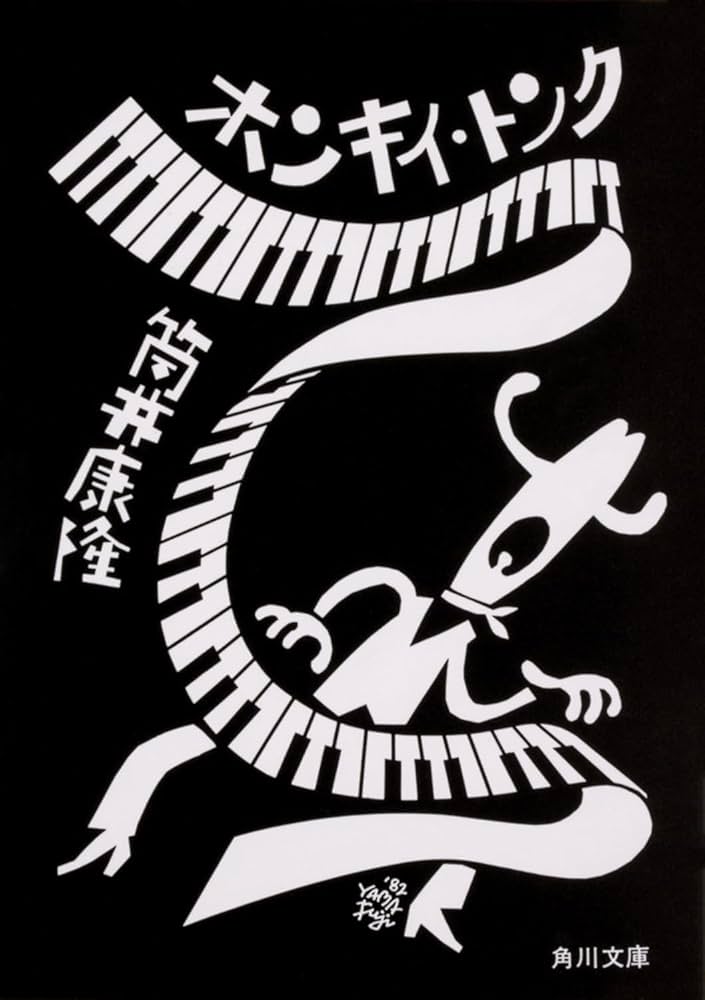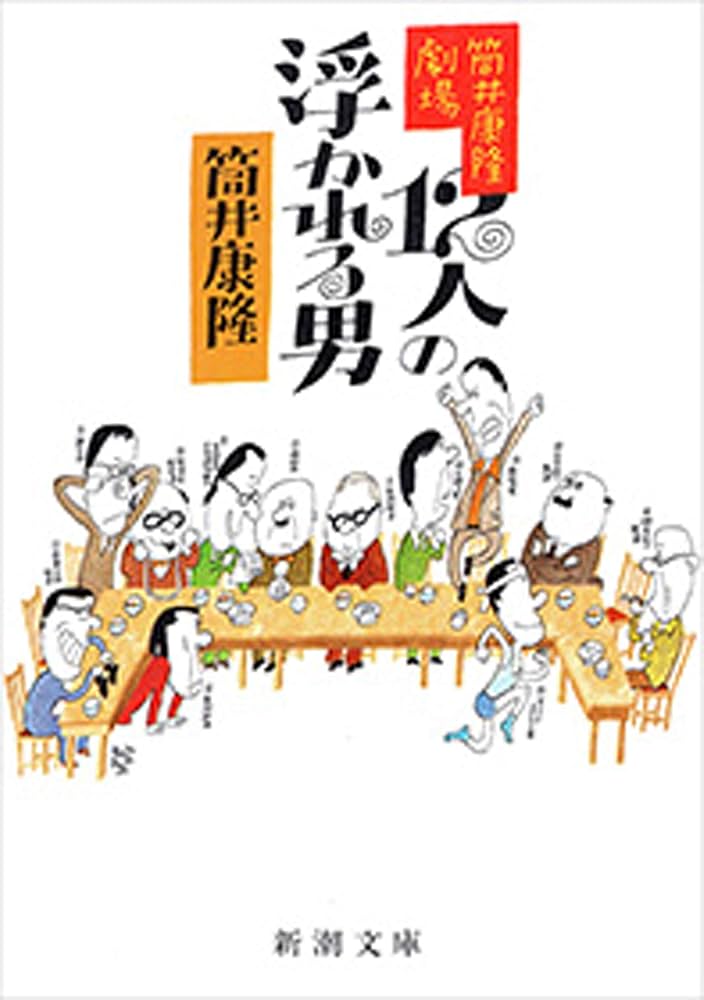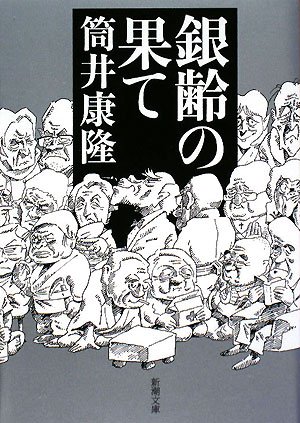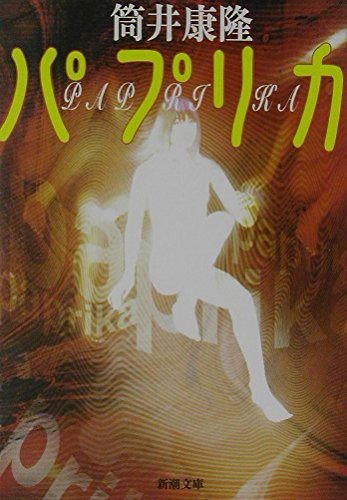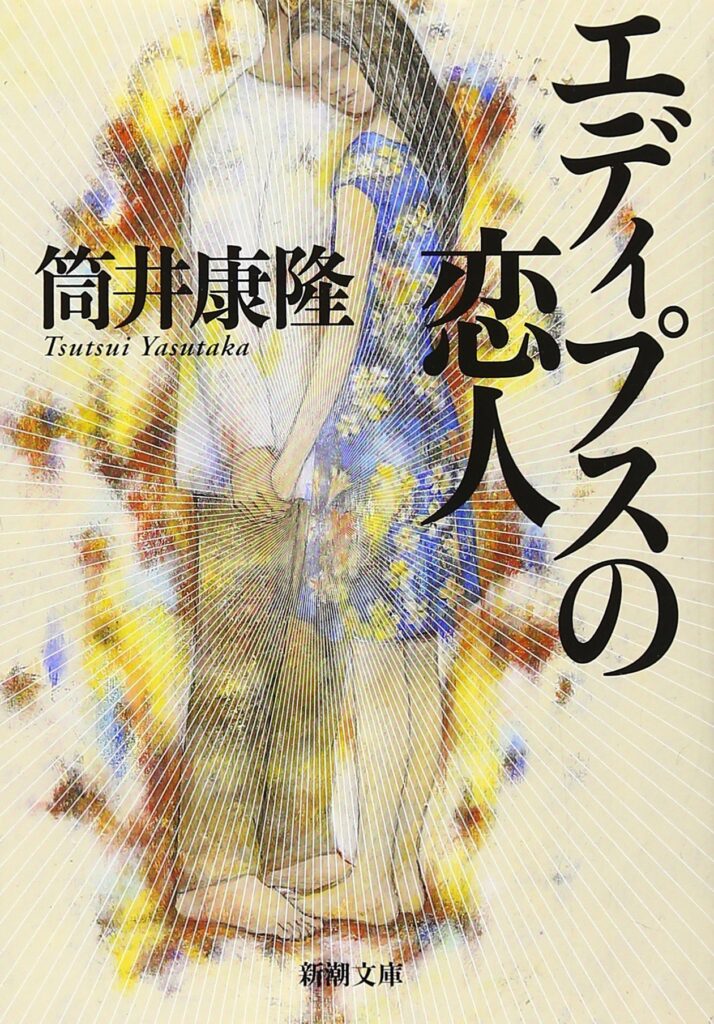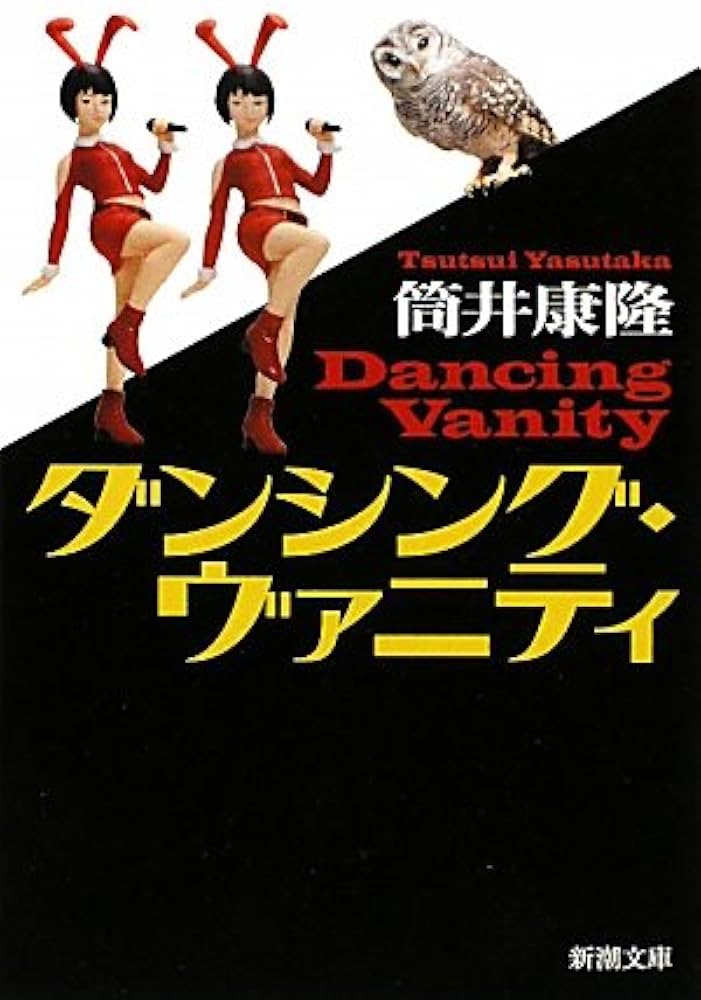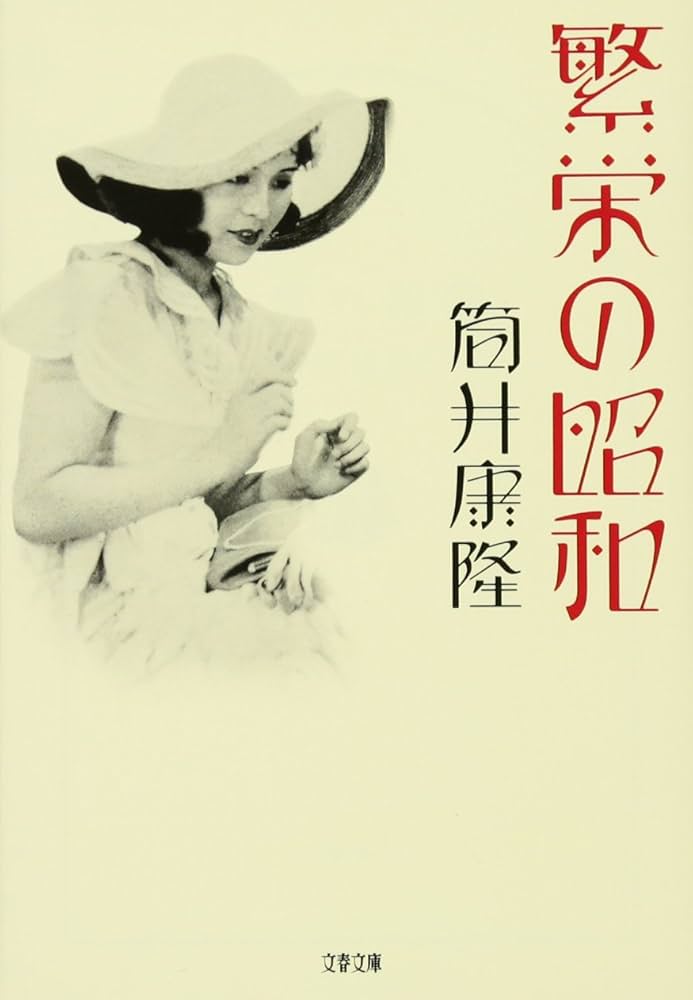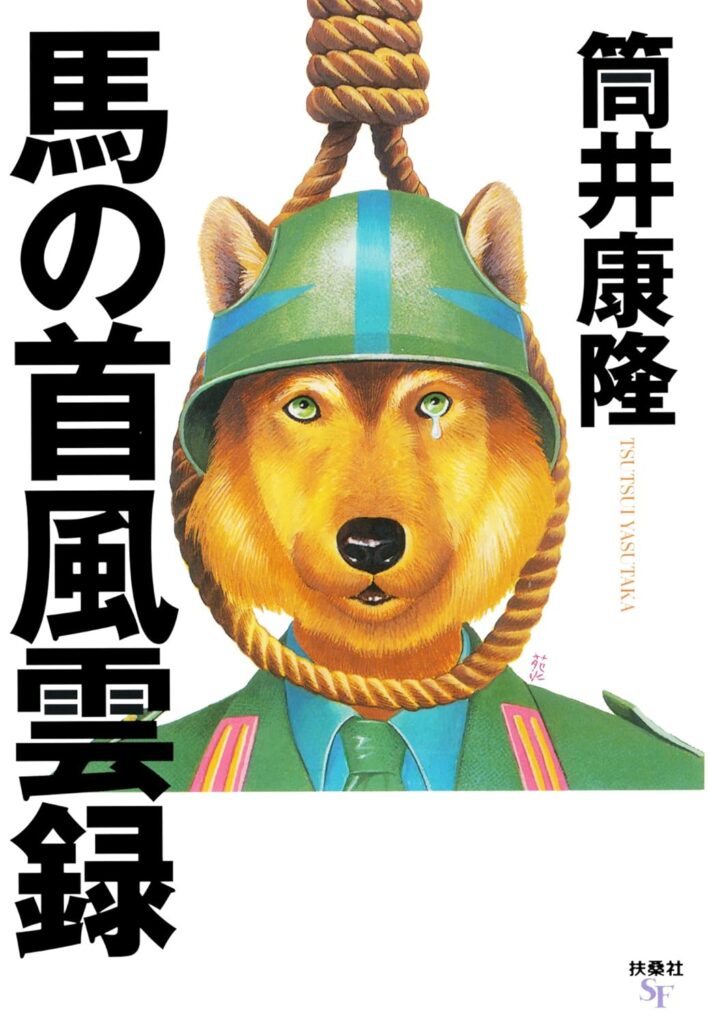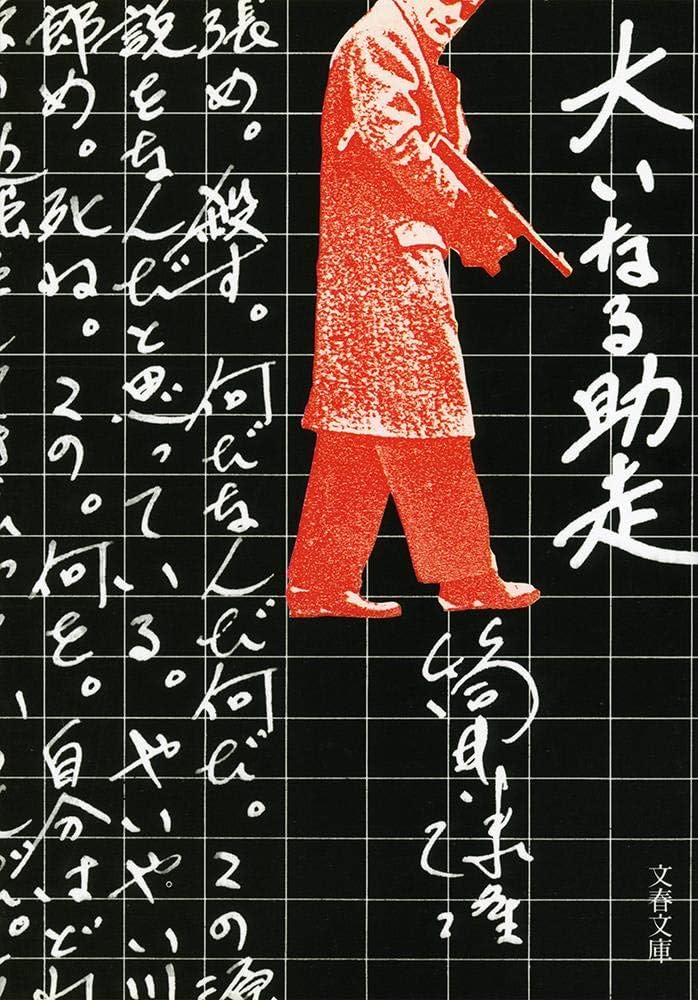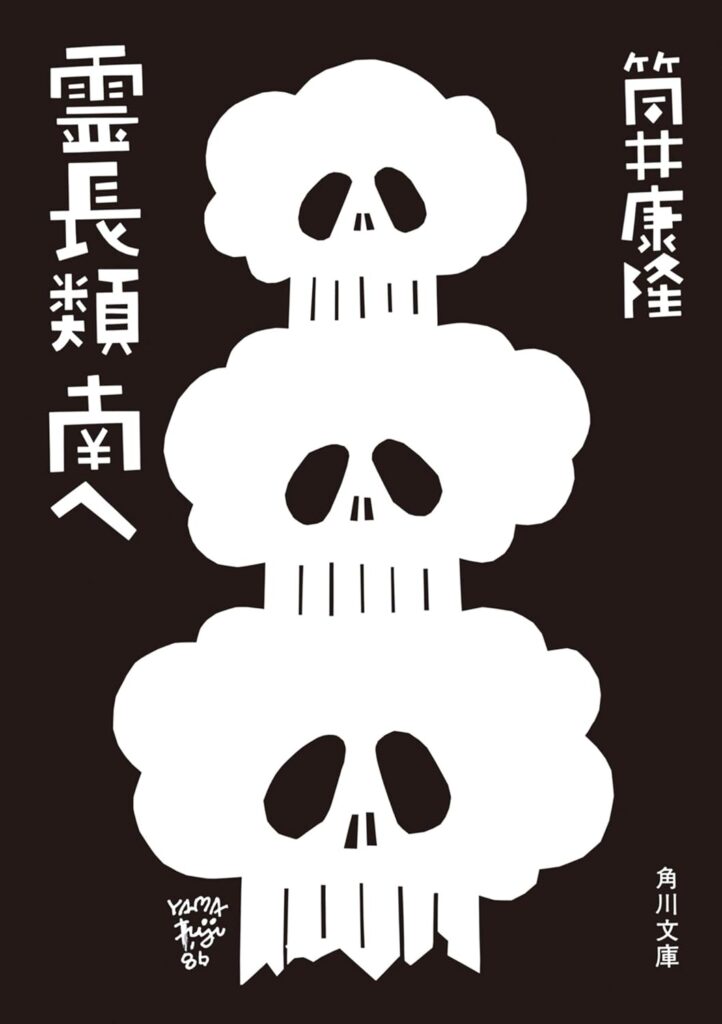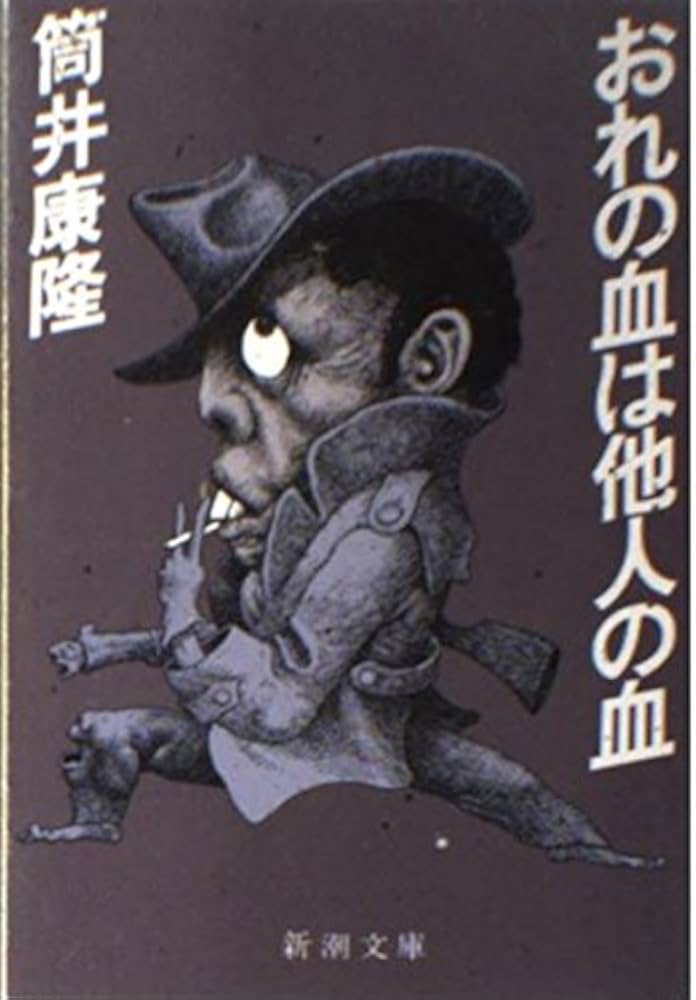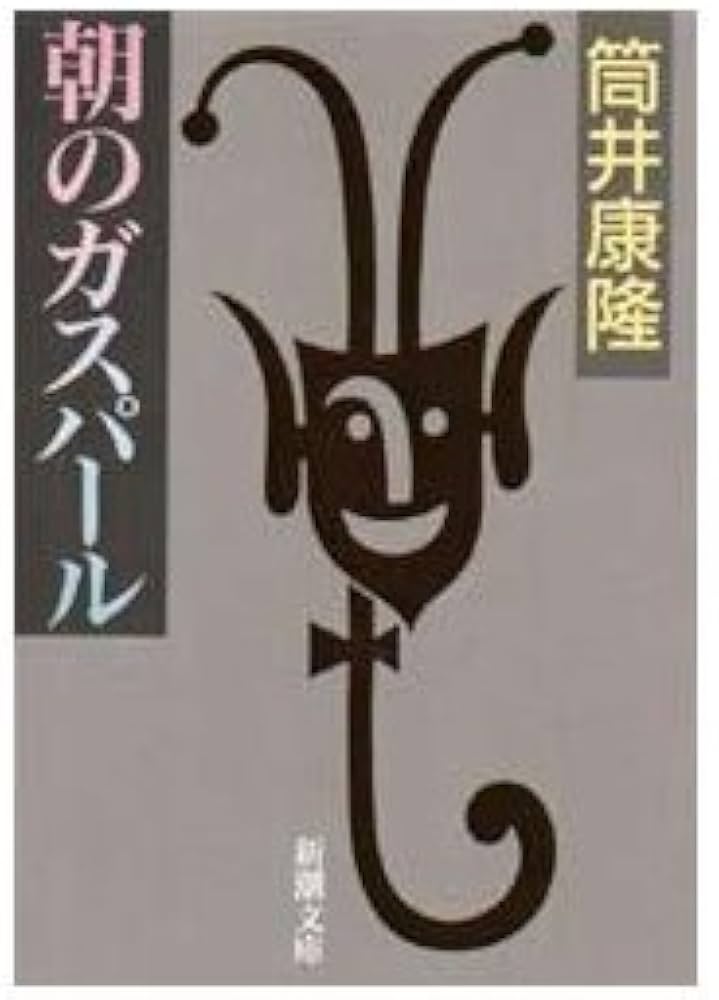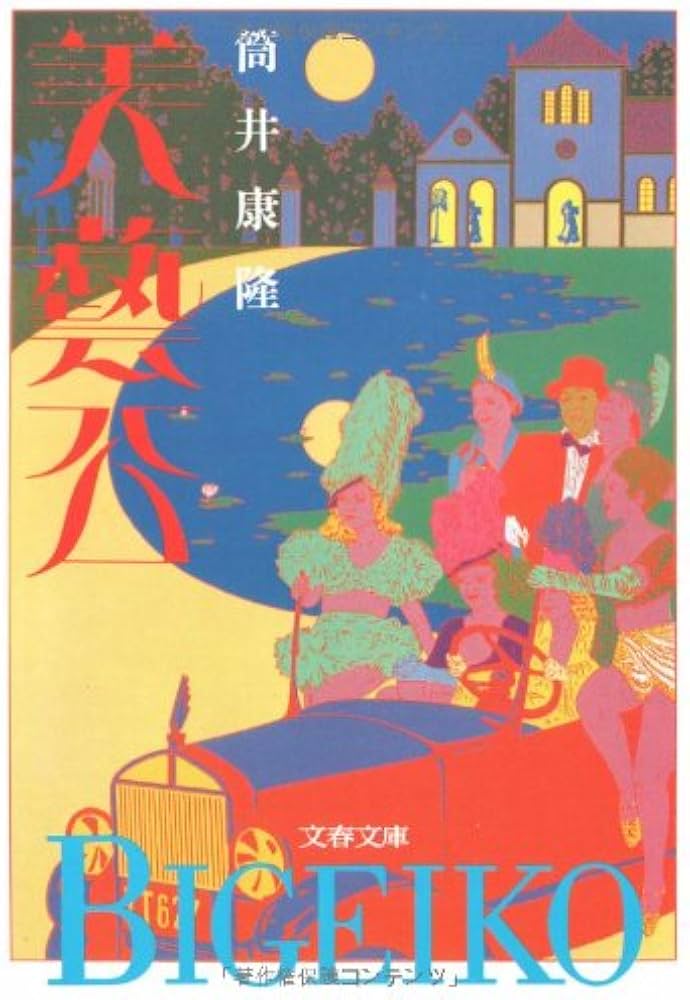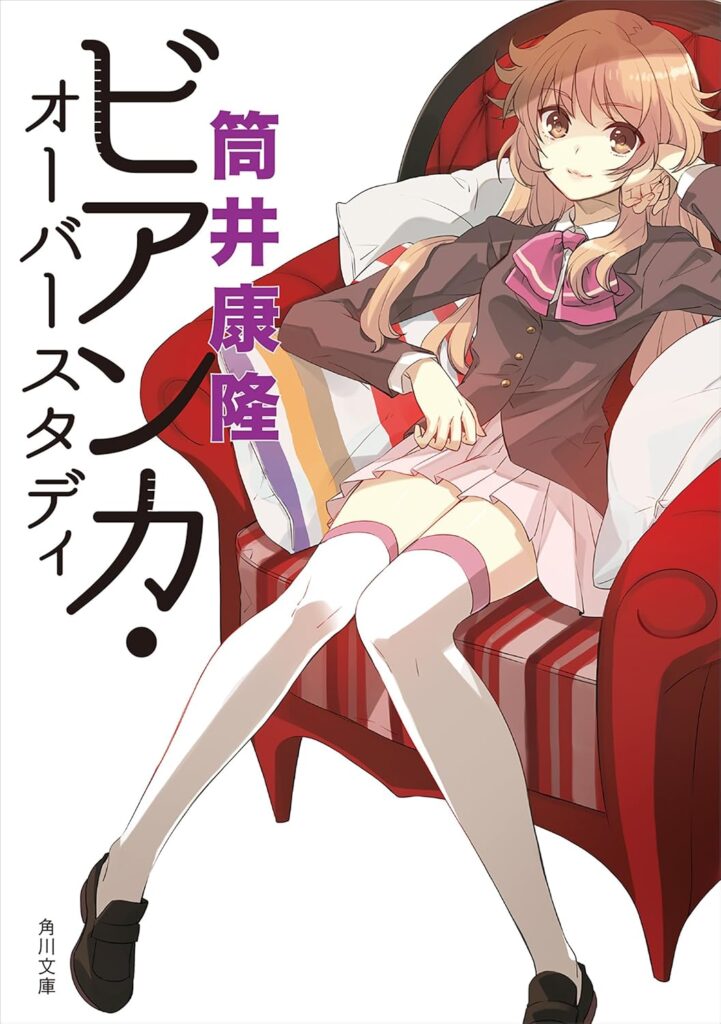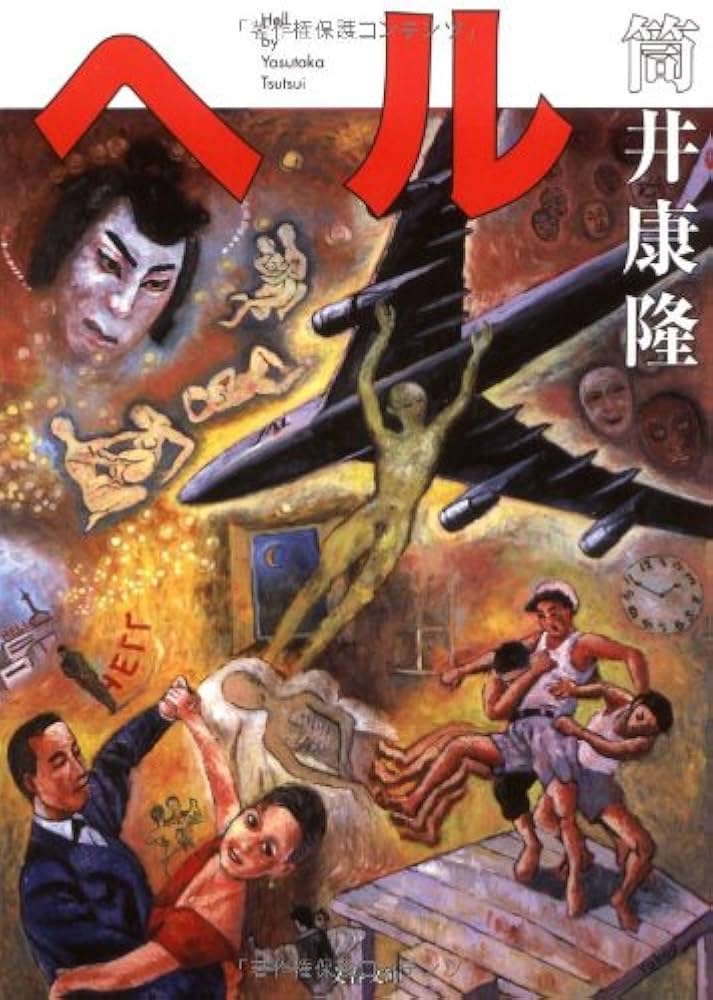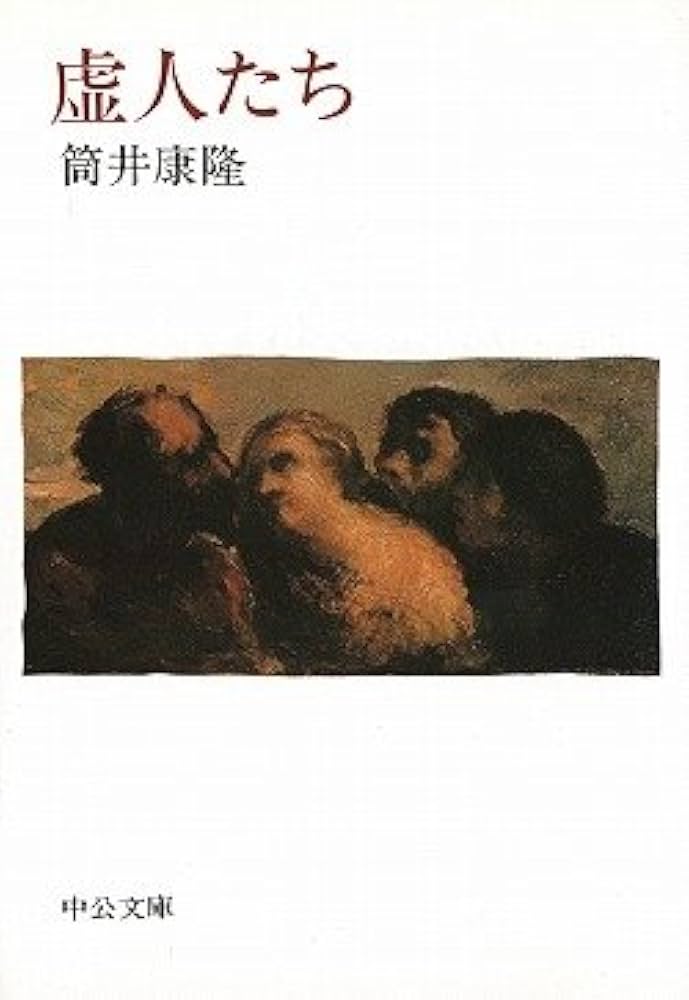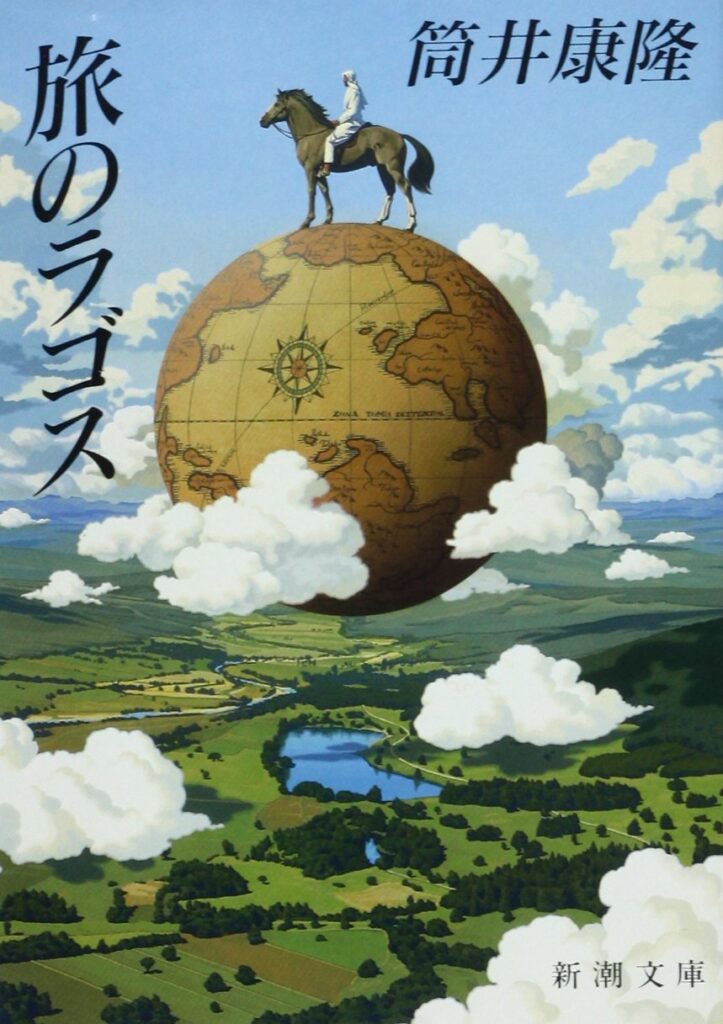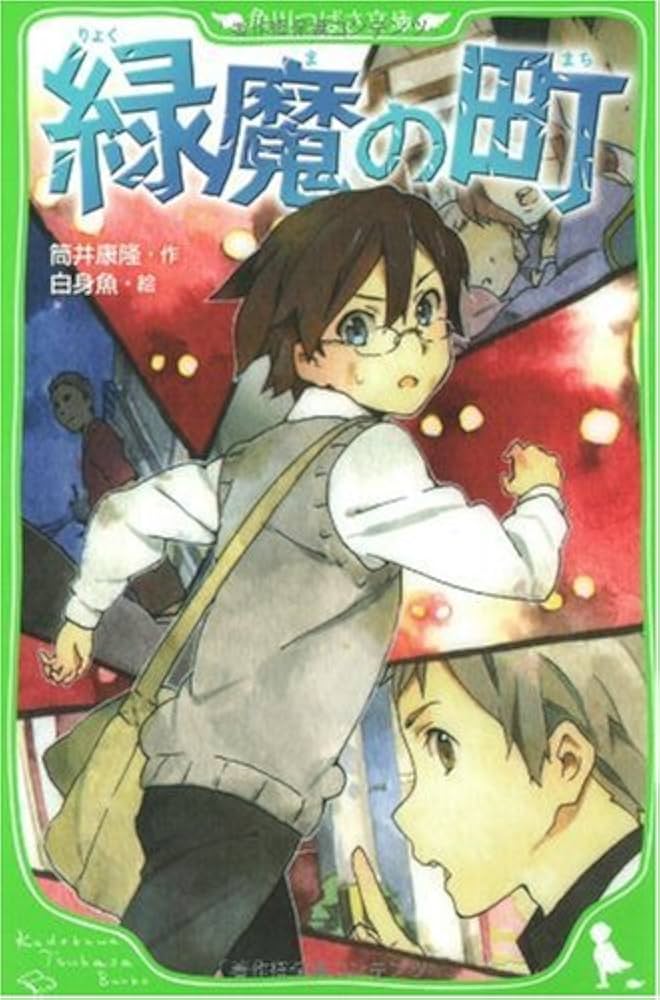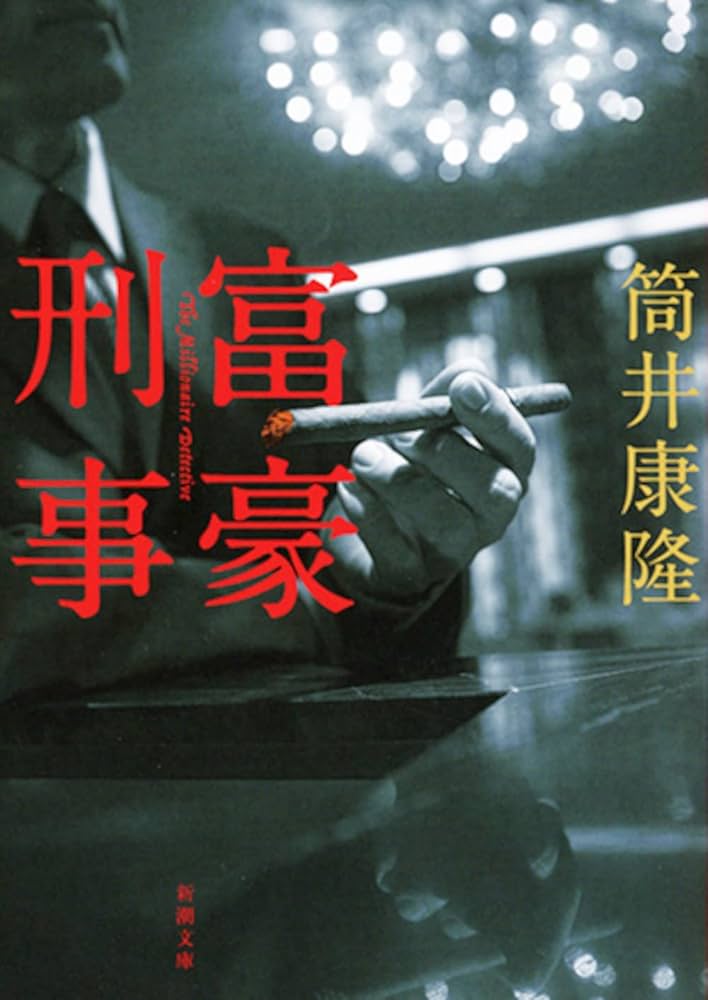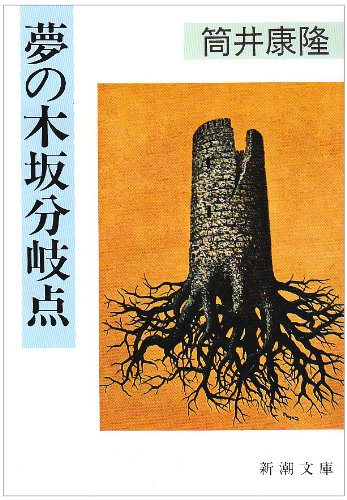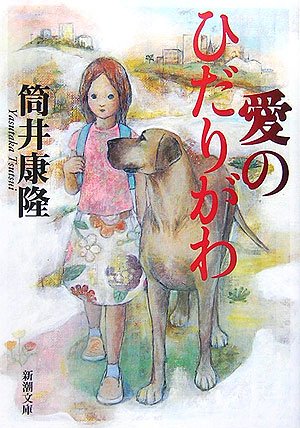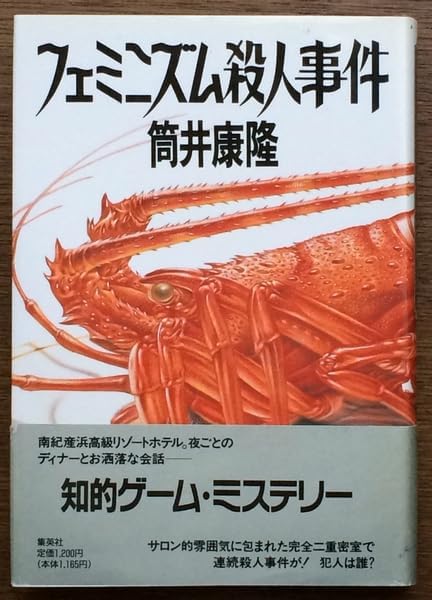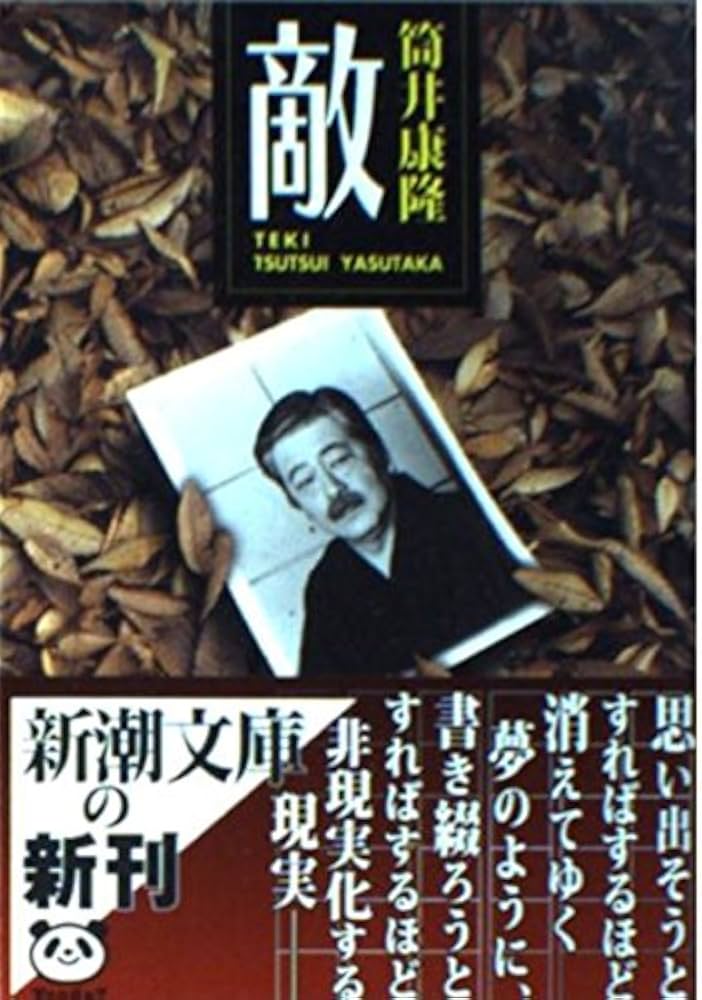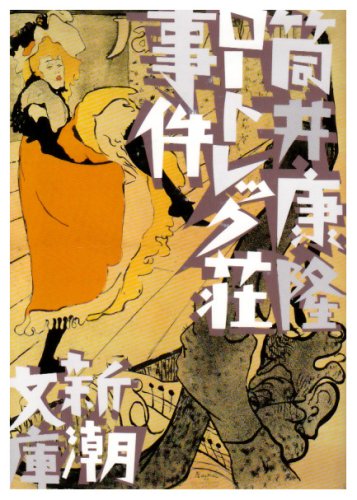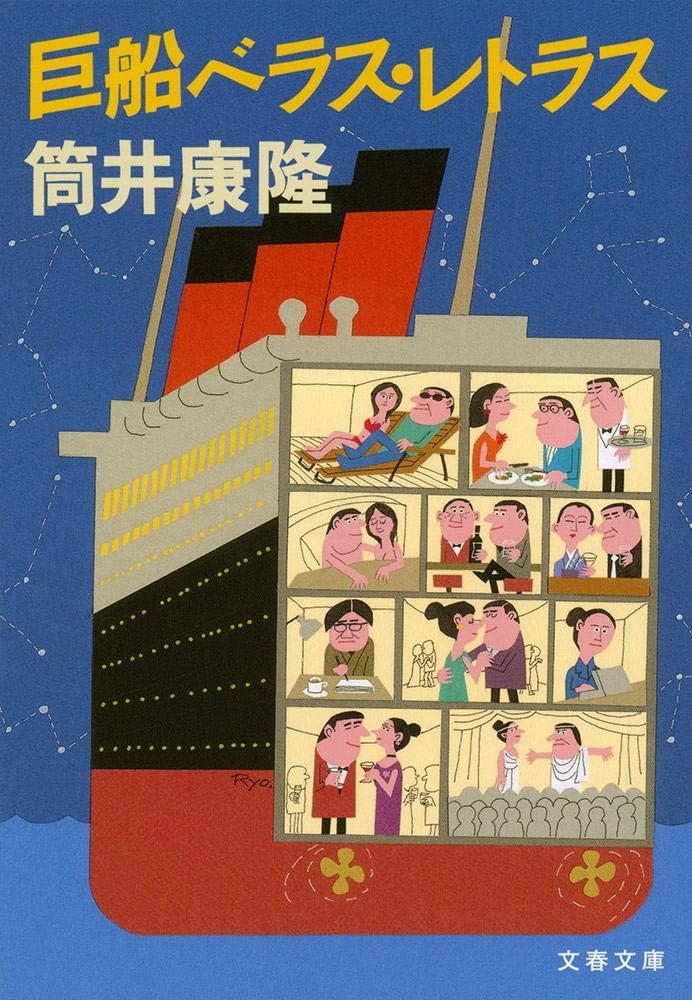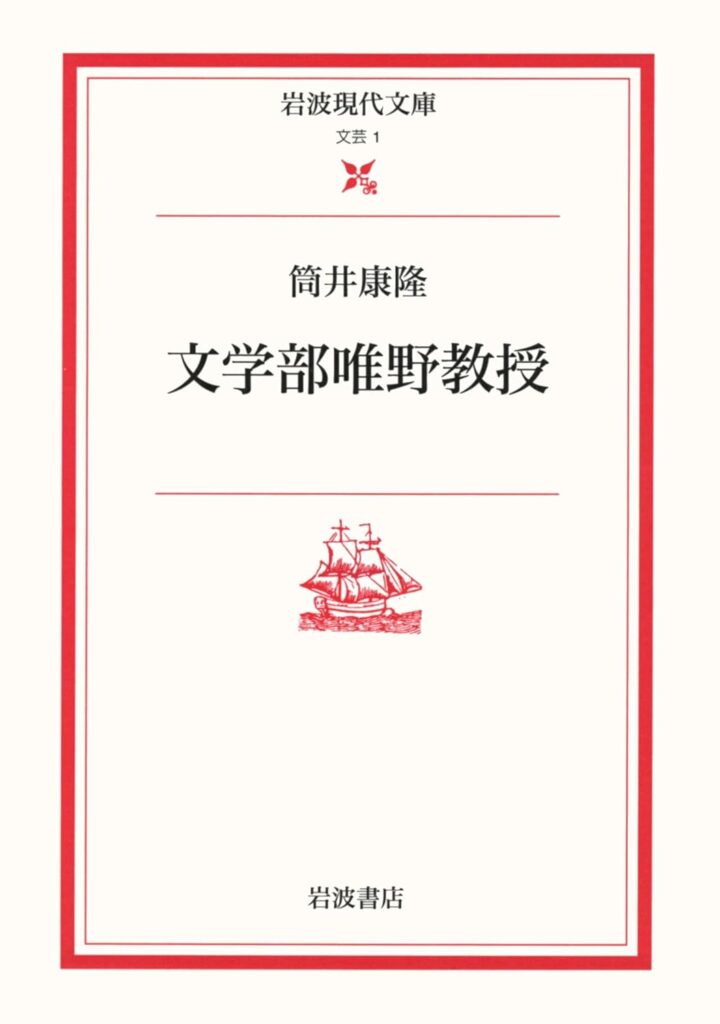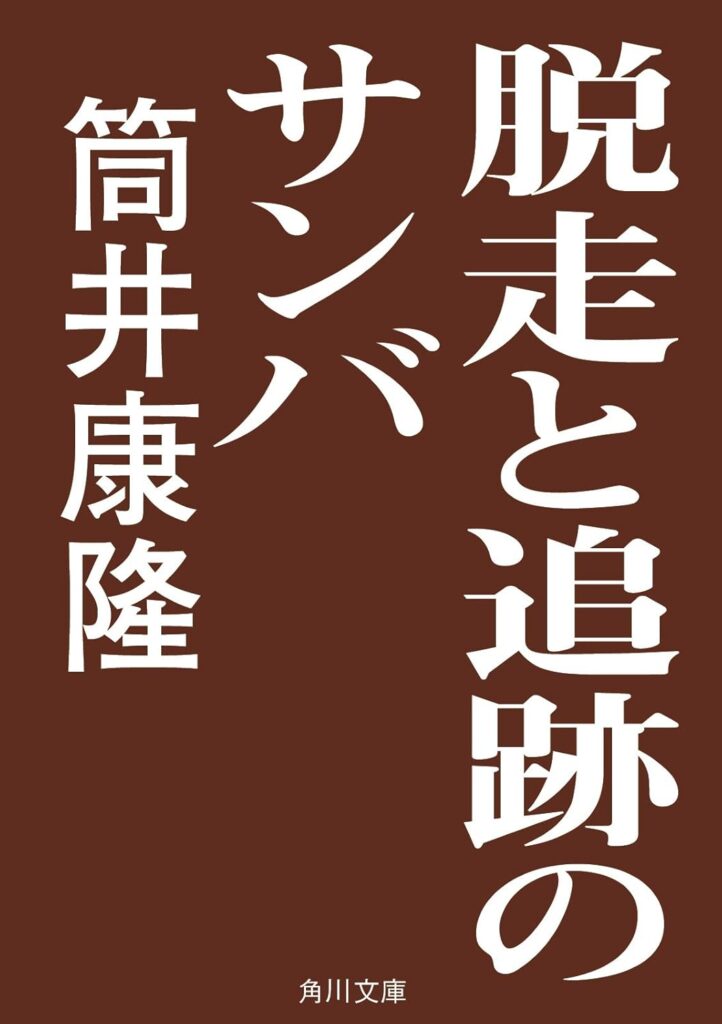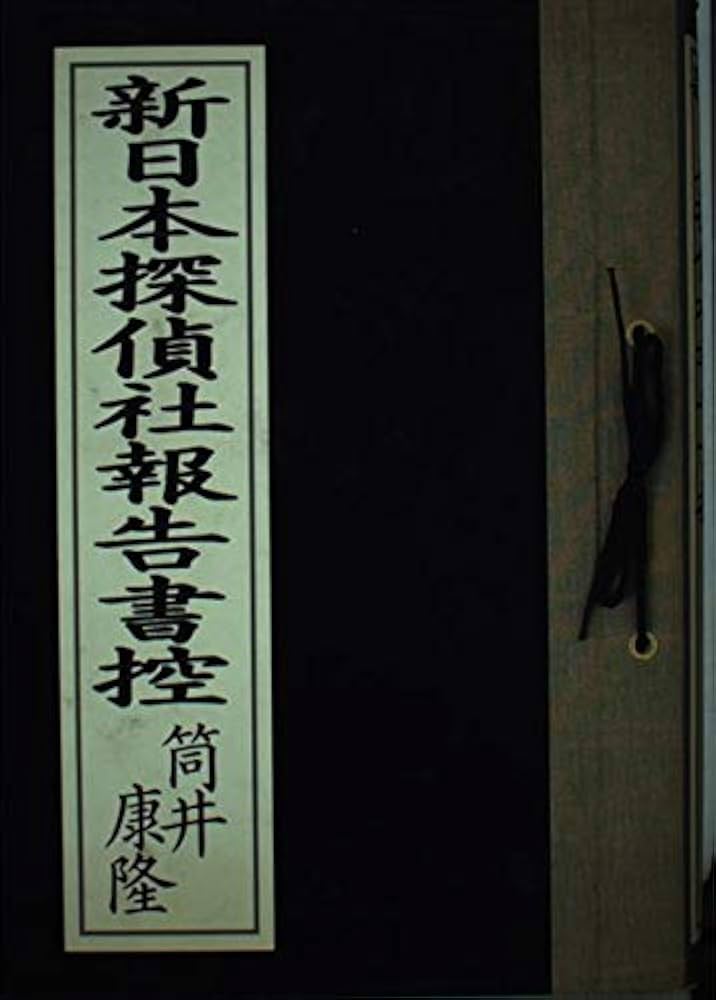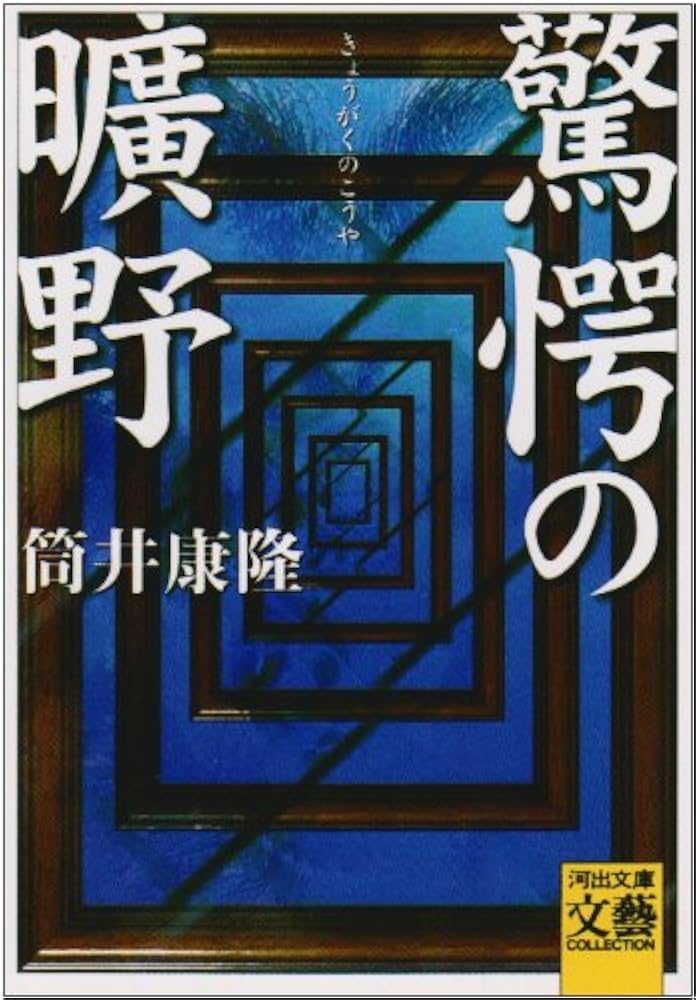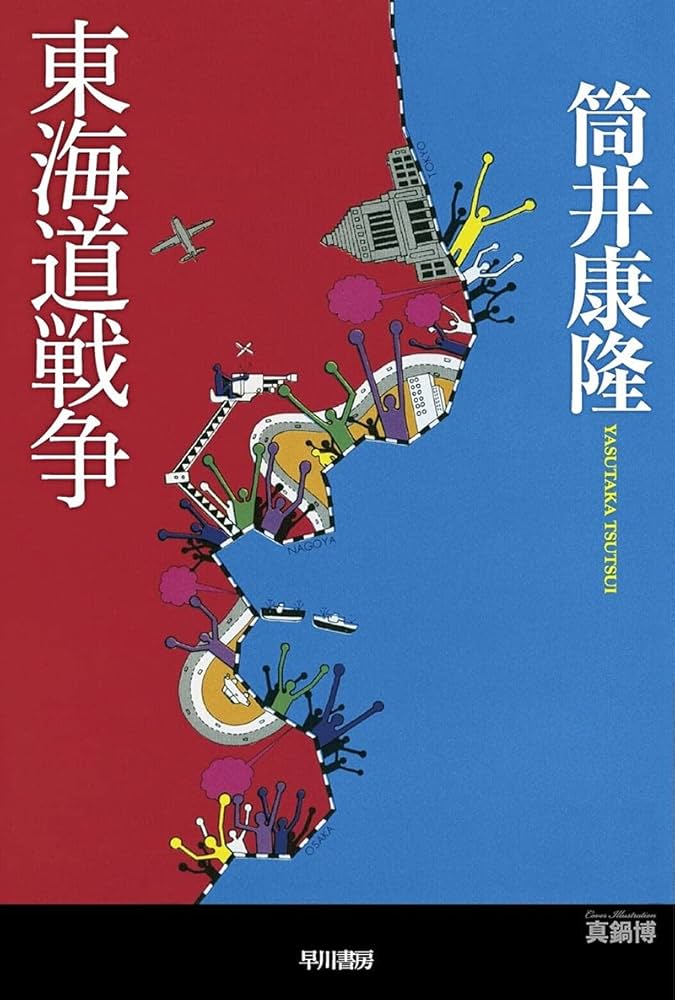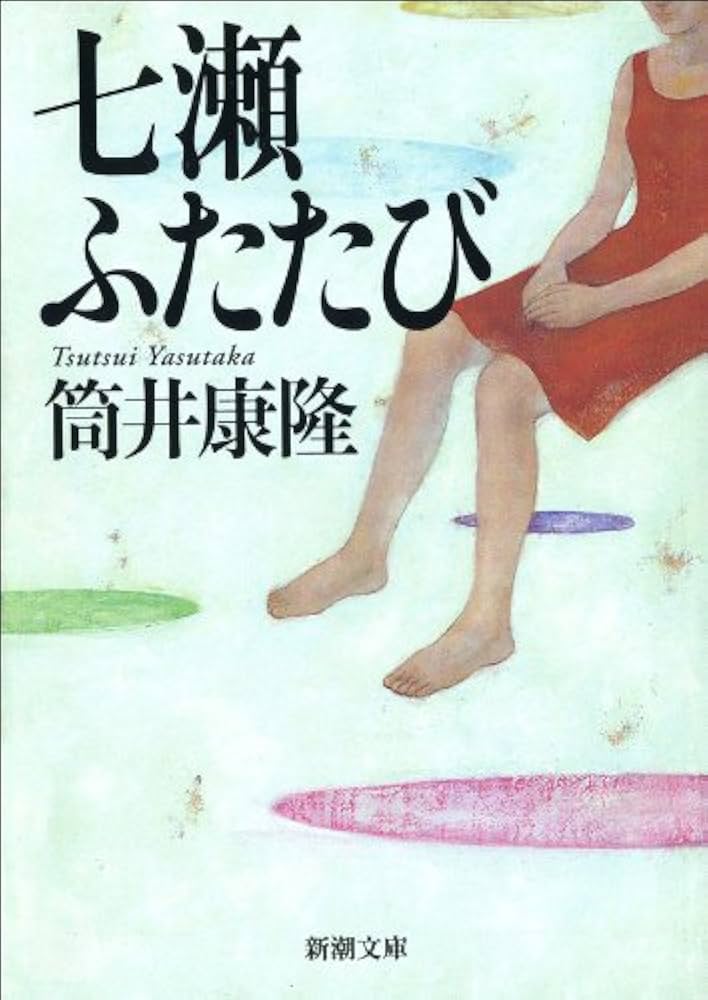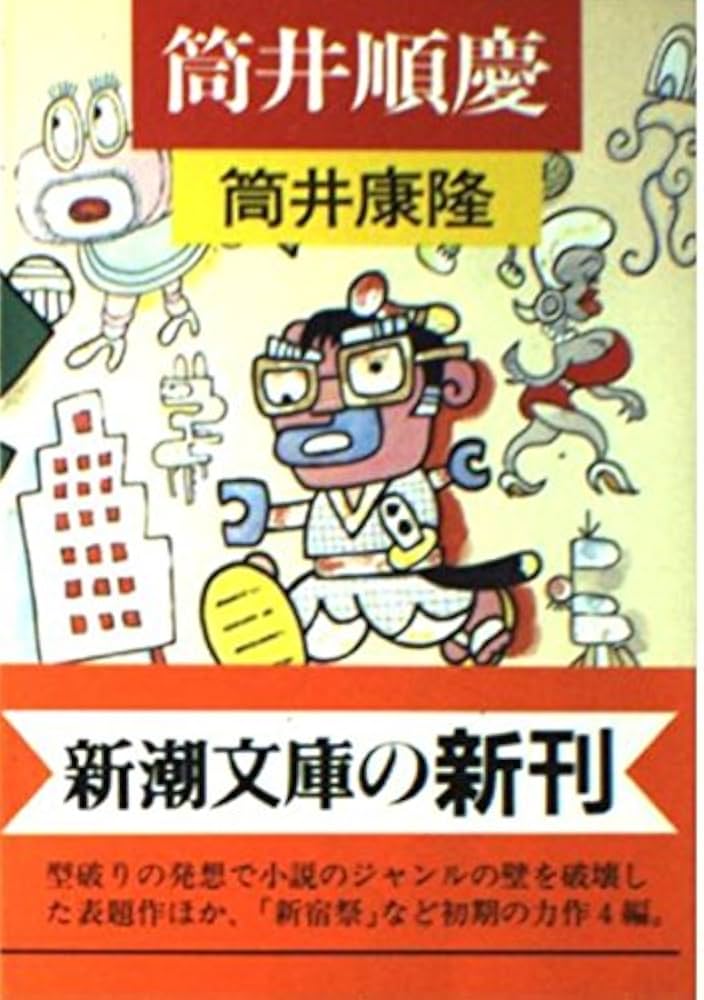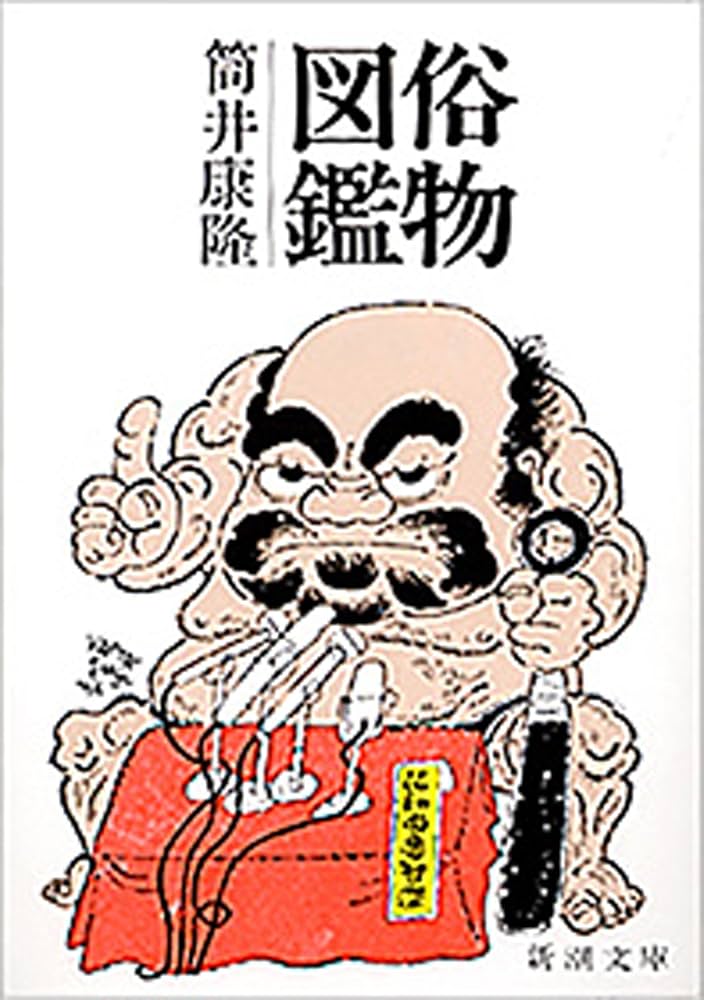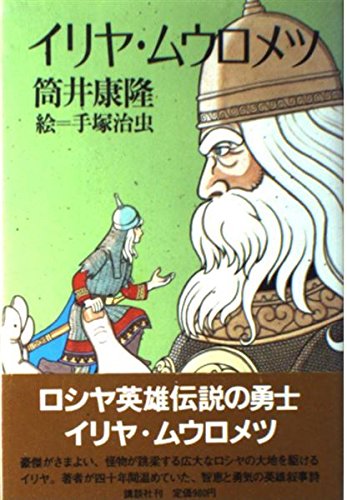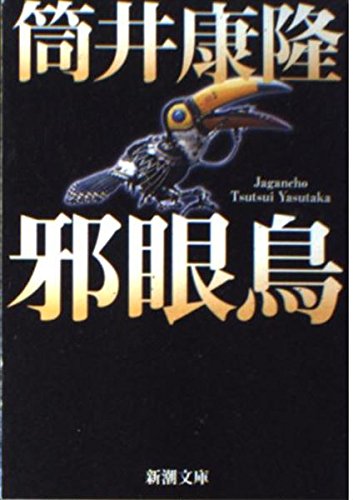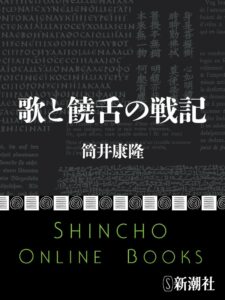 小説「歌と饒舌の戦記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「歌と饒舌の戦記」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
筒井康隆氏が1987年に発表したこの物語は、ある日突然、ソビエト連邦が北海道に侵攻してくるという、衝撃的な設定から幕を開けます。単なる架空の戦争記録ではなく、その中で繰り広げられる人々の狂騒と、飛び交う言葉の洪水を描いた、非常に密度の高い一作です。
タイトルにある「歌」と「饒舌」。この二つの言葉が、物語の全てを象徴していると言っても過言ではありません。何が真実で、何が虚構なのか。信念のこもった叫びである「歌」と、中身のない言葉の垂れ流しである「饒舌」。これらが入り乱れる戦場で、人々は何を信じ、どう行動するのでしょうか。
この記事では、まず物語の骨子となる出来事の流れを追いかけます。そして、物語の結末までを含めた詳細な解釈と、私が抱いた感情を、熱量をもって語り尽くしたいと思います。この壮大で混沌とした「戦記」の世界へ、一緒に飛び込んでいきましょう。
現代社会が抱える問題を、30年以上も前に予見していたかのような鋭い視点。読み終えた後、あなたの目に映る世界が少しだけ違って見えるかもしれません。そんな力を持つ、忘れがたい一冊についての記録です。
小説「歌と饒舌の戦記」のあらすじ
物語は、北海道の東端、納沙布岬から始まります。GRTテレビのディレクター森下義和率いる取材班は、「国境を越えて酒をせびりに来るソ連兵」という、どこかのんきな企画のために現地を訪れていました。しかし、彼らのカメラが捉えたのは、そんな牧歌的な風景ではなく、ソ連正規軍による大規模な侵攻という悪夢のような現実でした。
日本政府は狼狽し、初動が大きく遅れます。頼みの綱であるはずの日米安全保障条約は、米ソ間の密約によって機能せず、アメリカ軍が介入することはありませんでした。自衛隊もまた、法的な制約や指揮系統の混乱から有効な防衛行動を取れず、北海道はあっという間にソ連軍の占領下に置かれてしまうのです。
国家の防衛システムが麻痺する中、日本本土では奇妙な熱狂が生まれます。ヤクザや右翼団体、果ては血気盛んな一般市民までが「義勇軍」を名乗り、めいめいに武器を取って北海道へ渡ろうとします。その動機は愛国心、功名心、あるいは単なる野次馬根性と様々で、統一された戦略などあろうはずもありませんでした。
さらに、この未曾有の事態は、北海道の先住民族であるアイヌの人々に、日本からの独立という長年の悲願を成就させる好機と映ります。テレビクルーは戦争を視聴率の取れるショーとして追いかけ、大阪の書斎では一人の小説家が、この馬鹿げた戦争の顛末を冷ややかに見つめているのでした。
小説「歌と饒舌の戦記」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の核心に触れる内容を含みます。まだ未読の方で、結末を知りたくないという方はご注意ください。この物語が投げかけるものの本質は、その衝撃的な結末と、そこに至るまでの混沌とした過程にこそあるのですから。
まず語らなければならないのは、この物語を支配する圧倒的な「饒舌」の存在感でしょう。物語の冒頭から最後まで、中身のない、あるいは真実を覆い隠すための言葉が、洪水のように溢れかえっています。その最大の発生源は、ディレクター森下率いるGRTテレビの取材班です。彼らにとって戦争は、悲劇ではなく「番組のネタ」でしかありません。
森下は「突然おじゃま虫」という、その名からしてふざけた番組のために、危険な戦場を駆け回ります。彼の口から発せられるのは、視聴者を煽るためのセンセーショナルな言葉ばかり。兵士の死も、市民の恐怖も、すべては視聴率という数字に換算されるための素材にすぎません。この姿は、現実をエンターテイメントとして消費する現代のメディアのあり方そのものを、痛烈に描いているように感じました。
政治家たちの言葉もまた、空虚な「饒舌」の極みです。国会で繰り広げられる議論は、責任のなすりつけ合いと精神論に終始し、具体的な対策は何一つ生まれません。国民の生命と財産が脅かされているというのに、彼らの関心は次の選挙と自己保身だけ。その姿は滑稽であると同時に、深い絶望感を抱かせます。
さらに、筒井康隆氏自身の文体もまた、この「饒舌」を体現しているかのようです。次から次へと情報が叩きつけられ、多様な視点がめまぐるしく入れ替わり、読者はその奔流に飲み込まれそうになります。この圧倒的な情報量は、現代社会で私たちが日々浴び続けている、SNSやニュースサイトの情報の洪水と重なります。何が重要で、何がそうでないのか。判断する間もなく、次の言葉が押し寄せてくるのです。
では、この「饒舌」の濁流に対抗する「歌」は、物語の中に存在するのでしょうか。私は、アイヌ民族の独立運動に、そのか細くも切実な「歌」を見出しました。彼らの戦いは、日本の近代化の過程で虐げられてきた歴史への抵抗であり、自らの尊厳と文化を取り戻すための叫びです。それは、功名心や金目当てで集まった義勇軍の騒々しい声とは、明らかに異質なものでした。
彼らの「歌」は、国家とは何か、民族とは何かという根源的な問いを私たちに突きつけます。日本という大きな枠組みが崩壊しかけたとき、これまで抑圧されてきた小さな共同体が自らの声を上げる。この展開は、物語に一層の深みと複雑さを与えています。彼らの行動は、決して単純な正義として描かれているわけではありませんが、その叫びには無視できない重みがありました。
しかし、悲しいかな、この物語の世界では、そうした切実な「歌」さえも、やがては巨大な「饒舌」の渦の中に飲み込まれ、かき消されていきます。個人の真摯な思いや信念は、メディアが作り出す虚像や、大衆の無責任な熱狂の前では、あまりにも無力です。それが、この物語が描き出す冷徹な現実でした。
そして、この物語を語る上で欠かせないのが、作者自身を思わせる「おれ」という小説家の存在です。彼は大阪の書斎から一歩も出ず、テレビや新聞を通じてこの戦争を観戦しています。彼の視点は冷笑的で、戦場で右往左往する人々を突き放したように描写します。このメタフィクショナルな構造は、読者に対して「これは作り話なのだ」と絶えず意識させます。
この「おれ」の存在は、一体何を意味するのでしょうか。彼は、安全な場所から物事を批評するだけの知識人の戯画化かもしれません。あるいは、言葉を紡ぐこと、物語を創ることそのものへの自己言及的な問いかけとも読めます。彼が書斎で紡ぐ言葉もまた、戦場に響く「饒舌」の一部でしかないのではないか。そんな自嘲的な視線さえ感じさせるのです。
この物語は、特定の主人公が活躍する英雄譚ではありません。森下ディレクター、KGBの女スパイ・ナタリー、ヤクザの組長、アイヌの指導者、そして「おれ」。様々な人物の視点が交錯する群像劇であり、それによって社会全体の混乱と狂騒が立体的に描き出されています。誰もが自分の信じる正義や欲望に従って行動し、その結果、全体としては救いようのないドタバタ劇が進行していくのです。
この構造は、戦争という極限状況がいかに人間の理性を麻痺させ、本性を剥き出しにするかを浮き彫りにします。愛国心を叫ぶ者が火事場泥棒を働き、平和を訴える者が隣人を蹴落とす。その様は、まさに人間の愚かさの見本市のようであり、笑うに笑えない、乾いた感情を抱かされました。
さて、いよいよ物語の結末です。あれだけの大混乱を巻き起こしたソ連の侵攻は、驚くほどあっけなく、そして馬鹿げた形で終わりを迎えます。日ソ間で交わされたのは、なんと「北方領土と北海道の交換」という密約だったことが示唆されるのです。そして、その密約すらも反故にされ、結局ソ連軍は撤退。残されたのは、夥しい数の死者と、破壊し尽くされた大地だけでした。
戦争の理由も、結末も、すべてが茶番。命を懸けて戦った者たちの「歌」も、扇情的に煽り立てた者たちの「饒舌」も、すべてが無意味だったと突きつけられるのです。カタルシスなどどこにもありません。あるのは、巨大な虚無感と、人間という存在そのものへの深い徒労感です。これこそが、筒井康隆氏が描きたかった「戦記」の正体なのでしょう。
この物語が発表されたのは、日本がバブル経済の絶頂にあった1987年です。「思想も、宗教も、国家の目標ひとつない、金満日本の虚妄」という作中の言葉は、当時の日本社会に対する強烈な批判でした。経済的な豊かさに浮かれ、平和が永遠に続くと信じ込んでいた私たち日本人の足元がいかに脆いものであるかを、この物語は容赦なく暴き出したのです。
そして、その警鐘は、30年以上が経過した現代においても、全く色褪せていません。むしろ、インターネットとSNSの普及により、誰もが「饒舌」の発信者となりうる現代において、この物語の持つ意味はさらに増しているとさえ言えます。フェイクニュース、ヘイトスピーチ、根拠のない噂。言葉が現実を侵食し、社会を分断する光景は、もはや日常の一部です。
私たちは今、まさに『歌と饒舌の戦記』の世界を生きているのかもしれません。何が真実の「歌」で、何が空虚な「饒舌」なのか。その濁流の中で、私たちはどうやって自分の足で立ち、進むべき道を見定めれば良いのか。この物語は、明確な答えを与えてはくれません。ただ、その崩壊した結末を通して、私たちに深く、重い問いを投げかけ続けるのです。
まとめ
小説「歌と饒舌の戦記」は、単なる架空戦記というジャンルには到底収まらない、極めて射程の長い物語でした。ソ連の北海道侵攻という突飛な設定を入り口に、作者が描きたかったのは、日本という国家、そしてそこに住む私たち日本人が抱える、構造的な脆さそのものだったように思います。
物語を貫くのは、「歌」と「饒舌」という対立軸です。しかし、信念の叫びである「歌」は、空虚な言葉の洪水である「饒舌」の前にあまりにも無力で、次々と飲み込まれていきます。メディア、政治、そして私たち大衆が生み出す「饒舌」が、いかに現実を歪め、破壊していくか。その過程は、読んでいて背筋が寒くなるほどでした。
作者自身を登場させるという仕掛けや、英雄不在の群像劇という手法、そして何より、全てを茶番として突き放す衝撃的な結末。これらすべてが、私たちに安易な感動や教訓を与えることを拒否します。読後に残るのは、深い虚無感と、それでも考え続けずにはいられない、重い問いです。
この物語は、現代社会を生きる私たちにとって、一つの予言の書と言えるかもしれません。言葉の価値がかつてなく問われる今だからこそ、一人でも多くの人に手に取ってほしい。そう強く感じさせる、圧倒的な一作でした。