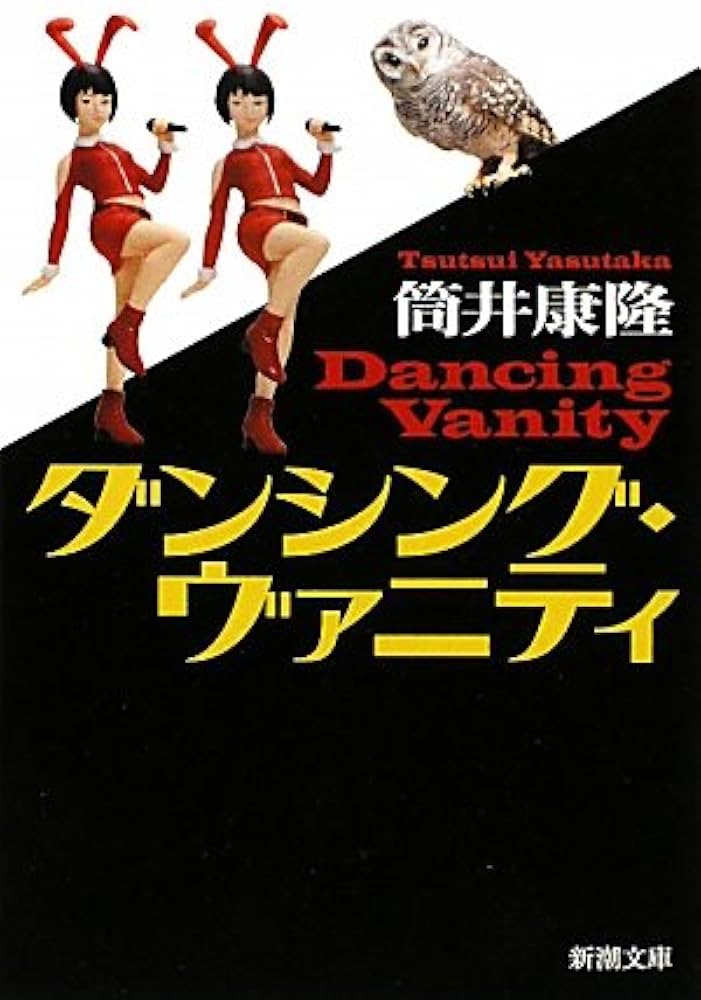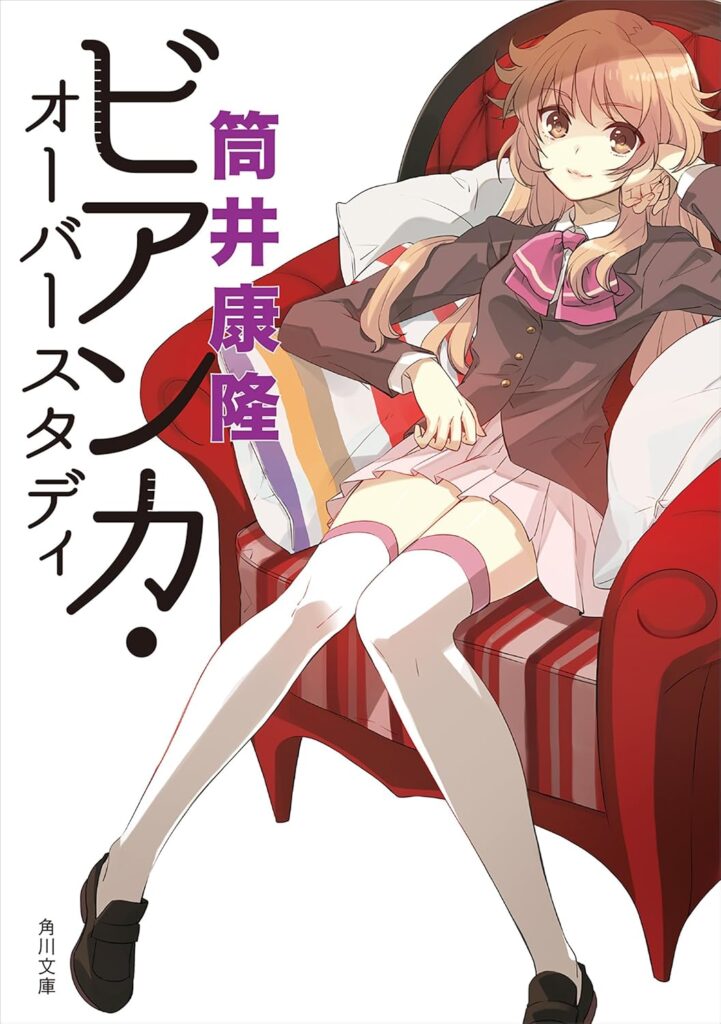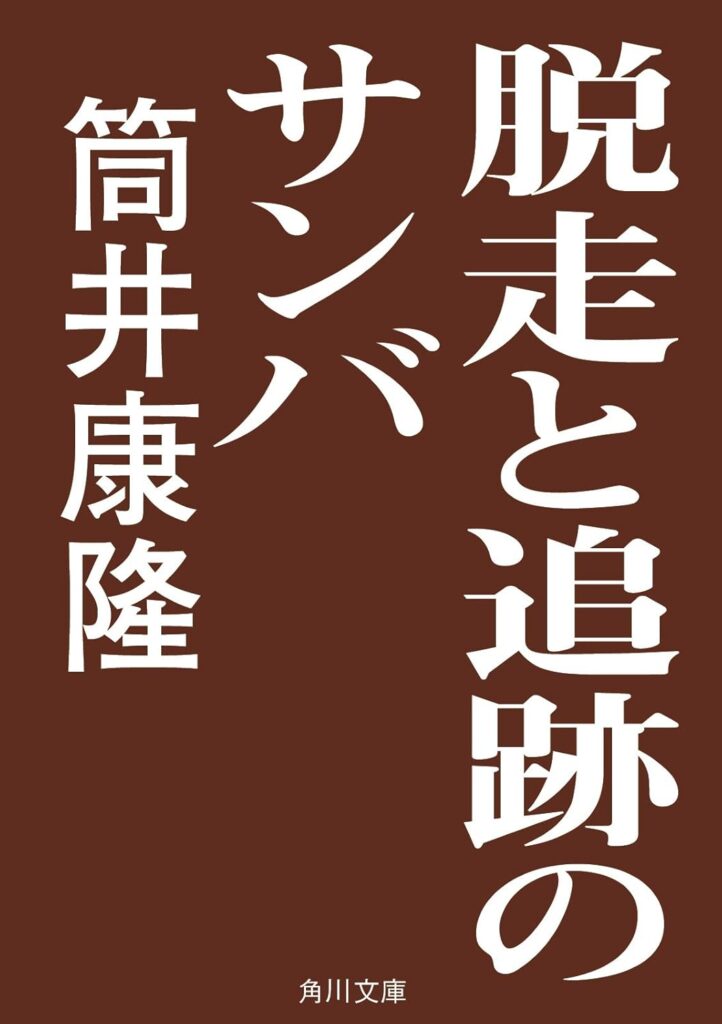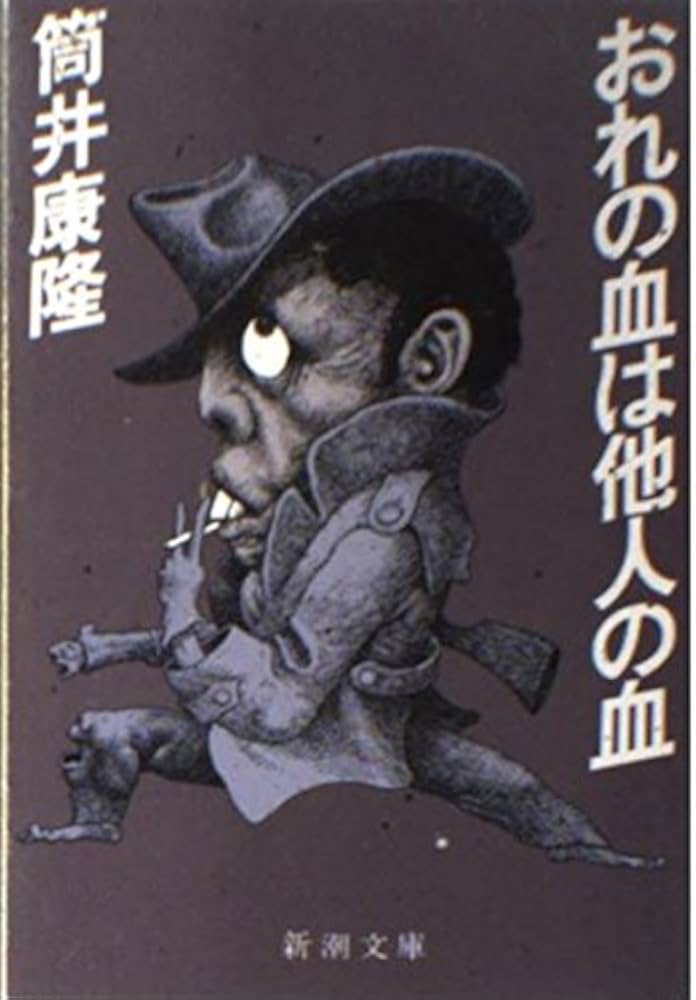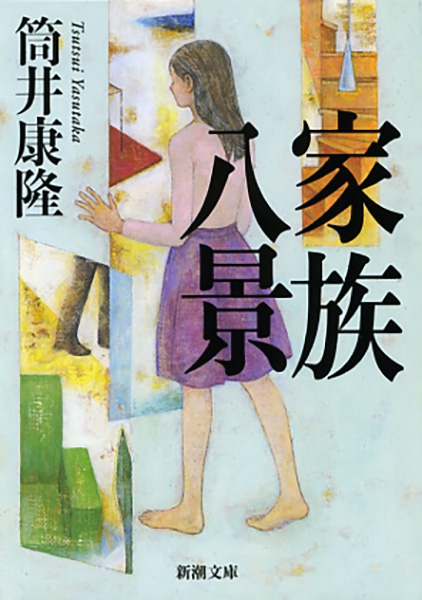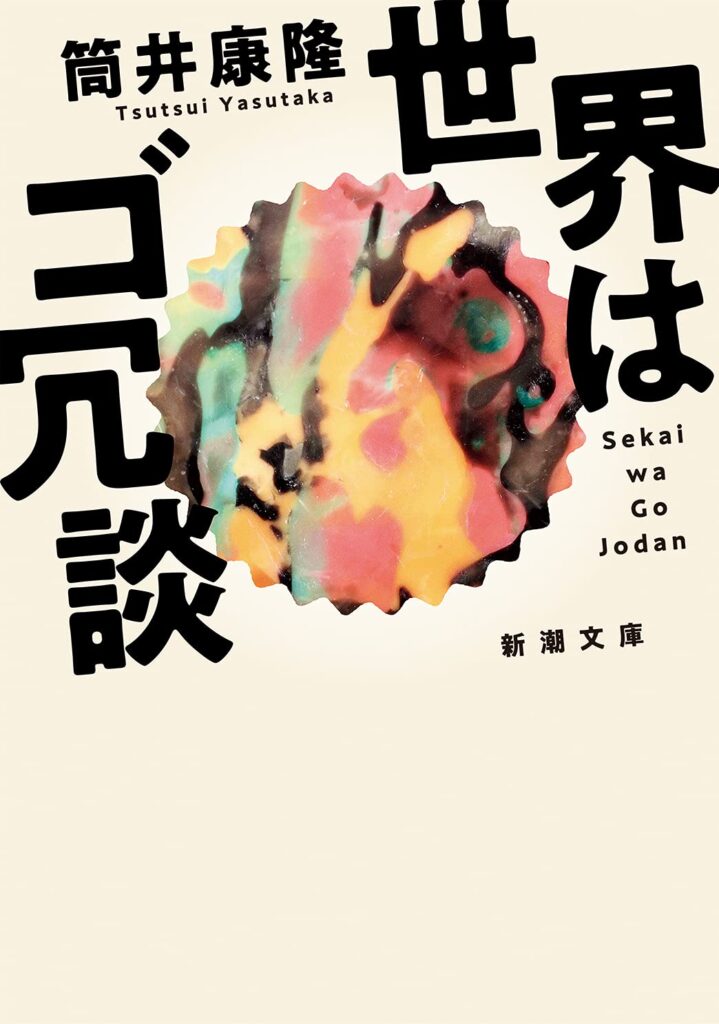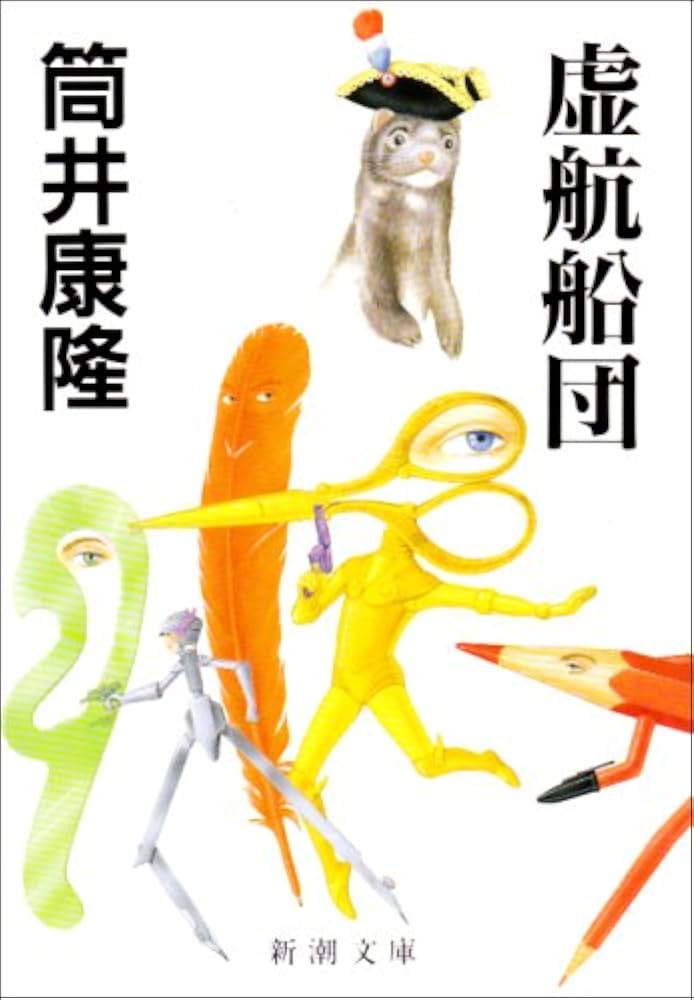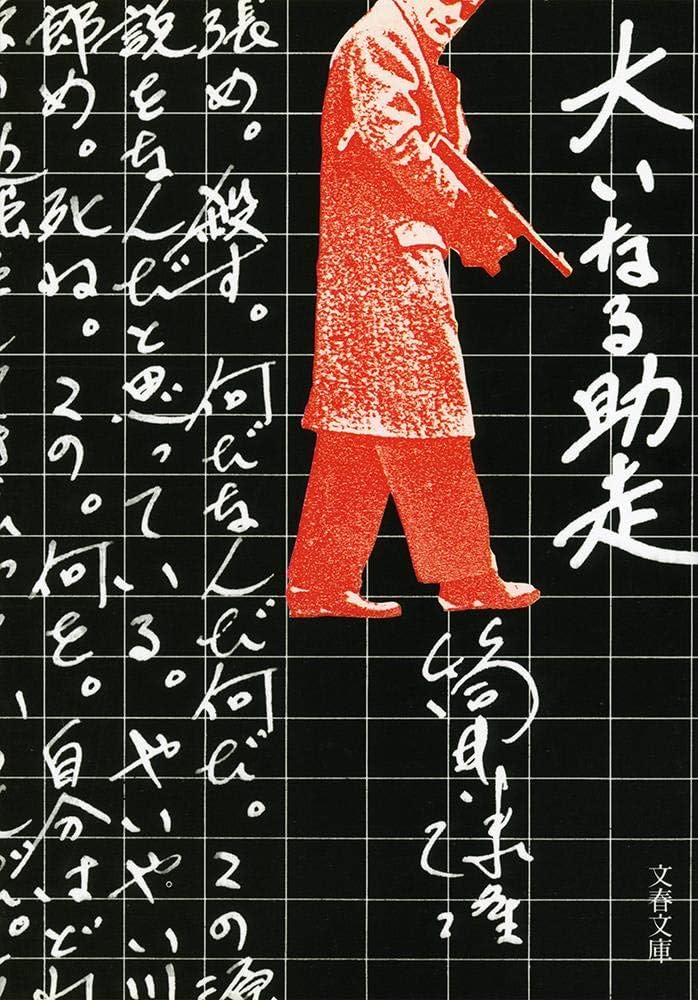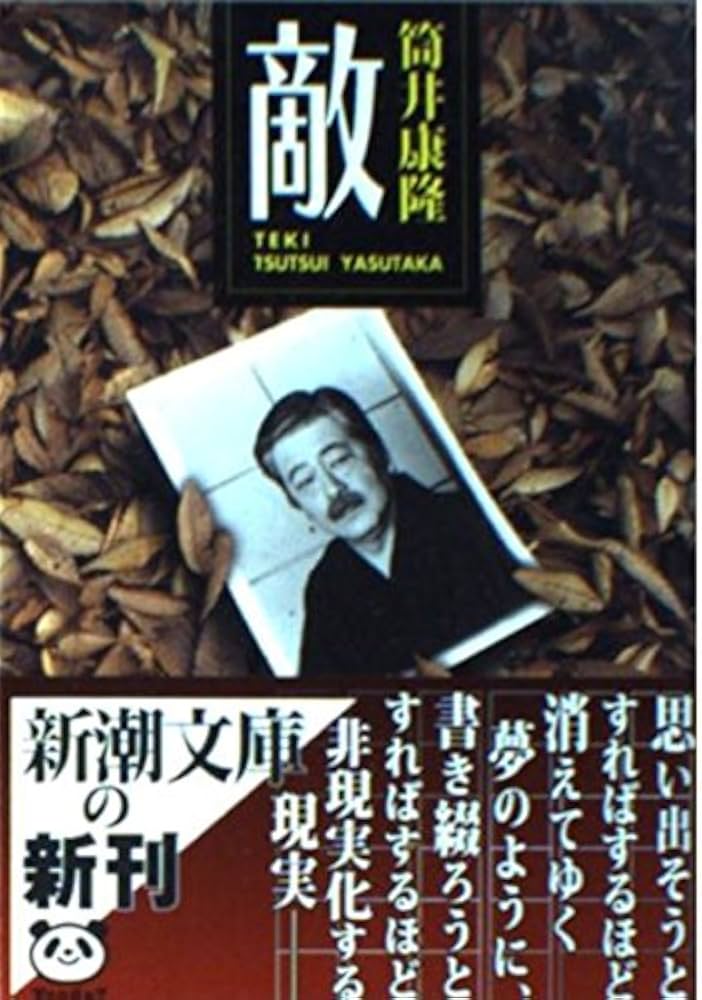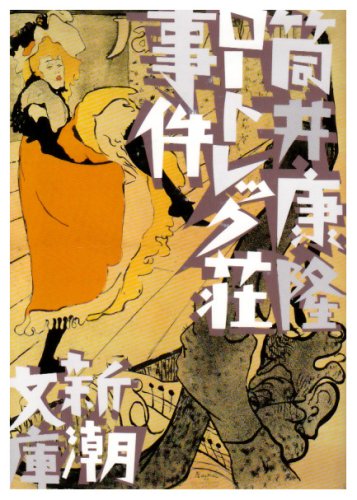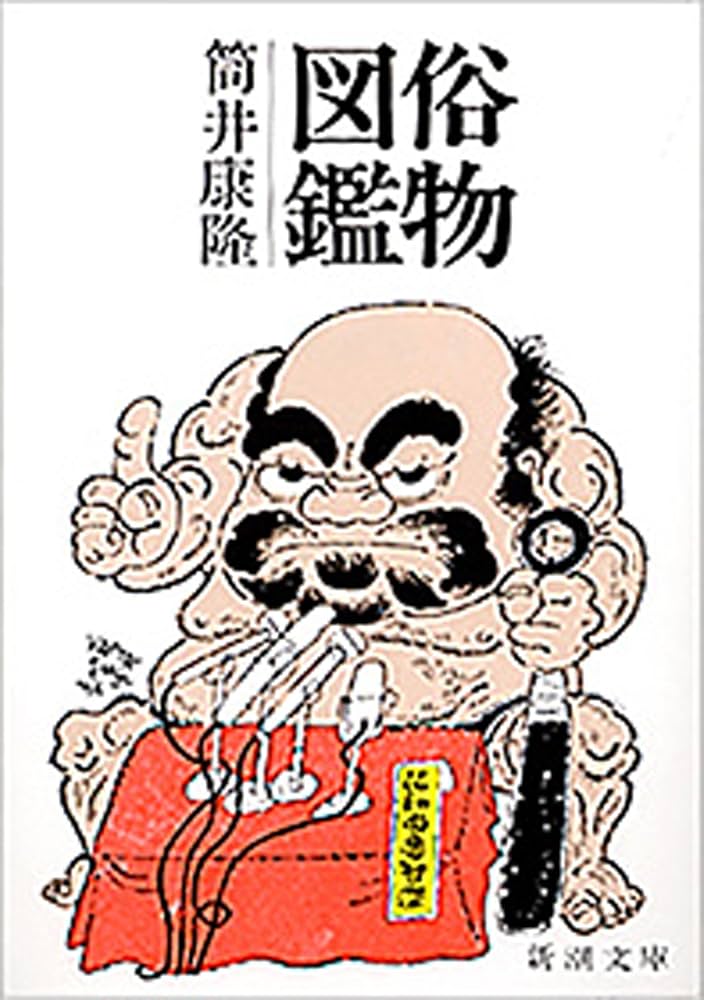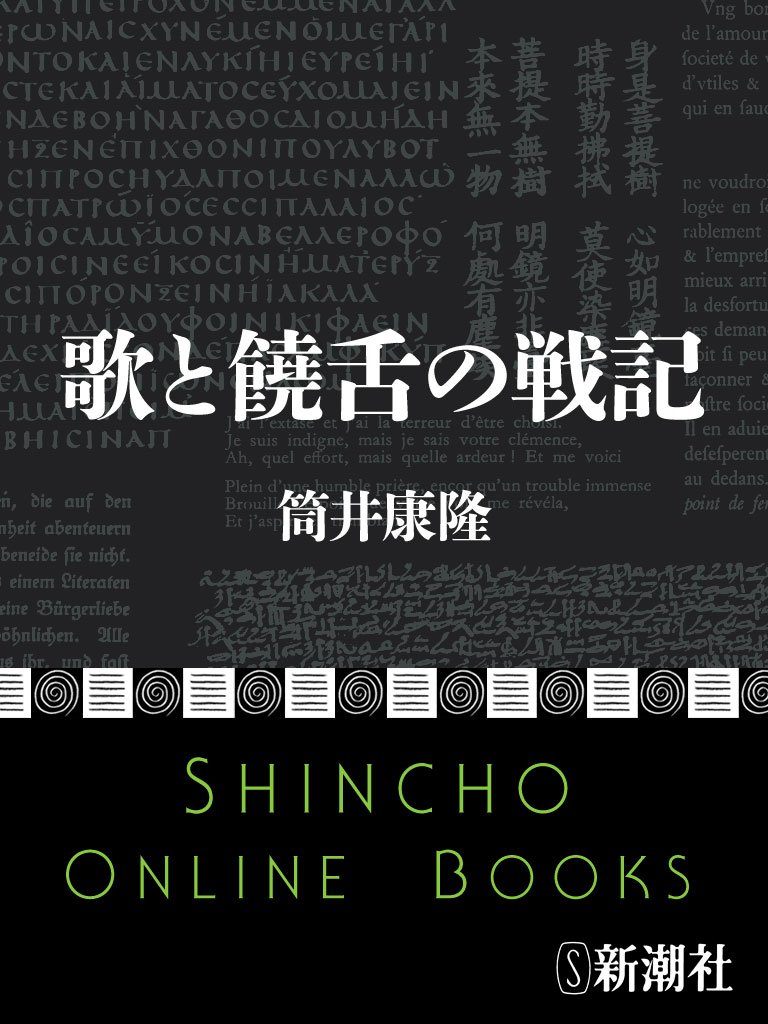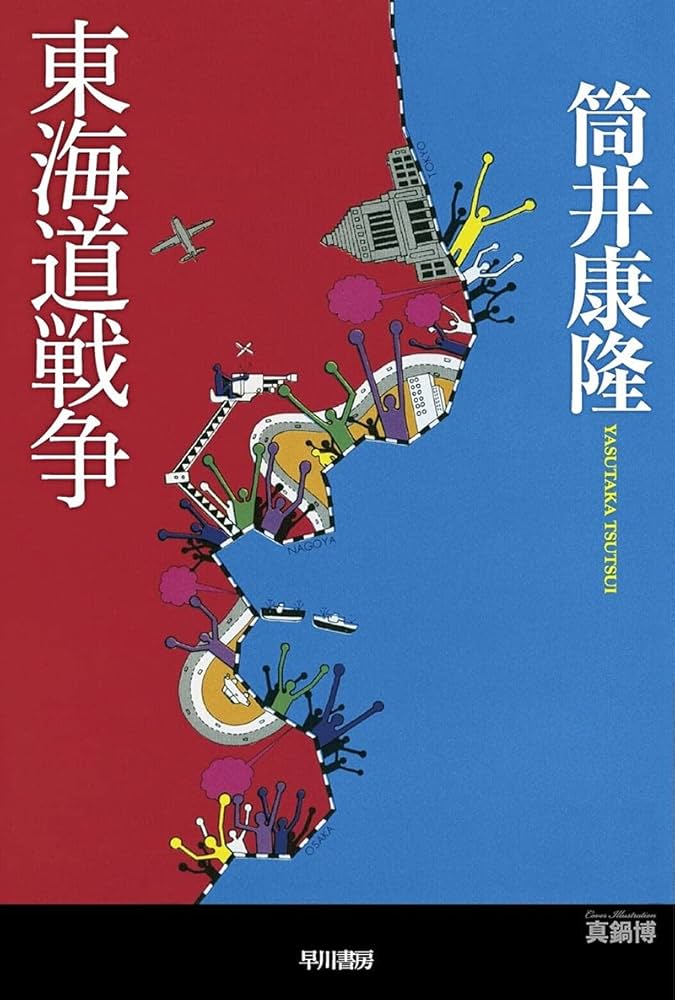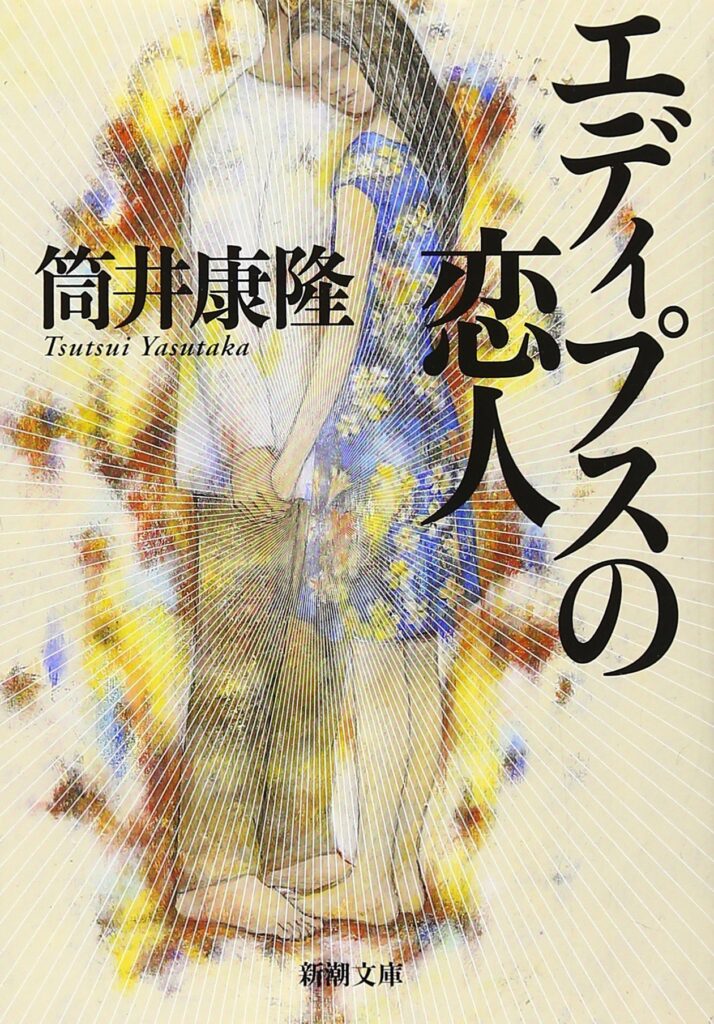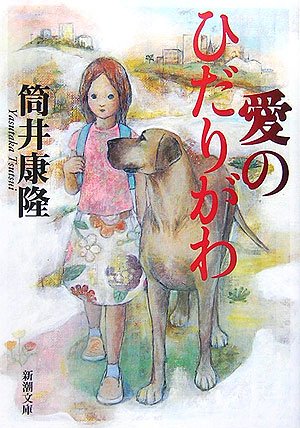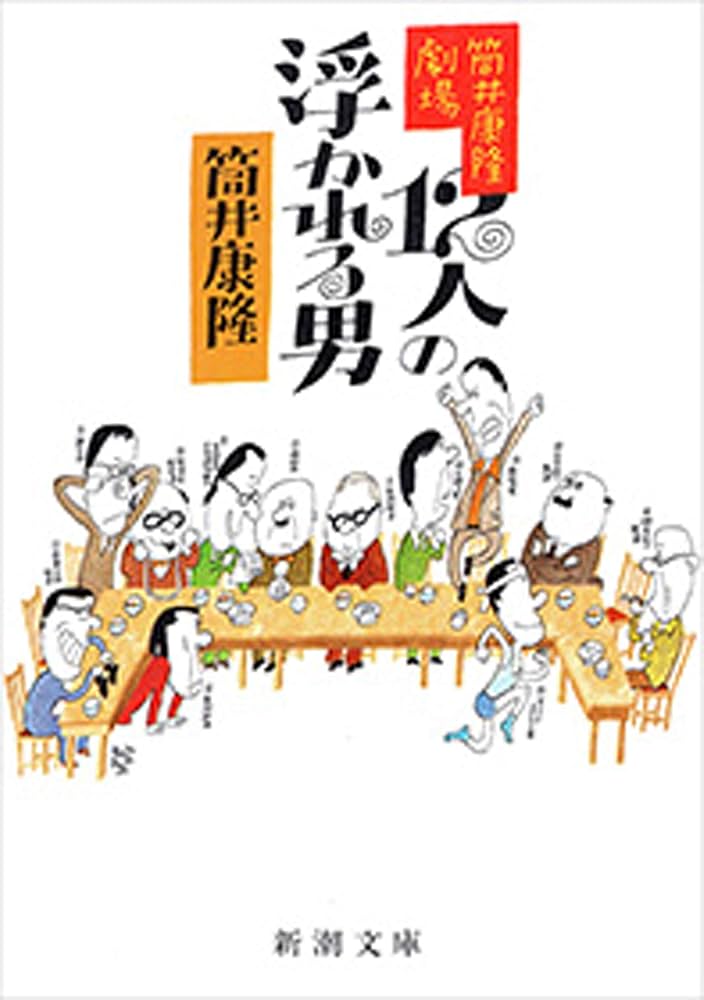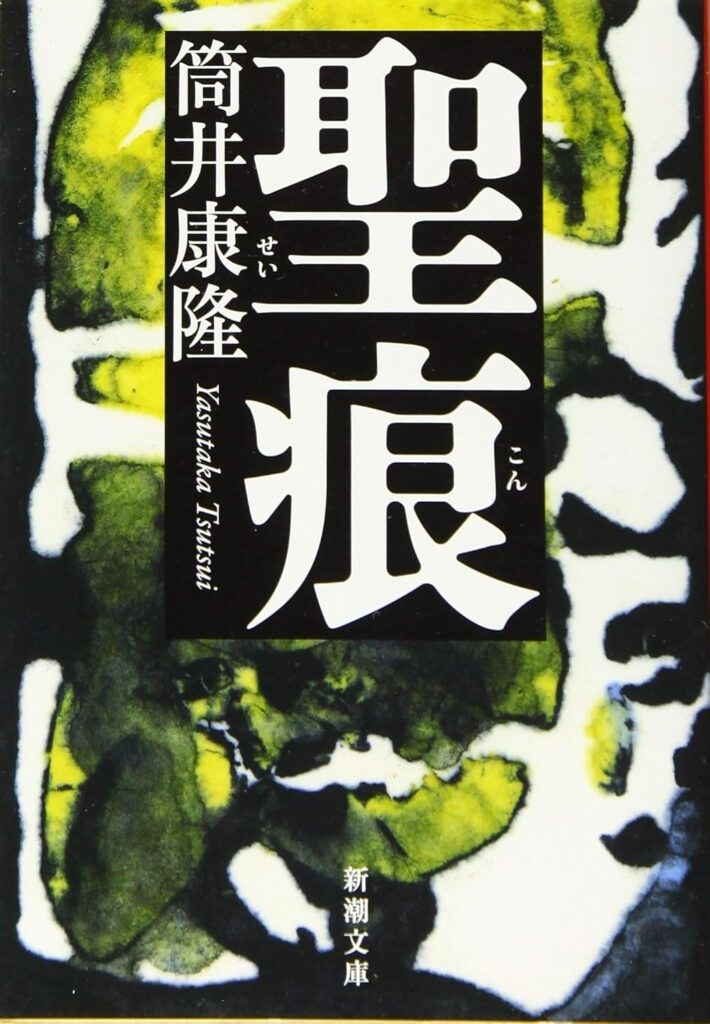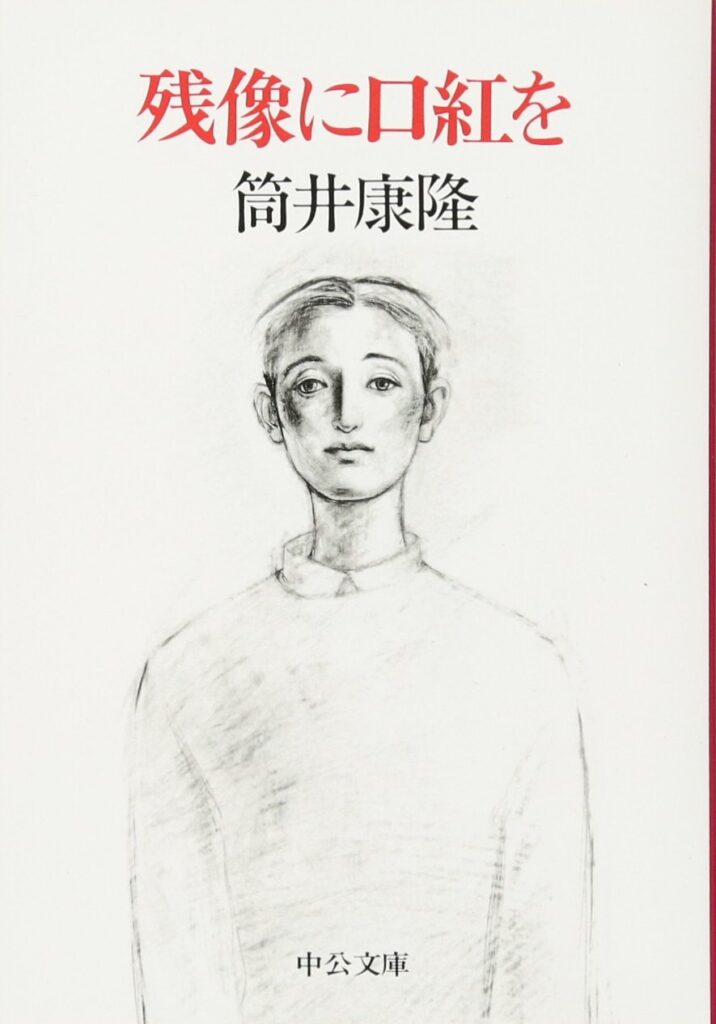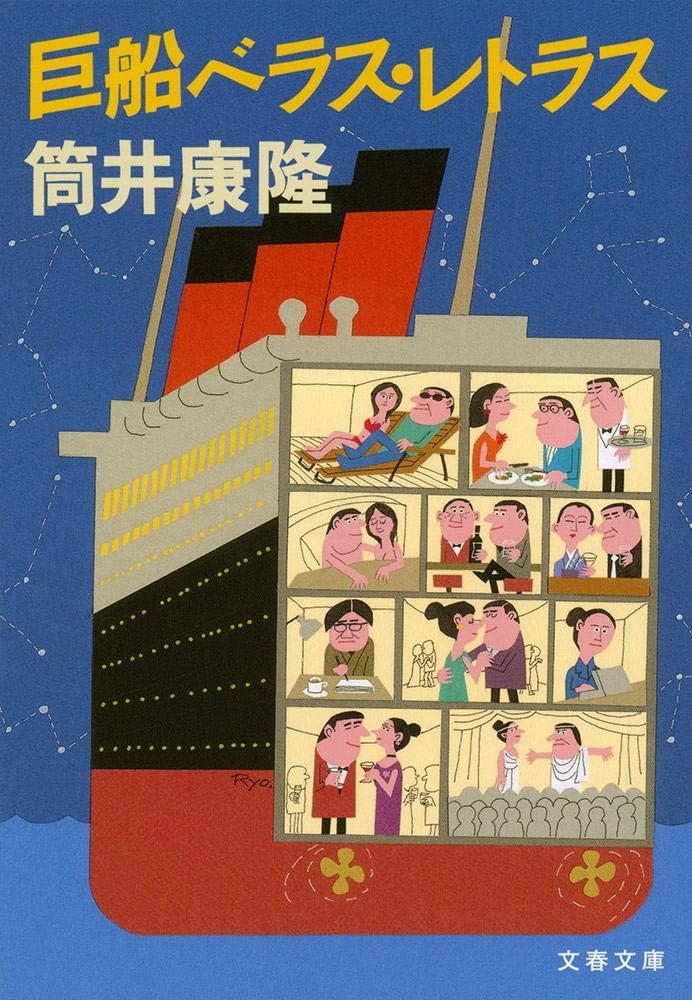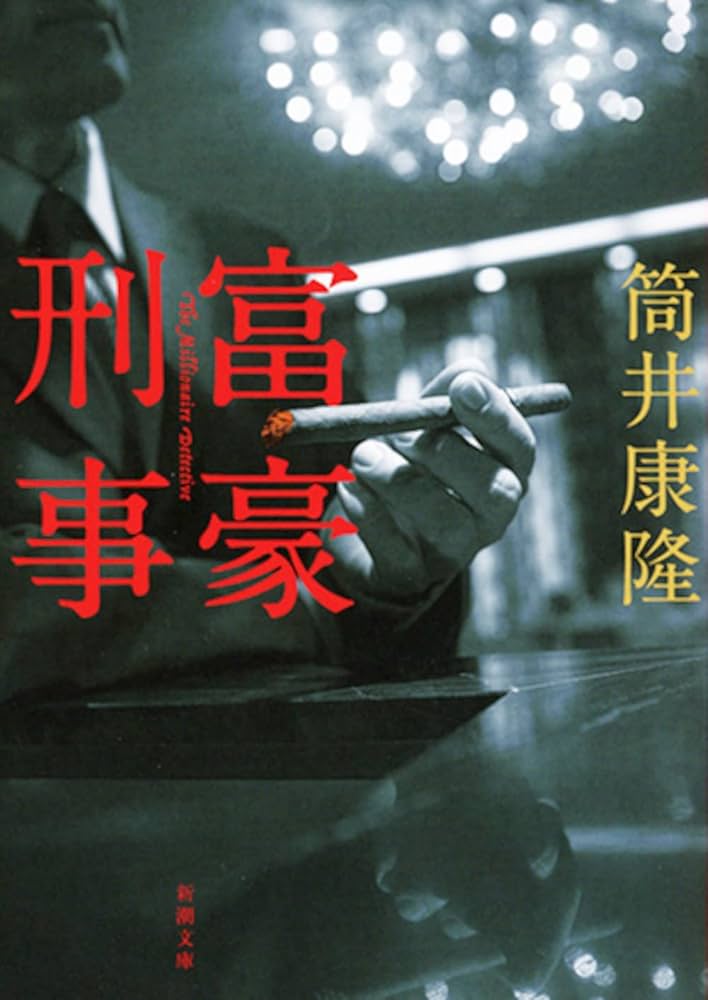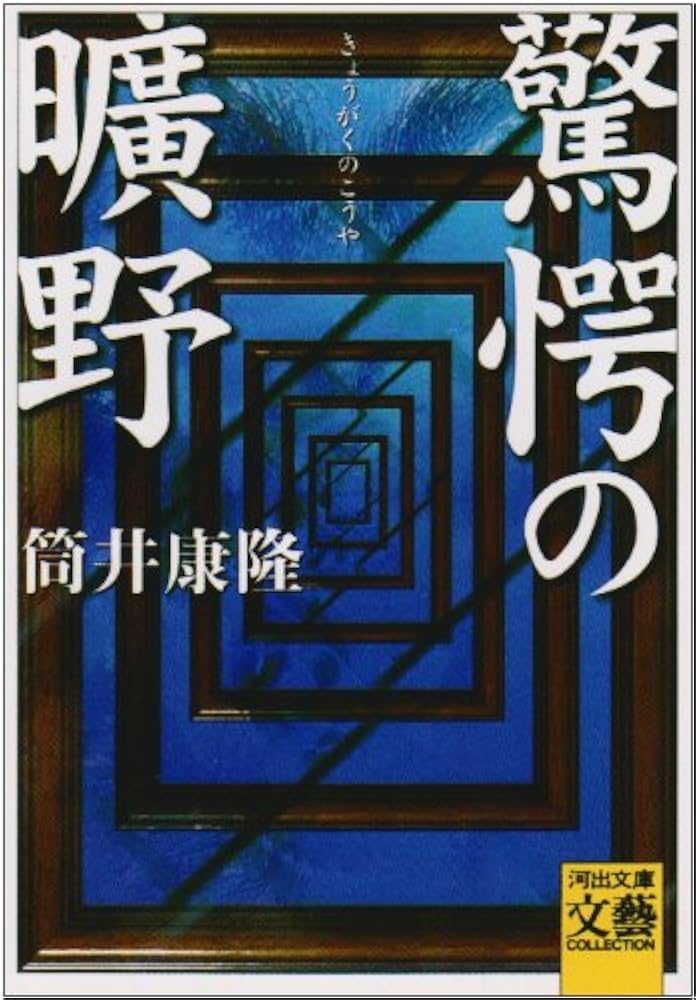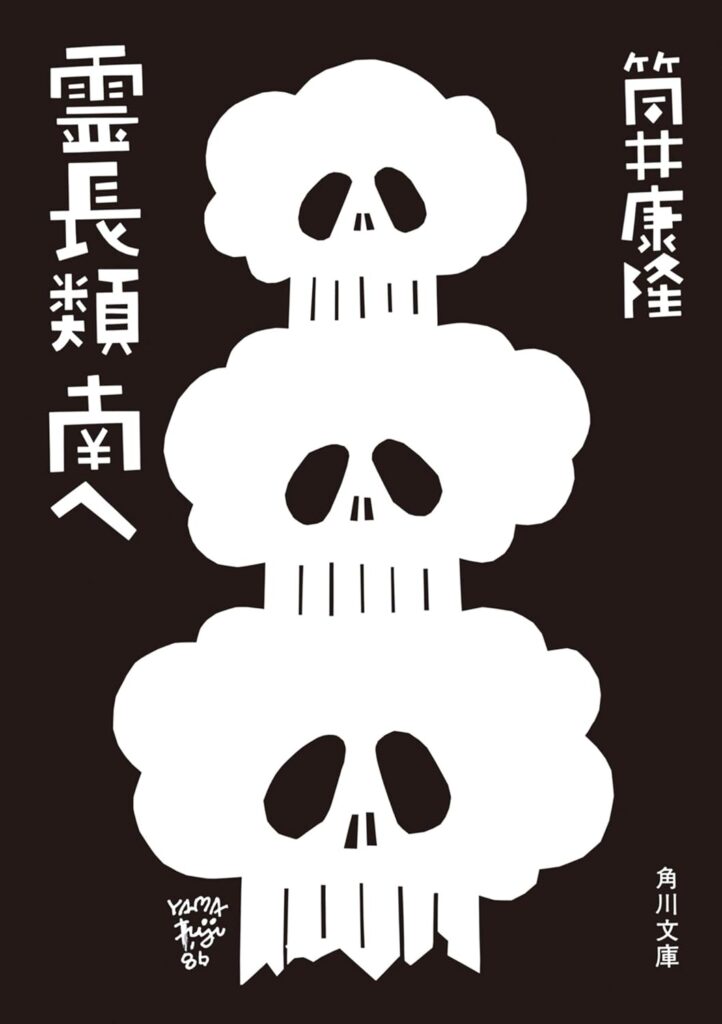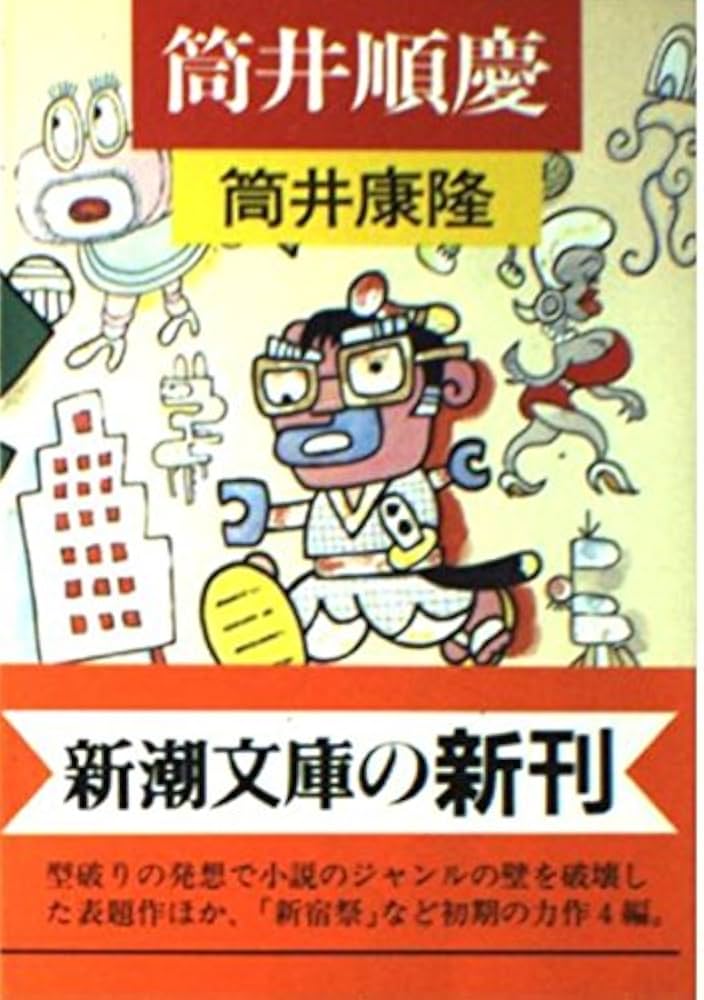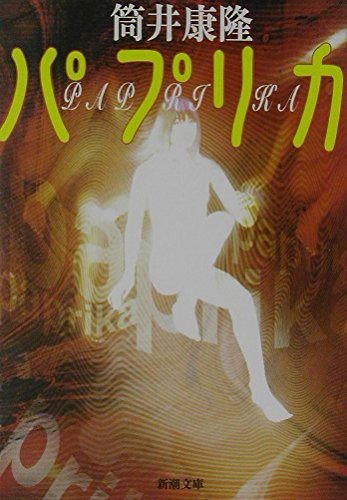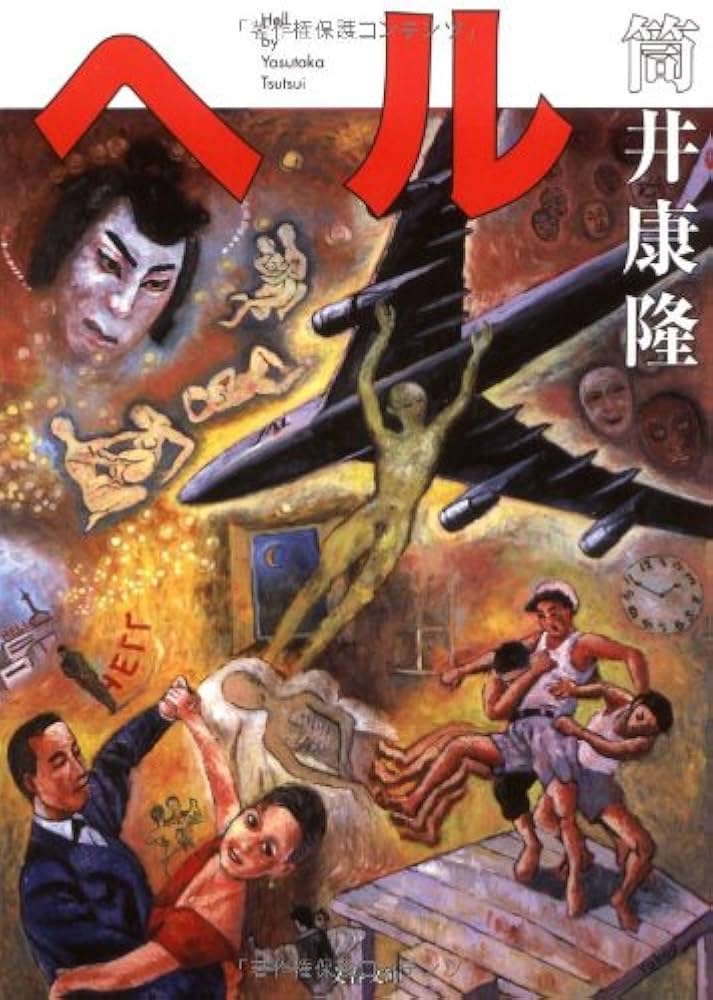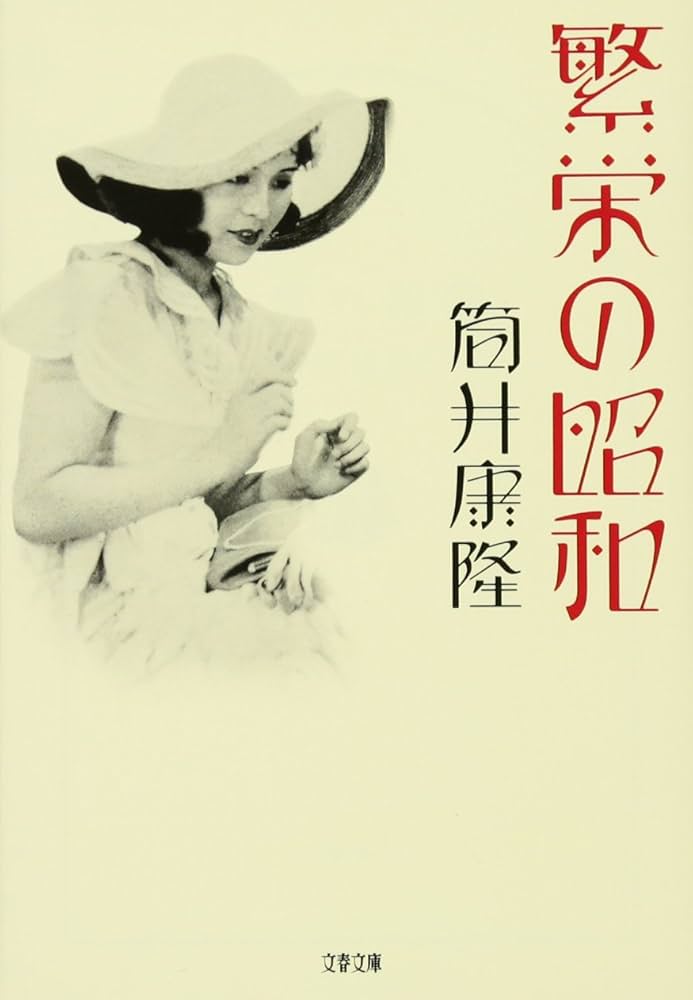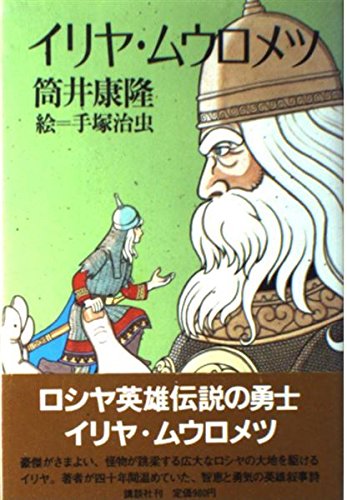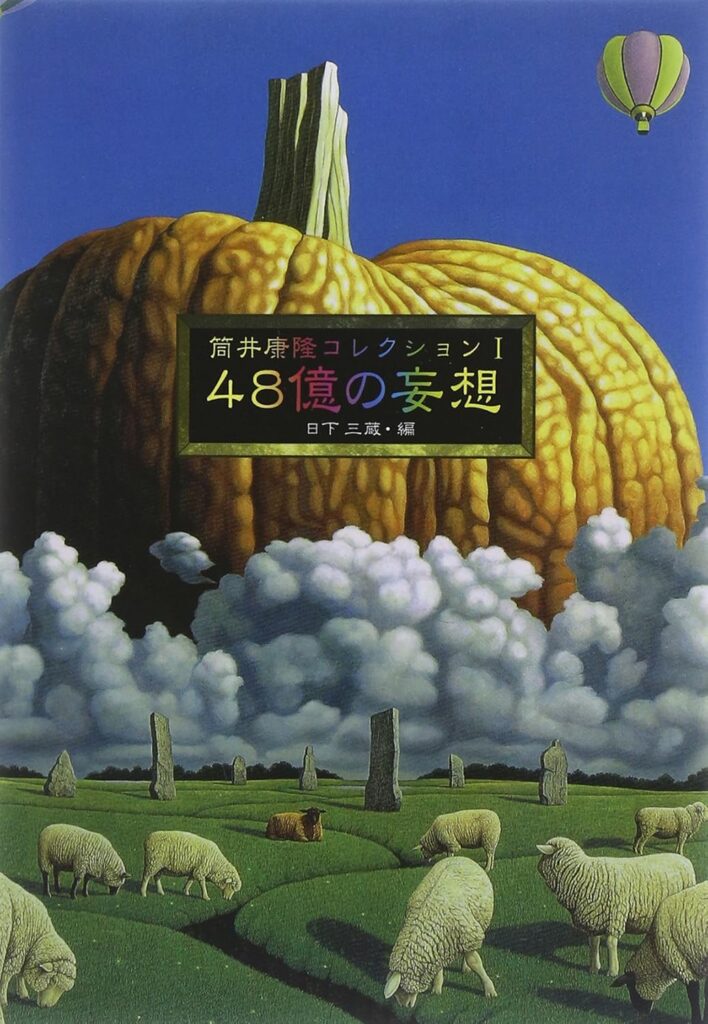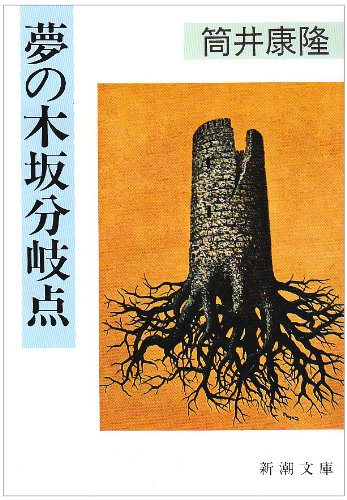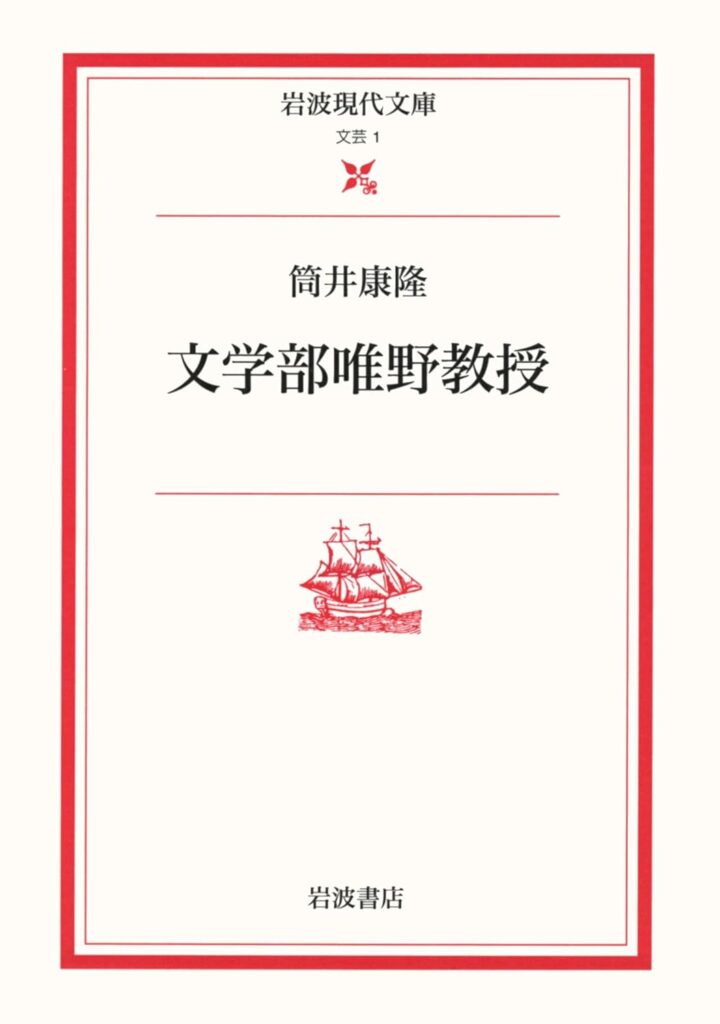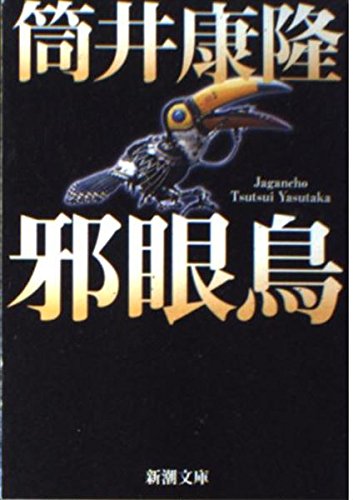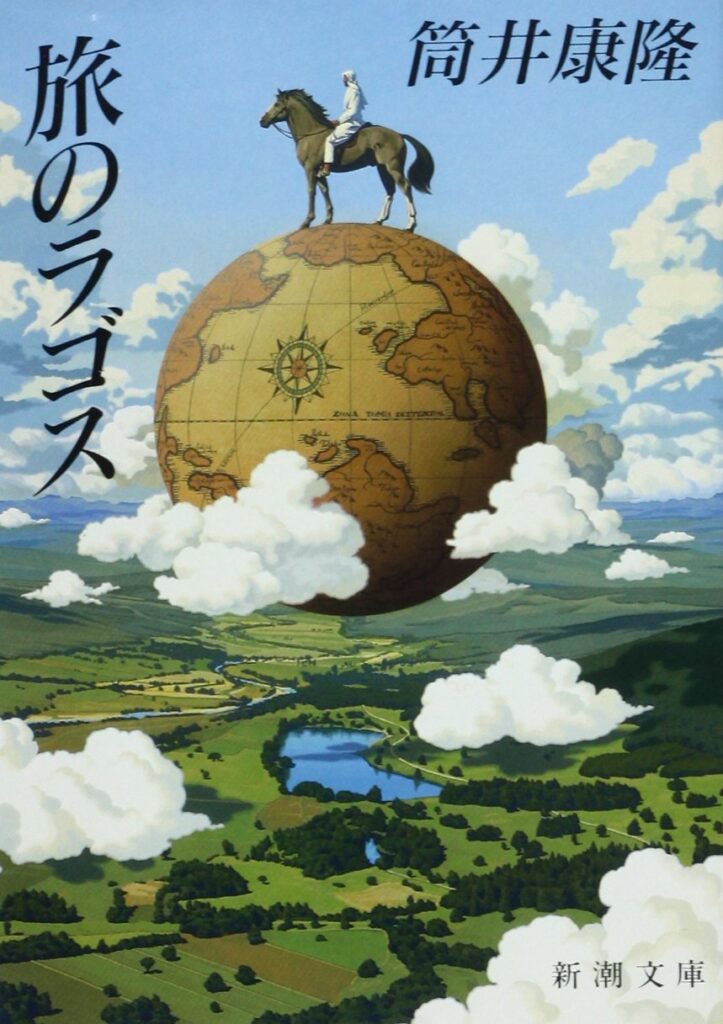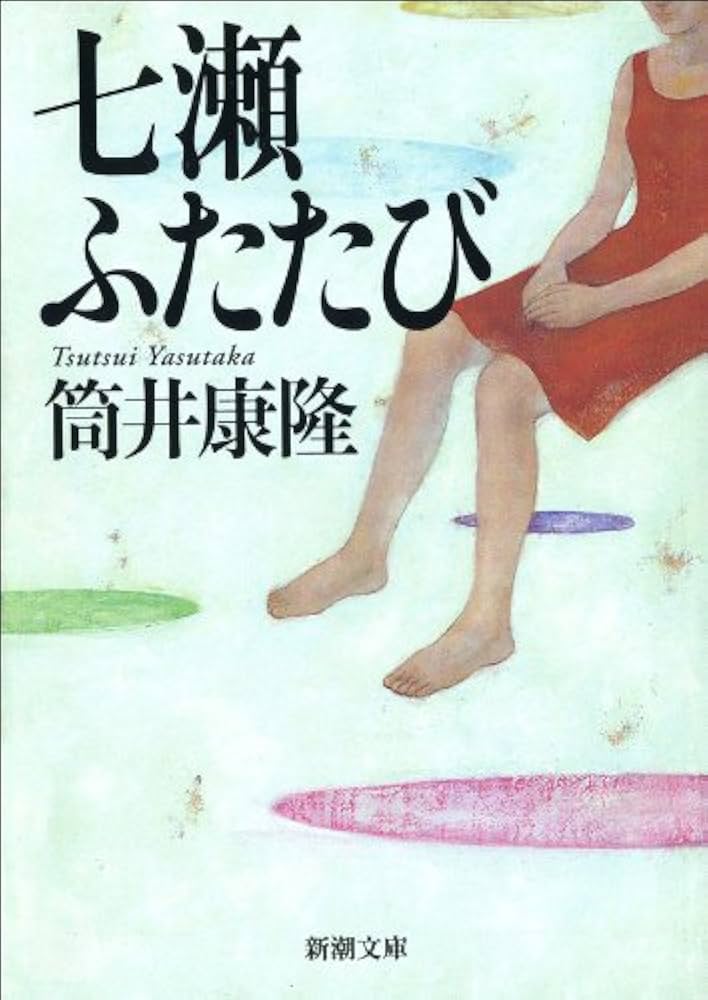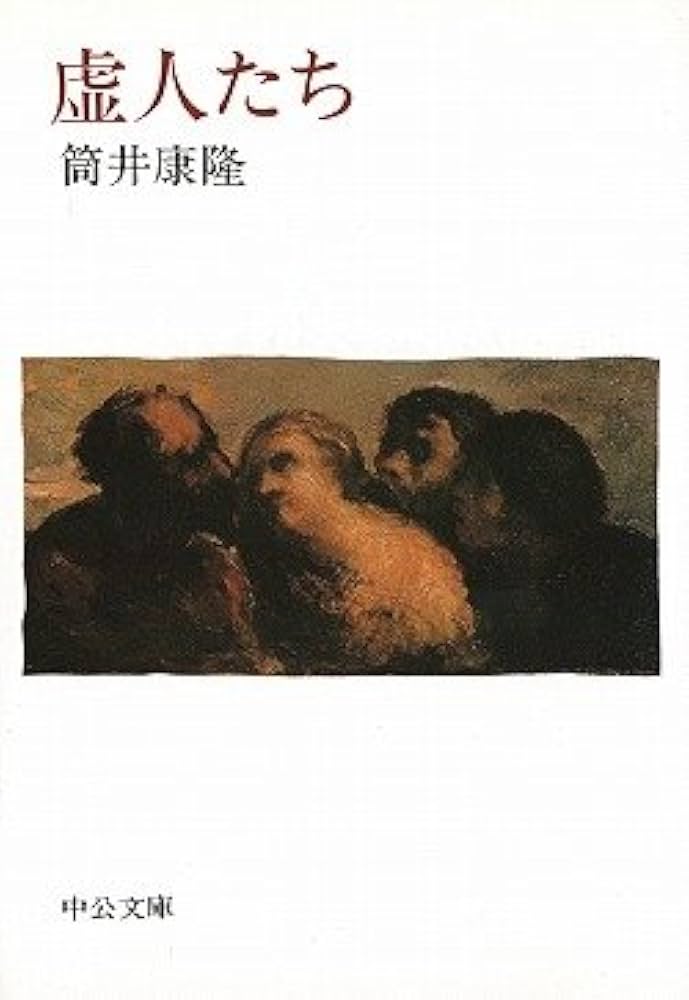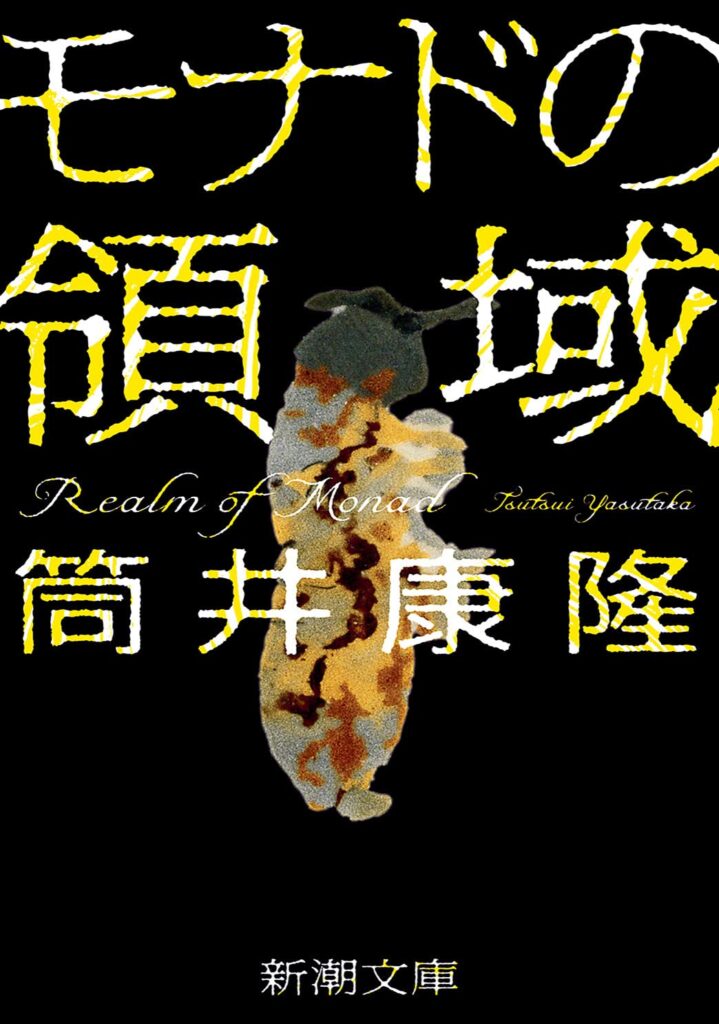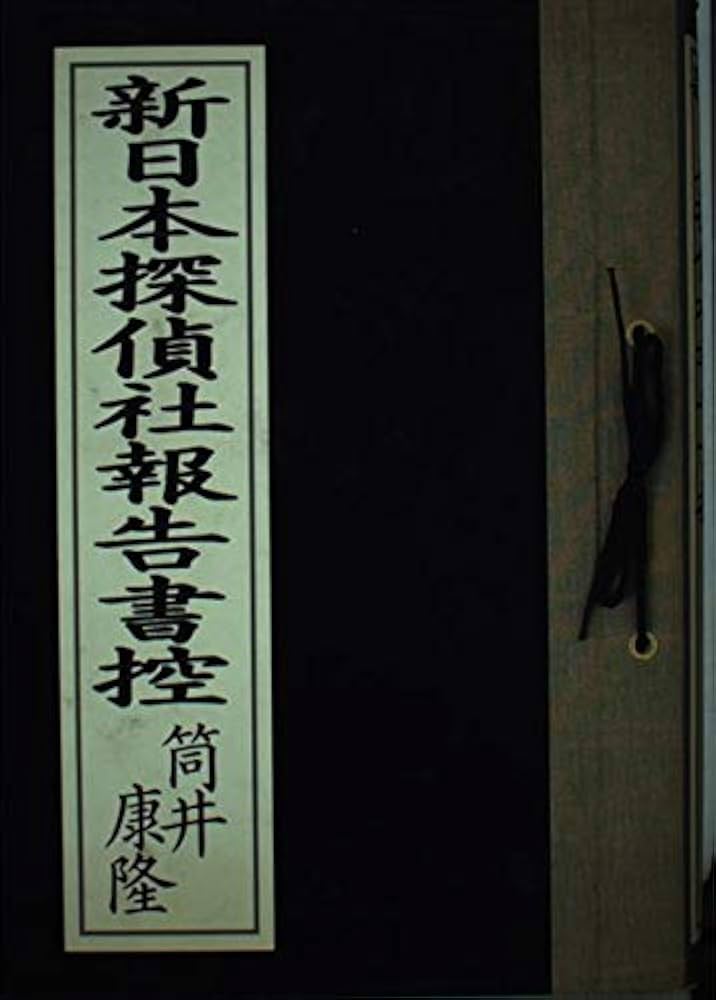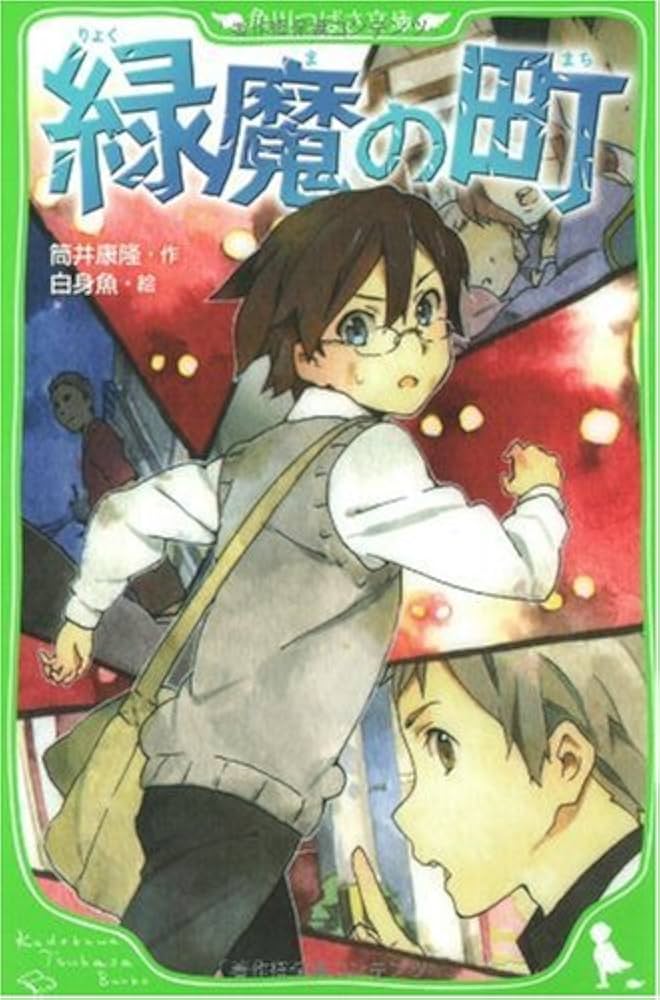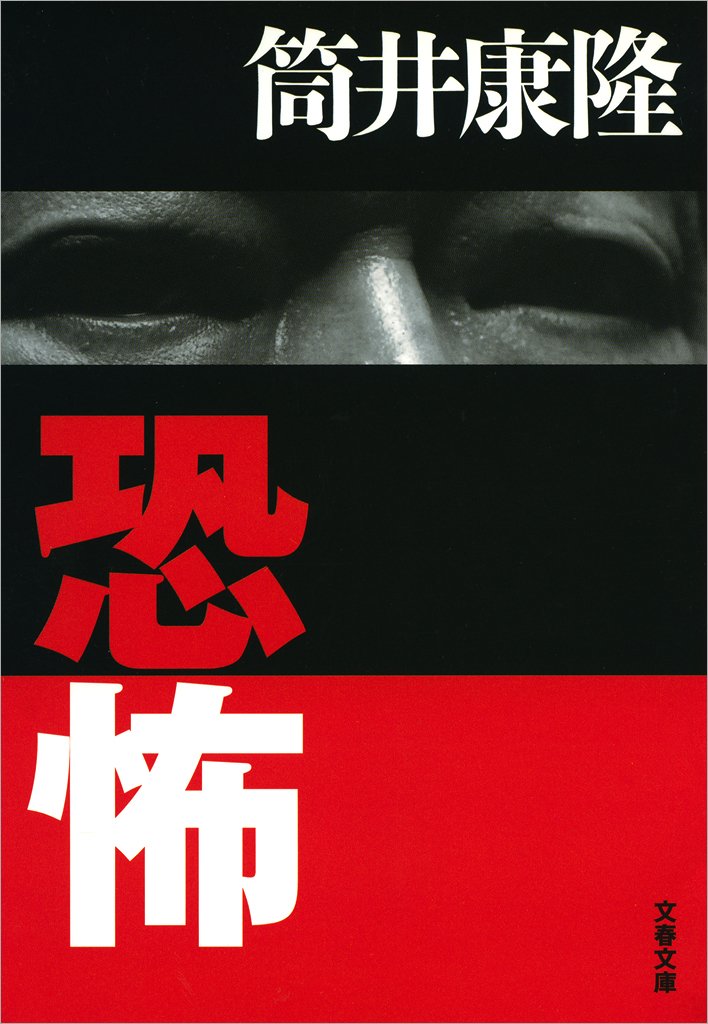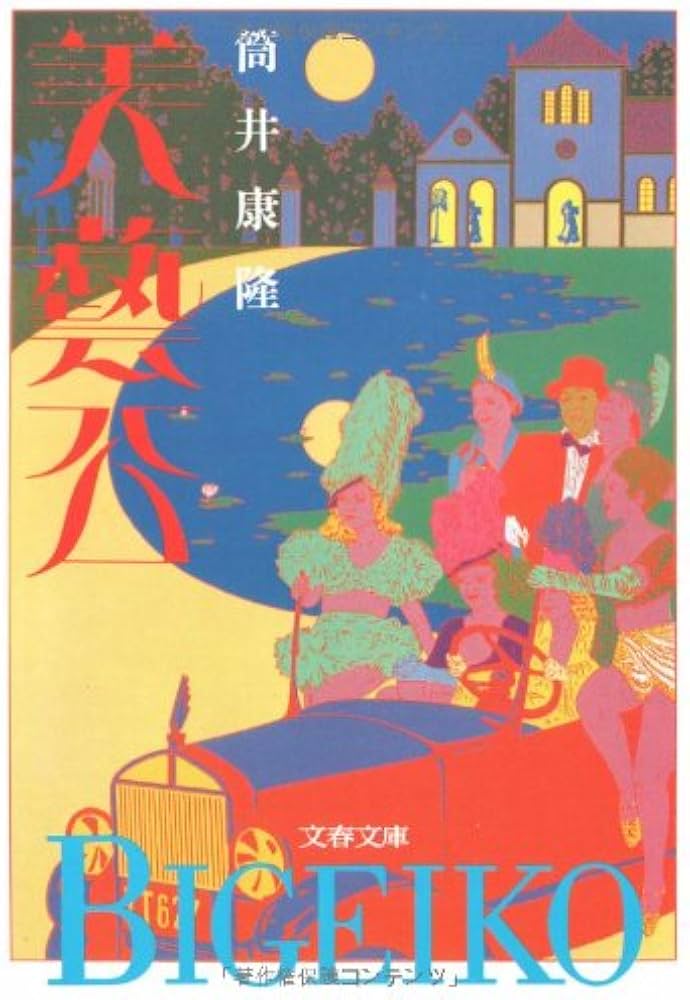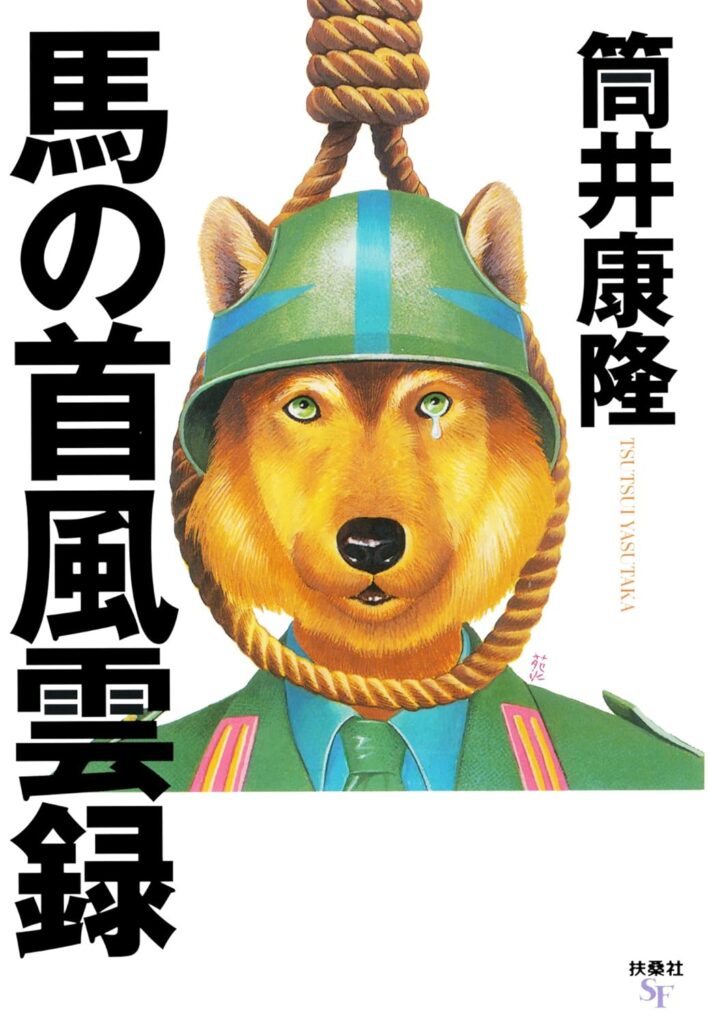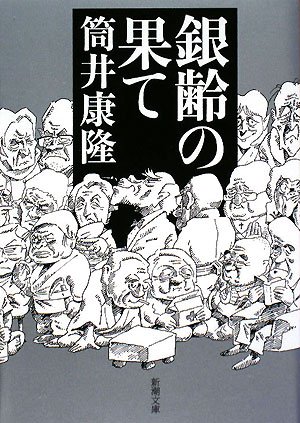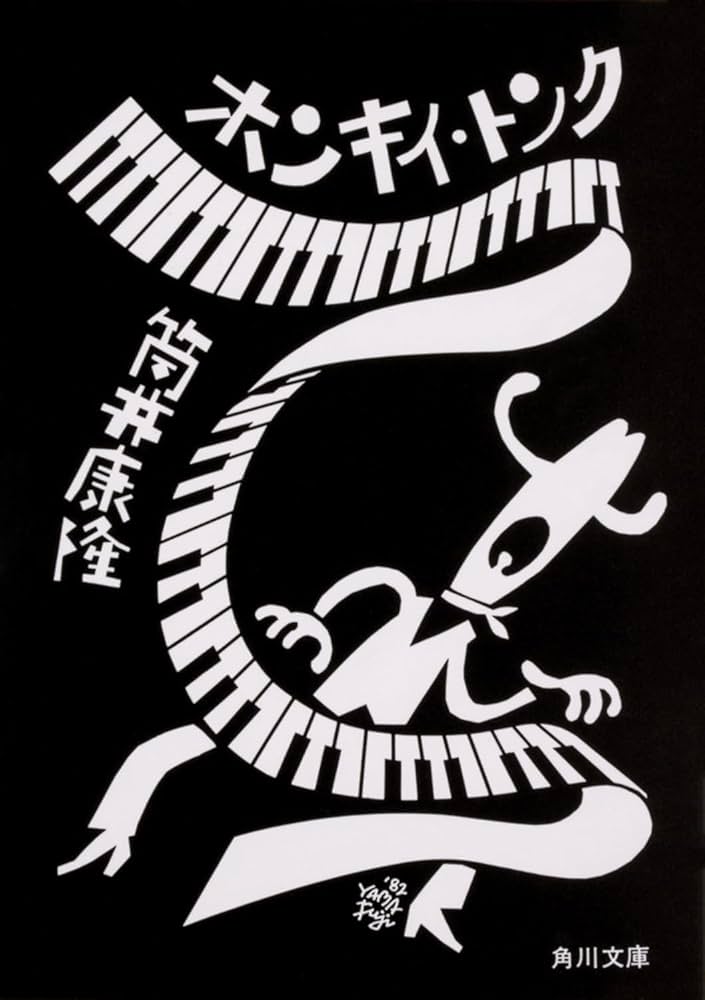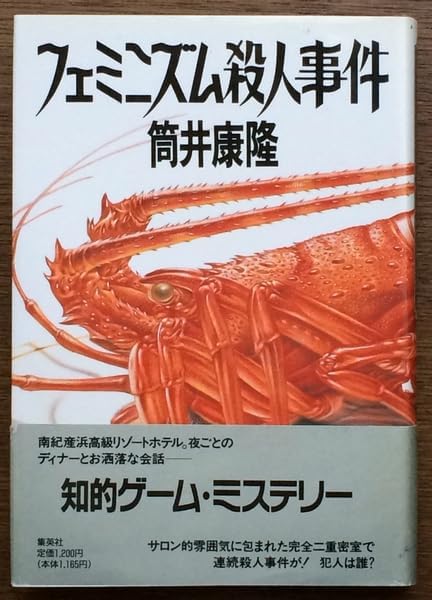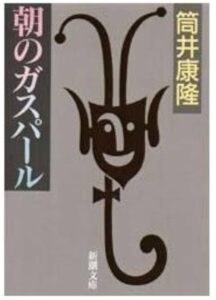 小説「朝のガスパール」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「朝のガスパール」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この作品は、ただの物語ではありません。1990年代初頭、インターネットが普及する黎明期に、新聞連載という形で読者を巻き込みながらリアルタイムで紡がれた、前代未聞の実験的な一作なのです。読者の声が、物語の登場人物を動かし、時にはその命運さえ左右してしまう。そんな仕掛けが施されています。
物語の中には、さらに別の物語が存在し、それらを書いている作者自身も登場人物として現れるという、複雑で入り組んだ構造を持っています。初めて読む方は、その仕掛けに少し戸惑うかもしれません。しかし、その構造こそが「朝のガスパール」という作品の醍醐味であり、他では味わえない読書体験を生み出しているのです。
この記事では、まず物語の導入部を紹介し、その後、物語の核心に触れる考察をたっぷりと語っていきます。この物語がどのようにして生まれ、どのようにして誰も予測しなかった結末へとたどり着いたのか。その壮大な実験の軌跡を、一緒に辿っていきましょう。この不思議な物語の扉を開ける準備はよろしいでしょうか。
小説「朝のガスパール」のあらすじ
物語は、遠い未来、惑星クォールを舞台にしたSF的な戦闘シーンから始まります。深江分隊長率いる「まぼろしの遊撃隊」が、異星人と熾烈な戦いを繰り広げているのです。読者はまず、この本格的なSFの世界に引き込まれることでしょう。ミリタリーの専門用語が飛び交い、緊迫した状況が続きます。
しかし、物語はすぐに視点を変えます。場面は現代日本の豪華な邸宅へ。実は、先ほどのSF活劇は、金剛商事に勤めるエリート、貴野原征三が夢中になっている最新のコンピューターゲームの世界だったのでした。彼の美しき妻、聡子は、夫がゲームに没頭する傍らで、静かに微笑んでいます。一見、何不自由ない裕福な夫婦の日常が描かれます。
ところが、その平和な日常の裏で、聡子はとんでもない秘密を抱えていました。彼女は夫に内緒で行った株式投資に大失敗し、家屋敷を抵当に入れても返せないほどの莫大な借金を背負ってしまっていたのです。誰にも相談できず、日に日に追い詰められていく聡子。彼女のこの絶望的な状況が、物語の大きな柱となっていきます。
さらに奇妙なことに、この物語を書いている作家「櫟沢(くぬぎざわ)」と、その担当編集者である「澱口(おりぐち)」までもが、作中に登場人物として現れます。彼らは、読者から新聞社に届く手紙やパソコン通信の書き込みに一喜一憂しながら、物語の舵取りに苦心します。こうして、三つの異なる世界が奇妙に絡み合いながら、物語は展開していくのです。
小説「朝のガスパール」の長文感想(ネタバレあり)
「朝のガスパール」を初めて読んだ時の衝撃は、今でも忘れられません。これは単なる「お話」ではない、読書という行為そのものを根底から揺さぶる、壮大な「事件」なのだと感じました。毎朝新聞をめくるたびに、物語が読者の声によって変容していく。そんな前代未聞の試みを、筒井康隆氏は1990年代に成し遂げてしまったのです。
この物語の凄みは、その重層的な構造にあります。まず、物語の一番奥深くには、SFゲーム「まぼろしの遊撃隊」の世界があります。読者は最初、これを純粋なSF作品として読み進めます。緻密な設定と迫力ある戦闘描写は、それだけでも一つの作品として成立するほどの完成度です。
しかし、すぐにそのゲームをプレイしている貴野原夫妻のいる「現代」の世界が立ち上がってきます。美しい妻・聡子が抱える巨額の借金という、極めて現実的な悩み。この生々しい人間ドラマが、SFの世界とは対照的なもう一つの物語の軸を形成します。ここまでは、まだ理解の範疇かもしれません。
本当の意味でこの物語が異常な姿を現し始めるのは、第三の層、つまり作者「櫟沢」と読者が存在する世界が顔を出してからです。「この展開はけしからん」「もっとSFシーンを出せ」「登場人物が多すぎる」といった、現実の読者からの投書やパソコン通信での書き込みが、作中で作者を悩ませるのです。
作者であるはずの櫟沢が、読者からの批判に右往左往し、時に激しく憤慨する。その葛藤そのものが、物語の一部として我々の前に提示されます。物語の創造主であるはずの作者が、創造物である登場人物と同じ地平に引きずり降ろされ、読者という名の神々の気まぐれに翻弄される姿は、滑稽でありながらも、創作という行為の本質を突いているように思えました。
この実験が最も過激化したのは、やはり中盤で起きる「登場人物大量死事件」でしょう。「登場人物が多くて覚えられない」という読者の不満に対し、作者・櫟沢はなんと、物語の登場人物の大半を弾道旅客ロケットの事故で死なせてしまうのです。これは、読者の声に応えた結果でありながら、同時に読者への痛烈な皮肉と反逆でもありました。
この事件を境に、物語の各階層を隔てていた壁は、完全に崩壊を始めます。それまでゲームの中の存在だったはずの「まぼろしの遊撃隊」が、聡子のいる「現実」に出現し、彼女を借金取りのヤクザから救うために銃撃戦を始めるのです。この展開には、もはや何でもありだと笑うしかありませんでした。
さらに驚くべきことに、読者がパソコン通信に書き込んだアスキーアートの核爆弾が、ゲーム世界に「投下」され、甚大な被害をもたらします。読者の悪ふざけが、虚構の世界に直接的な破壊力を持ってしまった瞬間です。現実と虚構の境界線が溶けてなくなり、混沌とした祝祭空間が生まれていきました。
私が特に心を揺さぶられたのは、このメタフィクションの嵐の中心に、貴野原聡子という一人の女性の苦悩が、確かな手触りをもって描かれ続けたことです。彼女が抱える借金問題は、物語の最後まで切実な人間ドラマとして機能し続けます。どんなに突飛な展開が起きても、聡子の存在が、この物語を地に足のついたものにしていたのです。
彼女は、追い詰められた末に、自らの貞操を犠牲にしようとさえします。この展開には、当時の読者から賛否両論が巻き起こったそうですが、極限状況に置かれた人間の弱さと強さを見事に描き切っていたと感じます。フィクションの構造を解体するという実験を行いながら、決して人間を描くことを放棄しない。そのバランス感覚こそ、筒井氏の真骨頂でしょう。
聡子の物語があったからこそ、「まぼろしの遊撃隊」が現実世界に現れて彼女を助けるという荒唐無稽な展開が、ただのギャグではなく、一種のカタルシスとして機能したのだと思います。虚構が現実の苦しみを救う。これほど物語の力を肯定するメッセージはありません。
物語の終盤は、まさに圧巻の一言です。作者・櫟沢、貴野原夫妻、まぼろしの遊撃隊の隊員たち、ロケット事故で死んだはずの人々、果ては読者の分身まで、ありとあらゆる階層の登場人物が一堂に会し、大パーティーを繰り広げるのです。
そこにはもう、物語の整合性や論理などありません。全てがごちゃ混ぜになり、ただただ joyous なカオスが広がっています。これは、物語の破綻なのではなく、物語が全ての制約から解き放たれ、無限の自由を獲得した瞬間だったのではないでしょうか。
この結末を読んで、私は「物語は誰のものか?」という問いを突きつけられた気がしました。作者のものでしょうか。それとも、登場人物のものでしょうか。あるいは、私たち読者のものでしょうか。「朝のガスパール」が出した答えは、「その全てであり、誰のものでもない」というものだったのかもしれません。
この作品は、作者、登場人物、読者が三位一体となって、一つのテクストを生成し、そして崩壊させていくプロセスそのものを描いた、壮大なドキュメンタリーでもあります。新聞連載という一度きりのライブパフォーマンスであったがゆえに、この奇跡的な作品は生まれ得たのでしょう。
今、私たちが日常的に触れているインターネット上のSNSや参加型コンテンツの世界は、ある意味で「朝のガスパール」が予見した世界の延長線上にあると言えます。匿名の声が飛び交い、時に誰かを称賛し、時に容赦なく傷つける。その光と影の両面を、この小説は30年以上も前に描き出していたのです。
ですから、「朝のガスガスパール」は、単なる過去の実験作としてではなく、現代を読み解くための予言の書としても読むことができます。物語とは何か、現実とは何か、そしてコミュニケーションとは何か。そうした根源的な問いを、これほどスリリングに、そして大胆に問いかけた作品を私は他に知りません。
未読の方には、ぜひこのめくるめく虚構と現実の迷宮に足を踏み入れてほしいと願います。最初は混乱するかもしれません。しかし、その混乱の先に、これまでの読書体験が覆されるような、とてつもない知的興奮が待っているはずです。この作品は、読むたびに新しい発見がある、まさに文学の奇跡なのです。
まとめ
「朝のガスパール」は、単に筋を追うだけではその真価を理解できない、非常に特殊な作品です。物語の中にゲームの世界があり、そのゲームをプレイする人々の世界があり、さらにその物語を書いている作者の世界が同時に進行するという、複雑な構造を持っています。
この作品の最大の特徴は、新聞連載当時、読者からの投書やパソコン通信の書き込みをリアルタイムで物語に反映させた点にあります。読者の声によって登場人物の運命が変わり、時には物語そのものが根底から覆されるという、前代未聞の試みが行われました。
その結果、物語の境界線は曖昧になり、虚構と現実が入り乱れる混沌とした展開へと突き進んでいきます。これは、作者、登場人物、そして読者が一体となって作り上げた、一度きりの文学的な「事件」と言えるでしょう。
もしあなたが、これまでにない刺激的な読書体験を求めているのなら、この奇妙で素晴らしい物語は、きっとその期待に応えてくれるはずです。物語の可能性を極限まで押し広げた、文学史に残る一作です。