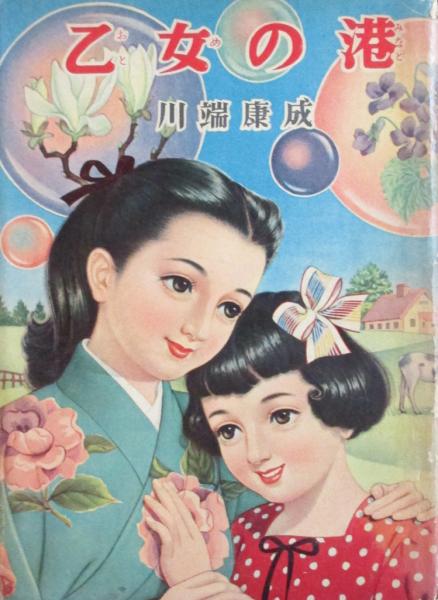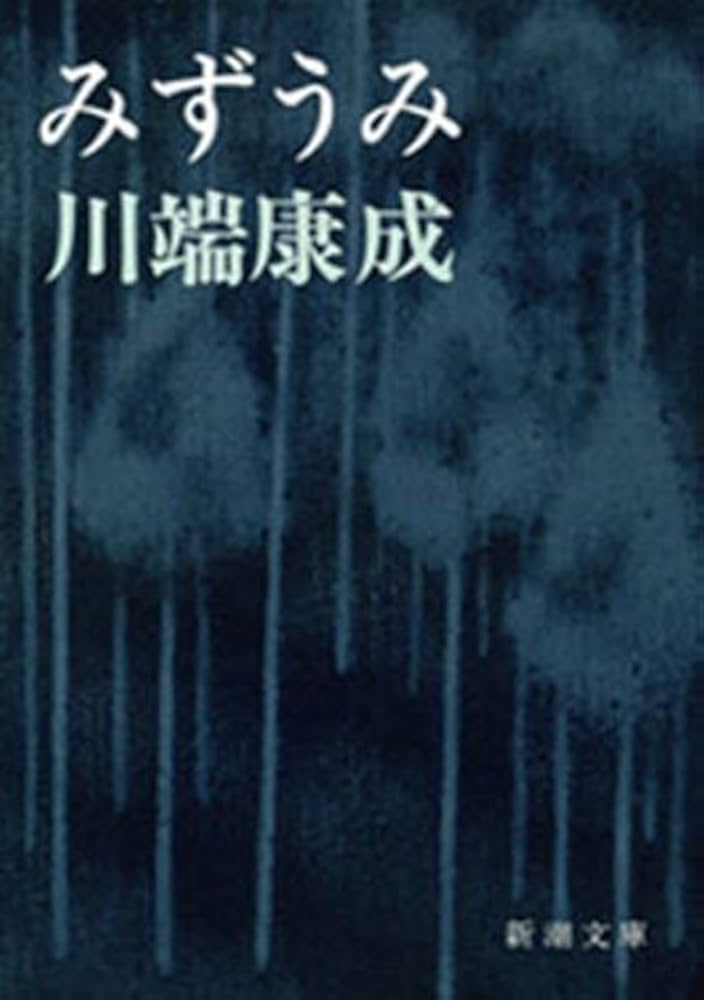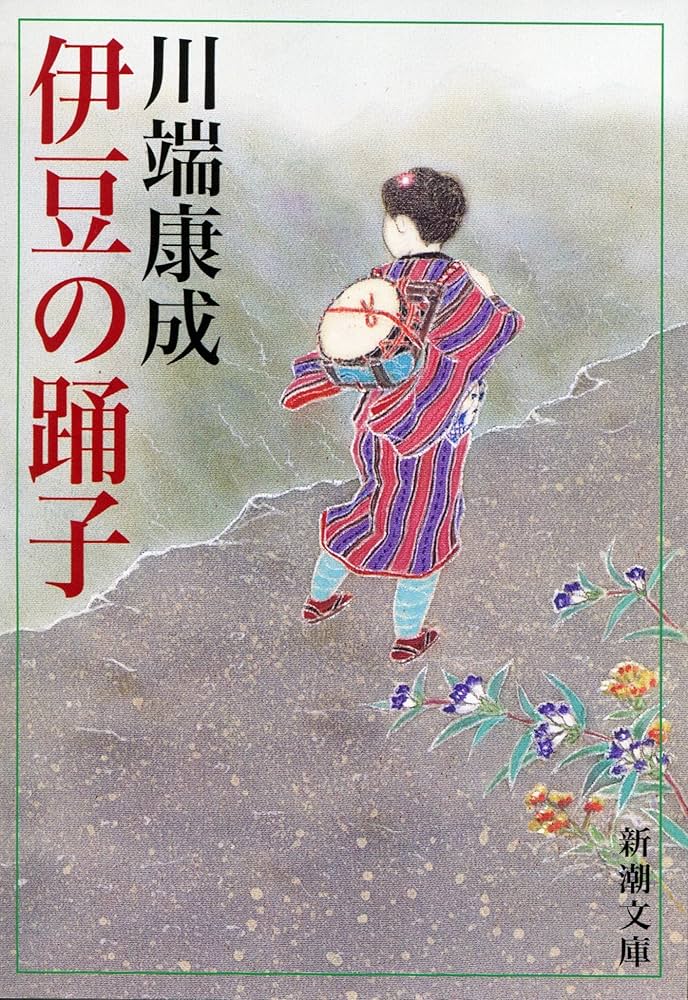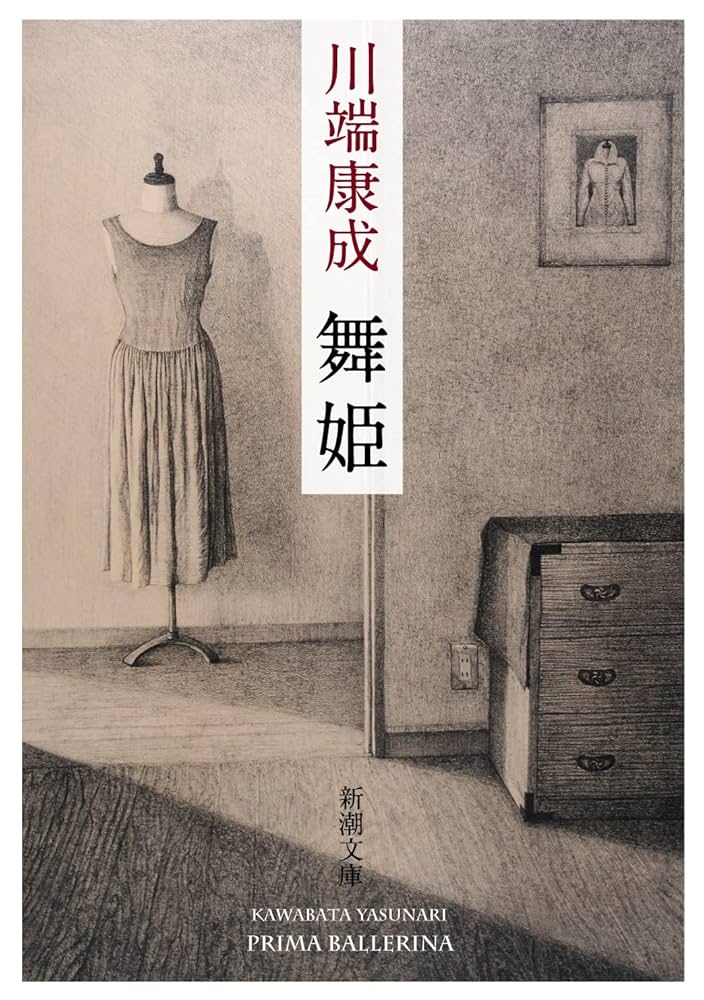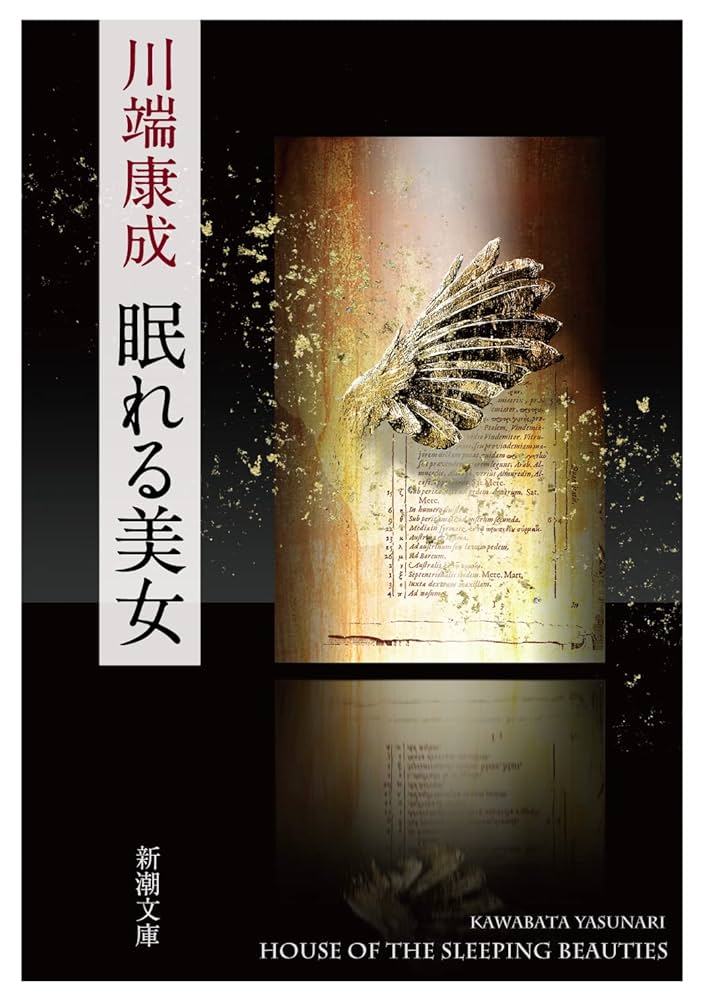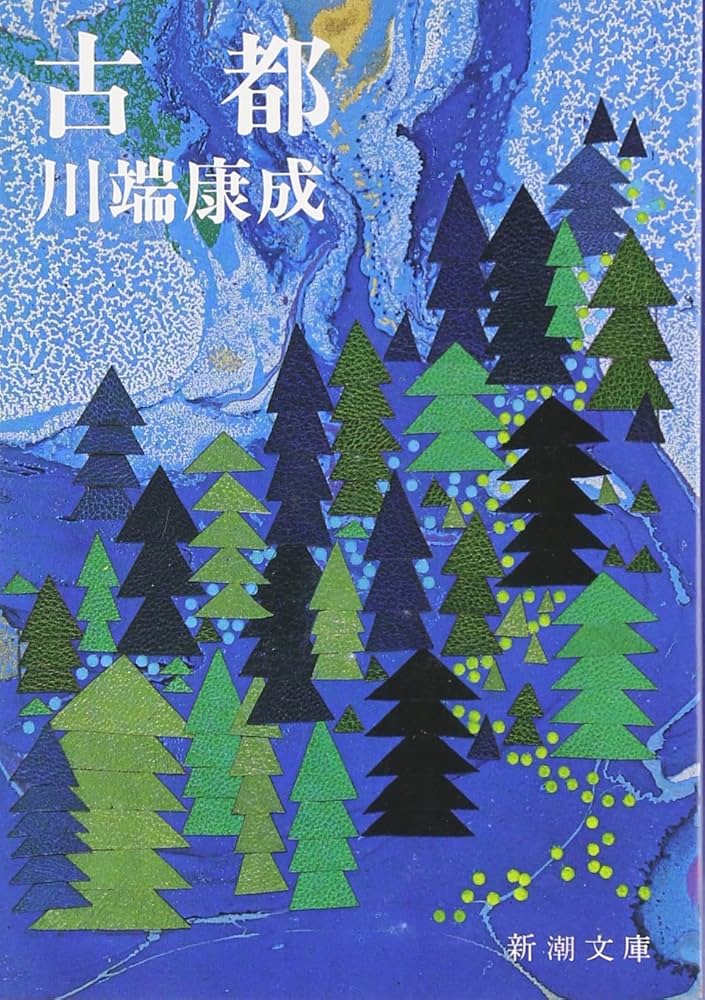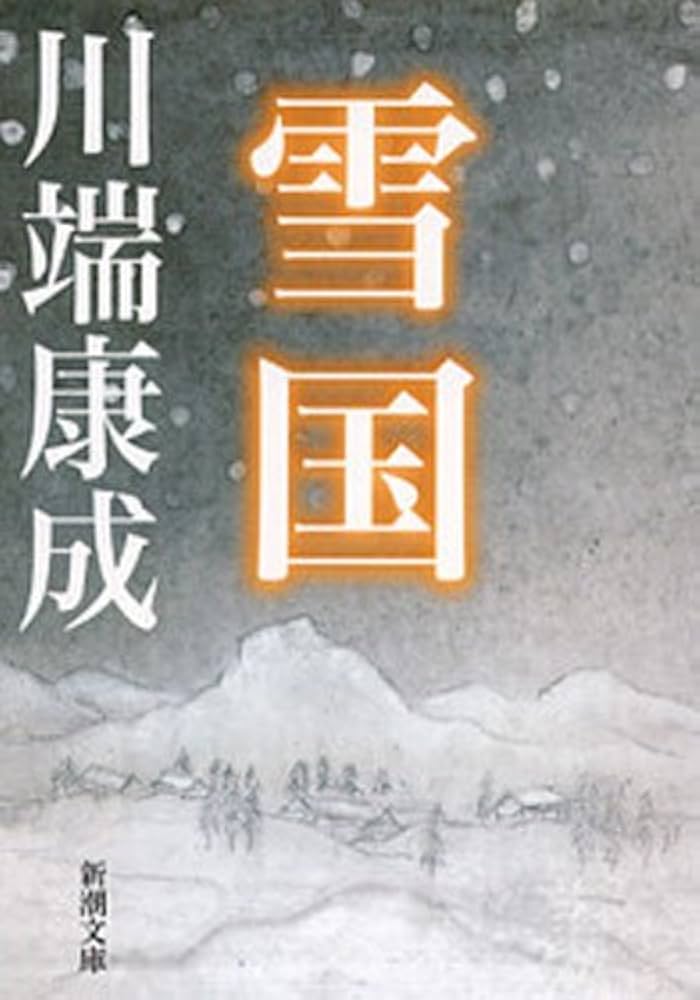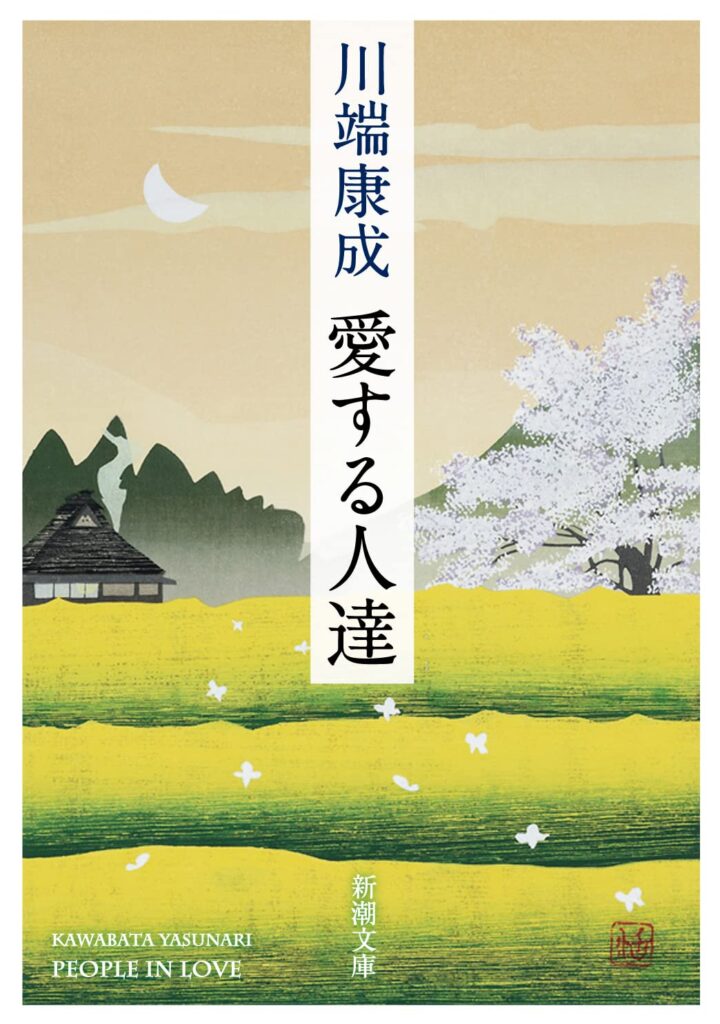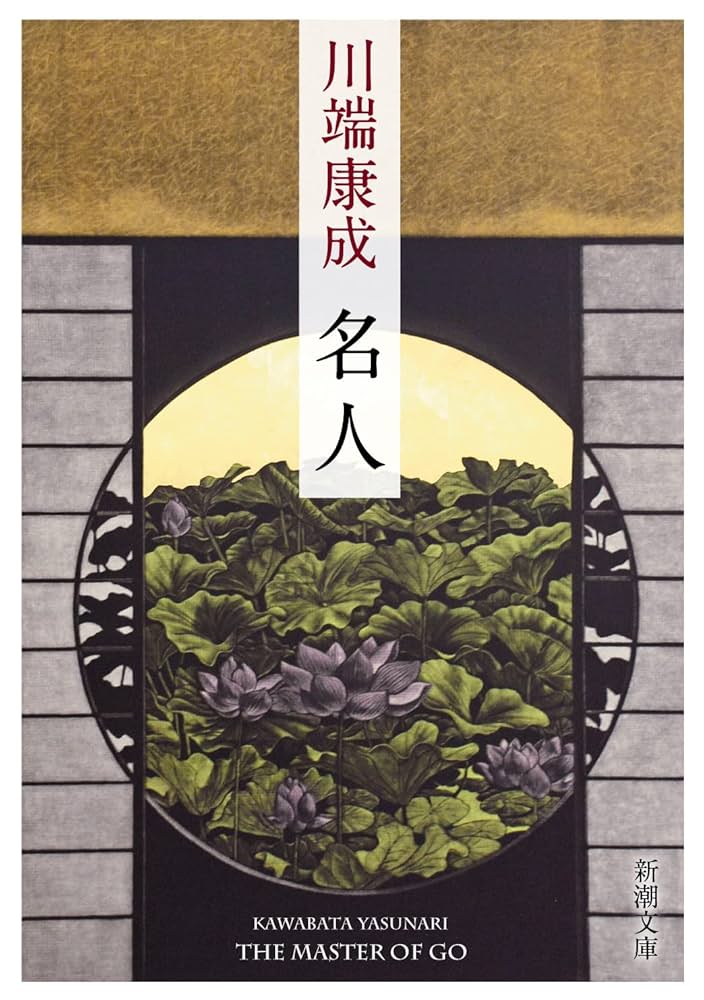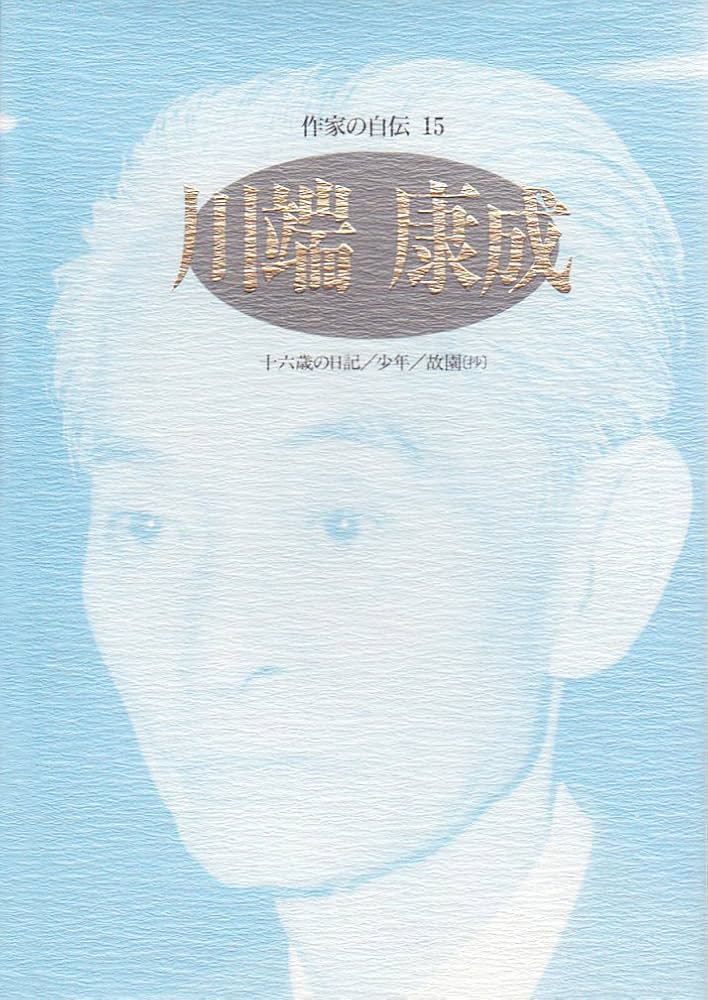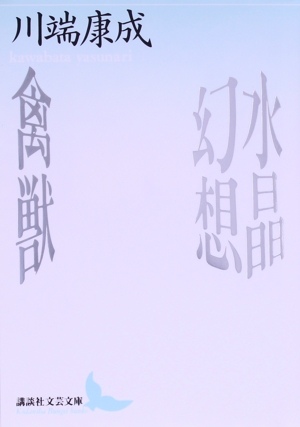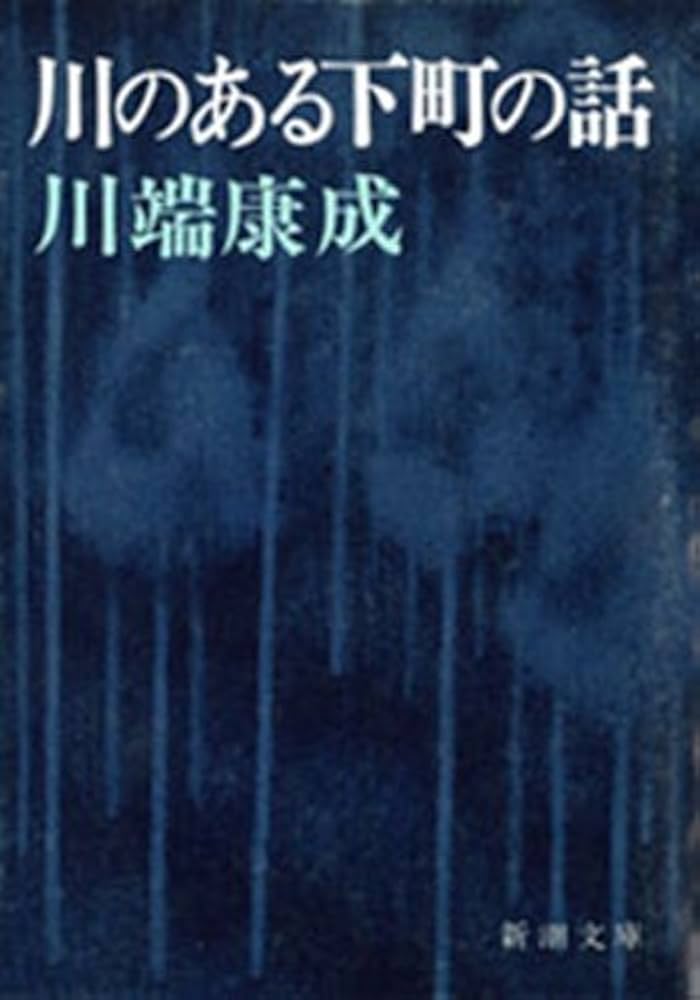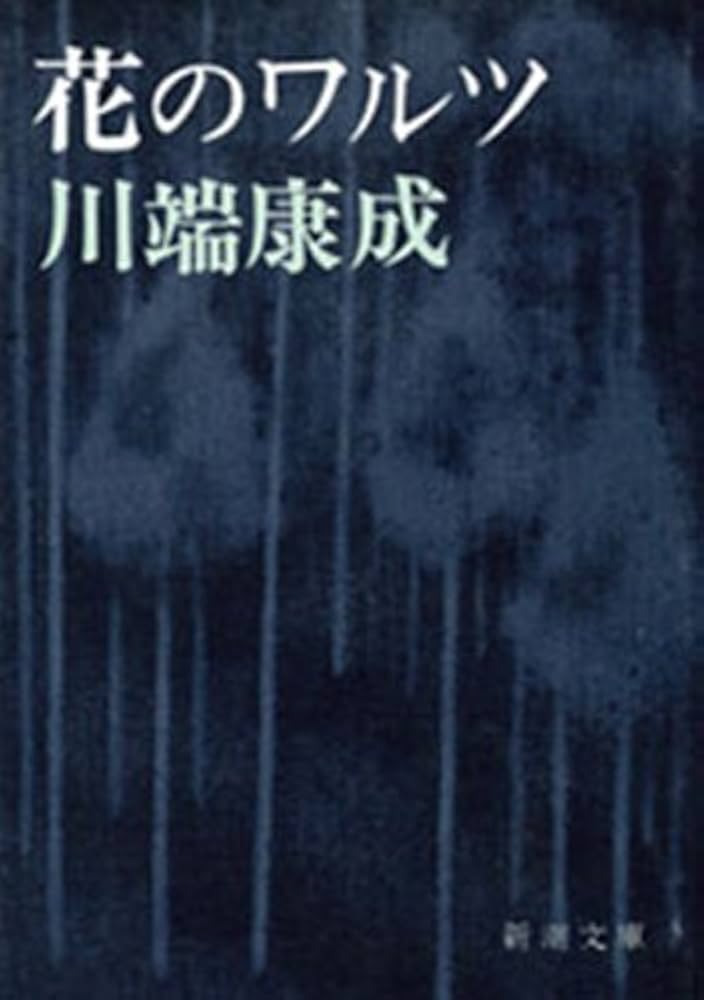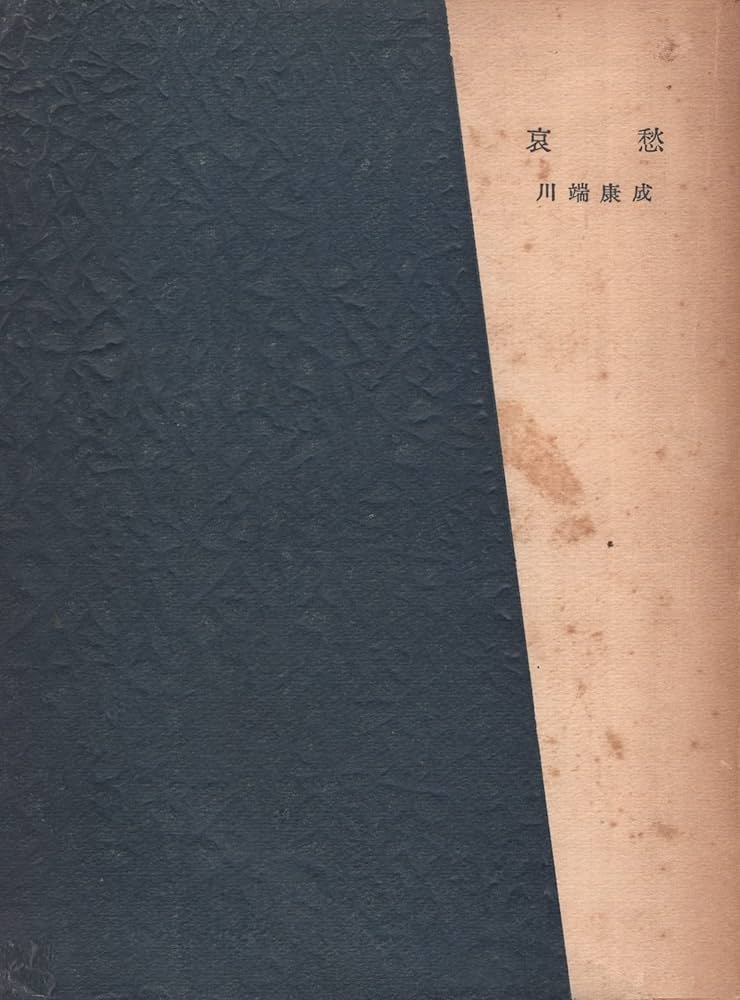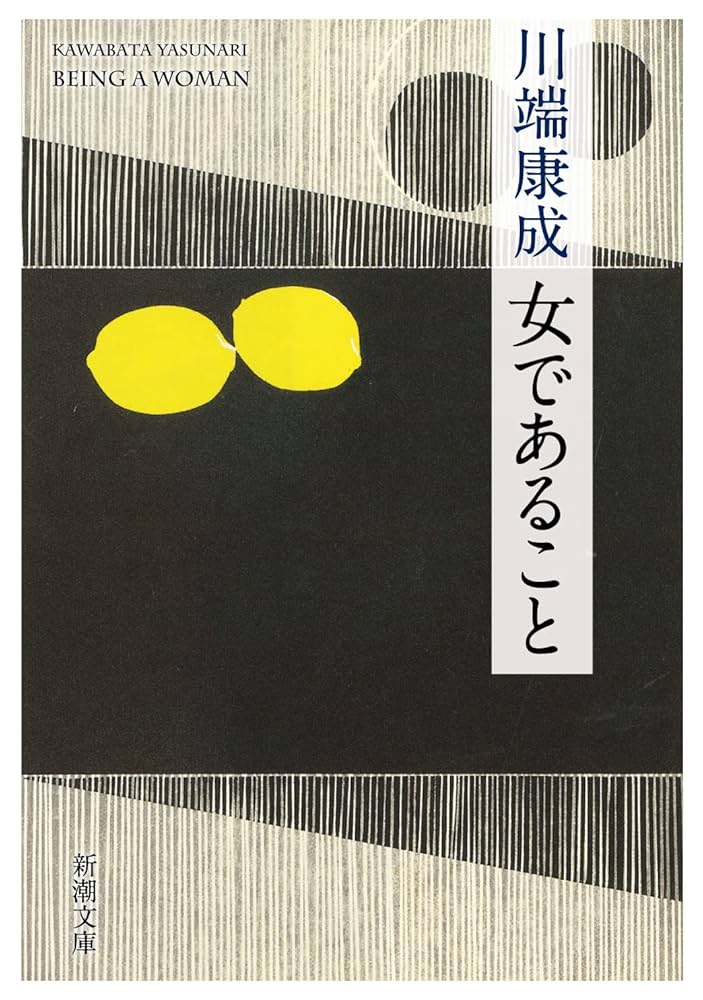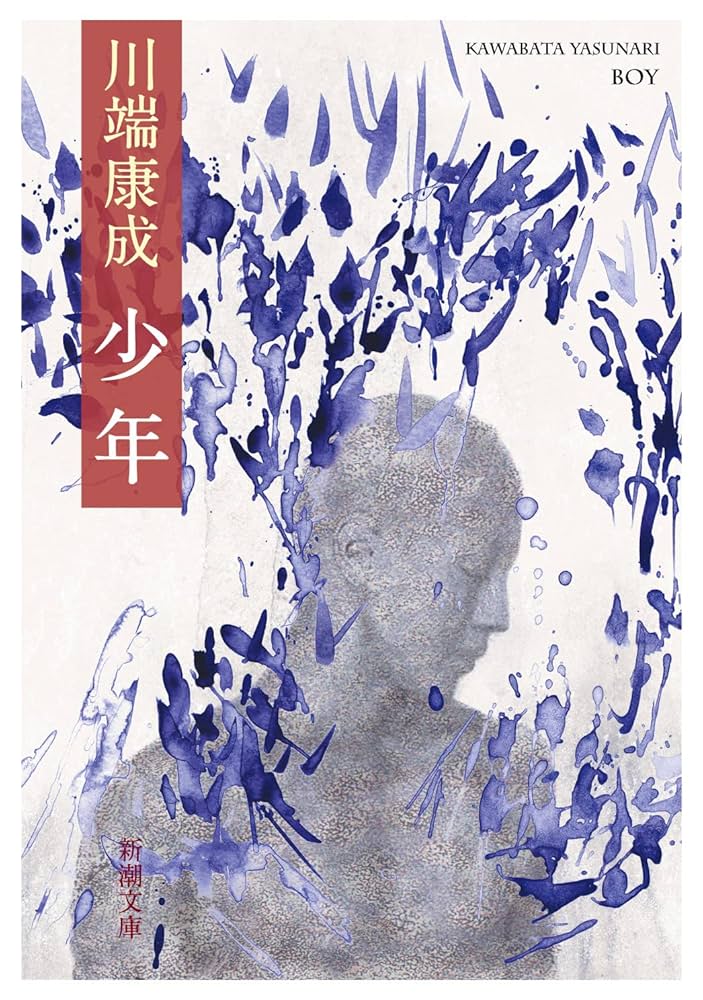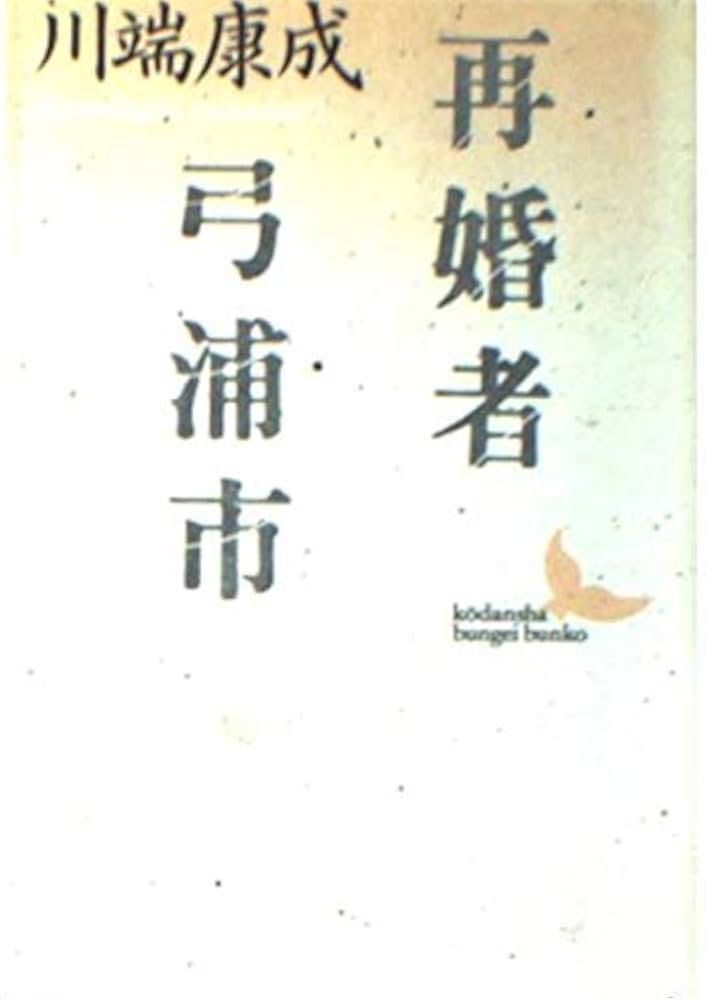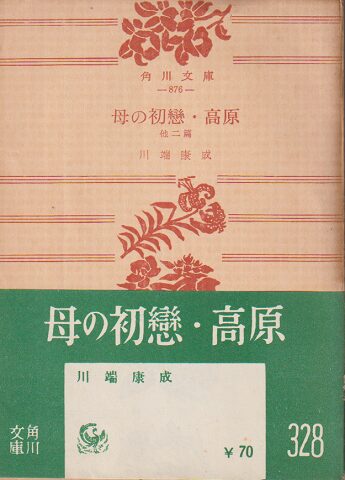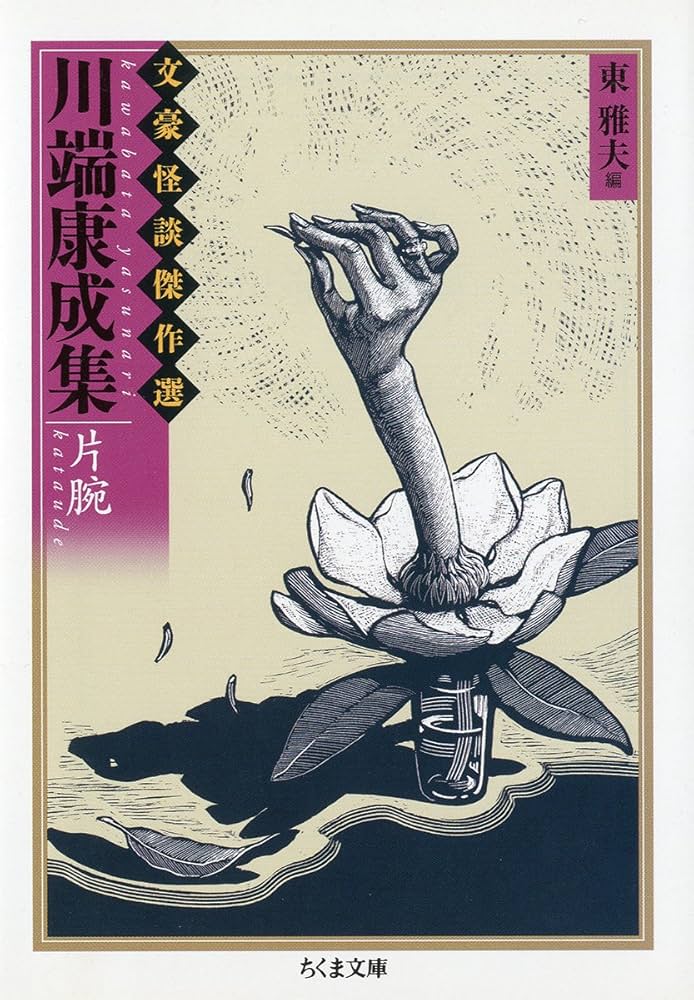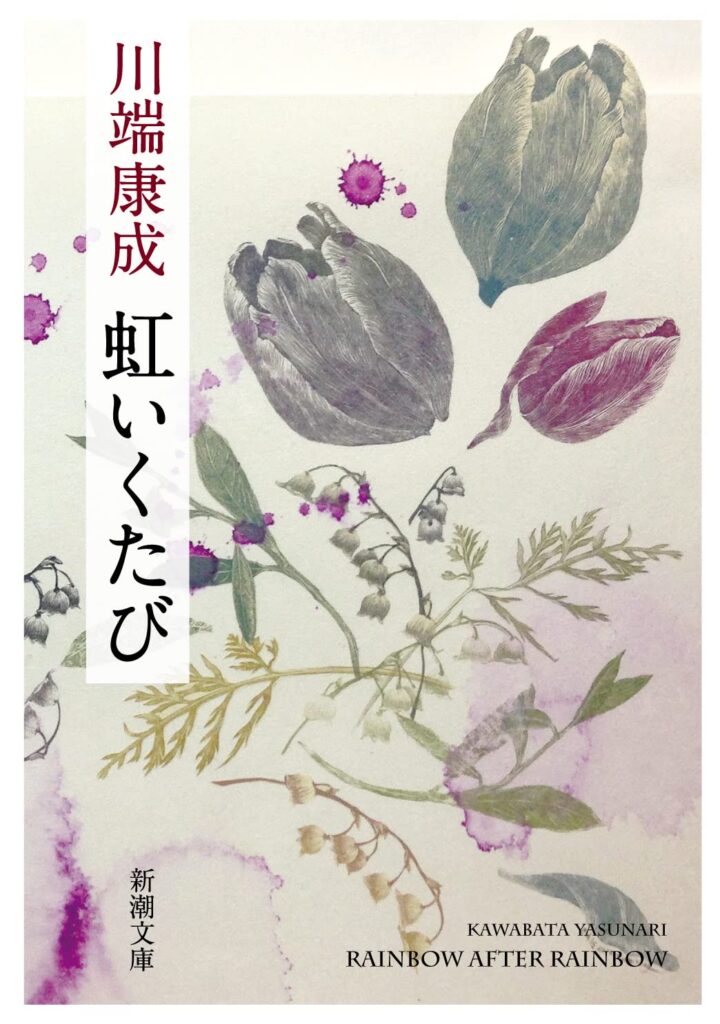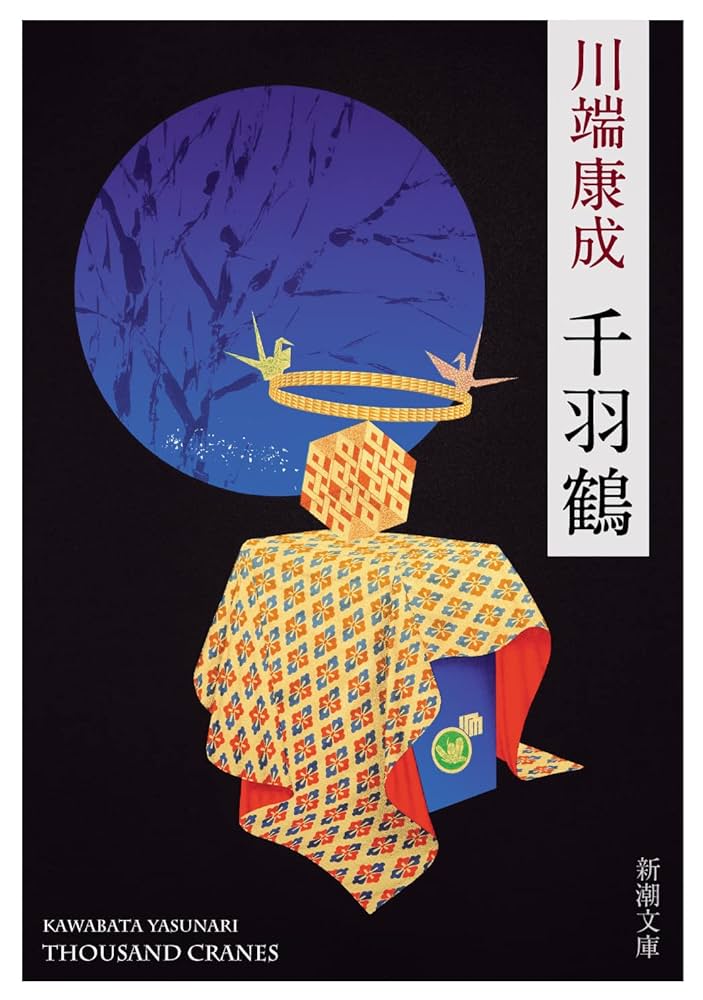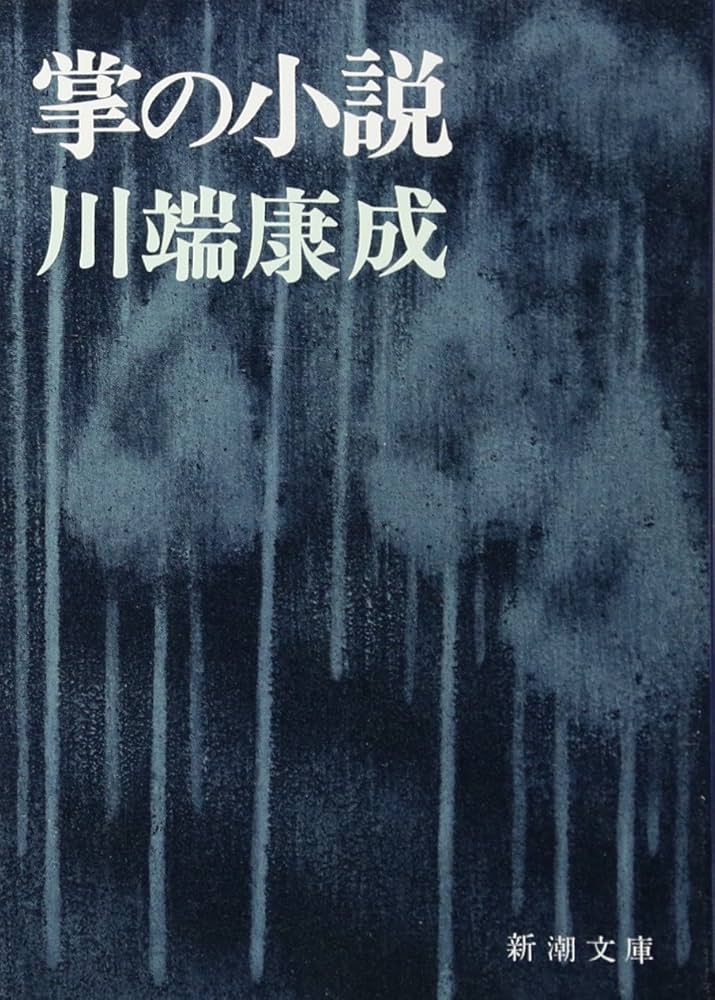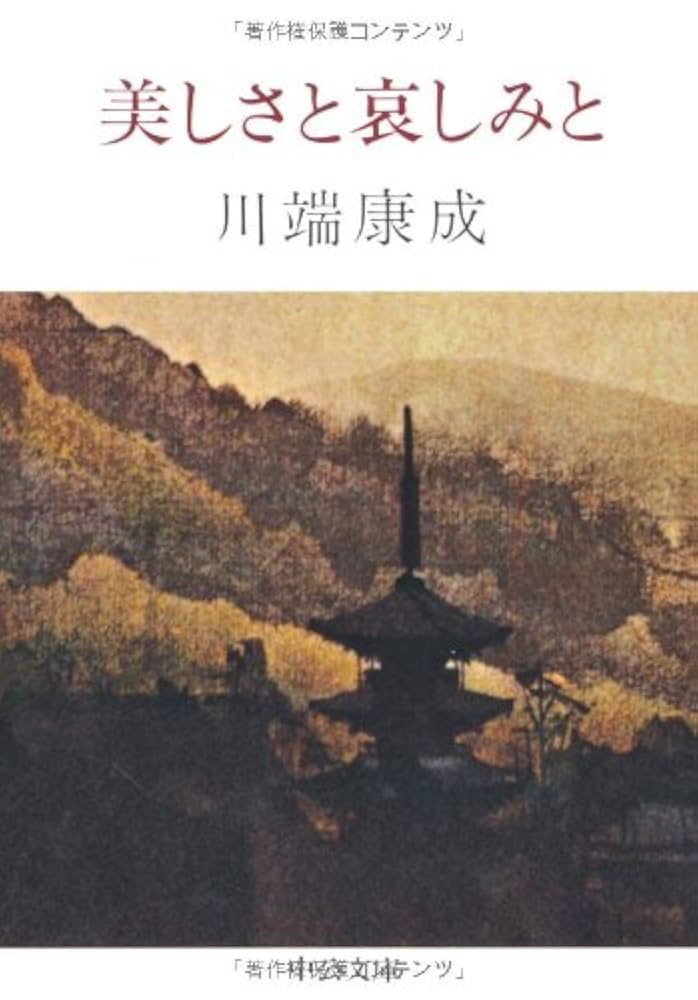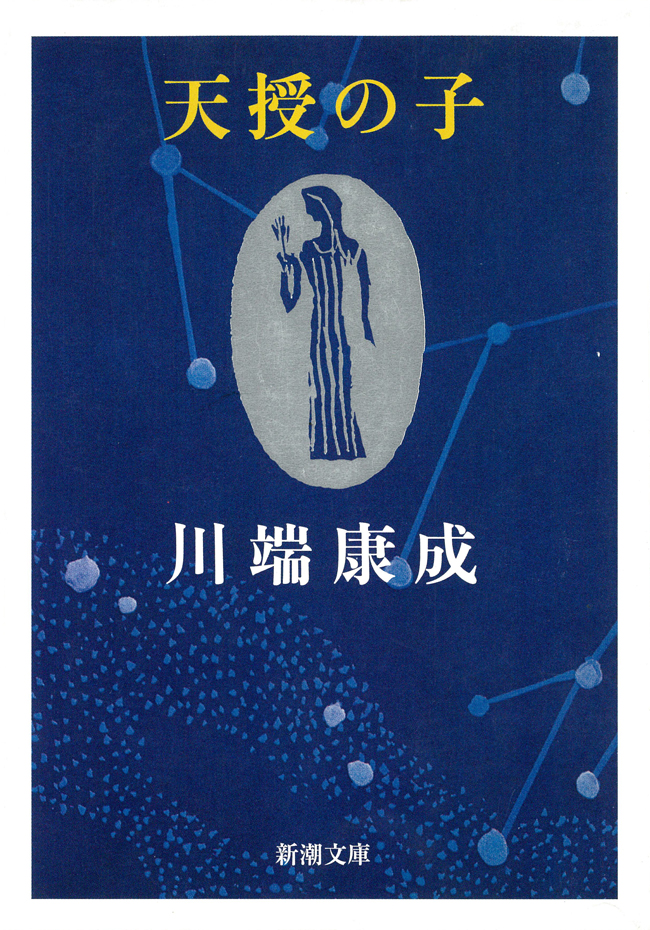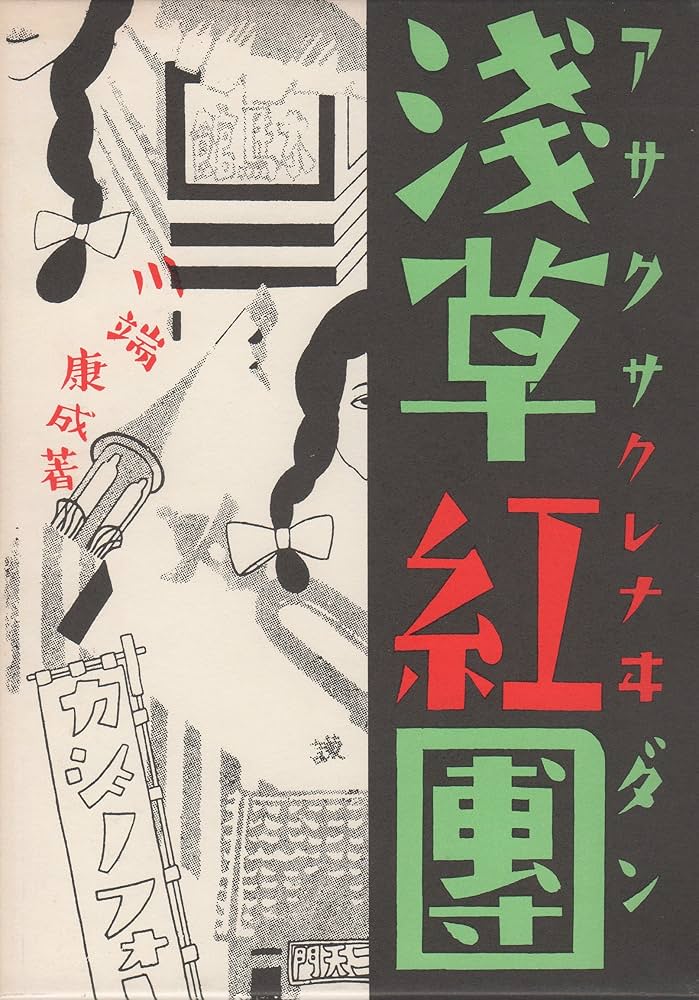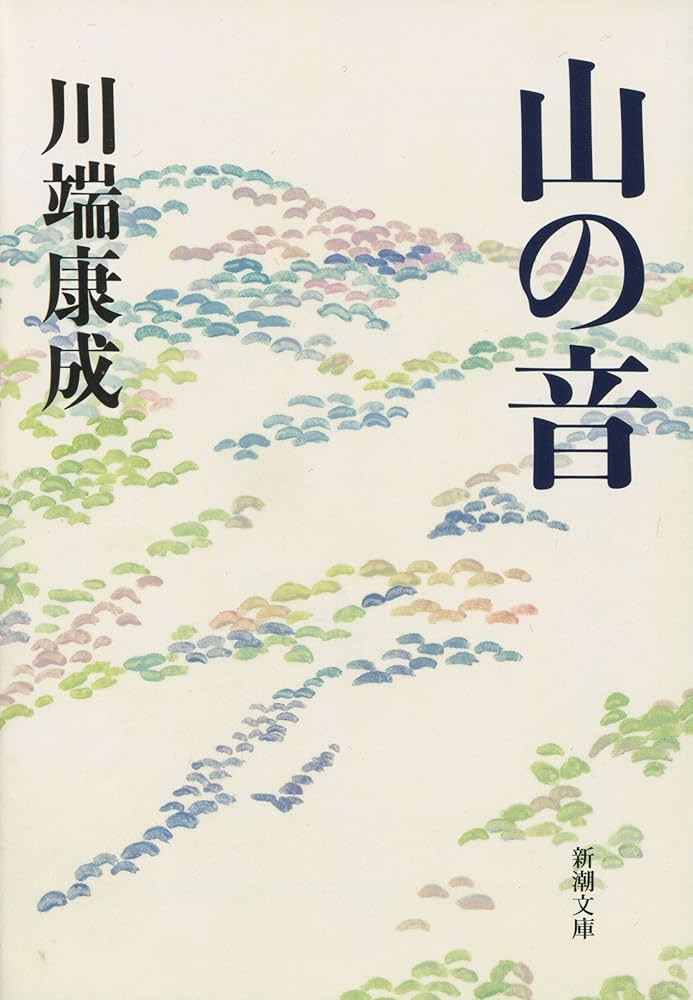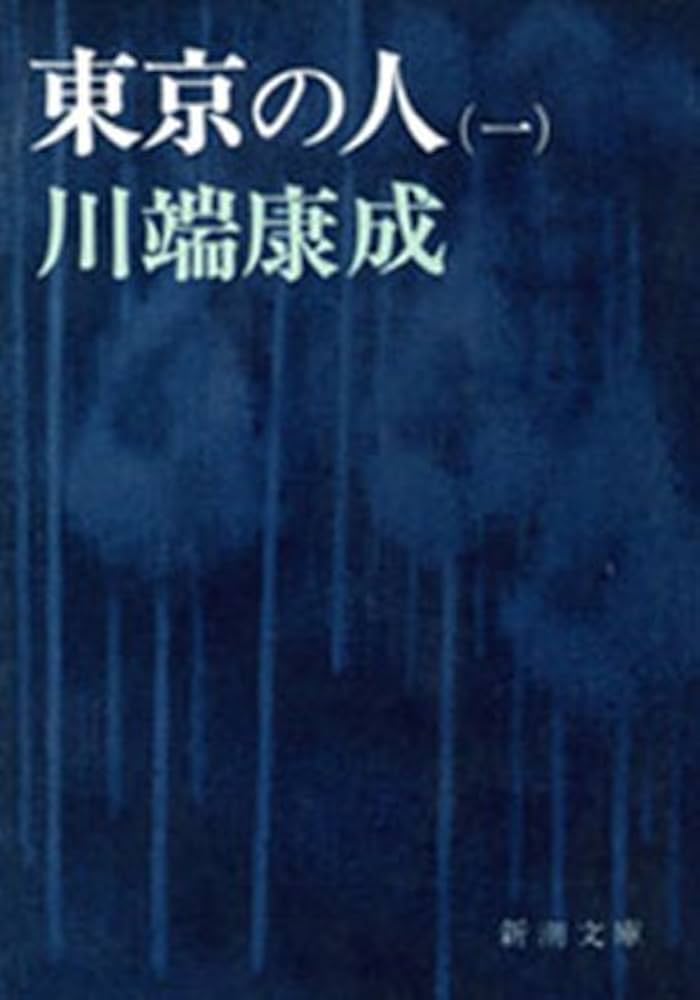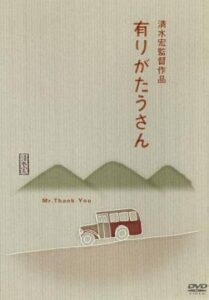 小説「有りがたうさん」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「有りがたうさん」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
ノーベル文学賞作家、川端康成の数ある作品の中でも、「掌の小説」と呼ばれる短編群は、特別な輝きを放っています。その一つである「有難う」は、のちに「有りがたうさん」という題名で映画化され、広く知られるようになりました。短い物語の中に、人間のどうしようもない運命と、そこに差し込む一筋の光のような情愛が、凝縮されて描かれています。
舞台は「伊豆の踊子」でもおなじみの天城の山道。しかし、旅の目的は淡い恋物語とはほど遠い、娘の身売りという過酷なものです。絶望的な状況下で、登場人物たちの心はどのように揺れ動き、どのような結末を迎えるのでしょうか。この記事では、物語の核心に触れるネタバレを含みながら、その深い魅力に迫っていきます。
本記事が、この不朽の名作との新たな出会いや、再読のきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。川端文学の精髄ともいえる、その世界をご案内いたしましょう。
「有りがたうさん」のあらすじ
物語の舞台は、柿が豊かに実る秋の伊豆。下田から三島へ向かう乗合バスの車内から、物語は始まります。そのバスの運転手は、道を譲ってくれる人や馬車に対して、いつも丁寧に「有難う」と声をかけるため、土地の人々から親しみを込めて「有りがたうさん」と呼ばれている実直な青年です。
彼のすぐ後ろの席には、十七歳の美しい娘と、その母親が座っています。しかし、二人の間には重苦しい沈黙が漂っていました。彼女たちの旅の目的は、家が貧しいために娘を遠い町へ身売りに行くという、悲痛なものだったのです。バスに揺られる道中、娘はただひたすらに、前席の運転手の背中を見つめ続けています。
そのまっすぐな肩は、未来への不安に苛まれる娘にとって、唯一の拠り所であるかのように見えました。娘の視線に気づいた母親は、評判の良い「有りがたうさん」のバスに乗り合わせることができたのをせめてもの幸運と考え、複雑な思いを抱きます。
やがてバスは目的地に到着します。そこで母親は、娘を案じるあまり、運転手に対してある驚くべき願い事をするのです。その願いが、三人の運命を予期せぬ方向へと動かしていくことになります。
「有りがたうさん」の長文感想(ネタバレあり)
この物語の冒頭は、「今年は柿の豊年で山の秋が美しい」という一文で始まります。そして驚くべきことに、物語の最後も全く同じ文章で締めくくられるのです。これは、過酷な人間ドラマが、美しくも移ろいやすい自然の摂理に静かに包み込まれていることを示しているように、私には感じられます。
舞台は、未舗装の天城街道を走る一台の乗合バス。中心となる登場人物は、道を譲る誰にでも「有難う」と声をかける実直な運転手、そして彼の真後ろの席に座る、身売りされる十七歳の娘とその母親の三人です。重い沈黙が支配する車内で、物語の核心は、この娘の視点を通して静かに紡がれていきます。
川端康成は、娘の心理を「山道に揺られながら娘は直ぐ前の運転手の正しい肩に目の光を折り取られている」と表現しました。これは、ただ見つめているという状態を遥かに超えています。娘の意識、彼女の存在そのものが、運転手の「正しい」と評される肩という一点に、まるで吸い寄せられるように集中していく様子を描いているのです。
この「正しい肩」という表現が、実に素晴らしいと思いませんか。絶望的な未来へと運ばれていく娘にとって、その肩は、物理的な安定だけでなく、道徳的な正しさをも感じさせる唯一の不動点だったのでしょう。彼女の不安な心は、その一点に救いを求めていたのです。
娘の心の中では、さらに大きな変化が起こります。「黄色い服が目の中で世界のように拡がって行く。山々の姿がその肩の両方へ分れて行く」。運転手の制服の色が視界のすべてを覆い尽くし、雄大な伊豆の山々でさえ、彼の存在を避けて流れていくように感じられる。これは、来るべき過酷な運命から心を守るための、無意識の防衛本能だったのかもしれません。運転手の背中が、彼女を守る盾であり、全世界そのものになった瞬間です。
一方、娘を売らねばならない母親は、自らの行為を必死に正当化しようとします。「有りがたうさん」という評判の運転手のバスに乗れたことを吉兆と捉え、「有りがたうさんに連れて行って貰うなら、この娘も幸せです…」と自分に言い聞かせるのです。その言葉は、悲痛な自己欺瞞であり、母親のどうしようもない苦しみが伝わってきます。
そして、物語は衝撃的なクライマックスを迎えます。ここからが、この物語の核心に触れるネタバレとなります。目的地に着いた後、母親は運転手に近づき、信じられないような嘆願をするのです。「この子がお前さんを好きじゃとよ…どうせ明日から見も知らない人様の慰み物になるんじゃもの」。娘が商品として扱われる前に、彼女が心を寄せた男性と、人間としての一夜を過ごさせてやってほしい、と。
この母親の行動は、常識的な道徳観からすれば逸脱しているかもしれません。しかし物語の中では、娘に与えることのできる最後の、そして究極の慈悲として描かれています。娘の人間としての尊厳を、失われる寸前で守ろうとした、母親の絶望的な愛の形だったのではないでしょうか。
そして、運転手は、この常軌を逸した母親の願いを受け入れます。物語の場面は、一夜が明けた朝へと移ります。ここで再び、娘の視点から世界が描写されます。「娘は直ぐ前の温かい肩に目の光を折り取られている。秋の朝風がその肩の両方へ流れて吹く」。あの「正しい肩」は、一夜を経て「温かい肩」へと変化しているのです。この一語の変化に、すべてが込められています。
この一夜によって、しかし事態は複雑になります。母親は運転手と娘の両方から「説教されて叱られ」、良かれと思ったことが裏目に出たと嘆きます。これは単なる道徳的な非難というより、一夜の結びつきが、娘を売るという計画そのものを感情的に不可能にしてしまったことへの困惑だったのでしょう。
結果として、娘は売られずに済みます。運転手もまた娘に心を寄せており、一つの提案をします。これから寒くなるから、春までは家に置いておく。しかし、暖かくなれば、やはり家を出ていかなければならないかもしれない、と。完全な救済や結婚の約束ではありません。それは、避けられない運命の、ほんの束の間の猶予に過ぎないのです。
この結末は、私たちに「善」とは何かを鋭く問いかけます。運転手の行為は、社会の規範からは外れているかもしれません。しかし、極限状況に置かれた一人の少女の心を救う、究極の共感の形だったともいえます。この曖昧さこそが、この物語の持つ深い魅力なのです。
ここで、清水宏監督によって映画化された「有りがたうさん」に少し触れてみたいと思います。映画では、この結末が大きく変更されています。映画の運転手(上原謙が演じています)は、母親の嘆願を穏やかに、しかし断固として拒絶するのです。
映画版の運転手は、誰からも慕われる「善良な好青年」として、その規範的な善性を最後まで貫きます。この改変は、映画というメディアが持つ公的な性格を考えれば、必然だったのかもしれません。観客が共感しやすい、明快なヒーロー像が求められた結果でしょう。
しかし、小説の運転手が体現する「善」は、より複雑で、私的な領域にあります。それは、マニュアル通りの正しさではなく、目の前の苦しみに寄り添うために、あえて社会の規範を踏み越えることを厭わない優しさです。どちらが正しいということではなく、二つの異なる「善」の形がここには存在します。
再び小説に立ち返ると、この物語の根底には、母親の犠牲的な愛と、娘のささやかな抵抗が見えてきます。母親の嘆願は、娘に最後の「人間らしい時間」を与えようとする絶望的な試みでした。そして、娘が運転手の背中に向けた静かな眼差しは、選択肢のない世界で、彼女に唯一残された自己決定の行為、彼女の力の表現だったのです。
最後に、この物語の題名にもなっている「有難う」という言葉の意味について考えてみたいと思います。この言葉は、もともと「有ることが難しい」、つまり「稀で、貴重である」という意味の「有り難し」という言葉から来ています。この物語で描かれているのは、まさにこの「有り難い」奇跡そのものです。
娘に与えられた救済は、完全なものではなく、冬が終われば消えてしまうかもしれない、儚いものです。しかし、過酷な現実の中で生まれたその束の間の恩寵は、何物にも代えがたい「有り難い」瞬間だったに違いありません。この短い物語全体が、「有難う」という言葉の持つ、深く、そして本来の意味を私たちに教えてくれるのです。
まとめ
川端康成の「有りがたうさん」(原作「有難う」)は、伊豆の美しい秋を背景に、人間の過酷な運命と、そこに差し込む一筋の光を描いた、まさに珠玉のような作品です。身売りされる娘と、彼女が心を寄せる実直なバス運転手、そして娘を想うがゆえに驚くべき行動に出る母親。三人の心が織りなす物語は、読む者の心を強く揺さぶります。
この記事では、物語の結末に至るまでのネタバレを含めながら、そのあらすじと感想を詳しくご紹介しました。特に、娘の心を救うために運転手が下した決断は、私たちに「善」とは何か、本当の優しさとは何かを深く問いかけます。
それは決して単純なハッピーエンドではありません。しかし、絶望の中に灯る束の間の救いこそが、「有ることが難しい」=「有り難い」奇跡なのだと、この物語は静かに語りかけてきます。短いながらも、人生の深淵を覗き込むような読書体験が、この作品にはあります。
この名作が持つ、静かで、しかし力強い感動を少しでもお伝えできていれば幸いです。機会があれば、ぜひ原作の「掌の小説」を手に取ってみてください。