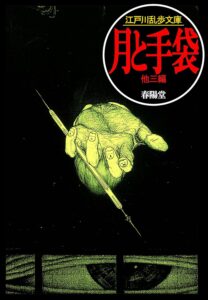 小説「月と手袋」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が戦後に発表した明智小五郎シリーズの一編ですが、読んだ方の多くは、その奇抜なトリックに驚き、もしかしたら少し呆気にとられてしまうかもしれません。率直に申し上げて、手放しで褒められる作品とは言い難い部分もあるでしょう。
小説「月と手袋」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。江戸川乱歩が戦後に発表した明智小五郎シリーズの一編ですが、読んだ方の多くは、その奇抜なトリックに驚き、もしかしたら少し呆気にとられてしまうかもしれません。率直に申し上げて、手放しで褒められる作品とは言い難い部分もあるでしょう。
しかし、この物語には、そうした評価だけでは語り尽くせない魅力が隠されていると、私は考えています。特に、追い詰められた人間の心理描写や、ふとした瞬間に現れる情景の美しさは、読む者の心に深く刻まれます。なぜ多くの人がこの作品のトリックに疑問を感じるのか、そして私がなぜそれでもこの作品に惹かれるのか、その理由を詳しくお話ししたいと思います。
物語の結末に深く関わる部分まで踏み込んで解説しますので、まだ未読で、ご自身で謎解きを楽しみたいという方はご注意ください。この記事では、物語の具体的な流れと、その仕掛けの全貌、そしてそれらを踏まえた上での私の個人的な思いを、余すところなくお伝えしていきます。
この記事を読むことで、「月と手袋」という作品が持つ独特の味わい、トリックの奇抜さの裏にあるかもしれない作者の意図、そして乱歩作品ならではの人間描写の深さに触れていただければ幸いです。それでは、まずは物語の概要から見ていきましょう。
小説「月と手袋」のあらすじ
物語の中心となるのは、シナリオライターの北村克彦です。彼は、元男爵で高利貸しの股野重郎(またの しげお)の妻、あけみと密かに愛し合っていました。あけみは元少女歌劇団のスターで、股野はその弱みにつけこんで彼女を妻にしたような男でした。股野は芸能界に顔が利き、多くの人々から恐れられていました。
ある晩、北村は股野に呼び出されます。股野は二人の関係を知っており、あけみと別れるよう迫り、法外な慰謝料を要求します。さらに、あけみに制裁を加えることを匂わせ、北村にも暴力を振るおうとしたため、逆上した北村は衝動的に股野を絞め殺してしまいます。
殺害後、北村は冷静さを取り戻し、完全犯罪を計画します。彼は、あけみと共謀し、巧妙な偽装工作を実行に移すことを思いつきます。ちょうどその時刻に警官が巡回に来ることを知っていた北村は、それを最大限に利用しようと考えたのです。
計画はこうです。まず、あけみが股野に変装し、あたかも強盗に襲われているかのように見せかけます。北村は家の外で強盗の侵入に気づいたふりをして、巡回中の警官に助けを求めます。警官と共に家に入ると、そこには首を絞められている股野(実は変装したあけみ)の姿が。警官が外へ応援を呼びに行っている隙に、あけみは素早く変装を解き、あたかも強盗に縛られて衣装箪笥に閉じ込められていたかのように見せかけます。手足を縛るのも自分で行います。
この大胆な偽装工作は見事に成功し、警察の捜査は難航します。北村は股野が殺された家に移り住み、股野の遺産であけみと共に何食わぬ顔で暮らし始めます。完璧に見えた彼らの計画でしたが、警視庁の花田警部だけは、二人に疑いの目を向け、友人として近づきながら、徐々に彼らを追い詰めていきます。
最終的に、花田警部は決定的な証拠を掴むことができません。しかし、北村とあけみの間に疑心暗鬼が生じ、互いを信じられなくなっていきます。花田警部は、二人の会話をマイクロフォンで盗聴するという手段を用い、彼らが犯行について語るのを待ちます。そして、ついに二人の口から真相が語られ、事件は解決へと向かうのでした。明智小五郎自身は登場せず、花田警部が事件を担当しますが、解決の決め手は探偵の推理ではなく、盗聴による自白だったのです。
小説「月と手袋」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここまで「月と手袋」の物語の筋書きを追ってきました。この作品を読まれた方なら、おそらく多くの方がトリックの実現性に疑問符を抱かれたのではないでしょうか。正直なところ、私も最初に読んだときは、「これはいくらなんでも無理があるのでは?」と感じた一人です。
特に重要な仕掛けである、あけみが股野に変装し、月明かりの下で首を絞められているように見せかける場面。そして、箒の毛を詰めた手袋で作った偽の手。これらは、暗闇と混乱という状況設定を考慮しても、かなり大胆というか、現実離れしていると言わざるを得ません。警官が間近で見ている状況で、変装した人間が絞殺されている演技をし、その後すぐに元の姿に戻って縛られた状態になるというのは、あまりにも綱渡りすぎます。
さらに、事件解決の決め手が、花田警部による盗聴であったという点も、ミステリとしてのカタルシスを削いでいると感じる方は多いでしょう。探偵の鋭い観察眼や論理的な推理によって真相が暴かれるのではなく、最新(当時としては)の科学技術によって犯人の自白を引き出すというのは、少々安直な解決方法に思えてしまうかもしれません。「それをやってしまったら、どんな難事件も解決できてしまうのでは?」という気持ちになるのも無理はありません。
明智小五郎シリーズの一編でありながら、名探偵自身は名前が登場するのみで、実際の捜査には関与しない点も、ファンにとっては少し寂しいところかもしれません。花田警部も魅力的ではありますが、やはり明智小五郎の鮮やかな推理を期待していた読者にとっては、物足りなさが残る可能性があります。
では、なぜ私は、このような欠点とも言える要素を抱えた「月と手袋」という作品に、強く惹かれるのでしょうか。それは、この作品が、トリックや謎解きの面白さとは別の次元で、深い魅力を持っていると感じるからです。その魅力の一つは、作者である江戸川乱歩の、新たな表現への挑戦です。
戦前の探偵小説、特に明智小五郎シリーズは、怪人二十面相との対決に代表されるように、ある種の様式美、いわば「型」が確立されていました。それはそれで非常に面白いのですが、長く続けばマンネリ化するという側面も持っています。本作で明智小五郎の出番が極端に少ないのは、乱歩自身がそのことを意識し、探偵役の活躍に頼らない新しい形のミステリを模索しようとした結果ではないでしょうか。
その試みの中で、乱歩が光を当てたのが、犯人である北村克彦の心理描写です。本作は、犯人の視点から物語が進む、いわゆる倒叙形式に近い構成を取っています(完全に倒叙ではありませんが)。これにより、読者は北村の犯行に至る動機、犯行後の動揺、偽装工作中の焦り、そして成功後の安堵と忍び寄る不安といった、心の動きを克明に追体験することになります。
特に印象的なのは、衝動的に股野を殺してしまった後の北村の心理です。彼は倫理的な呵責よりも、いかにして自分の犯行を隠蔽し、罰を逃れるかという利己的な計算に心を支配されていきます。そして、偽装工作が成功した後も、完全な安心感を得ることはできず、常に発覚の恐怖に怯え、次第にあけみとの間にも疑心暗鬼が生じていきます。この、決して英雄的でもなければ、極悪非道でもない、どこにでもいるような弱い人間の、等身大の姿が、実に生々しく描かれているのです。
そして、私がこの作品で最も心を揺さぶられたのが、ある情景描写です。股野を殺害した後、北村が夜道を歩く場面。引用してみましょう。
どぶ川が月の光をうけて、キラキラと銀色に光っていた。海の底のような静けさだ。向うに立っている何かの木の丸い葉もチカチカと光っていた。こちら側の生垣のナツメの葉もチカチカと光っていた。
(なんて美しいんだろう。まるでお伽噺とぎばなしの国のようだ)
こんなくだらない街角を、これほど美しく感じたのは、はじめての経験だった。
彼は口笛を吹き出した。偽装のためではない。なぜか自然に、そういう気持になった。口笛の余韻が、月にかすむように、空へ消えて行った。
人を殺めた直後であるにも関わらず、北村は目の前の光景に、これまでにない美しさを見出します。どぶ川でさえ、月の光を浴びれば銀色に輝く。ありふれた街角が、お伽噺の国のように見える。この感覚は、一体どこから来るのでしょうか。罪の意識からの逃避でしょうか、それとも極度の緊張状態が生み出した一時的な昂揚感でしょうか。
ここで、少し話が逸れますが、歌人の岡井隆氏のある短歌を思い出します。「つきの光に花梨かりんが青く垂れてゐる。ずるいなあ先に時が満ちてて」。この歌の後半、「ずるいなあ先に時が満ちてて」という言葉は、常に過去の後悔や未来への不安と共に生き、今この瞬間を完全には生きられない私たち人間が、圧倒的な「現在」の美しさや充実に直面した時の、ある種の戸惑いや羨望を表しているように私には思えます。
私たちは、普段、「現在」という瞬間を意識せずに生きています。むしろ、過去を反省し、未来に備えることで、現在の瞬間をやり過ごしていると言えるかもしれません。しかし、時として、月の光に照らされた花梨のように、あるいは銀色に光るどぶ川のように、圧倒的な「今」が目の前に現れることがあります。それは日常から切り離された、孤立した瞬間であり、美しくもあり、同時に少し恐ろしくもあります。生と死の境界が曖昧になるような、特別な時間です。
北村が感じた美しさも、これに近いものではないでしょうか。殺人を犯したという極限状況が、彼を日常から切り離し、普段は見過ごしてしまうような世界の美しさに気づかせた。それは祝福とも呪いともつかない、強烈な「現在」の体験だったのかもしれません。しかし、人間は長くその状態に留まることはできません。
「(だが待てよ。もう一度検算して見なければ……) 克彦はたちまち現実に帰って、不安におののいた。」
美しい情景に心を奪われたのも束の間、北村はすぐにアリバイ工作の心配という「現実」に引き戻されます。過去の犯行と未来の発覚への不安が、再び彼の心を支配します。この落差こそが、人間の、そして人生の本質なのかもしれません。私たちは生き続けるために、圧倒的な現在から目をそらし、過去と未来の間を行き来する。しかし、時折訪れる、息をのむような「今」の煌めき。その一瞬の輝きが、この「月と手袋」という作品には、見事に捉えられているのです。
この、トリックの奇抜さとは裏腹の、繊細で美しい人間心理と情景の描写こそが、私がこの作品を気に入っている最大の理由です。探偵小説としての完成度を問われれば、他の乱歩作品、例えば「何者」や「凶器」などに軍配が上がるかもしれません。しかし、「月と手袋」には、それらの作品とは異なる、独特の文学的な深みがあるように感じられます。
ちなみに、本作で用いられたトリックの一部、特に偽の手袋を使った部分は、戦時中に書かれた乱歩の長編小説「偉大なる夢」からの流用であると言われています。「偉大なる夢」も、戦争という特殊な状況下で書かれたためか、いくつかの制約が見られる作品ですが、それでも一つの物語として成立しており、乱歩の創作への情熱を感じさせます。「月と手袋」のトリックの奇抜さも、もしかしたらそうした過去のアイデアを再利用しつつ、戦後の新しい読者に驚きを与えようとした、乱歩なりのサービス精神の表れだったのかもしれません。
「月と手袋」は、ミステリとしての評価は分かれるかもしれませんが、人間の弱さや脆さ、そして日常の中に潜む非日常的な美しさを描いた作品として、読む価値のある一編だと私は思います。トリックの荒唐無稽さに目くじらを立てるのではなく、その奥にある人間のドラマや情景の描写に目を向ければ、きっと新たな発見があるはずです。
まとめ
この記事では、江戸川乱歩の小説「月と手袋」について、物語の結末を含む詳しい流れと、それに対する私の考えをお話しさせていただきました。本作は、トリックの奇抜さや実現性について、しばしば議論の的となる作品です。確かに、変装や偽の手袋を用いた偽装工作は、現実的に考えると無理があると感じられるかもしれません。
また、事件解決の決め手が探偵の推理ではなく、盗聴による自白である点も、本格ミステリを期待する読者にとっては、物足りなさを感じる要因かもしれません。名探偵・明智小五郎の活躍が見られないことも、シリーズのファンにとっては残念な点でしょう。
しかし、そうした点を差し引いても、この作品には独特の魅力があります。それは、犯人である北村克彦の、揺れ動く心理の丁寧な描写です。衝動的な犯行から、保身のための偽装工作、そして共犯者との間に生まれる疑心暗鬼に至るまで、決して特別ではない、一人の弱い人間の姿がリアルに描かれています。
そして何より、私が感銘を受けたのは、殺害直後の北村が目にする夜の情景の美しさです。極限状況の中で、ありふれた街角が非日常的な輝きを放つ瞬間。それは、人間の生と死、日常と非日常が交錯する、忘れがたい場面として心に残ります。トリックの評価とは別に、こうした文学的な深みこそが、「月と手袋」が読み継がれる理由なのかもしれません。






































































