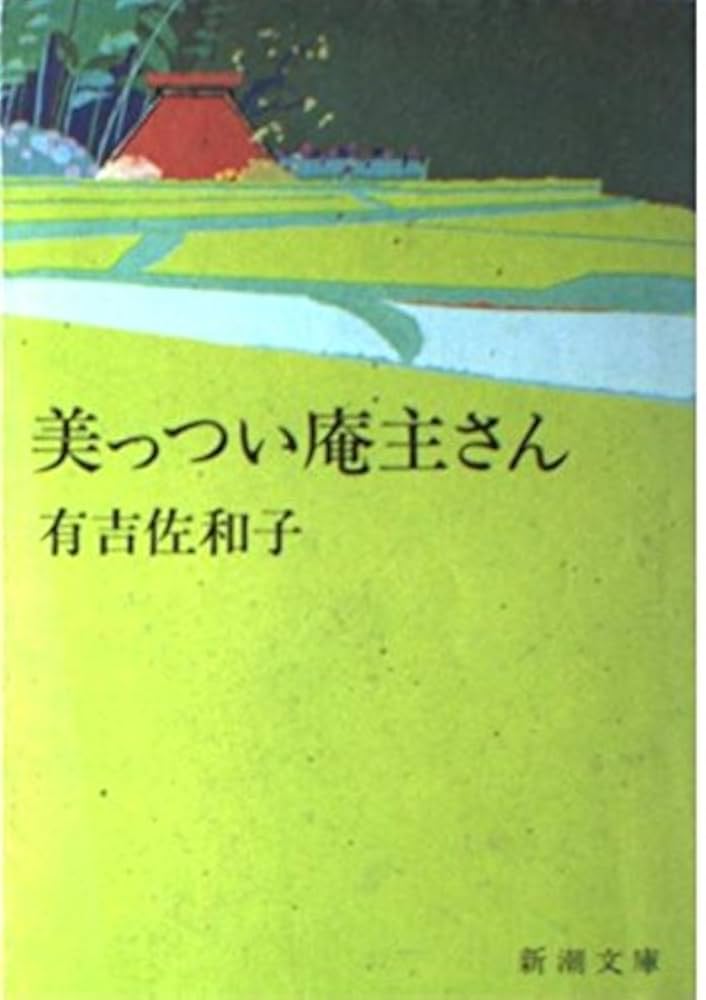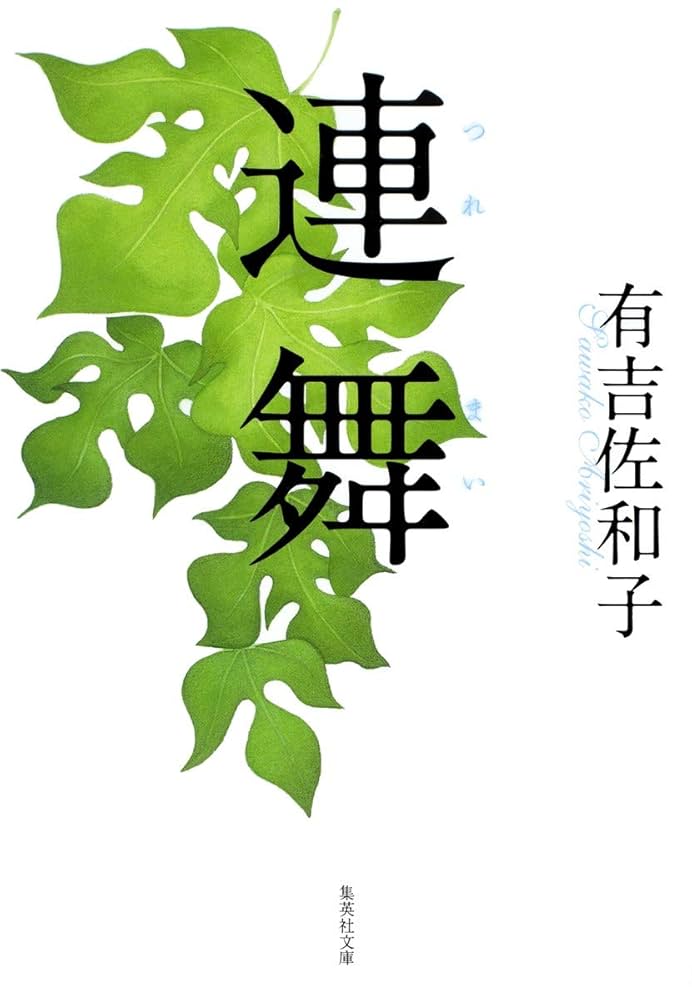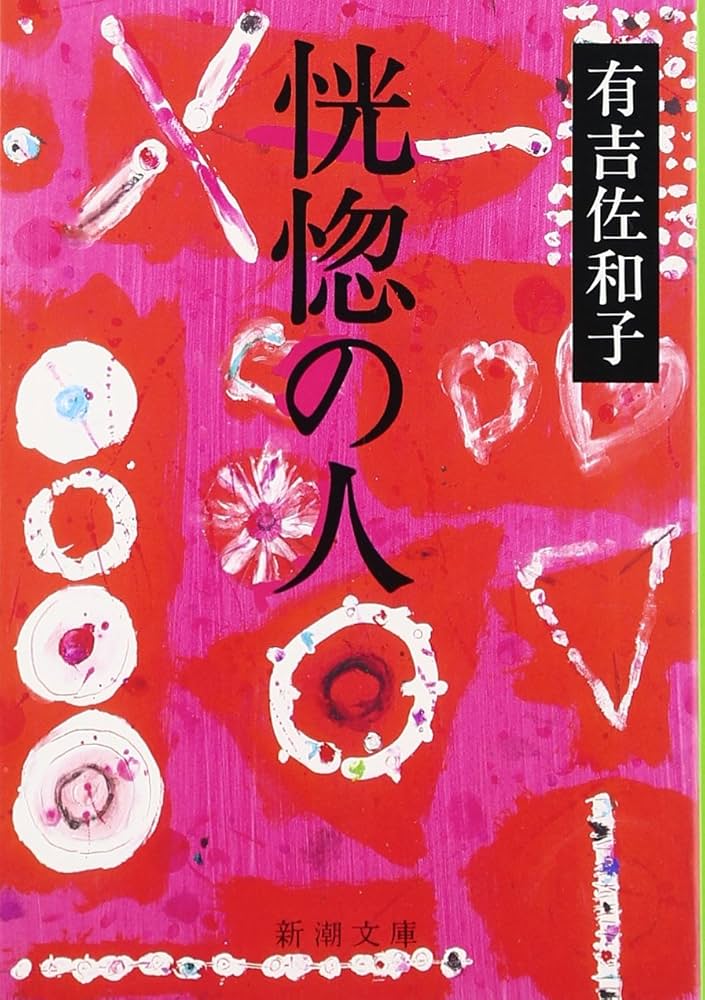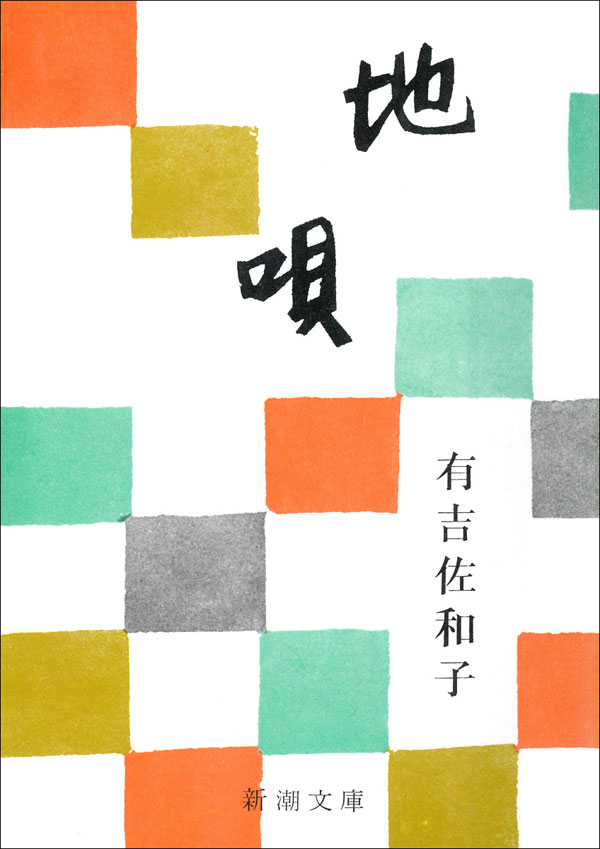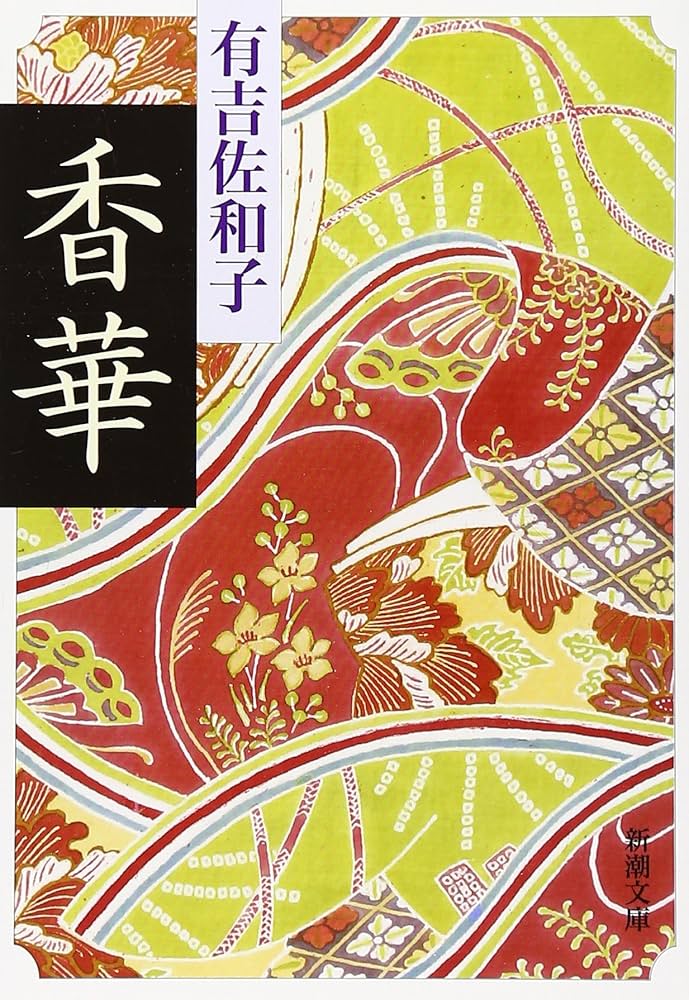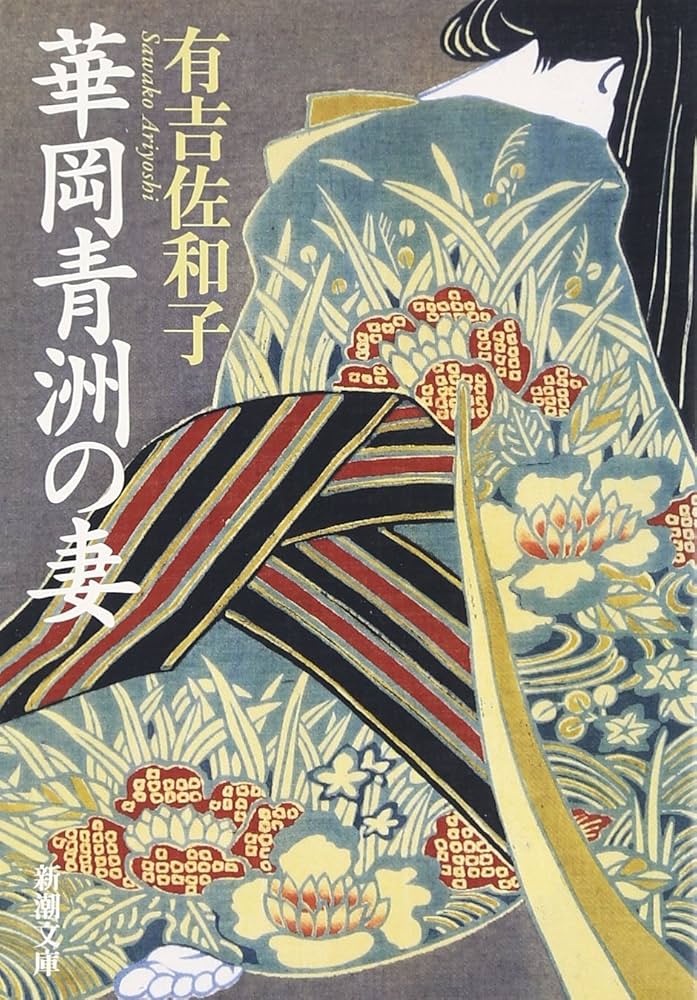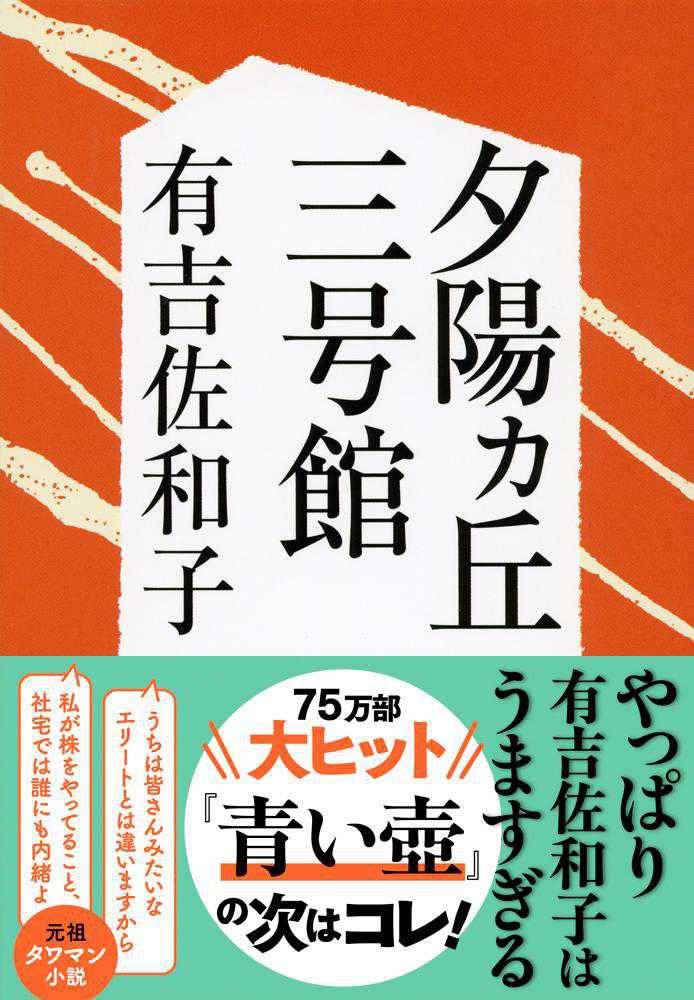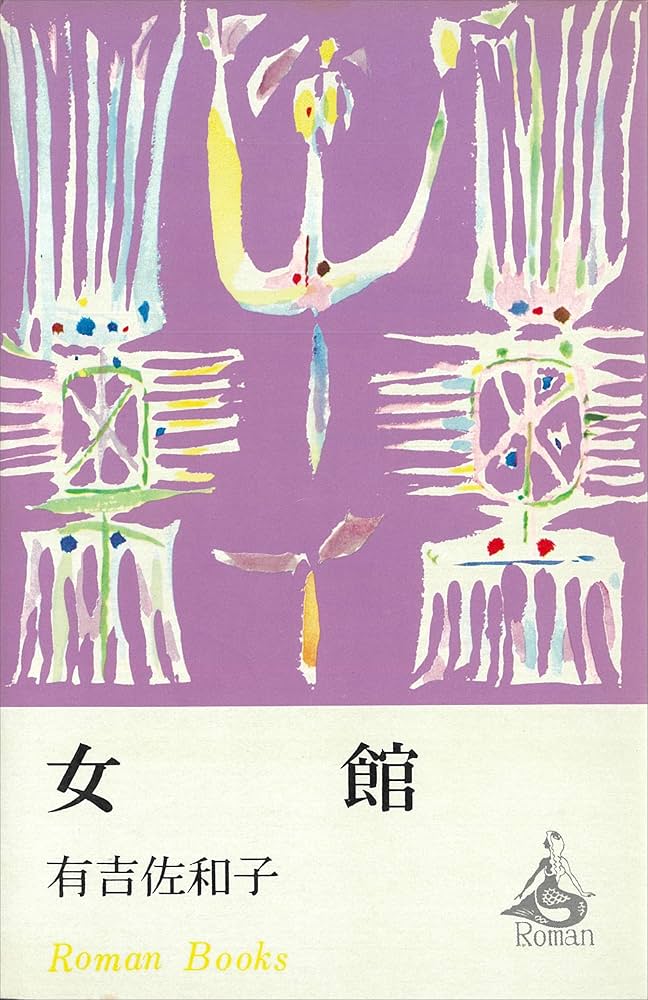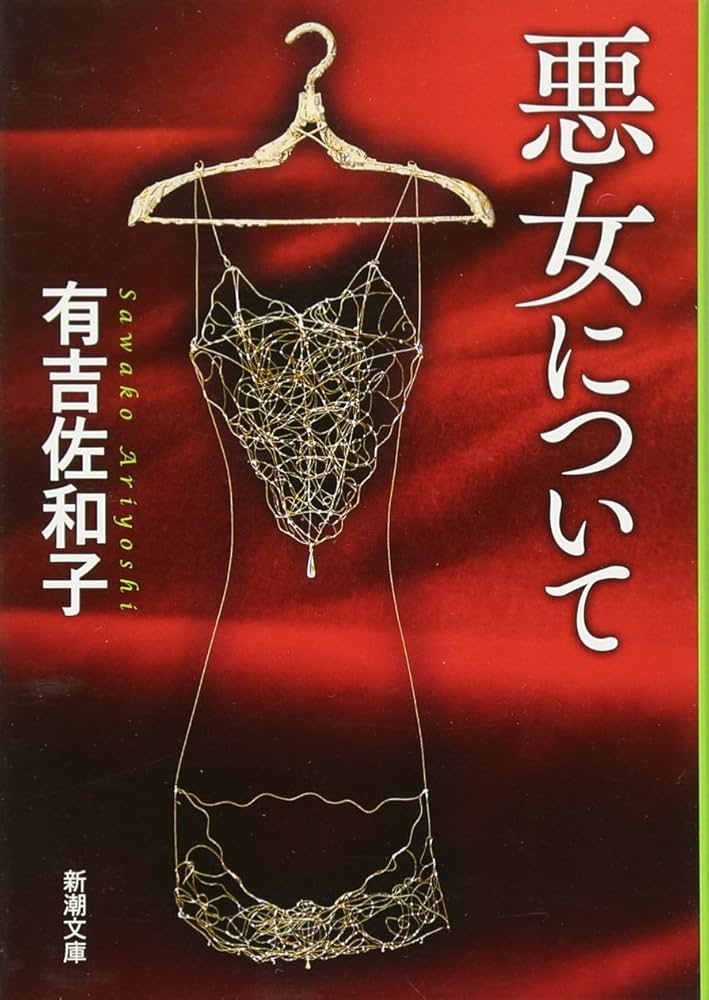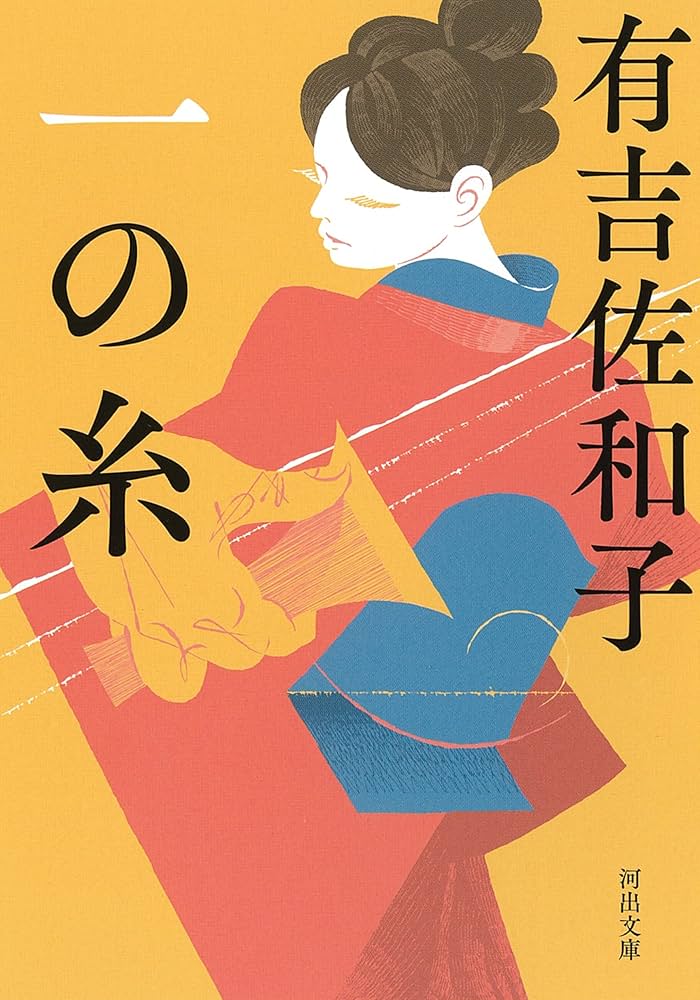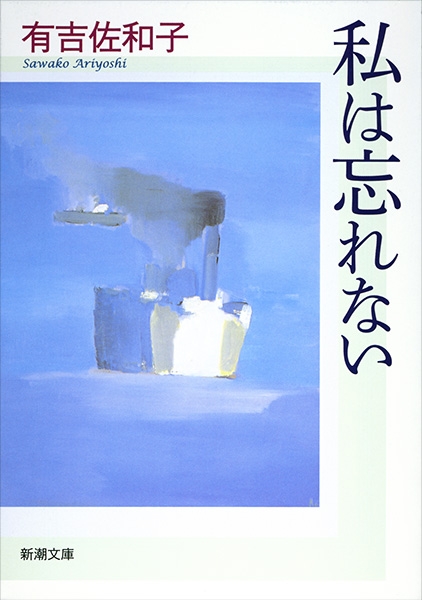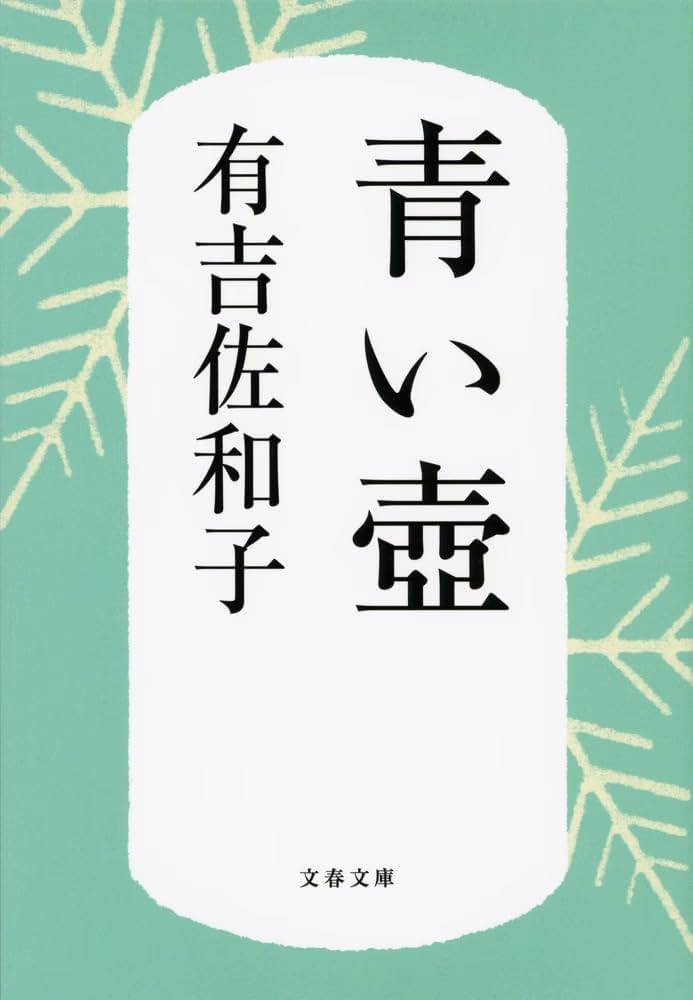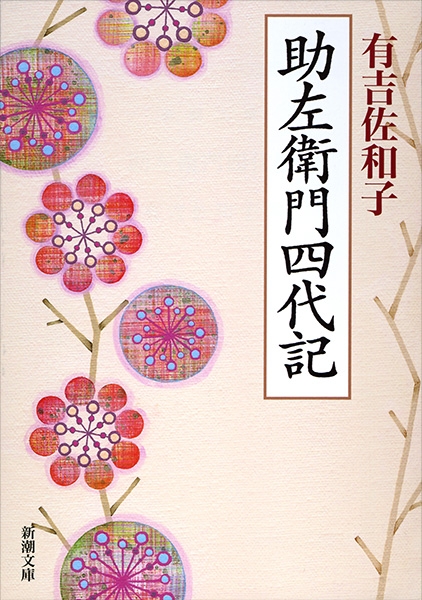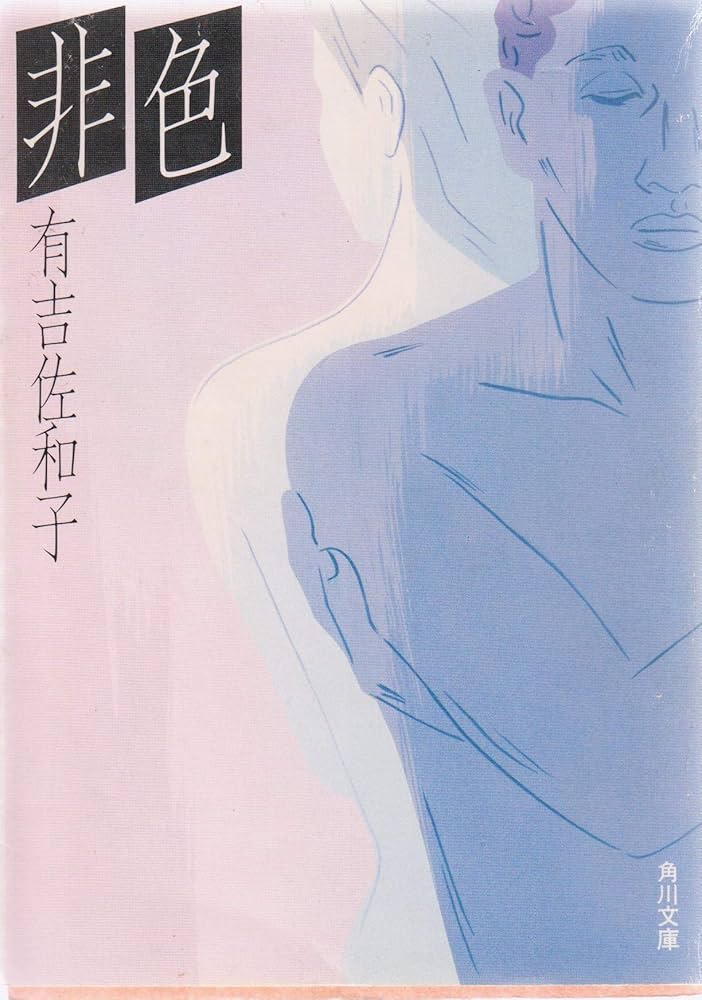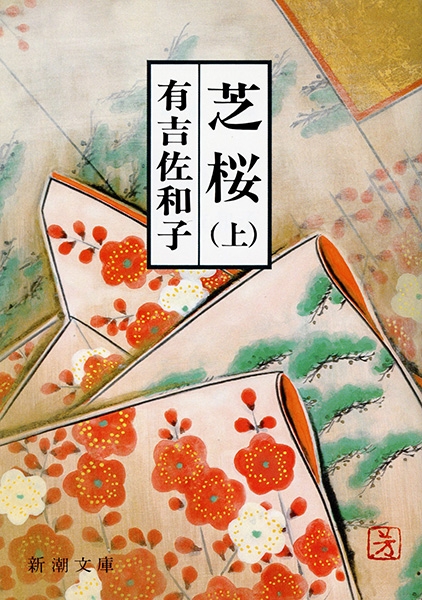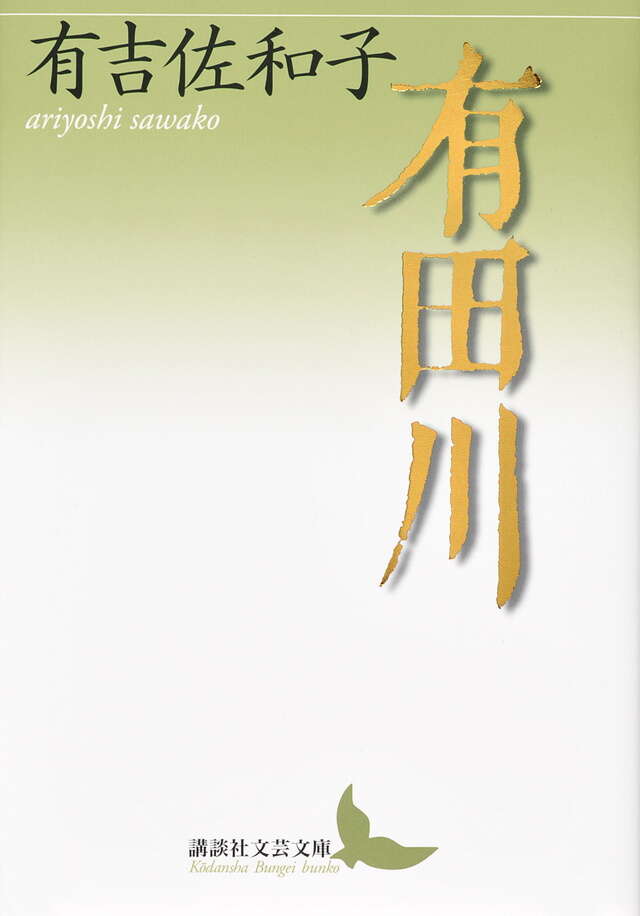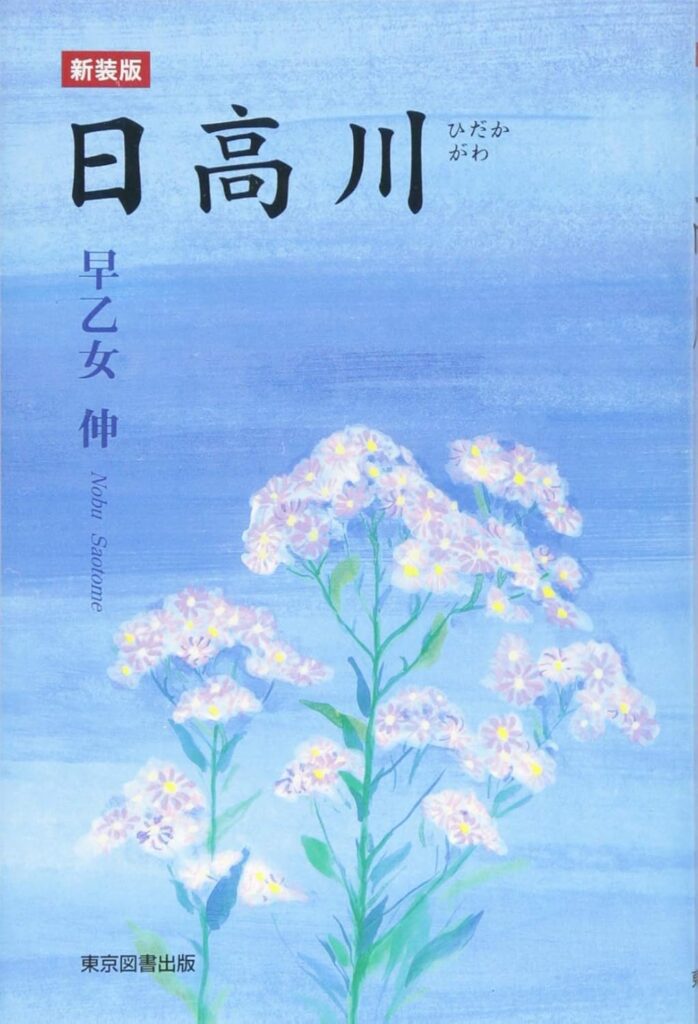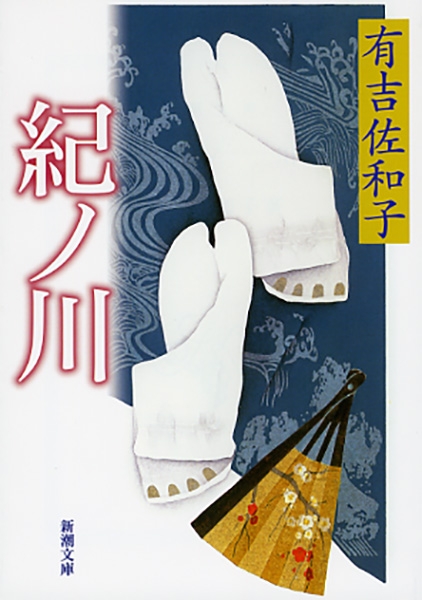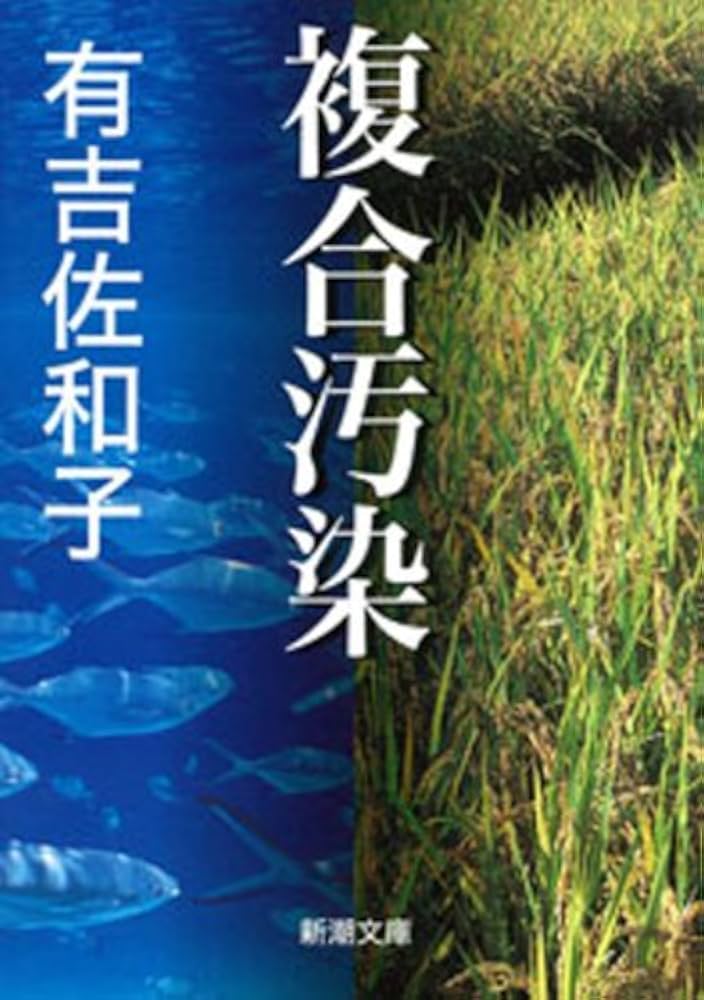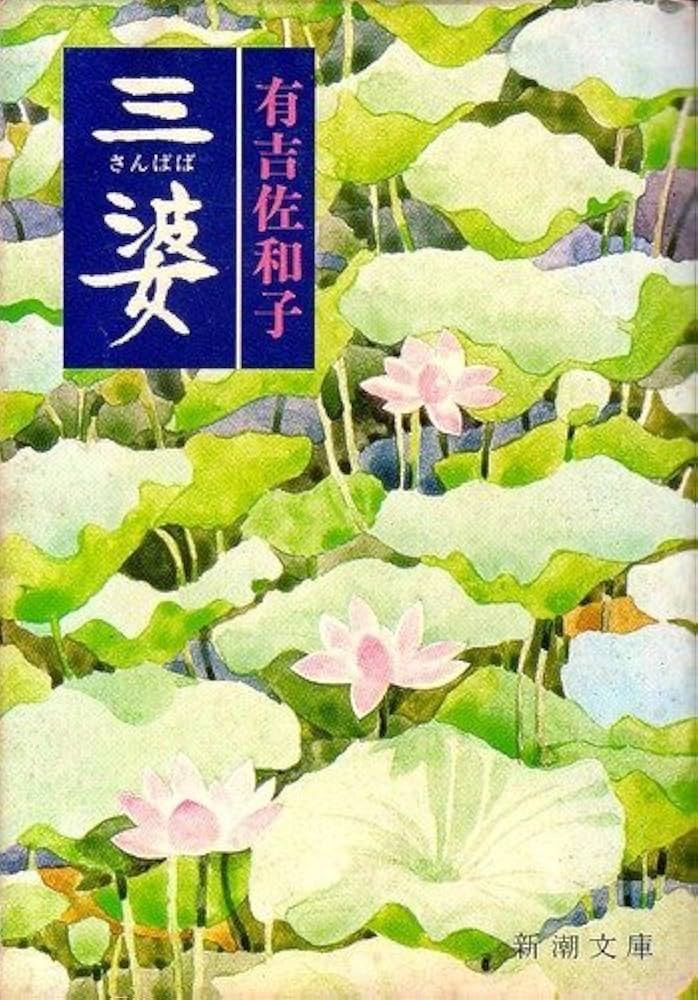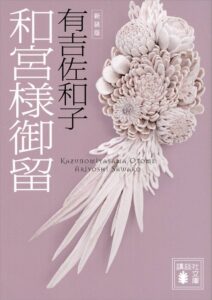 小説『和宮様御留』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説『和宮様御留』のあらすじをネタバレ込みでご紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
有吉佐和子さんの『和宮様御留』は、歴史の表舞台に立つ人物の裏に隠された、もう一つの物語を鮮やかに描き出しています。幕末という激動の時代、公武合体の象徴として降嫁した和宮親子内親王。その華やかな歴史の裏側で、もし全く別の運命が紡がれていたとしたら——そんな大胆な仮説が、本書の根幹をなしています。
本書は、単なる歴史の解説ではありません。名もなき女性たちの苦悩や葛藤、そして時代に翻弄されながらも失われなかった矜持が、読み手の心に深く響きます。作者の緻密な取材と、それを土台にした豊かな想像力が、私たちを幕末の京都、そして江戸へと誘います。
歴史的事実と、そこに息づく人間の感情が織りなす物語は、時に切なく、時に胸を締め付けるほどに悲劇的です。それでも、登場人物たちがそれぞれの宿命と向き合う姿は、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれるでしょう。
『和宮様御留』は、一度読み始めたら止まらない、そんな魅力に満ちた一冊です。歴史小説が好きな方だけでなく、人間ドラマに心を揺さぶられたい方にも、ぜひ手に取っていただきたい作品だと私は感じています。
『和宮様御留』のあらすじ
有吉佐和子さんの『和宮様御留』は、激動の幕末、公武合体の一環として徳川家へ降嫁することになった孝明天皇の妹、和宮親子内親王の物語を軸に展開します。しかし、この物語には歴史の裏側を覗き見るような、ある大胆な仕掛けが隠されています。それは、「和宮替え玉説」という、まさに本作の肝となる設定です。
物語の始まりは、京都の町方で捨て子として育ち、和宮の生母である観行院の実弟、橋本実麗邸で下女として働く少女フキです。快活で明るい性格のフキは、自分の境遇を淡々と受け入れながら日々を過ごしていました。一方、頑なな性格で降嫁を強く拒んでいた和宮に代わり、観行院は娘を守るため、ある重大な決断を下します。
それが、フキを和宮の「替え玉」として立てるという計画です。フキは自分がなぜそのような境遇に置かれるのかを知らされないまま、ある日突然、和宮の居室に潜むことになります。そして、宮中での厳しい生活や作法を学び始め、本来の快活さを失っていきます。
東下への旅が始まると、フキは監視の目を逃れることができず、精神的に追い詰められていきます。慣れない環境と過酷な旅路の中で、フキの心は徐々に疲弊し、自身の正体に対する疑問と不安が募っていきます。物語は、そんなフキの心の変化と、迫りくる運命の行方を丁寧に描き出していきます。
『和宮様御留』の長文感想(ネタバレあり)
有吉佐和子さんの『和宮様御留』を読み終えて、まず感じたのは、歴史の表舞台の裏側に、これほどまでに人間ドラマが凝縮されていたのかという驚きでした。公武合体という大義のために翻弄された和宮親子内親王の降嫁。その史実の隙間に、「替え玉」という大胆な仮説を挿入することで、作者は私たちに、名もなき個人の悲劇と、それでも失われない人間の尊厳を深く問いかけてきます。
物語の主人公、フキの存在は、まさにその象徴と言えるでしょう。捨て子として育ち、己の身分も知らずに生きてきたフキが、ある日突然、国の命運を背負う皇女の身代わりとなる。この理不尽なまでの運命の変転は、読み手の胸に深く突き刺さります。当初の快活で明るい性格が、宮中での厳しい生活、そして替え玉としての重圧によって徐々に陰りを見せていく様は、読んでいて胸が締め付けられる思いでした。特に、少進がフキに課す宮仕えの作法や、文字の習得といった厳しい訓練の描写は、フキの精神的な負担がいかに大きかったかを物語っています。
そして、その重圧をさらに強めるのが、庭田嗣子や能登命婦といった女官たちの存在です。彼女たちがフキの正体を疑い、常に監視の目を光らせる様子は、フキの孤立感を際立たせ、読者である私たちも息苦しさを感じずにはいられませんでした。自分は偽物なのではないかという疑念に怯えながら生きるフキの心境は、まさに針のむしろに座るようなものだったに違いありません。明るかったフキの眼差しから光が失われ、笑顔が消え去っていく描写は、言葉にならない悲しみを呼び起こします。
江戸への東下という旅路は、フキにとって肉体的にも精神的にも限界を試されるものでした。慣れない長旅、食欲の減退、そして心を許していた少進が同行しないことへの不安。周囲の女官たちが旅慣れず、互いに神経質になっている様子も、フキへの配慮がまったくない状況を浮き彫りにしています。この過酷な状況下で、フキがどれほどの孤独と絶望を感じていたかと思うと、胸が潰れるような思いがしました。
物語のクライマックス、板橋宿でのフキの叫びは、まさに圧巻でした。「あて、宮さんやおへん」。この一言に、フキがそれまで抱え込んできた全ての苦悩、そして自分自身が何者であるのかという真実が凝縮されています。この瞬間、フキは自身の正体を一切知らされていなかったという事実が明かされ、その衝撃からついに正気を失ってしまうのです。読み手としては、フキが自分自身の真実に辿り着く瞬間の痛ましさに、ただただ言葉を失いました。
そして、岩倉具視によって新たな替え玉、宇多絵が用意される展開は、フキの悲劇をさらに際立たせます。フキは、自分の存在が、ただの大義のための道具でしかなかったという現実を突きつけられるわけです。そして、誰にも看取られることなく、ひっそりと横死したフキの最期は、物語全体を覆う悲劇性を決定づけるものでした。遺書もなく、事件性も定かでないまま消えていくフキの命は、歴史の闇に葬られた無数の名もなき人々の象徴であるかのようです。
しかし、物語はフキの死をもって終わりではありません。二度目の替え玉交代が成就し、史実通りの和宮の降嫁が暗示されることで、私たちは歴史の表舞台がいかにして作られていったのかという、ゾッとするような真実に直面させられます。1862年2月11日に行われた実際の婚儀の裏側で、このような陰謀と悲劇が繰り広げられていたかもしれないという作者の仮説は、歴史に対する新たな視点を与えてくれます。
登場人物たちのそれぞれの運命もまた、深く心に残ります。娘を守ろうとしたがゆえに、取り返しのつかない策を巡らせてしまった観行院の苦悩。権力と掟の間で葛藤しながらも、それぞれの役目を全うしようとする庭田嗣子や能登命婦らの複雑な心境。そして、若さゆえに大きな運命に巻き込まれていく宇多絵。彼ら一人ひとりが、時代の奔流の中でそれぞれの思いを抱え、変化していく姿が丁寧に描かれています。特に、フキの「あて、宮さんやおへん」という叫びが、周囲の「正常なる虚偽」と対比される描写は、真実と虚偽の境界線がいかに曖昧であるかを突きつけるかのようです。
作者の有吉佐和子さんは、この作品を通して「女性の立場から見た歴史の見直し」というテーマを私たちに提示しているように感じます。歴史は、往々にして権力者の視点、男性の視点から語られがちですが、本作は、その裏側で翻弄された女性たちの哀歓を活写しています。幻像と現実、個人と大義、真実と虚偽が複雑に絡み合う物語は、まさに有吉作品の真骨頂と言えるでしょう。
『和宮様御留』は、歴史小説としての面白さだけでなく、人間ドラマとしての深みも兼ね備えた作品です。幕末という激動の時代に生き、自らの運命に抗い、あるいは受け入れた人々の姿は、現代を生きる私たちにも多くの問いを投げかけます。歴史の陰に埋もれた悲劇と、それでも確かに存在したであろう人間の尊厳を、私たちはこの作品から学ぶことができるでしょう。何度読んでも、新たな発見と感動がある、そんな珠玉の一冊です。
まとめ
有吉佐和子さんの『和宮様御留』は、幕末の史実である和宮親子内親王の降嫁を題材にしながらも、「替え玉」という大胆な創作を織り交ぜた歴史小説です。この作品は、歴史の表舞台の華やかさとは裏腹に、その陰で繰り広げられたであろう人間ドラマ、特に名もなき女性たちの悲劇と葛藤を深く掘り下げています。
主人公のフキが、自らの意思とは関係なく和宮の身代わりとして重責を担わされ、過酷な運命に翻弄されていく様は、読み手の心を強く揺さぶります。フキの心の変化、そして「あて、宮さんやおへん」という魂の叫びは、虚偽に満ちた世界の中で、唯一真実を訴えかける痛ましい場面として深く印象に残ります。
物語全体を通して描かれるのは、大義のために個人が犠牲となる悲劇、そしてそれでも失われない人間の尊厳です。歴史的事実と作者の豊かな想像力が融合することで、私たちは幕末という時代に生きる人々の息遣いを肌で感じることができます。
『和宮様御留』は、単なる歴史物語としてだけでなく、人間の内面に迫る深遠なテーマを扱った作品としても、非常に読み応えがあります。歴史が好きな方はもちろん、人間の生き様や運命に思いを馳せたい方にも、自信を持っておすすめできる一冊です。