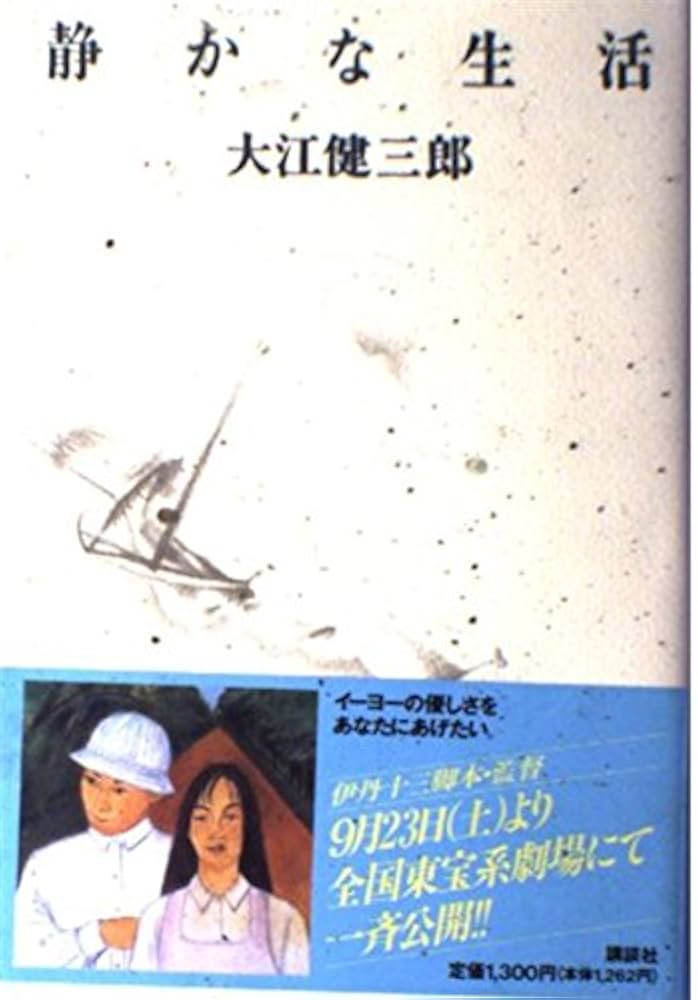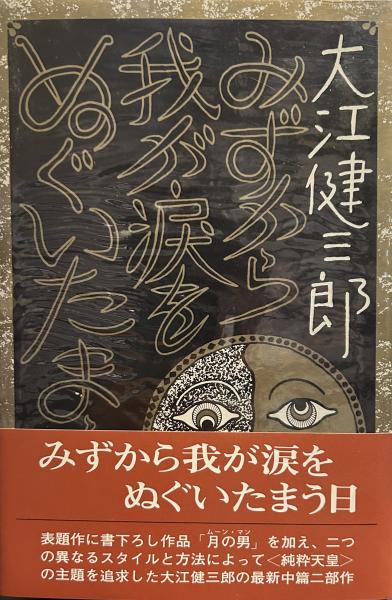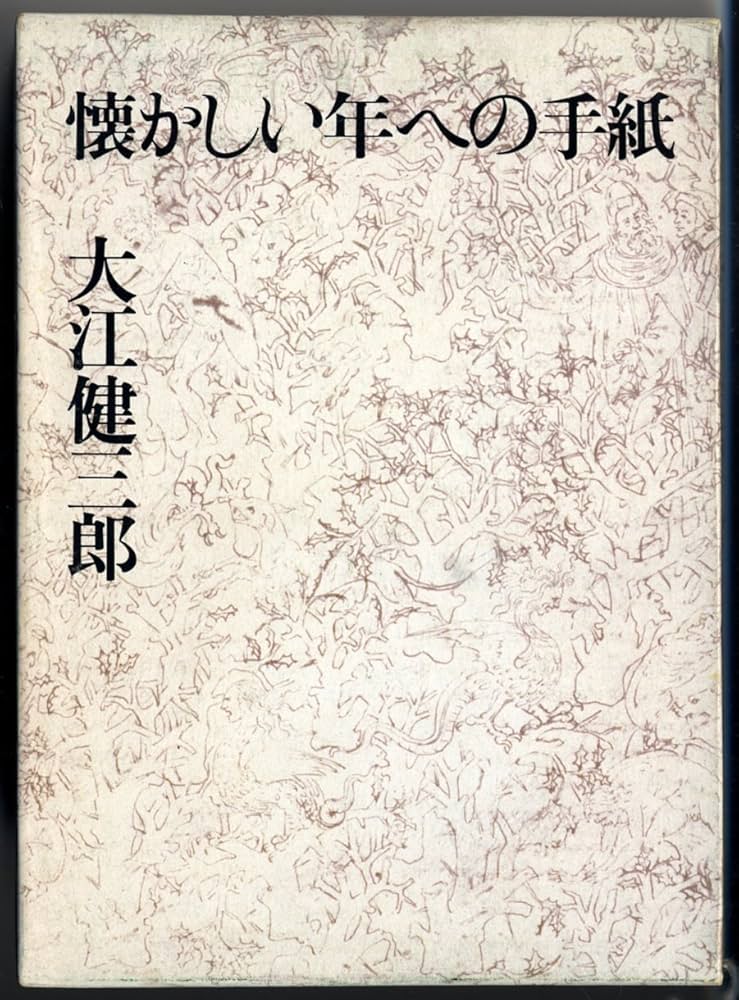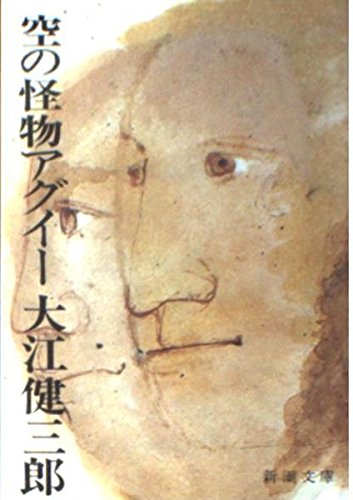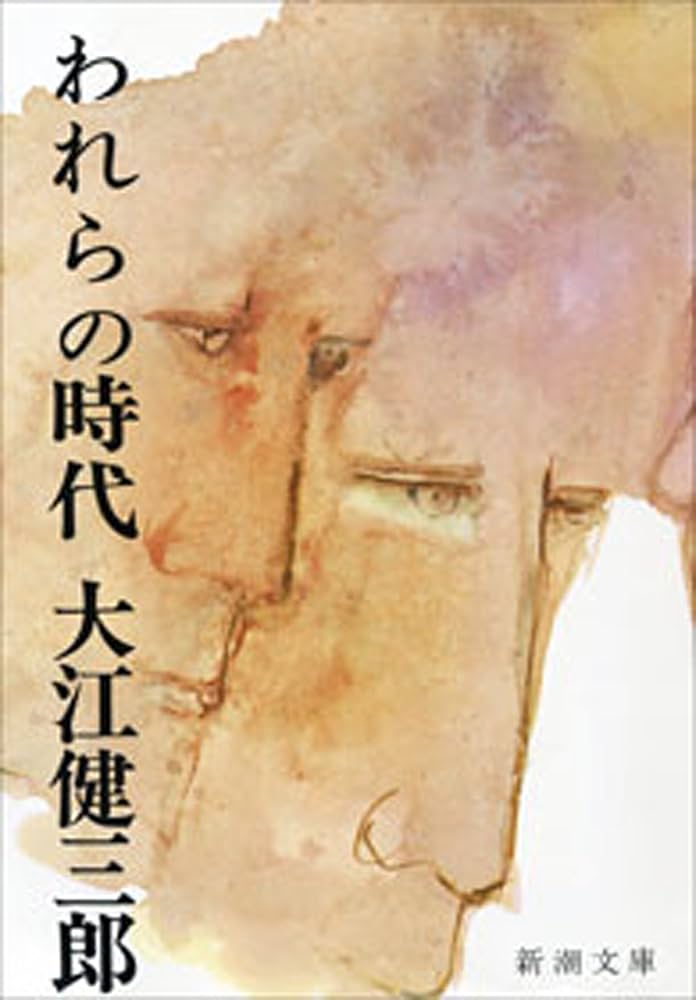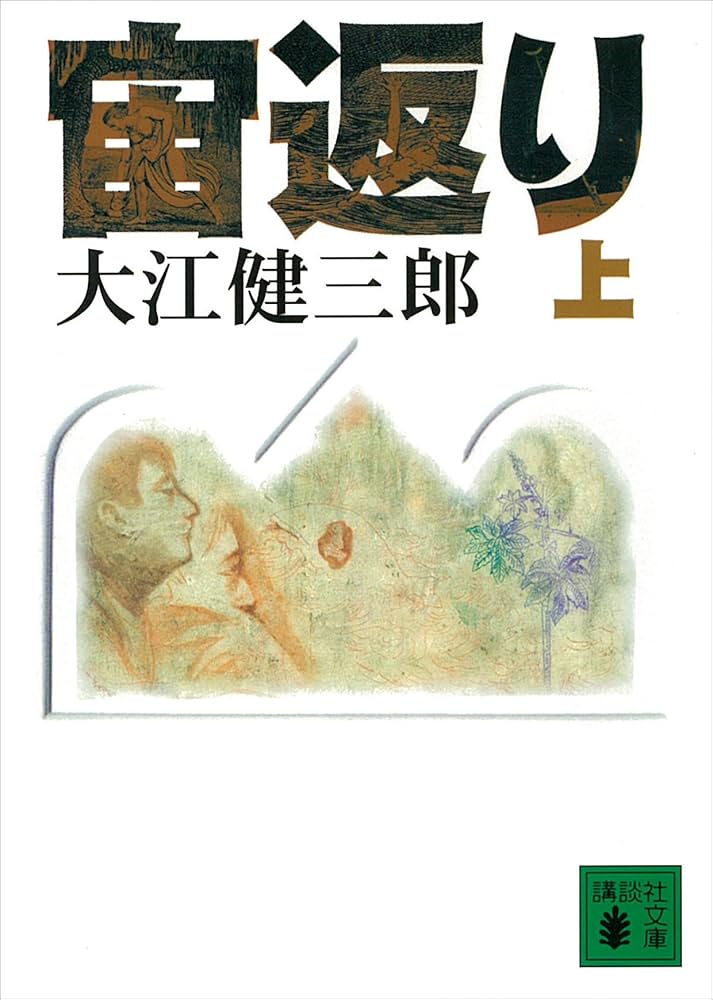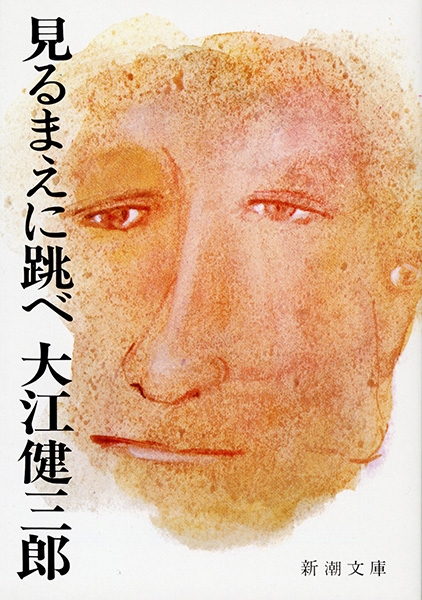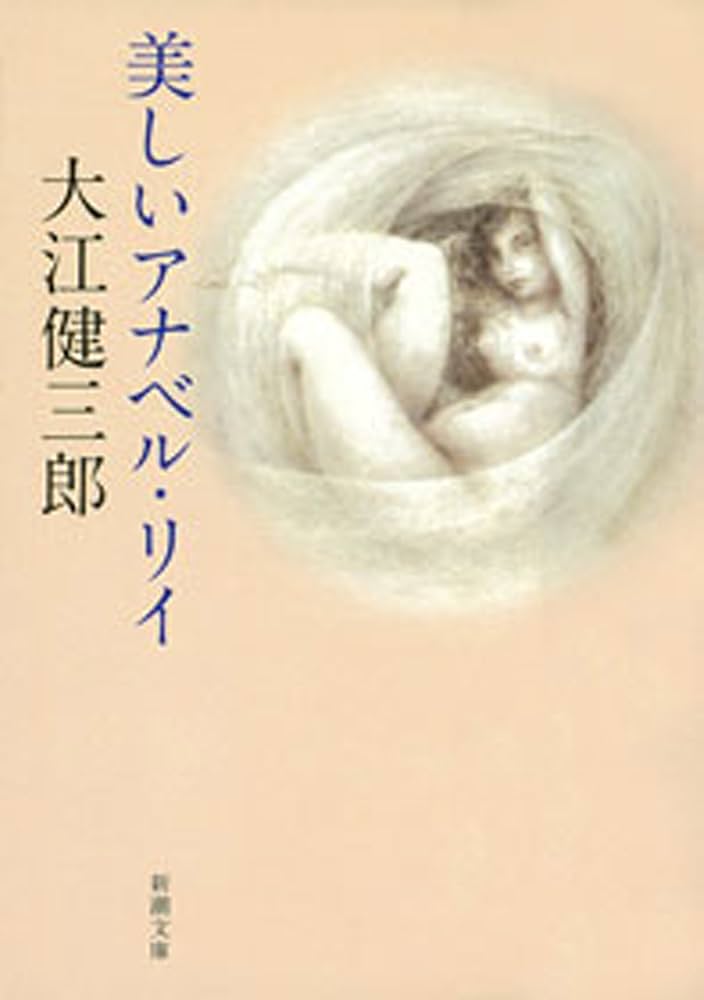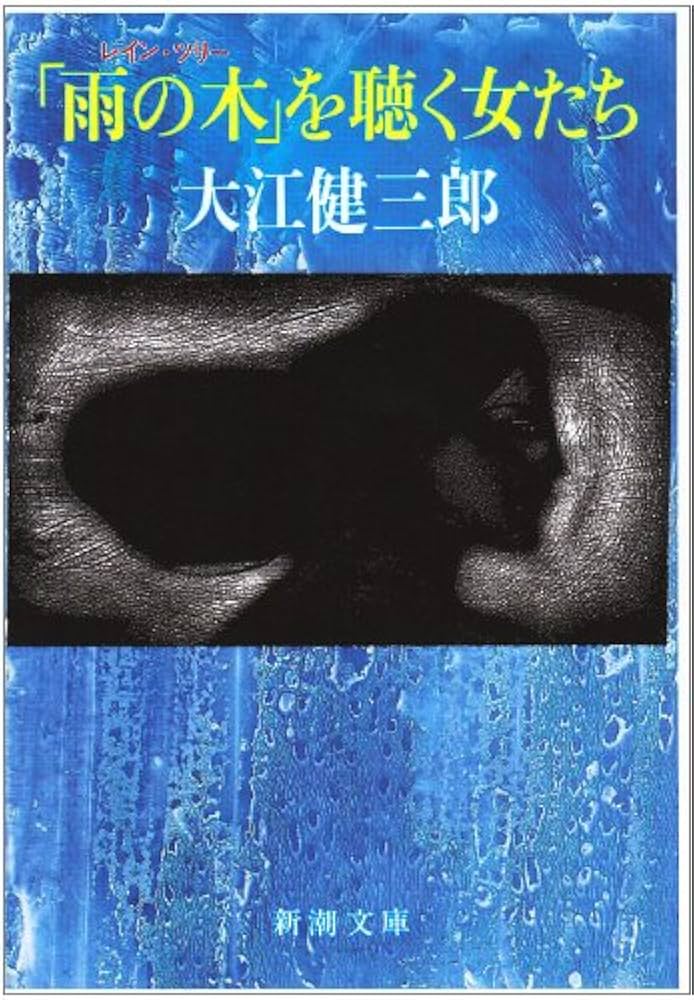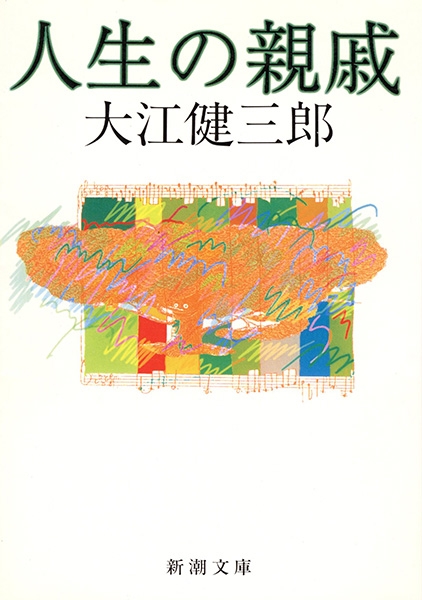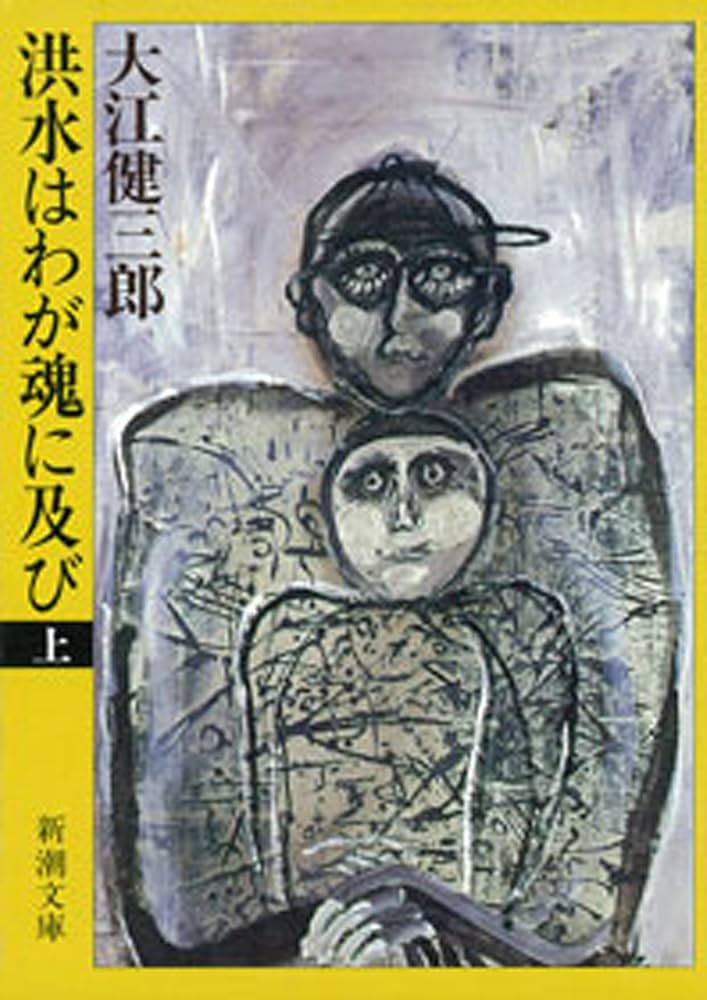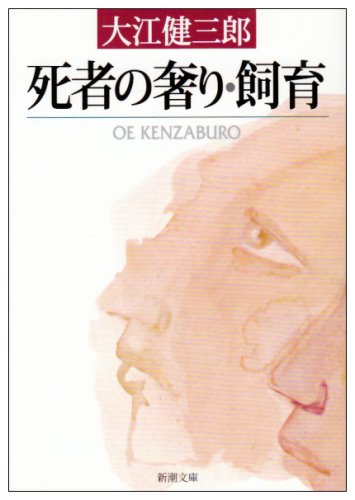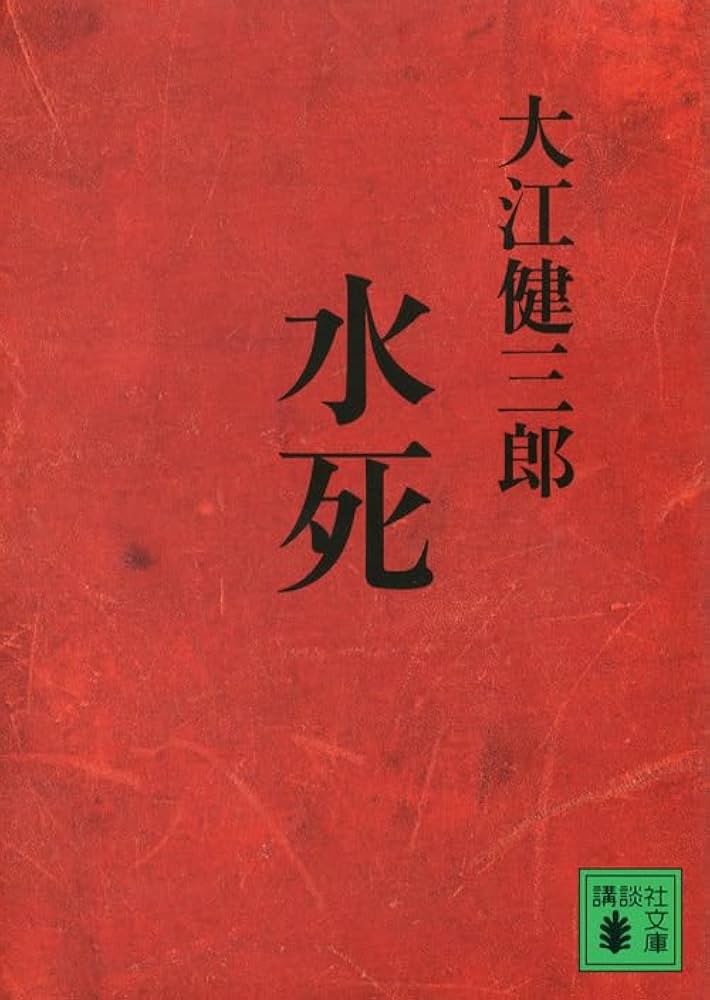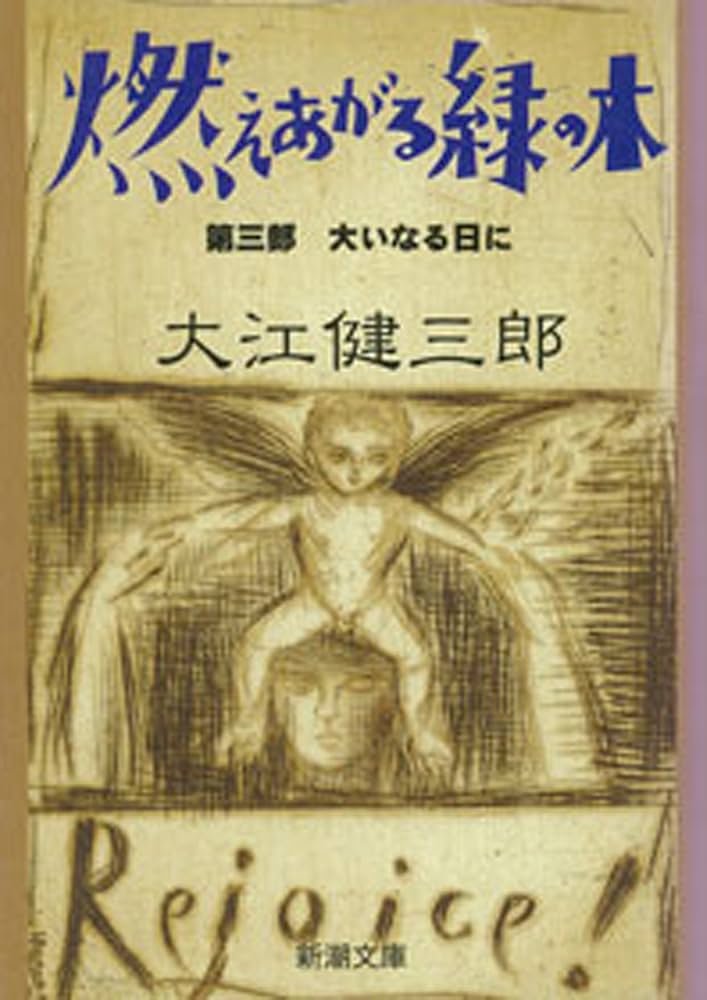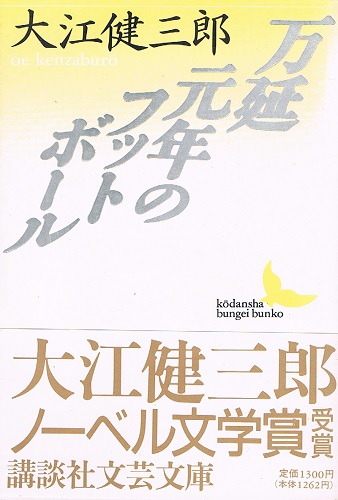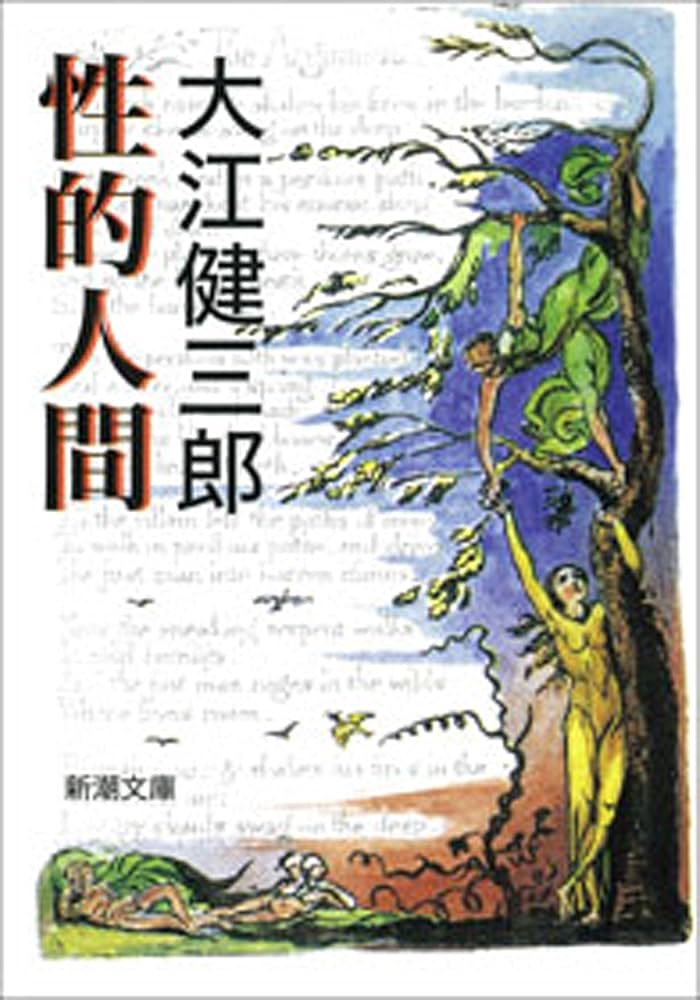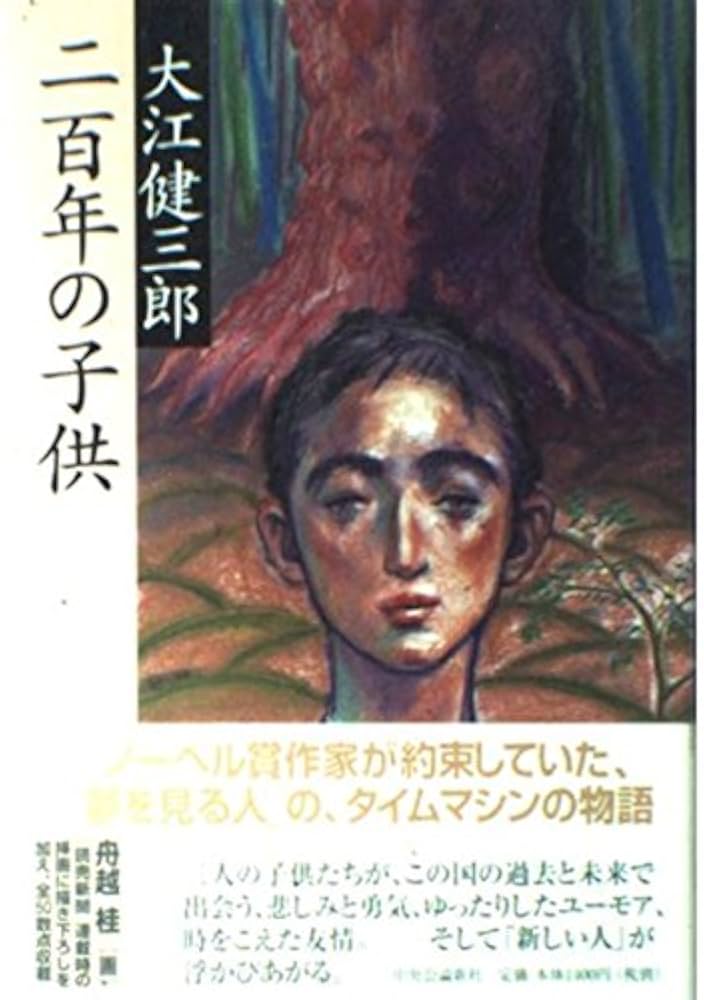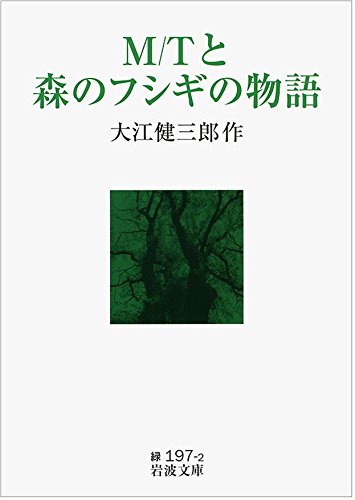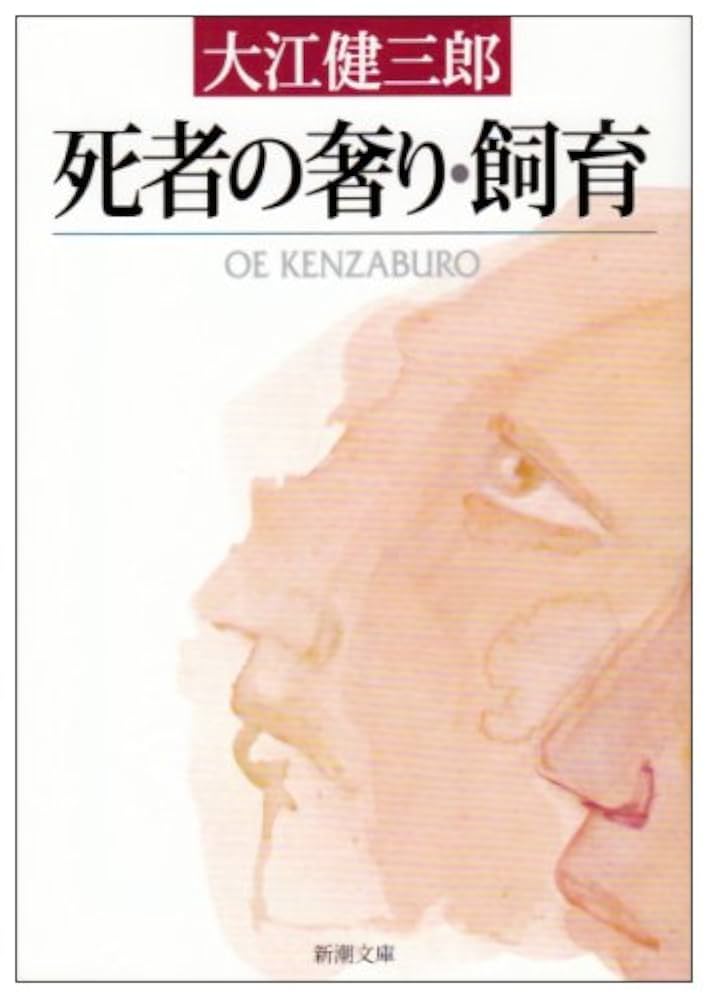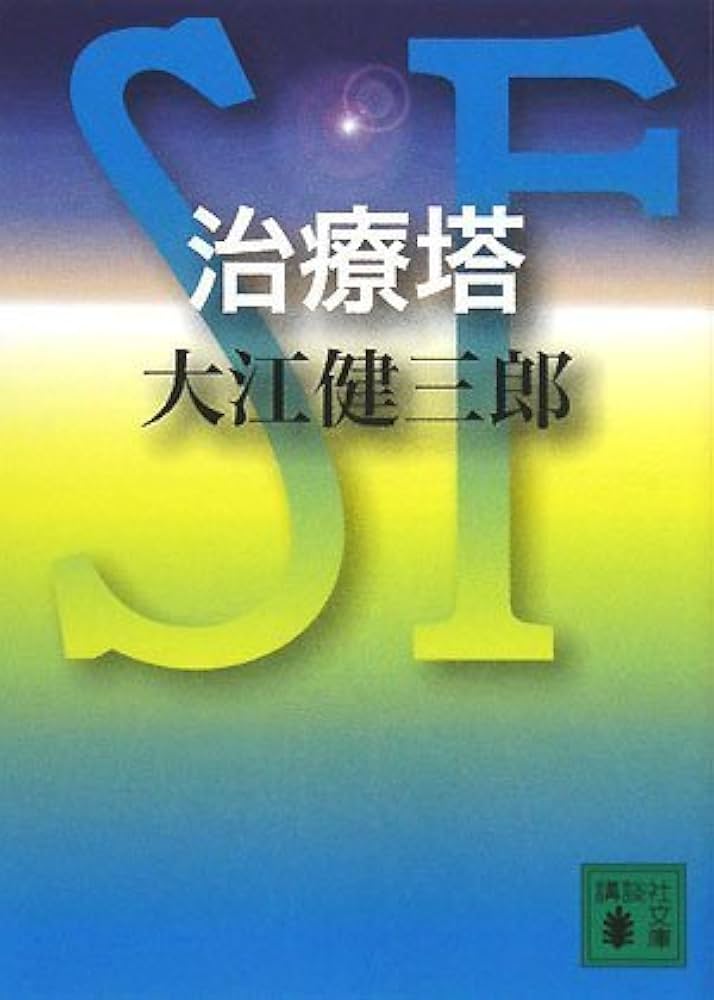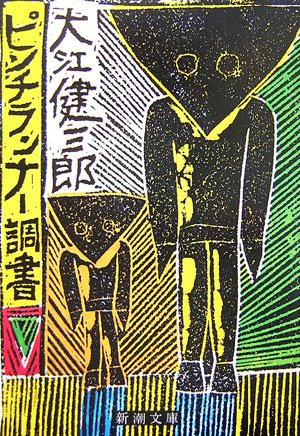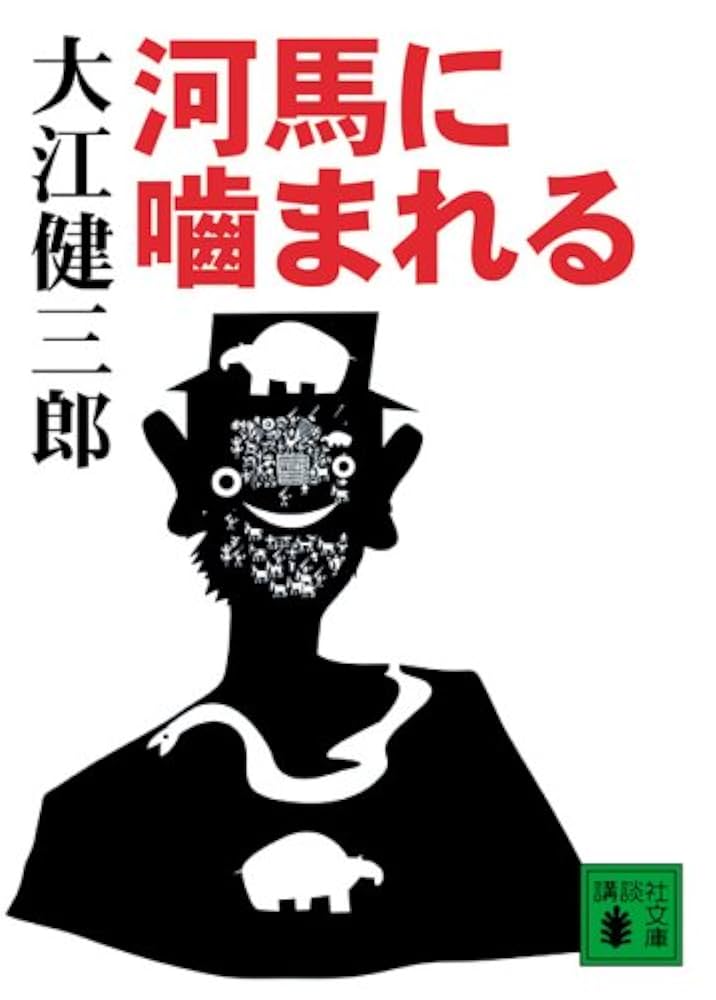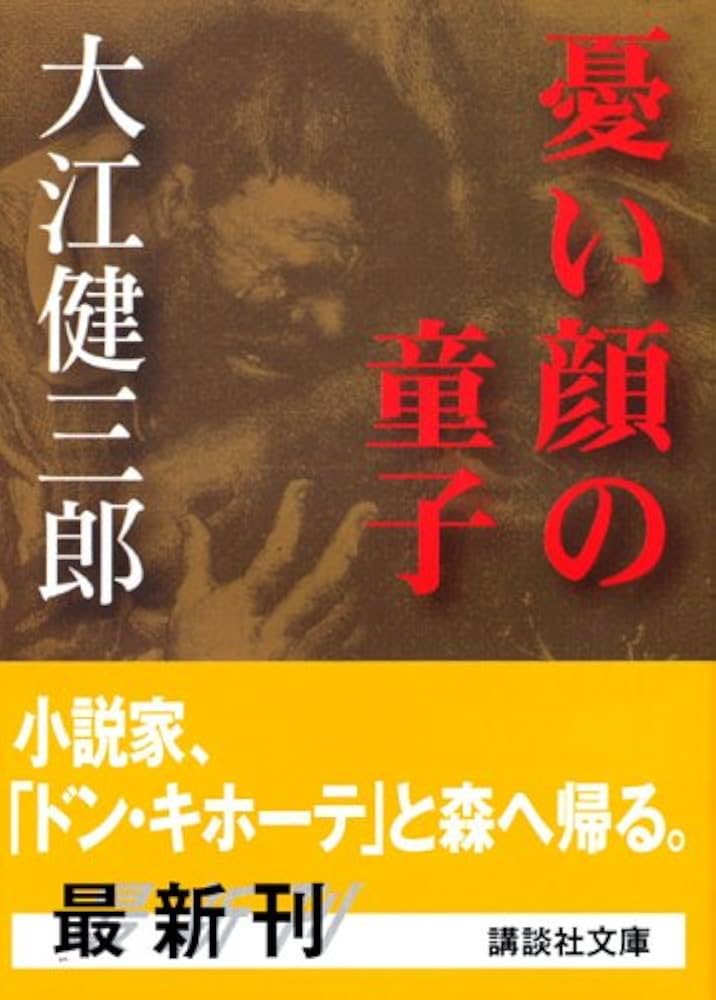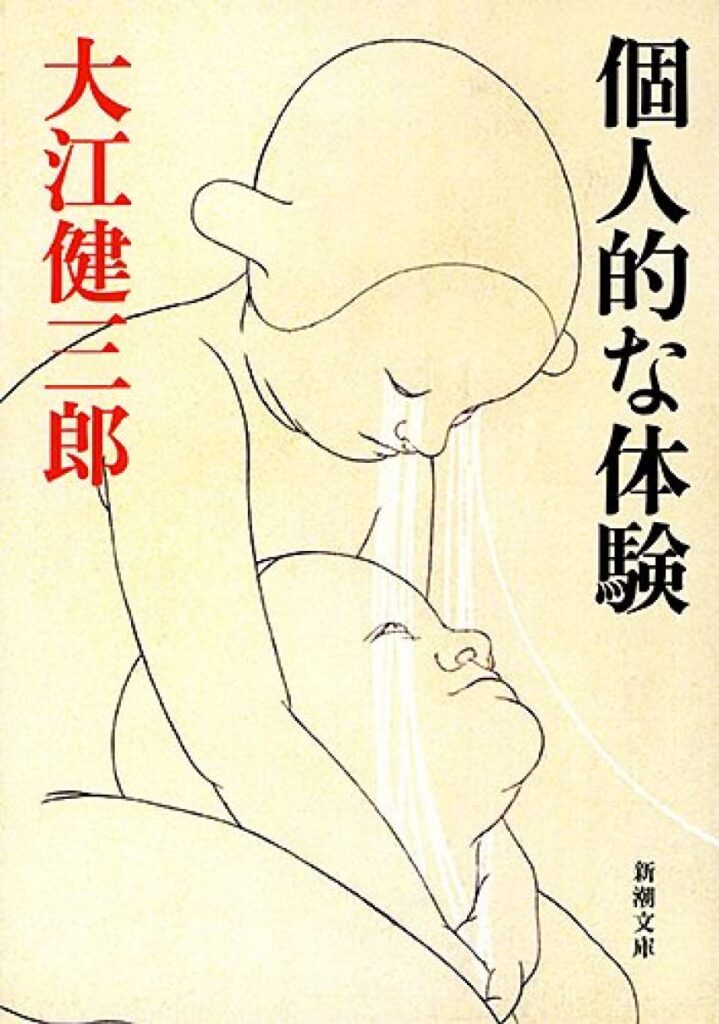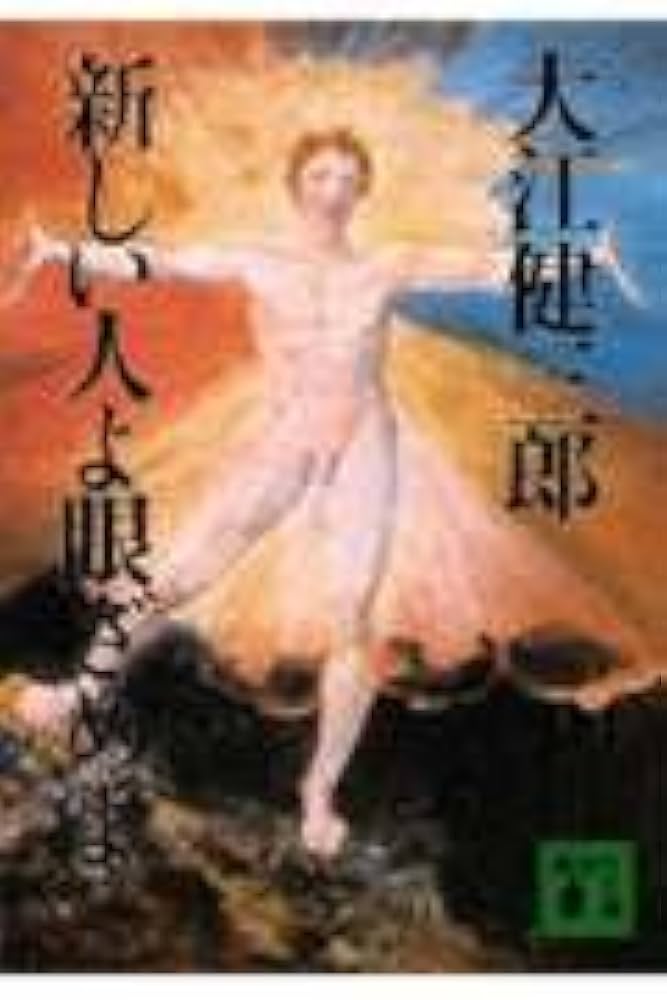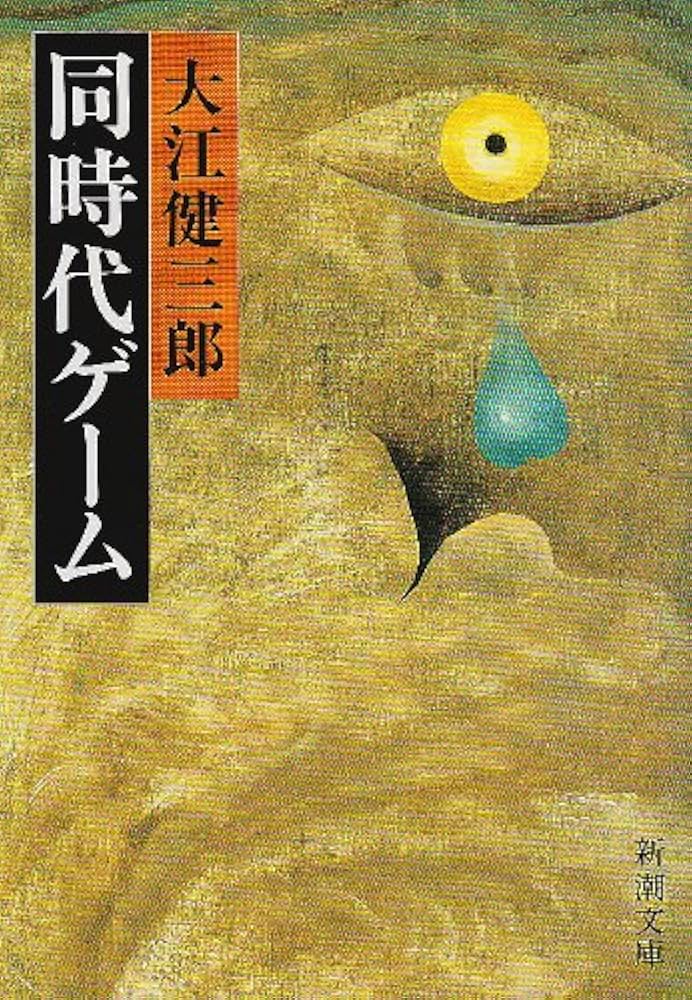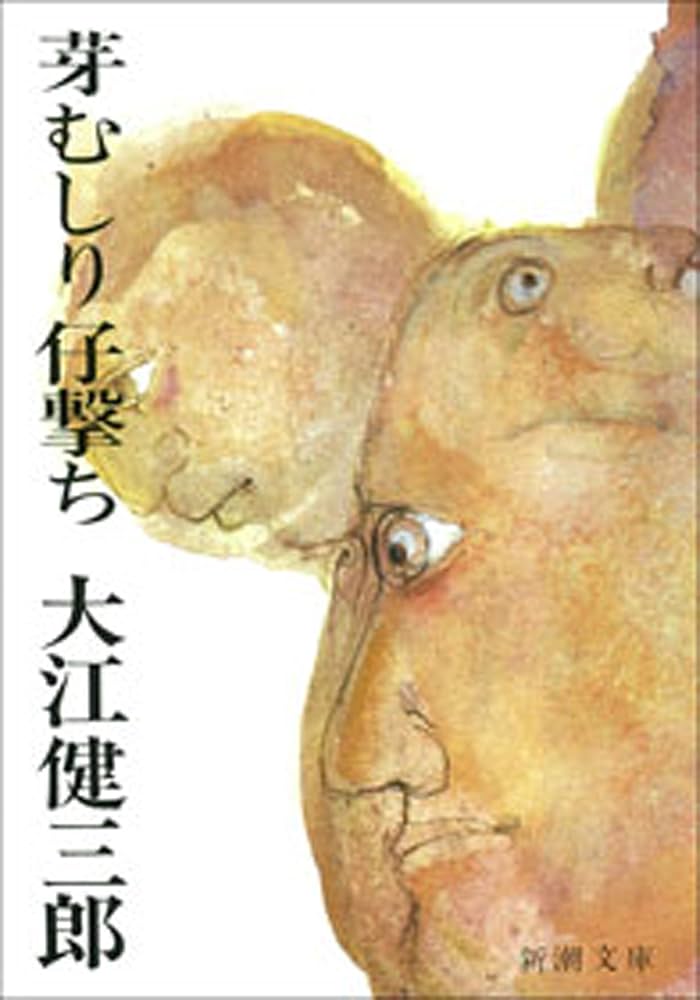小説「取り替え子」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この作品は、作者である大江健三郎氏の義兄であり、映画監督の伊丹十三氏の突然の死が色濃く反映された、極めて私小説的な物語です。親友であり義兄でもある人物の死という、あまりにも大きな喪失に直面した主人公が、いかにしてその死と向き合い、自らの魂を再生させていくのかが描かれます。
物語はスリリングな謎解きの要素を持ちながら、人間の内面の深い部分へと分け入っていきます。なぜ彼は死を選んだのか。彼が遺したテープに込められたメッセージとは何だったのか。主人公と共に、読者もまたその謎を追いかけることになるのです。この記事では、感動的な小説「取り替え子」の核心に触れつつ、その魅力をお伝えします。
この物語のタイトルである「取り替え子」とは、ヨーロッパの民間伝承に由来する言葉です。美しい赤ん坊が妖精によって醜い子供と取り替えられてしまうというこの伝承は、物語全体を貫く重要なテーマとなっています。なぜこのタイトルが選ばれたのか、その意味を考えながら読み進めることで、「取り替え子」という作品をより深く味わうことができるでしょう。
この記事では、まず物語の骨子となるあらすじを紹介し、その後でより踏み込んだ長文の感想を記していきます。感想部分では物語の核心に触れるネタバレも含まれますので、未読の方はご注意ください。しかし、この壮大な魂の記録である「取り替え子」の深い感動の一端に触れていただければ幸いです。
「取り替え子」のあらすじ
国際的に名高い作家である長江古義人(ながえ こぎと)のもとに、ある夜、衝撃的な一本のカセットテープが届きます。それは、彼の義兄であり、高校時代からの親友でもある著名な映画監督、塙吾良(はなわ ごろう)が自殺する直前の声が録音されたものでした。テープの最後には「おれは向こう側に移行する」という言葉と、ビルから飛び降りたことを示す生々しい衝撃音が残されていました。
吾良の死はスキャンダラスに報じられ、その死の尊厳はメディアによって著しく傷つけられます。世間の喧騒から逃れるように、古義人は書庫に閉じこもり、吾良が生前に遺した膨大な数のテープを夜ごと聴き始めます。ヘッドホンを通して聴こえてくるのは、二人の過去の思い出を語る吾良の声。古義人はその声に応答し、死者との架空の対話を重ねることで、吾良の死の謎へと迫ろうとします。
物語の核心には、二人が高校時代に体験した「アレ」と呼ばれる暴力的な事件の記憶が存在します。この事件は二人の心に深い傷を残し、その後の人生を決定づけるほどの大きな影響を与えていました。吾良はなぜ死ななければならなかったのか。彼が抱えていた苦悩の根源には、自分は「本物」ではないという「取り替え子」としての意識があったことが、次第に明らかになっていきます。
古義人は、吾良がテープに託したメッセージの真意を確かめるため、二人の記憶が眠る故郷・四国の森へ、そして大学からの招聘に応じてドイツのベルリンへと旅立ちます。異国の地での新たな出会いを通して、古義人は親友の知られざる一面と、自らの過去に対峙していくことになるのです。
「取り替え子」の長文感想(ネタバレあり)
大江健三郎氏の『取り替え子』は、単なる小説という枠を超え、読む者の魂を激しく揺さぶる力を持った作品です。これは、義兄・伊丹十三氏の死という作者自身の個人的な体験を昇華させた、痛切な鎮魂歌であり、同時に未来への希望を紡ぐ再生の物語でもあります。この感想では、物語の核心に触れるネタバレを含みながら、その深淵な世界を探求してみたいと思います。
物語は、主人公・古義人の親友であり義兄の吾良の衝撃的な自殺から幕を開けます。吾良が遺したカセットテープ、通称「田亀(たがめ)のシステム」を通じて、古義人は死者との対話を始めます。この設定がまず秀逸です。一方通行であるはずの死者からのメッセージに、古義人が応答するという行為は、喪失の悲しみを乗り越えようとする人間の切実な祈りのようにも見えます。
吾良はなぜ死を選んだのか。その謎を追う過程で浮かび上がるのが「取り替え子(チェンジリング)」というキーワードです。吾良は、ある時から自分自身を「本物ではない、偽りの存在」だと感じていました。この疎外感と絶望が、彼を死へと追いやった根源的な要因として描かれます。これは現代を生きる我々にとっても、決して無関係なテーマではないでしょう。
そして、二人の過去を縛り続けるのが「アレ」と呼ばれる暴力的な事件の記憶です。高校時代、右翼的な思想を持つ男に率いられて起こしたこの事件は、彼らの心に消えない傷跡を残しました。吾良はこの体験を映画にしようと試みますが果たせず、その遺志を小説家である古義人に託す形で死んでいきます。この部分には、芸術による魂の救済という、大江文学に一貫して流れるテーマが色濃く表れています。
この物語は、極めて私的な体験から出発しながらも、非常に普遍的な問いを私たちに投げかけます。かけがえのない他者の死を、残された者はどう受け止め、生きていけばいいのか。過去のトラウマといかに向き合い、乗り越えていくべきなのか。『取り替え子』は、その問いに対する一つの答えを、静かに、しかし力強く示してくれるのです。
古義人は吾良の死の真相を探るため、故郷の四国へと向かいます。「アレ」の現場でもあるその場所は、二人の記憶の原点であり、物語の重要な舞台装置として機能します。故郷の森の描写は、大江氏の他の作品にも通じる、神話的で濃密な空気に満ちており、読者を物語の世界へと深く引き込みます。
その後、古義人はベルリンへと旅立ちますが、この場所の移動も象徴的です。故郷という過去の記憶が凝縮された場所から、歴史の大きな傷跡が残る異国の地へ。そこで彼は、吾良の過去を知る女性シマ・浦と出会い、親友の新たな一面を知ることになります。この出会いが、物語を予期せぬ方向へと展開させ、再生への道筋を照らし出すのです。
この小説の特筆すべき点は、重厚で難解とも言えるテーマを扱いながらも、読者を惹きつけてやまない物語性を失っていないことです。吾良の死の謎、過去の事件の真相、そして「取り替え子」という言葉に込められた意味。これらの謎が少しずつ解き明かされていく過程は、ミステリー小説を読むようなスリルさえ感じさせます。
しかし、『取り替え子』の本当の価値は、謎が解明された後に訪れる深い感動にあります。吾良の死は、ヤクザの襲撃やスキャンダルといった社会的な要因も絡んでいますが、その根底にはやはり、自分は「取り替え子」であるという個人的な絶望がありました。そして彼は、古義人に「本物」として生き続けてほしいという願いを込めて、テープを遺したのです。これは、究極の友情の物語とも言えるでしょう。
この物語の結末には、一条の光が差し込みます。それは、シマ・浦が吾良の面影を持つ男性の子を身ごもり、出産を決意するという形で示されます。古義人の妻であり吾良の妹である千樫は、その子を「吾良の取り替え子」と呼び、新しい生命の誕生を助けるためにベルリンへ向かう決意をします。
死から始まり、絶望と喪失の淵をさまよった物語が、新しい生命の誕生という希望に着地する。この構成の見事さには、ただただ圧倒されるばかりです。破壊の先にある再生、絶望の先にある希望という、人間存在の根源的なテーマがここに描かれています。
ウォーレ・ショインカの戯曲の一節「もう死んでしまった者らのことは忘れよう、生きている者らのことすらも。あなた方の心を、まだ生まれて来ない者たちにだけ向けておくれ」という引用で物語は締めくくられます。この一文は、『取り替え子』という作品全体を象徴しており、読者の胸に深く刻まれることでしょう。
本作は、大江氏の後期のキャリアを代表する「おかしな二人組(スードウ・カップル)」三部作の第一作にあたります。主人公の古義人は、この後も『憂い顔の童子』『さようなら、私の本よ!』といった作品に登場し、彼の魂の旅は続いていくことになります。
『取り替え子』を読むという体験は、一人の人間の内面世界を、その最も深い場所まで旅するようなものです。古義人の苦悩や葛藤は、読者自身のものとして感じられ、彼の魂が再生していく過程は、私たち自身の救済にも繋がっていくかのようです。
特に印象的なのは、古義人が死んだ吾良と「田亀のシステム」を通して対話を続ける場面です。これは単なる感傷的な回想ではありません。過去を再検証し、自己を分析し、そして未来へ向かうための、積極的で創造的な行為なのです。この死者との対話を通して、古義人は吾良の死を乗り越えるのではなく、その死を抱きしめて生きていく覚悟を固めていきます。
ネタバレになりますが、物語の終盤で示唆されるのは、吾良の死が、古義人を小説家としてさらに成熟させるための、ある種の「贈り物」であったという解釈です。もちろん、それはあまりにも痛ましく、残酷な贈り物です。しかし、吾良はその死をもって、古義人にしか書けない物語を書くことを託したのです。芸術家の業のようなものさえ感じさせます。
この『取り替え子』という作品は、読む人を選ぶかもしれません。しかし、一度その世界に入り込むことができれば、間違いなく一生忘れられない読書体験となるはずです。人間の弱さと強さ、絶望と希望、そして死と再生という普遍的なテーマが、見事な物語として結晶化した、まさに文学の到達点の一つと言えるでしょう。
最終的に、この物語は個人的な悲劇を超えて、より大きな何かを語りかけてきます。それは、いかにして他者と深く結びつき、その魂を受け継ぎ、未来へと繋げていくかという問いです。大江健三郎氏が『取り替え子』に込めた切実なメッセージを、ぜひ受け取ってみてください。
まとめ:「取り替え子」のあらすじ・ネタバレ・長文感想
この記事では、大江健三郎氏の小説『取り替え子』について、あらすじの紹介から、ネタバレを含む深い感想までを述べてきました。義兄であり親友であった映画監督の死という、作者自身の体験が色濃く反映されたこの物語は、読む者の心を強く揺さぶる力を持っています。
物語の導入は、主人公・古義人が、自殺した義兄・吾良が遺したカセットテープを聴く場面から始まります。死者との対話を通じて、古義人は吾良の死の謎と、二人の過去に横たわる暴力的な事件「アレ」の真相に迫っていきます。なぜ吾良は自分を「取り替え子」と感じ、死を選ばなければならなかったのか。その問いが物語を貫いています。
感想の部分では、ネタバレを交えながら、この作品が単なる喪失の物語ではなく、魂の再生と未来への希望を描いた壮大な物語であることを論じました。吾良の死を受け入れ、その遺志を継いで小説家として生きていくことを決意する古義人の姿は、深い感動を与えます。
『取り替え子』は、死という重いテーマを扱いながらも、最終的には新しい生命の誕生という希望に着地します。かけがえのない人間の死という大きな喪失から、いかにして再生への道を歩むかを描いたこの傑作は、現代を生きる私たちに多くのことを示唆してくれるでしょう。