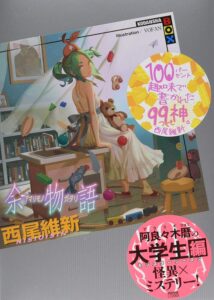 小説「余物語」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。西尾維新さんの作品世界にまた新たな一ページが加わりましたね。大学生になった阿良々木暦が、今回もまた奇妙な事件に巻き込まれていく様子が描かれています。
小説「余物語」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。西尾維新さんの作品世界にまた新たな一ページが加わりましたね。大学生になった阿良々木暦が、今回もまた奇妙な事件に巻き込まれていく様子が描かれています。
物語シリーズといえば、高校生の暦のイメージが強いですが、本作では少し大人になった彼の姿を見ることができます。それでも、事件を引き寄せる体質は相変わらずのようで、安心しました、と言うべきでしょうか。彼の周りには、いつも通り個性的なキャラクターたちが集まってきます。
今回は、児童虐待という少し重いテーマが扱われていますが、そこは西尾維新さん。独特の言葉遊びや展開で、私たち読者を飽きさせません。斧乃木余接との掛け合いも健在で、シリアスな中にもクスリとさせられる場面が散りばめられています。
この記事では、そんな「余物語」の物語の詳しい流れと、私が感じたことや考えたことを、ネタバレを気にせずにたっぷりと語っていきたいと思います。まだ読んでいないけれど内容が気になる方、読んだけれど他の人の意見も聞いてみたい方、ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。
小説「余物語」のあらすじ
大学生になった阿良々木暦は、ひょんなことから「児童虐待の専門家」という、なんとも物々しい肩書きで紹介されてしまいます。その紹介をしたのは、かつての級友であり、今は同じ大学に通う老倉育でした。そんなある日、暦はスイス語担当の家住羽衣(いえすみはごろも)准教授から呼び出しを受けます。
家住准教授の相談内容は衝撃的なものでした。「三歳になる一人娘を虐待してしまった、正確には、しそうになってしまった。急に可愛く思えなくなった」と言うのです。あまりにも異質な相談に戸惑う暦でしたが、育からの紹介もあり、話を聞くことになります。さらに家住准教授は、「娘を籠に閉じ込めていたが、ここ三日ほど忙しくて家に帰れていない。娘の様子を見てきてほしい」と依頼し、家の鍵を渡します。
渋々ながらも家住准教授の家へ向かう暦。道中、なぜか派手な服を着た斧乃木余接が後部座席に現れます。曰く、暦の妹である月火から逃げてきたとのこと。いつものような軽口を叩きながら家へ到着し、娘の部屋と思われる鍵のかかった部屋を余接がこじ開けると、そこには籠があり、中には人形が入っていました。暦はひとまず安堵します。
しかし、その人形は背中からナイフで突き刺され、固定されていました。この異様な状況に、暦は家住准教授と改めて話をする必要があると考えますが、当の家住准教授は行方をくらましてしまいます。途方に暮れる暦のもとに、神原駿河の友人である日傘星雨から連絡が入り、神原家へ向かうと、そこにいたのは忍野扇(男バージョン)。扇との会話の中で、家住の夫の存在や、家のドアを破壊したままだったことを思い出し、急いで家住家へ戻ります。
家住家に戻った暦は、子供部屋のドアを修理しようとしますが、籠の中にあったはずの人形が消えていることに気づきます。家の中にまだ潜んでいる可能性を考え捜索を始めようとした矢先、何者かに襲われ、今度は自分が籠の中に閉じ込められてしまいます。なんとか脱出したものの、追跡手段である愛車はパンクさせられていました。
もはや自分の手には負えないと判断した暦は、余接に協力を依頼します。再び家住家を捜索すると、二人はまたしても襲撃を受けますが、これを撃退。その後、大学の家住准教授の研究室で、複数の言語で書かれた置手紙を発見します。友人たちの協力を得て解読すると、家住准教授自身も幼少期に虐待を受けていたこと、そしてその影響で自ら命を絶とうとしていることが判明します。暦たちは間一髪のところで彼女を救い出し、事件は一応の解決を見るのでした。
小説「余物語」の長文感想(ネタバレあり)
いやはや、今回もまた西尾維新さんの世界にどっぷりと浸らせていただきました。「余物語」、大学生になった暦の新たな一面が見られるかと思いきや、相変わらずの巻き込まれ体質で、どこかホッとしてしまう自分がいましたね。
物語の始まりは、暦が「児童虐待の専門家」として誤解されるところから。老倉育が絡んでいると聞いて、ああ、なるほど、と妙に納得してしまいました。彼女らしいと言いますか、暦にとっては迷惑千万な話でしょうけれど、物語の導入としては非常にスムーズで、読者を引き込む力があります。
家住羽衣准教授のキャラクターは、最初は本当に掴みどころがなかったですね。「娘を可愛く思えなくなった」という告白は衝撃的で、一体どんな闇を抱えているのだろうかと、ページをめくる手が止まりませんでした。彼女の抱える問題の根深さが、物語全体に重たい雰囲気を与えていたように感じます。
そして、我らが斧乃木余接。今回は月火から逃れて暦のもとへやってくるわけですが、その登場シーンからして、もう彼女らしさ全開。派手な服のチョイスも「らしい」ですし、暦との間で交わされる、どこか噛み合っているようで噛み合っていない会話は、本作でも健在で、物語の清涼剤のような役割を果たしていましたね。特に、シリアスな場面での彼女の淡々としたツッコミは、絶妙なバランス感覚です。
家住准教授の家で発見された、ナイフで刺された人形。この場面は、かなりゾッとさせられました。ただの人形ではなく、まるで何かを象徴しているかのような不気味さ。家住准教授の精神状態の異常さを際立たせると同時に、この先に待ち受けるであろう事件の複雑さを予感させるに十分な演出だったと思います。
家住准教授が姿を消し、物語は一気にミステリーの様相を呈してきます。暦が忍野扇と事件について推理を交わすシーンは、物語シリーズのファンにとってはニヤリとするところではないでしょうか。扇の登場は、いつも物語に新たな視点と混乱(良い意味での)をもたらしてくれますね。
そして、消えた人形。これがただの人形ではなく、成長する怪異だったという展開には、度肝を抜かれました。暦が逆に籠に閉じ込められてしまうシーンは、攻守逆転の面白さがあり、緊迫感も高まりました。西尾維新さんの作品では、こういった予想の斜め上を行く展開が本当に巧みですよね。
余接に助けを求め、再び家住家へ向かう暦。ここでの余接の戦闘シーンは、相変わらずの強さで、読んでいて爽快感すら覚えます。「僕はキメ顔でそう言った」の決め台詞もバッチリ決まっていました。ただ、家を一部破壊してしまうのは、まあ、ご愛嬌ということで。
置手紙の解読シーンでは、暦の周りの友人たちの協力が描かれます。物語シリーズを通して描かれてきた、暦と仲間たちとの絆の強さを再確認できる場面でもありました。様々な言語で書かれた手紙というのも、家住准教授の知性や、彼女が抱える問題の複雑さを表しているようで、興味深い設定でした。
家住准教授が抱えていた過去のトラウマ、そしてそれが現在の行動に繋がっていたという真相は、非常に重く、考えさせられるものでした。児童虐待というテーマはデリケートですが、西尾維新さんはそれをエンターテイメントとして昇華しつつも、決して軽んじることなく描いていると感じました。
最終的に家住准教授を救うことができたのは、暦と余接、そして間接的に関わった多くの人々の力があったからでしょう。特に、最後に羽川翼が登場し、事件の腑に落ちない点について解説を加えることで、物語全体が綺麗に収束していく様は見事でした。彼女の存在は、まさに「何でも知ってるお姉さん」ですね。
「余物語」を通して感じたのは、人は誰しも多かれ少なかれ「物語」を抱えて生きていて、時にはそれが重荷になることもあるけれど、誰かとの関わりの中で救われることもあるのだな、ということです。暦が、意図せずとも専門家として頼られ、結果的に家住准教授を救ったように。
また、斧乃木余接の感情の在り様も、本作では少し掘り下げられていたように思います。普段は感情がないように振る舞う彼女が、月火に対しては明確な「嫌悪」のような感情を見せたり、暦との間には友情のようなものが確かに存在していることが示唆されたり。彼女の人間(人形?)らしさが垣間見えるようで、嬉しくなりました。
暦自身の成長も感じられましたね。高校生の時のような無鉄砲さや危うさは少し影を潜め、大学生らしい落ち着き……とまではいかないまでも、問題解決に向けてより多角的にアプローチしようとする姿勢が見られたように思います。まあ、結局は怪異とのバトルになるわけですが。
「余物語」はシリアスなテーマを扱いながらも、西尾維新さんらしい言葉遊びやキャラクターの魅力、そして意表を突く展開が詰まった、非常に読み応えのある一冊でした。物語シリーズの新たなステージを感じさせるとともに、これまでのシリーズを読み返したくなるような、そんな作品だったと思います。読後感は、重いテーマを扱っているにも関わらず、どこか爽やかさも残る、不思議なものでした。
まとめ
さて、今回は西尾維新さんの小説「余物語」について、物語の詳しい流れや、私が感じたことを色々と語らせていただきました。大学生になった阿良々木暦が、新たな事件に挑む姿、そして斧乃木余接との変わらぬ絆が描かれた、読み応えのある一作でしたね。
児童虐待という重いテーマを扱いながらも、西尾維新さんならではの筆致で、エンターテイメントとして楽しめる作品に仕上がっていたと思います。登場人物たちの個性的な魅力や、先の読めない展開は、ページをめくる手を止めさせてくれませんでした。
特に印象的だったのは、家住准教授が抱える心の闇と、それに向き合おうとする暦たちの姿です。そして、それを支える斧乃木余接の存在も欠かせません。彼女たちのやり取りを見ていると、どんな困難な状況でも、誰かとの繋がりが救いになるのだと感じさせられます。
もし、あなたが西尾維新さんのファンであるならば、もちろんのこと、そうでなくても、少し変わったミステリーや、魅力的なキャラクターたちが織りなす物語に触れてみたいと思っているのなら、この「余物語」はきっと楽しめるはずです。ぜひ手に取ってみてください。



青色サヴァンと戯言遣い-722x1024.jpg)





曳かれ者の小唄-721x1024.jpg)








.jpg)




















赤き征裁vs橙なる種-728x1024.jpg)














十三階段.jpg)



















兎吊木垓輔の戯言殺し-724x1024.jpg)















.jpg)








