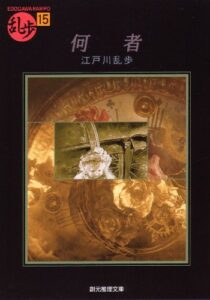 小説「何者」の物語の筋を、結末の暴露を含めて詳しくお話しします。長文の受け止め方も記していますので、どうぞご覧ください。
小説「何者」の物語の筋を、結末の暴露を含めて詳しくお話しします。長文の受け止め方も記していますので、どうぞご覧ください。
江戸川乱歩によって生み出されたこの物語は、1929年から新聞で読者を楽しませた作品です。名探偵・明智小五郎が登場するシリーズの一つとしても知られていますね。鎌倉の屋敷で起こる一つの事件を発端に、人間関係のもつれや隠された意図が明らかになっていく過程が描かれます。
この記事では、まず「何者」の物語がどのように進んでいくのか、その流れを詳しく追っていきます。事件の発生から捜査、そして意外な犯人の指摘に至るまで、物語の核心に触れる部分も隠さずにお伝えします。どのような結末を迎えるのか、気になる方は読み進めてみてください。
さらに、物語を読み終えて私がどう感じたか、その詳しい所感を述べていきます。トリックの巧妙さ、登場人物たちの心理描写、そして物語全体の構成について、深く掘り下げていきます。結末を知った上で読むと、また違った側面が見えてくるかもしれません。どうぞ最後までお付き合いください。
小説「何者」のあらすじ
物語は、語り手である「私」(松村)が、友人の甲田伸太郎と共に、もう一人の友人である結城弘一の鎌倉にある邸宅で、学生最後の夏休みを過ごす場面から始まります。結城家は陸軍少将を父に持つ裕福な家柄で、弘一の従妹であり許嫁でもある美しい志摩子も同居していました。穏やかな日々は、ある夜、突然破られます。
その夜は、結城少将の誕生祝いの宴が開かれていました。宴もたけなわとなった頃、弘一は小説の執筆のため自室の書斎へと戻ります。しばらくして、邸内に銃声が響き渡りました。異変に気づいた甲田が宴会場に駆け込み、弘一が大変なことになっていると告げます。皆が書斎へ駆けつけると、そこには足を撃たれて倒れている弘一の姿がありました。窓ガラスは割れ、部屋には多くの足跡が残されていました。
奇妙なことに、犯人は大金の入った札入れには目もくれず、それほど価値のない金製品ばかりを盗んでいったのです。現場には、結城家の下男である常爺さんが窓際に座り込んでいる姿があり、「私」はわずかな違和感を覚えます。やがて警察から波多野警部が到着し、本格的な捜査が開始されました。書斎の外に残された往復の足跡を辿ると、それは空き地の古い井戸の前で途切れていました。探偵好きの弘一と親しい、同じく探偵趣味を持つ赤井という客人も、興味深げに捜査の様子を見守ります。
第一発見者の甲田は、部屋の電気が消えており犯人の姿は見ていないと証言します。一方、志摩子は、隣の部屋にある自分の書斎から日記帳が持ち出され、放り出されていたことに気づきます。数日後、病院に見舞いに行った「私」に対し、回復しつつある弘一は、これは単なる強盗ではなく、もっと恐ろしい犯罪だと語ります。彼は足跡の不自然さや盗品が金製品ばかりである点、そして常爺さんの行動から、犯人に心当たりがある様子を見せますが、その名前を明かしません。
「私」は独自に調査を進め、結城邸の花壇から常爺さんの老眼鏡のサックを発見します。その直後、ずぶ濡れの赤井に出くわします。彼は庭の池に落ちたと説明しますが、どこか不自然です。病院で弘一にサックを見せると、彼は犯人を確信したようでした。そこへ波多野警部が現れ、琴野光雄という青年を逮捕したと告げます。光雄は金製品収集の趣味があり疑われていましたが、盗品は見つかっていませんでした。しかし弘一は、光雄は犯人ではないと断言し、自身の推理を語り始めます。
弘一は、足跡は内部犯が外部犯に見せかけるための偽装であり、盗まれた金製品は屋敷の池に沈められているはずだと指摘します。そして、犯人の真の目的は金品ではなく、自分自身の命であり、その犯人は第一発見者の甲田伸太郎だと告発するのです。弘一と甲田の間には、志摩子を巡る恋の争いがあり、それが動機だと。甲田が常爺さんの眼鏡サックを使っていたことも状況証拠とされ、甲田は逮捕されますが、犯行を否認し続けます。物語は、この甲田逮捕では終わりませんでした。
小説「何者」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは小説「何者」を読了した上での、私の率直な受け止め方を詳しく述べていきたいと思います。結末、つまり真犯人が誰であったかを知った上で振り返ると、この物語は非常に興味深い構造を持っていると感じます。しかし同時に、ミステリとしての驚きという点では、少々物足りなさを感じたのも事実です。
まず、多くの読者が比較的早い段階で「真相」に気づいてしまうのではないか、という点が挙げられます。物語に登場する赤井という人物の存在感が、序盤から非常に際立っています。彼の探偵趣味や、事件現場での意味深な行動、そして時折見せる鋭い観察眼は、彼がただの逗留客ではないことを強く示唆しています。江戸川乱歩作品に慣れ親しんだ読者であれば、この「怪しい赤井」こそが、名探偵・明智小五郎の変装した姿ではないかと推測するのは、それほど難しくないでしょう。
赤井が「探偵役」である可能性が高いと考えると、次に疑いの目が向かうのは、探偵役のように振る舞い、自らの推理を披露する結城弘一その人です。彼が入院先のベッドから指示を出し、警察さえも感心するような推理を展開する様は、あまりにも出来すぎているように感じられます。特に、友人である甲田を犯人として名指しする場面は、やや強引さも否めません。この時点で、「弘一が何かを隠しているのではないか」「彼自身が事件の首謀者なのではないか」という疑念が、読者の心に芽生えやすい構造になっていると感じます。
物語の核となるトリック、すなわち「外部からの侵入に見せかけた内部犯行」という構図も、比較的オーソドックスなものと言えるでしょう。書斎に残された往復の足跡が、実は犯人が内部から井戸まで行って戻ってきただけ、という真相は、論理的に考えれば不自然な点が見えてきます。また、価値のない金製品ばかりが盗まれたという点も、金銭目的の強盗としては不自然であり、別の目的、すなわち犯行の偽装や特定の人物への嫌疑誘導を示唆しています。これらの要素が、真相解明へのヒントとして機能する一方で、ミステリとしての意外性をやや削いでしまっている側面もあるかもしれません。
犯行の動機として提示される二つの要素、すなわち志摩子を巡る甲田との三角関係、そして弘一自身の兵役逃れという理由は、非常に人間臭く、説得力のあるものです。特に後者は、発表当時の社会情勢を色濃く反映しており、単なる個人的な感情のもつれだけではない、より切実な背景を物語に与えています。愛する女性を手に入れたいという欲望と、過酷な軍隊生活から逃れたいという利己的な願いが、友人を陥れてまで自作自演の犯罪を計画させるに至った、その心理の闇は深く、考えさせられるものがあります。
結城弘一という人物の造形は、この物語の最も興味深い点の一つかもしれません。彼は被害者でありながら、事件を捜査する探偵役を演じ、最終的には真犯人であったことが暴露されます。持ち前の探偵趣味を、自らの犯罪を隠蔽し、友人を犯人に仕立て上げるために利用するという皮肉。彼の知性とプライド、そして内に秘めた嫉妬心や利己主義が複雑に絡み合い、悲劇的な結末へと突き進んでいく様は、読んでいて痛々しさすら感じさせます。彼の行動は、知性が必ずしも善なる方向に使われるわけではない、という人間の暗い側面を浮き彫りにしています。
一方で、弘一によって犯人に仕立て上げられそうになった甲田伸太郎は、まさに悲劇の人物と言えるでしょう。親友だと思っていた人間に裏切られ、愛する女性を巡る争いから無実の罪を着せられそうになる。彼の驚き、怒り、そして絶望は察するに余りあります。弘一と甲田の間にあった友情が、いかに脆いものであったかを示すと同時に、恋愛感情が時として友情をも破壊してしまう残酷さを描いています。彼の潔白が最終的に証明されることに、読者は安堵を覚えるでしょう。
そして、物語の解決をもたらすのが、謎の男・赤井、すなわち名探偵・明智小五郎です。彼は当初、事件の周辺をうろつく怪しい人物として描かれますが、その観察眼は常に鋭く、弘一の推理の綻びや現場の不自然な点を見逃しません。最終場面、海岸で弘一と対峙し、冷静かつ論理的に彼の自作自演を暴いていく様は、まさに名探偵の面目躍如と言えます。特に、ハンカチの結び目や靴足袋のサイズといった物的証拠から甲田の無実を証明し、弘一の動機を鋭く指摘する場面は、鮮やかです。
「何者」における明智小五郎の描き方は、彼の多面性を示す一例と言えるでしょう。怪しげな風貌で事件の関係者に近づき、情報を集め、最後には颯爽と真相を解き明かして去っていく。その姿は、後の作品で見せる超人的な名探偵というよりも、まだ人間味のある、変装を得意とする探偵という印象が強いかもしれません。彼の存在が、この物語に一筋の光をもたらし、歪んだ状況を正常に戻す役割を果たしています。
物語の語り手である「私」(松村)は、読者と同じ視点を提供する重要な役割を担っています。彼は友人たちの間で起こる出来事に巻き込まれ、事件の真相に近づこうとしますが、弘一や赤井(明智)のような鋭い洞察力は持っていません。彼の目を通して語られることで、読者は事件の展開を自然に追いかけ、登場人物たちの感情に寄り添うことができます。彼の平凡さが、弘一の異常性や明智の非凡さを際立たせる効果も生んでいます。
事件の中心人物でありながら、どこか影の薄い存在にも感じられるのが、結城志摩子です。彼女は弘一の許嫁であり、甲田からも想いを寄せられるという、いわば悲劇のヒロインです。しかし、彼女自身の内面や葛藤が深く描かれる場面は少なく、物語の歯車として機能している側面が強いかもしれません。最後に弘一の自作自演と、その動機に自分自身が深く関わっていることを知った時の衝撃は、察するに余りあります。彼女の今後の人生を考えると、やるせない気持ちになります。
物語全体の構成としては、鎌倉の裕福な邸宅という舞台設定、夏の日の事件という雰囲気作りは巧みです。序盤で提示された謎が、中盤の捜査と弘一による一応の解決を経て、終盤で赤井(明智)によってひっくり返されるという展開は、ミステリの定石を踏んでいます。しかし、前述の通り、真相への道筋が比較的見えやすい点は否めず、読者をあっと驚かせるような、もう一段階のどんでん返しがあれば、さらに印象深い作品になったかもしれません。
江戸川乱歩の作品に共通する、どこか陰鬱で退廃的な雰囲気は、「何者」にも漂っています。特に、結城弘一の屈折した心理描写や、友情と恋愛が複雑に絡み合う人間関係には、乱歩ならではの قلم (fude) の冴えが感じられます。直接的な猟奇描写は少ないものの、人間の内面に潜む悪意や利己主義を鋭く抉り出す筆致は健在です。
結論として、「何者」は、ミステリとしての驚きやトリックの斬新さという点では、乱歩の他の代表作に比べるとやや見劣りするかもしれません。犯人やトリックの予測がつきやすいという評価も、ある程度は妥当でしょう。しかし、自らの欲望のために友人を陥れる人間の心理や、名探偵・明智小五郎の活躍を描いた人間ドラマとしては、十分に読み応えのある作品です。特に、弘一の動機に当時の社会背景が織り込まれている点は、作品に深みを与えています。
この物語を読む意義は、単なる謎解きを楽しむだけでなく、人間の心の複雑さや脆さ、そして時代が生み出す個人の苦悩に触れることにあるのかもしれません。江戸川乱歩のファンはもちろん、人間ドラマに関心のある方にとっても、一読の価値はある作品だと私は思います。明智小五郎が登場する初期の作品として、そのキャラクターの変遷を知る上でも興味深い一編と言えるでしょう。
まとめ
この記事では、江戸川乱歩の小説「何者」の物語の筋を、結末まで含めて詳しく紹介し、あわせて私の読後感を述べさせていただきました。鎌倉の屋敷で起こった銃撃事件を発端に、探偵趣味の青年・結城弘一が自らの推理で友人の甲田を犯人だと指摘しますが、最終的には謎の男・赤井(実は明智小五郎)によって、事件が弘一自身の自作自演であったことが暴かれる、という物語でした。
物語の核心、つまり弘一が自らの足を撃ち、友人に罪を着せようとした理由は、従妹の志摩子を巡る恋愛感情のもつれと、間近に迫った兵役から逃れたいという利己的な動機でした。この結末は、ミステリとしてはやや意外性に欠ける部分もあるかもしれませんが、人間の複雑な心理や当時の社会状況を反映したドラマとしては、深く考えさせられるものがあります。
「何者」は、名探偵・明智小五郎が登場する作品の一つとしても読むことができます。事件の真相を見抜く彼の鋭い観察眼と推理力は、物語の大きな魅力です。一方で、犯人である弘一の屈折した心理描写や、彼に陥れられそうになる甲田の悲劇性など、登場人物たちの織りなす人間模様も見どころと言えるでしょう。
もしあなたがこれから「何者」を読まれるのであれば、単なる犯人当てに留まらず、登場人物たちの心情や、なぜこのような事件が起こってしまったのかという背景に注目してみるのも面白いかもしれません。この記事が、あなたの「何者」体験をより豊かなものにする一助となれば幸いです。






































































