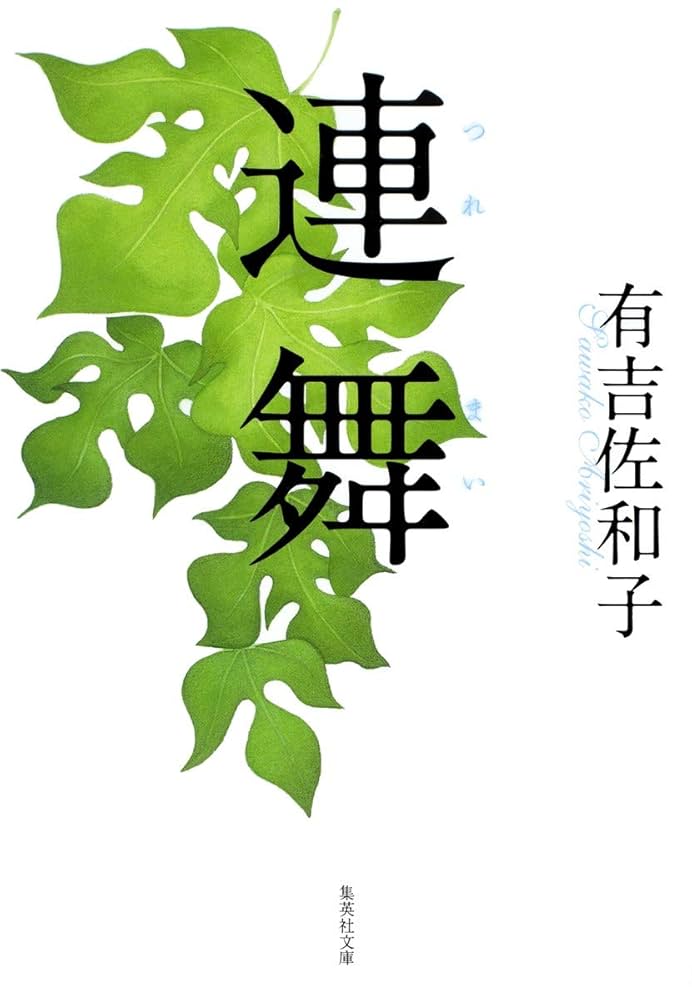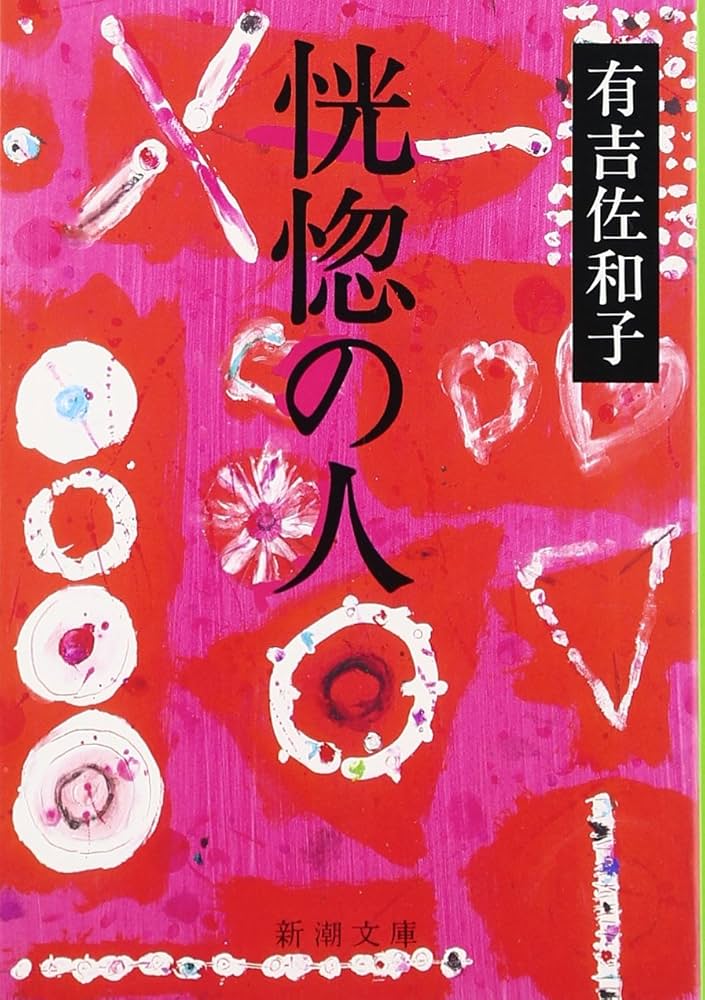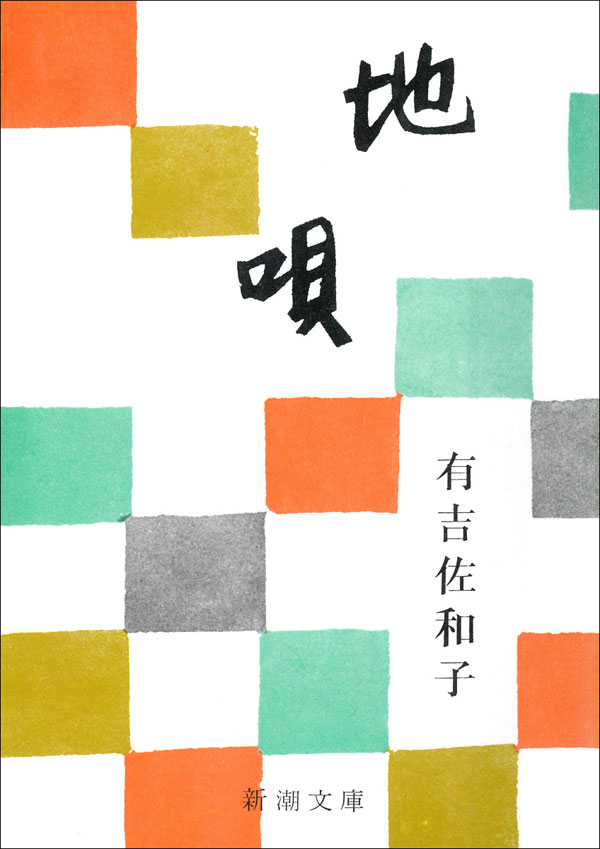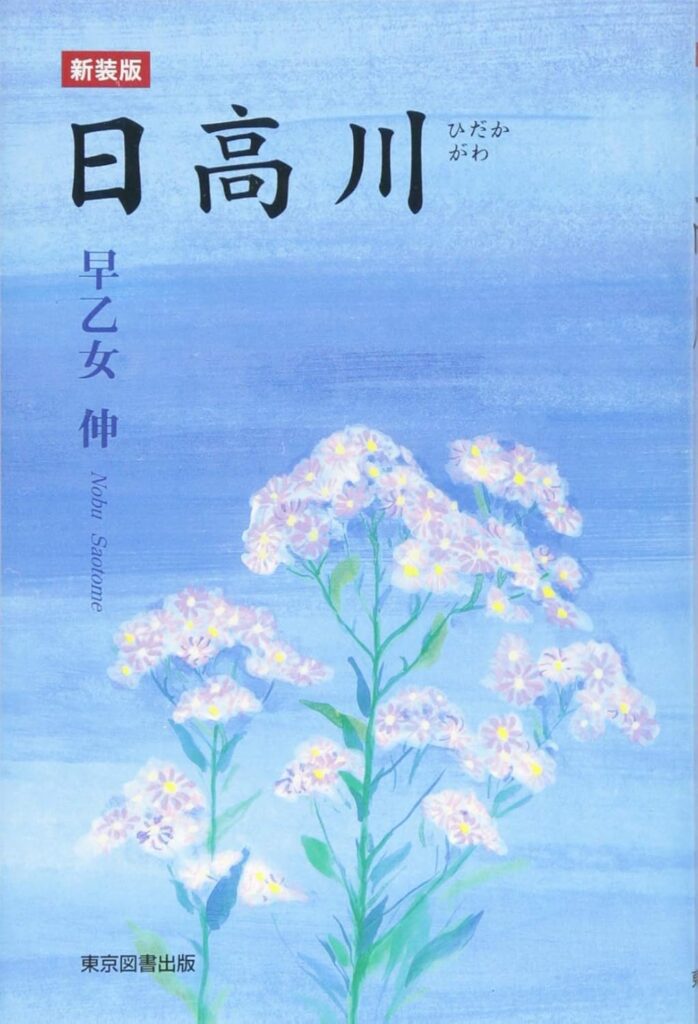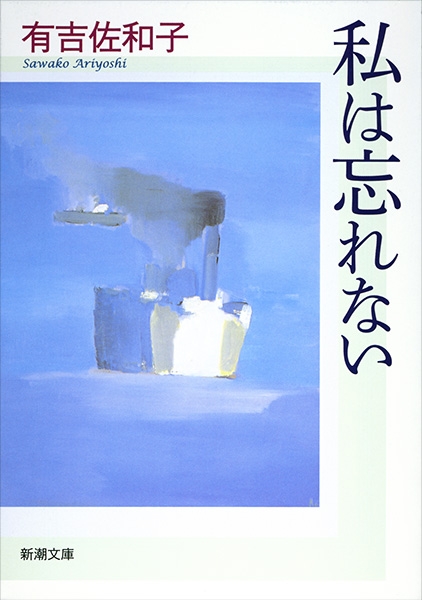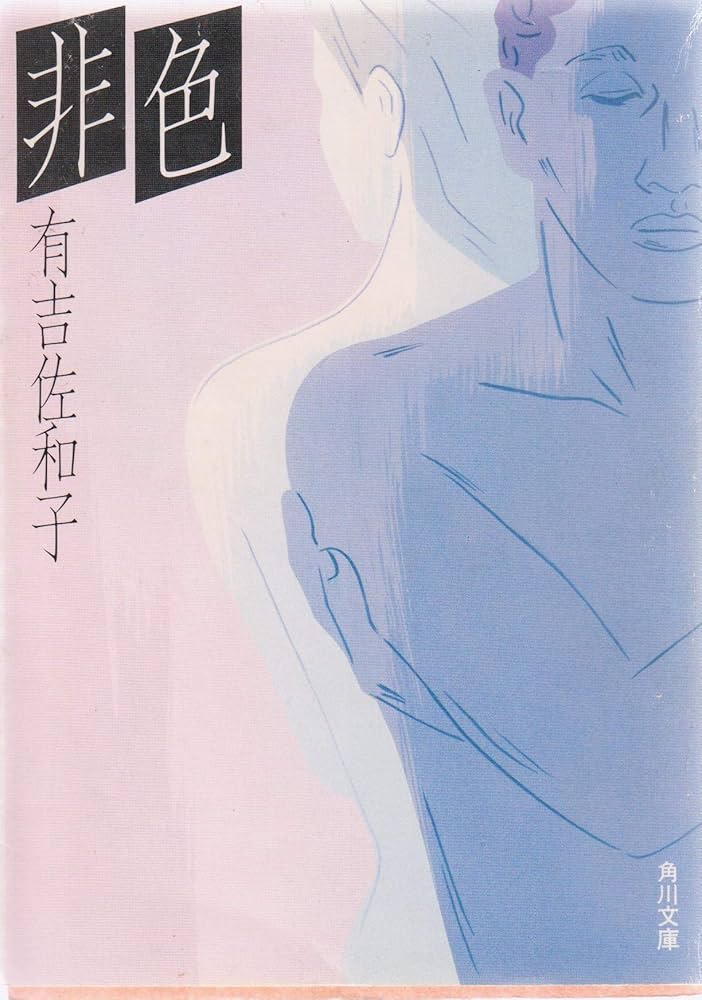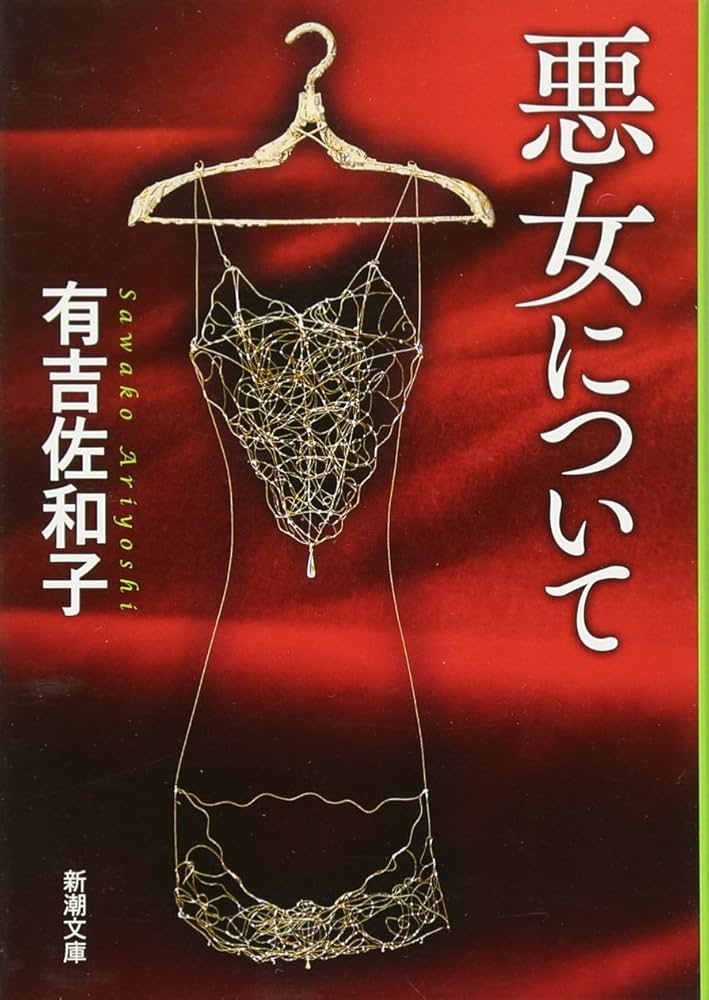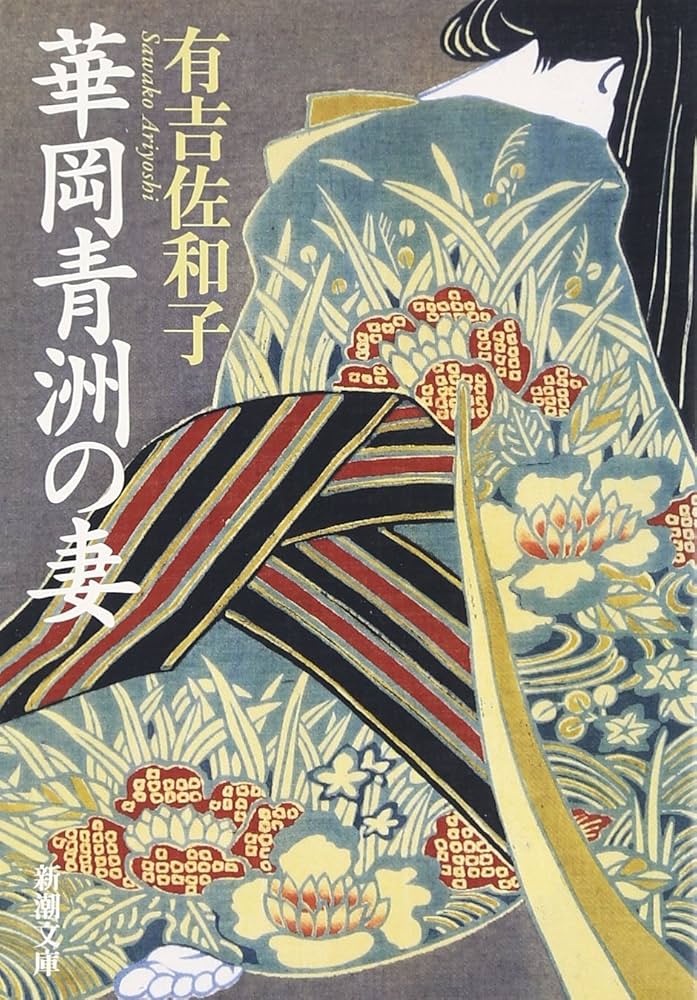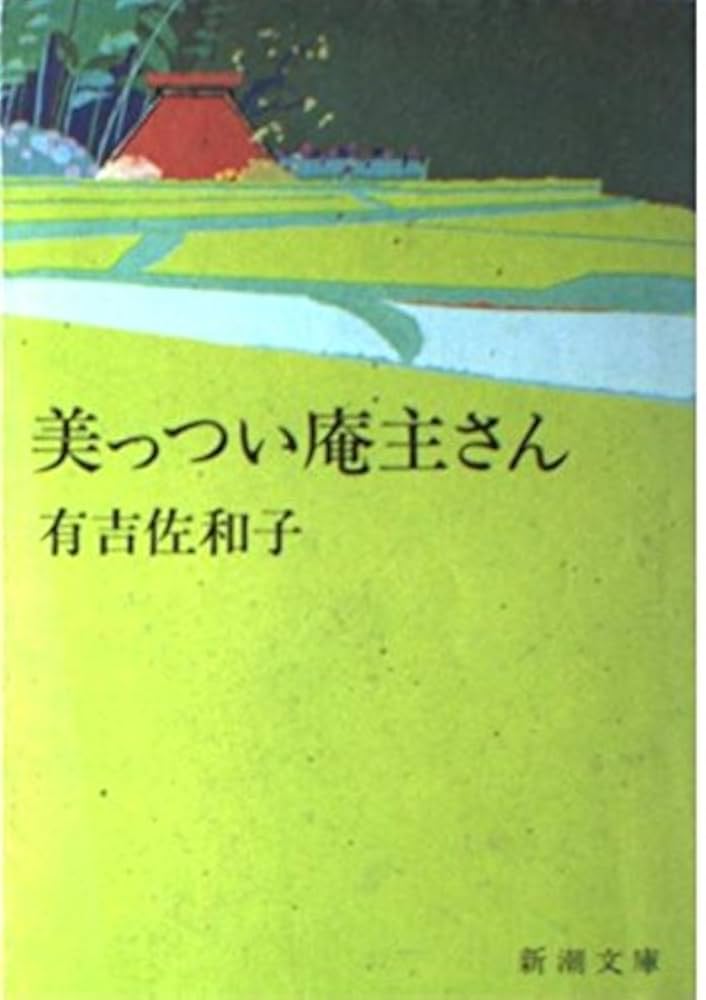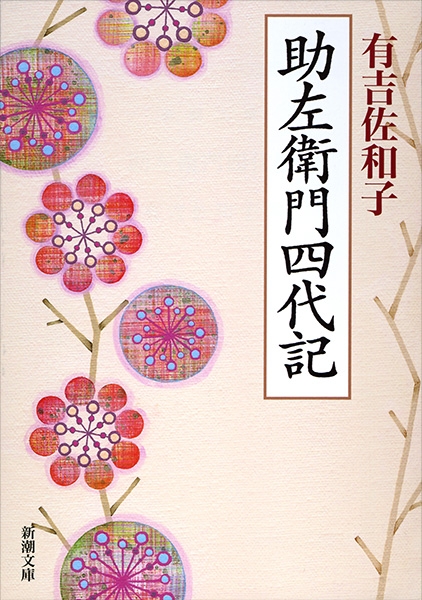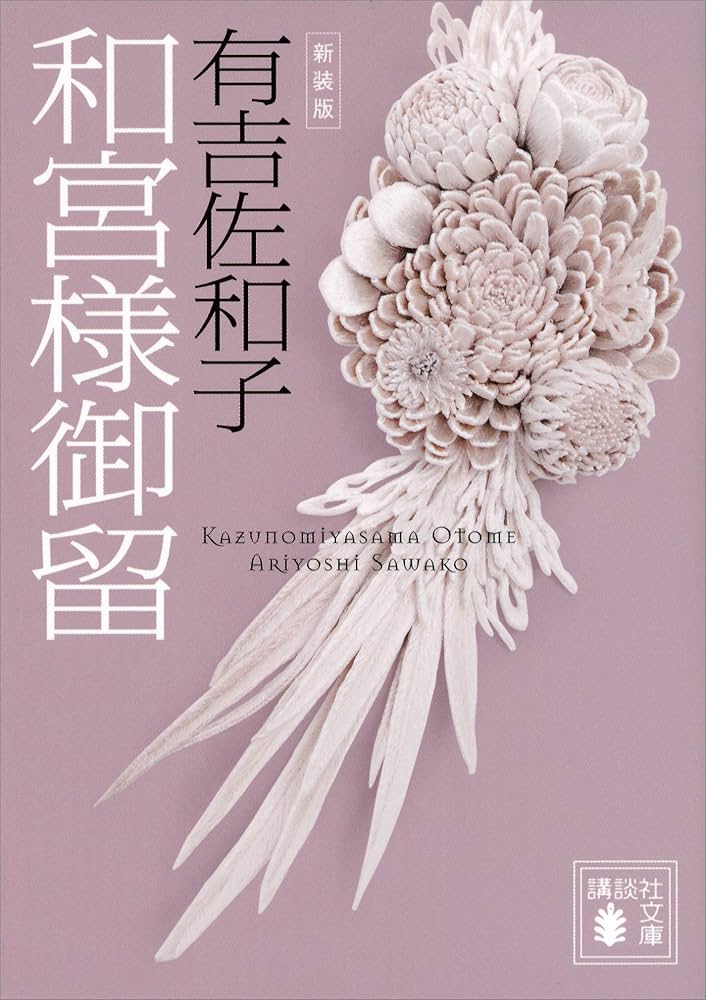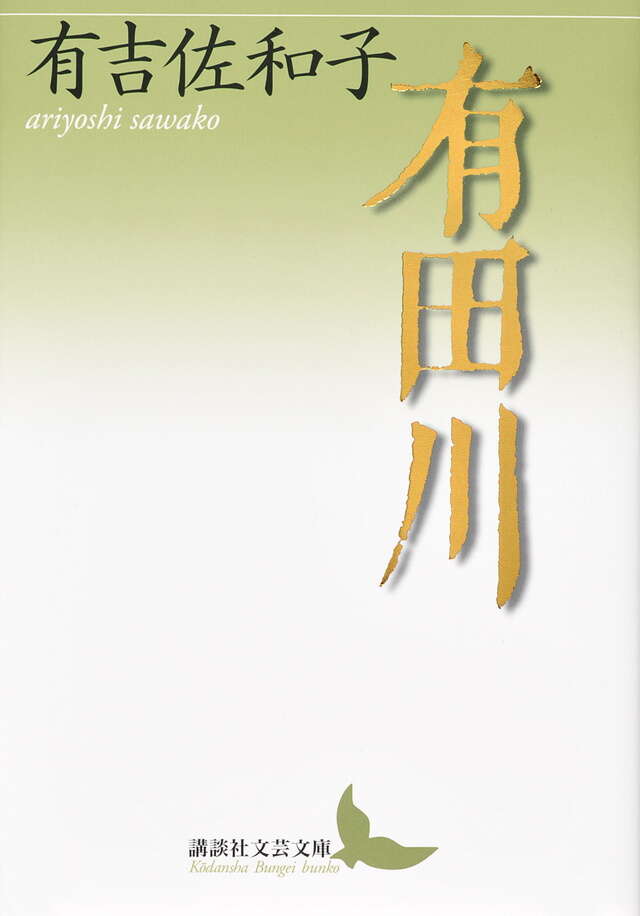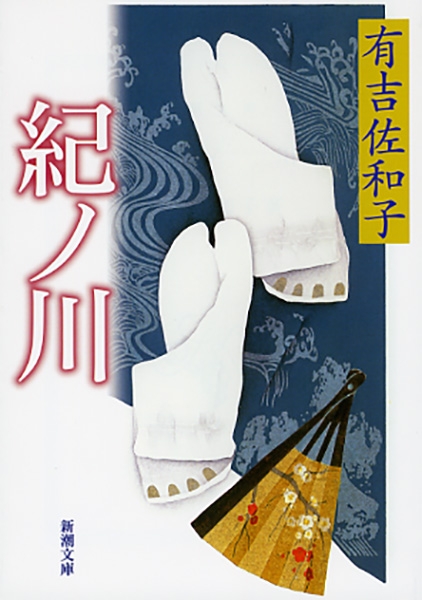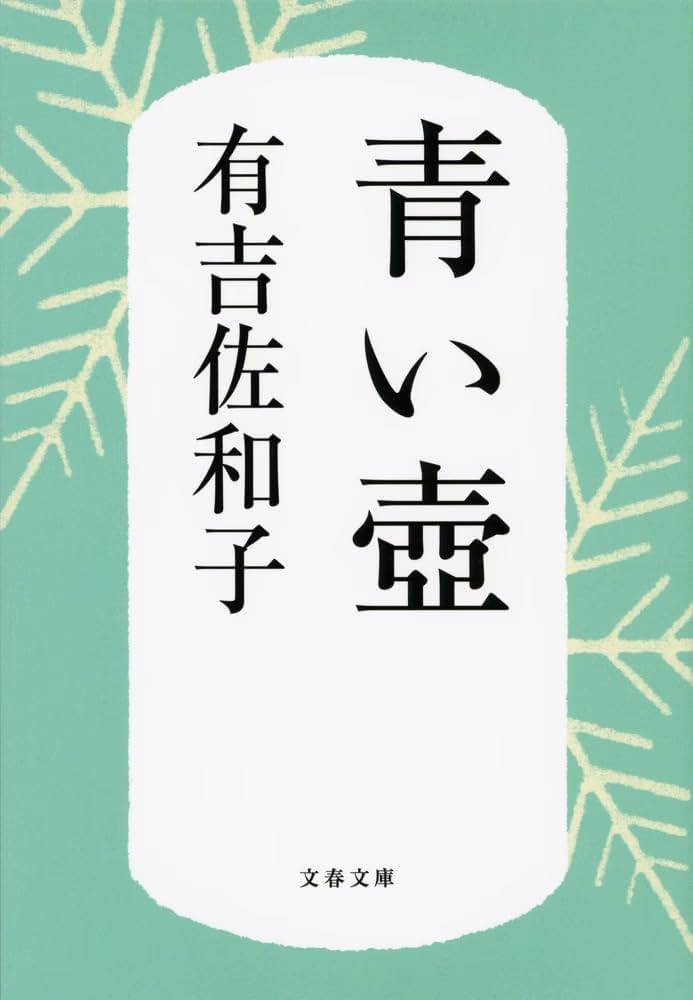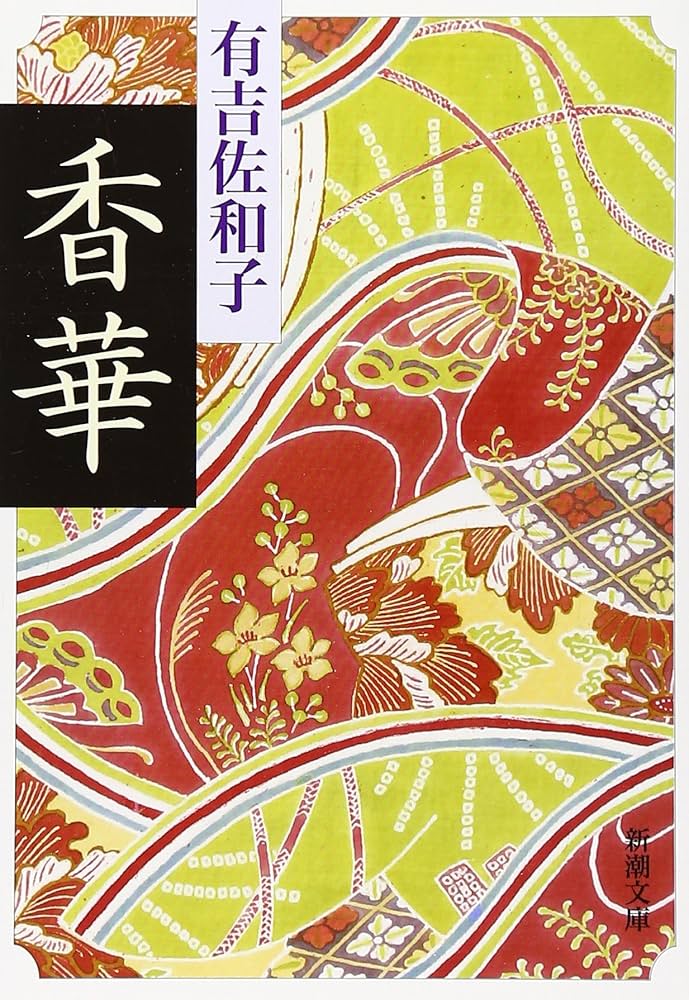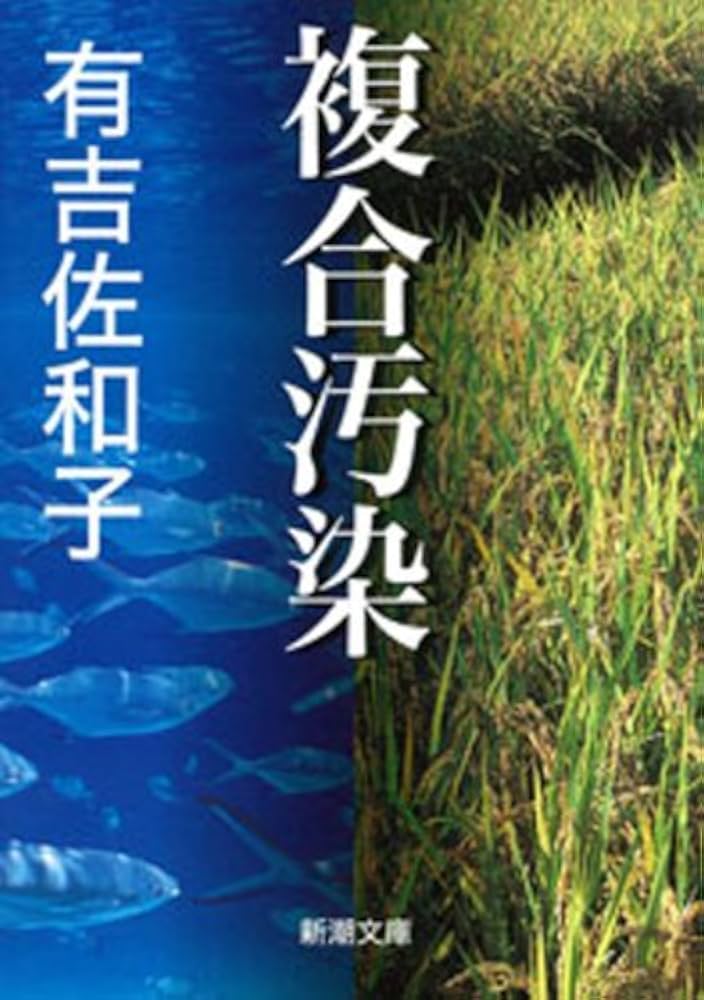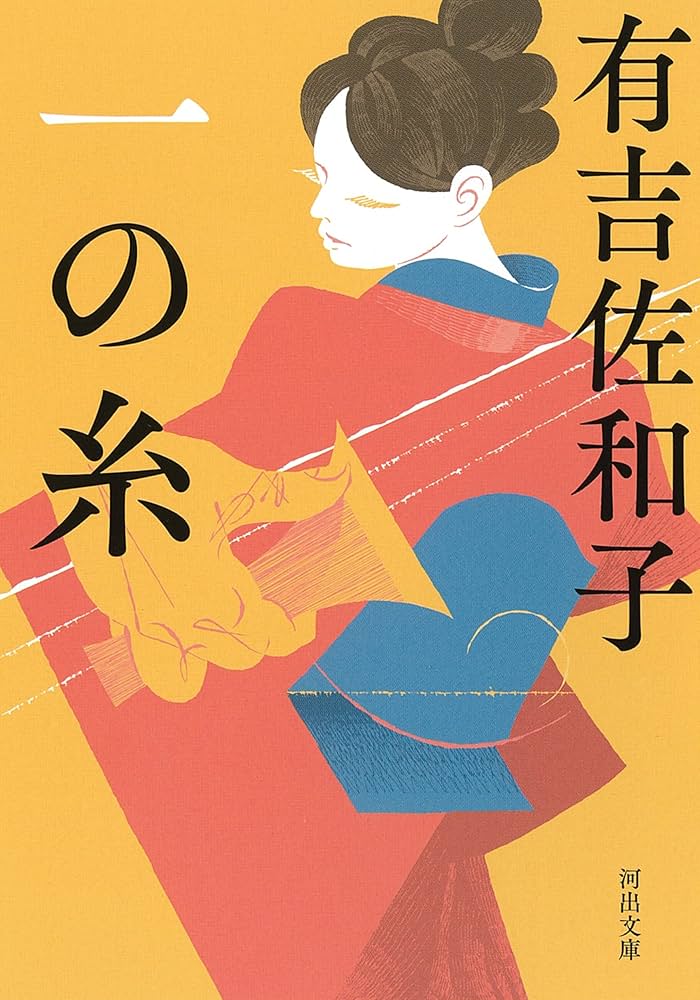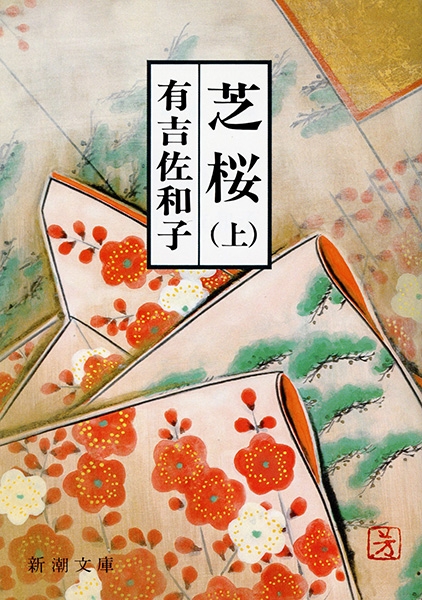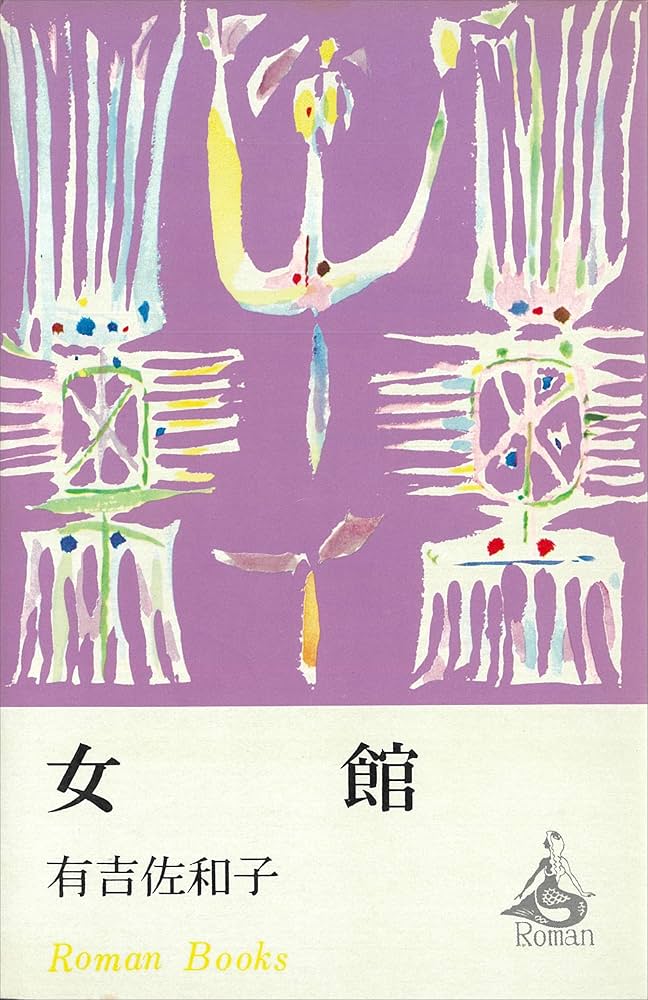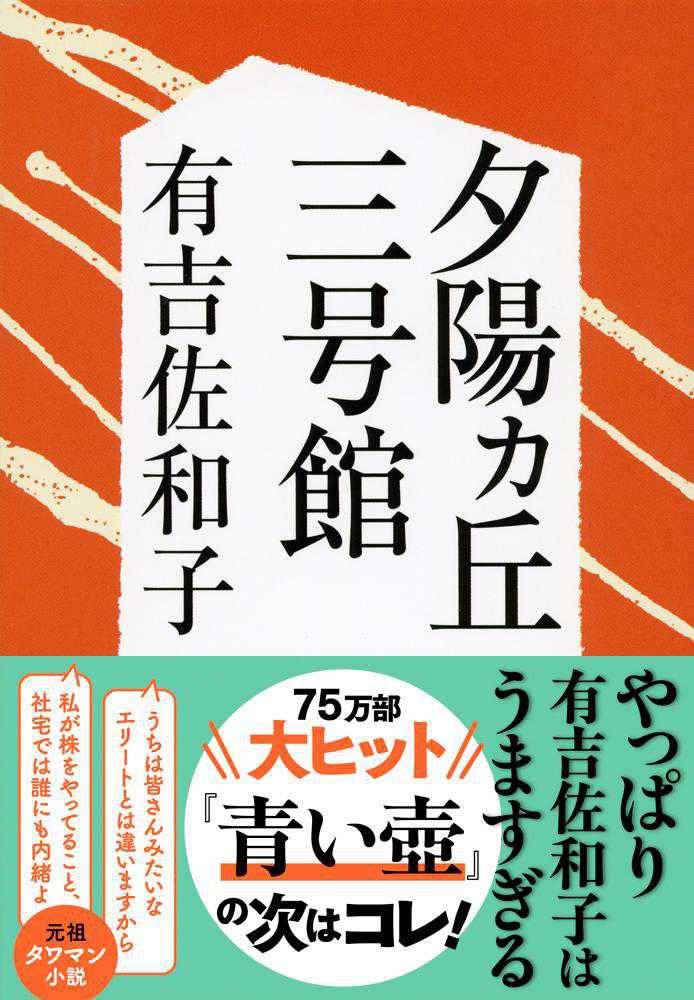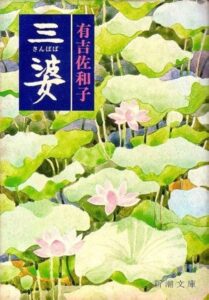 小説「三婆」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「三婆」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、単なる嫁姑の争いを描いた作品ではありません。女の意地とプライド、そして何よりも「孤独」への深い恐怖が渦巻く、壮絶な人間ドラマが繰り広げられます。昭和という時代を背景にしながらも、そのテーマは驚くほど現代的で、私たちの心に鋭く突き刺さるものがあります。
本妻、愛人、そして小姑。亡き一人の男を巡って集った三人の女性が、一つ屋根の下で繰り広げる凄まじい共同生活。最初は憎しみ合っていた彼女たちの関係は、時間と共に、そして予期せぬ出来事を経て、誰も想像しなかった形へと変化していきます。
この記事では、物語の序盤から結末までの詳細なネタバレを含みつつ、その奥深い魅力を余すところなく語っていきます。有吉佐和子という作家が描きたかったものは何だったのか。三人の「婆」たちがたどり着いた境地とは。ぜひ最後までお付き合いください。
「三婆」のあらすじ
物語は、金融会社社長・武市浩蔵が、愛人である富田駒代の家で急死するところから始まります。この知らせを受け、本妻の武市松子は、亡き夫の妹である小姑の武市タキを連れて、怒りと侮蔑を胸に愛人の家へと乗り込みます。彼女の目的はただ一つ、世間体のため、葬儀の主導権を愛人から奪い取ることでした。
松子にとって、元芸者の駒代は「かぼちゃ婆ぁ」、何を考えているかわからないタキは「電気クラゲ」と、それぞれが我慢ならない存在。壮絶な舌戦の末、松子は強引に通夜の場所を自宅へと移し、本妻としての面目を保ちます。これで厄介な二人とは縁が切れるはずでした。
ところが、浩蔵が遺したのは莫大な資産ではなく、巨額の借金だったことが判明します。資産整理の結果、松子の手元には北沢の家一軒が残るのみ。するとそこへ、家を失ったタキが「兄の家なのだから自分にも権利がある」と転がり込んできます。
さらに、新橋に小料理屋を開く準備が整うまで、という約束で駒代までもが居候を願い出る始末。こうして、互いに憎しみ合う三人の女性、通称「三婆」の、奇妙で熾烈な共同生活が幕を開けるのです。このあらすじの先には、想像を絶する展開が待っています。
「三婆」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の結末を含む完全なネタバレありの感想です。まだ作品を読んでいない方はご注意ください。この物語の本当の凄みは、その衝撃的な結末と、そこに至るまでの三人の関係性の変化にあります。
さて、一つ屋根の下に集った松子、タキ、駒代の三人。彼女たちの共同生活は、案の定、静かなものではありませんでした。家の所有者である松子は、居座りを決め込む二人を追い出すため、法的な家主としての権威を振りかざそうとします。
彼女が打った手は「家賃の請求」。タキと駒代を単なる同居人ではなく「借家人」と位置づけることで、いずれは立ち退きを迫ろうという算段です。これは、三人の関係性を、血縁や情といった曖昧なものではなく、金銭的な契約関係へと切り替えようとする、松子なりの最後通牒でした。
しかし、一筋縄ではいかないのがこの女たちです。共通の敵、つまり「家主・松子」と「家賃」という脅威を前に、昨日までの敵であったタキと駒代は、いともあっさりと手を結びます。二人は共謀して家賃の支払いを拒否。家の中は「二対一」の構図となり、松子の計画は早々に頓挫してしまいます。
このあたりの展開は、実に小気味がいいですね。敵の敵は味方、というわけです。しかし、このかりそめの同盟は、タキの強欲によってすぐに崩れ去ります。松子が空き部屋を第三者である山田夫妻に貸し出そうとすると、タキがその情報を先取りし、自分が家主だと偽って夫妻から敷金と家賃をだまし取ってしまうのです。
この裏切り行為が発覚し、さすがの駒代もタキに愛想を尽かします。タキという共通の敵ができたことで、今度は駒代が松子に接近。家の力関係は目まぐるしく変化し、三人が互いに牽制し合う「三つ巴」の泥沼の戦いへと突入していくのです。
この家に、さらなる混乱をもたらす人物が登場します。亡き浩蔵の会社の元専務で、今や娘に家を追い出されてしまった老人、瀬戸重助です。彼は行くあてがなく、かつての社長宅を頼って転がり込んできます。こうして、女三人に男一人の、四人の老人による奇妙な共同生活が完成します。
彼女たちの争いは、一見すると醜い縄張り争いにしか見えません。しかし、見方を変えれば、これこそが彼女たちにとって唯一のコミュニケーションだったのではないでしょうか。相手の出方を読み、裏をかき、時には手を結ぶ。その激しいやり取りの中に、憎しみを超えた、奇妙な「関わり」が生まれていたのです。愛情が欠落したこの家では、この否定的な関わりこそが、お互いの存在を確認し合うための、倒錯した絆となっていたように私には思えました。
物語は、若い世代の退場によって、大きな転換点を迎えます。この家には、女中のお花という若い女性がいました。彼女は出入りの八百屋の青年・辰夫と恋仲で、子供のいない松子の養女となってこの家を相続することを夢見ていました。しかし、松子にその気がないことを悟ったお花は、家を出て辰夫と結婚し、自分たちの力で生きていくことを選びます。
お花の退場は、松子に大きな衝撃を与えました。若さの象徴であったお花がいなくなった家は、まるで光が消えたかのよう。松子は、自分が憎んでいる二人の老婆と、年老いた元専務と共に、この家でただ老いていくだけだという、残酷な現実に直面させられるのです。
追い詰められた松子は、最後の手段に打って出ます。最も厄介な存在であるタキを、公的な老人ホームへ強制的に入所させようと画策するのです。福祉事務所と密かに連絡を取り、迎えの車がやってくるその日まで、タキには一切知らせませんでした。このあたりの松子の行動には、彼女の追い詰められた心情が表れていて、読んでいて胸が苦しくなります。
そして、物語はクライマックスを迎えます。何も知らされていなかったタキの元に、福祉事務所の職員が迎えに現れます。すべてを悟ったタキは、凄まじい剣幕で抵抗します。「いやだ、行きたくない!」と泣き叫び、暴れ、職員にしがみつく。その姿は、これまで松子が忌み嫌っていた「電気クラゲ」などではなく、ただ見捨てられることを恐れる、一人の弱い人間の姿でした。
このタキの剥き出しの絶望を目の当たりにした松子の心に、ある変化が起きます。敵がいなくなり、静かになった家で一人で暮らす未来。それは勝利ではなく、完全な孤独と沈黙の世界でしかありませんでした。あれほど憎かったタキの存在が、実は自分を孤独から救ってくれていたのだと、この時初めて気づいたのです。
松子は、泣き崩れました。そして、職員に懇願します。「この人を連れていかないでください」。さらに、タキに、駒代に、重助に、涙ながらに訴えるのです。「ここにいてほしい。これからもずっと、四人で一緒に暮らしてほしい」と。この劇的な場面は、この物語の核心を突いています。長年の憎しみよりも、絶対的な孤独への恐怖が勝った瞬間でした。
そして、物語は終幕へ。十年という歳月が流れます。かつての女中お花が、夫の辰夫と子供を連れて、懐かしい北沢の家を訪れます。そこで彼女が目にしたのは、信じがたい光景でした。
松子、駒代、タキ、そして重助の四人は、今もなお、共に暮らしていました。しかし、その姿は十年前とは全く違いました。四人ともが「桃惚の人」、つまり、もうろくしてしまっていたのです。かつての鋭い個性や激しい憎悪はどこへやら、彼らは互いの名前もおぼつかない様子で、ただ静かに、穏やかにそこにいました。
あれほど熾烈を極めた戦いは、老いという抗いがたい力によって、静かに終焉を迎えていたのです。憎しみも、意地も、策略も、すべては時間の中に溶け去り、そこには奇妙な「調和」だけが残されていました。この結末には、一種の安らぎすら感じられますが、同時に背筋が凍るような恐ろしさも感じずにはいられません。
お花たちが呆然と立ち尽くす中、家の外を一台の選挙カーが通り過ぎます。そして、拡声器が「老人福祉問題の解決」を声高に叫ぶ声が響き渡るのです。この最後の場面が、有吉佐和子の真骨頂でしょう。家の中では、社会からこぼれ落ちた老人たちが、互いを支え合う(というより、共倒れする)ことで、奇妙な共同体を形成し、かろうじて生き永らえている。その一方で、家の外では、政治家が空虚なスローガンを叫んでいる。この皮肉な対比に、作者の鋭い社会批評の視線を感じます。
この物語は、高齢化社会が深刻化するずっと以前に書かれました。しかし、描かれている問題は、驚くほど現代の日本と重なります。家族の形骸化、老老介護、孤独死。そうした問題を、有吉佐和子は半世紀以上も前に見抜き、この恐ろしくも滑稽な物語として描き出したのです。これは、三人の老婆の特殊な物語ではありません。私たちの未来を予見した、普遍的な物語なのです。
まとめ
有吉佐和子の「三婆」は、一人の男を巡る三人の女性の壮絶な同居生活を描いた物語です。本妻、愛人、小姑という、決して相容れないはずの三人が、憎しみ合い、いがみ合いながらも、奇妙な共同体を形成していく様子が描かれます。
物語の結末には、衝撃的なネタバレが待っています。長年の憎悪の果てに彼女たちがたどり着いた境地は、私たちの想像を遥かに超えるものでした。それは、人間の「老い」と「孤独」という根源的なテーマを、強烈に突きつけてきます。
本作は、単なるエンターテインメント作品にとどまりません。家族とは何か、共生とは何か、そして人間が生きることの滑稽さと哀しさとは何か。そうした深い問いを投げかける、力強い社会批評の側面も持っています。
昭和の時代に書かれたとは思えないほど、現代に通じるテーマ性に満ちた一冊です。まだ読んだことがない方は、ぜひ手に取ってみてください。きっと、忘れられない読書体験になるはずです。