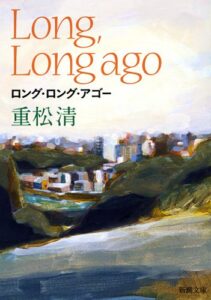 小説「ロング・ロング・アゴー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「ロング・ロング・アゴー」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
重松清さんの作品には、どこか懐かしくて、胸の奥がきゅっとなるような物語が多いように感じます。この「ロング・ロング・アゴー」も、まさにそんな一冊でした。
本書は六つの短編からなる物語集です。それぞれの物語は独立しているようでいて、どこか響き合い、「再会」という一つの大きな流れを形作っています。子供の頃に出会った人々、忘れられない出来事、そして大人になった今、ふとその頃を思い出す瞬間。そんな、誰の心にもあるであろうノスタルジーと、ちょっぴりほろ苦い現実が描かれています。
時が経てば、人も町も変わっていきます。かつてキラキラして見えたものが色褪せたり、逆に、当時は気づかなかった大切なものが見えてきたり。この物語を読むと、自分の子供時代や、かつて出会った人たちのことを、ふと思い出してしまうかもしれません。切なくて、でも温かい。そんな気持ちにさせてくれる作品です。どうぞ、物語の世界にゆっくりと浸ってみてください。
小説「ロング・ロング・アゴー」のあらすじ
「ロング・ロング・アゴー」は、六つの短編で構成されています。それぞれの物語は、子供時代のある出来事や出会いと、大人になってからの「再会」を軸に展開していきます。
第一話「いいものあげる」では、父親の転勤で地方の町に引っ越してきた少女、中村さんが主人公です。彼女は、地元の老舗デパート「ちどりや」の娘である美智子ちゃんと、そのお菓子屋の娘スズちゃんと出会います。しかし、父親が関わる新しいショッピングモールの開店により、町の力関係は変化し、それは子供たちの世界にも影響を及ぼしていきます。
第二話「ホラ吹きおじさん」は、主人公ヒロシの叔父さんのお話。親戚からは厄介者扱いされているけれど、ヒロシにとってはどこか特別な存在だった叔父さん。大人になったヒロシが、今は亡き父親と叔父さんの姿を重ね合わせながら、子供の頃の記憶を辿ります。
第三話「永遠」は、小学校教師である姉の視点から、自閉症スペクトラムの傾向がある弟ユウちゃんとの日々が描かれます。子供の頃、近所の年下の子どもたちと無邪気に遊んでいたユウちゃん。しかし子供たちは成長と共にユウちゃんから離れていきます。そんな中、ユウちゃんの結婚が決まり、姉はかつてユウちゃんと仲の良かった少年シノケンを探し出すことになります。
第四話「チャーリー」では、息子が読んでいた「ピーナッツ」をきっかけに、父親が自身の小学生時代を回想します。勉強も運動も苦手で、どこかチャーリー・ブラウンに似ていた自分。学級委員に立候補したものの、空回りばかりしていたあの頃の記憶と、担任だった生駒先生への複雑な思いが語られます。
第五話「人生はブラの上を」は、ユミちゃんが、少し風変わりで、いつも笑顔を絶やさない幼なじみのムウちゃんを思い出す物語です。家庭の事情に翻弄されながらも、前向きに生きてきたムウちゃん。大人になったユミちゃんは、ムウちゃんとの過去を振り返りながら、彼女の人生に思いを馳せます。
最終話「再会」は、「いいものあげる」の後日談。大人になった瀬尾くんが、仕事で故郷の町を訪れます。かつて中村さんや美智子ちゃんと過ごした町は様変わりし、栄枯盛衰の現実を目の当たりにします。そして、彼は美智子ちゃんのその後を知ることになるのです。
小説「ロング・ロング・アゴー」の長文感想(ネタバレあり)
重松清さんの「ロング・ロング・アゴー」、読み終えた後、しばらくの間、物語の余韻から抜け出せませんでした。六つの短編、それぞれが独立した物語でありながら、「時間」「記憶」「再会」という糸で緩やかに結ばれていて、読み進めるうちに、まるで自分の過去のアルバムをめくっているような、不思議な感覚に包まれました。ネタバレを含みますが、それぞれの物語について感じたことを、少し詳しく書いてみたいと思います。
まず、「いいものあげる」。この話は、子供の世界の残酷さと、その中で見せる一瞬の強さが印象的でした。主人公の中村さんは、東京から転校してきた「よそ者」。彼女の視点を通して、地方の小さな町にある既存のコミュニティと、新しいものの流入によって起こる変化が描かれます。老舗デパート「ちどりや」の娘・美智子ちゃんは、最初はいわゆる「女王様」的な存在。取り巻きのスズちゃんは、分かりやすく彼女に媚びへつらっています。中村さんは、そんな二人を少し冷めた目で見ていますよね。でも、父親が関わる新しいショッピングモール「シンフォニー」が成功するにつれて、「ちどりや」は衰退し、美智子ちゃんの立場は揺らぎ始めます。大人の世界の力関係が、そのまま子供の世界に反映される様子は、読んでいて胸が痛みました。特に、あれだけ美智子ちゃんに従っていたスズちゃんが、手のひらを返したように無視する場面。子供だからこその無邪気な残酷さが、リアルに伝わってきます。中村さんは、自分には直接関係ないはずなのに、言いようのない罪悪感のようなものを感じてしまいます。その感情の輪郭がはっきりしないところが、また子供らしいというか、読んでいて苦しくなりました。でも、そんな状況の中で、美智子ちゃんが見せる態度は、驚くほど毅然としています。特に、学校の下駄箱で中村さんに「いいものあげる」と、あるものを差し出すシーン。それは決して物質的な豊かさからくるものではなく、彼女の心の奥底にある、けなげで、そして強い意志の表れのように感じました。転校していく最後に、瀬尾くんが声をかける場面も、わずかな希望を感じさせてくれて、読後感は意外にも爽やかでした。子供時代の、どうしようもない理不尽さの中で揺れ動く感情が、見事に描かれていると感じました。
次に「ホラ吹きおじさん」。これは、大人になるということ、そして家族というものの複雑さを考えさせられる話でした。ヒロシにとって、叔父さんは「ホラ吹き」で、親戚中からは問題児扱い。お金にだらしなく、迷惑ばかりかけている。客観的に見れば、確かに「どうしようもない大人」なのかもしれません。でも、子供の頃のヒロシにとっては、どこかワクワクさせてくれる、特別な存在だったんですよね。父親は真面目で立派な人だけれど、叔父さんのように型破りな魅力はなかった。その対比が鮮やかです。大人になったヒロシが、亡くなった父親の意外な一面を知り、そして、あのどうしようもなかったはずの叔父さんとの間に、ある種の共通点を見出す場面が心に残りました。「立派な大人」と「ダメな大人」、その境界線は、実は私たちが思っているよりも曖昧なのかもしれない。そして、子供の頃には理解できなかった大人の弱さや孤独が、自分が大人になったからこそ、少しだけ分かるようになる。叔父さんの「ホラ」も、もしかしたら、現実の厳しさから自分を守るための鎧だったのかもしれない、なんて考えてしまいました。ヒロシが叔父さんに対して抱いていた「特別」な感情が、時を経ても色褪せないところに、血の繋がりの不思議さや、子供時代の記憶の強さを感じます。
「永遠」は、この短編集の中でも特に涙を誘われた物語です。自閉症スペクトラムの弟を持つ姉の視点。この設定だけでもう、切なさが込み上げてきます。ユウちゃんは、純粋で優しい心を持っているけれど、コミュニケーションの取り方や興味の対象が、周りの子とは少し違う。小さい頃は、近所の年下の子たちが一緒に遊んでくれるけれど、彼らが成長するにつれて、ユウちゃんの世界から「卒業」していってしまう。その様子が、姉の回想を通して淡々と、でも克明に描かれていて、胸が締め付けられました。私たちは、知らず知らずのうちに「離れていく」側になることが多いけれど、「離れていかれる」側の寂しさや、変わらずにそこに居続けることの切なさに、この物語を通して初めて深く思いを馳せた気がします。ユウちゃんの結婚が決まり、姉は、かつてユウちゃんが大好きだったシノケンに、結婚式への出席をお願いしようと奔走します。もう何年も会っていない、中学生になり、受験勉強で忙しいであろうシノケン。連絡を取るのも気が引けるし、彼がユウちゃんのことを覚えているかも分からない。姉の葛藤も、連絡を受けたシノケンの戸惑いも、すごくよく分かります。だからこそ、最後の場面、シノケンが結婚式に駆けつけてくれた時、ユウちゃんが見せた涙と、それを見守る姉の心中を思うと、もう涙が止まりませんでした。ベタかもしれないけれど、こういう優しさや繋がりが、やっぱり人の心を打つのだと思います。また、姉が勤める小学校での、中学受験を巡る子供たちの対立と和解のエピソードも、物語に温かい彩りを添えていました。
「チャーリー」は、自分自身の子供時代を重ね合わせて、読んでいて少し苦しくなった話です。「ピーナッツ」のチャーリー・ブラウン。彼は決してヒーローじゃない。むしろ、ちょっと不器用で、うまくいかないことの方が多い男の子。主人公の父親は、子供の頃の自分が、まさにそんなチャーリー・ブラウンのようだったと回想します。勉強も運動も、何をやっても中途半端。特別な才能なんてない。自分が「凡庸」であることに気づいてしまった瞬間の、あの何とも言えない感覚。誰にでも、多かれ少なかれ、そういう経験があるのではないでしょうか。世界が急に色褪せて見えたり、自分には見えない壁があるように感じたり。あの子供時代特有の、万能感の喪失と、現実への直面。そのもどかしさや痛みが、ひしひしと伝わってきました。学級委員に立候補してみるものの、やっぱり空回りしてしまう。周りの目も気になる。そんな、もがけばもがくほど泥沼にはまっていくような感覚、すごく身に覚えがあります。そんな父親が、まだ無垢な息子に対して向ける眼差しは、どこか達観していて、でも温かい。自分と同じような痛みを感じる時が来るかもしれないけれど、今はまだそのままでいいんだよ、と語りかけているようです。ただ、担任だった生駒先生の存在は、少し謎めいていました。熱血教師だった過去と、主人公に対してどこか冷めているように見えた現在の姿。そのギャップに込められた意味は、私の人生経験ではまだ完全には理解しきれないのかもしれません。でも、それも含めて、人生の複雑さを感じさせる物語でした。
「人生はブラの上を」は、タイトルからは想像もつかないような、切なくて、でも力強い物語でした。主人公ユミちゃんの幼なじみ、ムウちゃん。彼女は、周りから見れば少し「変わっている」女の子。おっとりしていて、どこか抜けているように見えるけれど、どんな時も笑顔を絶やさない。でも、その笑顔の裏で、彼女はたくさんの困難を抱えていました。父親の事業失敗と死、母親が頼りない男性と一緒になってしまうこと。家庭の事情に翻弄され、苦労が絶えないはずなのに、ムウちゃんはいつも飄々としているように見える。その姿が、読んでいて本当に切なかったです。ビートルズの「オブ・ラ・ディ・オブ・ラ・ダ」が、物語の中で重要なモチーフとして使われています。「Life goes on, bra」という歌詞(実際はLa la la, how the life goes on ですが、ムウちゃんの聞き間違い)が、彼女の生き方を象徴しているようで、胸に迫りました。どんなに辛いことがあっても、人生は続いていく。その現実を、彼女は無意識のうちに受け入れて、ただ前を向いていたのかもしれません。そして、ユミちゃんもまた、ムウちゃんの存在に救われていたことに、大人になってから気づきます。互いに支え合い、影響し合っていた二人の関係。ユミちゃんのお母さんが、ムウちゃんに対して向けるさりげない優しさも、涙を誘いました。ムウちゃんが最後には幸せを掴んでいることが分かり、本当に良かったと思える、読後感の良い物語でした。不器用ながらも懸命に生きる人の姿に、心を揺さぶられました。
そして最後の「再会」。これは第一話「いいものあげる」の直接的な続編であり、この短編集全体を締めくくるにふさわしい物語でした。大人になった瀬尾くんが、仕事で久しぶりに故郷の町を訪れます。かつて「ちどりや」を駆逐した「シンフォニー」も、今では新しい巨大ショッピングモール「ガーデン」にその座を脅かされている。町の風景も、人の営みも、絶えず変化していく。その諸行無常観が、瀬尾くんの心に重くのしかかります。彼自身も、仕事で思うような成果を出せず、どこか満たされない気持ちを抱えている。そんな彼の哀愁や、故郷に対する郷愁の念が、非常に濃密に描かれていて、読んでいるこちらも引き込まれました。そして、彼が知る、美智子ちゃんのその後。彼女が若くして亡くなっていたという事実は、衝撃的でした。「いいものあげる」で見せたあの強さ、気高さを持っていた彼女が、こんなにも早く…。時間の流れの残酷さと、人生の儚さを突きつけられたような気がします。それでも、瀬尾くんが仕事を通して少しだけ成長を見せるラストは、かすかな光を感じさせてくれます。過去は変えられないけれど、現在と未来に向かって歩いていくしかない。そんなメッセージが込められているように思えました。
「ロング・ロング・アゴー」は、人の記憶の曖昧さと確かさ、時間の経過がもたらす変化と不変、そして人生における「再会」の意味を深く問いかけてくる作品でした。再会は、必ずしもハッピーエンドをもたらすわけではありません。時には、知りたくなかった現実を知ることもあるし、過去の輝きが失われていることに気づかされることもある。それでも、私たちは過去を振り返り、誰かを思い出し、そしてまた前を向いて生きていく。そんな人生の普遍的な営みを、重松清さんは、登場人物たちのささやかな日常を通して、丁寧に、そして温かく描き出していると感じました。読んでいる間、自分の子供の頃の友達や、疎遠になってしまった人のことを、たくさん思い出しました。彼らは今、どうしているんだろう。もし再会したら、どんな話をするんだろう。そんなことを考えさせてくれる、深く心に残る一冊でした。
まとめ
重松清さんの「ロング・ロング・アゴー」は、「再会」をテーマにした六つの物語が収められた短編集です。子供の頃の忘れられない記憶や出会いが、大人になった主人公たちの現在と交錯し、読む人の心の琴線に触れる作品となっています。
それぞれの物語は、地方の町の変化と子供たちの世界の残酷さを描いた「いいものあげる」、ダメな叔父さんとの特別な絆を描く「ホラ吹きおじさん」、障害を持つ弟とその姉、そして周囲の人々との繋がりを描いた「永遠」、凡庸な自分に気づいた少年時代の痛みを回想する「チャーリー」、不器用ながらも笑顔で生きる幼なじみの姿を描く「人生はブラの上を」、そして過去との再会と時の流れの切なさを描く「再会」と、どれも個性的でありながら、どこか通底する切なさや温かさを持っています。
登場人物たちが経験する出来事や感情は、決して特別なものではなく、誰もが心のどこかで感じたことのあるような普遍的なものばかりです。だからこそ、読者は物語に深く共感し、自身の過去や人間関係に思いを馳せることになるでしょう。時間の経過による変化の寂しさや、それでも変わらないものの尊さ、そして人生のほろ苦さとささやかな希望が、心に深く染み渡ります。
読後には、懐かしさと共に、今を生きること、そしてこれから出会うであろう未来について、静かに考えさせられるような余韻が残ります。切ないけれど、どこか心が温かくなるような読書体験を求めている方に、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。
































































