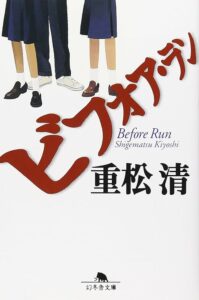 小説「ビフォア・ラン」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。重松清さんのデビュー作として知られるこの物語は、読む人の心に、どこか懐かしく、そして少しばかりほろ苦い感情を呼び起こすかもしれません。
小説「ビフォア・ラン」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。重松清さんのデビュー作として知られるこの物語は、読む人の心に、どこか懐かしく、そして少しばかりほろ苦い感情を呼び起こすかもしれません。
舞台は1980年代の瀬戸内海に面した地方の高校。主人公は、陸上部に所属する高校三年生の永沢優(マサル)。彼は、どこにでもいるような平凡な自分に物足りなさを感じています。「今の自分に足りないものはこれだ」――そう思い込んだ彼と友人たちは、授業で知った「トラウマ」という言葉に妙に惹かれ、なんと「トラウマづくり」を計画します。
その計画とは、休学中の同級生・久保田まゆみが死んだことにして、彼女の墓を作るという、今思えばなんとも突拍子もないものでした。しかし、その計画は思わぬ方向へと転がり始めます。死んだことにしたはずのまゆみが、ある日突然、優の前に現れるのです。しかも、まゆみは奇妙な記憶を語り、優に対して恋人であるかのように振る舞い始めます。
この出来事をきっかけに、優たちの平凡だったはずの日常は、幻想と現実が入り混じった、少し奇妙で、そして切ない青春の日々へと変わっていきます。「かっこ悪い青春」と称されるこの物語は、重松清さんの原点とも言える作品であり、その後の作品にも通じるテーマの萌芽が感じられます。この記事では、そんな「ビフォア・ラン」の世界を、物語の詳しい流れから、個人的な深い思い入れまで、たっぷりと語っていきたいと思います。
小説「ビフォア・ラン」のあらすじ
物語の舞台は、瀬戸内海に面したとある地方都市の高校です。主人公は高校三年生の永沢優。彼は陸上部に所属する長距離ランナーですが、特に目立った成績を残しているわけでもなく、受験生としても平凡な日々を送っていました。彼には、同じくどこか満たされない日常を送る友人、橋本(ハシ)と田口(タグチ)がいます。
1980年、高校二年の秋。彼らは授業で「トラウマ」という言葉を知ります。その言葉の響きに妙に心を奪われた優たちは、「自分たちには決定的な何かが足りない、それはトラウマではないか」と考え、大胆にも「トラウマづくり」を実行に移すことを決意します。平凡な日常からの脱却を夢見ていたのかもしれません。
彼らがターゲットに選んだのは、ノイローゼで高校を休学していた同級生の久保田まゆみでした。優たちは、まゆみが死んだという嘘の設定を作り上げ、学校近くの山中に彼女の偽の墓を建てます。墓石には「久保田まゆみ ここに眠る」と刻み、これで自分たちにも深い心の傷、すなわちトラウマが刻まれるはずだと考えたのです。なんとも浅はかで、それでいて切実な行動でした。
しかし、事態は予想外の展開を迎えます。ある日、死んだことにしたはずのまゆみが、突然学校に現れたのです。しかも、まゆみは優たちの前に立ち、「あなたたちが、私のために墓を作ってくれたんでしょう?」と言い放ちます。彼女は、優たちが作り上げた偽りの記憶を、まるで本当にあったことのように語り始め、さらには優のことを「恋人」だと宣言する始末。
まゆみの出現により、優、ハシ、タグチ、そして優の幼なじみである紀子の日常は一変します。まゆみは優たちにつきまとい、奇妙な言動を繰り返します。受験勉強に集中すべき時期なのに、彼らはまゆみに振り回され、教室よりも屋上に集まる時間が増えていきます。優たちは、自分たちが作り出したはずの幻想に、逆に飲み込まれていくような感覚に陥ります。
物語は、優やまゆみ、友人たちの内面的な葛藤や成長、そして彼らが直面する現実と、自ら作り出した幻想との間で揺れ動く姿を描いていきます。まゆみの真意は?優たちの「トラウマづくり」の結末は?そして、彼らの「かっこ悪い青春」はどこへ向かうのか。重松清さんのデビュー作は、そんな甘酸っぱくもほろ苦い青春の一コマを、独特の筆致で描き出しています。
小説「ビフォア・ラン」の長文感想(ネタバレあり)
重松清さんの作品には、いつも心を掴まれてしまいます。特に、初期の作品には、荒削りながらも瑞々しい感性が溢れていて、読むたびに新鮮な気持ちになります。その中でも、デビュー作である「ビフォア・ラン」は、私にとって特別な一冊です。初めて読んだ時の衝撃と、どこか共感してしまうような切なさは、今でも忘れられません。
物語の始まりは、高校二年生の主人公・優が「トラウマ」という言葉に出会うところから。平凡な自分を変えたい、何か特別な経験をしたいという、思春期特有の焦りや願望が、彼を「トラウマづくり」という奇妙な計画へと駆り立てます。この発想自体が、なんとも若々しく、そして危うげですよね。まだ死んでもいない同級生の墓を作るなんて、不謹慎極まりないけれど、その裏にある「何か者かになりたい」という切実な思いには、少しだけ頷いてしまう部分もありました。
計画の対象となった久保田まゆみの存在が、この物語の鍵を握っています。彼女は、優たちが作り出した「死んだはずの同級生」という役割を、まるで自ら引き受けるかのように現れます。そして、優たちが作り上げた嘘の記憶を語り、優を「恋人」と呼ぶ。この展開には、読んでいて本当にドキドキさせられました。まゆみは一体何者なのか?彼女は本当に優たちの計画を知っていたのか?それとも、彼女自身もまた、何かから逃れるために幻想の世界を必要としていたのか?
まゆみの言動は、優たちの日常をかき乱します。受験勉強に身が入らず、屋上で過ごす時間が増える優たち。彼らの姿は、どこか頼りなく、滑稽でさえあります。でも、その「かっこ悪さ」こそが、この作品の大きな魅力だと感じます。誰もが経験するわけではないけれど、青春時代特有の、理由のない焦燥感や、現実から少しだけ浮遊しているような感覚。そういったものが、優たちの行動を通してリアルに伝わってくるのです。
重松清さんの文章は、この頃からすでに独特の温かみと、人の心の機微を捉える繊細さを持っていました。優の内面の葛藤、友人たちとの微妙な関係性、そしてまゆみに対する戸惑いや、かすかな惹かれる気持ち。それらが、実に丁寧に描かれています。特に、瀬戸内海に面した地方の町の描写は、物語全体の雰囲気を決定づけているように思います。どこか閉塞感がありながらも、穏やかで、少し物悲しい風景が、優たちの心情と重なり合って、物語に深みを与えています。
作中には、様々な「対」の構造が見られます。受験勉強に没頭するクラスメートと、屋上に集う優たち。現実と幻想。生と死。尊敬される存在と、厄介者扱いされる存在。これらの対比が、物語のテーマをより際立たせています。優たちは、この「対」の世界の中で、自分たちの立ち位置を探し、悩み、少しずつ成長していくのです。
特に印象的なのは、優とまゆみの関係です。優が作り出した幻想の存在であるはずのまゆみが、逆に優の現実を揺さぶる。まゆみが語る「あらぬ記憶」は、優にとって都合の良い幻想だったのかもしれませんが、同時にそれは、彼が向き合わなければならない現実の一部でもありました。この幻想と現実の交錯が、物語を単なる青春小説に留まらない、不思議な魅力を持つものにしています。
重松清さんは、文庫版のあとがきで「赤面や冷汗の箇所は書きあらためたが、苦笑いの箇所は、あえて残した」と記しています。この言葉通り、「ビフォア・ラン」には、若さゆえの過ちや、今から思えば少し恥ずかしくなるような青臭さが、そのままの形で残されています。でも、それが決して欠点ではなく、むしろこの作品を輝かせている要素だと感じます。完璧ではない、どこかぎこちない青春の姿だからこそ、私たちの心に響くのではないでしょうか。
読み返してみると、後の重松作品に繋がるテーマの萌芽も感じられます。例えば、家族との関係。優は、無口な父親や優しいけれどどこか距離を感じる母親との関係に、漠然とした不満を抱えています。これは、後の作品でより深く描かれる家族というテーマの原点とも言えるかもしれません。また、喪失感や、それと向き合うことの難しさといった要素も、形は違えど通底しているように感じます。
「ビフォア・ラン」は、決して派手な物語ではありません。劇的な事件が次々と起こるわけでもない。けれど、高校生たちの日常と非日常が入り混じる中で描かれる、心の揺らぎや成長の過程は、読む人の心に静かに、しかし深く染み込んできます。読み終わった後には、自分の青春時代を思い出し、少しだけ切ない気持ちになるかもしれません。
私自身、この作品に出会ったのは、重松さんの他の作品をいくつか読んだ後でした。だからこそ、デビュー作ならではの熱量や、後の洗練された作風とはまた違う、荒削りな魅力に強く惹かれたのかもしれません。古本屋で初版本を見つけた時の喜びは、今でもよく覚えています。単行本と文庫本で、タイトルの表記や細かな言い回しが違うことにも、作者のこだわりを感じました。
「かっこ悪い青春」を描ききった、と紹介されるこの作品。でも、そのかっこ悪さの中には、誰もが心のどこかに持っているであろう、純粋さや切実さが詰まっていると思います。もし、重松清さんの作品が好きで、まだこのデビュー作を読んだことがない方がいらっしゃれば、ぜひ手に取ってみてほしいです。きっと、あなたの心にも、何か響くものがあるはずです。
この物語の結末について、深くは語りませんが、優たちが作り出した「トラウマ」が、彼らにとってどのような意味を持つようになったのか。そして、まゆみとの関係はどうなったのか。それは、ぜひご自身の目で確かめてみてください。読み終えた時、きっと優たちの不器用な青春が、愛おしく感じられることでしょう。
まとめ
重松清さんのデビュー作「ビフォア・ラン」は、1980年代の地方の高校を舞台にした、少し風変わりで、心に残る青春物語です。平凡な日々に物足りなさを感じていた主人公の優たちが、「トラウマづくり」と称して、まだ生きている同級生の墓を作るという突飛な計画から物語は始まります。
この計画がきっかけとなり、死んだことにしたはずの同級生・まゆみが現れ、優たちの日常は大きく揺らぎ始めます。まゆみが語る奇妙な記憶や言動に振り回されながら、優たちは幻想と現実の狭間で悩み、戸惑い、そして自分たちなりの成長を遂げていきます。受験という現実と、自分たちが作り出した非現実的な状況が交錯する日々は、読んでいてハラハラさせられます。
この物語の魅力は、なんといってもその「かっこ悪さ」にあります。優たちの行動は浅はかで、時に滑稽にさえ見えますが、その根底にある思春期特有の焦りや、何か者かになりたいという切実な願いには、どこか共感せずにはいられません。重松清さんならではの繊細な心理描写と、どこか懐かしい地方都市の風景描写が、物語に深みと温かみを与えています。
後の作品にも通じるテーマの萌芽が見られる点も興味深いです。「ビフォア・ラン」は、重松清さんの原点を知る上で欠かせない一冊と言えるでしょう。荒削りながらも瑞々しい感性と、青春の痛みや輝きが詰まったこの物語は、読後、きっとあなたの心に、甘酸っぱくもほろ苦い余韻を残してくれるはずです。
































































