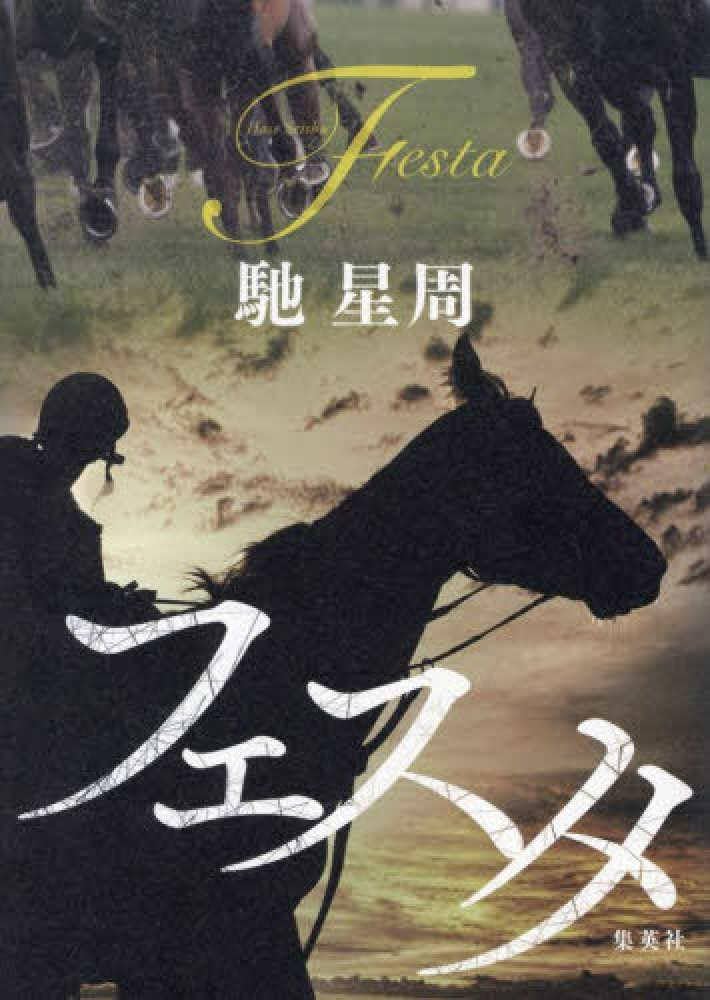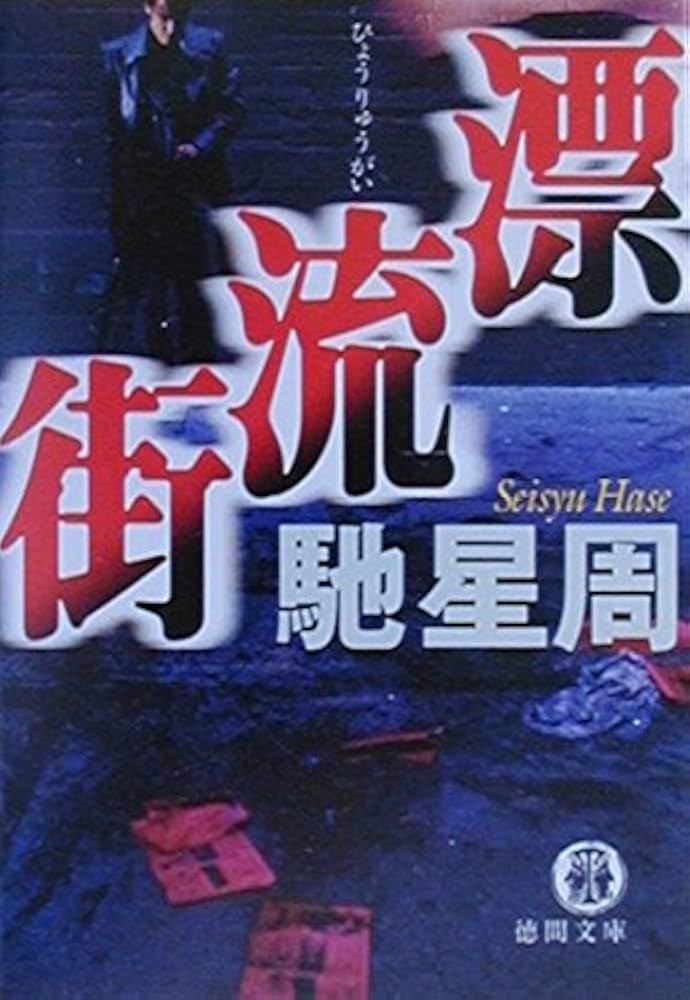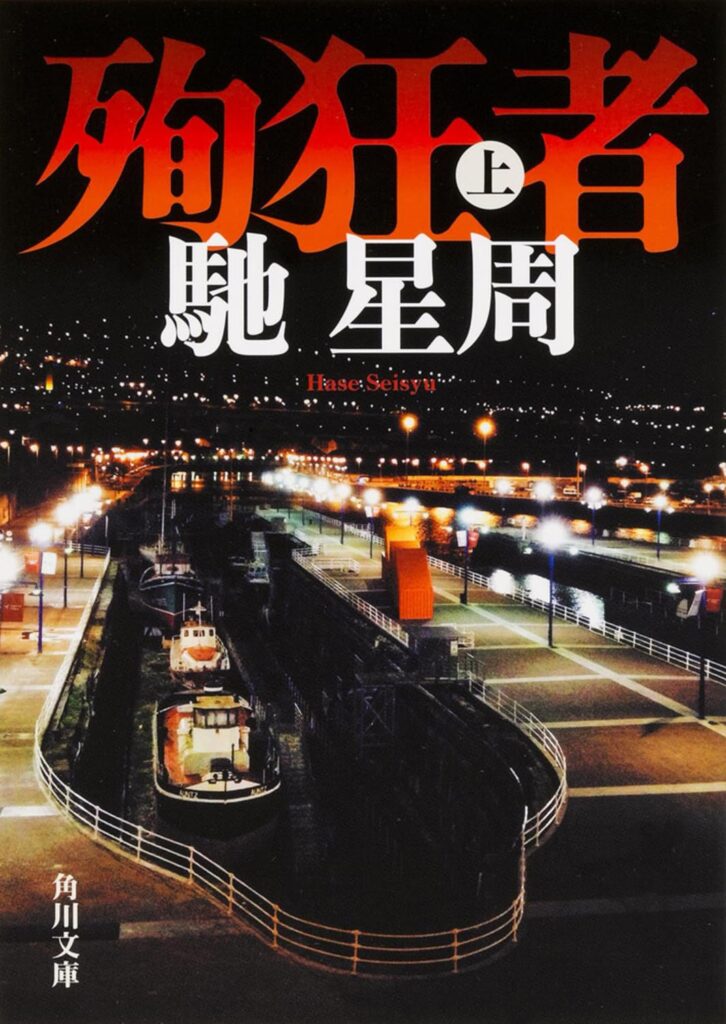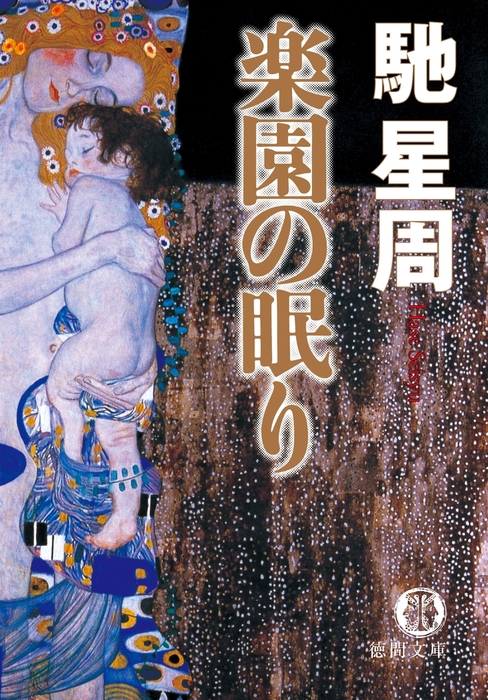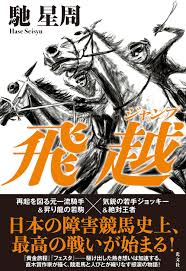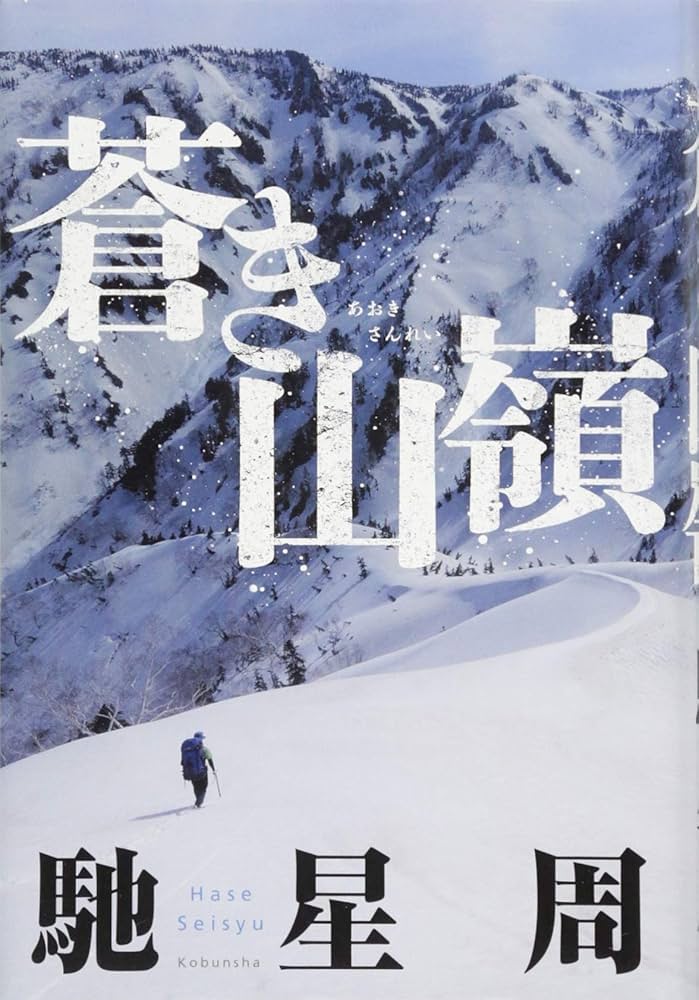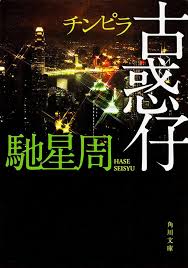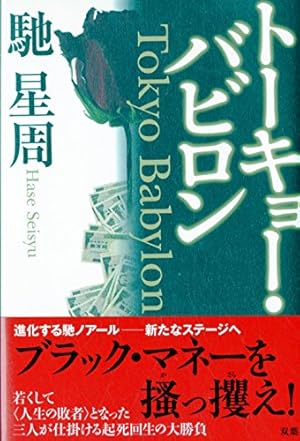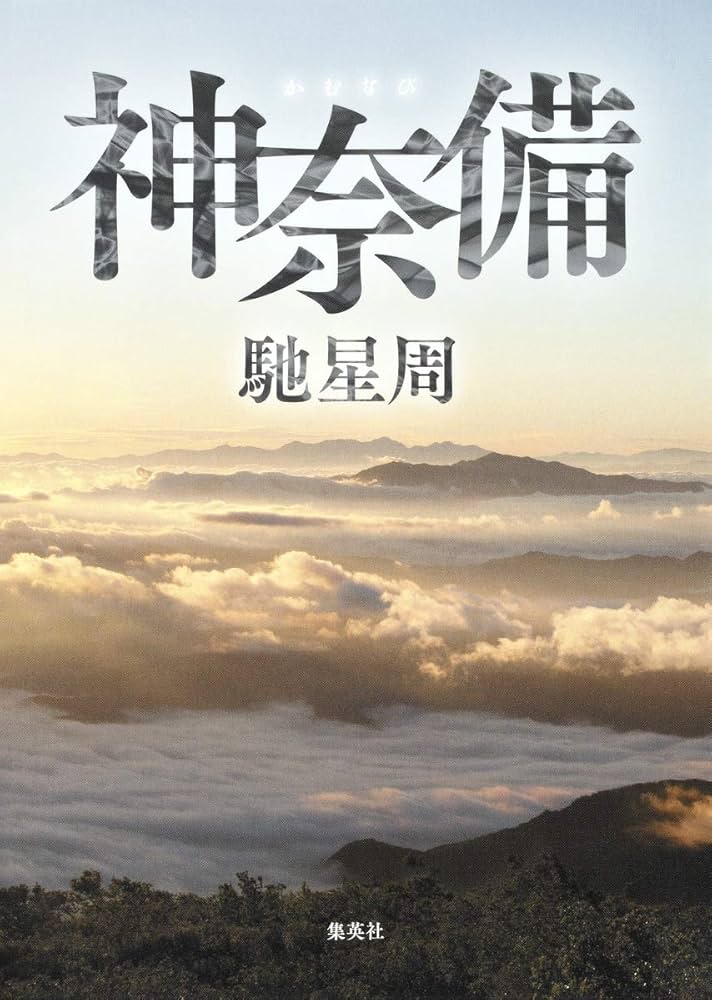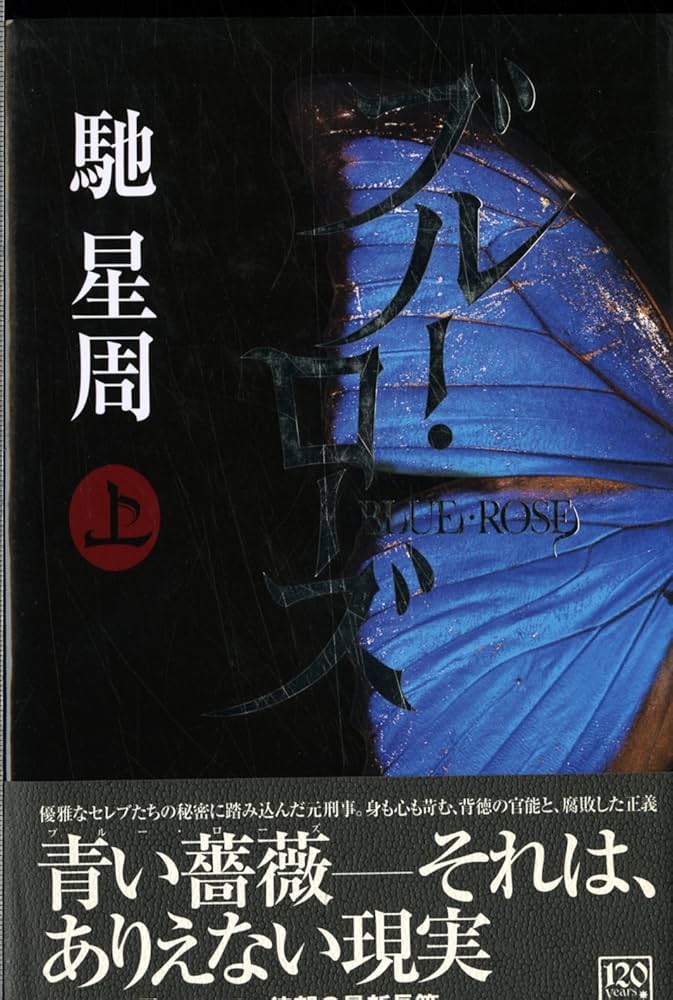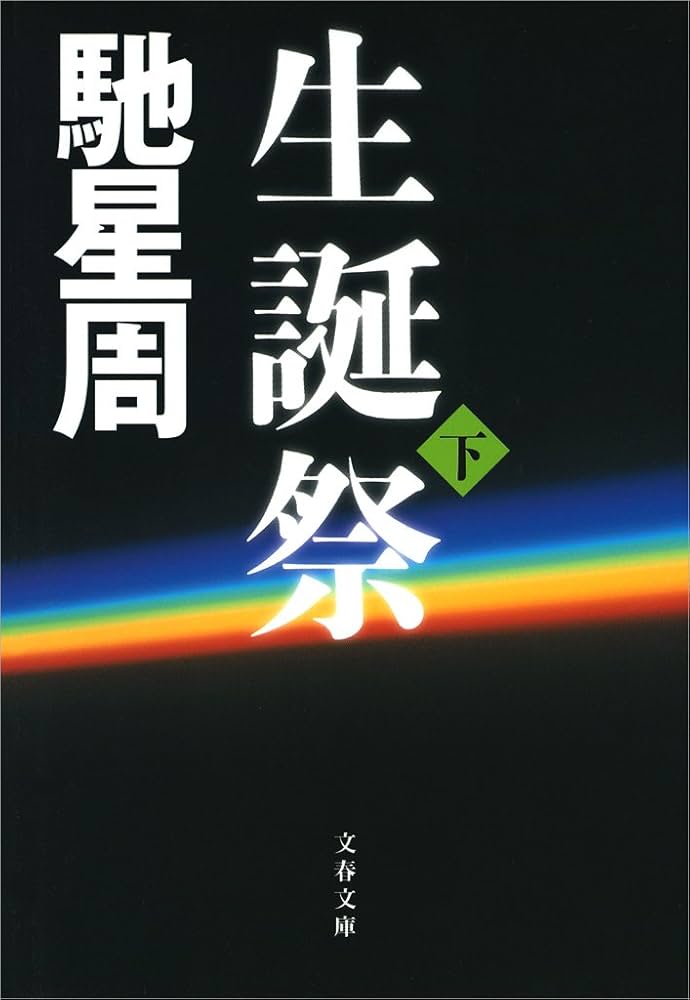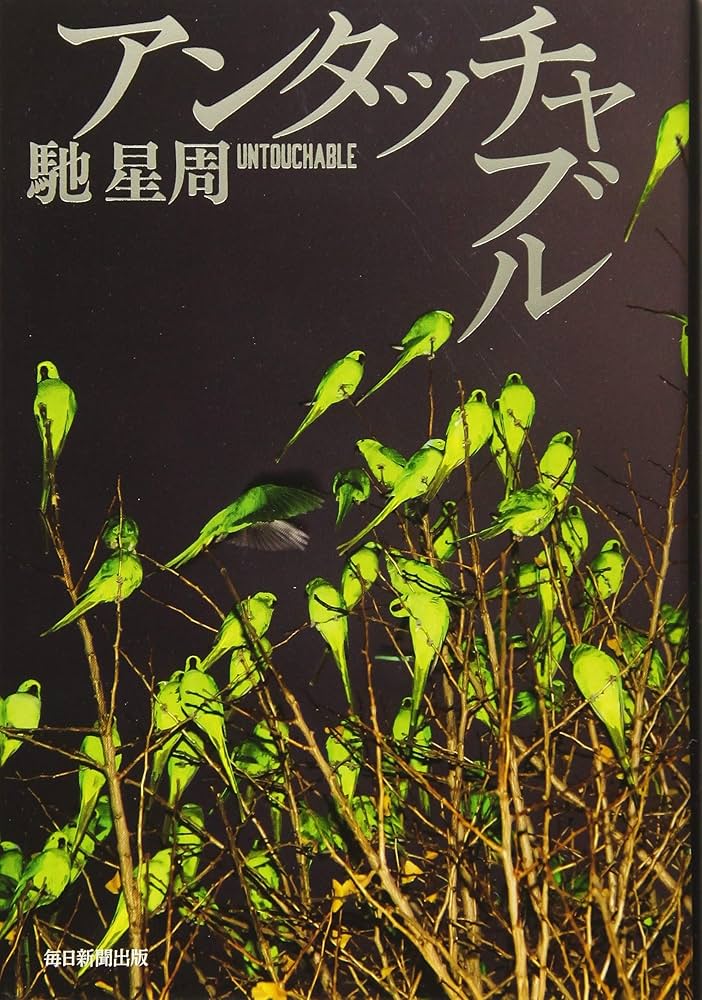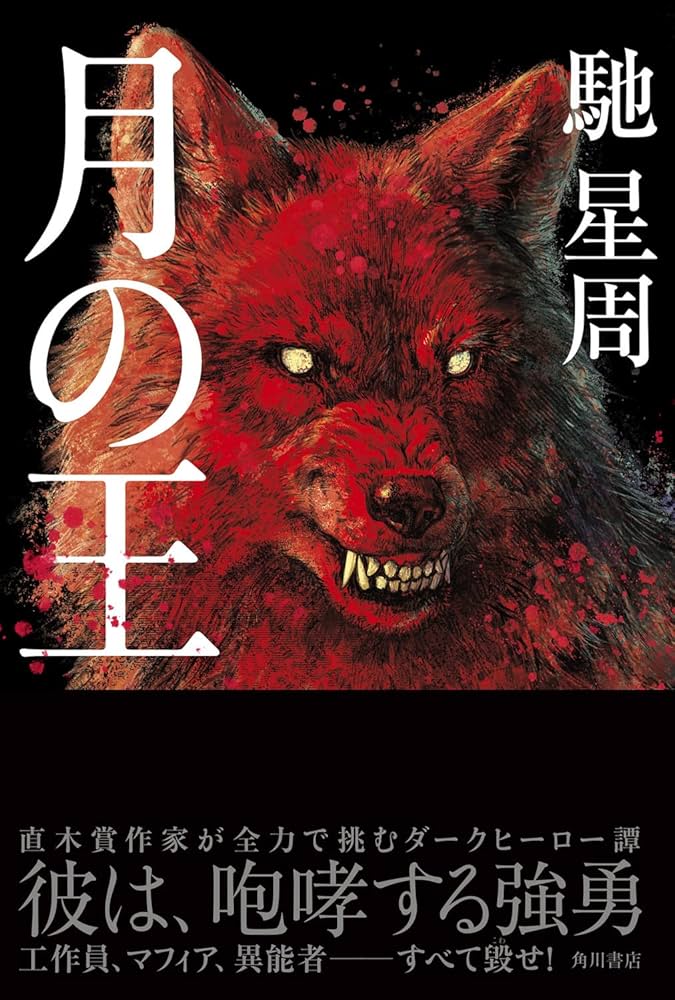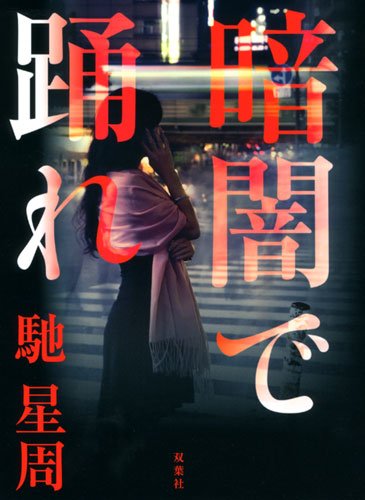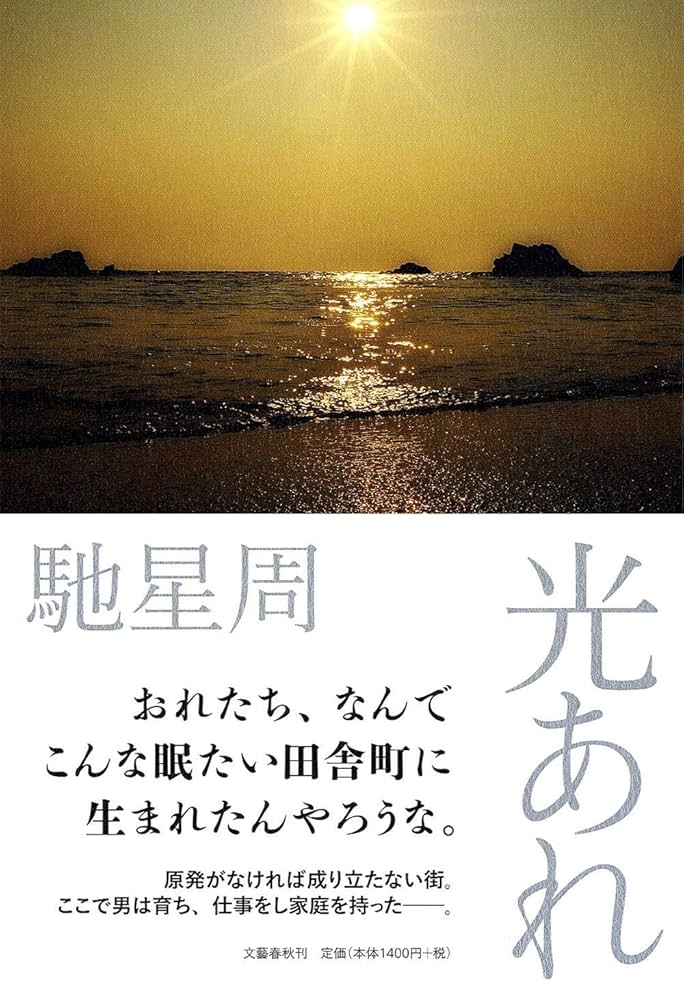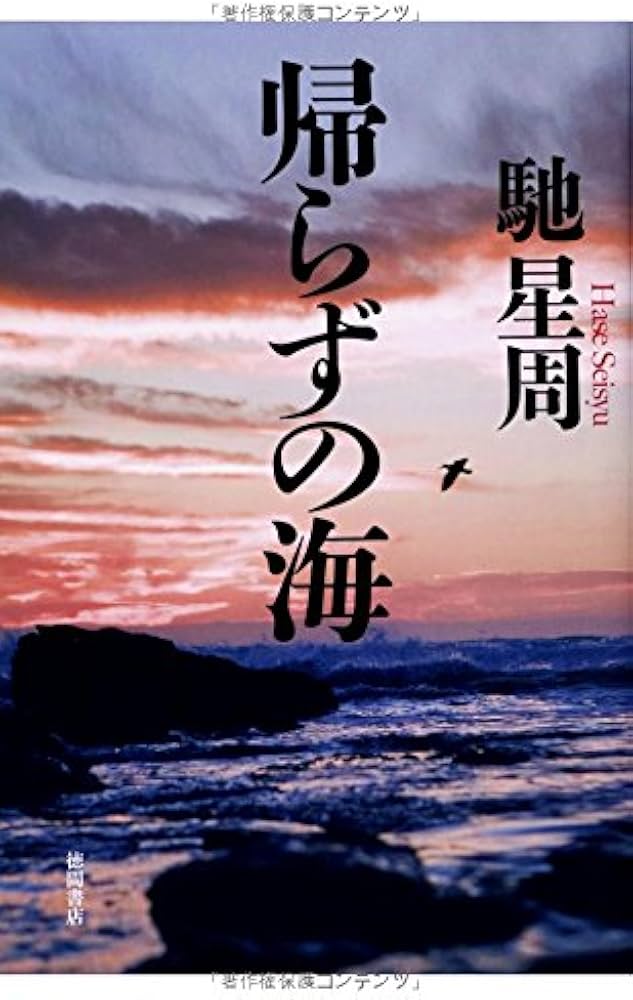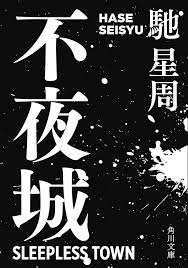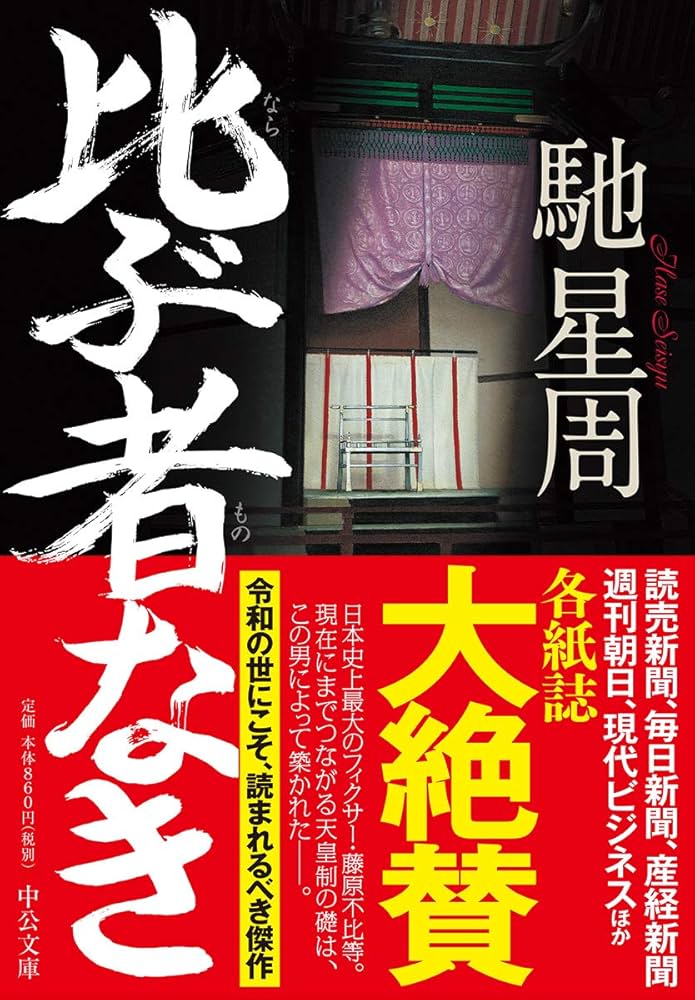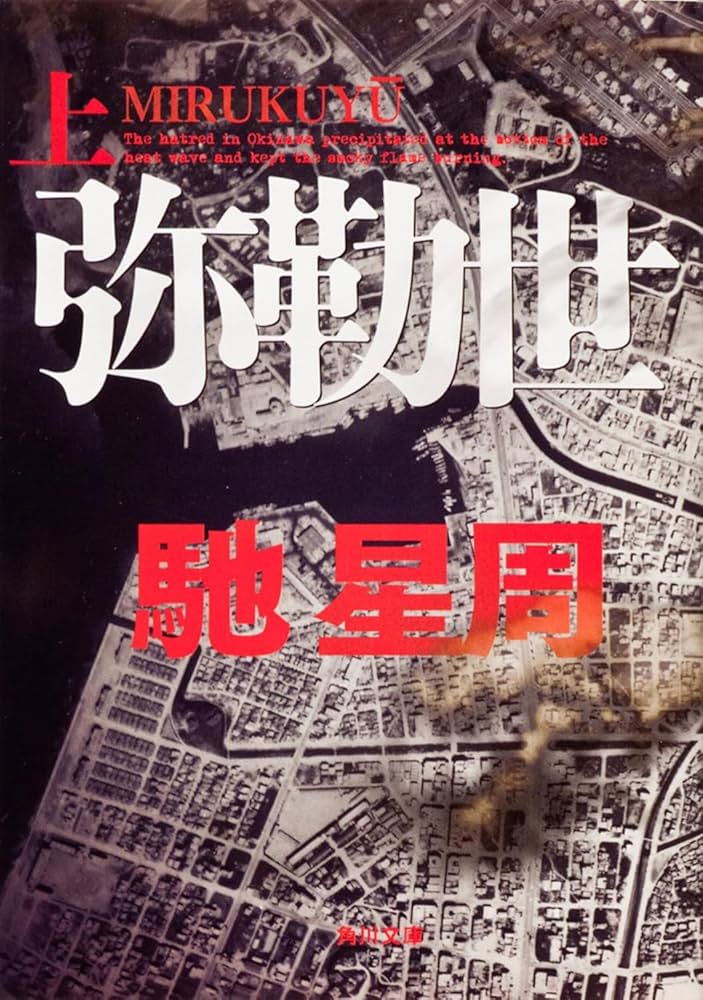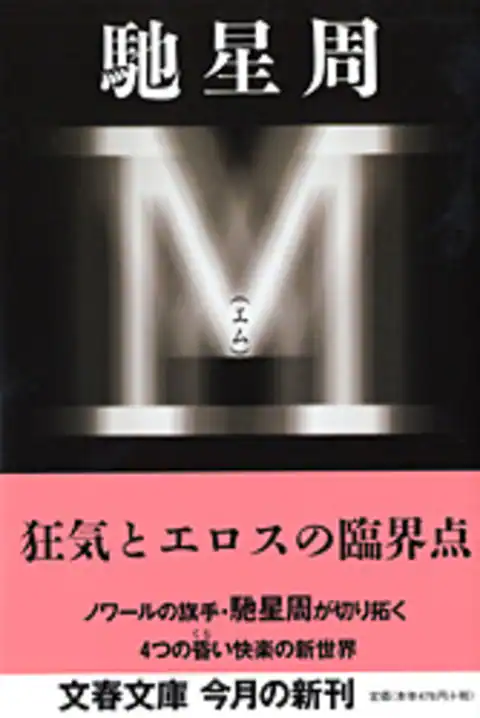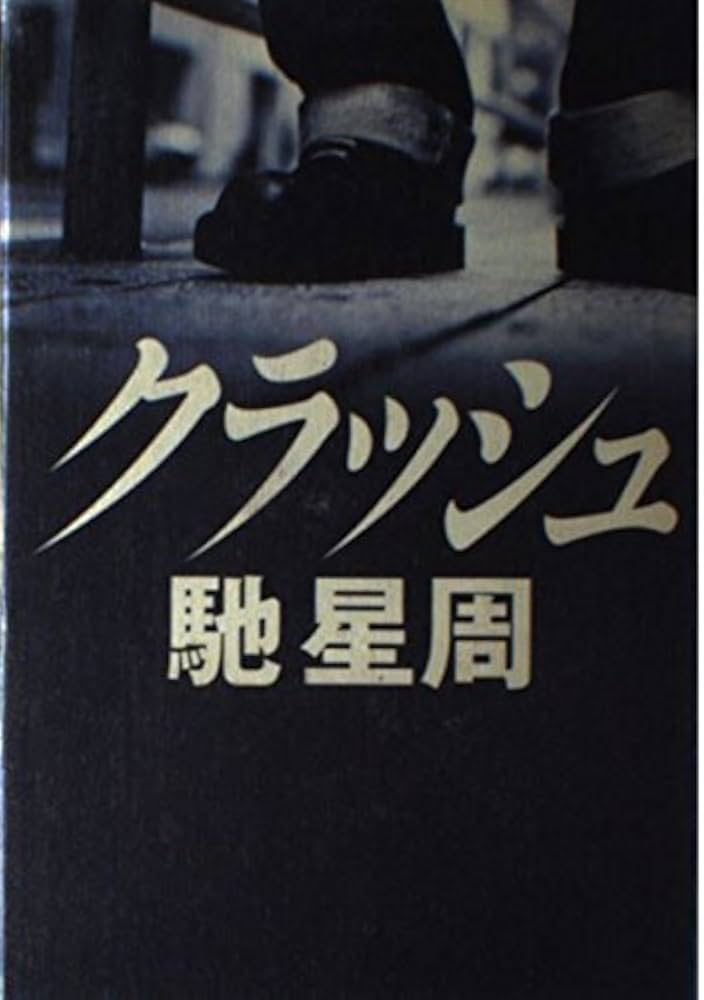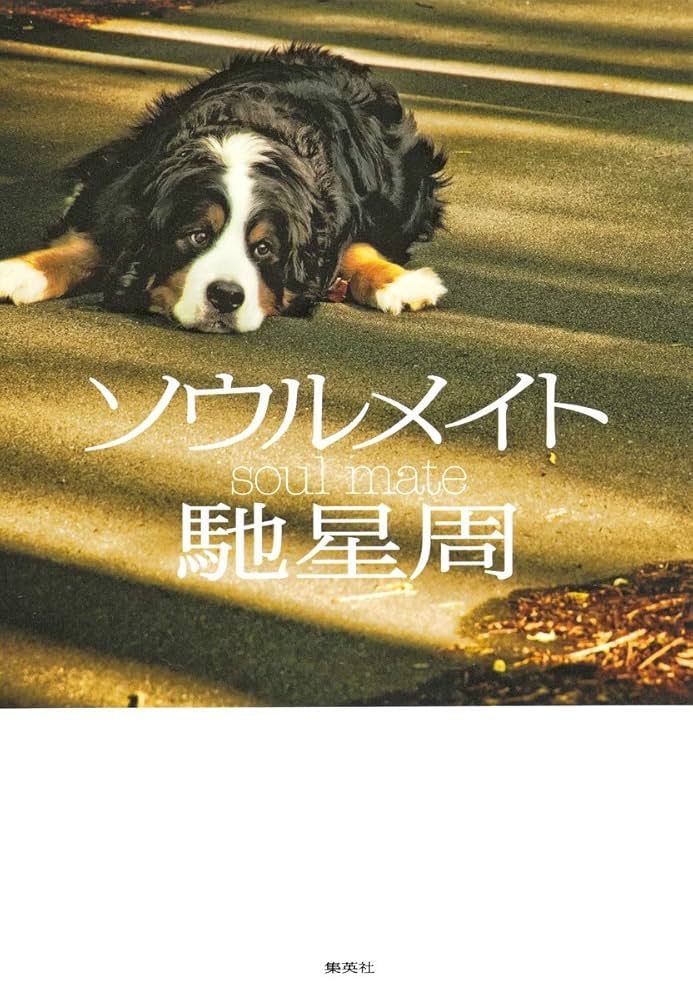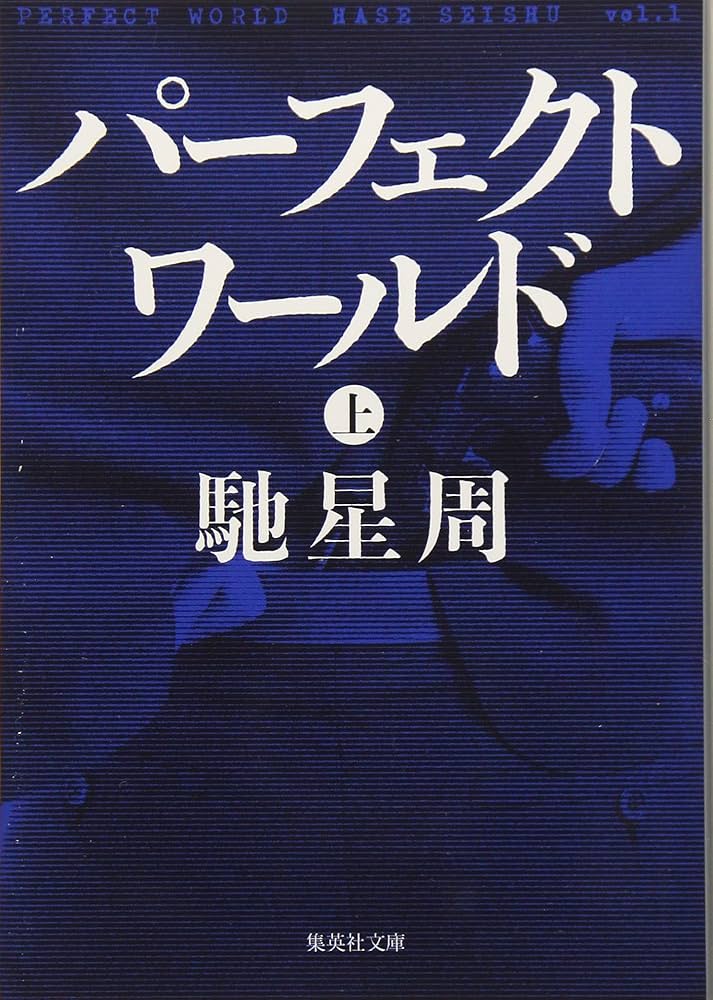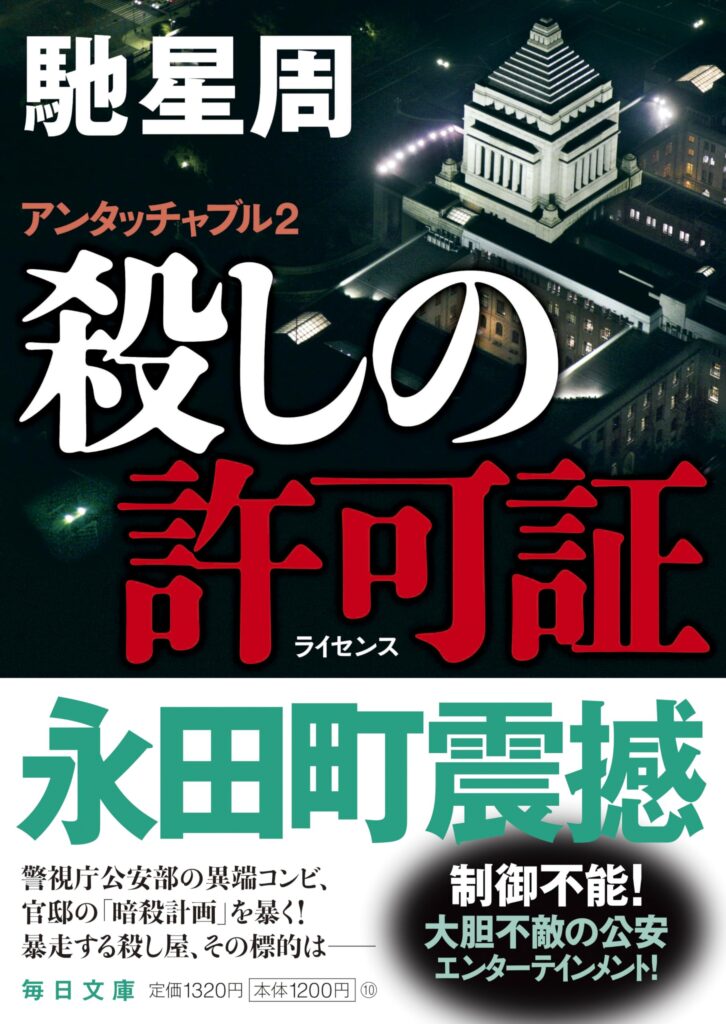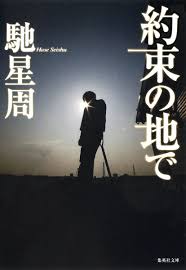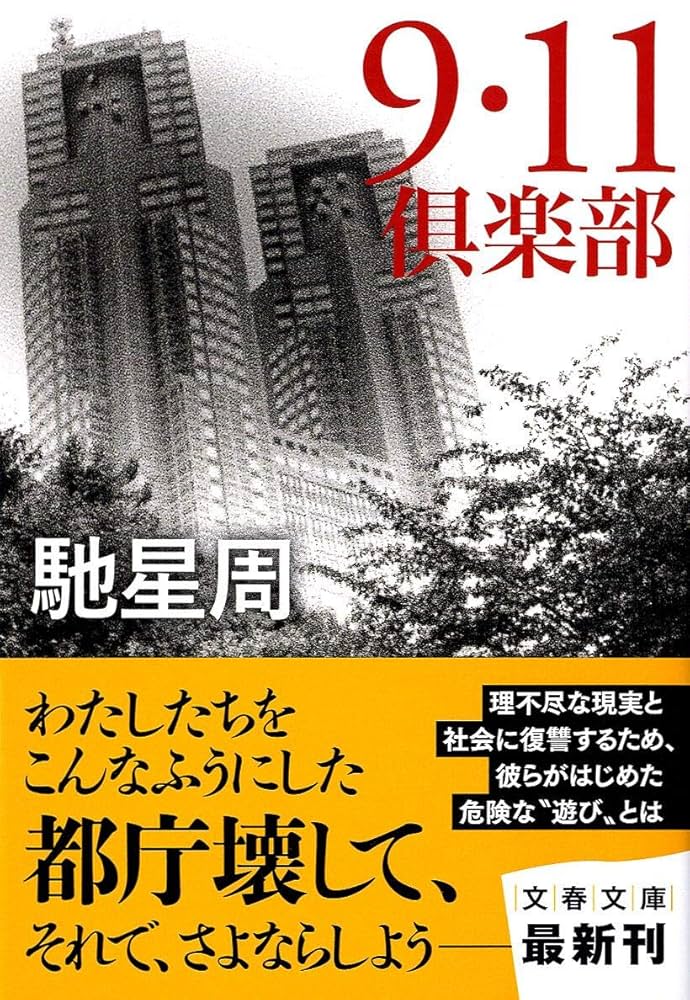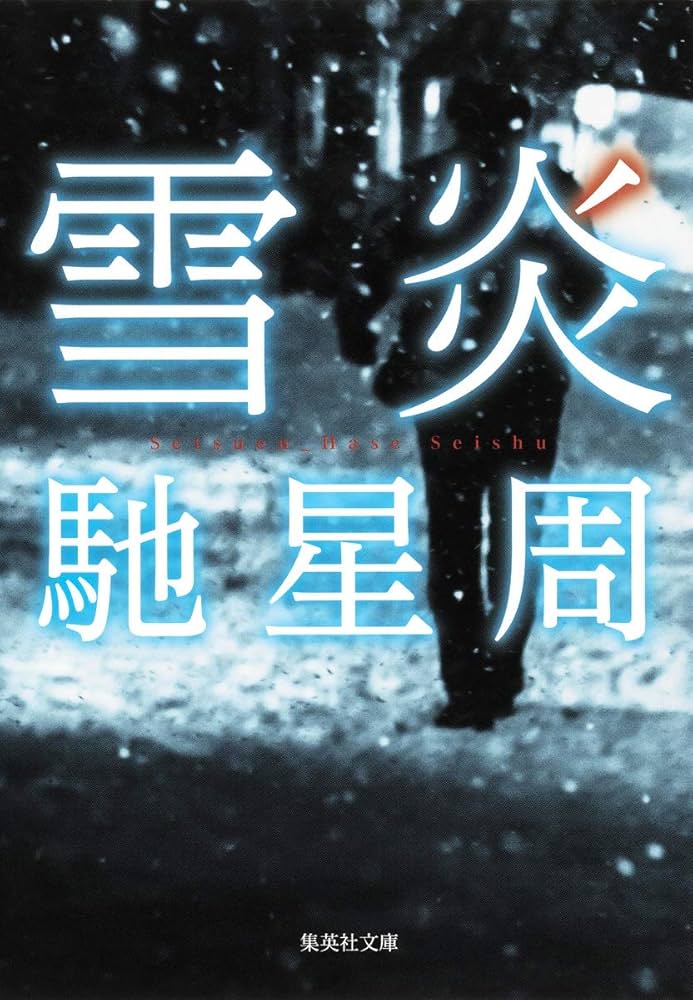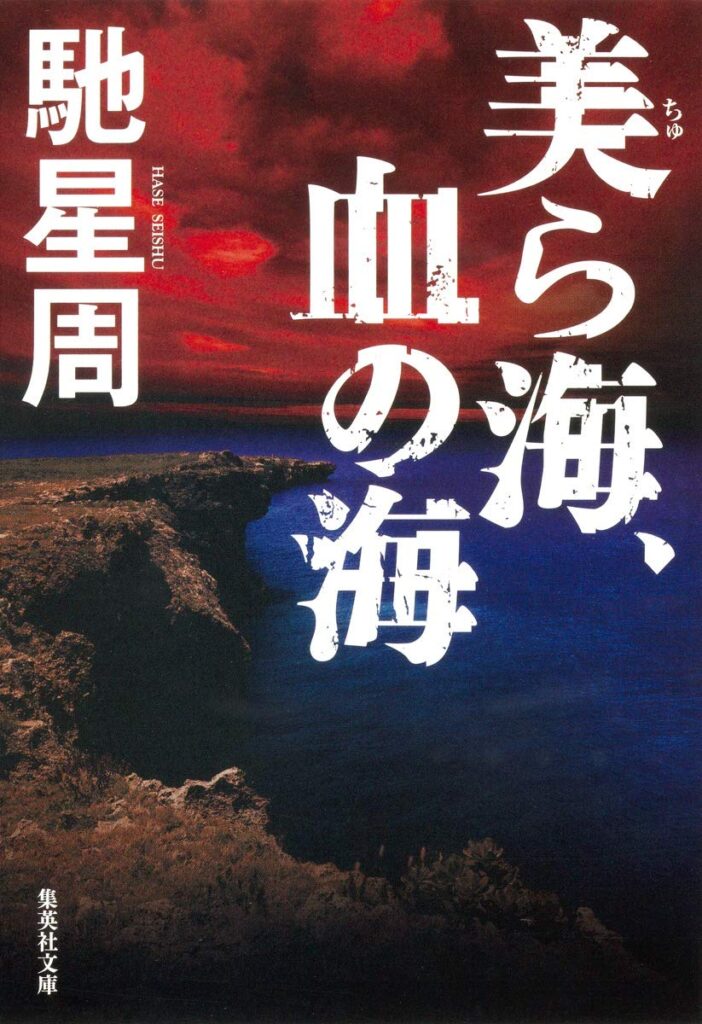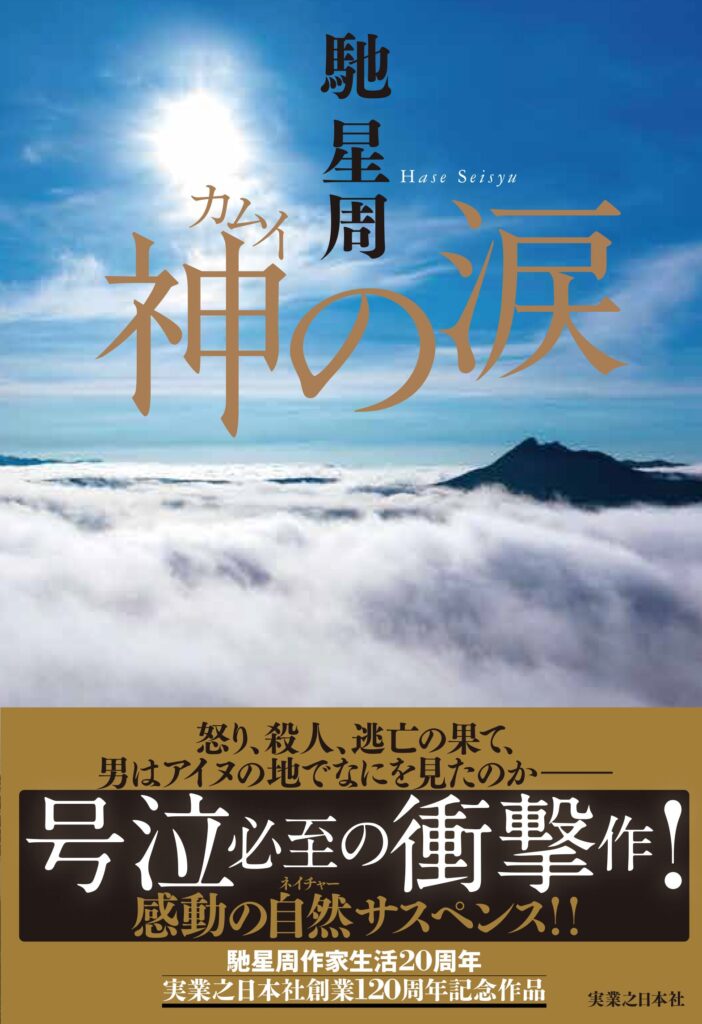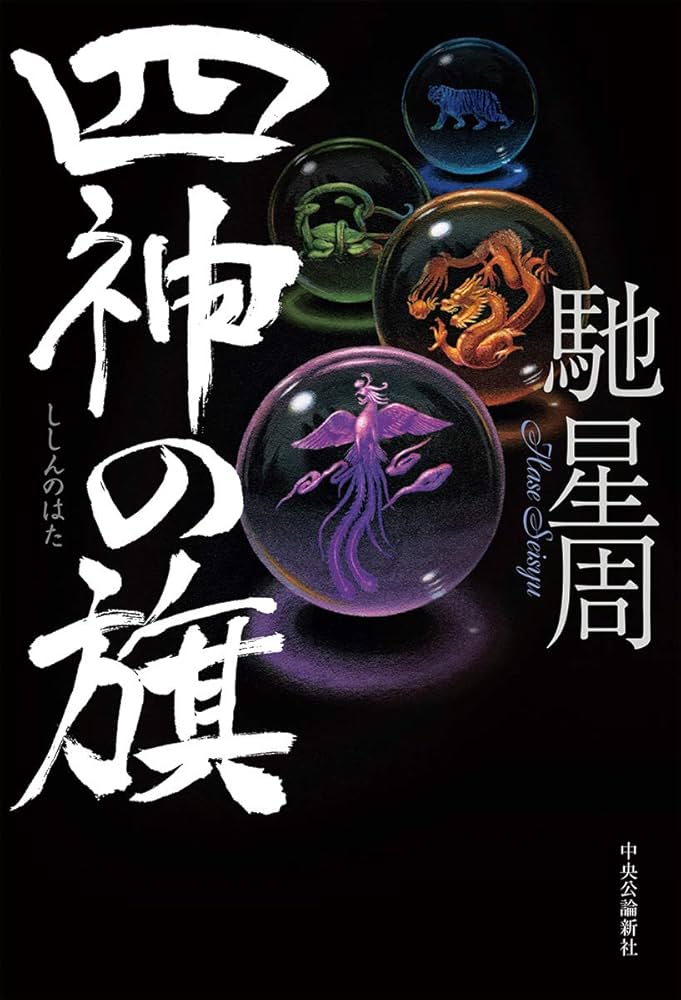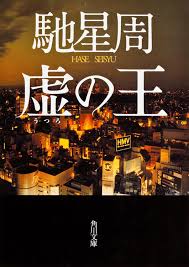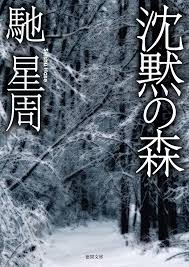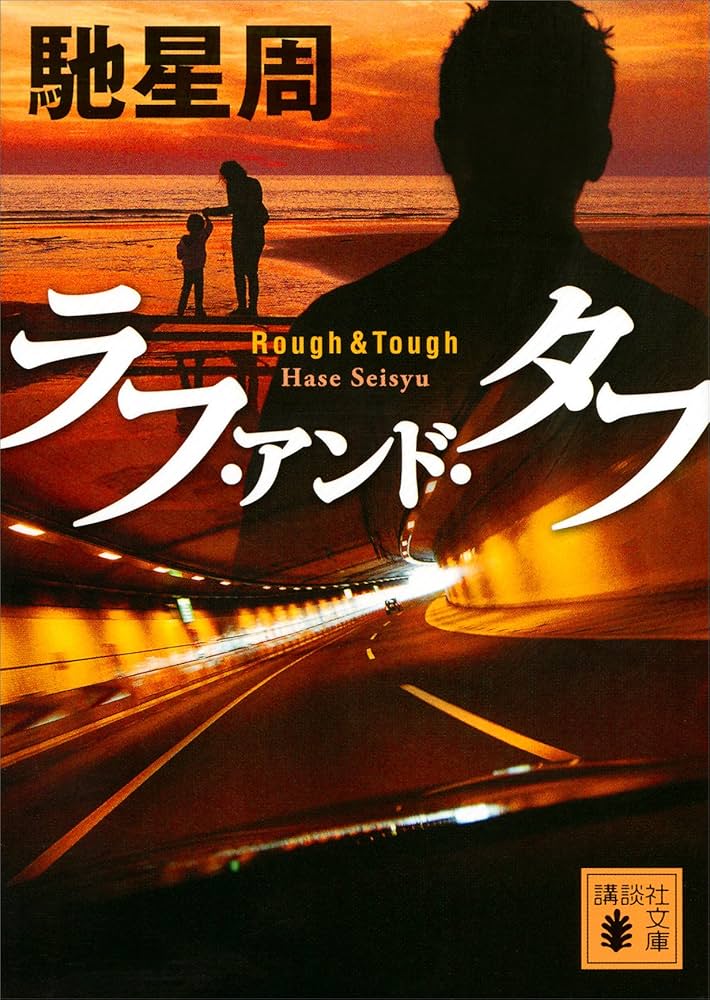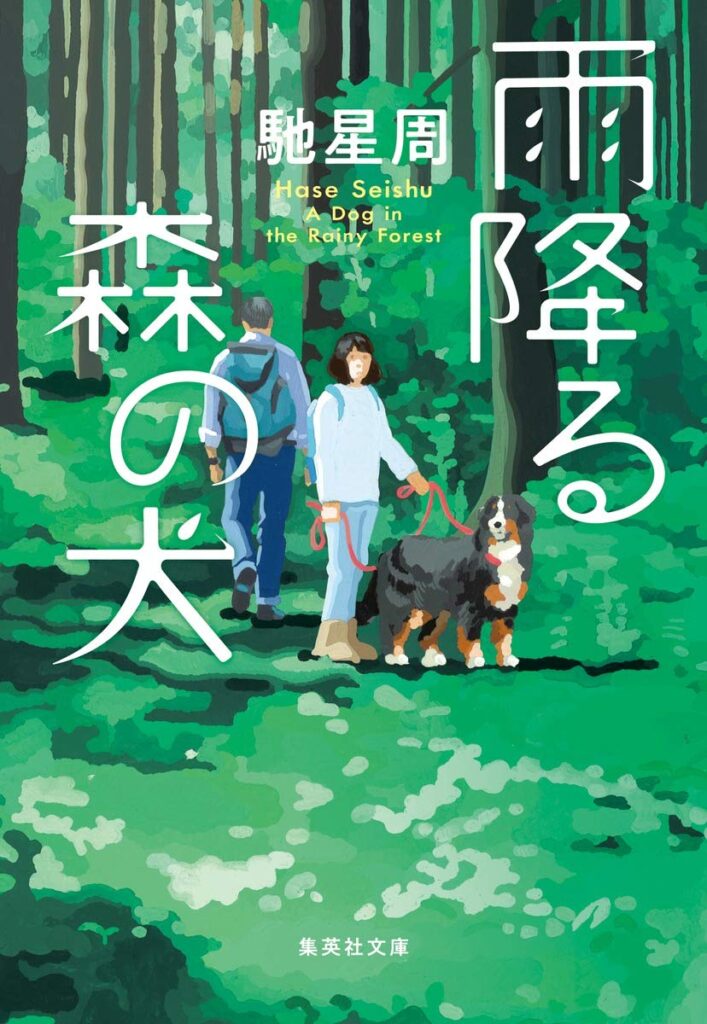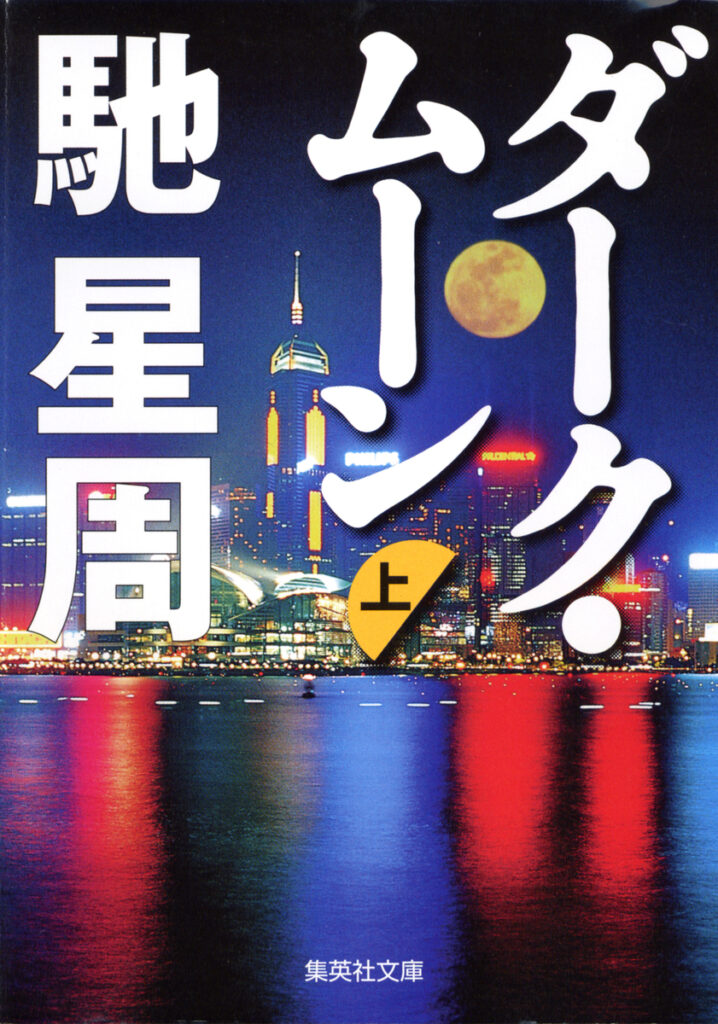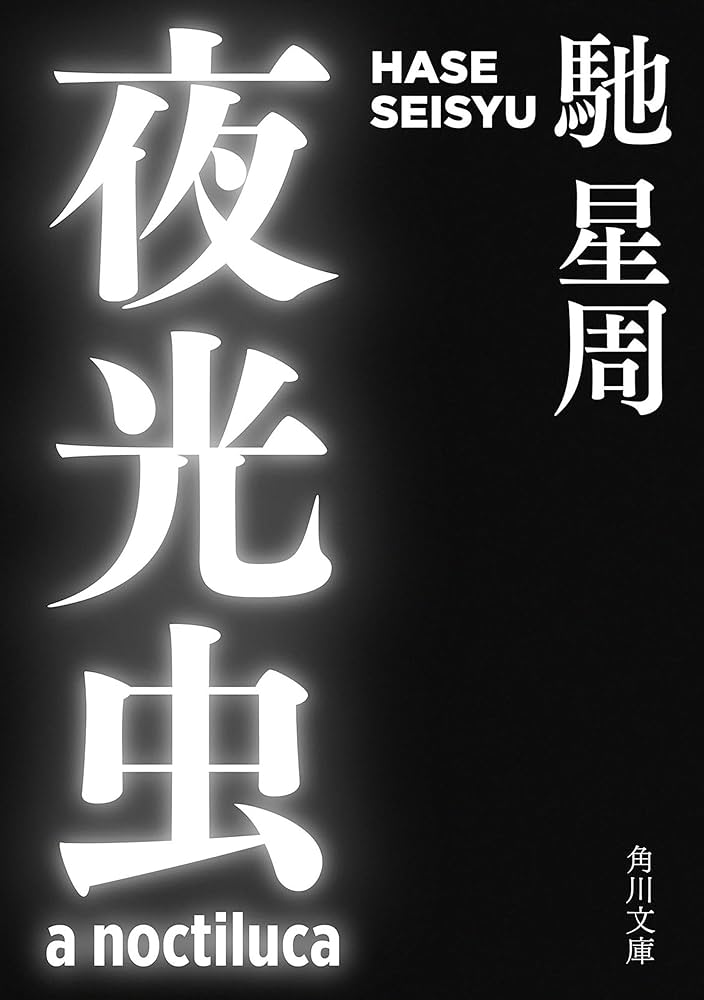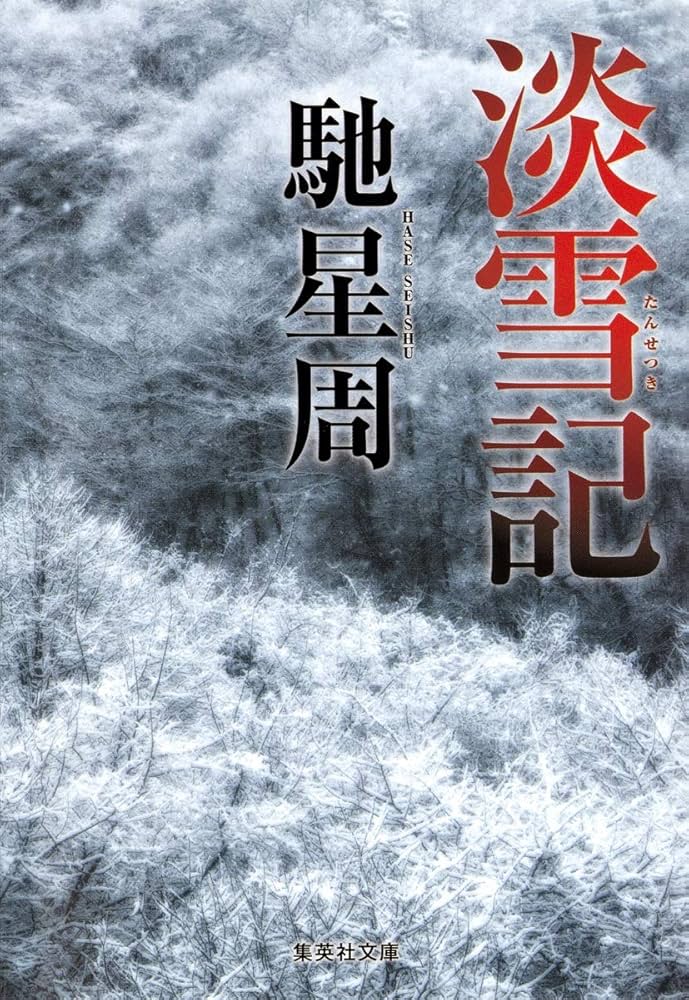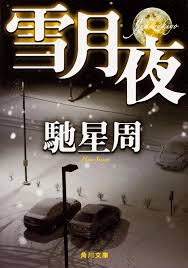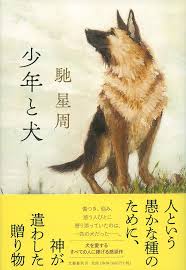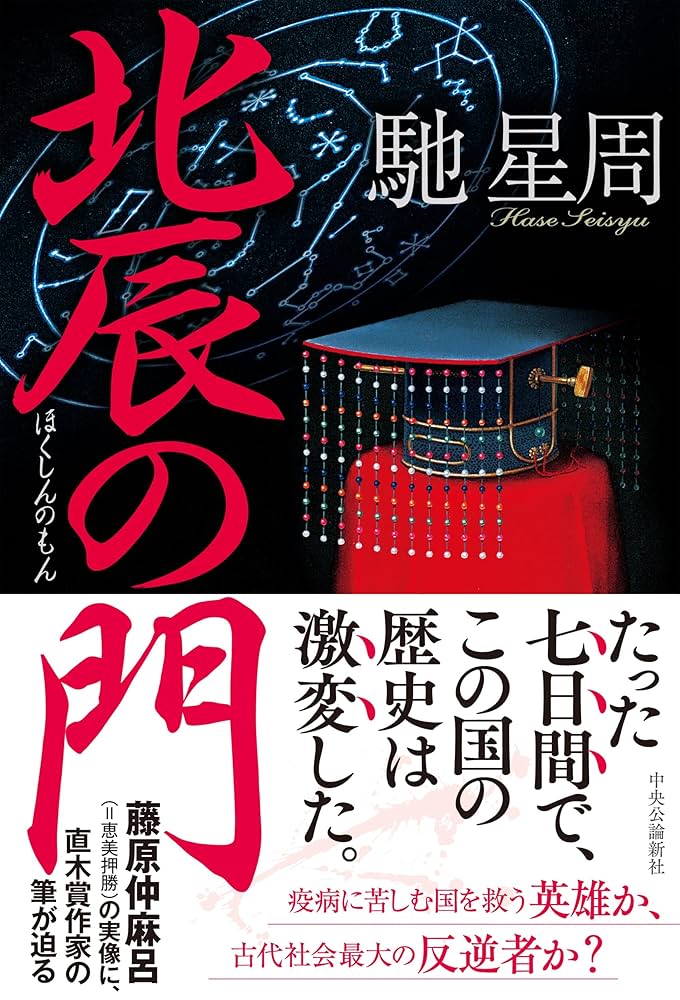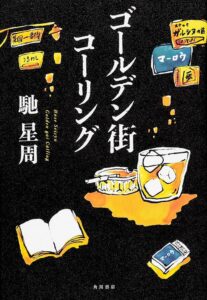 小説「ゴールデン街コーリング」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「ゴールデン街コーリング」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
この物語は、ただの青春小説ではありません。1985年という、日本が熱狂と狂乱の時代へ突入する直前の新宿ゴールデン街。その猥雑で、けれど人間臭いエネルギーに満ちた場所で、一人の青年が経験するすべてを描いた、あまりにも濃密な記録なのです。作家・馳星周さんの自伝的物語でありながら、その枠を遥かに超えた普遍的な輝きと痛みを内包しています。
文学への憧れを胸に田舎から出てきた青年が、いかにして現実の厳しさに打ちのめされ、人々と出会い、別れ、そして自らの道を見つけていくのか。その過程は、甘酸っぱいどころか、血と汗と涙にまみれています。しかし、だからこそ私たちの心を強く揺さぶるのでしょう。この記事では、物語の核心に触れながら、その魅力を余すところなく語っていきたいと思います。
これから語られるのは、一つの時代の肖像であり、失われた場所への挽歌であり、そして一人の作家が誕生するまでの壮絶な物語です。この熱い物語の世界に、少しだけお付き合いいただければ幸いです。
「ゴールデン街コーリング」のあらすじ
物語の舞台は1985年の新宿。主人公の坂本俊彦は、ハードボイルド小説に憧れ、北海道の田舎町から上京してきたばかりの大学生です。彼の聖地は、作家や編集者たちが夜な夜な集うという新宿ゴールデン街。その中でも、特に「日本冒険小説協会公認酒場」の看板を掲げるバー<マーロウ>は、彼にとって特別な場所でした。
ある日、坂本は店のマスターである斉藤顕に手紙を送ったことをきっかけに、憧れの<マーロウ>で働くことになります。そこは、彼の夢見ていた通り、文学や映画を愛する人々が集う刺激的な空間でした。しかし、店の日常は彼の想像を絶するものでした。マスターの斉藤は、ひとたび酒が入ると手が付けられない暴君へと変貌し、坂本は日々、理不尽な罵声と暴力の嵐に耐えなければなりませんでした。
そんな過酷な日々の中、坂本はゴールデン街で生きる個性的な人々と出会い、奇妙な絆を育んでいきます。心優しい常連客のナベさん、近所のオカマバーのママであるリリーさん、そして恋心を抱くホステスの由香。彼らとの交流は、坂本の荒んだ心を少しずつ癒していきます。
しかし、街にはバブル経済の波が押し寄せ、地上げ屋の影がちらつき始めます。不穏な空気が漂う中、ある夜、街を揺るがす悲劇的な事件が発生します。信頼していた仲間が、何者かによって殺されてしまったのです。警察の捜査が進まないことに苛立ちを覚えた坂本は、自らの手で真実を突き止めることを決意するのでした。
「ゴールデン街コーリング」の長文感想(ネタバレあり)
ここからは、物語の結末に触れていきます。まだ読んでいない方はご注意ください。この「ゴールデン街コーリング」という物語が、私の心にどれほど深く刻まれたか、その熱い思いの丈を語らせていただきます。これは単なる自伝的小説という言葉では片付けられない、一つの時代の魂を描ききった傑作だと感じています。
まず語りたいのは、この物語の舞台設定の絶妙さです。1985年の新宿ゴールデン街。それは、戦後の闇市の記憶を色濃く残しながら、文化人たちのサロンとして独自の空気を醸成し、そしてすぐそこまで迫るバブル経済という巨大な波に飲み込まれようとしている、奇跡のような場所でした。その熱気、猥雑さ、そして内に秘めた暴力性。この街の空気を吸い込むだけで、読んでいるこちらの胸まで高鳴るようでした。
主人公の坂本俊彦が抱く、文学への純粋な憧れには、誰もが少しばかりの共感を覚えるのではないでしょうか。好きな作家たちが集う酒場、そこで交わされるであろう知的な会話。そんな夢を抱いて上京してきた彼の前に広がるのは、理想とはかけ離れた現実でした。この理想と現実のギャップこそが、この物語の最初の大きな推進力になっているのです。
そして、この物語を語る上で絶対に外せないのが、バー<マーロウ>のマスター、斉藤顕の存在です。実在の人物をモデルにしたという彼の造形は、まさに圧巻の一言。素面の時は魅力的で知的な語り手でありながら、酒に酔うと手が付けられない暴君と化す。その二面性は、恐怖を通り越して、ある種の人間的な魅力を感じさせます。坂本が彼に抱く、尊敬と憎しみが入り混じった「愛憎」こそ、この物語の核となる感情の一つでしょう。
斉藤が坂本に浴びせる罵詈雑言は、現代で言うところの完全なパワーハラスメントです。その描写はあまりに生々しく、読んでいるこちらの胃まで痛くなるほどでした。しかし、その理不尽な環境の中で、必死に自分の居場所を見つけようともがく坂本の姿に、私たちは強く心を揺さぶられるのです。それは決して美しい青春の姿ではありませんが、だからこそ、その苦闘には真実味がありました。
そんな地獄のような日々の中にも、救いはありました。ナベさん、リリーさんといったゴールデン街の住人たちです。彼らは血のつながりこそありませんが、間違いなく一つの「家族」でした。特に、誰にでも優しく、混沌とした街の良心のような存在だったナベさん。そして、母親のように坂本を気遣ってくれるリリーさん。彼らが織りなす人間関係の温かさが、この物語の過酷さを和らげてくれるのです。
坂本がこの街に対して抱く「嫌いだ。なのに、この街の住人だという感覚は…」というセリフは、彼のアンビバレントな感情を完璧に表現しています。知的な興奮と、酔っぱらいの汚物。本物の仲間意識と、常に漂う暴力の匂い。この光と影が混じり合った空気こそがゴールデン街そのものであり、坂本は、そして私たち読者は、その魅力と魔力に抗えなくなっていくのです。
物語が中盤に差しかかると、不穏な空気が一気に現実のものとなります。地上げ屋の暗躍と、放火未遂事件。時代の暴力が、彼らのささやかな共同体をじわじわと蝕んでいく様に、言い知れぬ恐怖を感じました。そして、その恐怖は最悪の形で爆発します。
街の平和を守るために自主的な夜警をしていたナベさんが、何者かに殺害されるのです。この展開には、本当に頭を殴られたような衝撃を受けました。あの優しかったナベさんが、なぜ。この事件は、単なる物語の転換点ではありません。それは、ゴールデン街という共同体が持っていた、最後の無垢さが失われた瞬間を象徴していたように思います。
ここから物語は、青春小説の様相から一転し、殺人ミステリーの色合いを帯びていきます。愛する仲間を殺した犯人を、自分の手で見つけ出す。坂本の決意は、悲しみに打ちひしがれた者の、燃えるような怒りの発露でした。このジャンルの大胆な越境が、読者をぐいぐいと物語の深みへと引きずり込んでいきます。
坂本の捜査は、もちろん専門家のものではなく、素人ならではの不器用なものです。人々に話を聞いて回り、事件当夜のピースを一つひとつ組み立てていこうとします。しかし、その不器用な行動の中にこそ、彼のナベさんへの深い愛情と、正義への渇望が表れていて、胸を打ちました。
そんな彼の奮闘と並行して、もう一つの光が描かれます。それは、彼が作家になるという夢の、具体的な第一歩です。彼が書いた文章が、実在の雑誌『本の雑誌』に掲載されるのです。この部分は、作者である馳星周さん自身の経歴と重なることもあり、ひときわ感動的な場面でした。絶望の淵にいても、彼の中の創作への炎は消えていなかった。その事実に、救われるような気持ちになりました。
しかし、人生は光ばかりではありません。彼が想いを寄せていたホステスの由香との恋は、実ることなく終わりを迎えます。失恋の痛みにもがき苦しむ坂本。成功と挫折、喜びと喪失。このコントラストの中で、一人の人間が、そして一人の作家が、少しずつ形作られていく過程が、見事に描き出されていました。
そして、物語はついに核心へとたどり着きます。衝撃的な犯人の正体。ナベさんを殺したのは、なんと、あの心優しいオカマバーのママ、リリーさんだったのです。この真実が明かされた時、私は言葉を失いました。なぜ、あのリリーさんが。その動機は、悪意からではありませんでした。それは、あまりにも悲しい、絶望的な愛情の物語だったのです。
父親の借金と、地上げによる立ち退きの恐怖に追い詰められたリリーさんは、自分の店を守るため、自ら放火に及びます。それを偶然、夜警中のナベさんに見られてしまった。殺害は計画的なものではなく、パニックに陥った末の、偶発的な悲劇でした。ゴールデン街を愛する者同士が、時代の波に翻弄された末に起こしてしまった、あまりにも痛ましい事件だったのです。
この物語が真に傑作であると私が確信したのは、その後の場面でした。犯人がリリーさんだと知った坂本は、彼女を糾弾しません。怒りや憎しみではなく、彼の心を占めたのは、リリーさんの絶望に対する、圧倒的なまでの共感でした。彼はリリーさんを赦し、二人はただ、抱き合って泣き続けるのです。ハードボイルド小説の定石を根底から覆すこの場面こそ、本作の魂であり、正義よりも共感を、断罪よりも赦しを選んだ、人間賛歌の極致だと感じました。
事件のあと、リリーさんは街を去り、坂本もまた、<マーロウ>を辞め、ゴールデン街から離れることを決意します。愛と死、憧れと幻滅。そのすべてを経験した彼の青春は、ここに終わりを告げました。彼は多くのものを失いましたが、その代わりに「作家」という、揺るぎない天職を得たのです。彼の旅立ちの姿は、寂しくも、どこか清々しいものでした。
そして、物語を締めくくるエピローグの鮮やかさには、ただただ脱帽するしかありません。時間は一気に20年後に飛び、坂本は成功した「流行作家」として、ゴールデン街を再訪します。しかし、かつて自分が青春のすべてを捧げたバー<マーロウ>の扉は、彼に固く閉ざされるのです。満席か、あるいは主人の機嫌が悪いのか。かつて自分が客に対して行っていたのと同じ理由で、彼は部外者として拒絶されます。この完璧な円環構造は、時の流れの無情さと、決して過去には戻れないという真理を、痛いほどに突きつけてきました。
この「ゴールデン街コーリング」は、一人の作家の誕生を描いた物語です。しかしそれ以上に、失われてしまった一つの時代、一つの場所への、熱烈で、そしてこの上なく切ない恋文なのではないでしょうか。読後、自分の青春時代を思い出し、胸が締め付けられるような感覚に襲われました。間違いなく、私の心に永遠に残り続ける一冊です。
まとめ
「ゴールデン街コーリング」は、馳星周さんの自伝的要素を色濃く反映した、熱量あふれる青春物語です。1985年の新宿ゴールデン街という、猥雑ながらも人間味に満ちた場所を舞台に、一人の青年が経験する憧れと幻滅、出会いと別れ、そして成長を描いています。
物語は単なる感傷的な思い出話に留まりません。中盤からは友人の死をきっかけとしたミステリー要素が加わり、読者をぐいぐいと引き込みます。しかし、その結末で提示されるのは、単純な勧善懲悪ではない、人間の弱さと愛おしさに根差した、深い共感と赦しのドラマです。この感動的な展開は、多くの読者の心を揺さぶることでしょう。
ハードボイルドな作風で知られる馳星周さんの原点が、ここにあると言っても過言ではありません。作家が、いかにして現実の痛みや喪失を乗り越え、物語を紡ぐ力を得ていくのか。その壮絶な過程が、圧倒的な筆力で描かれています。
馳星周ファンはもちろんのこと、熱い人間ドラマを読みたい、一つの時代が放つ輝きと切なさに触れたいと願う、すべての方に手に取っていただきたい傑作です。読後、きっとあなたの心にも、忘れられない風景が刻まれるはずです。