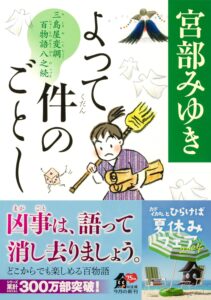 小説「よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが紡ぐ、江戸は神田にある袋物屋「三島屋」を舞台にした、不思議で、時にぞっとするような物語を集める「三島屋変調百物語」シリーズ。その第八弾(続編としては)となるのが、この「よって件のごとし」です。前作「魂手形」から引き続き、主人公のおちかの従兄弟である富次郎が、語り手の話を聞き、墨絵に描いて「聞き捨てる」役目を担っています。
小説「よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんが紡ぐ、江戸は神田にある袋物屋「三島屋」を舞台にした、不思議で、時にぞっとするような物語を集める「三島屋変調百物語」シリーズ。その第八弾(続編としては)となるのが、この「よって件のごとし」です。前作「魂手形」から引き続き、主人公のおちかの従兄弟である富次郎が、語り手の話を聞き、墨絵に描いて「聞き捨てる」役目を担っています。
最初は少し頼りなげだった富次郎も、聞き手として少しずつ成長を見せている様子がうかがえます。彼のもとを訪れる語り手たちが打ち明けるのは、今回もまた、人知を超えた出来事や、心の奥底にしまい込まれた秘密ばかり。可愛らしい装丁に油断していると、ページをめくる手が止まらなくなるような、深い怖さや切なさが待っていますよ。
この記事では、そんな「よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続」に収録されている三つのお話、『賽子と虻』『土鍋女房』そして表題作『よって件のごとし』の内容に触れつつ、物語の核心にも迫っていきます。読み終えた後の、私の心に残ったあれこれを、ネタバレも気にせずにたっぷりと語らせていただきますね。シリーズファンの方はもちろん、これから読んでみようかなと考えている方にも、この物語世界の雰囲気を感じ取っていただけたら嬉しいです。
小説「よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続」のあらすじ
江戸は神田の袋物屋、三島屋。ここでは、次男坊の富次郎が、訪れる人々の不思議な体験談を聞き、それを墨絵に描くことで「聞き捨て」ています。これは、かつて従姉のおちかが行っていた「変わり百物語」を引き継いだもの。最初は戸惑いながらも、富次郎はこの役に少しずつ慣れてきました。そんな彼のもとに、今回も三人の語り手が、奇妙で、そして心に深く刻まれるような物語を携えてやってきます。
第一話『賽子と虻』。語り手は、わけあって笑うことができなくなってしまったという青年、餅太郎。彼は幼い頃、玉の輿に乗ることになった姉が、妬みから恐ろしい呪いをかけられたと語ります。瀕死の姉を救うため、餅太郎はその呪いを自ら引き受けます。その結果、彼は人間界ではない、八百万の神々が集う不思議な世界へと飛ばされてしまうのでした。そこで彼が見たのは、博打に興じる神様や、苦しむ神様の姿。餅太郎は、神々の世界で働きながら、優しい心根から、困っている神様を助けようと奔走することになります。しかし、そこには疫神のような恐ろしい存在もいました。
第二話『土鍋女房』。語るのは、代々続く川の渡し守の家に生まれた娘、おとび。彼女は、朴訥で口下手ながら船を操る腕は確かな兄、喜代丸について語ります。喜代丸には良い縁談もあったのに、なぜか頑なに「嫁はいらぬ」と言い張るのでした。その理由を、おとびはある日知ってしまいます。それは、いつの間にか家にあった不思議な土鍋の存在。空のはずなのに温かく、時に中で何かが蠢く気配がする土鍋。それは、兄がある存在と結んだ、人ならぬ縁の証だったのでした。純粋な兄妹と、彼らを取り巻く人間の欲望が交錯する、静かながらも切ない物語です。
第三話『よって件のごとし』。これは、ある山深い村を襲った、未曾有の恐怖の物語。語り手は、その惨劇を生き延びた人物です。ある日突然、地面に開いた穴から、おびただしい数の異形の化け物が出現します。その化け物に噛まれた者もまた、同じ化け物へと変貌してしまうのです。愛する家族や隣人が、次々と恐ろしい姿に変わっていく地獄絵図。化け物になってしまえば、首を落とさない限り滅びることはありません。人々は、泣きながら愛する者の首を落とさねばならないという、究極の選択を迫られます。手に汗握る展開と、絶望的な状況の中で見せる人間の絆が描かれます。
小説「よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続」の長文感想(ネタバレあり)
宮部みゆきさんの「三島屋変調百物語」シリーズ、待望の続編「よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続」を読み終えました。いやあ、今回もまた、心に深く染み入る物語ばかりでしたね。表紙の三好愛さんのイラストが、どこかほのぼのとしていて可愛らしいのですが、油断は禁物。その柔らかなタッチとは裏腹に、収録されているお話は、背筋が凍るような怖さや、胸が締め付けられるような切なさを孕んでいます。このギャップもまた、三島屋シリーズの魅力の一つなのかもしれません。
前作「魂手形」に続き、聞き手を務めるのは富次郎。おちかちゃんからバトンタッチして、彼が聞き手になってからもう三冊目(前々作「黒武御神火御殿」、前作「魂手形」を含めると)になるのですね。最初はどこかおっかなびっくりで、聞いているこちらも「大丈夫かな?」と少し心配になるようなところもあった富次郎ですが、本作を読むと、だいぶ聞き手役が板についてきたように感じられます。語り手の言葉に真摯に耳を傾け、その背景にある想いを汲み取ろうとする姿勢は、おちかちゃんとはまた違った形で、語り手の心を解きほぐしていく力があるのかもしれません。墨絵で聞き捨てる、というスタイルも、富次郎ならではの向き合い方として定着してきた感じがします。
さて、本作に収められた三編のお話について、ネタバレも気にせずに、感じたことをたっぷりと語っていきましょうか。
第一話『賽子と虻』
まず、このお話の語り手、餅太郎の健気さには、読んでいて本当に胸が締め付けられました。笑えなくなってしまった、という彼の背景には、幼い頃のあまりにも過酷な経験があったのですね。姉の玉の輿を妬んだ者の呪い。その呪いの恐ろしさもさることながら、「蝉くらいの虻」という描写にはゾッとしました。想像しただけで、全身に鳥肌が立つようです。しかも血を吸うというのですから、たまりません。
その恐ろしい呪いを、姉を救うために自ら引き受ける決断をした幼い餅太郎。その勇気と自己犠牲の精神には、ただただ頭が下がります。その結果、飛ばされたのが八百万の神々が集う世界、というのもまた、宮部さんらしい設定ですよね。参考にした他の感想でも「千と千尋みたい」という表現がありましたが、なるほど、確かに、人間が迷い込む異世界、そこで働くことになるという筋立てには、通じるものを感じます。
しかし、その神々の世界の描写がまた、一筋縄ではいかない。神様たちが丁半博打に興じているなんて!日本の八百万の神様というのは、本当に人間味があって、どこか親しみやすいというか、良くも悪くも「俗っぽい」ところがあるのかもしれませんね。でも、もちろん神様ですから、恐ろしい力も持っている。特に疫神の描写は、現代を生きる私たちにとっても、他人事とは思えない怖さがありました。作中では疱瘡の疫神でしたが、これがもし別の病の神だったら…と考えると、ぞっとします。
そんな世界で、餅太郎は神様の姿を見てはいけないというルールの中、懸命に働きます。賽子たちが彼のお供をしてくれるのが、せめてもの救いでしょうか。彼らの存在が、餅太郎の孤独を少し和らげてくれたように思います。そして、博打で負けて泣いている燕の神様。なんとも可愛らしいけれど、賭けたものが「今年の春から夏にかけての燕全部」で、取り返すには「来年の燕を賭けるしかない」なんて、神様、無茶苦茶すぎます!でも、そんなダメな神様(失礼!)を放っておけないのが、餅太郎の優しいところ。自分の身を顧みず、燕の神様のためにも奔走する姿には、もう「餅太郎、君はなんて良い子なんだ!」と声をかけたくなりました。
姉への呪いも、嫉妬という人間の醜い感情が発端でした。宮部さんの作品には、しばしばこうした人間の心の闇が描かれますが、本作の加害者は反省の色も見せないというあたりが、またやるせないですね。「あやし」の中の「梅の雨降る」という作品を思い出した、という感想もありましたが、確かに通じるテーマ性を感じます。
餅太郎が神様の社で働き続ける、ということの過酷さも考えさせられました。「十二国記」の鈴のエピソードを思い出したという感想もありましたが、幼い子供が家族と引き離され、異世界で長年労働を強いられるというのは、現代の感覚からすると、あまりにも辛い状況です。弥生様との扱いの差にも、身分のようなものが感じられて、少し嫌な気持ちにもなりました。
「人がいるから神々がいるのか、神々がおわすから人がいるのか」という問いかけも印象的でした。信仰と神々の力の関係、そして時に人間が神々に対して残酷な仕打ちをすることもある、という描写は、人間の傲慢さや信仰の移ろいやすさについて、深く考えさせられます。
物語の終わり方には、餅太郎の今後について、何やら含みがあるような感じがしましたね。語り捨てなので、彼の物語はこれで終わりのはずですが、もしかしたら、また何かの形で三島屋と関わることになるのかもしれない…そんな予感をさせる終わり方でした。餅太郎には、本当に幸せになってほしいと、心から願わずにはいられません。
第二話『土鍋女房』
このお話は、どこか日本の古い民話のような、不思議で物悲しい雰囲気が漂っていましたね。代々続く「三笠の渡し守」という仕事。村人からは尊ばれつつも、貧しく、危険と隣り合わせで短命…という設定が、まず切ないです。誇りはあるけれど、生活は苦しい。もう少し報われてもいいのではないか、と思ってしまいますが、お金目当てでやる仕事ではない、という価値観もまた、昔ながらの美徳なのかもしれません。
語り手である妹のおとびが、とても良い味を出していました。彼女の視点を通して語られる、朴訥だけれど腕は確かな兄、喜代丸。彼が頑なに嫁をもらおうとしない理由が、あの不思議な土鍋にあったとは。空のはずなのに温かく、中で何かが蠢く気配がする…この描写だけで、じわじわと不気味さが募ってきます。最初、私はてっきり、渡し守の仕事に関わる何か、あるいは以前の縁談相手だった築地屋の因縁か何かかと思ったのですが、違いましたね。
土鍋の正体は、兄が結んだ人ならぬものとの縁、神様との契りでした。「神様と夫婦になる」というモチーフは、昔話にもよく見られますが、そこに宮部さんならではの人間模様の描写が加わることで、物語に深みが増しています。喜代丸とおとび兄妹の純粋さ、素朴さと、彼らを取り巻く村の人々の、時に見える生々しい欲望との対比が鮮やかでした。特に、兄の秘密を知った上で、それでも兄を思いやるおとびの気持ちが、読んでいて切なかったです。
そして、このお話の最後、富次郎がおとびから頂き物(土鍋そのものではなかったと思いますが、関連するもの)を受け取ってしまう、という展開には、少し驚きました。これまでの「聞き捨て」のルールからすると、少し異例のことですよね。これは、富次郎の聞き手としての在り方が、少しずつ変化してきているということなのでしょうか。あるいは、百物語そのものの性質が、少しずつ変わっていく予兆なのかもしれません。この変化が、今後のシリーズにどう影響していくのか、気になるところです。
第三話『よって件のごとし』
そして、表題作でもあるこの第三話。これは……怖かったです!参考にした感想の中に「宮部版ゾンビホラー」という表現がありましたが、まさにその通り!いや、それ以上かもしれません。
突然、地面に開いた穴から現れる異形の化け物。三好さんの可愛らしいタッチで描かれた挿絵が、逆にそのグロテスクさを際立たせていて、強烈な印象を残します。あの化け物に噛まれると、人もまた化け物になってしまう。しかも、化け物になったら首を落とさない限り死なない……。この設定が、容赦なくて本当に恐ろしい。
愛する家族、友人、隣人が、目の前で化け物へと変わり果て、自分に襲いかかってくるかもしれない。そして、もしそうなってしまったら、自らの手で、その首を落とさなければならない……。想像を絶する状況です。これはもう、物理的な恐怖だけでなく、精神的に追い詰められる、究極の選択を迫られる恐怖ですね。次から次へと襲いくる化け物の群れ、閉鎖された村、いつ誰が化け物になるかわからない疑心暗鬼。手に汗握る、とはまさにこのこと。ページをめくる手がもどかしくなるほどの緊迫感でした。
さらに、この物語には、単なるホラー要素だけでなく、どこかSF的な、パラレルワールドを思わせるような要素も含まれていました。語り手が迷い込んだ「違う世界」の可能性。元の世界に戻れなくなってしまったため、真偽は確かめようがないのですが、この設定が物語にさらなる奥行きを与えています。もしかしたら、あの化け物は、全く別の世界の存在だったのかもしれない…?
そんな絶望的な状況の中にあっても、輝きを放つのが人間の絆や勇気です。中ノ村の人々が、危険を顧みずに助けに向かおうとする姿には、胸が熱くなりました。なかなかできることではありません。そして、生まれ育った村を捨てるか、それとも化け物と戦い続けるかの苦渋の決断。これもまた、非常に重い選択です。
物語の中で語られる「繋がる縁なら、どんな困難だって乗り越えて繋がる」という言葉が、心に響きました。化け物との戦いという極限状況を生き延びた語り手と、その伴侶となった女性の姿を見ていると、この言葉の重みが実感されます。人との出会いは本当に不思議なもので、どんな状況で出会うか、どんなタイミングで出会うかで、その後の人生が大きく変わっていく。他の感想にもありましたが、失恋の経験やパートナーとの出会いなど、自分自身の経験と重ね合わせて、縁というものについて改めて考えさせられました。
この『よって件のごとし』は、三島屋シリーズの中でも、特に「恐怖」という要素が前面に出た、強烈な一編だったと思います。しかし、ただ怖いだけではなく、極限状態における人間の強さや弱さ、そして縁の不思議さをも描き切った、読み応えのある物語でした。
シリーズ全体を通して
本作を読んで改めて感じたのは、富次郎という聞き手の成長と変化です。おちかちゃんが持つ、どこか巫女的な鋭さとは違う、朴訥さと優しさで語り手の心に寄り添う富次郎。彼なりの「聞き捨て」の形が、確立されつつあるのを感じます。墨絵という媒体も、彼の個性と合っているように思えますね。
そして、三島屋を取り巻く人々の環境も、少しずつ変化しています。おちかちゃんがお嫁に行き、今はお腹に新しい命を宿しているとのこと。これは嬉しい知らせですが、三島屋の日常からは少し離れてしまったのだな、と思うと、少し寂しい気持ちもあります。さらに、長年三島屋に仕えてきた古参のおしまさんが、事情があって夜逃げ同然に瓢箪古堂へ移ったというのも、衝撃でした。江戸時代の身分制度や、女性が置かれた立場の厳しさを感じさせる出来事です。これもまた、時代のリアルな一面なのでしょうね。
その一方で、なんと、家を出ていた長男の伊一郎が帰ってくるという、大きな変化も!これは驚きました。伊一郎が今後、三島屋の百物語にどう関わっていくのか、あるいは関わらないのか、非常に気になります。富次郎、おちか(時々?)、そして伊一郎?三島屋の次世代が、これからどんな物語を紡いでいくのか、楽しみです。
ただ、本作の最後で、百物語はしばらく小休止する、というような雰囲気が示唆されていましたね。これは少し残念ですが、宮部さんのことですから、きっとまた、素晴らしい物語と共に再開してくれると信じています。この「含み」を持たせた終わり方も、実に巧みだなと感じ入りました。続きを待ち焦がれる気持ちを、さらに掻き立てられます。
宮部みゆきさんの描く物語は、いつも私たちをその世界に深く引き込んでくれます。怖い話、不思議な話、切ない話…そのどれもが、ただ怖いだけ、不思議なだけ、切ないだけではなく、人間の心の機微や、時代の空気、そして時には人知を超えた存在の気配までをも、鮮やかに描き出しています。まるで、目の前で語り手が息遣いまで伝わるように話しているかのような、そんな臨場感があります。
「よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続」もまた、そんな宮部さんの筆致が存分に発揮された一冊でした。怖いけれど、温かい。切ないけれど、どこかに救いがある。読み終えた後、物語の世界の余韻に、しばらく浸っていたくなるような作品です。
まとめ
宮部みゆきさんの人気シリーズ最新刊、「よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続」は、今回も期待を裏切らない、読み応えのある一冊でしたね。聞き手役となった富次郎の成長ぶりを感じさせつつ、彼のもとに集まる物語は、どれも個性的で、心に強く響くものばかりでした。
『賽子と虻』では、神々の世界の不思議さと恐ろしさ、そして自己犠牲の精神を持つ少年の健気さに胸を打たれ、『土鍋女房』では、民話のような雰囲気の中に漂う静かな怖さと、人ならぬものとの縁の切なさに触れました。そして表題作『よって件のごとし』は、息もつかせぬ展開のホラーでありながら、極限状況での人間の絆や縁について深く考えさせられる、強烈な印象を残す物語でした。
三島屋の面々にも変化があり、おちかの嫁入りや妊娠、おしまさんの旅立ち、そして伊一郎の帰還など、今後のシリーズ展開がますます気になる要素もたくさんありました。百物語は一旦小休止とのことですが、この魅力的な世界がこれからも続いていくことを、心から願っています。怖い話が好きな方はもちろん、じっくりと物語の世界に浸りたい方におすすめしたい作品です。































































