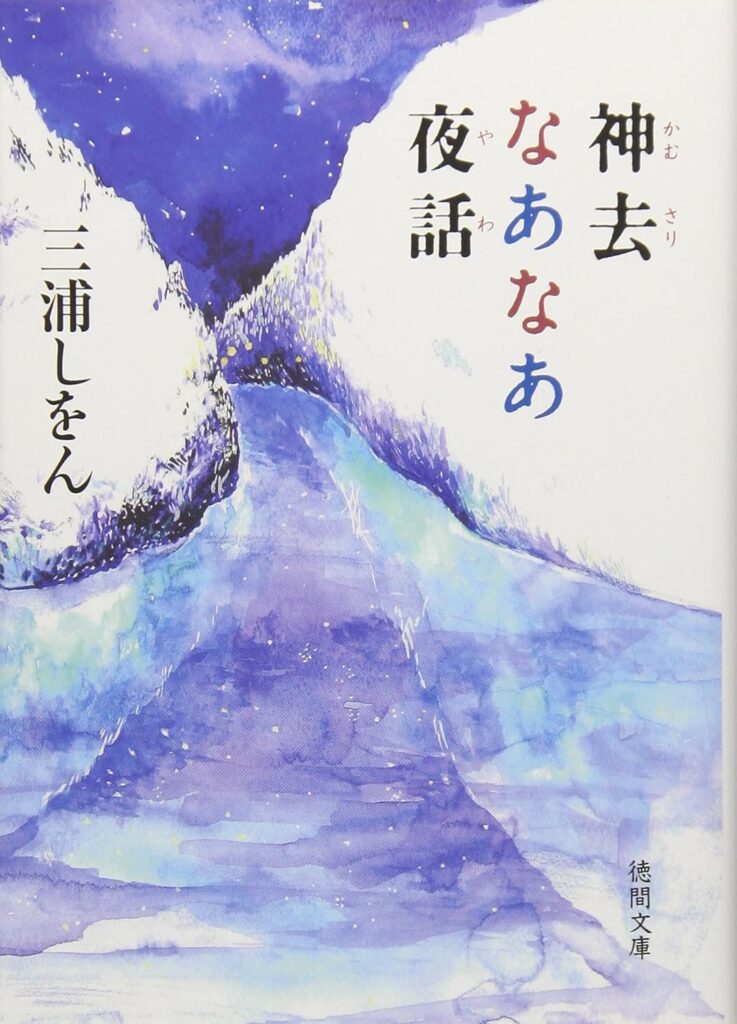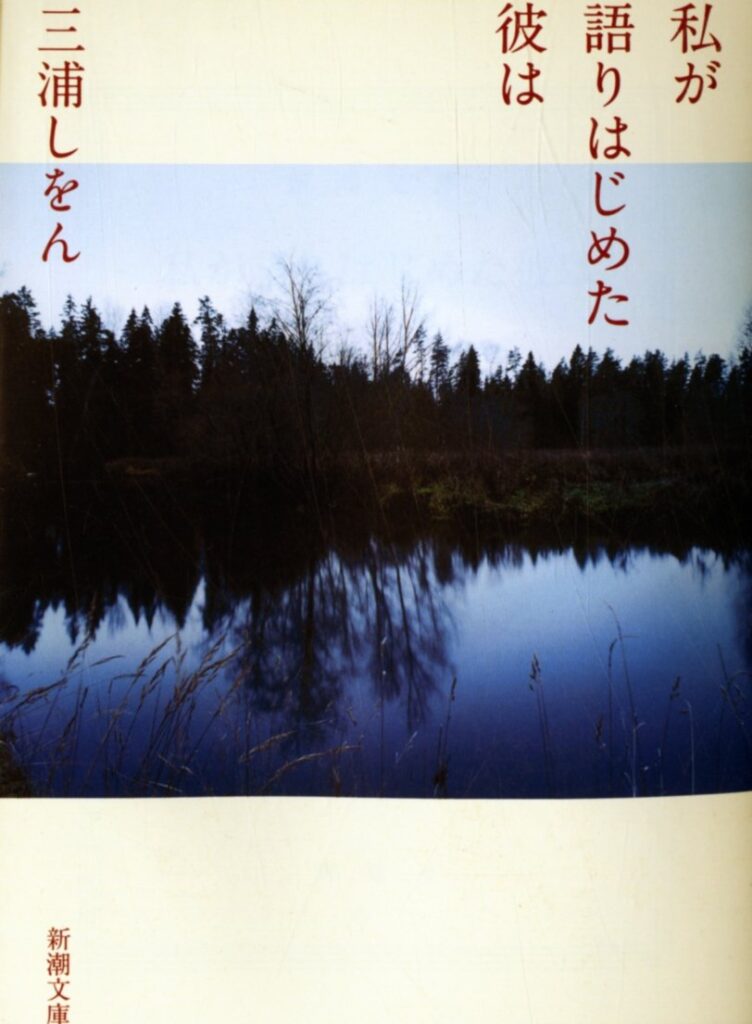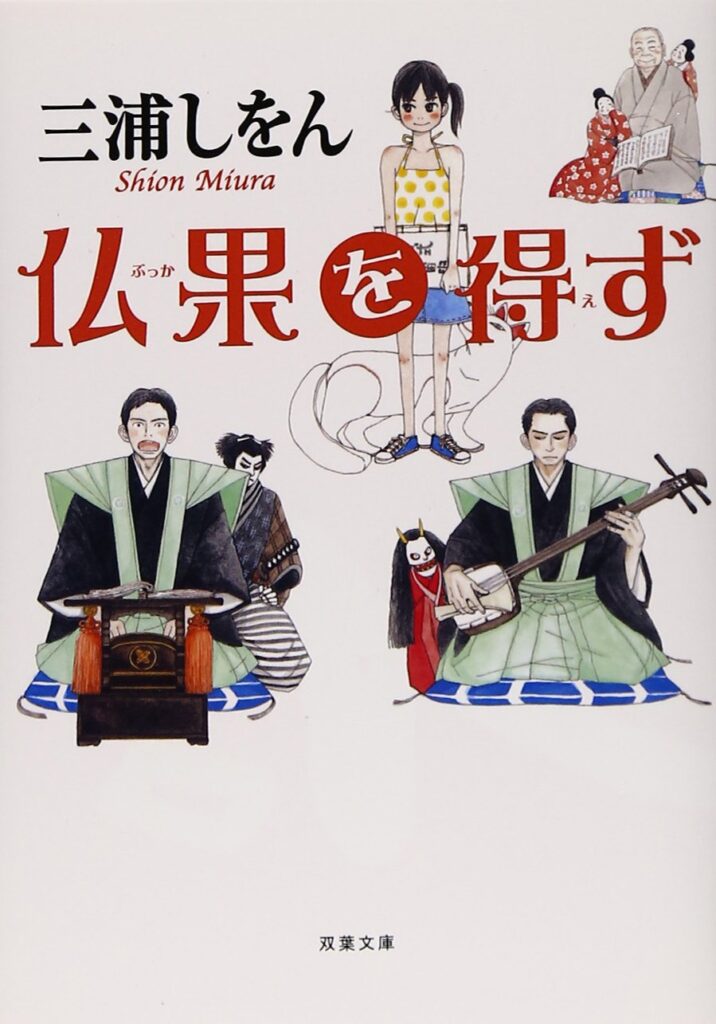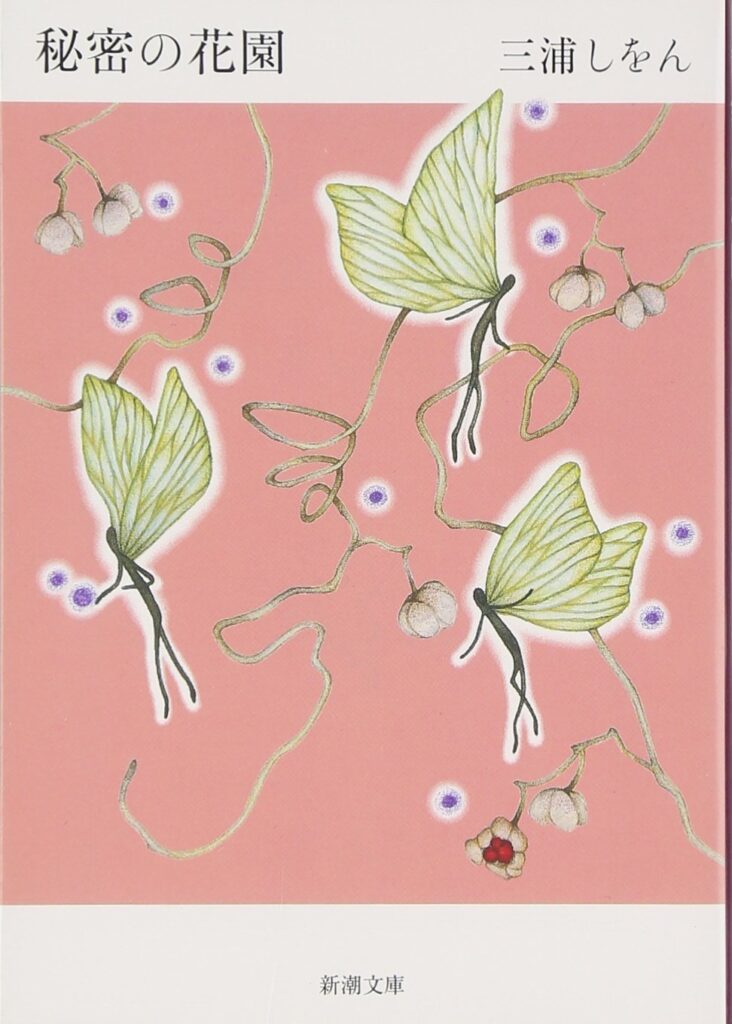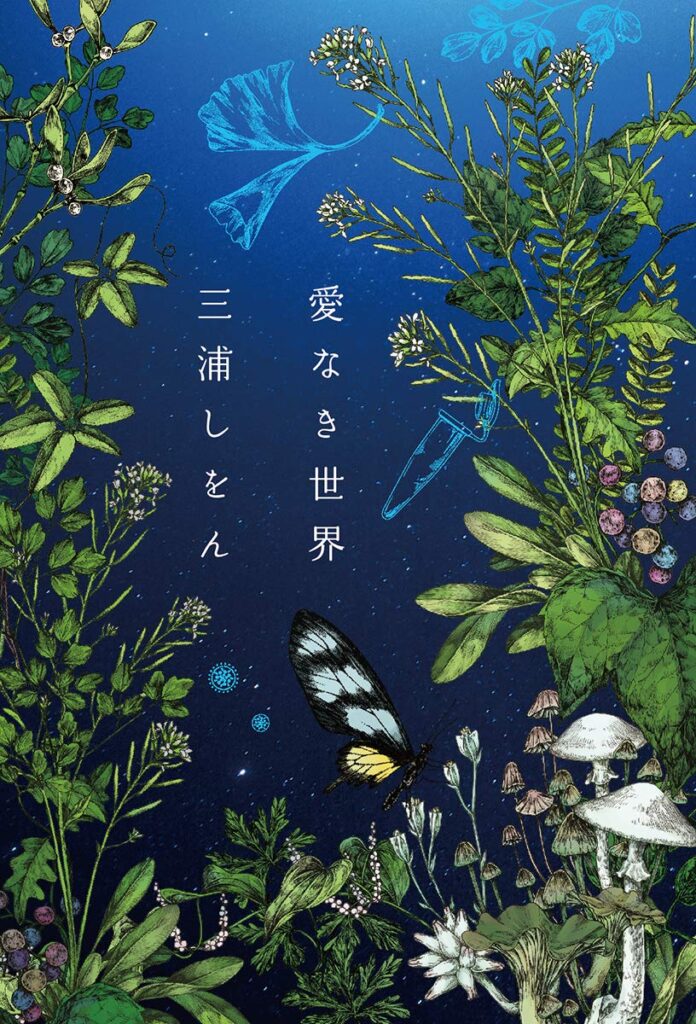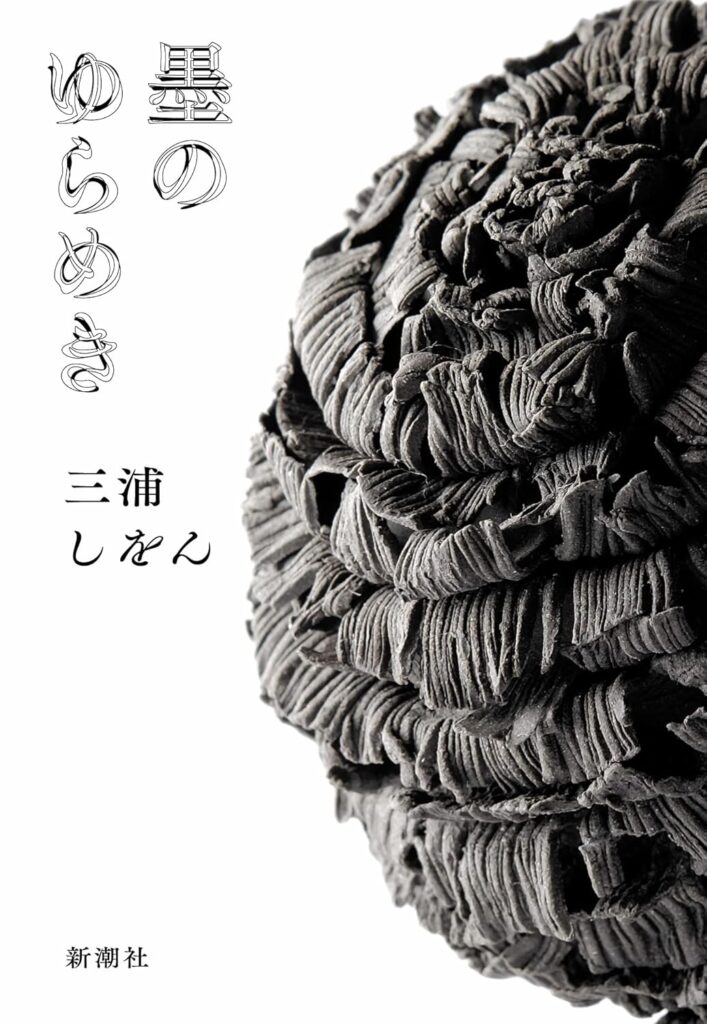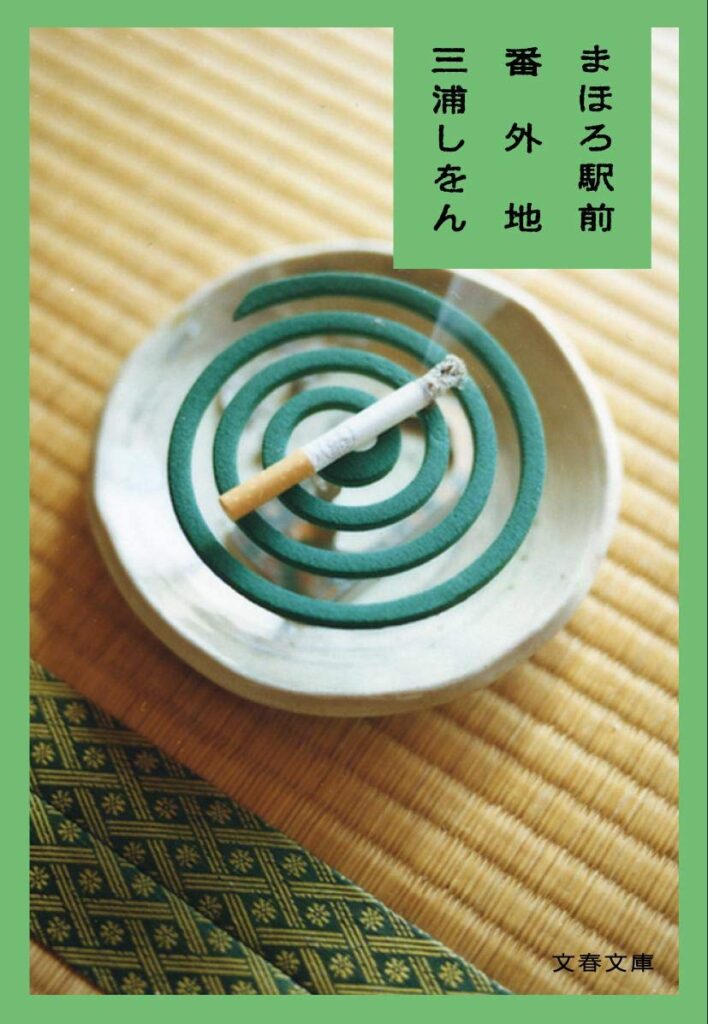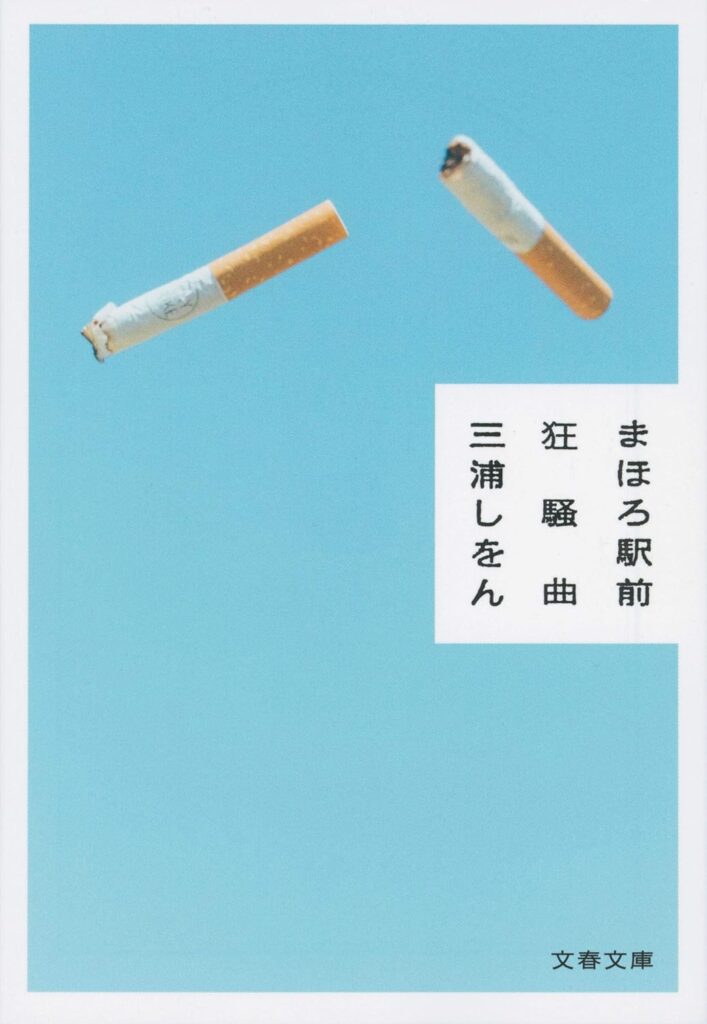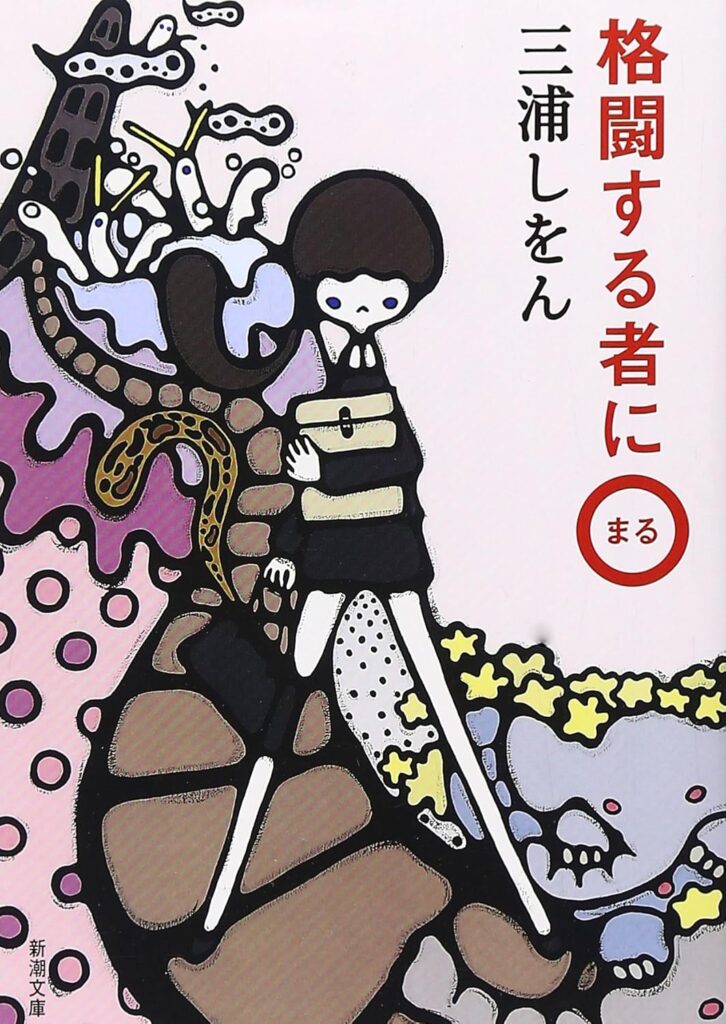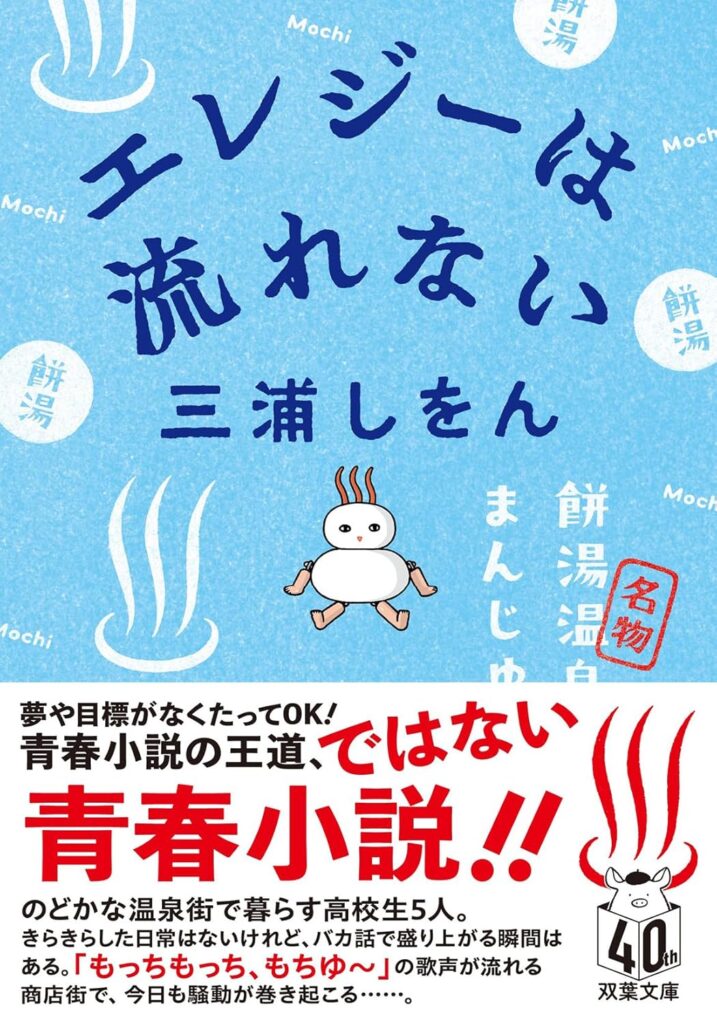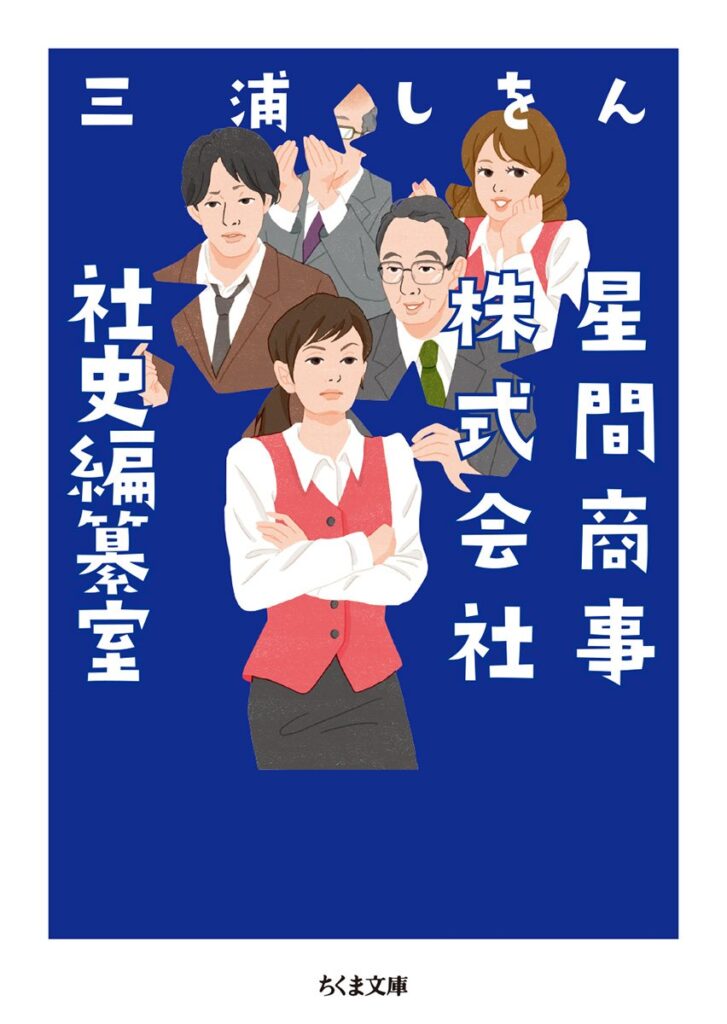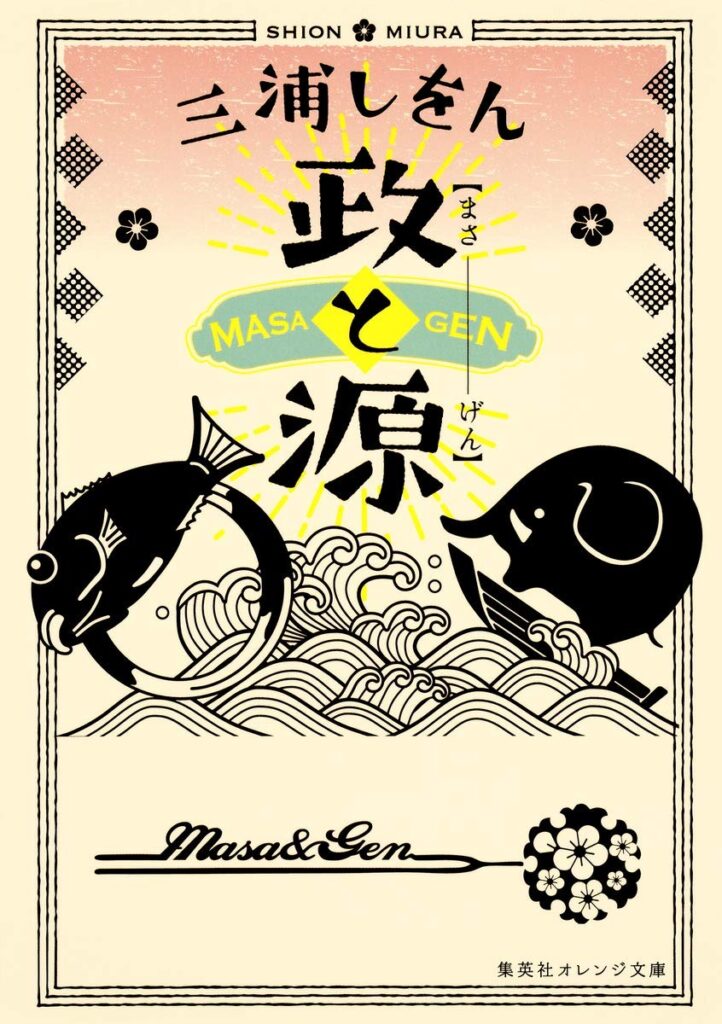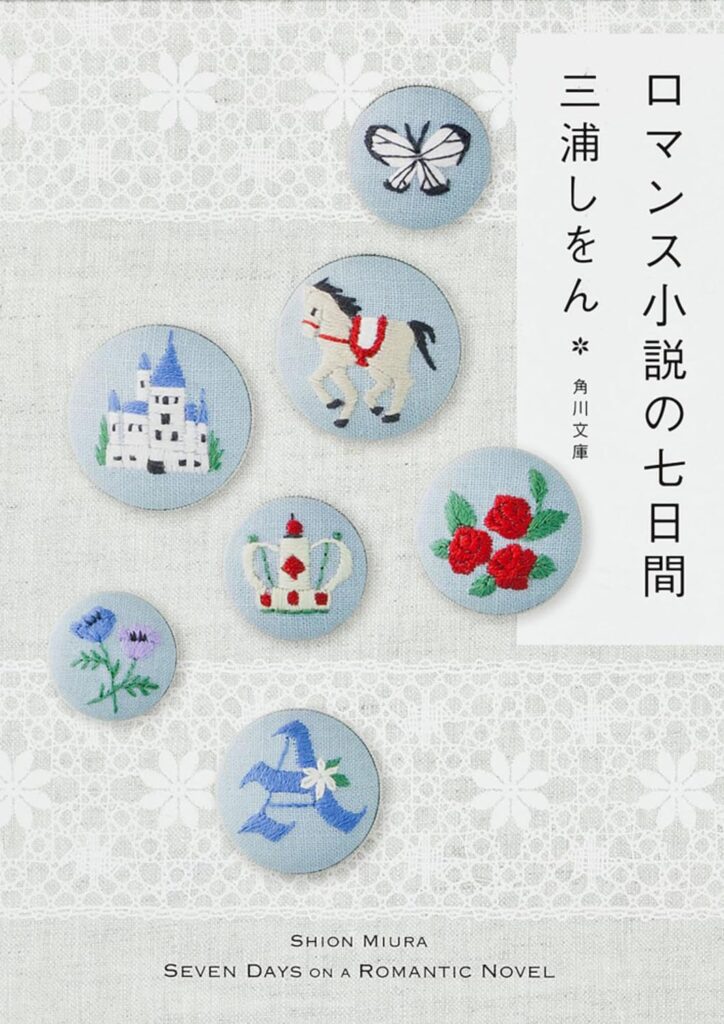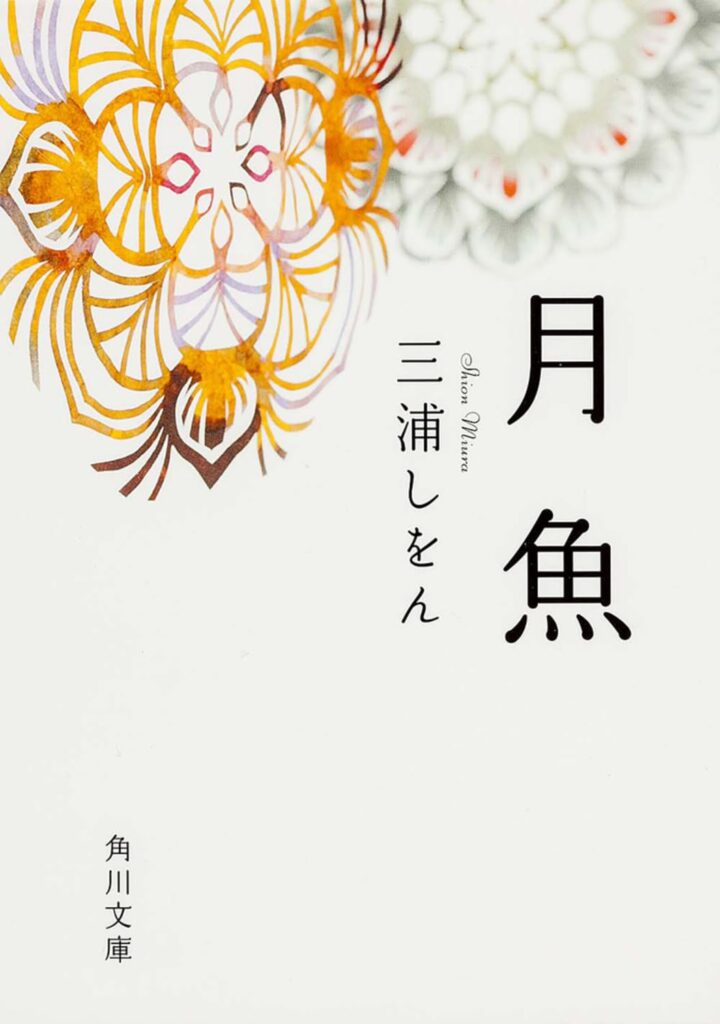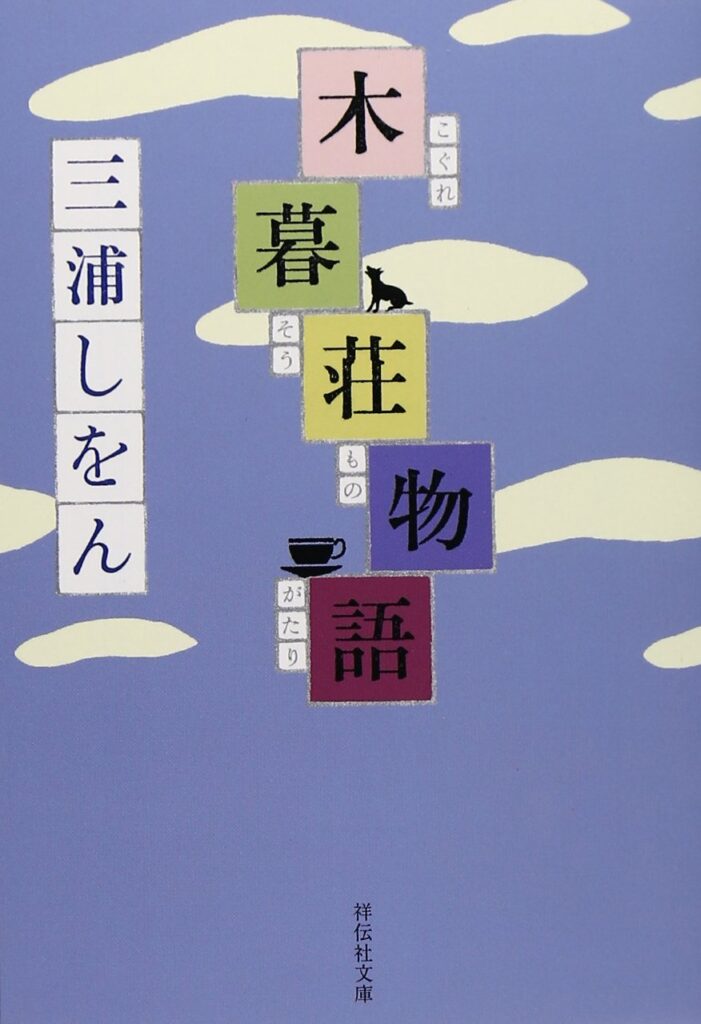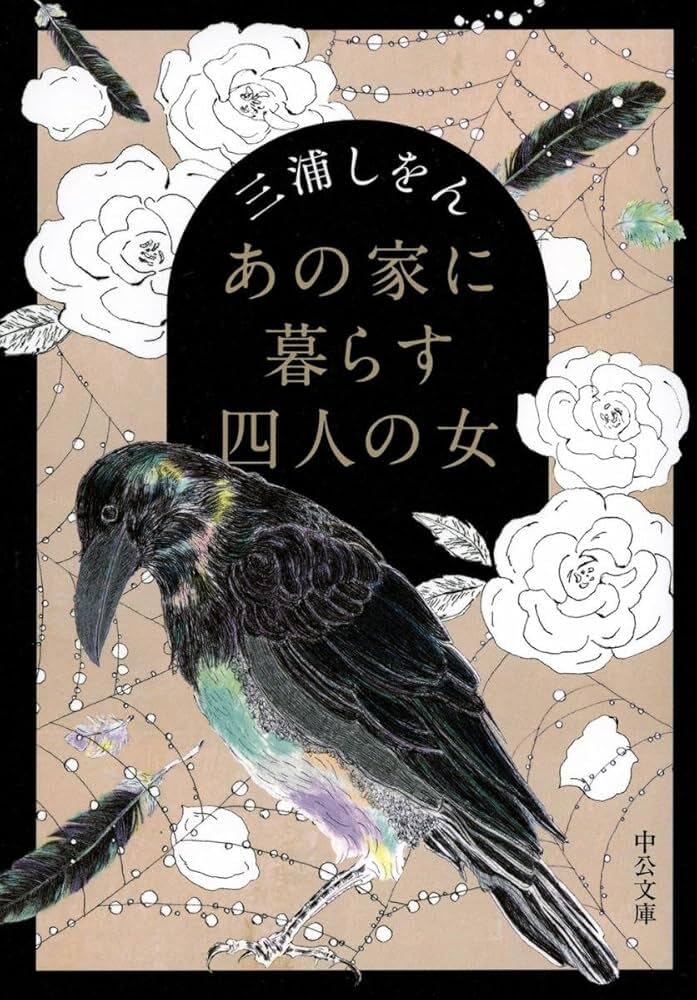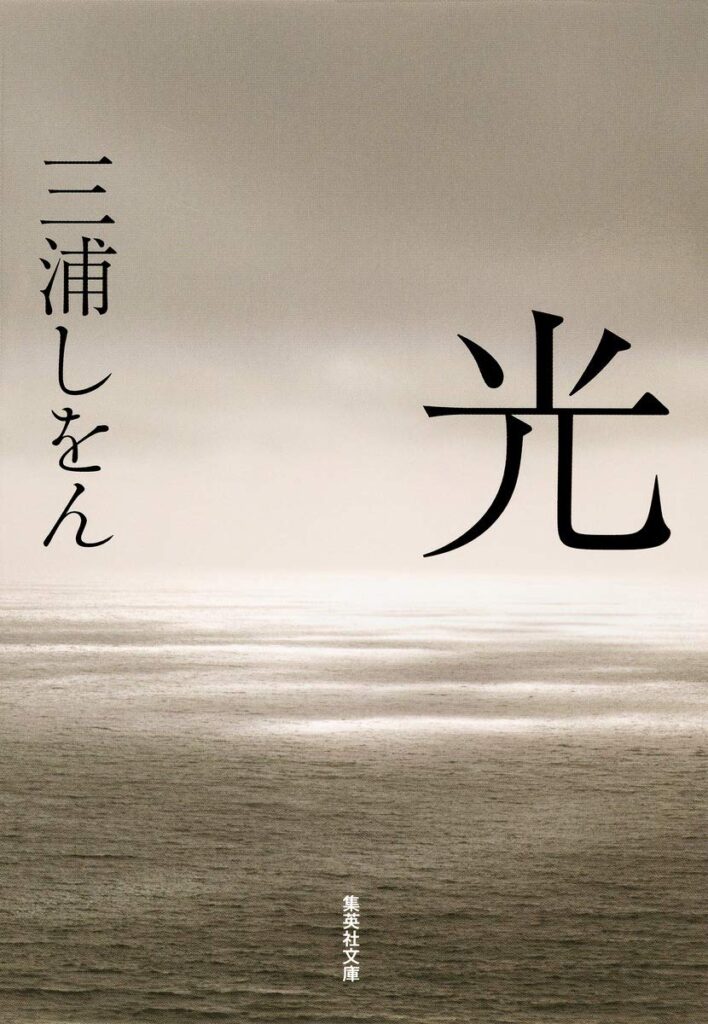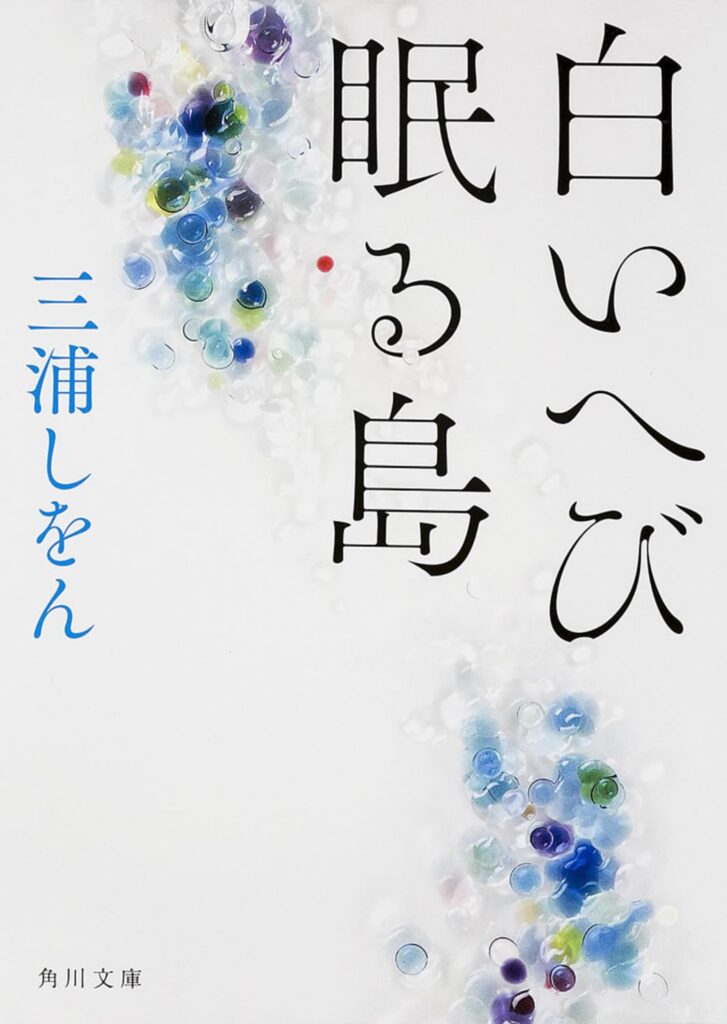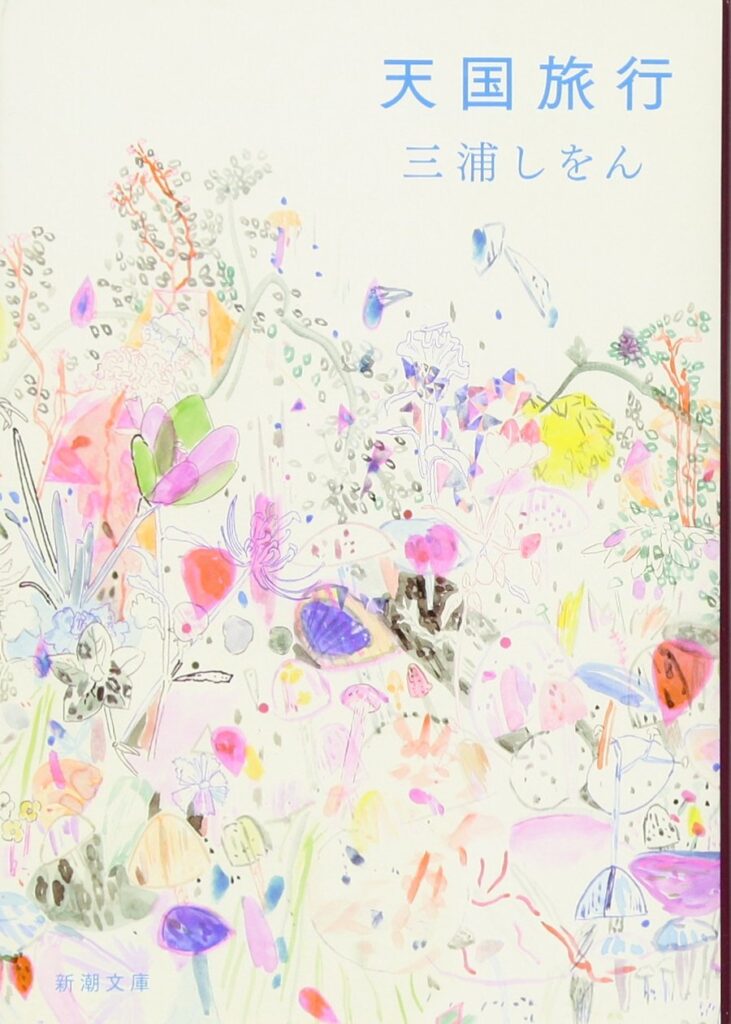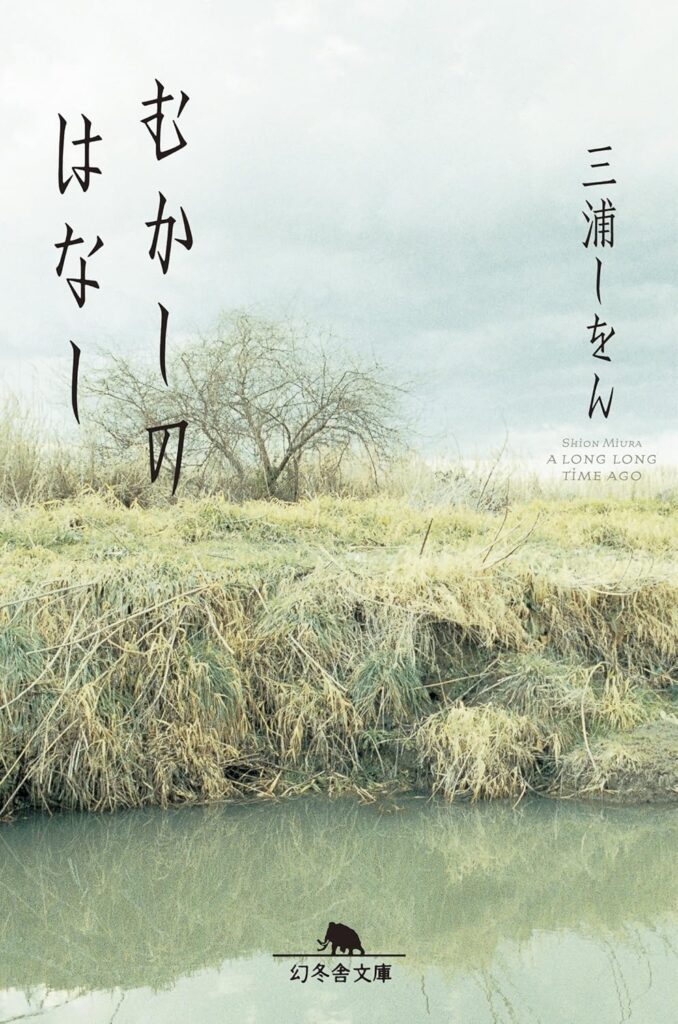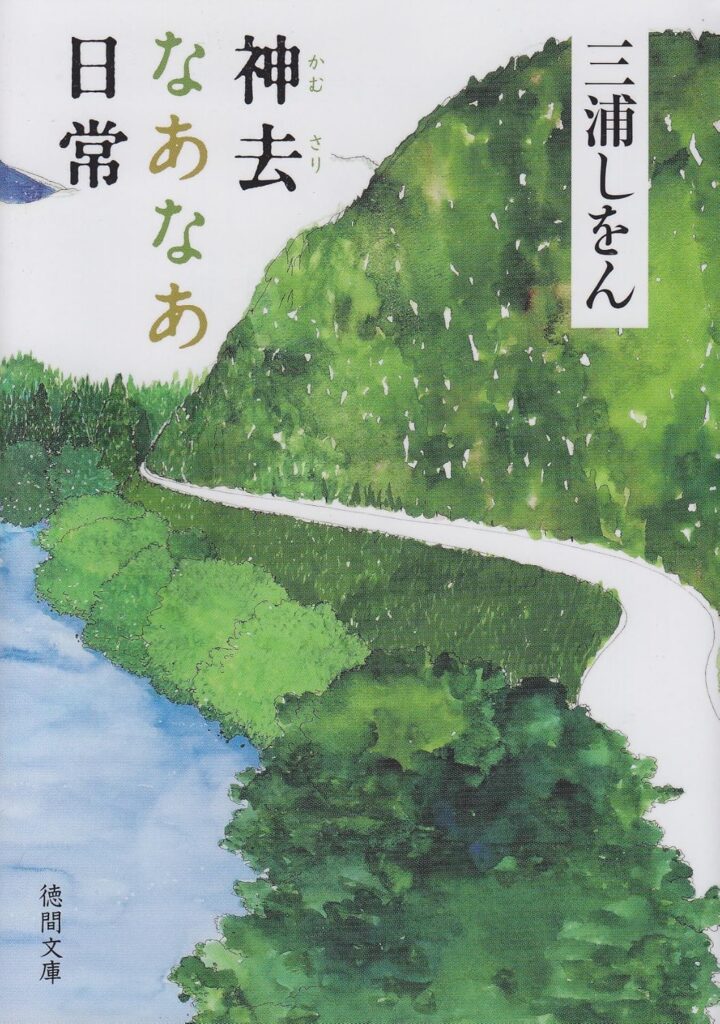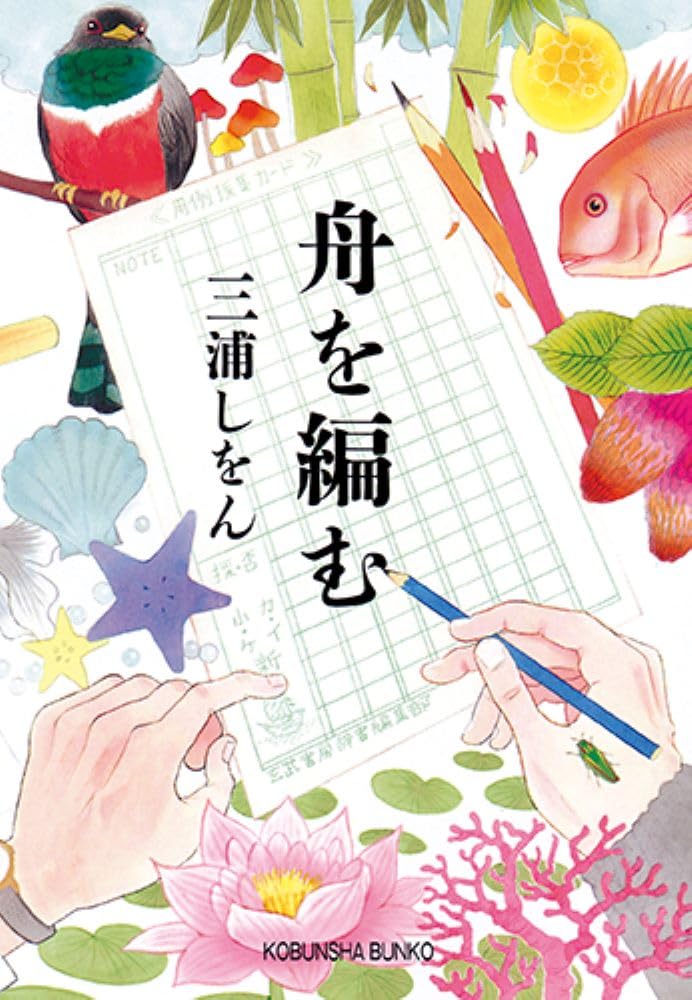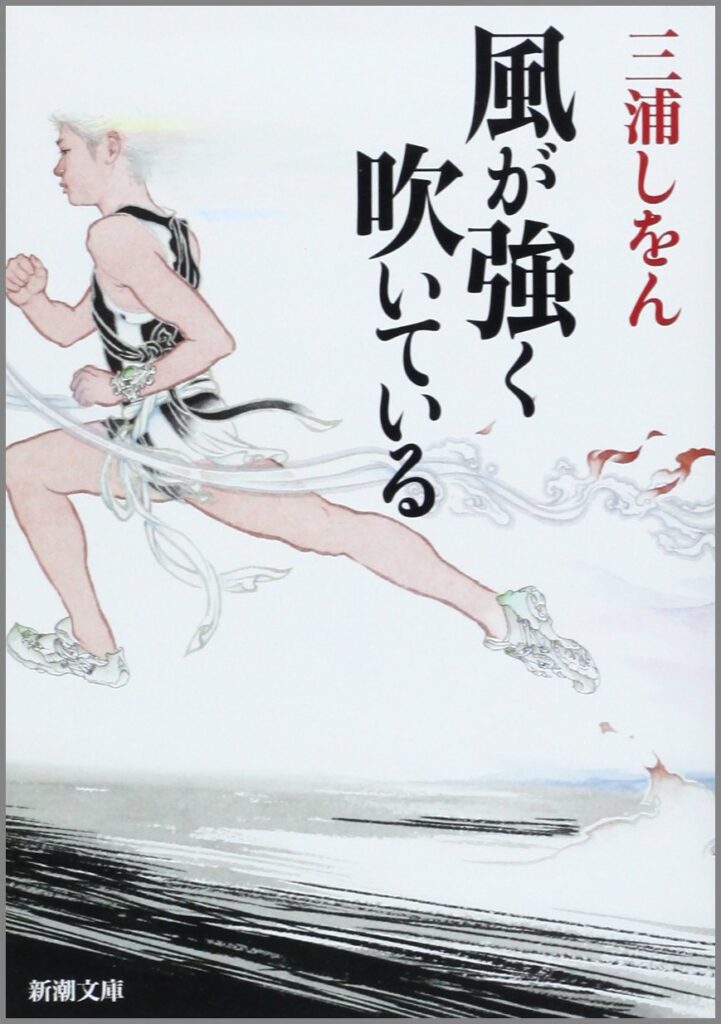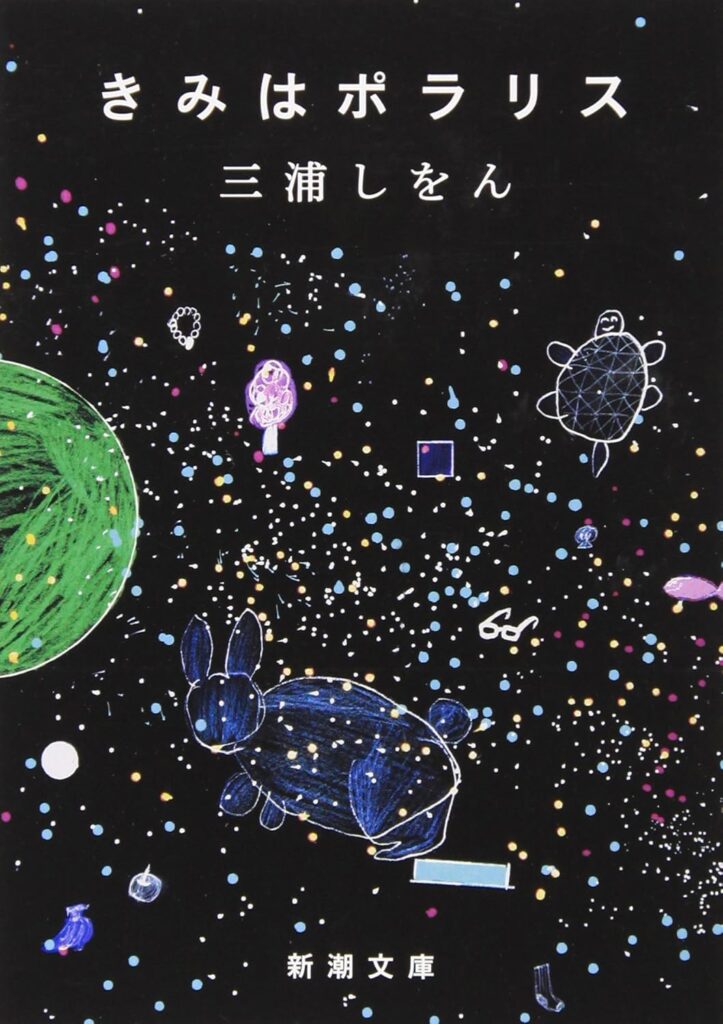小説「まほろ駅前多田便利軒」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、東京のはずれに位置するとされる架空の都市、まほろ市で便利屋を営む多田啓介と、彼の元に転がり込んできた高校時代の同級生、行天春彦の日常と、彼らが関わる様々な出来事を描いています。
小説「まほろ駅前多田便利軒」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。この物語は、東京のはずれに位置するとされる架空の都市、まほろ市で便利屋を営む多田啓介と、彼の元に転がり込んできた高校時代の同級生、行天春彦の日常と、彼らが関わる様々な出来事を描いています。
まほろ市という街自体が、まるで生きているかのように物語の中で重要な役割を果たしています。そこは、都会の喧騒と郊外ののどかさが混ざり合い、さまざまな問題を抱えた人々が暮らす場所。多田便利軒に舞い込む依頼は、そんな街の縮図のようです。小さなことから、時には少しばかり危険なことまで、二人は淡々と、しかしどこか人間味あふれる形でこなしていきます。
この記事では、多田と行天、そして彼らを取り巻く人々の織りなす物語の詳しい筋立てに触れながら、彼らの関係性や心の動き、そして作品全体から感じ取れるテーマについて、私なりの解釈を交えつつ深く掘り下げていきたいと思います。読み進めていただくことで、この作品が持つ独特の空気感や、登場人物たちの魅力、そして物語の奥深さを感じていただければ幸いです。
どうぞ最後までお付き合いくださいませ。この作品が描き出す、どこか切なくて、でも温かい世界を一緒に味わっていきましょう。
小説「まほろ駅前多田便利軒」のあらすじ
物語は、バツイチでどこか影のある男、多田啓介が経営する「多田便利軒」から始まります。彼は、まほろ市の駅前で、小さな事務所兼住居を構え、様々な依頼をこなして日々を暮らしていました。ある年の正月、多田はバス停で偶然、高校時代の同級生であった行天春彦と再会します。行天は薄汚れた格好で、行くあてもない様子。多田はためらいながらも、彼を事務所に連れ帰り、二人の奇妙な同居生活がスタートします。
行天は掴みどころがなく、自由奔放な性格。口数は少ないものの、時折核心を突くようなことを言ったり、大胆な行動に出たりして、多田を驚かせます。便利屋の仕事は多岐にわたり、老婦人の話し相手から、子どもの塾の送迎、ペットの世話、さらにはちょっときな臭い筋からの依頼まで様々です。多田は真面目に、行天は飄々と、時には衝突しながらも、二人でこれらの依頼に取り組んでいきます。
物語は連作短編のような形で進み、一つ一つの依頼が、まほろ市に住む人々の抱える孤独や問題、そして人間模様を浮き彫りにしていきます。風俗嬢、薬物の売人、家庭内に問題を抱える少年、過去に傷を持つ人々。多田と行天は、彼らと関わる中で、否応なく街の暗部や人間の複雑な感情に触れていくことになります。
特に、行天の謎めいた過去が徐々に明らかになるにつれて、物語は不穏な様相を帯び始めます。彼がかつて関わっていた人間関係や、彼自身が抱える心の傷が、現在の二人の生活にも影を落とすようになります。ある事件では、行天が何者かに襲われ、深刻な事態に陥ることも。
一方で、多田もまた、自身の過去のトラウマ――幼い我が子を失ったこと、そしてそれが原因で妻と離婚したこと――と向き合うことになります。ある女子高生が両親を殺害した事件の調査に関わった際、その悲劇的な背景が、多田自身の心の奥底にしまい込んでいた痛みを呼び覚ますのです。
様々な出来事を経て、互いの過去や弱さを知り、ぶつかり合いながらも、多田と行天の間には言葉では言い表せないような不思議な絆が育まれていきます。行天が一度は事務所を出て行きますが、やがて戻ってくるというエピソードは、二人の関係性が新たな段階に入ったことを示唆しています。彼らは、傷を抱えたまま、それでも前を向いて生きていこうとするのです。
小説「まほろ駅前多田便利軒」の長文感想(ネタバレあり)
「まほろ駅前多田便利軒」を読み終えてまず感じるのは、登場人物たちが持つ、どうしようもないほどの「ままならなさ」と、それでも確かにそこにある「温もり」です。多田と行天、この二人の主人公の関係性は、決して一般的な友情やパートナーシップの形には収まりきらない、独特の引力とバランスで成り立っています。
多田啓介は、過去のトラウマから抜け出せず、どこか人生を諦観しているような雰囲気を漂わせています。彼の真面目さや誠実さは、便利屋という仕事を通して垣間見えますが、それは同時に、人と深く関わることを避けているようにも映ります。彼がかつて経験した、子供の死と妻との離別は、彼の心に深い影を落とし、新たな関係を築くことへの臆病さにつながっているのでしょう。
そこへ現れるのが、行天春彦です。彼はまさに多田とは対照的な存在。飄々としていて、何を考えているのか分からない。しかし、その一方で、物事の本質を見抜く鋭さや、他人の痛みに寄り添える優しさを秘めています。彼の過去もまた複雑で、幼少期の家庭環境や経験が、彼の特異なパーソナリティを形成したことがうかがえます。行天の存在は、多田の静かで閉じた日常に波紋を投げかけ、彼を否応なく変化へと導いていきます。
物語は、まほろ市という架空の街を舞台に展開されますが、この街の描写がまた秀逸です。猥雑で、どこか寂れていて、でも人々の生活の匂いが確かにそこにある。そんなまほろ市は、多田と行天が請け負う様々な依頼と見事にリンクしています。ペット探し、子守り、家の片付けといった日常的なものから、少しばかり危ない橋を渡るようなものまで。これらの依頼を通して、現代社会が抱える孤独、貧困、家族の問題などが、リアルな手触りをもって描かれます。
特に印象に残るのは、由良少年と関わるエピソードです。ネグレクトされている少年を気にかける多田と行天の姿には、彼らの不器用な優しさが表れています。多田の中にある父性の目覚めや、行天の子供に対する意外なまでの共感が、胸を打ちます。このエピソードは、血のつながりだけではない、人と人との結びつきの可能性を示唆しているように感じました。
また、行天が過去の因縁から刺されてしまう事件は、物語の大きな転換点となります。この出来事によって、行天の隠された過去や脆さが露わになり、多田は行天という存在の重みを改めて認識します。そして、多田自身も、芦原園子の事件を通して、自らのトラウマと向き合うことを余儀なくされます。虐待の末に両親を殺害した少女の姿は、多田にとって、過去の悲劇と罪悪感を呼び覚ます強烈な鏡となったのです。
これらの出来事を経て、二人の関係はより深く、複雑なものへと変化していきます。彼らは互いの傷に触れ、痛みを共有し、時には反発しながらも、なくてはならない存在として互いを認識するようになります。行天が一度事務所を出て行く場面は、読んでいるこちらも胸が締め付けられるようでしたが、彼の帰還は、言葉にはならない確かな絆がそこにあることを証明してくれました。
この物語の魅力は、決して綺麗事ではない現実を描きながらも、どこかに救いを感じさせてくれる点にあると思います。登場人物たちは皆、何かしらの欠落や傷を抱えて生きています。しかし、そんな彼らが、偶然出会い、関わり合う中で、ほんの少しずつ変化し、再生していく姿が描かれます。多田が最後に抱く「幸福は再生する」という思いは、この物語のテーマを象徴していると言えるでしょう。
行天の存在は、多田にとって、そして読者にとっても、一種の触媒のようなものなのかもしれません。彼の予測不可能な言動は、停滞した日常に風穴を開け、隠されていた感情や問題を表出させます。そして、その過程で生じる摩擦や混乱の中から、新たな関係性や希望の光が生まれてくるのです。
まほろ駅前多田便利軒という場所は、単なる仕事場ではなく、傷ついた魂が寄り添い、再生するためのシェルターのような役割を果たしています。多田と行天が築き上げた関係は、従来の家族の形とは異なりますが、そこには確かな温もりと安心感が存在します。彼らは互いに依存し合うわけではなく、かといって完全に自立しているわけでもない。その絶妙な距離感が、この物語にリアリティと深みを与えています。
読み終えた後、多田と行天のこれからに思いを馳せずにはいられません。彼らの便利屋稼業は続いていくでしょうし、また新たな事件や出会いが待っているのかもしれません。しかし、どんな困難が待ち受けていようとも、この二人ならきっと乗り越えていけるだろう、そんな確信めいたものを感じさせてくれます。
この作品は、人間関係の複雑さや、生きることのままならなさを描きつつも、人と人との間に生まれるささやかな希望や温もりを丁寧に拾い上げています。派手な出来事や劇的な展開があるわけではありませんが、じんわりと心に染み渡るような、味わい深い物語でした。
まほろ市の雑踏の中で、多田と行天が今日も誰かの「困った」に耳を傾けている姿を想像すると、なんだか少しだけ心が軽くなるような気がします。彼らの存在は、社会の片隅で生きる人々の小さな灯りのようです。
この物語を通じて、私たちは、完璧ではない人間同士が、それでも支え合い、共に生きていくことの尊さを改めて教えられるのかもしれません。そして、どんな過去を抱えていても、未来には再生の可能性があるのだということを。
まとめ
小説「まほろ駅前多田便利軒」は、便利屋を営む多田啓介と、彼の元に転がり込んできた同級生・行天春彦の、どこかぎこちなくも温かい日々を描いた物語です。彼らは、まほろ市という、様々な顔を持つ街で、大小さまざまな依頼をこなしながら、互いの過去や心の傷と向き合っていきます。
一つ一つのエピソードは、現代社会が抱える問題や、そこに生きる人々の孤独、そして人間関係の複雑さを映し出しています。多田と行天は、依頼を通して出会う人々と関わる中で、否応なくそうした現実に直面し、時には危うい状況に巻き込まれることもあります。
しかし、この物語の核となるのは、やはり多田と行天という二人の関係性です。それぞれに癒えない過去を抱え、不器用ながらも互いを必要とし、支え合う姿は、読む者の心に深く響きます。彼らの間には、言葉では表しきれないような、静かで確かな絆が育まれていくのです。
決して派手さはありませんが、日常の中に潜む小さな事件や心の機微を丁寧に描き出し、読後にはじんわりとした温かさと、かすかな希望を感じさせてくれる作品です。傷つきながらも再生しようともがく人々の姿は、私たち自身の人生にも重なり、静かな共感を呼ぶことでしょう。