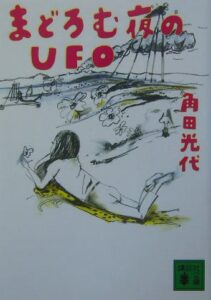 小説「まどろむ夜のUFO」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
小説「まどろむ夜のUFO」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。
角田光代さんの初期の作品を集めた短編集ですね。表題作を含めて三つの物語が収められています。発表されたのは1993年から95年にかけてということで、作家としてのキャリアの早い段階で書かれたものたちです。
この時期の角田さんの作品には、後の円熟味とはまた違う、若々しい感性や、どこか定まらない不安定な空気感が漂っているように感じられます。日常の中にふと現れる非日常のかけらや、人と人との間の微妙な距離感、言葉にならない思いなどが、独特の筆致で描かれています。
この記事では、そんな「まどろむ夜のUFO」に収められた各編の物語の筋立てを、結末にも触れながら詳しくお伝えし、さらに、私が読んで感じたこと、考えたことを、少し長くなりますが、じっくりと語っていきたいと思います。初期作品ならではの魅力や、少し戸惑う部分も含めて、率直な思いを綴っていきますね。
小説「まどろむ夜のUFO」のあらすじ
この短編集「まどろむ夜のUFO」には、表題作の「まどろむ夜のUFO」のほかに、「もう一つの扉」、「ギャングの夜」という三つの物語が収められています。それぞれ独立したお話ですが、どこか通底する空気感があるように思います。
まず表題作「まどろむ夜のUFO」です。主人公の「私」には、少し風変わりな弟がいます。ある日、その弟が「彼女ができた」と言い出します。しかし、その彼女というのが、どうも普通の存在ではないようなのです。弟は、夜中にUFOが迎えに来て、彼女と一緒にそれに乗ってどこかへ行くのだ、と真顔で語るのです。
弟の言葉をにわかには信じられない「私」ですが、彼の部屋からは奇妙な音が聞こえたり、ベランダには焦げ跡のようなものが見つかったりと、不思議な出来事が続きます。弟の話は本当なのでしょうか。それとも、彼の孤独が生み出した妄想なのでしょうか。
「私」は弟の真意を探ろうとしますが、核心にはなかなか触れられません。弟は多くを語らず、ただ夜空を見上げているばかり。結局、弟に本当に彼女がいたのか、UFOは実在したのか、明確な答えは示されないまま、物語はどこかぼんやりとした、掴みどころのない余韻を残して終わります。弟の語る不思議な話は、彼の寂しさの裏返しだったのかもしれない、そんな想像をさせる結末です。
二編目の「もう一つの扉」は、ルームシェアを繰り返す女性が主人公です。最初は友人との共同生活でしたが、友人の引っ越しなどを経て、いつしか見知らぬ人とも抵抗なく部屋を共有するようになります。ただし、「男性とはシェアしない」というルールだけは守っていました。しかし、ある時、失踪した元同居人の彼氏が「住みたい」と言い出し、主人公はそれを受け入れてしまいます。奇妙な同居生活が始まりますが、二人の間に男女の関係はありません。どこか現実離れしたような、不思議な空気感の中で物語は進み、ラストは幻想的な雰囲気で締めくくられます。
三編目の「ギャングの夜」は、主人公の若い女性が、独身の叔母に誘われて温泉旅行に行く話です。叔母はエネルギッシュで活動的な人物に見えますが、その裏には深い孤独を抱えていることが伺えます。友人や恋人がおらず、一度も男性と付き合ったことがないという事実が、物語の中で明かされます。主人公は、そんな叔母に対して、どこか憐れみのような感情を抱きつつ、旅行に付き合います。並行して、主人公自身のあまり上手くいっていない彼氏・春男との関係も描かれ、登場人物たちの抱える寂しさやうまくいかない現実が浮き彫りにされます。
小説「まどろむ夜のUFO」の長文感想(ネタバレあり)
さて、ここからは「まどろむ夜のUFO」を読んだ私の詳しい思いを、物語の結末にも触れながら、自由に語らせていただこうと思います。初期作品集ということで、後の角田作品とはまた違った味わいがありますね。
まず表題作「まどろむ夜のUFO」ですが、正直に申し上げると、最初に読んだ時は少し戸惑いを覚えました。弟が語るUFOの話、彼女の話。これが現実なのか、それとも彼の作り話なのか、最後まで判然としないまま終わります。この曖昧さが、もしかしたらこの作品の持ち味なのかもしれませんが、私のような、つい物語に明確な答えや着地点を求めてしまう読者にとっては、少々物足りなさを感じてしまう部分もありました。参考にした文章にあったように、「ハイティーンの女子が空想を頼りに創作した作品」という手厳しい評価も、設定だけを見ると、なるほど、そう感じられる部分もあるかもしれません。
ただ、それは表面的なストーリーラインだけを追った場合の話であって、もう少し深く読み込んでみると、違った景色が見えてくるようにも思います。弟の語るUFOの話は、彼の内面に渦巻く孤独感や、現実世界への適応の難しさ、あるいは非日常への強い憧れの表れと解釈することもできるのではないでしょうか。彼が「彼女がいる」と嘘をついた(のかもしれない)のは、姉である「私」に対する精一杯の虚勢だったのかもしれませんし、あるいは、彼にとってはその「彼女」や「UFO」こそが、現実よりもよほど確かな存在だったのかもしれません。
弟と「私」の関係性も、非常に興味深い点です。姉弟でありながら、どこか微妙な距離感があり、お互いの心の内を探り合っているようでいて、核心には触れられないもどかしさが漂っています。弟の不可解な言動に対して、「私」は心配し、理解しようと努めますが、結局、弟の世界に入り込むことはできません。このコミュニケーションの断絶、理解しきれない他者の存在というテーマは、後の角田作品にも通じるものがあるように感じます。弟が本当に「不思議君」だったのか、それとも何か別の理由があったのか。その答えを探そうと真剣に考える気持ちに、すぐにはなれなかった、というのも正直なところです。ただ、それもまた一つの読み方として、ありなのかもしれません。
次に「もう一つの扉」。これは、ルームシェアという設定が現代的で面白いと感じました。主人公が、最初は友人、そして次第に見ず知らずの人へと、シェアする相手を変えていく過程は、現代における人間関係の流動性や希薄さを象徴しているようにも思えます。誰かと一緒にいたい、けれど深く関わるのは怖い、というようなアンビバレントな感情が、主人公の行動の根底にあるのかもしれません。
特に印象的だったのは、失踪した元同居人の彼氏との奇妙な共同生活です。男女が一つ屋根の下に暮らしながら、性的な関係には至らない。そこには緊張感と同時に、ある種のプラトニックな、あるいは無機質な関係性が描かれています。この距離感が、かえって二人の孤独を際立たせているようにも感じられました。ラストシーンの幻想的な雰囲気は、現実からの逃避願望のようにも、あるいは新しい関係性の始まりのようにも解釈でき、読後に様々な想像を掻き立てられます。この作品にも、「失踪」というモチーフが登場しますね。角田さんの作品において、「失踪」は重要な要素の一つなのかもしれません。
そして三編目の「ギャングの夜」。これは個人的に、三編の中で最も心に残った作品です。短い物語の中に、登場人物たちの人生の陰影が濃密に描かれていると感じました。パワフルで行動的に見える叔母が、実は深い孤独を抱えているという設定は、胸に迫るものがあります。「一度も男性と付き合ったことがない」という告白は、彼女のこれまでの人生や、人知れぬ寂しさを想像させます。
主人公が叔母に対して抱く、少し憐れみを含んだような視線も、リアルで印象的でした。年下の自分が、どこか「付き合ってあげている」というような、無意識の優越感。これは、私自身にも覚えがあるような感覚で、少しドキリとさせられました。人間関係の中に潜む、こうした微妙な力関係や感情の機微を描き出すのが、角田さんは本当に巧みだと思います。
また、主人公自身の恋愛模様、あまり魅力的とは言えない彼氏・春男との関係が挿入されることで、物語に奥行きが生まれています。叔母の孤独と、主人公自身のうまくいかない現実が対比され、登場人物たちがそれぞれに抱える人生のままならさ、やるせなさが伝わってきます。参考文章にもありましたが、角田さんの小説には、どこか「ダメな人」というか、うまくいかない状況の中でもがきながら生きている人々が登場することが多いように感じますね。そして、その姿に妙に共感してしまうのです。
この三編を通して感じたのは、角田光代という作家の初期衝動のようなものです。まだ洗練されきっていない部分や、物語の着地点が曖昧な部分もありますが、そこには瑞々しい感性や、人間の内面に対する鋭い洞察力の萌芽が確かに感じられます。特に、若い女性の視点から描かれる日常の閉塞感や、人との繋がりを求めながらも上手く関係を築けないもどかしさ、言葉にならない感情の揺らぎといったテーマは、この頃から既に角田さんの作品世界の中核を成していたのだな、と感じ入りました。
後の代表作、例えば「対岸の彼女」などと比較してみると、その変化と深化は明らかです。「対岸の彼女」では、女性同士の友情と亀裂、あるいは社会の中で生きていくことの困難さといったテーマが、より深く、多層的に掘り下げられています。小夜子と葵という二人の女性の生き様を通して、「人と出会うことの意味」「歳を重ねることの意味」「孤独とどう向き合うか」といった普遍的な問いが投げかけられます。
「まどろむ夜のUFO」に登場する人物たちもまた、それぞれの形で「出会い」を経験し、「孤独」と向き合っています。「まどろむ夜のUFO」の弟は、現実の人間関係から距離を置き、UFOや架空の彼女との「出会い」に救いを求めたのかもしれません。「もう一つの扉」の主人公は、次々と相手を変えるルームシェアという形で、刹那的な「出会い」を繰り返しながらも、深い孤独からは逃れられずにいます。「ギャングの夜」の叔母は、「出会い」を渇望しながらも、それを得られずにいるように見えます。
「対岸の彼女」で描かれたように、「出会い」が人生を前に進めるための「熱源」となりうるのだとすれば、「まどろむ夜のUFO」の登場人物たちは、まだその「熱源」をうまく見つけられずに、まどろんでいる状態なのかもしれません。彼らの抱える孤独や不安は、「対岸の彼女」の小夜子や葵が抱えるものと、本質的には繋がっているのではないでしょうか。ただ、その描き方や物語の résolution(解決)の仕方が、初期と後では異なっているのだと感じます。
「まどろむ夜のUFO」の読後感は、すっきりとしたカタルシスというよりは、どこか靄のかかったような、考えさせられる余韻が残るものです。それは、登場人物たちが抱える問題が、物語の中で明確に解決されるわけではないからでしょう。しかし、その解決されなさ、割り切れなさこそが、私たちの生きる現実の複雑さを映し出しているのかもしれません。角田光代さんの初期の、荒削りながらも強いエネルギーを秘めた作品世界に触れることができ、非常に興味深い読書体験でした。後の作品を知っているからこそ、その原点にあるもの、そして作家としての確かな歩みを感じ取ることができたように思います。
まとめ
角田光代さんの初期短編集「まどろむ夜のUFO」は、表題作を含む三つの物語を通して、若々しい感性と、後の作品にも通じるテーマの萌芽を感じさせてくれる一冊でした。物語の筋立ては、結末の曖昧さも含めてお伝えした通りです。
UFOを待つ弟、ルームシェアを繰り返す女性、孤独を抱える叔母。登場人物たちはそれぞれに、日常の中の違和感や、人との繋がりの難しさ、そして自身の内なる孤独と向き合っています。明確な答えや救いが示されるわけではありませんが、その宙吊りのような状態が、かえって私たちの心に深く響くのかもしれません。
私がこの本を読んで感じたのは、初期作品ならではの魅力と、少し戸惑う部分、そして作家・角田光代の原点ともいえる視点でした。その詳しい思いは、結末の内容にも触れながら、長文の感想として述べさせていただきました。
角田光代さんのファンの方はもちろん、日常に潜む不思議な感覚や、人間の心の機微に触れる物語を読んでみたいという方におすすめしたい作品集です。読後、登場人物たちの抱える思いや、物語の余韻について、じっくりと考えてみるのも良いのではないでしょうか。

























































