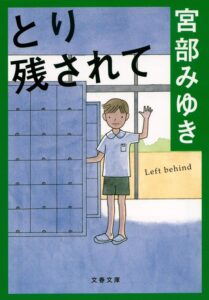 小説「とり残されて」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品の中でも、少し不思議で、心にずしりと響く短編集ですよね。表題作をはじめ、収録されている七つの物語は、どれも人間の心の奥底にある感情や、日常に潜むちょっとした歪み、そして時を超えた繋がりを描いていて、読み終わった後も深く考えさせられます。
小説「とり残されて」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。宮部みゆきさんの作品の中でも、少し不思議で、心にずしりと響く短編集ですよね。表題作をはじめ、収録されている七つの物語は、どれも人間の心の奥底にある感情や、日常に潜むちょっとした歪み、そして時を超えた繋がりを描いていて、読み終わった後も深く考えさせられます。
この短編集が発表されたのは1990年代ですが、今読んでも全く色褪せない魅力があります。それはきっと、描かれているテーマが普遍的だからなのでしょうね。悲しみ、憎しみ、愛情、後悔、希望…そういった感情は、時代が変わっても私たちの心の中に存在し続けるものですから。それぞれの物語が独立していながら、どこか通底する空気感があって、一冊を通して宮部みゆきさんの世界観に浸ることができます。
この記事では、まず表題作「とり残されて」の物語の筋道を詳しくお伝えします。少し怖い部分もありますが、物語の核心に触れていきますので、未読の方はご注意くださいね。そして、その後には、収録されている全七編について、私の心に残ったことや感じたことを、ネタバレを気にせずにたっぷりとお話ししていきたいと思います。それぞれの物語が持つ独特の味わいや、読後に残る余韻について、一緒に感じていただけたら嬉しいです。
小説「とり残されて」のあらすじ
物語の語り手である「わたし」は、小学校の養護教諭です。結婚を目前に控えていた大切な人を、不注意な運転による交通事故で突然失ってしまいました。加害者は免許取り立ての未成年の女性で、法的には軽い罰で済んでしまいます。やり場のない悲しみと怒りは、次第に加害者への強い復讐心へと変わっていきます。そんな日々の中、「わたし」は勤務先の小学校で不思議な体験をするようになります。誰もいないはずの廊下で子供の足音が聞こえたり、古い制服を着た見知らぬ男の子の姿を見かけたりするのです。
その男の子は、「わたし」の意識の中に直接語りかけてきます。「せんせい、あそぼ。プールへおいでよ」と。夢の中にまで現れるその声に導かれるように、ある朝、「わたし」はいつもより早く出勤し、小学校の屋外プールへと向かいます。すると、プールサイドにあの男の子が一瞬見えたかと思うと、水面には女性の遺体が浮かんでいたのです。第一発見者となった「わたし」は、警察から事情を聞かれることになります。被害者は、この小学校の教師である今崎明子(旧姓:伊藤)だと判明。彼女は何者かにハサミで刺殺されていたのです。
捜査が進む中、「わたし」は地元警察の少年課に勤める相川浩一という刑事から連絡を受けます。彼は、驚くべき事実を打ち明けます。相川は二十年前、この小学校の生徒で、当時教師だった伊藤明子とその恋人(後の夫である今崎行雄)から酷い仕打ちを受け、物置に一晩以上閉じ込められた過去があったのです。その時の恐怖と憎しみがあまりに強かったため、彼の思念が子供の姿となって学校に「とり残され」、明子への復讐を果たしたのではないか、と彼は考えていました。そして、相川は「わたし」が婚約者を失ったことによる強い復讐心を持っていること、その負の感情が、とり残された思念と共鳴したのではないかと示唆します。
さらに事態は動きます。校庭から古い不発弾が発見され、その処理のために自衛隊が出動する騒ぎとなる夜。「わたし」は、校舎に忍び込む相川刑事と、妻を殺され呆然とする今崎行雄(教頭であり、明子の夫)が対峙する場面を目撃します。その直後、原因不明の爆発が起こり、「わたし」は意識を失います。気が付くと、瓦礫の中で今崎行雄は死亡し、相川刑事も瀕死の状態でした。相川は「あなたがあいつを呼んだんですよ」という意味深な言葉を残し、息を引き取ります。「わたし」は、婚約者を奪われた自身の強い憎しみが、相川のとり残された思念を呼び覚まし、一連の事件を引き起こしたのだと悟るのでした。相川は復讐を遂げましたが、「わたし」の復讐はまだ終わっていません。「わたし」は、自分自身のとり残された思念を探しに、事故現場へと向かう決意をするのです。
小説「とり残されて」の長文感想(ネタバレあり)
宮部みゆきさんの短編集「とり残されて」、本当に読み応えがありました。七つの物語、それぞれが独立しているのに、どこか共通する「人の心の影」や「見えない繋がり」みたいなものを感じさせて、読み終わった後もしばらくその世界から抜け出せないような、そんな感覚に包まれましたね。特に表題作の「とり残されて」は、タイトルの意味がじわじわと心に染みてくるようで、読後感が深かったです。
まず、表題作「とり残されて」について。
主人公の「わたし」が抱える、婚約者を奪われたことへの深い悲しみと、加害者への抑えきれない憎しみ。この感情が、物語全体の重たい空気を作っていますよね。すごく共感できる部分なんです。理不尽な出来事で大切な人を失ったら、誰だって加害者を許せないと思う。法で裁かれても、それで気持ちが晴れるわけじゃない。その行き場のない感情が、復讐心という形をとるのは、すごく人間的な反応だと思うんです。
そこに、相川刑事の過去が絡んでくる。彼が子供の頃に受けた教師からの虐待。これもまた、許しがたい仕打ちですよね。そして、その時の強烈な恐怖と憎しみが、「思念」となって二十年間も小学校に「とり残されていた」という設定。これがもう、宮部さんらしいというか、ホラー的な要素でありながら、すごく切ないんです。相川刑事自身は、その思念に突き動かされるように生きてきて、ついに復讐を遂げるわけですが、その過程で「わたし」の復讐心と共鳴してしまう。
「あなたがあいつを呼んだんですよ」という相川の最期の言葉。これは重いですよね。「わたし」の憎しみが、眠っていた古い憎しみを呼び覚まし、悲劇を連鎖させてしまった。自分の負の感情が、意図せずとも誰かの運命を狂わせ、さらなる死を招いてしまったという事実に、「わたし」は打ちのめされます。でも、それで彼女の復讐心が消えるわけじゃない。むしろ、相川が自分の思念によって復讐を果たしたのを見て、「わたし」もまた、自分の「とり残された」思念を探しに行こうとする。このラスト、希望とも絶望ともつかない、なんとも言えない余韻が残りませんか? 復讐の連鎖は断ち切れないのか、という問いを突き付けられたような気がしました。人の強い想い、特に負の感情は、時空を超えて影響を与えうるのかもしれない、そんな怖さも感じました。
次に、「おたすけぶち」。
これは、以前別の短編集で読んだことがあったのですが、改めて読んでもゾッとしました。事故で亡くなったはずの兄が生きていた、という喜びも束の間、その裏には恐ろしい村の秘密が隠されている。閉鎖的な共同体が、自分たちの存続のために外部の人間を犠牲にするという構図は、人間のエゴイズムや集団心理の怖さを描いていますよね。兄を想う孝子の気持ちが、逆に彼女を危険に引きずり込んでしまう皮肉。助けを求める声が聞こえる「おたすけぶち」という名前自体が、もう罠なんですよね。怪談のような雰囲気もありつつ、人間の業の深さを感じさせる話でした。
「私の死んだ後に」は、打って変わって、すごく温かい気持ちになれる物語でした。
正直、最初は野球選手の主人公が刺されて…という展開で、スポーツものかな? と少し身構えたのですが、死の淵で出会う幽霊の女性との交流が、本当に感動的でした。彼女が、実は主人公が子供の頃に起こしてしまった事故の被害者だった、という事実が明かされた時、胸が締め付けられました。恨んでいてもおかしくないのに、彼女は主人公を励まし、生きる力を与えてくれる。そして、主人公も過去の過ちと向き合い、再起を誓う。
この物語は、死んでしまった後も、人の想いは残り、誰かを支える力になることがある、ということを教えてくれるようです。そして、どんな過去があっても、未来に向かって歩き出すことができるんだ、という希望を感じさせてくれました。他の作品が持つ影の部分とは対照的に、光を感じる一篇で、読後感がとても爽やかでした。こういう救いのある話も描けるのが、宮部さんの幅広さですよね。
「居合わせた男」は、ミステリー要素が強い作品でしたね。
特急列車で乗り合わせた女性たちの噂話から、自殺した上司の死の真相を探ろうとする鳥羽。彼の推理は冷静で的確なのですが、結末はなんとも後味が悪い。自殺した上司が見たのは、薬の副作用による幻覚ではなく、本当に事故死した部下の亡霊だったかもしれない。そして、鳥羽自身がその亡霊と間違われ、さらに別のOLが錯乱してしまう。偶然居合わせただけなのに、意図せず人を恐怖に陥れてしまう。
この話の怖さは、見えないものへの恐怖だけじゃなくて、「思い込み」や「勘違い」が引き起こす悲劇にもあると思うんです。人は、自分が信じたいように物事を解釈してしまうことがある。そして、その思い込みが、時には誰かを深く傷つけたり、取り返しのつかない事態を招いたりする。日常の中に潜む、ちょっとしたすれ違いや誤解が、実は大きな闇につながっているのかもしれない、と考えさせられました。前半の軽妙な雰囲気からの落差が、余計に結末の不気味さを際立たせていました。
「囁く」も、じわじわとくる怖さがありました。
「お札が話しかけてくる」という幻聴。最初は気のせいだと思っていたものが、実はもっと不穏な何かにつながっている。銀行員が囁きに従って「楽になった」という噂を聞いた男が、まるで救いを求めるかのように猟銃を手に走り去っていくラストシーンは、衝撃的でした。囁きは、その人の心の弱さや欲望につけ込んでくるのかもしれないですね。楽になりたい、解放されたいという願望が、破滅的な行動へと駆り立ててしまう。
この物語は、現代社会のストレスや孤独感とも結びつけて考えられるかもしれません。誰にも言えない悩みを抱えている人が、ふとしたきっかけで心のバランスを崩してしまう。その「きっかけ」が、もし「囁き」のような形をとって現れたら…? そう考えると、他人事とは思えない怖さがあります。タイトルの「囁く」が持つ意味が、読後に重くのしかかってきました。
「いつも二人で」は、幽霊に取り憑かれた男性の話ですが、これもまた一筋縄ではいかない展開でした。
若い女性の幽霊が、主人公の真琴に「身体を貸してほしい」と頼む。その目的は、かつての愛人だった会社の役員に復讐…ではなく、「一生共にあること」。この執念、すごいですよね。死んでなお、愛した(あるいは憎んだ?)相手のそばにいようとする。そのために、真琴を利用し、女装させてまで面接に送り込み、最後は役員に乗り移る。
計画の周到さや実行力の描写がリアルで、少しコミカルな感じもするのですが、根底にあるのは深い孤独と執着だと思うんです。生きていても死んでいても、誰かと繋がっていたい、忘れられたくない、という強い想い。幽霊の女性の行動は常軌を逸しているけれど、その根っこにある感情には、どこか同情してしまう部分もありました。愛憎って、本当に複雑ですよね。そして、利用された真琴にとっては、たまったものじゃないですが…。これもまた、奇妙な「とり残され方」と言えるのかもしれません。
そして、最後の「たった一人」。
この物語が、私は一番好きかもしれません。切なくて、儚くて、でもどこか温かい。毎晩見る不思議な場所の夢。その意味を知りたいと願う梨恵子。彼女が依頼した調査員の男性が、実はその夢の場所と深い関わりがあった、という運命的な展開に、読んでいて胸が高鳴りました。梨恵子と同じように、「きっとこの人が運命の人なんだ!」と信じたくなりました。
調査員の男性が、子供の頃、その場所で謎の声に命を救われたという過去。そして、その声の主が、もしかしたら梨恵子だったのかもしれない、という可能性。二人の間には、時を超えた不思議な繋がりがあったのかもしれない。そう思わせる展開が、本当に素敵でした。でも、彼は「本来死ぬはずだった運命を捻じ曲げてしまった」と感じ、梨恵子の前から姿を消してしまう。この結末が、本当に切ない。運命の相手に出会えたと思ったのに、その出会い自体が、何か良くないことを引き起こしたのかもしれない、という彼の後悔。
「信じるのも信じないのも自由だと思う」という作中の言葉が、心に残ります。梨恵子にとっては、彼との出会いは紛れもない事実で、運命だったと信じたいはず。でも、彼は消えてしまった。この物語は、目に見えない繋がりや運命というものを信じさせてくれる一方で、その儚さや、時には残酷さも突き付けてくるようです。梨恵子の気持ちを思うと、本当にやりきれない。でも、どこかでまた彼と再会できるんじゃないか、そんな淡い希望も抱かせてくれる、不思議な魅力のある物語でした。まるで、水面に映った月のように、掴もうとすると消えてしまうけれど、確かにそこにあると感じられる、そんな存在として、調査員の男性のことが梨恵子の心に残り続けるのかもしれません。
この短編集全体を通して感じるのは、やはり「とり残された」想いの力強さです。それは憎しみや後悔といった負の感情であることもあれば、「私の死んだ後に」や「たった一人」のように、誰かを支えたり、繋いだりする温かいものであることもある。人の想いは、簡単に消え去るものではなくて、様々な形でこの世に残り、影響を与え続けるのかもしれない。そう思うと、日々の自分の感情や、人との関わり方について、改めて考えさせられます。
宮部みゆきさんの描く世界は、日常と非日常が絶妙に混ざり合っていて、すぐ隣に不思議な出来事が起こってもおかしくないような、そんな気にさせてくれます。怖い話も、切ない話も、温かい話も、すべてが「人間」という存在の複雑さや奥深さを描き出していて、読み終わった後には、物語の登場人物たちがすぐそばにいるような、そんな感覚さえ覚えるのです。この「とり残されて」という短編集は、そんな宮部さんの魅力が詰まった、珠玉の一冊だと感じました。何年経っても、きっとまた読み返したくなる、そんな作品です。
まとめ
宮部みゆきさんの短編集「とり残されて」は、七つの異なる物語を通して、人の心の奥深くにある感情や、目に見えない繋がり、そして日常に潜む不思議を描き出した、非常に印象深い作品集でした。表題作をはじめ、どの物語も読後に深く考えさせられるテーマを内包しており、読み応えがあります。
収録されている物語は、ホラーテイストの強いものから、切ない恋物語、心温まる再生の物語まで多岐にわたりますが、共通して感じられるのは「とり残された想い」の存在です。それは憎しみや後悔といった負の感情であったり、愛情や希望といった温かい感情であったりしますが、いずれも時を超え、場所に残り、時に人の運命に影響を与えるほどの力を持っています。このテーマが、作品全体に独特の深みと余韻を与えているように感じます。
1990年代に発表された作品でありながら、描かれている人間の感情や関係性は普遍的で、現代を生きる私たちにも強く響くものがあります。ミステリー、ホラー、ヒューマンドラマといった様々な要素が巧みに織り交ぜられており、読者を飽きさせません。宮部みゆきさんの巧みな筆致によって、非日常的な設定も自然に受け入れられ、物語の世界に没入することができました。読後、しばらく登場人物たちのことが頭から離れなくなるような、心に残る一冊です。































































