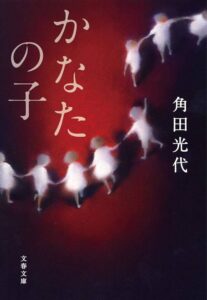 小説「かなたの子」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんの作品の中でも、少し異質な、それでいて心に深く染み入るような短編集です。図書館で偶然手に取ったのですが、読み進めるうちにその独特の世界観に引き込まれました。
小説「かなたの子」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。角田光代さんの作品の中でも、少し異質な、それでいて心に深く染み入るような短編集です。図書館で偶然手に取ったのですが、読み進めるうちにその独特の世界観に引き込まれました。
収録されているのは8つの物語。それぞれ独立した話でありながら、どこか通底するテーマ、空気感があります。それは、日常に潜む仄暗さであったり、過去の出来事が現在に落とす影であったり、あるいは、この世に生を受けること、受けられなかったことへの複雑な想いであったりします。ホラー的な要素も含まれていて、夜中に読むと少し背筋が寒くなるかもしれません。
しかし、ただ怖いだけではありません。描かれているのは、人間の弱さ、愚かさ、そしてそれらを抱えながらも生きていかざるを得ない切なさ、愛おしさです。特に、女性たちの抱える痛みや秘密、そして母性の深淵に触れる描写は、胸を締め付けられるものがあります。男性にとっては、少し耳の痛い、あるいは居心地の悪い話もあるかもしれません。
この記事では、「かなたの子」がどのような物語なのか、その概要をお伝えするとともに、各編を読んだ私の個人的な思いや解釈を、結末の内容にも触れながら詳しく語っていきたいと思います。少し長い文章になりますが、この作品の持つ魅力や深さを、少しでも共有できたら嬉しいです。
小説「かなたの子」のあらすじ
角田光代さんの「かなたの子」は、八つの短編から成る作品集です。それぞれ異なる時代や状況設定でありながら、見えない存在や過去の記憶、そして生と死の境界にまつわる不思議な出来事を描いています。全体を通して、どこか薄暗く、湿った空気が漂っているのが特徴です。
最初の物語「おみちゆき」では、ある村で行われた即身仏になるための儀式と、それに関わった人々の記憶と罪悪感が描かれます。続く「同窓会」は、小学校時代の出来事を引きずる大人たちの物語。毎年開かれる同窓会の裏には、決して忘れられない、そして許されないであろう過去が横たわっています。
「闇の梯子」は、新しい家に引っ越してきた夫婦の物語。妻の様子が徐々におかしくなっていく様を夫の視点から描きますが、そこには見えない世界の力が関わっているのかもしれません。一方、「道理」は、現代を舞台に、妻と喧嘩した男性が元恋人と再会し、過去の関係に引き戻されそうになる中で、日常に潜む不気味な出来事に遭遇する話です。
「前世」では、貧しい時代、飢饉に見舞われた村で、母親が子を思う気持ちと、生きるための過酷な選択が描かれます。生まれてくることのできなかった命への想いが、物語の核心にあります。「わたしとわたしではない女」は、自分には生まれなかった双子の妹が見えるという老女の、曖昧な記憶と現在が交錯する物語です。
表題作でもある「かなたの子」は、死産した子供に名前をつけて呼び続ける女性が主人公。再び妊娠した彼女の前に現れる不思議な出来事を通して、母性の複雑な側面が描かれます。最後の「巡る」では、パワースポット巡りのツアーに参加した女性が、道中で倒れ、自分がなぜここに来たのかを思い出せない状況に陥ります。断片的な記憶をたどるうちに、彼女自身の過去と罪が明らかになっていきます。
これらの物語は、時に恐ろしく、時に切なく、人間の心の奥底にある闇や、見えない世界との繋がりを描き出しています。読者は、登場人物たちの抱える秘密や痛みに触れ、生きていくことの意味を静かに問われることになるでしょう。
小説「かなたの子」の長文感想(ネタバレあり)
角田光代さんの「かなたの子」、読み終えてからしばらく、ずっしりと重いものが心に残りました。「八日目の蝉」のような、母性を力強く肯定する物語を想像していたら、少し面食らうかもしれません。むしろ、母性というものの持つ光と影、その深淵を覗き込むような、ある意味で「八日目の蝉」の裏側を描いた作品集とも言えるのではないでしょうか。八つの短編は、それぞれが独立していながら、「生まれてこられなかった命」「過去の罪」「見えない存在」「女性が抱える痛みや業」といったテーマで緩やかに繋がっています。全体的にホラーテイストが漂いますが、それは単なる怪談ではなく、人間の心の闇や、どうしようもない現実の恐ろしさから来るものです。
まず「おみちゆき」。即身仏の話と聞いて、どこか神聖なものを想像しましたが、描かれていたのは凄惨な現実でした。和尚さんが土の中で鈴を鳴らし続ける描写は、想像するだけで息が詰まります。そして、それを「まだ生きている」と解釈し、事実から目を背け続けた村人たちの姿。恐怖と罪悪感がないまぜになった、人間の弱さが見事に描かれていました。主人公が受けたトラウマもさることながら、信仰や集団心理の恐ろしさを感じさせる一編でした。
「同窓会」は、読んでいて胸が苦しくなりました。「うわやめろ、やめてくれ頼むお願いだ」と心の中で叫んでいました。子供たちの無邪気な残酷さが、取り返しのつかない悲劇を生む。そして、その罪の意識を抱えたまま大人になった彼らが、毎年同窓会を開くことでしか繋がりを確認できない、ある種の共犯関係のような状態。死んだ子の親の気持ちを思うと、彼らが負っている「暗闇が恐い」とか「毎年顔を合わせる」なんていう罰は、あまりにも軽いと感じてしまいます。湊かなえさんの作品なら、間違いなく復讐劇が始まりそうなものですが、ここでは静かな苦しみが描かれるだけです。それがかえって、罪の重さを際立たせているように思いました。
「闇の梯子」は、ミステリーのような趣もあります。妻の不可解な行動に怯える夫の視点で物語が進むので、読者も夫に感情移入しがちです。しかし、最後まで読むと、その視点が一方的なものであった可能性に気づかされます。「片方の話だけ聞いて、わかったつもりでいてはいけませんなぁ。特に夫婦の問題は」という参考文章の言葉が、まさに腑に落ちます。見えない何かに妻が「請われていく」ように見えるけれど、もしかしたら夫自身が原因を作り出していたのかもしれない。妻を追い詰めたのは、夫の無理解や支配欲だったのではないか…。そう考えると、夫への共感は一転し、むしろ彼こそが罰せられるべき存在に思えてきます。こういう男性、現実にもいそうですよね。
「道理」に出てくる主人公の男性には、私も読んでいて腹が立ちました。「闇の梯子」の夫以上に、その身勝手さ、お調子者ぶりがリアルで、実に不快です。妻と喧嘩したからといって、すぐに元恋人に連絡を取り、いい雰囲気になる…。そして、その先に待っている結末。幽霊などが出てくるわけではないのに、日常の中に潜む悪意や因果応報のようなものが、じわじわと怖さを感じさせます。こういう男性が、現実では何の罰も受けずに平然と生きているかもしれないと思うと、それもまた別の種類の恐怖ですね。物語としては、テンポも良く、非常に完成度が高いと感じました。まさに「世にも奇妙な物語」になりそうな一編です。
「前世」は、読んでいて最も心が痛んだ話かもしれません。飢饉という極限状況の中で、母親が下す「口減らし」という選択。その決断の裏にある、母親自身の痛みと、子供への愛情。そして、そんな母親を最終的に許してしまう子供の存在。そこには、理屈を超えた母と子の強い絆が描かれています。しかし、その一方で、全く責任を果たそうとしない父親(夫)の存在が、強烈な怒りを感じさせます。食べるものがないのに子作りはし、生まれたら面倒は妻に押し付け、自分はどこかへ逃げてしまう。そして、妻が子を殺めて帰ってきたとしても、おそらく彼はまた妻を抱き、同じことを繰り返させるのでしょう。このやるせなさは、現代の少子化問題で女性ばかりが責任を問われる風潮と無関係ではないように思えてなりませんでした。なぜ、こうも男性は無責任でいられるのか、と。桐野夏生さんなら…という想像も、妙に納得してしまいます。
「わたしとわたしではない女」は、不思議な浮遊感のある物語でした。生まれなかった双子の妹が見える、という設定自体が幻想的ですが、老いた主人公の語る現在が、過去の出来事よりも曖昧で断片的であるところに、リアリティと不気味さを感じました。彼女は本当に生きているのか、それともすでに境界の向こう側にいるのか。明確な答えは示されません。過去の回想で語られる夫の酷さも、やはりこの短編集に共通するテーマ性を補強しています。老いること、記憶が薄れていくことの寂しさや不安も伝わってきました。
表題作「かなたの子」。死産した子に名前をつけ、その名を呼び続ける母親。タブーを犯してでも、我が子との繋がりを保とうとする姿は切実です。そして再び宿した命。ここで物語は希望に向かうのかと思いきや、予想外の展開を迎えます。あの「八日目の蝉」で描かれたような、母性の絶対的な肯定とは異なる、もっと複雑で、時には残酷な側面を突きつけられます。「女性は“子供を産んで母親になる”ことで自らも子供に還る」というテーマが、他の作品にも見られましたが、この作品では特に強く印象づけられました。それは、母親になることで自身の原点に立ち返る、ということなのでしょうか。だとしたら、父親になる男性はどうなのでしょう。ここでもまた、男性の不在、あるいは役割の希薄さが際立ちます。母性賛美に酔いしれていた人には、ぜひ読んでほしい一編だと感じました。
最後の「巡る」。パワースポット巡りという現代的な設定ですが、内容は非常に重いものです。記憶を失った主人公が、断片的な情報を繋ぎ合わせながら、自分が犯したであろう罪の輪郭に近づいていく過程は、スリリングでありながら恐ろしい。周囲の人々の証言が食い違っていたり、どこか胡散臭かったりするのも、不安感を煽ります。おそらく彼女は、自分の娘に対して、取り返しのつかないことをしてしまったのでしょう。しかし、物語は彼女を断罪しません。むしろ、罪を抱えたまま、それでもまた誰かと出会い、関係性を紡いでいく可能性を示唆して終わります。これは、角田さんの優しさなのか、それとも、罪から逃れることはできないという厳しさの現れなのか。解釈が分かれるところだと思います。
八つの物語を通して感じるのは、やはり「男のもげなさ」と、それによって女性が負わされる痛みの深さです。もちろん、すべての男性がそうだとは言いませんが、この短編集に出てくる男性たちの身勝手さ、無責任さ、鈍感さには、読んでいて何度も溜息が出ました。そして、そんな男性たちの存在を許容し、あるいはその犠牲となりながらも、女性たちは子供を産み、育て、あるいは失い、見えないものと繋がりながら、それぞれの生を生きていきます。そこには、諦念や悲しみだけでなく、ある種の強かさや、深い愛情も感じられます。
パンドラの箱の底に残った希望のように、これらの物語の結末にも、かすかな光が見えることがあります。しかし、その希望は、決して手放しで喜べるものではなく、むしろ厄介なものとして描かれているようにも感じます。希望があるからこそ、人はまた過ちを繰り返すのかもしれない。それでも、希望なしには生きていけない。そんな人間の業のようなものを、突きつけられた気がします。
「八日目の蝉」が母性の光の部分を感動的に描いたとすれば、「かなたの子」は、その光の裏にある影、痛み、そして不可解さを、静かに、しかし深くえぐり出す作品だと言えるでしょう。読後感は決して明るいものではありませんが、人間の心の複雑さ、生と死の不思議さについて、深く考えさせられる、忘れがたい一冊となりました。男性読者にとっては、自らのあり方を省みるきっかけになるかもしれませんし、女性読者にとっては、言葉にならない感情を掬い取ってくれるような、ある種の共感を覚えるかもしれません。読み返すたびに、新たな発見がありそうな、奥行きの深い作品集です。
まとめ
角田光代さんの短編集「かなたの子」は、八つの物語を通して、日常に潜む仄暗さや、過去から逃れられない人間の姿を描き出しています。ホラー的な要素も含まれていますが、それは超自然的な恐怖というより、人間の心の闇や、どうしようもない現実から来るものです。
特に印象的なのは、女性たちが抱える痛みや秘密、そして母性の複雑な側面です。生まれてくることのできなかった命への想い、男性の身勝手さによって負わされる傷、それでも続いていく生と、その中で見出すかすかな希望。これらのテーマが、時に恐ろしく、時に切なく、読者の心に深く響きます。
「八日目の蝉」とはまた異なる角度から、生と死、罪と赦し、そして見えない世界との繋がりを描いた本作は、読後に重い余韻を残します。しかし、それは不快な重さではなく、人間の存在そのものが持つ深淵を覗き込んだような、静かな問いかけを与えてくれるものです。
角田光代さんのファンはもちろん、人間の心の複雑さや、日常に潜む不思議な物語に興味がある方におすすめしたい一冊です。読み終えた後、きっとあなた自身の内面と静かに向き合う時間を持つことになるでしょう。

























































