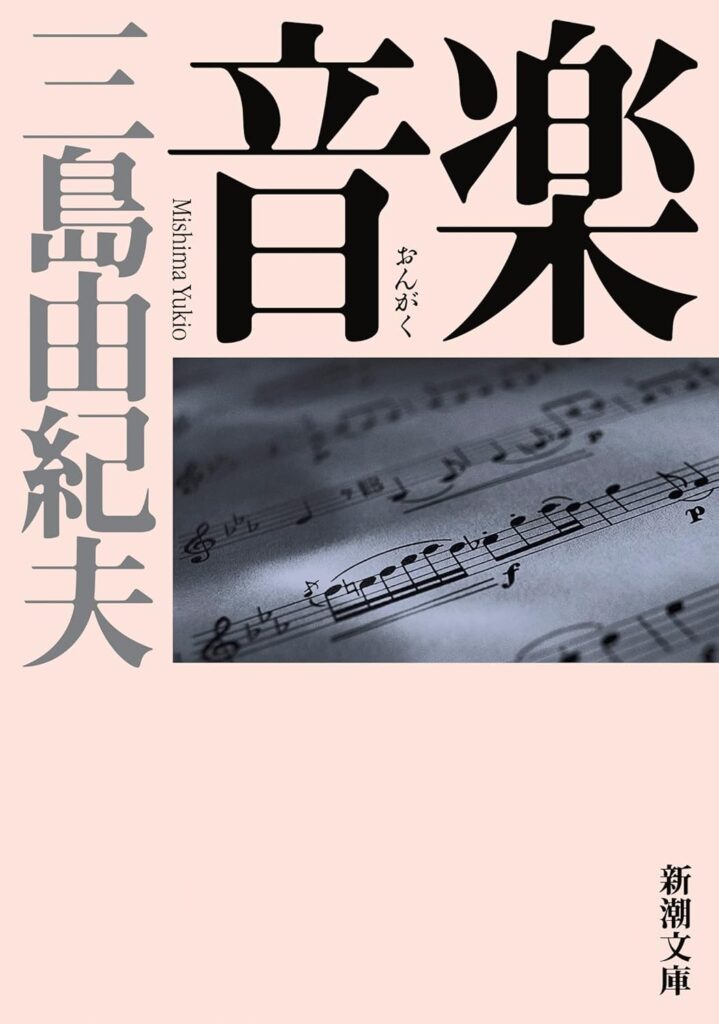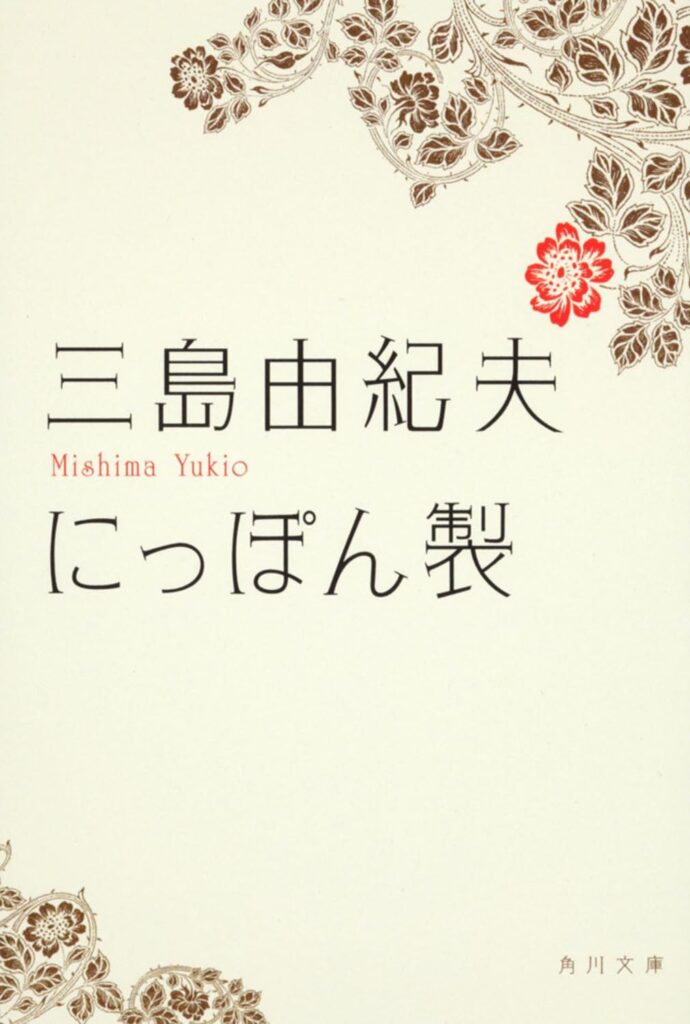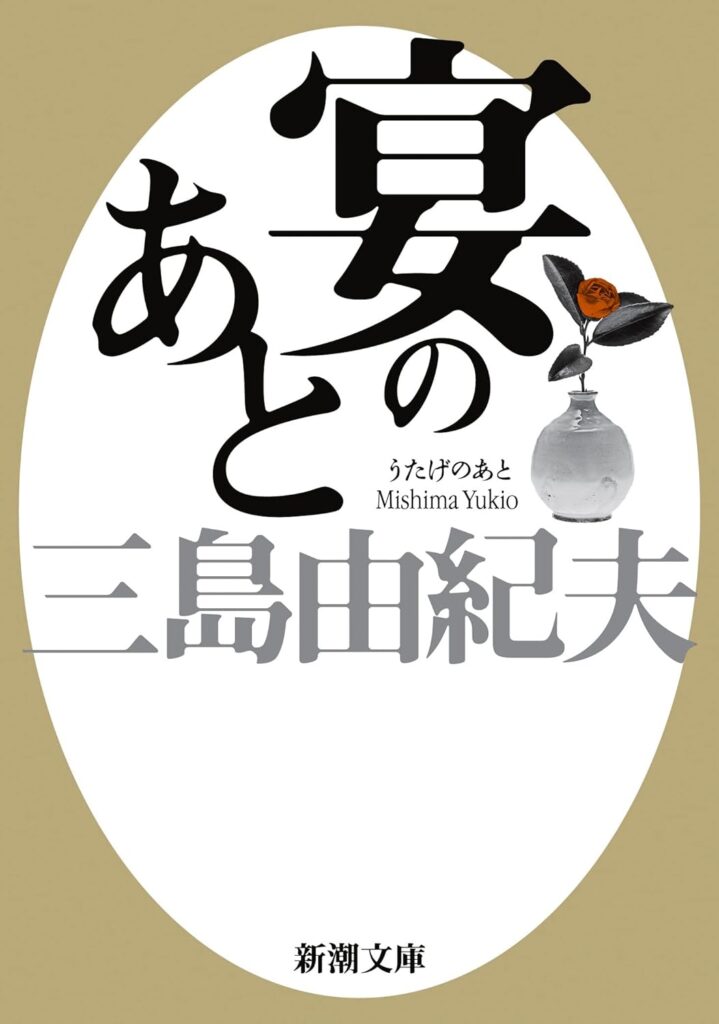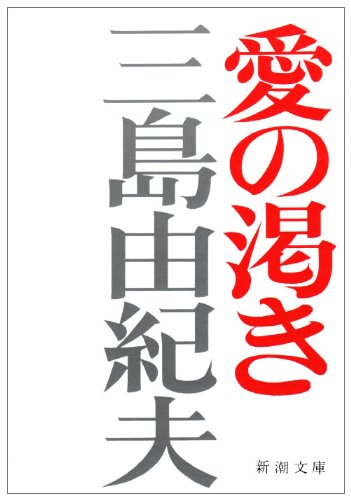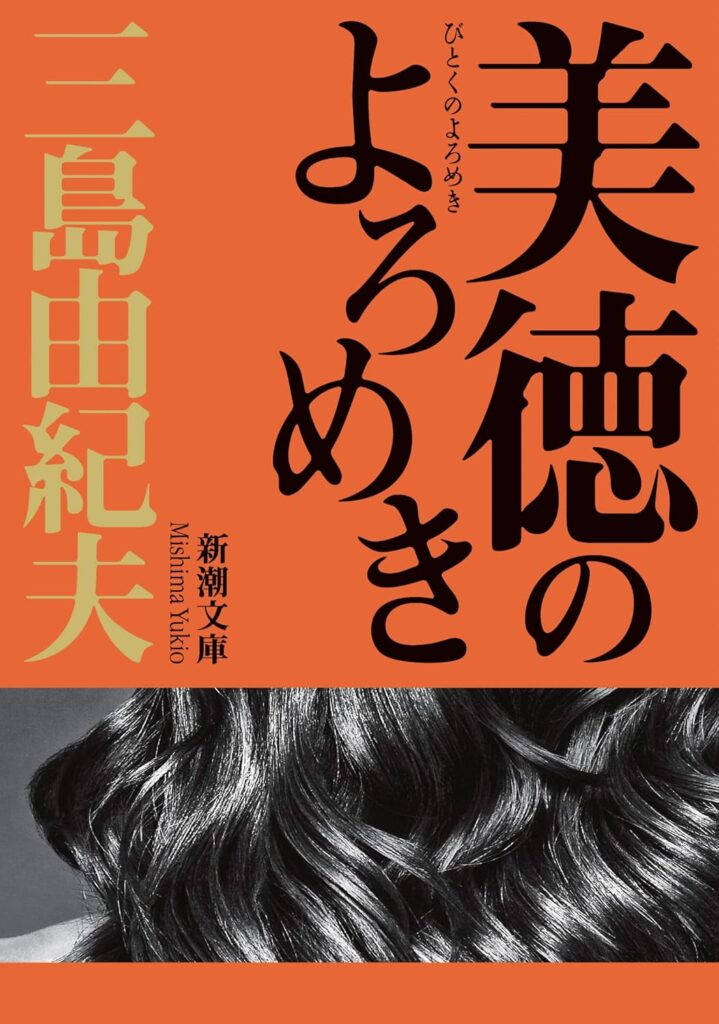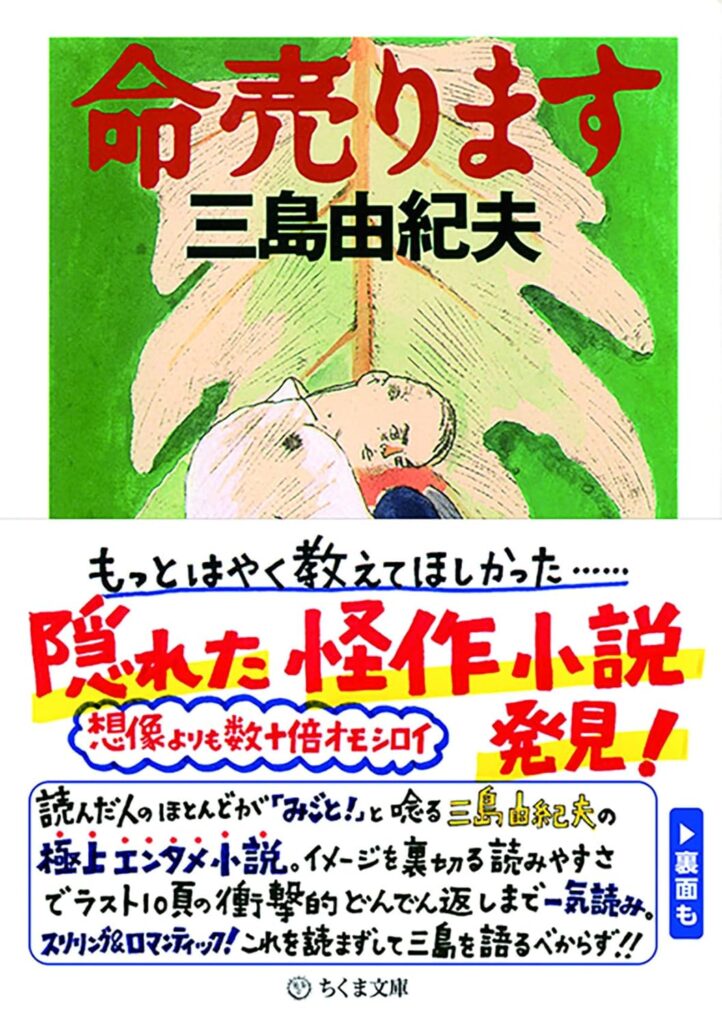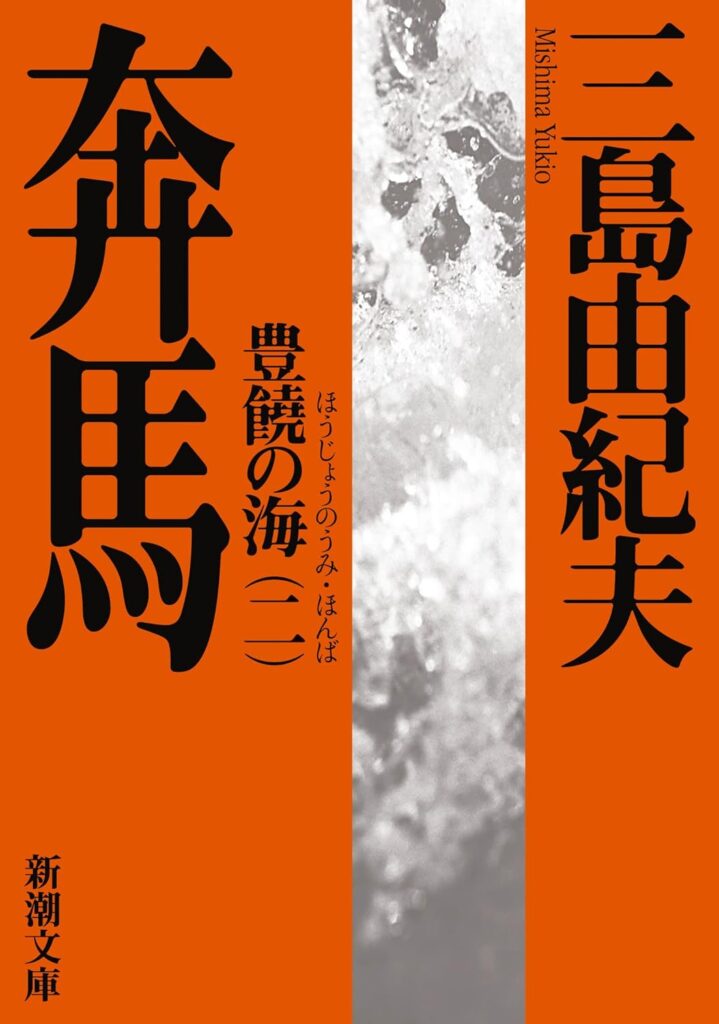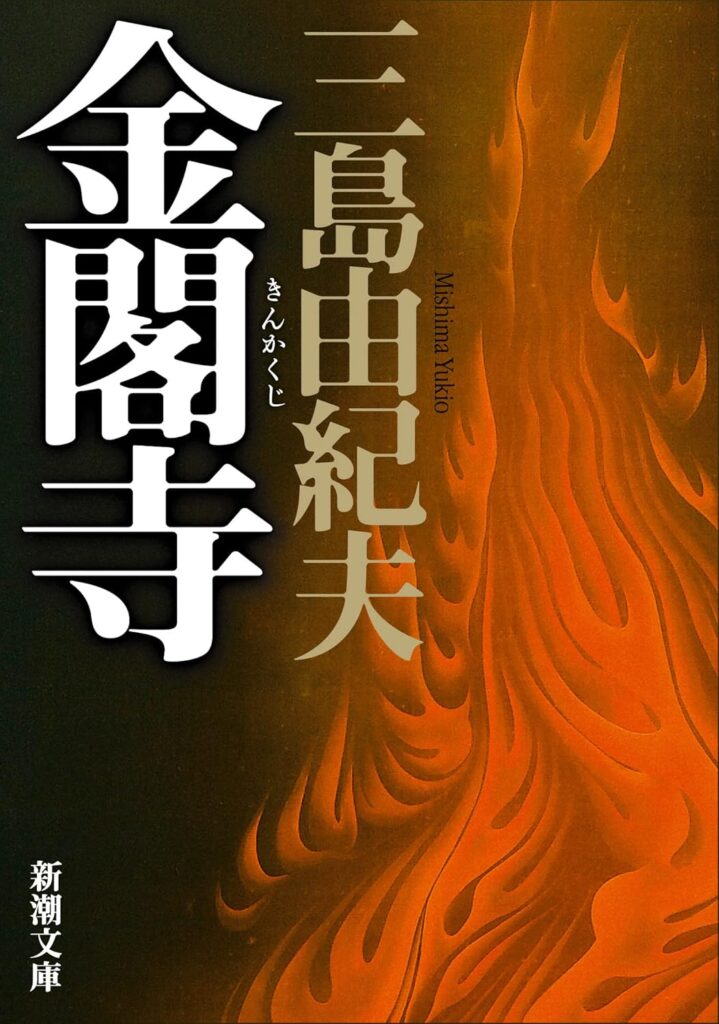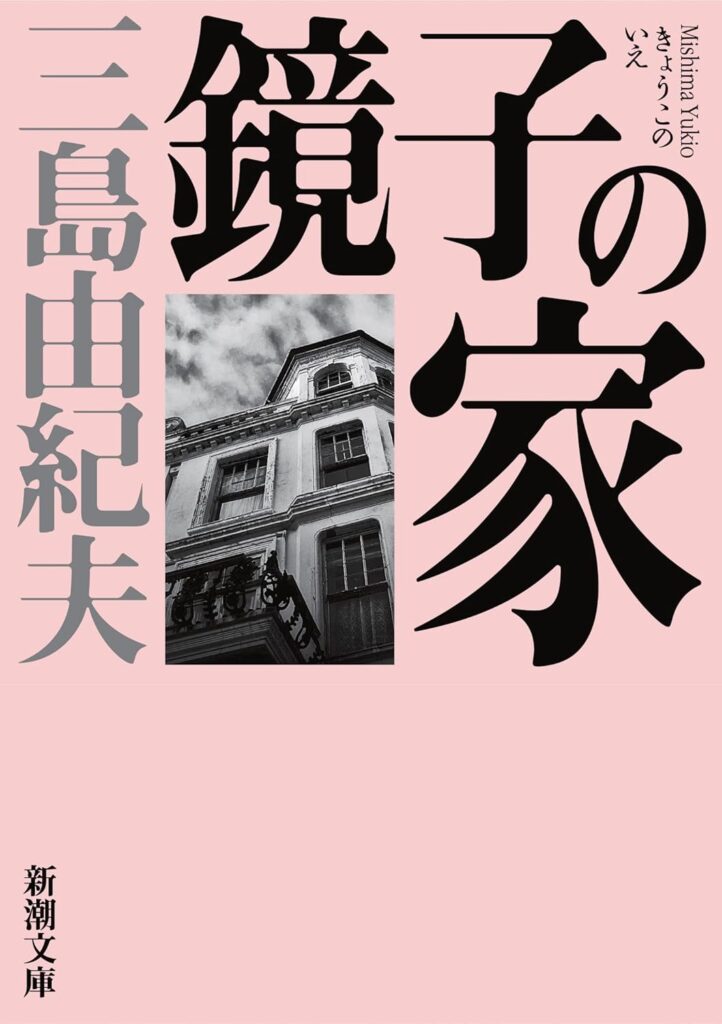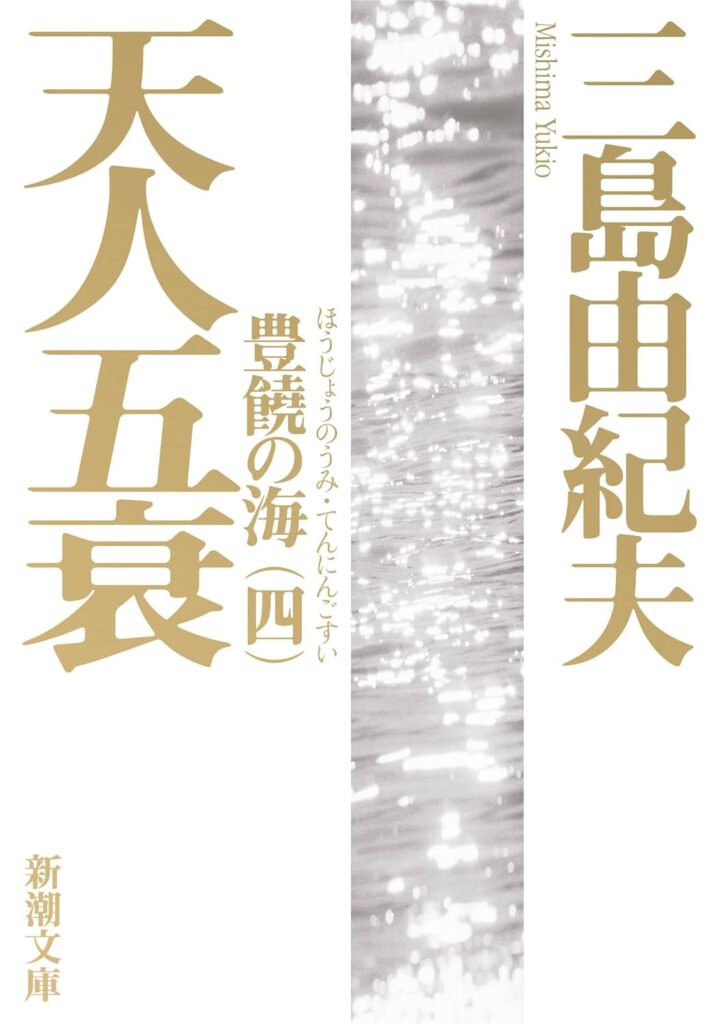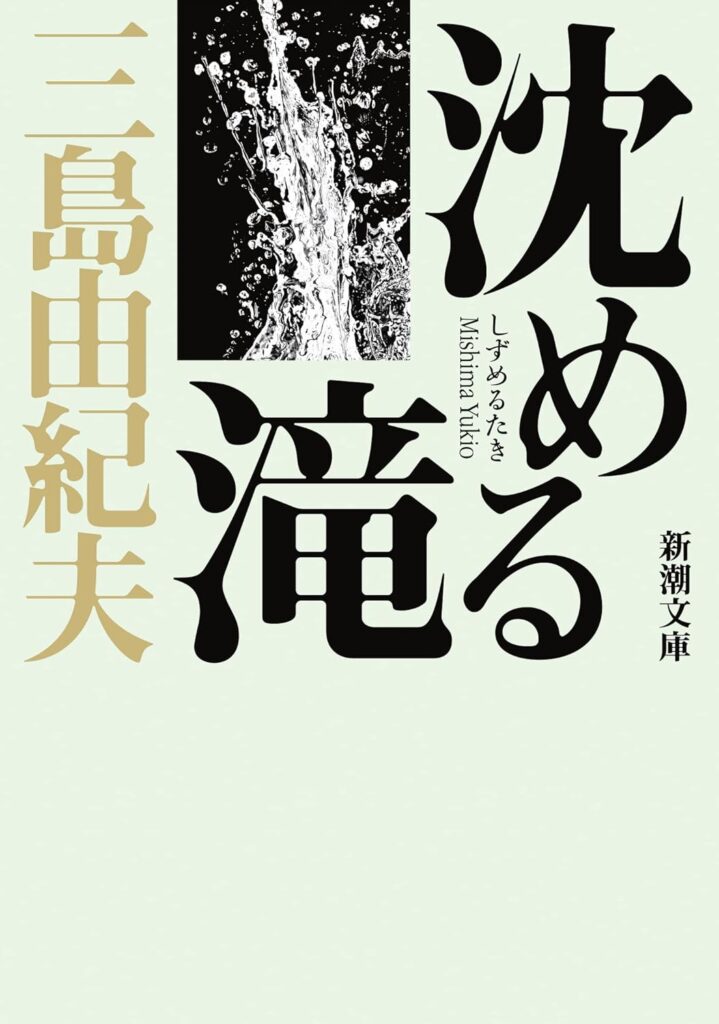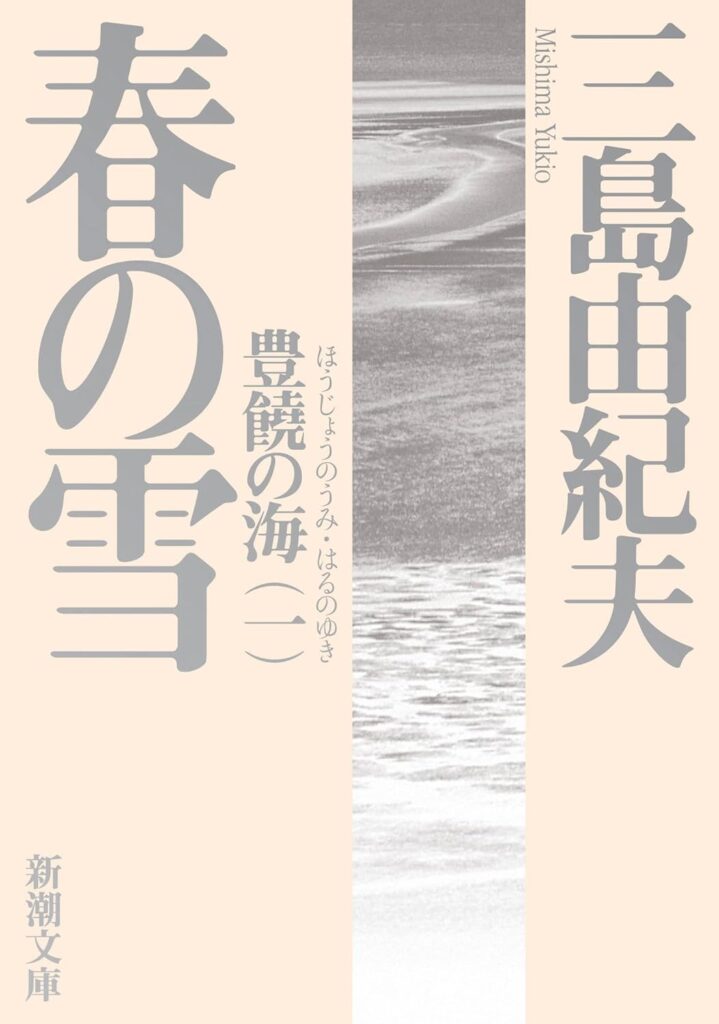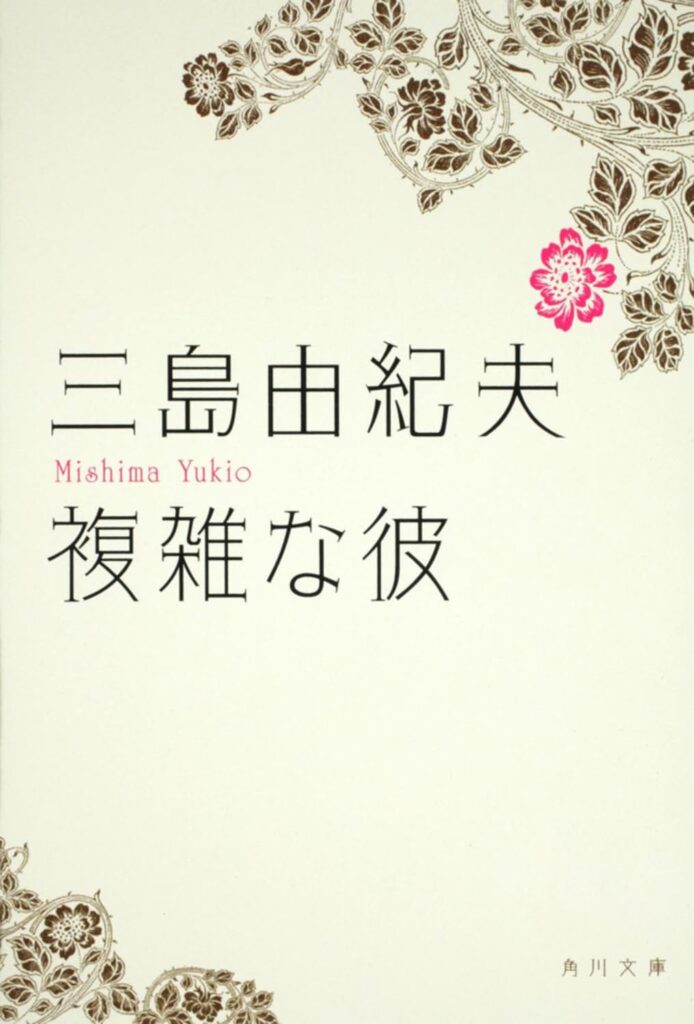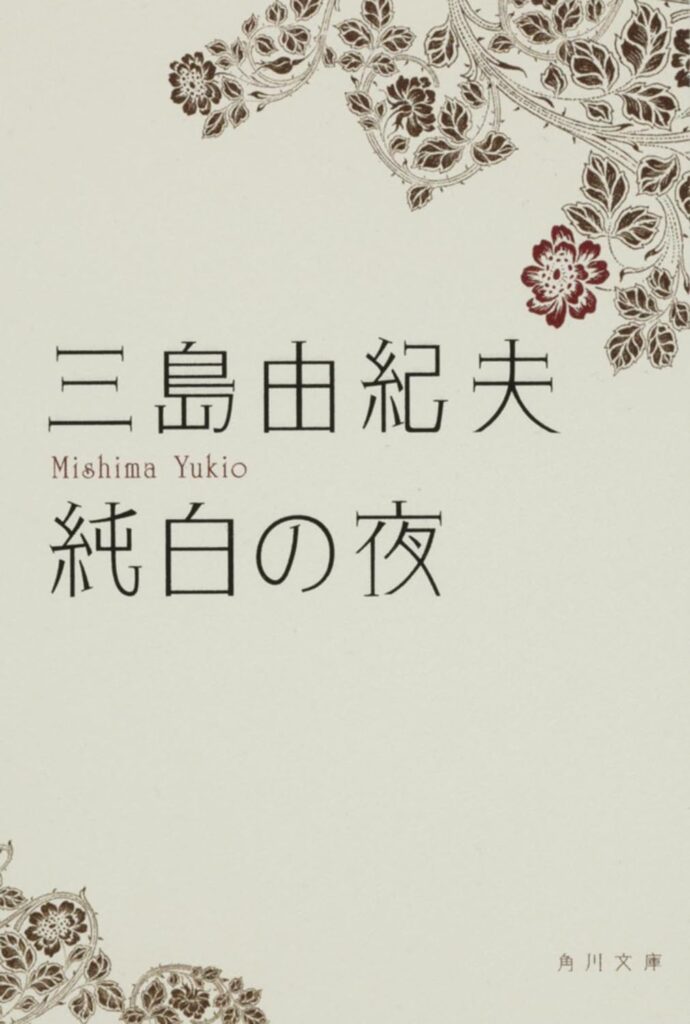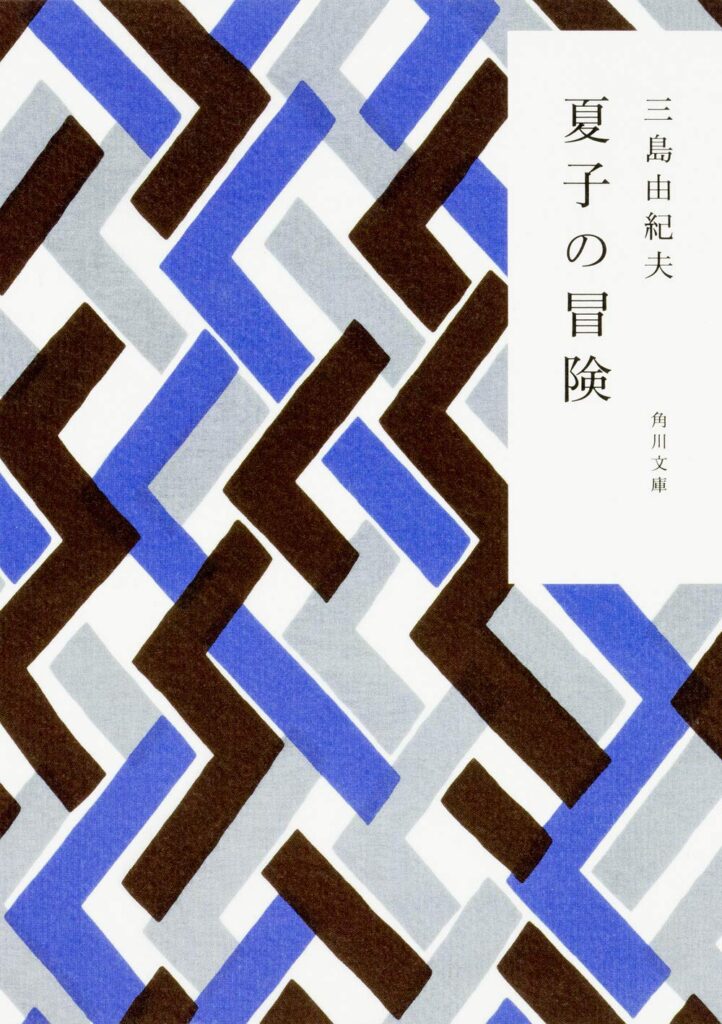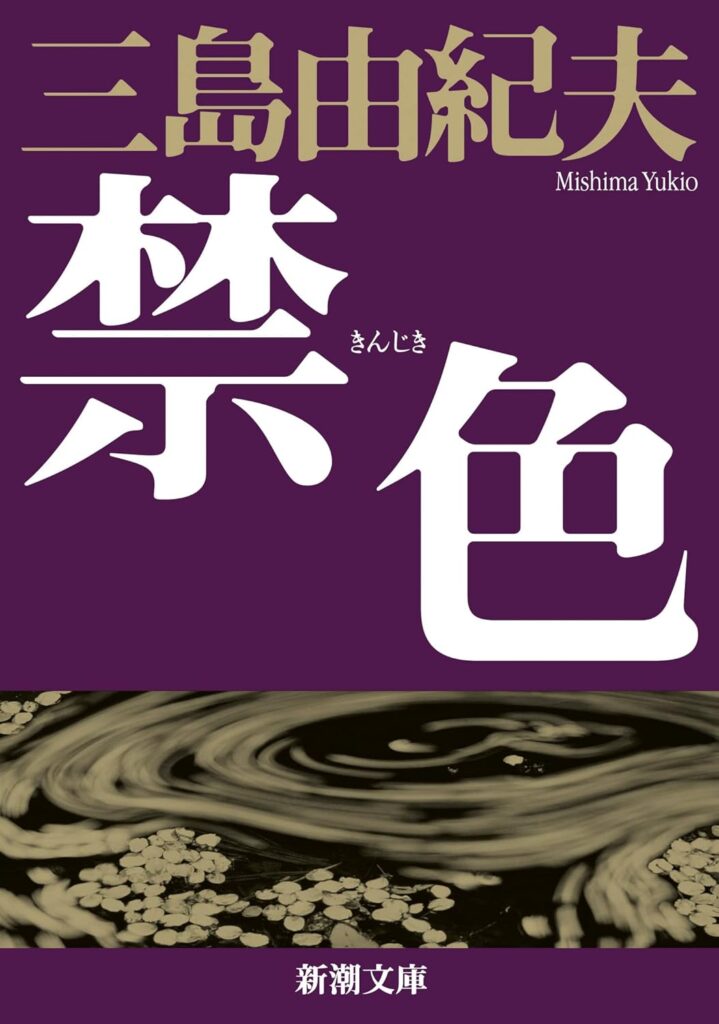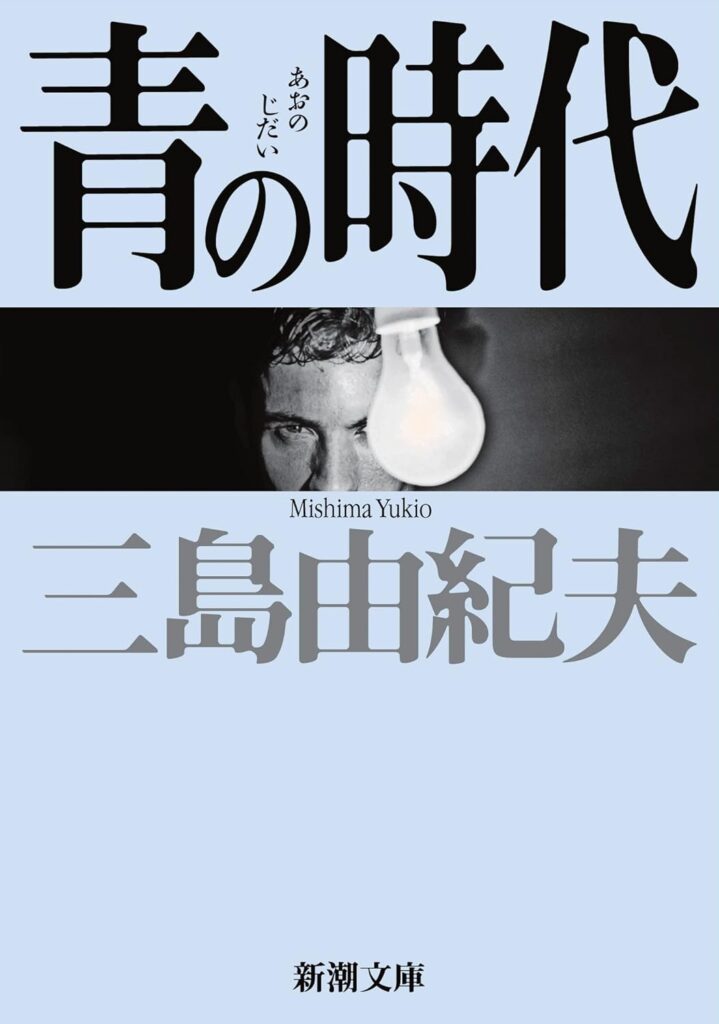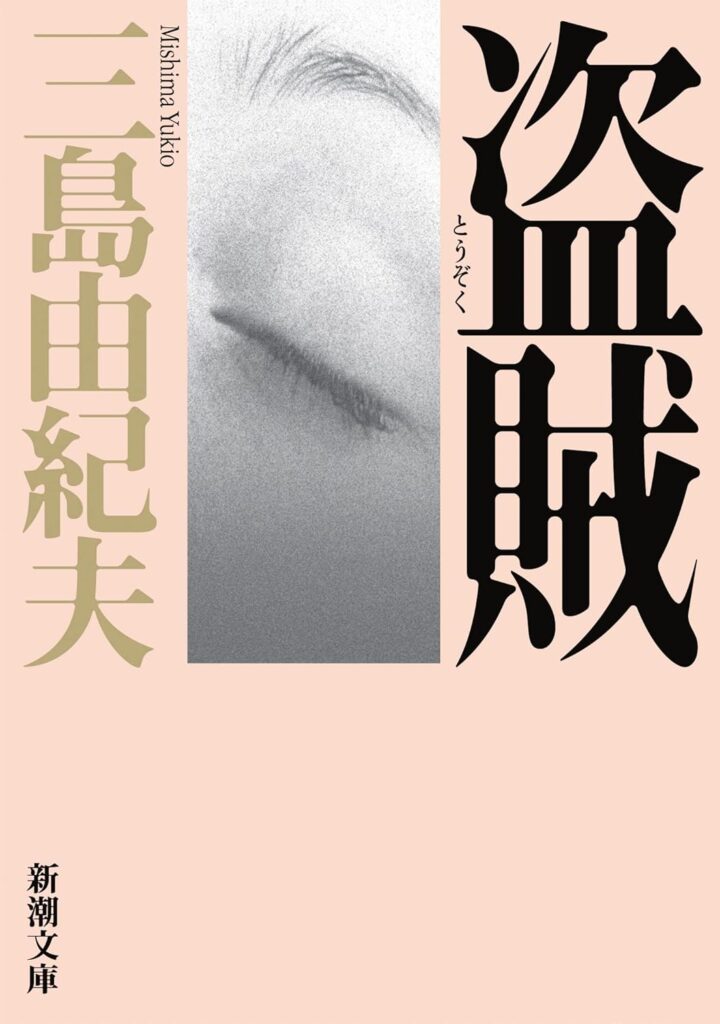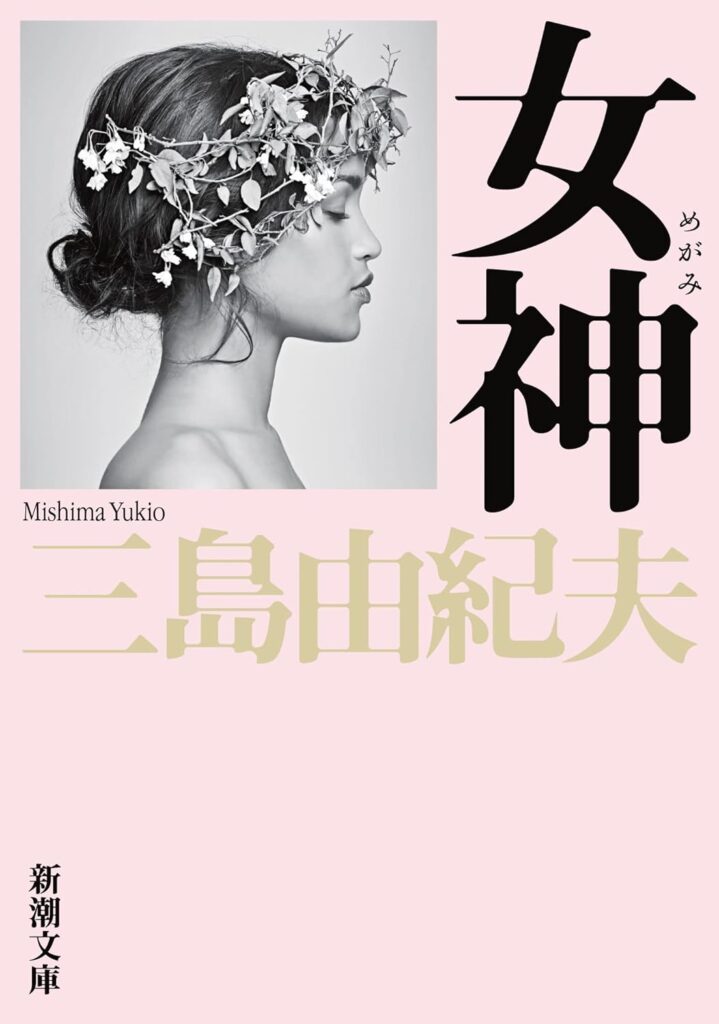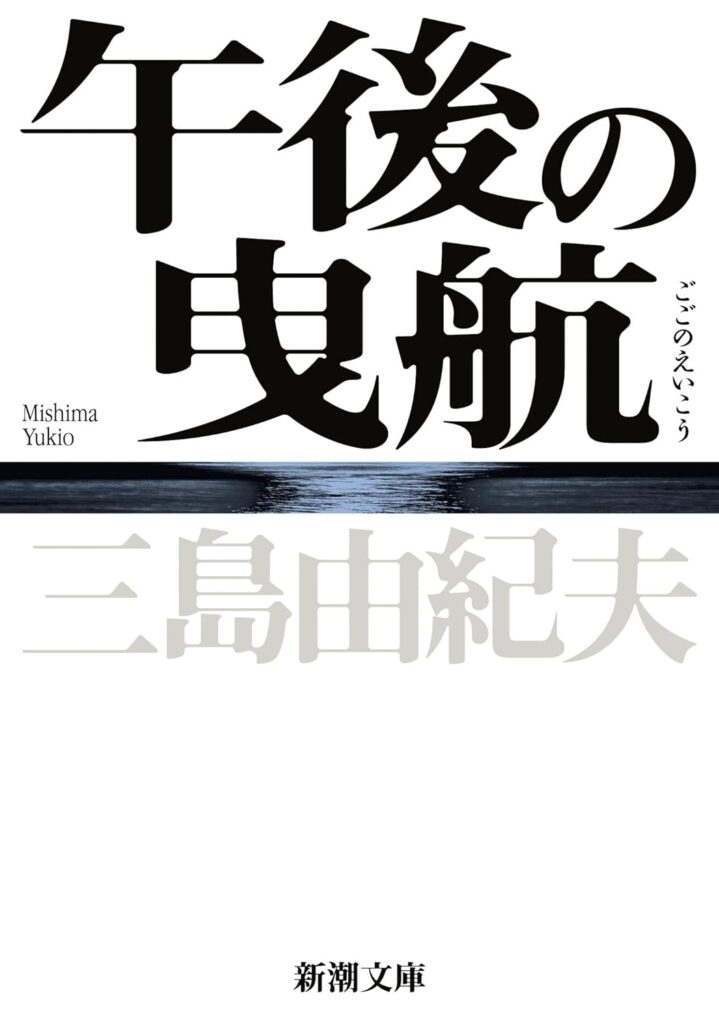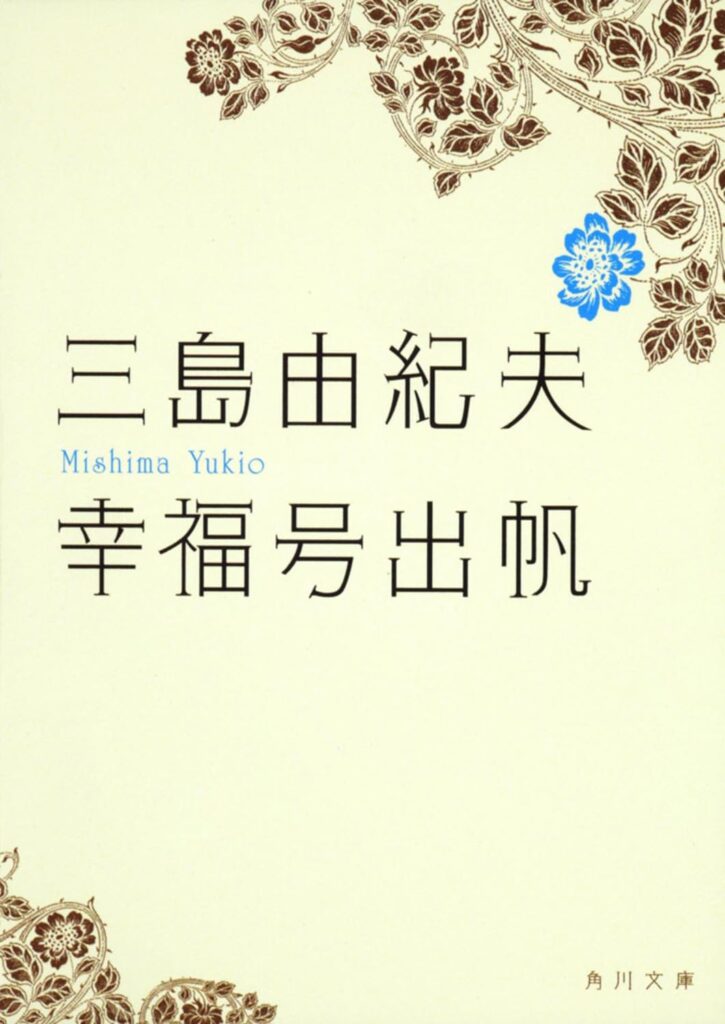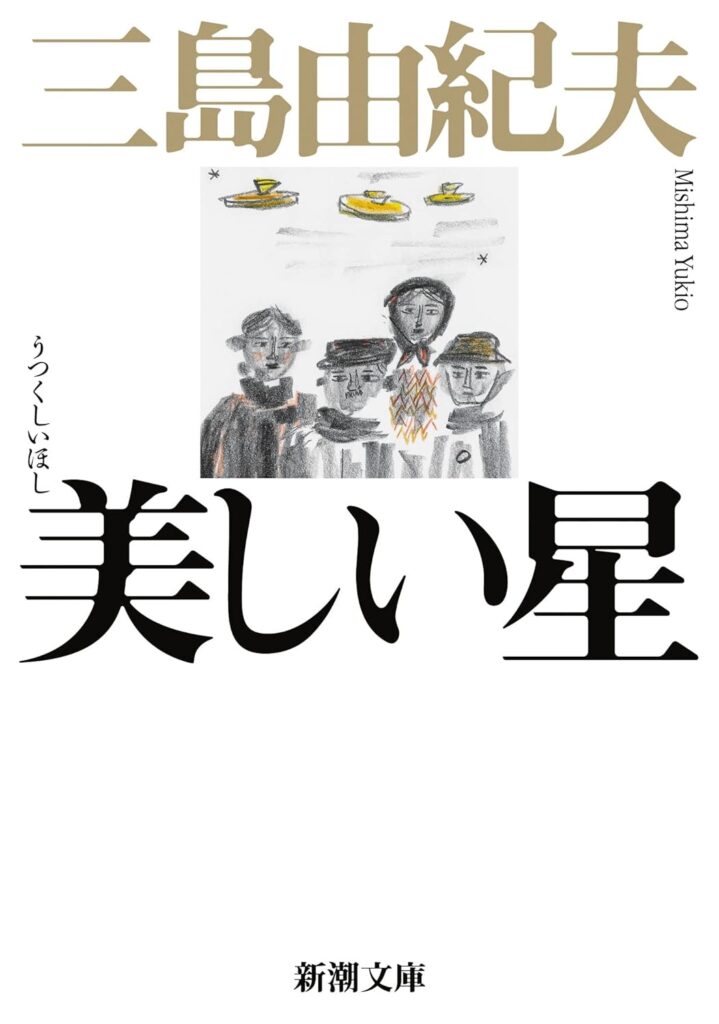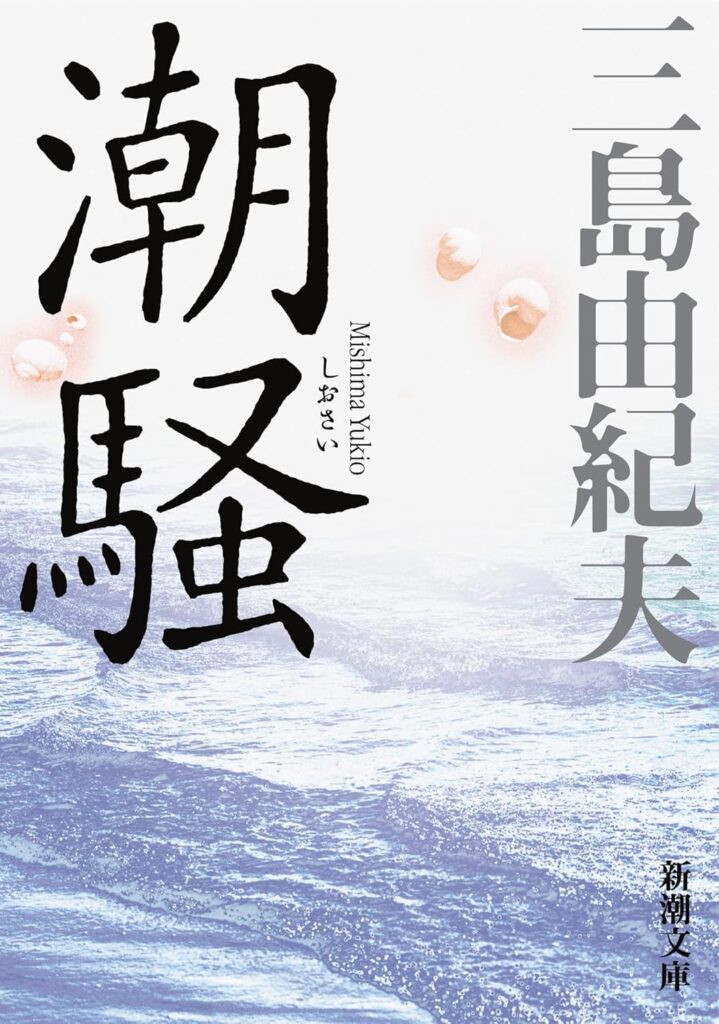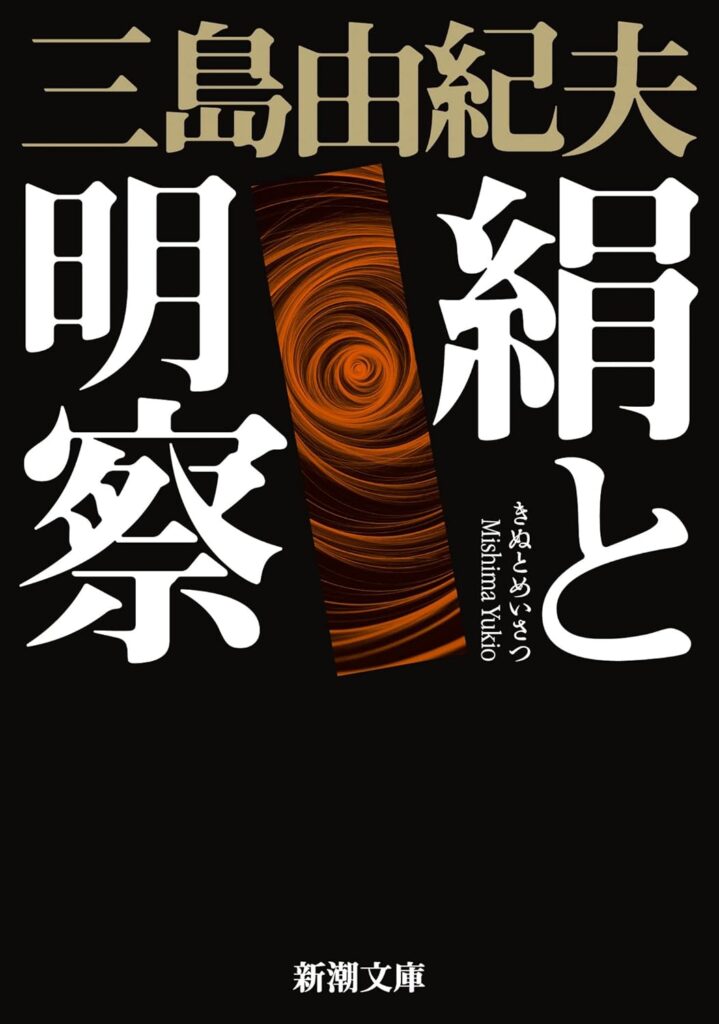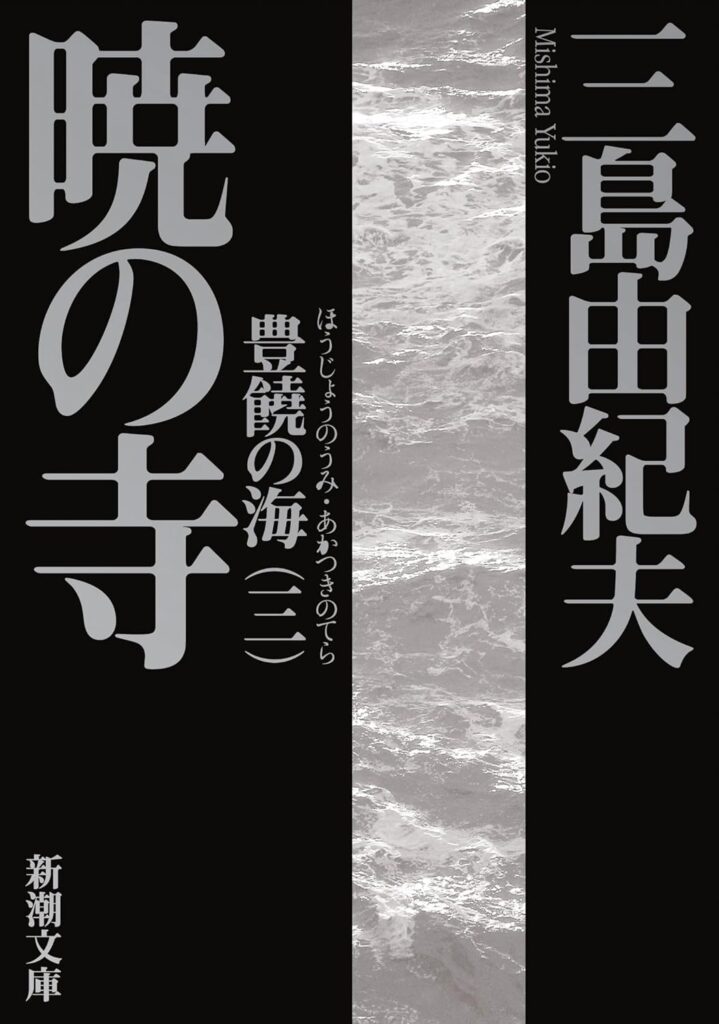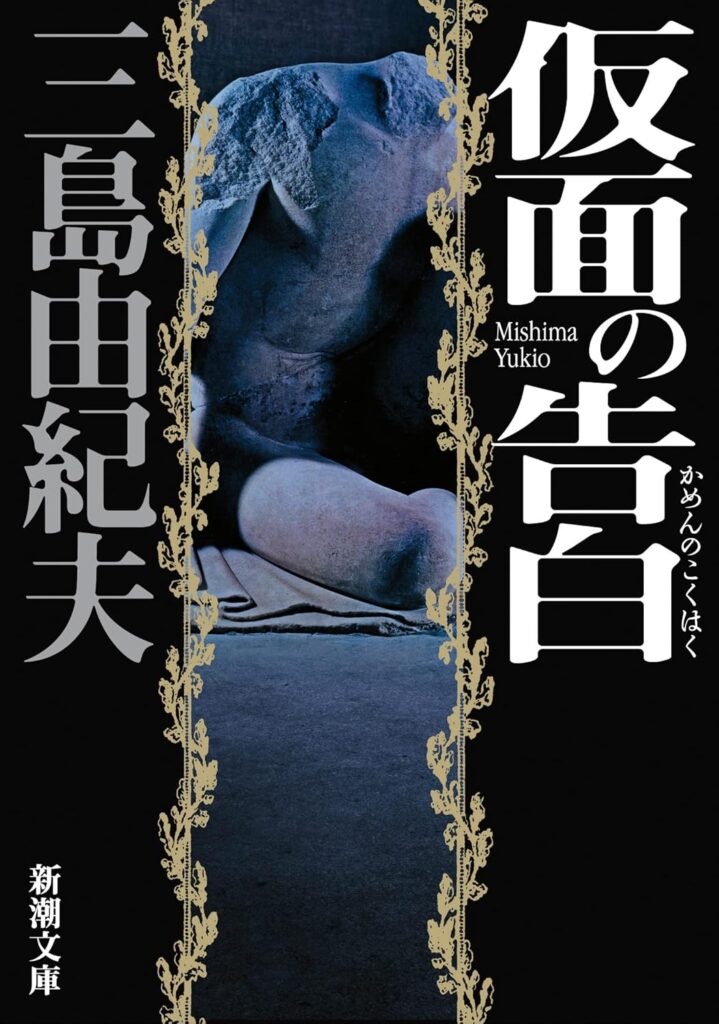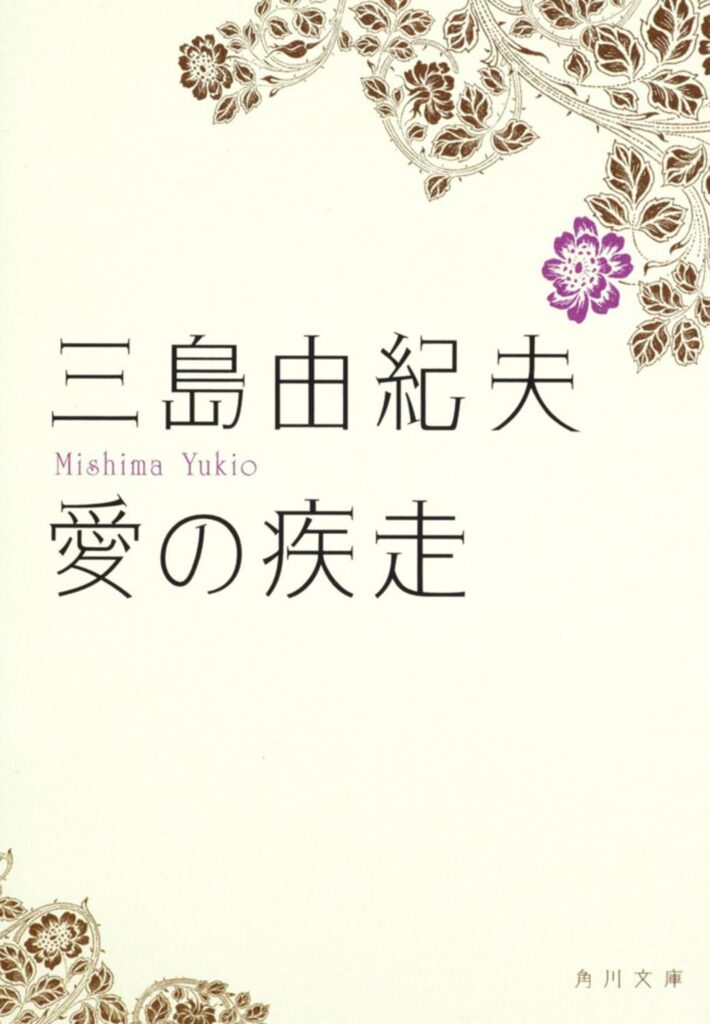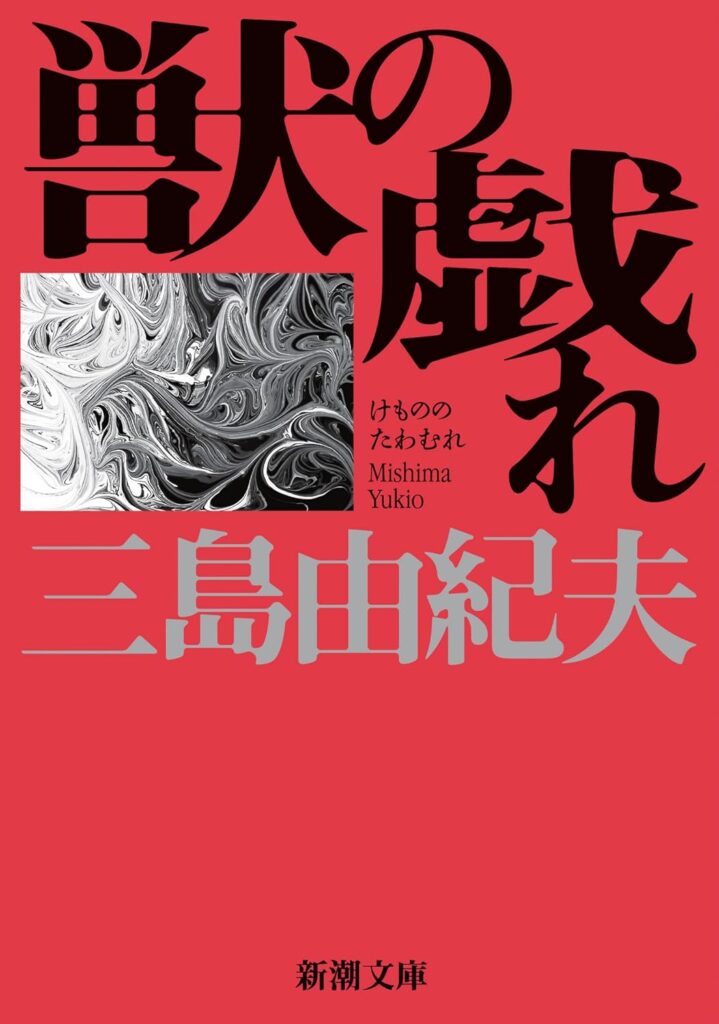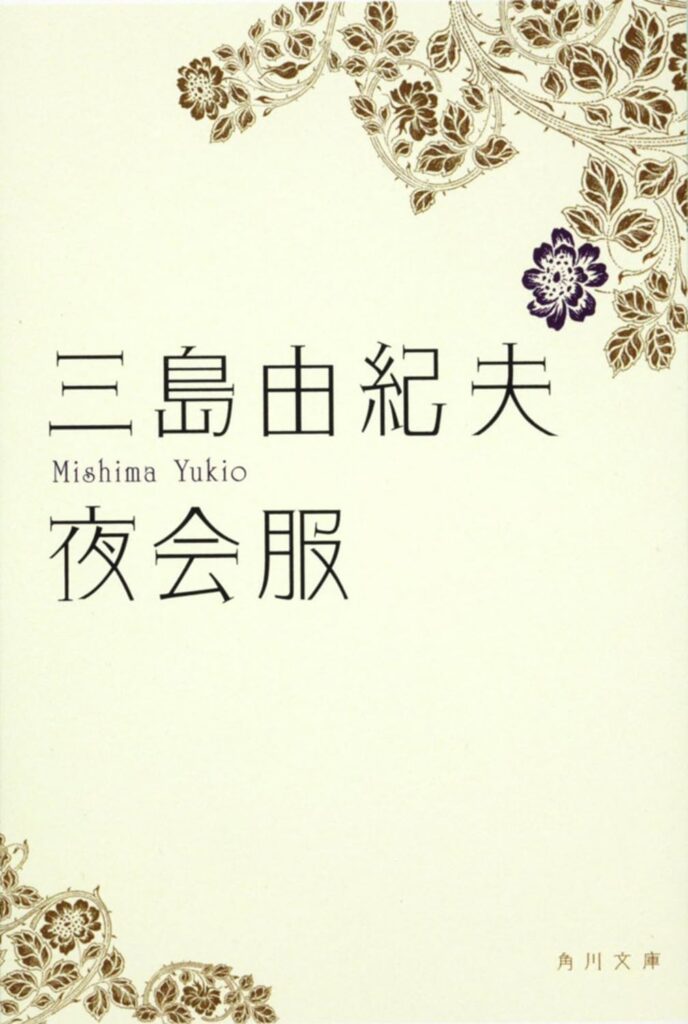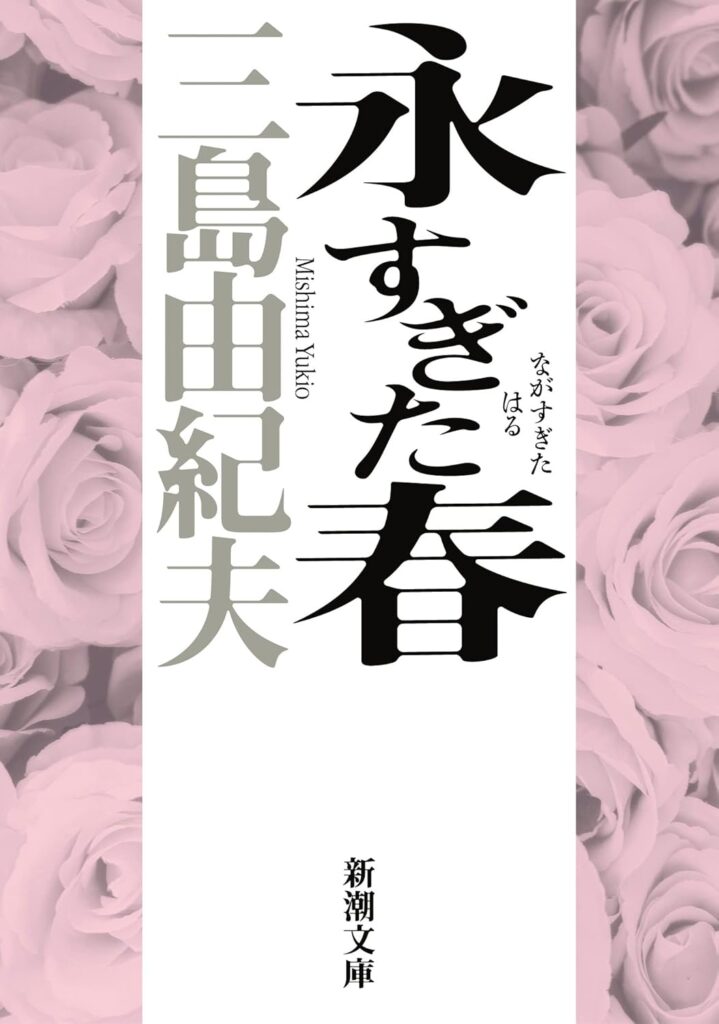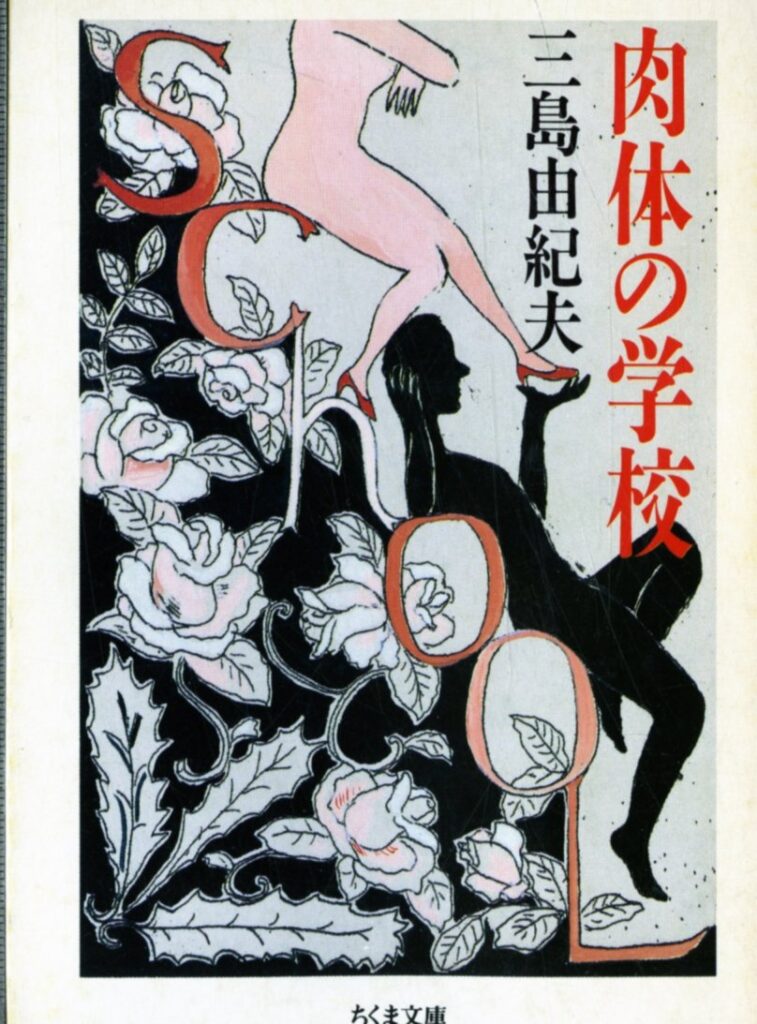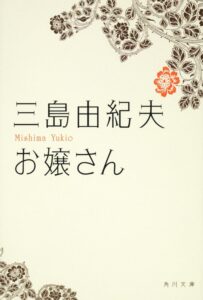 小説「お嬢さん」のあらすじを物語の結末に触れつつ紹介します。長文で読んでみて感じたことも書いていますのでどうぞ。
小説「お嬢さん」のあらすじを物語の結末に触れつつ紹介します。長文で読んでみて感じたことも書いていますのでどうぞ。
三島由紀夫が描く、一見軽やかでいて、その実、人間の複雑な心理や当時の世相を映し出すこの物語は、多くの読者を引き込んできました。特に主人公かすみの心の動きや、彼女を取り巻く個性的な人々との関係性は、現代に生きる私たちにも通じるものがあるのではないでしょうか。
この物語は、戦後の日本が新たな価値観を模索する中で、旧来の「お嬢さん」という存在がどのように生き、変化していくのかを描いた作品と言えるかもしれません。結婚という制度、男女の恋愛遊戯、そして一人の女性としての自立。これらが軽快なタッチで描かれつつも、読後には深い余韻を残します。
この記事では、まず「お嬢さん」がどのような物語なのか、その概略と結末までの流れを追っていきます。その後、私がこの作品を読んで心に響いた点や、考えさせられた事柄を、物語の核心にも触れながら詳しく述べていきたいと思います。
三島由紀夫の作品の中でも、比較的読みやすいと評されることの多い「お嬢さん」ですが、その魅力は決して表面的なものだけではありません。この機会に、作品世界の奥深さに触れていただければ幸いです。
小説「お嬢さん」のあらすじ
物語の主人公は、裕福な家庭に育った女子大生の藤沢かすみ。彼女は、父親である一太郎が催したホームパーティーで、少々派手な噂の絶えない青年、沢井景一と出会います。かすみは、どこか型にはまらない景一に興味を抱き始めます。
景一には、彼に執拗に好意を寄せる浅子という女性がいました。浅子から逃れるため、そしてかすみ自身のどこか退屈な日常からの変化を求める気持ちも手伝って、かすみは景一に偽装結婚を持ちかけます。二人の利害は一致し、周囲も認める形で結婚生活がスタートします。
新婚生活は穏やかに始まったものの、かすみは次第に夫の景一と、自身の義理の姉である秋子の親密な関係を疑い始めます。美しい秋子と、かつては遊び人だった景一。二人の間に何かがあるのではないかという疑念は、かすみの心を徐々に蝕んでいきます。
そんな中、かつて景一を追いかけていた浅子が、再びかすみの前に現れます。最初は警戒心と複雑な感情を抱くかすみでしたが、意外にも浅子はかすみの相談相手となり、的確な助言を与えます。浅子の言葉は、かすみが抱いていた疑念が妄想であったことを気づかせ、彼女を精神的な危機から救い出します。
浅子との交流を通じて、かすみは精神的に成長し、夫である景一への信頼を取り戻します。そして、景一との間に新しい命を授かることが判明します。物語の終わりでは、かすみのお腹の子の誕生を心待ちにする父・一太郎の姿が描かれ、新しい家族の始まりを予感させます。
この一連の出来事を通して、世間知らずだった「お嬢さん」かすみは、現実の人間関係の複雑さや、人を信じることの大切さを学び、一人の女性として、また妻として成長していくのです。
小説「お嬢さん」の長文感想(ネタバレあり)
三島由紀夫の「お嬢さん」を読み終えて、まず心に残ったのは、その軽やかな筆致の裏に潜む、人間の心理に対する鋭い洞察と、時代を映す鏡のような鮮やかさでした。1960年に発表されたこの作品は、半世紀以上の時を経た今読んでも、色褪せることのない魅力を放っているように感じます。
主人公の藤沢かすみは、まさに名家の「お嬢さん」として、何不自由なく育った女性です。大学での勉強にも身が入らず、将来に対する明確な目標もない。そんな彼女が、ふとしたきっかけで出会った沢井景一という男性に、ある種の好奇心と憧れを抱き、衝動的に偽装結婚という大胆な行動に出るところから物語は動き出します。このかすみの行動は、一見突飛に見えますが、彼女の抱える漠然とした日常への不満や、未知の世界への憧れの表れなのかもしれません。
景一という男性もまた、非常に興味深い人物です。プレイボーイとして名を馳せ、どこか掴みどころのない彼ですが、物語が進むにつれて、彼なりの誠実さや、かすみに対する愛情が垣間見えてきます。三島由紀夫は、単純な「善人」「悪人」という型にはまらない、多面的な人間像を描き出すことに長けていると改めて感じました。かすみと景一の関係は、偽りから始まったものでありながら、様々な出来事を経て、少しずつ本物の絆を育んでいく過程が丁寧に描かれています。
この物語の中で、私が特に印象深く感じたのは、浅子という女性の存在です。当初は景一に付きまとう、いわば恋敵として登場する彼女ですが、後半ではかすみを救う重要な役割を果たします。浅子は、情熱的でありながらも現実を冷静に見つめる強さを持ち合わせており、その言動はかすみにとって大きな気づきを与えます。特に、かすみが夫と義姉の関係を疑い、嫉妬と妄想に囚われていく場面での浅子のアドバイスは、的確かつ力強いものでした。
浅子はかすみに対して、「あなたはまだ本当の苦労を知らないお嬢さんだ」といった趣旨の言葉を投げかけますが、それは決して意地悪からではなく、かすみの成長を願う心からの叱咤激励のように私には聞こえました。世間の荒波を経験してきた浅子だからこそ言える言葉であり、その言葉がかすみの目を覚まさせ、凝り固まった心を解きほぐしていくのです。この浅子の存在は、物語に深みを与え、単なる恋愛劇に終わらせない重要な要素となっていると言えるでしょう。
また、かすみの義理の姉である秋子の存在も忘れてはなりません。社交的で洗練された美しい女性として描かれる秋子は、かすみにとって憧れの対象であると同時に、嫉妬の対象ともなります。しかし、物語の終盤で、その疑惑がかすみの早合点であったことが明らかになることで、読者は安堵するとともに、人間関係の複雑さ、そして誤解が生み出す悲劇の可能性について考えさせられます。秋子自身は、終始一貫して善良な人物として描かれており、それ故にかすみの疑心暗鬼がより際立つ効果を生んでいます。
三島由紀夫の文体は、この作品では比較的平易で、テンポ良く物語が展開していくため、非常に読みやすいと感じました。しかし、その軽快さの中にも、人間の心の機微を捉える繊細な描写や、時折見せる鋭い社会風刺のようなものが織り込まれており、読者を飽きさせません。特に、登場人物たちの会話は生き生きとしており、それぞれの性格や立場が巧みに表現されています。
1960年代という時代背景も、この物語に独特の雰囲気を与えています。戦後の復興期から高度経済成長期へと向かう中で、人々の価値観も大きく変化しようとしていた時代。そんな中で生きる若い男女の姿は、どこか自由で、しかし不安定さも抱えているように見えます。かすみの父親である一太郎が夢見るアメリカ式のホームパーティーやマイホーム主義は、当時の日本の世相を反映していると言えるでしょう。
物語の終盤、かすみがお腹に新しい命を宿したことを知る場面は、彼女の成長と、新たな始まりを象徴しているように感じました。様々な経験を通して、世間知らずの「お嬢さん」から脱皮し、一人の女性として、妻として、そして母として歩み始めるかすみの姿は、読者に温かい感動を与えてくれます。それは、彼女が自分自身の力で困難を乗り越え、幸福を掴み取った証でもあるのでしょう。
この作品を通して三島由紀夫が描きたかったのは、単なる恋愛の駆け引きや結婚生活の顛末だけではないように思います。それは、人間が他者との関わりの中でいかに影響を受け、成長していくかという普遍的なテーマであり、また、表面的な事象に惑わされず、物事の本質を見抜くことの重要性ではないでしょうか。かすみは、浅子という鏡を通して自分自身を見つめ直し、真実の姿に気づくことができました。
現代社会においても、私たちは情報過多の中で、何が真実で何が虚偽なのかを見極めることが難しくなっています。そんな時代だからこそ、「お嬢さん」で描かれるような、人間同士の直接的な関わり合いや、率直な言葉の持つ力が、より一層重要になってくるのかもしれません。
そして、この物語は、結婚というものに対する一つの見方も提示しているように感じます。かすみと景一の結婚は、恋愛感情よりも打算的な側面から始まりましたが、結果的には互いを理解し合い、支え合う関係へと発展していきます。結婚の形は様々であり、必ずしも情熱的な恋愛だけがその基盤となるわけではないということを、この物語は教えてくれているようです。
登場人物たちの心の揺れ動き、特に女性心理の描写は、三島由紀夫ならではの鋭さで描かれており、読んでいて引き込まれるものがありました。かすみの不安や嫉妬、そしてそこからの解放といった感情の起伏は、多くの女性読者が共感できる部分があるのではないでしょうか。
物語の舞台となる東京の街並みや風俗の描写も、当時の雰囲気を伝える上で効果的です。銀座のブティックや喫茶店、郊外の住宅地の様子などが目に浮かぶようで、読者を1960年代の東京へと誘ってくれます。こうした細やかな描写が、物語世界にリアリティを与えているのです。
最後に、「お嬢さん」というタイトルについて改めて考えてみると、これは単にかすみの出自を示すだけでなく、彼女が物語を通して乗り越えるべき壁、あるいは成長の出発点としての意味合いも込められているように感じられます。甘やかされた環境で育ち、世間知らずだった「お嬢さん」が、様々な経験を通して現実を知り、自立した一人の人間へと変わっていく。その過程こそが、この物語の核心なのかもしれません。読後感が爽やかで、どこか希望を感じさせる作品でした。
まとめ
三島由紀夫の「お嬢さん」は、一人の若い女性が経験する心の葛藤や成長を、軽快な筆致で描き出した魅力的な作品です。主人公かすみが、偽装結婚から始まる夫との関係や、周囲の人々との交流を通じて、次第に自分自身を見つめ直し、大人へと変わっていく姿が印象的に描かれています。
物語の中では、嫉妬や誤解といった人間関係の難しさも描かれますが、それを乗り越えるためのヒントも示唆されています。特に、個性的な脇役である浅子の存在は、物語に深みを与え、かすみの成長を促す重要な役割を果たしています。彼女の言葉は、現代に生きる私たちにも響くものがあるのではないでしょうか。
1960年代という時代背景を感じさせつつも、そこで描かれる若い男女の恋愛模様や心理描写は、現代の読者にも新鮮な驚きと共感を与えてくれます。三島由紀夫の作品に初めて触れる方にも、比較的読みやすい一冊としておすすめできるでしょう。
この物語を読み終えたとき、読者はかすみの成長に温かい拍手を送りたくなるかもしれません。そして、自分自身の人間関係や生き方について、少し立ち止まって考えてみる良いきっかけを与えてくれる作品だと感じました。