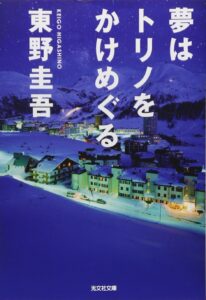 エッセイ「夢はトリノをかけめぐる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏といえば、緻密なプロットのミステリーを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、本作は少し毛色が異なります。なんと、彼の愛猫が人間になり、冬季オリンピックを目指す(?)という、奇想天外な設定のエッセイ風小説なのです。
エッセイ「夢はトリノをかけめぐる」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。東野圭吾氏といえば、緻密なプロットのミステリーを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、本作は少し毛色が異なります。なんと、彼の愛猫が人間になり、冬季オリンピックを目指す(?)という、奇想天外な設定のエッセイ風小説なのです。
舞台はトリノオリンピック。直木賞作家となったばかりの東野氏が、人間に化けた愛猫「夢吉」とともに現地へ飛ぶ。そこで繰り広げられるのは、各種競技の観戦記であり、冬季スポーツへの愛憎半ばする思いであり、そしてイタリアという国のリアルな姿です。夢吉の視点から語られることで、普段のエッセイとは一味違う、斜めからの観察眼が光ります。
この記事では、そんな「夢はトリノをかけめぐる」の物語の核心に触れつつ、その魅力を深く掘り下げていきます。単なるあらすじ紹介に留まらず、ネタバレ情報を含めた詳細な解説、そして僕自身の穿った視点からの長文感想を記します。東野ファンはもちろん、少し変わった読書体験を求めている方にも、きっと興味深い内容となるでしょう。
エッセイ「夢はトリノをかけめぐる」のあらすじ
物語は衝撃的な一文で始まります。「僕はネコである」。語り手は作家・東野圭吾氏の愛猫、夢吉。ある日突然、彼は人間の姿になってしまいます。その変貌ぶりを見た飼い主、東野氏(夢吉からは「おっさん」と呼ばれています)は、なぜか「オリンピックに出て金メダルを取れ」と無茶な指令を下すのです。猫だった頃の怠惰な生活を人間として続けることに腹を立てたのでしょうか。
こうして、夢吉とおっさんの奇妙な冬季スポーツ探訪が始まります。どの競技で金メダルを目指すのか。それを決めるため、二人は札幌の「冬季戦技教育隊」などを訪れ、様々な選手や関係者から話を聞いて回ります。スキー、スノーボード、スケート、カーリング… 各競技の現状や課題、魅力に触れる中で、夢吉とおっさんは冬季スポーツの世界に深く引き込まれていきますが、肝心の種目はなかなか決まりません。
そんな中、おっさんは直木賞を受賞。その授賞式翌日という慌ただしいスケジュールで、編集者の「黒衣君」も伴い、トリノオリンピックが開催されているイタリアへと旅立ちます。現地では、カーリングの「チーム青森」の活躍、荒川静香選手の金メダル獲得の瞬間に立ち会い、ジャンプ団体やスノーボードクロスなどを観戦。言葉の壁に苦労しながらも、指さし会話帳を片手に奮闘し、オリンピックの熱気と感動、そしてイタリアならではの(良くも悪くも)大らかな運営を体験します。
夢吉の視点を通して、トリノの街の様子、競技会場の雰囲気、そしておっさんの冬季スポーツに対する熱い思いや、時に見せる辛辣な意見が描かれます。観戦を通して、おっさんは日本の冬季スポーツ界が抱える問題点や、オリンピックでメダルを獲得するための独自の分析を展開していきます。果たして、彼らがトリノで見出したものとは何だったのでしょうか。そして、夢吉は結局、どの種目で金メダルを目指すことになるのでしょう。
エッセイ「夢はトリノをかけめぐる」の長文感想(ネタバレあり)
さて、東野圭吾氏の「夢はトリノをかけめぐる」。これを単なる「トリノ五輪観戦記」と片付けるのは、あまりにも芸がないというものでしょう。なにせ、語り手が「人間に化けた猫」なのですから。この設定だけで、普通の旅行記やエッセイとは一線を画す、独特の味わいが生まれています。東野氏自身が「エッセイは苦手だから」という理由でこの形式を選んだとあとがきで語っていますが、結果として、その「苦手意識」が功を奏したと言えるのかもしれません。
まず面白いのが、この「夢吉」という視点人物の設定です。彼は元々猫ですから、人間社会の常識や建前に縛られません。飼い主である「おっさん」こと東野氏に対しても、遠慮なくツッコミを入れたり、その言動を冷静(あるいは冷淡)に観察したりします。おっさんが冬季スポーツの現状を憂い、熱く語れば語るほど、夢吉の「やれやれ、また始まった」的な視線が、読者にある種の共感、あるいはクスリとした笑いを誘うのです。これは、東野氏自身が三人称で自分を描くのとは全く異なる効果を生んでいます。自己批評的な視線を、愛猫というフィルターを通すことで、嫌味なく、むしろ愛嬌をもって描き出すことに成功しているのです。
おっさんと夢吉、そして編集者の黒衣君。この三人のトリノでの道中は、珍道中と呼ぶにふさわしいものです。言葉の壁、文化の違い、そして何よりイタリア特有の「アバウトさ」。特にトイレ事情に関する執拗なまでの描写は、東野氏の几帳面な性格をうかがわせると同時に、海外旅行経験者なら誰もが一度は感じるであろう「不便さ」への共感を呼びます。高級ホテルだろうが競技会場だろうが、お構いなしに汚いトイレ。この一点だけでも、イタリアという国、そしてオリンピックという巨大イベントの裏側を垣間見るようで興味深い。指さし会話帳を駆使して現地の人々と交流しようとする姿も、微笑ましくも切実です。
しかし、本作は単なるドタバタ旅行記ではありません。根底には、東野氏の深い「冬季スポーツ愛」と、それゆえの「危機感」が流れています。特に、ご自身が嗜むスノーボードをはじめとする雪上競技に対する思い入れは強いようです。日本における冬季スポーツのマイナーさ、競技人口の少なさ、強化体制の不備、メディアの扱いの小ささ…。これらが相互に作用し、負のスパイラルを生んでいる現状を、彼は繰り返し指摘します。
「なぜ、日本は冬季オリンピックで勝てないのか?」
この問いに対する彼の分析は、なかなか鋭いものがあります。例えば、最終盤で展開される「メダル至上主義」と「入賞者の多さ」をめぐる夢吉との対話。メダル獲得に特化して資源を集中投下する中国のような戦略が良いのか、それとも多くの種目で入賞者を出すことで、全体の裾野を広げ、多様な楽しみ方を提供する日本のあり方が良いのか。東野氏は後者を支持します。結果だけを見ればメダルが多い方が華々しいかもしれない。しかし、様々な競技で「もしかしたら」と思える選手がいる方が、観る側としては多様な興奮を味わえるし、それが結果的に競技全体の発展につながるのではないか、と。これは、単なるスポーツ論にとどまらず、多様性や持続可能性といった、より大きなテーマにも通じる視点と言えるでしょう。
僕自身は、正直なところ、オリンピックやスポーツ観戦というものに、それほど熱心な人間ではありません。参考文章にあった『筋書きがないドラマだからつまらない』という友人の意見には、なるほど、一理あると感じてしまうタイプです。試合全体の流れよりも、編集されたハイライトの方が効率的に興奮を得られる、と考えてしまう。また、国を背負う選手への過度な期待や、結果が出なかった際のメディアや一部の観客によるバッシングには、正直うんざりさせられることも少なくありません。外野が騒ぎ立てる姿は、どうにも品がないように思えてしまうのです。
しかし、本作を読むと、東野氏の「それでも、スポーツには、冬季スポーツには可能性がある」という情熱が伝わってきます。彼が指摘するように、スキーやスノーボードは、都市生活者にとって「自然に触れる」貴重な機会を与えてくれます。雪という自然現象を意識し、その量や質を気にかける。それは、ひいては環境問題への関心にも繋がっていく。巻末の書き下ろし短編「2056 クーリンピック」では、温暖化によって冬季五輪が消滅した未来が描かれており、彼の懸念が単なる杞憂ではないことを示唆しています。このあたりは、単なるスポーツ愛好家ではなく、社会を見つめる作家としての視点が感じられる部分です。
そして、何よりこの作品をユニークにしているのは、やはり夢吉の存在でしょう。彼が人間になった理由は最後まで明かされません。オリンピックを目指すという当初の目的も、トリノでの観戦を経て、なんだか有耶無耶になっていきます。しかし、それでいいのです。この物語は、明確なゴールを目指すスポ根ものではなく、あくまで「おっさん」とその「元・猫」が、オリンピックという祭典を通して様々な物事を見聞きし、感じ、考える、そのプロセスそのものを楽しむためのものだからです。夢吉の、どこか達観したような、それでいて時折見せる猫らしい(?)気まぐれさが、物語全体に軽妙なリズムを与えています。彼が時折漏らす「めんどくさい」「早く帰って寝たい」といった本音は、オリンピックの熱狂に対する、ある種の清涼剤のようです。それはまるで、喧騒の中でふと見つけた、静かな裏通りのカフェのような、心地よい距離感を与えてくれます。
ファンタジーの設定を借りながらも、描かれているのは極めて現実的なトリノの姿であり、冬季スポーツ界の課題であり、そして東野圭吾という一人の作家(兼スノーボード愛好家)の偽らざる思いです。フィクションとノンフィクションの境界線を曖昧にしながら、読者を不思議な読書体験へと誘う。ミステリーとは違う形で、東野氏の「語りの巧みさ」を堪能できる一冊と言えるでしょう。気軽に読めるエンターテイメント性の中に、社会やスポーツに対する批評的な視点が織り込まれている。そのバランス感覚が、本作の大きな魅力ではないでしょうか。トリノ五輪から時は流れましたが、冬季スポーツを取り巻く状況が劇的に改善されたとは言い難い現在、彼の提起した問題は、今なお有効性を失っていないように思えます。
まとめ
エッセイ「夢はトリノをかけめぐる」は、東野圭吾氏の作品群の中でも異色の輝きを放つ一冊です。愛猫・夢吉が人間になり、飼い主である「おっさん」(東野氏)と共にトリノオリンピックを観戦するという奇抜な設定。しかし、その実態は、冬季スポーツへの深い愛情と鋭い問題意識に裏打ちされた、ユニークなエッセイ風小説となっています。
夢吉の斜めからの視点を通して語られるトリノのリアルな空気感、おっさんのスポーツに対する熱意と時折見せる辛辣な本音、そして日本の冬季スポーツ界が抱える課題。これらが、フィクションとノンフィクションの境界を自在に揺らぎながら、軽妙な筆致で描かれます。単なる観戦記に終わらない、批評性とエンターテイメント性を兼ね備えた作品です。
スポーツ観戦にそれほど興味がない読者であっても、夢吉とおっさんのコミカルな掛け合いや、異文化体験としてのトリノの描写は十分に楽しめるでしょう。そして、東野ファンであれば、ミステリー作家としての顔とはまた違う、彼のパーソナルな一面や社会への関心の深さを垣間見ることができるはずです。一風変わった読書体験を求める方に、ぜひ手に取っていただきたい一作と言えます。
































































































