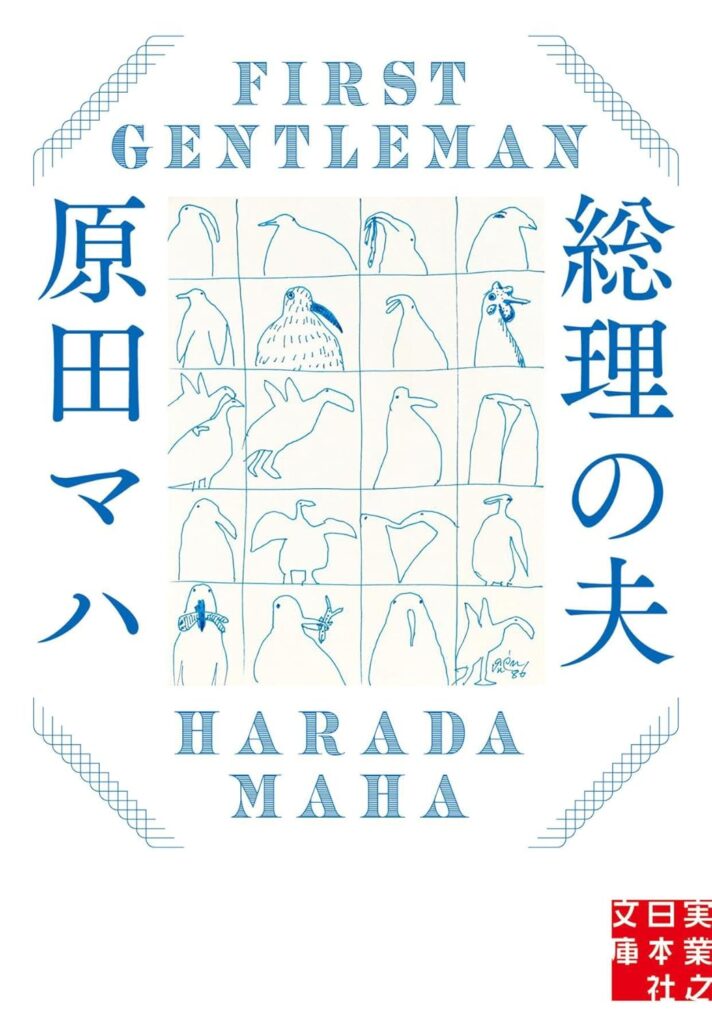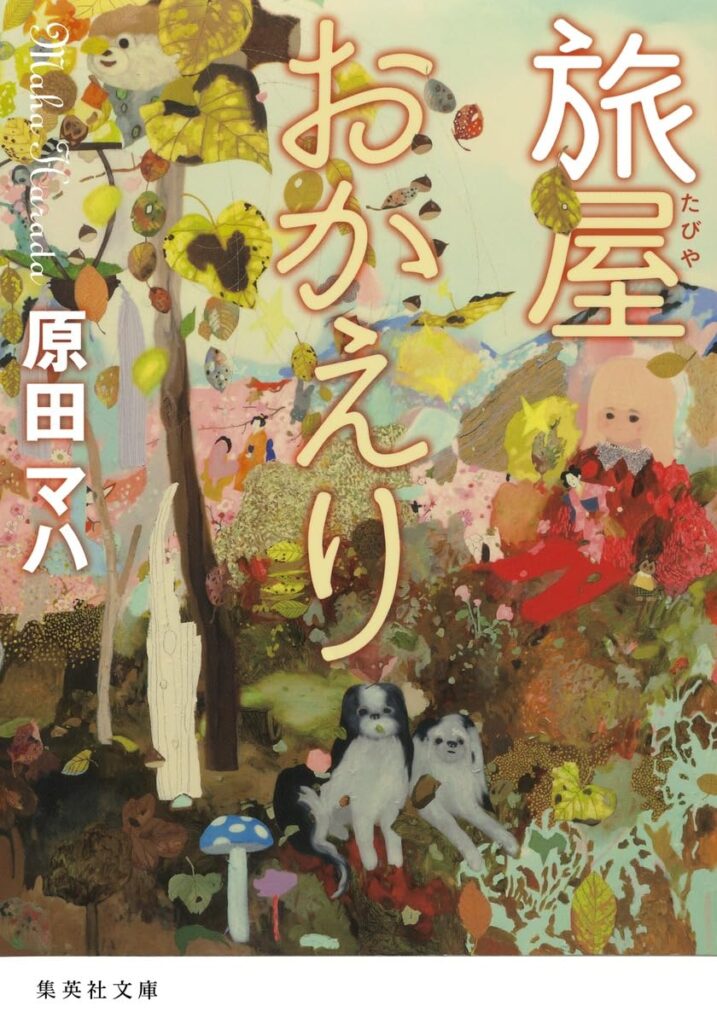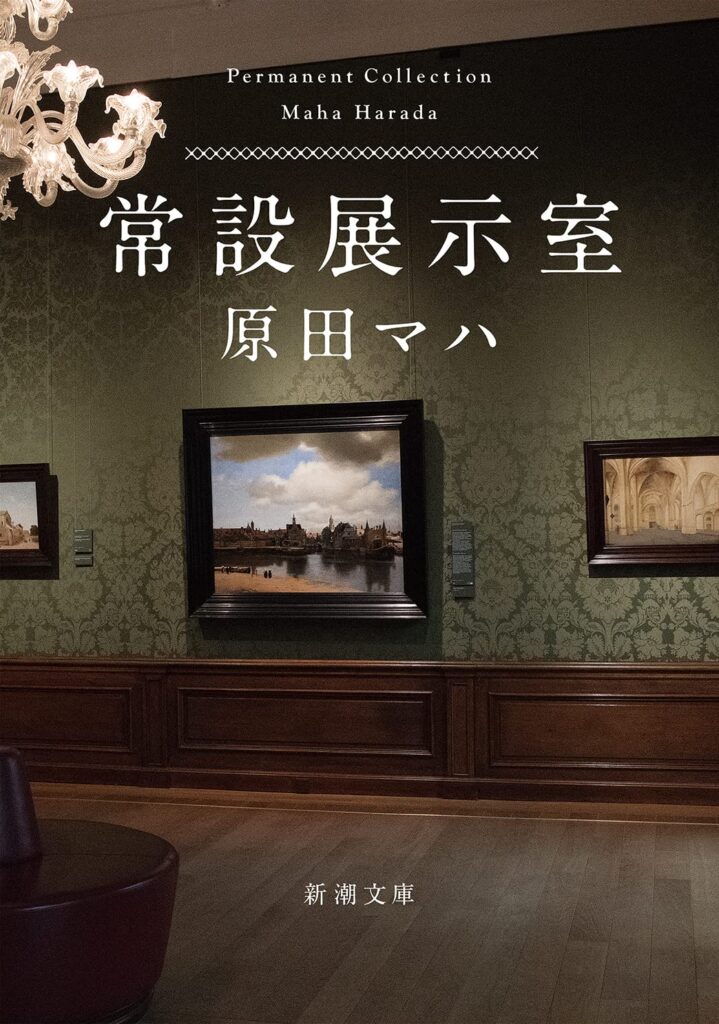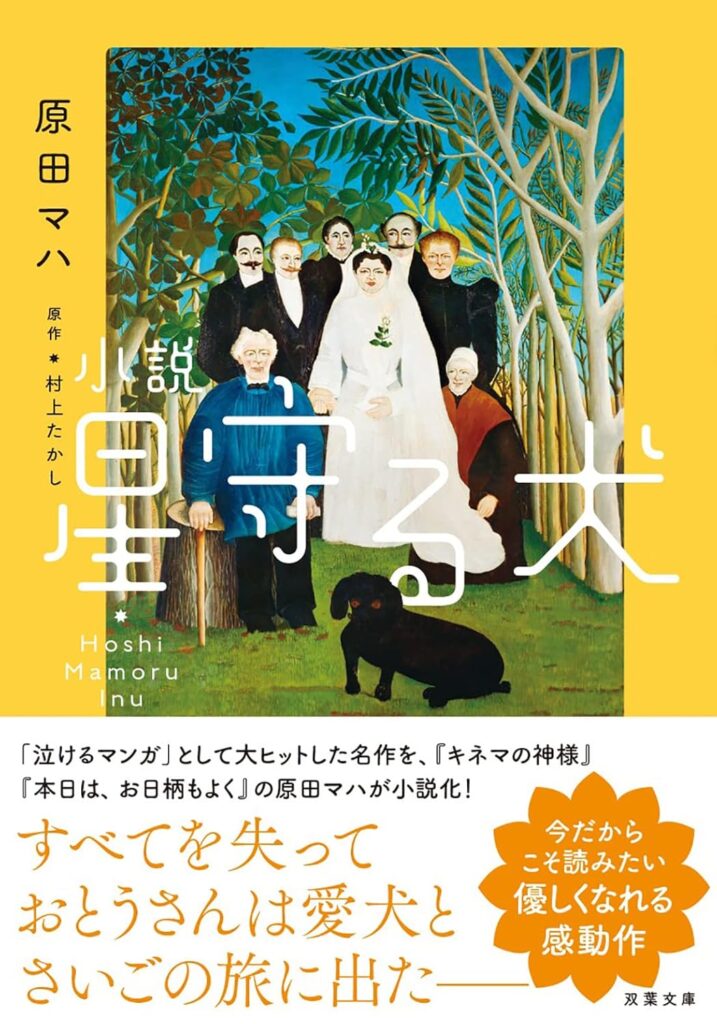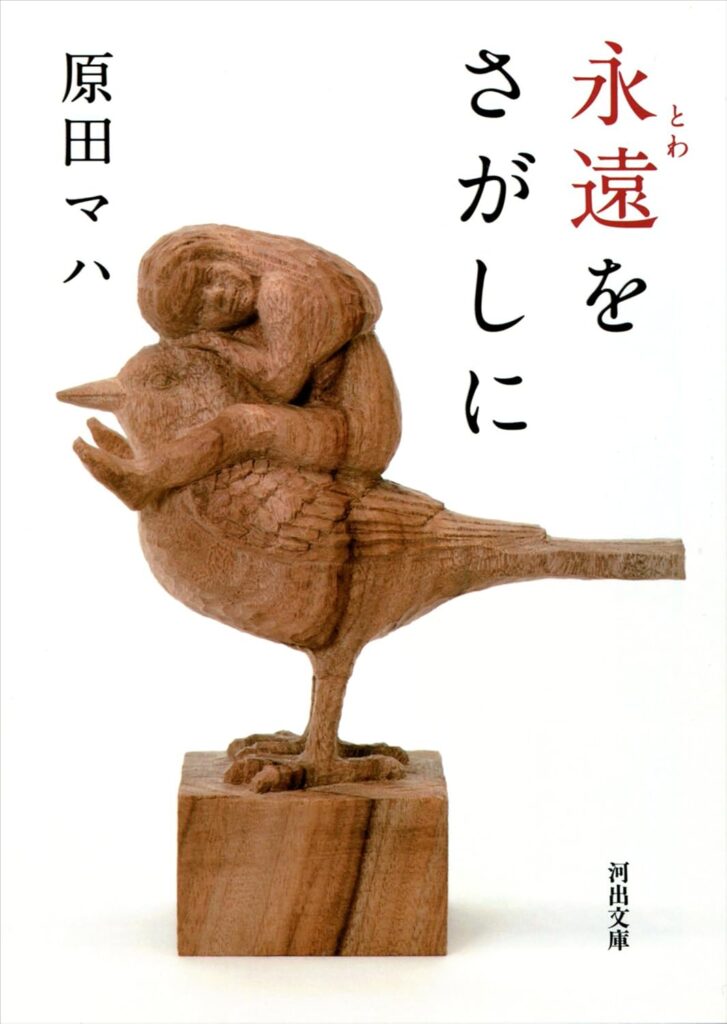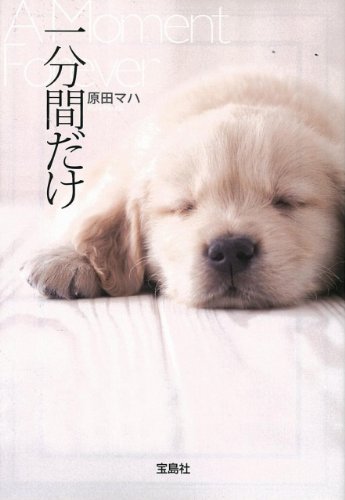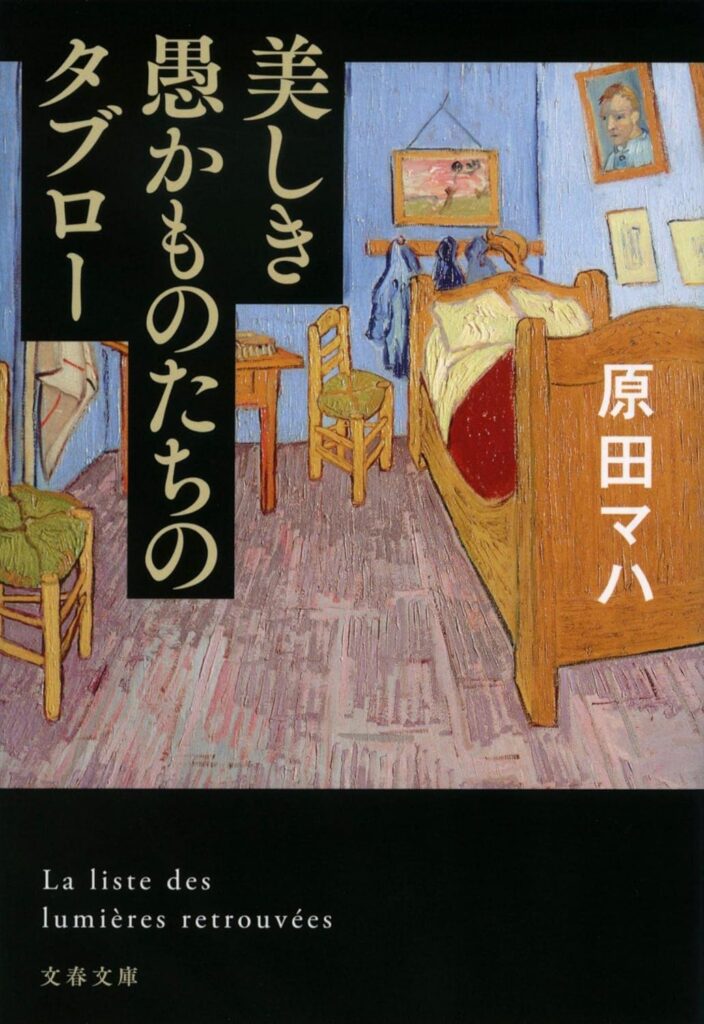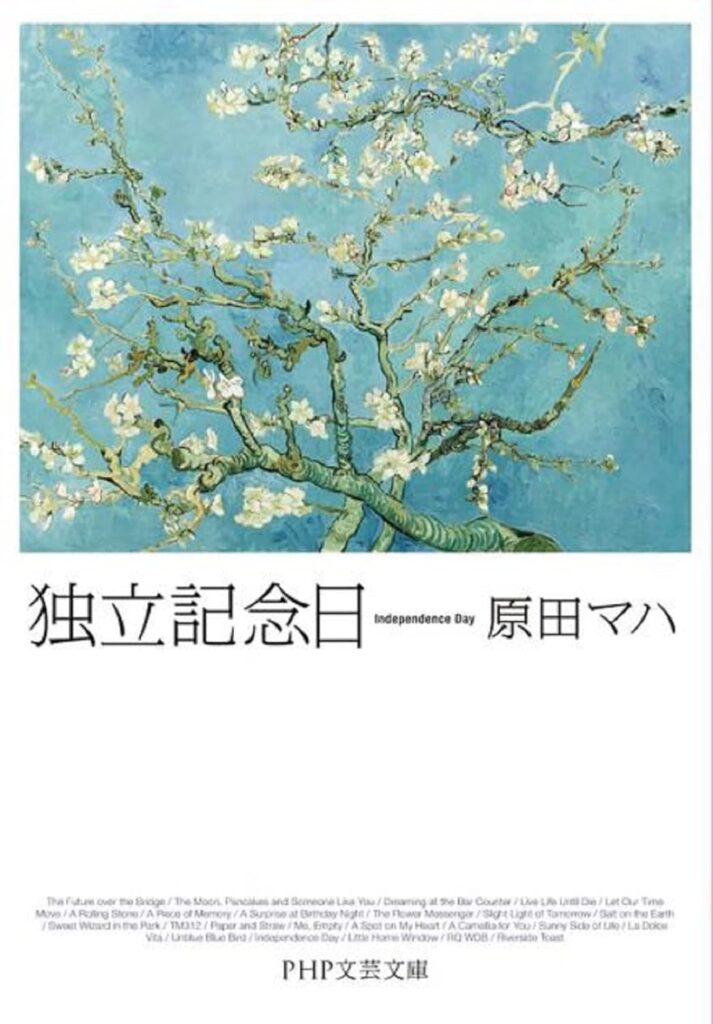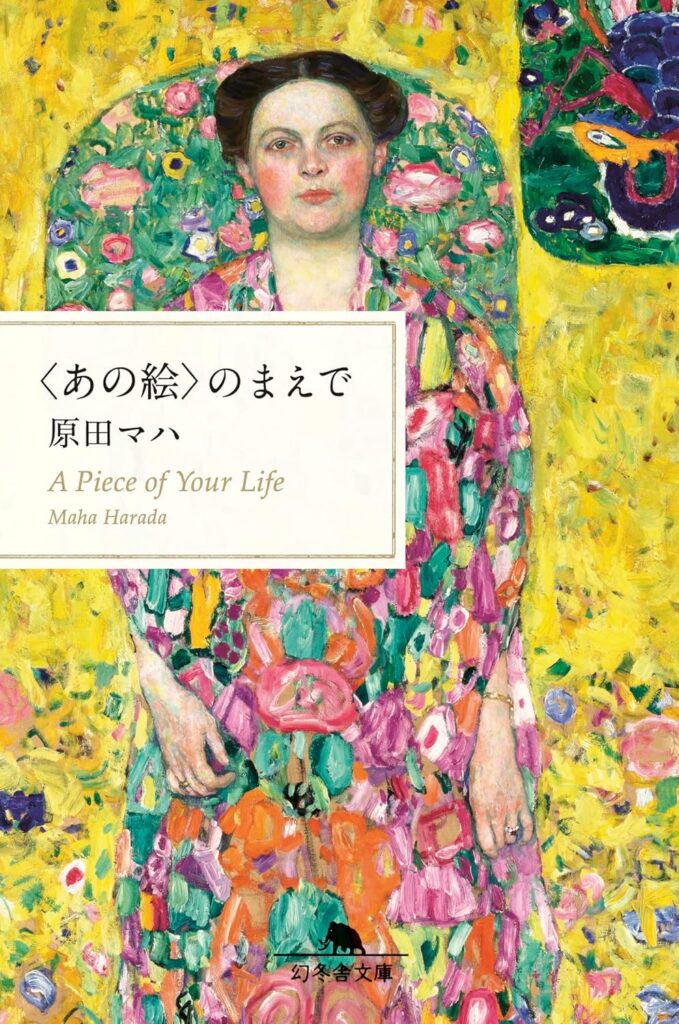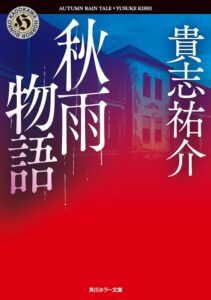 小説「秋雨物語」のあらすじを、ネタバレ込みで紹介します。長文でその深淵なる魅力に迫る批評も展開しますので、どうぞお楽しみください。貴志祐介氏が紡ぎ出すこの短編集は、読者の心にじっとりとした恐怖と、抗いがたい不条理を深く刻み込むことでしょう。まるで肌寒い秋の雨が降り続くかのように、物語全体を覆う陰鬱な雰囲気は、読む者の日常にひび割れを生じさせ、見えない恐怖が確かに存在するのだと囁きかけてきます。
小説「秋雨物語」のあらすじを、ネタバレ込みで紹介します。長文でその深淵なる魅力に迫る批評も展開しますので、どうぞお楽しみください。貴志祐介氏が紡ぎ出すこの短編集は、読者の心にじっとりとした恐怖と、抗いがたい不条理を深く刻み込むことでしょう。まるで肌寒い秋の雨が降り続くかのように、物語全体を覆う陰鬱な雰囲気は、読む者の日常にひび割れを生じさせ、見えない恐怖が確かに存在するのだと囁きかけてきます。
本書を手に取った方は、きっとそのタイトルから、幽玄で美しい物語を想像されるかもしれません。しかし、現実はその想像をはるかに超える、人間の業と宿命を深くえぐり取る内容です。貴志氏の作品に共通する「逃れられない絶望」というテーマは、本作でより一層研ぎ澄まされ、読者を底なし沼のような世界へと誘います。それぞれの物語が独立していながらも、根底に流れる「生きながらにして地獄を見る」という共通の感覚が、読後も長く心に残り続けるはずです。
小説「秋雨物語」のあらすじ
「秋雨物語」は、貴志祐介氏が描く四つの独立した短編からなる、不条理と絶望に満ちた奇譚集です。上田秋成の古典「雨月物語」にオマージュを捧げつつも、現代的な解釈で人間の内面に潜む闇を深く掘り下げています。収録作は「餓鬼の田」、「フーグ」、「白鳥の歌」、そして「こっくりさん」の四編です。
「餓鬼の田」では、恋愛がうまくいかない男・青田の奇妙な体験が語られます。彼は前世の業のために誰とも結ばれない運命にあると信じており、その告白失敗の連続は、常識では考えられない理由ばかり。愛を渇望しながらも、永遠に孤独である彼の姿は、まさに現代の「餓鬼」を彷彿とさせます。読者は、彼を襲う「飢餓」が運命的なものなのか、それとも内面的なものなのか、深い問いを投げかけられるでしょう。
続く「フーグ」は、意思に反して瞬間移動を繰り返す作家・青山の恐怖を描きます。彼は夢の中で異郷を見、目覚めると見知らぬ場所に転移しているという不可解な現象に苦しめられます。砂漠や樹海、大海原といった命の危険に晒される場所へワープさせられる彼の運命は、抗うことのできない「者の力」によって操られているかのようです。彼の残した原稿は、その異常な体験を克明に綴っており、読者を現実と非現実の境界が曖昧になる世界へと引き込みます。
「白鳥の歌」は、幻の歌声を持つ日系アメリカ人歌手ミツコ・ジョーンズの悲劇的な生涯を追う音楽奇談です。彼女の特殊な歌声の秘密を探る資産家・嵯峨の依頼を受けた作家・大西は、差別の中で生き、歌に全てを捧げたミツコの人生を知ります。世界で二人しか出せないというその歌声には、想像を絶する恐ろしい真実が隠されており、その真相は聞く者の心に深いショックを与えます。音楽がもたらす美と同時に、それが引き起こす悲劇が描かれる一篇です。
最後の「こっくりさん」は、誰もが知る遊びが命がけのデスゲームへと変貌する物語です。自殺願望を持つ小学生たちが集められ、通常のこっくりさんとは異なる残酷なルールに従い、「闇バージョン」に挑戦します。生き残る者と犠牲になる者がいるこの儀式は、参加者の切迫した状況と希死願望が交錯する中で進行します。しかし、生き残った者たちにも救いは訪れず、彼らが抱えていた問題が単なる「悩み事」ではなかったことが示唆され、人間の業の深さが浮き彫りにされます。
小説「秋雨物語」の長文感想(ネタバレあり)
貴志祐介氏の「秋雨物語」を読み終えて、まず感じたのは、乾いた恐怖と、言いようのない不条理感でした。全四編を通じて描かれるのは、人間が抗うことのできない大きな力に翻弄され、絶望へと追い込まれていく姿です。それは、古典「雨月物語」が描いた幽玄な怪異譚とは異なり、現代的な感覚に訴えかける、じっとりと心にまとわりつく「嫌な感じ」を呼び起こします。
第一編「餓鬼の田」は、現代の恋愛における「業」を痛烈に描き出しています。主人公の青田が、なぜか誰とも結ばれないという奇妙な運命を背負っている。彼が告白する相手が、ことごとく常識では考えられない理由で彼を拒絶する場面は、滑稽でありながらも、彼の絶望的な孤独を際立たせます。前世の報いという超常的な説明がなされることで、彼の恋愛における「飢餓」が、もはや個人の努力ではどうにもならない、根源的な呪縛であるかのように感じられます。特に印象的だったのは、彼が「人一倍寂しがり屋として生まれた」にもかかわらず、生涯を独りで過ごすという皮肉な運命です。これは、現代人が抱える「つながりを求める心」と「孤独」という普遍的なテーマに深く刺さります。物語は、その謎を明確に解き明かすことなく終わりますが、だからこそ、読者は青田の孤独の根源にある、説明のつかない恐怖を心に抱き続けることになります。
第二編「フーグ」は、貴志氏のSF的側面とホラー的側面が融合した、まさに真骨頂と言える作品です。作家・青山が、自身の意思とは無関係に瞬間移動を繰り返すという設定は、読者の好奇心を強く刺激します。砂漠や樹海、大海原といった死と隣り合わせの場所へワープさせられる彼の体験は、身体的な苦痛と同時に、精神的な絶望を伴います。あらゆる対策を講じても、その現象を止められないという描写は、人間の無力さをこれでもかと突きつけてきます。最終的に彼がウォーターベッドで遺体となって発見されるという皮肉な結末は、彼を動かしていたのが単なる病気ではなく、常識では説明できない「悪意に満ちた者の力」であったことを強く示唆します。この作品の最大の恐怖は、自分の身体が自分の意思では制御できないという、根源的な自由の喪失にあります。日常が突然非日常に侵食される、その理不尽さが、読者に深い不安を与えます。また、「餓鬼の田」にも登場した霊能者・賀茂禮子がここでも姿を見せることで、この短編集全体に共通する、日常に潜む超常的な現象という世界観がより強固なものになっていると感じました。
第三編「白鳥の歌」は、音楽を巡る悲劇的な奇談です。幻の歌声を持つ歌手ミツコ・ジョーンズの伝記を追う物語は、差別の中で苦難を強いられた彼女の人生と、その歌声に隠された恐ろしい真実を明らかにしていきます。特に心に残ったのは、ミツコとメアリーという、世界で二人しか出せない特殊な歌声を持つ者たちの存在です。この「特殊な歌声」が、彼女たちの歌手生命を奪う致命的な原因となったという示唆は、美と破滅が隣り合わせであることを教えてくれます。資産家・嵯峨が、その真実を知って大きなショックを受けるという結末は、単なる技術的な秘密ではなく、倫理的あるいは超常的な何か、人の業が深く関わっていることを匂わせます。この作品は、何かを極限まで突き詰めることの光と影、そして、時を超えて繋がる人々の運命を描いていると感じました。音楽が持つ、人を魅了し、時に破滅へと導く力が、静かに、しかし確実に描かれています。
そして最後の第四編「こっくりさん」は、誰もが一度は耳にしたことのある遊びが、予想もしない残酷なデスゲームへと変貌する衝撃的な作品です。自殺願望を持つ小学生たちが集められ、通常のこっくりさんとは一線を画す「闇バージョン」に挑むという設定は、貴志氏らしいひねりが効いています。生き残る者と犠牲になる者がいるというロシアンルーレットのような仕組みは、人間の本質的なエゴと、運命の残酷さを浮き彫りにします。しかし、この物語の真の恐怖は、生き残った者たちに救いが訪れないという結末にあります。彼らが抱えていた問題が、こっくりさんをもってしても解決できない「悪いこと」であったという示唆は、安易な解決策を求めることの危険性と、人間の業の深さを読者に突きつけます。表面的な恐怖だけでなく、登場人物たちの心理的な不穏さが、読後にも長く尾を引きます。これは、人生における苦悩が、そう簡単に解決できるものではないという、現実の厳しさを暗示しているようにも思えました。
「秋雨物語」は、貴志祐介氏が追求するホラー文学の新たな境地を示しています。それは、直接的な恐怖やグロテスクな描写に頼らず、人間の内面に潜む「絶望」と「業」、そして抗うことのできない「不条理」を深く掘り下げた作品集です。それぞれの物語は、読者に明確な答えを与えることなく、消化しきれない不気味さと、説明のつかない「わからなさ」を残します。しかし、その「わからなさ」こそが、この物語の真髄であり、読者の想像力を刺激し、長く心に残り続ける理由なのです。貴志氏の筆致は抑制されていながらも、読者の心にじっとりと嫌な感情を植え付け、現代社会における見えない不安や、人間の存在の根源的な闇を見事に描き出しています。まさに、現代ホラーの真髄を味わえる一冊と言えるでしょう。
まとめ
貴志祐介氏の「秋雨物語」は、私たちの日常に潜む不条理と、人間が抗うことのできない運命を描き出した、珠玉の短編集でした。収録された四つの物語は、それぞれが異なる形で「絶望」と「業」という共通のテーマを深く掘り下げ、読者の心にじっとりとした恐怖と、拭い去れない不安を残します。貴志氏ならではの、直接的な表現に頼らない「嫌な感じ」の描写が、読後も長く心にまとわりつくことでしょう。
それぞれの物語が描くのは、愛に飢える男の孤独、意思とは無関係に体がワープする作家の絶望、歌声に隠された悲劇、そして命がけの「こっくりさん」がもたらす業の深さです。これらの物語は、明確な解決策や安易な救いを提供しません。むしろ、説明のつかない現象や、人間のどうすることもできない無力感を提示することで、読者に深い余韻と、ある種の諦めすら感じさせます。
貴志祐介氏が本書で描きたかったのは、「きちんと言葉で説明できないような、結局あれは何だったんだ?という未解決な恐怖感」だったと言えるでしょう。まさにその狙い通り、本書は読者に「わからなさ」の恐怖を深く印象づけます。それは、現実離れした設定の中に、どこか身近で耳にしたことのあるようなリアルさを感じさせる、貴志氏ならではのホラーなのです。
「秋雨物語」は、単なる恐怖小説に終わらず、人間の存在の根源的な不条理や、抗うことのできない宿命、そしてその中で人々が抱える「業」を深く掘り下げた、「絶望の奇譚集」として、読者の心に長く残る作品です。ぜひ一度、この「秋雨物語」の世界に触れてみてはいかがでしょうか。

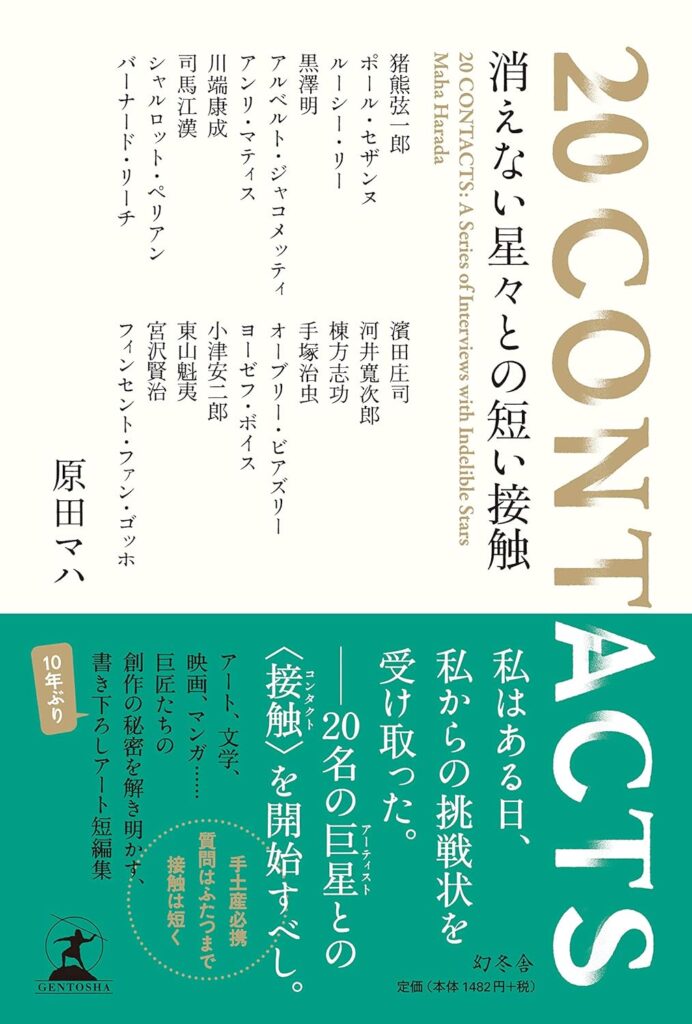
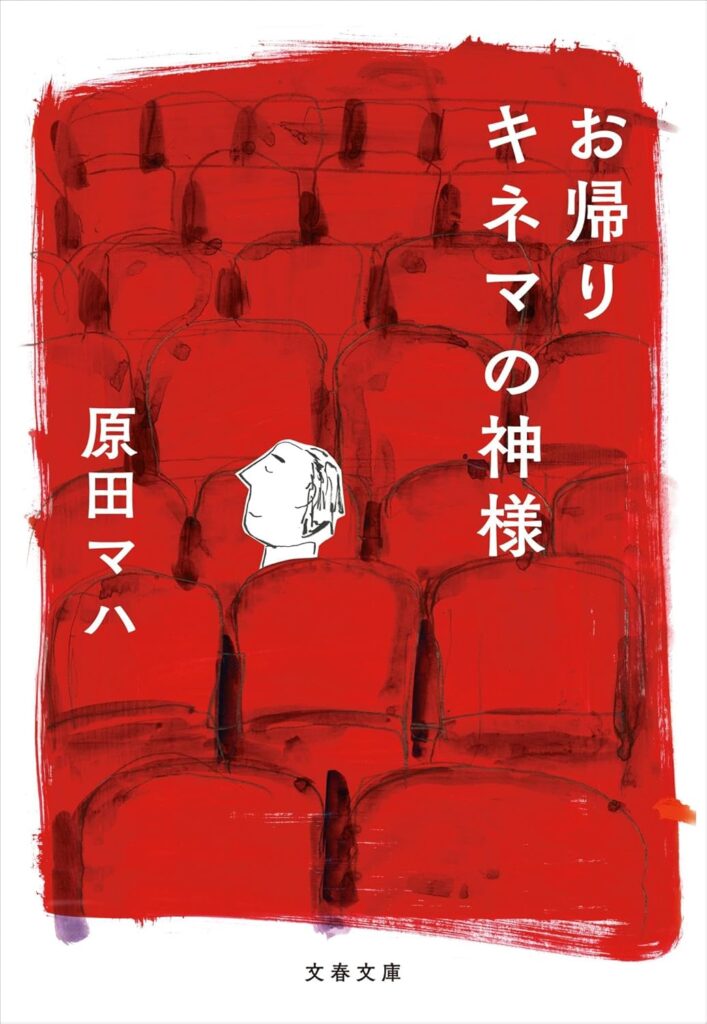
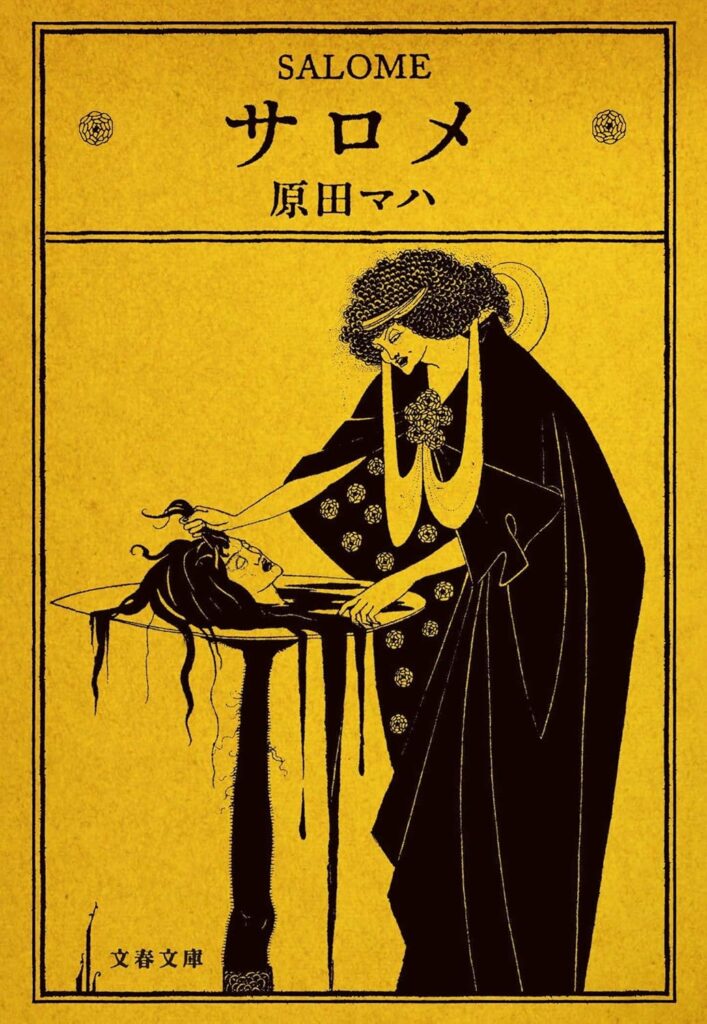
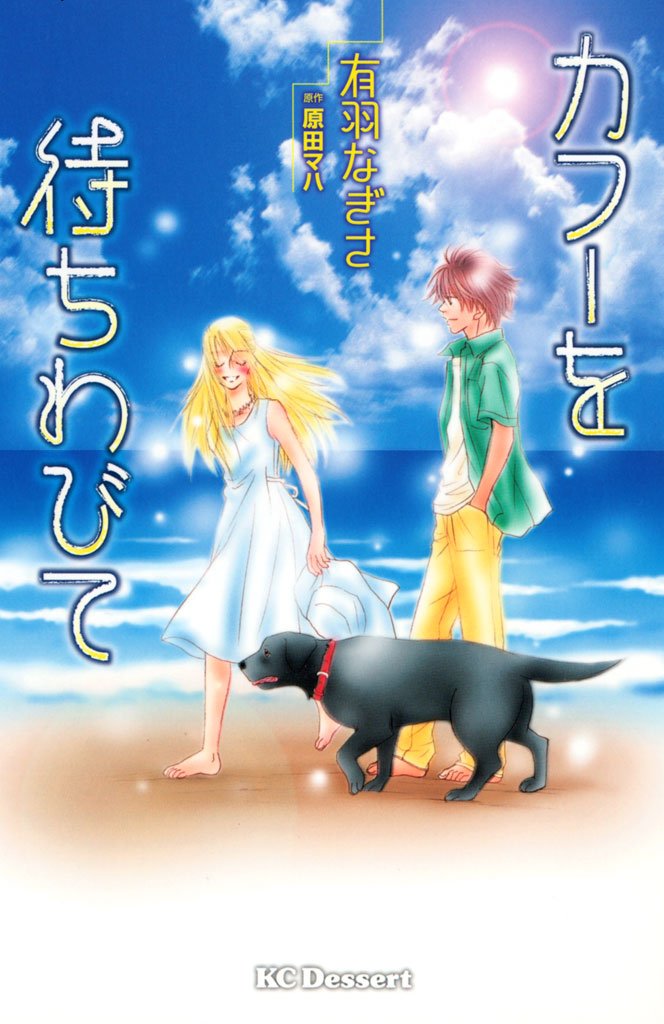
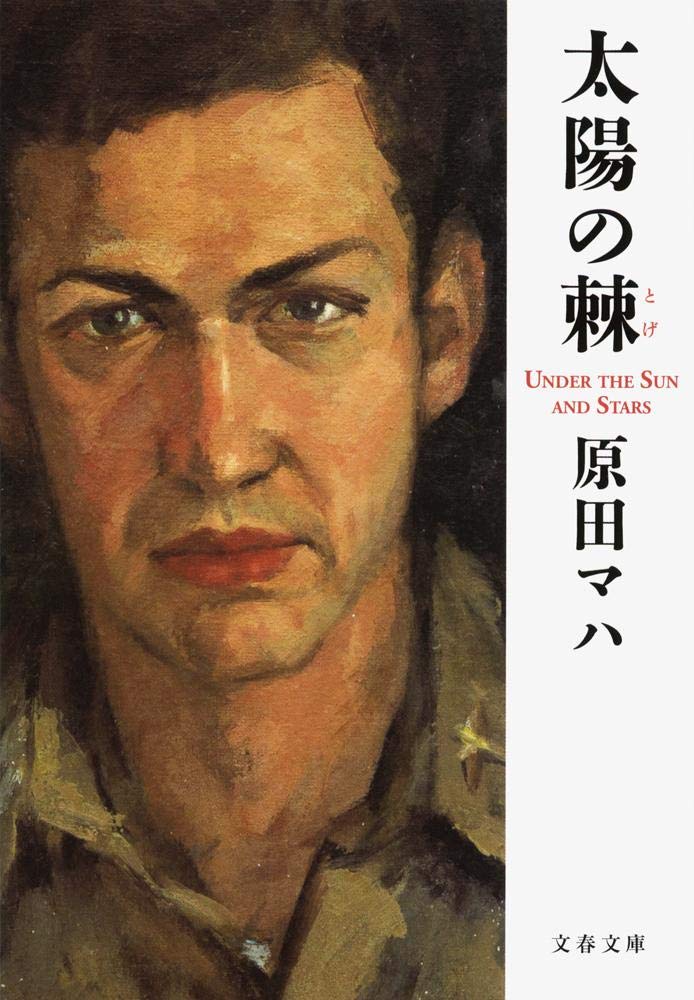
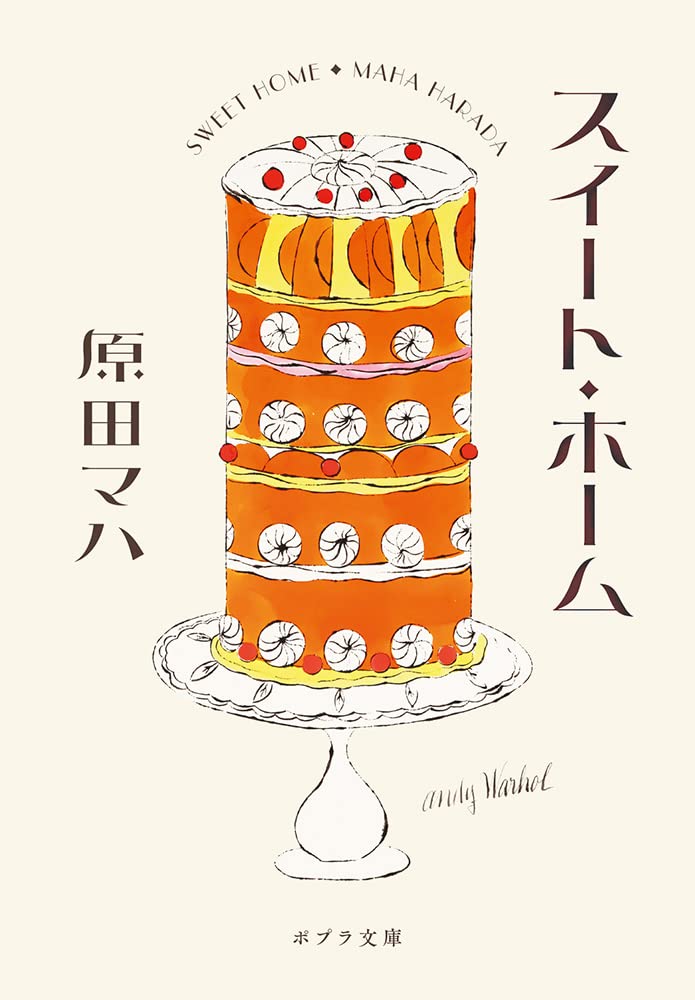
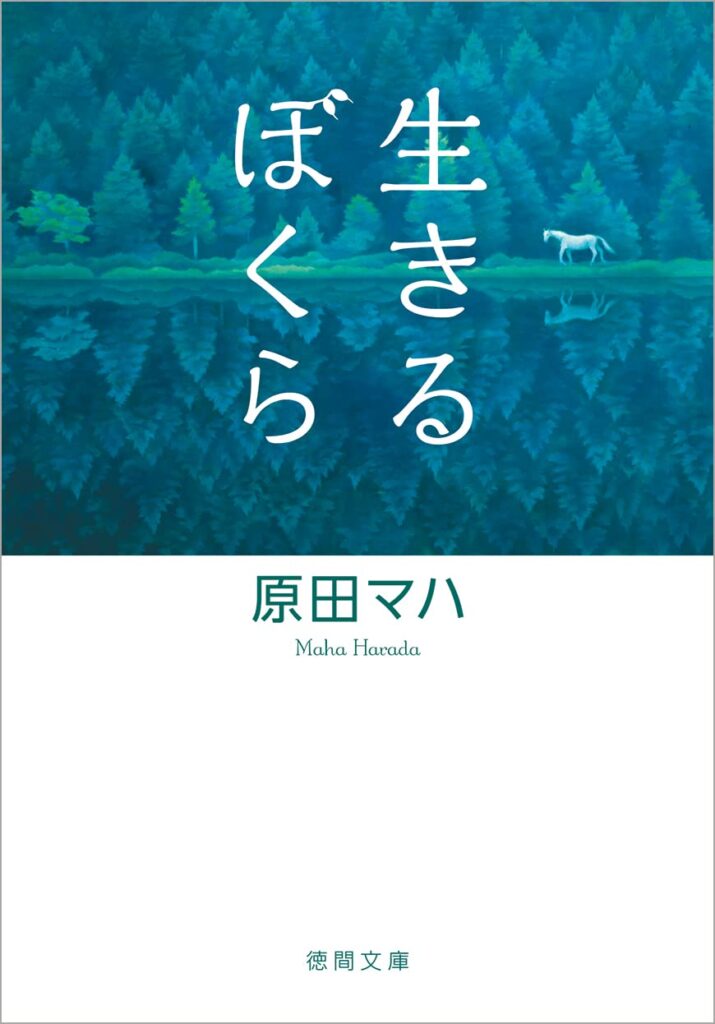
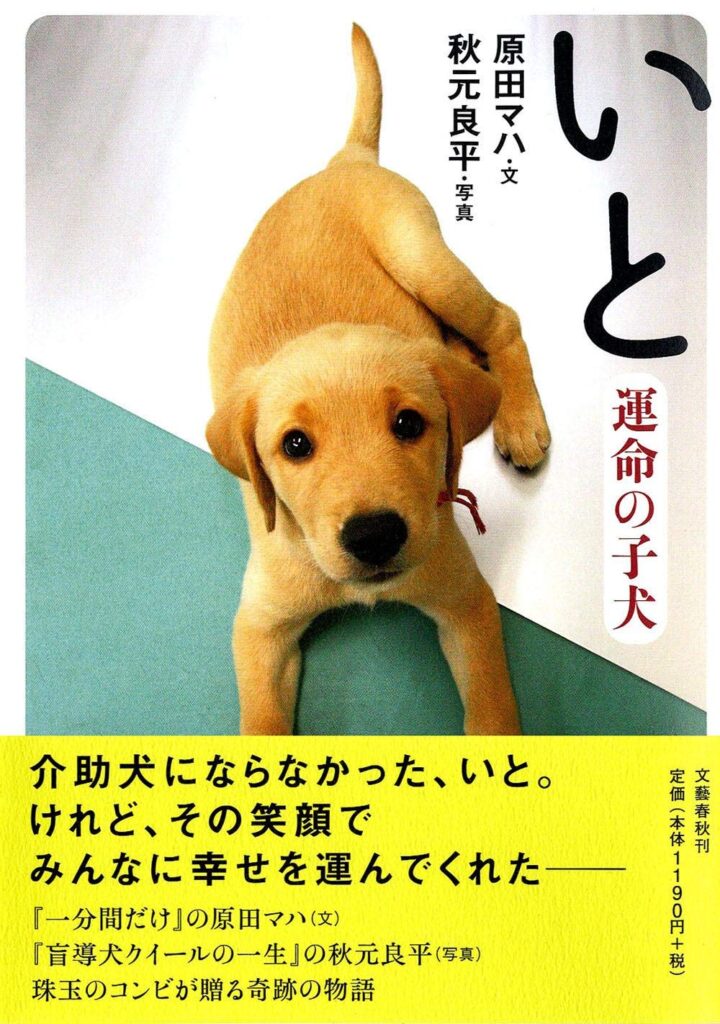
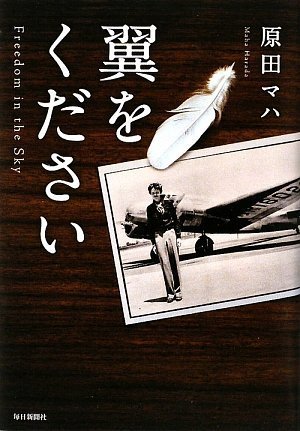
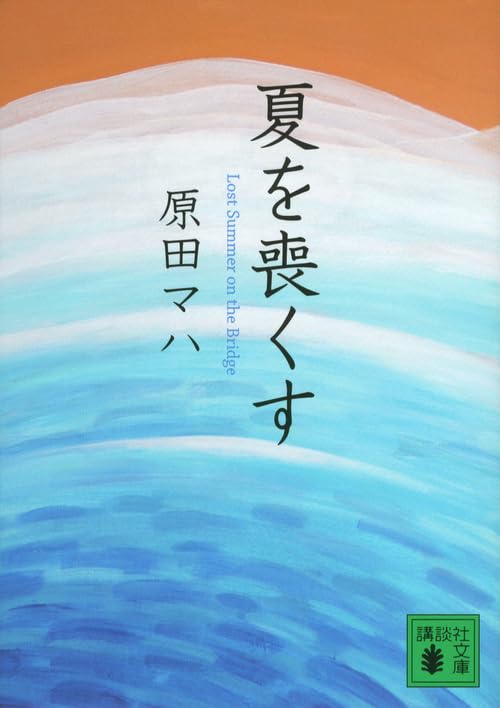

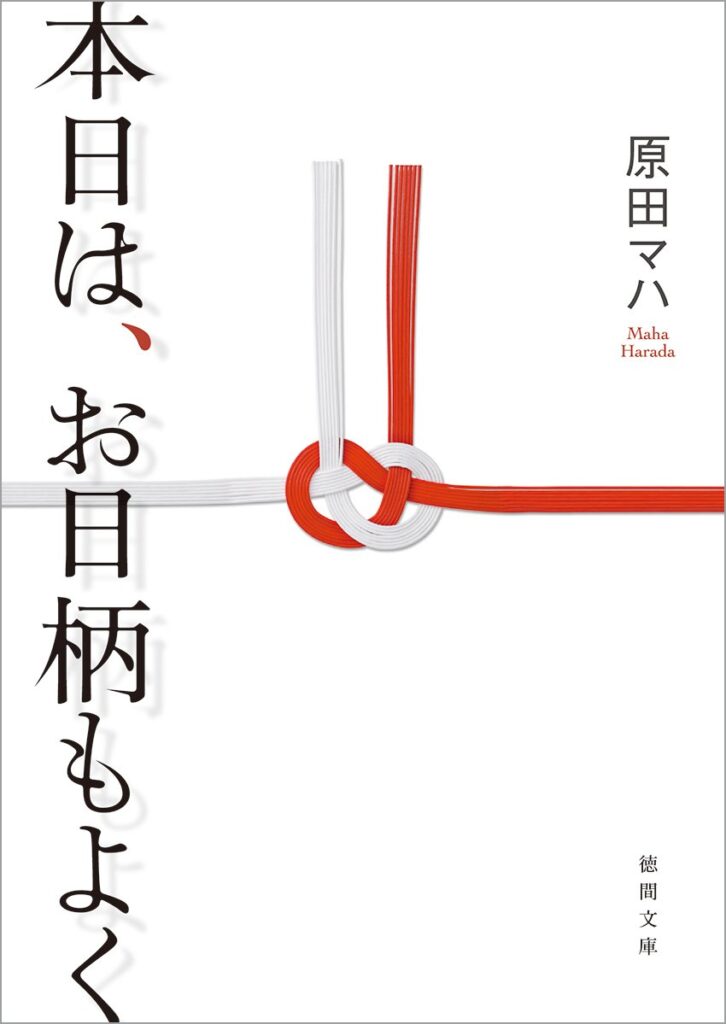
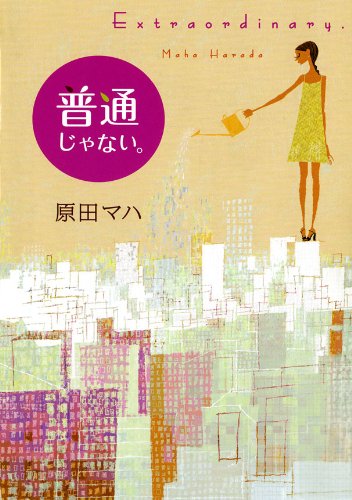
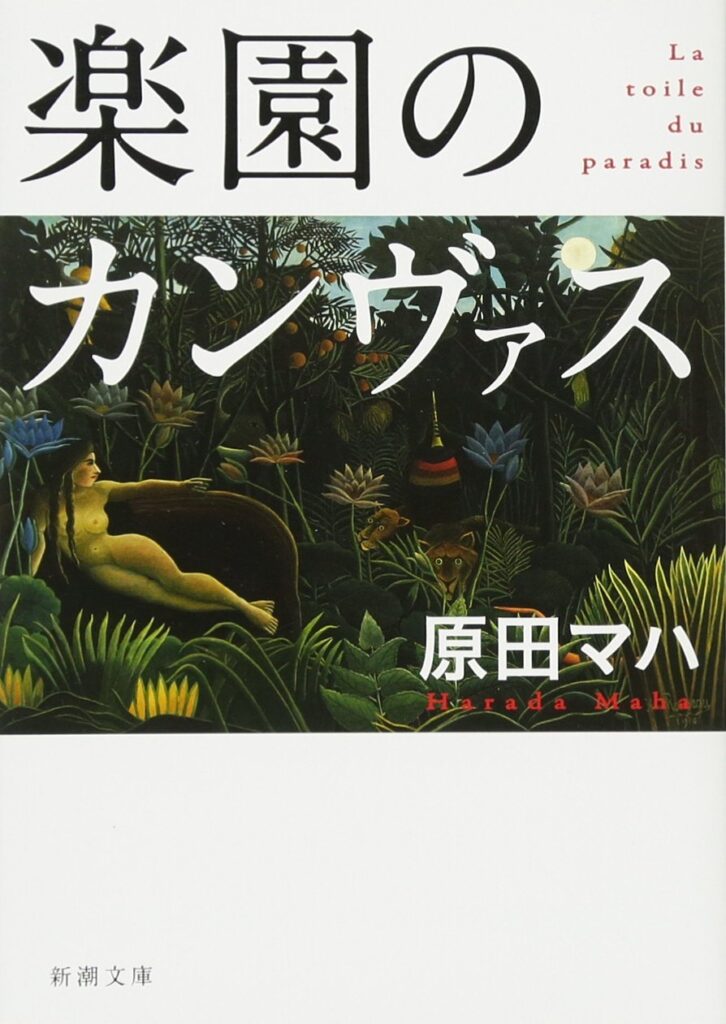
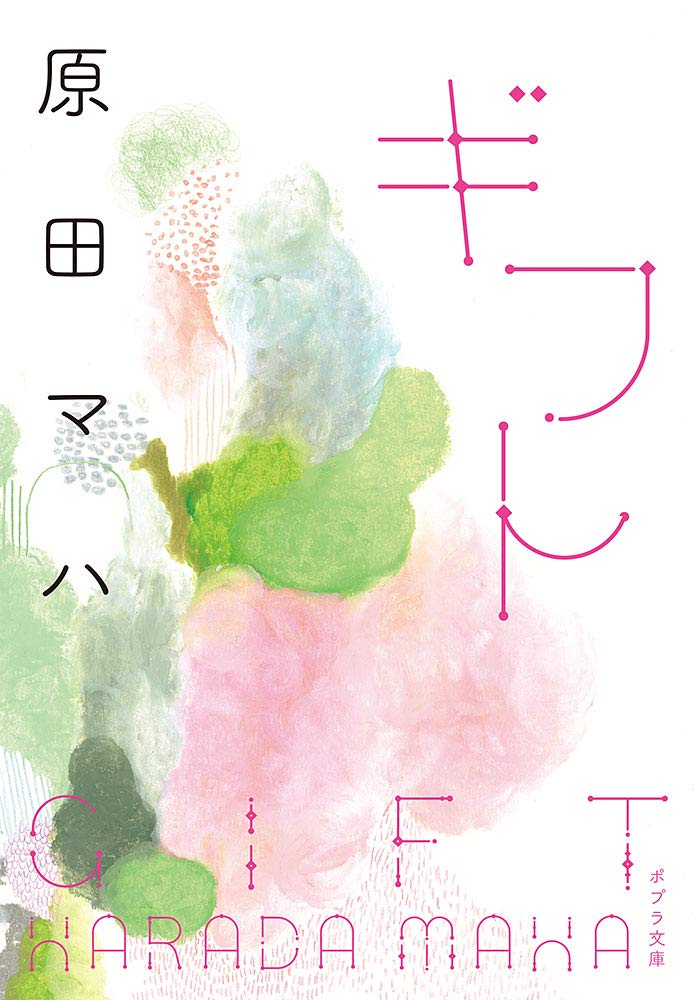
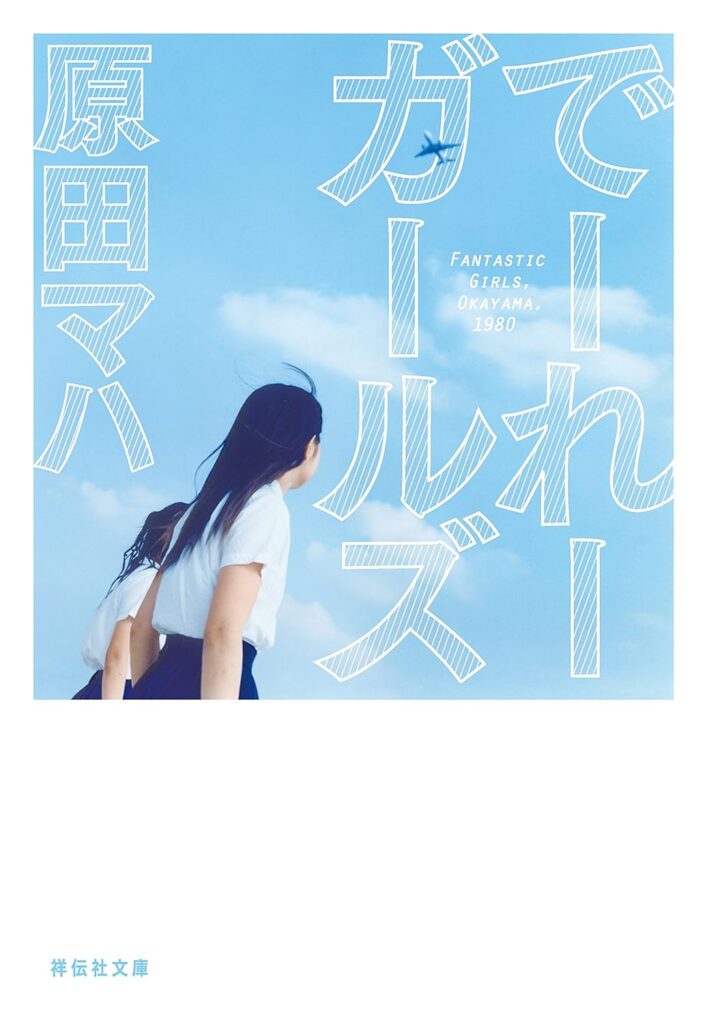
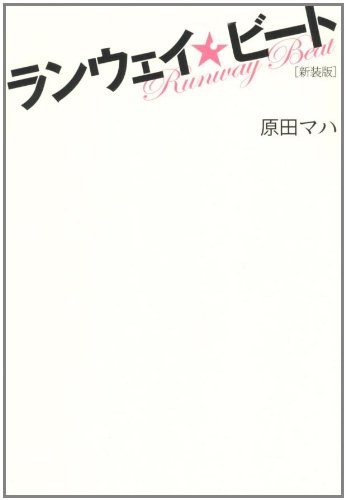
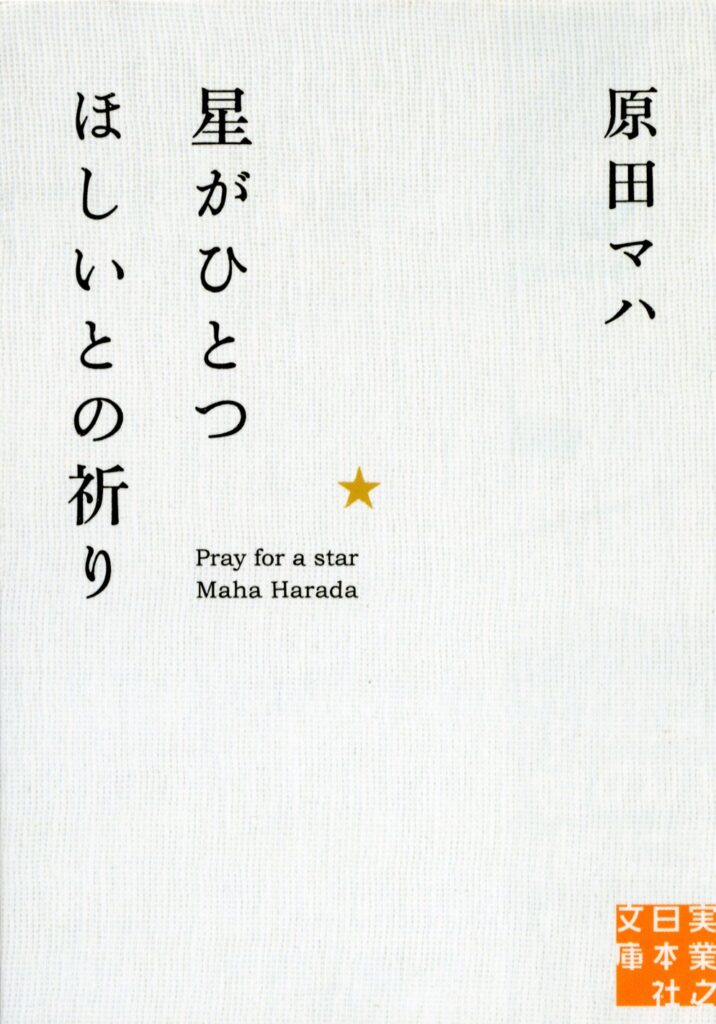
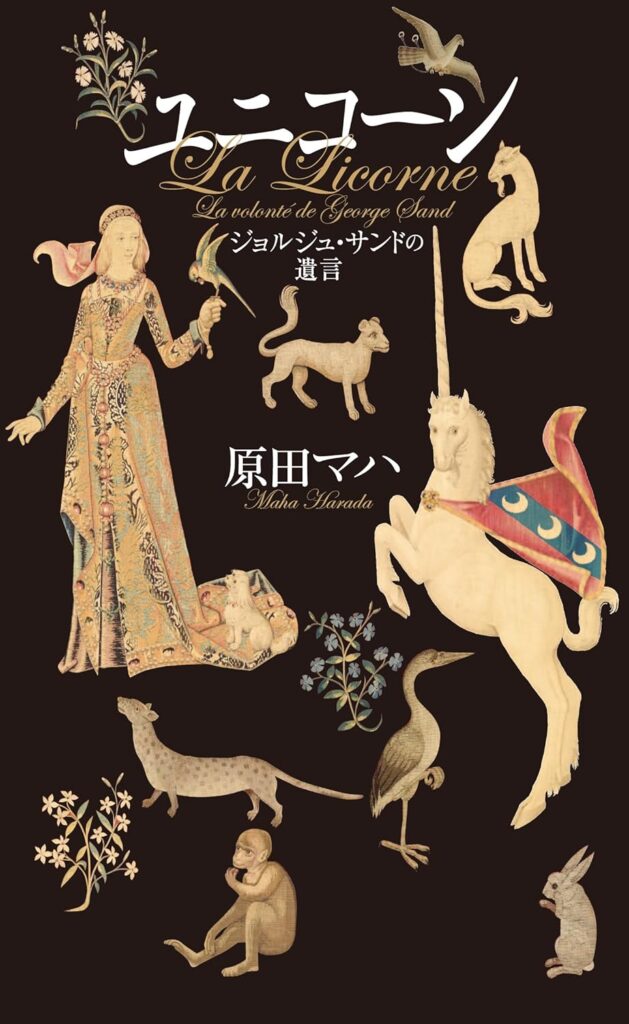
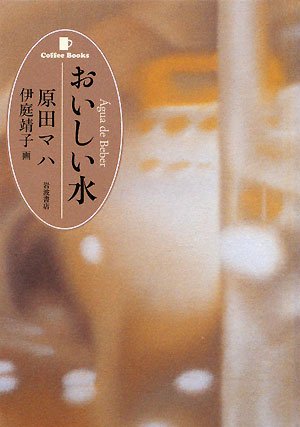
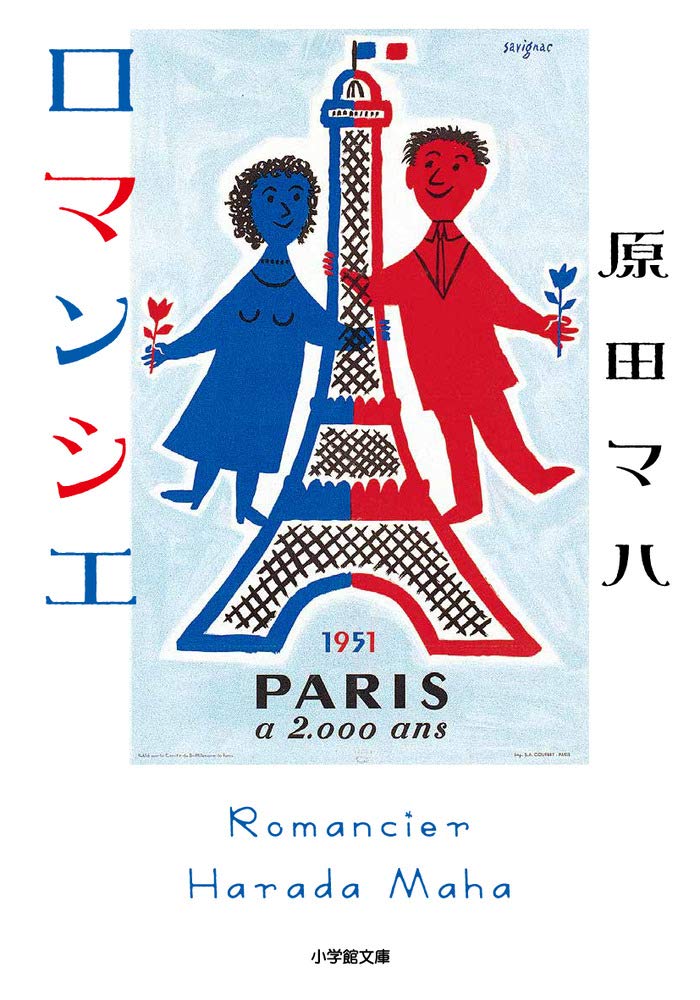
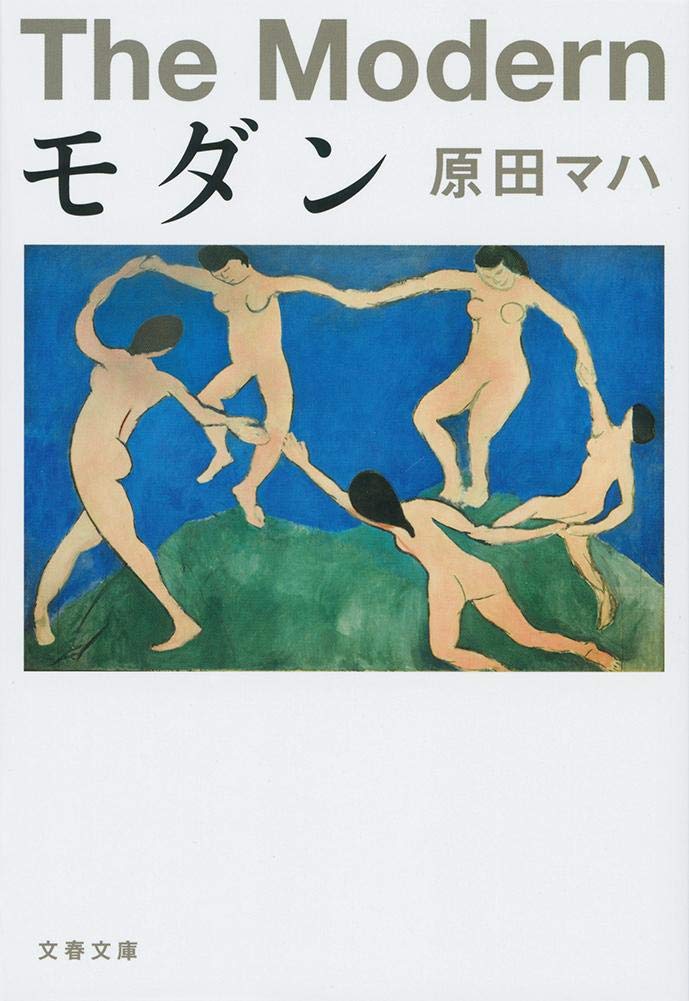
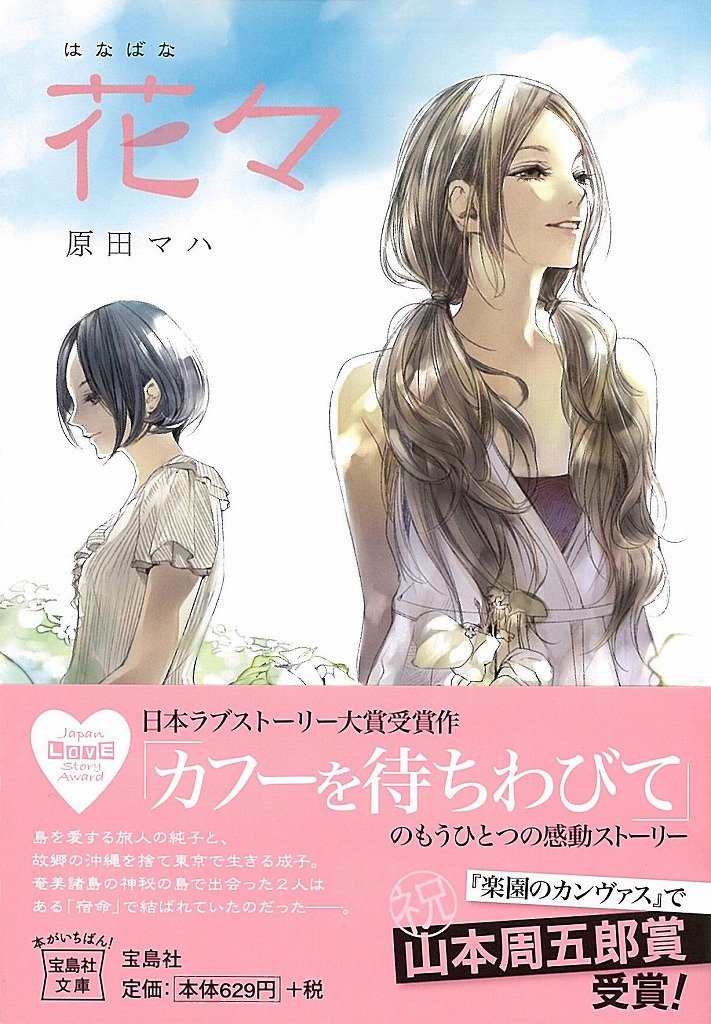
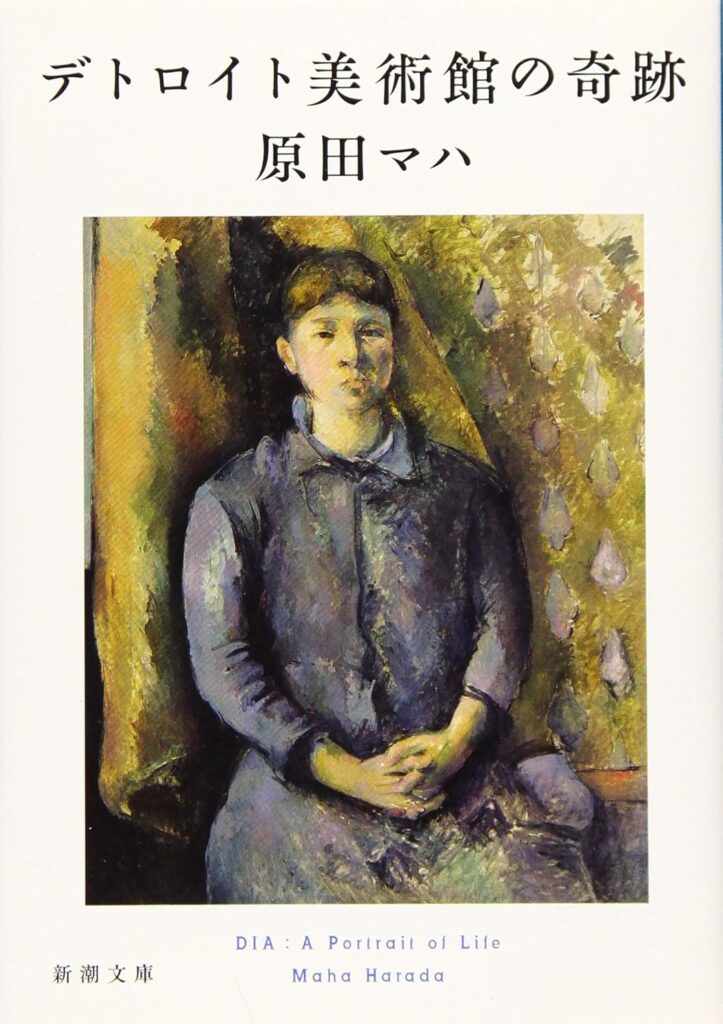
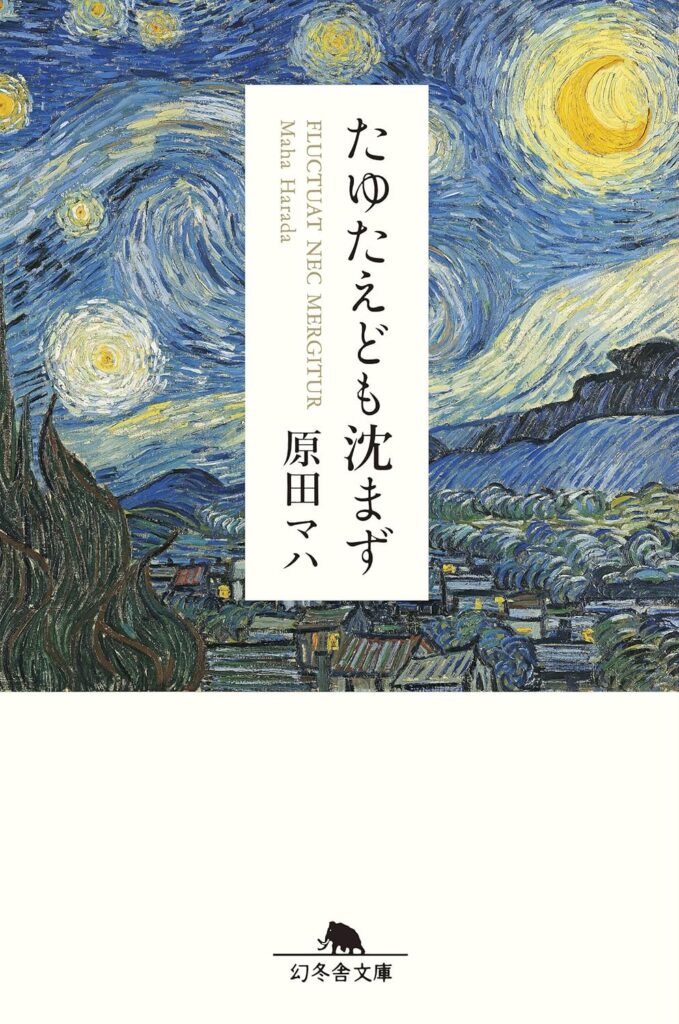
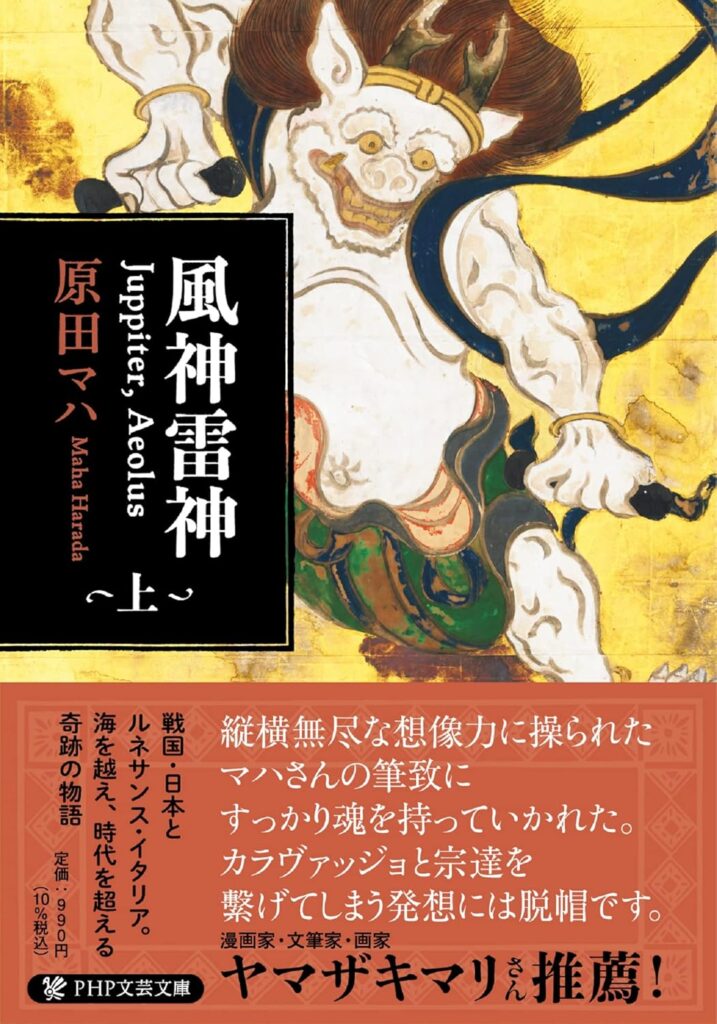
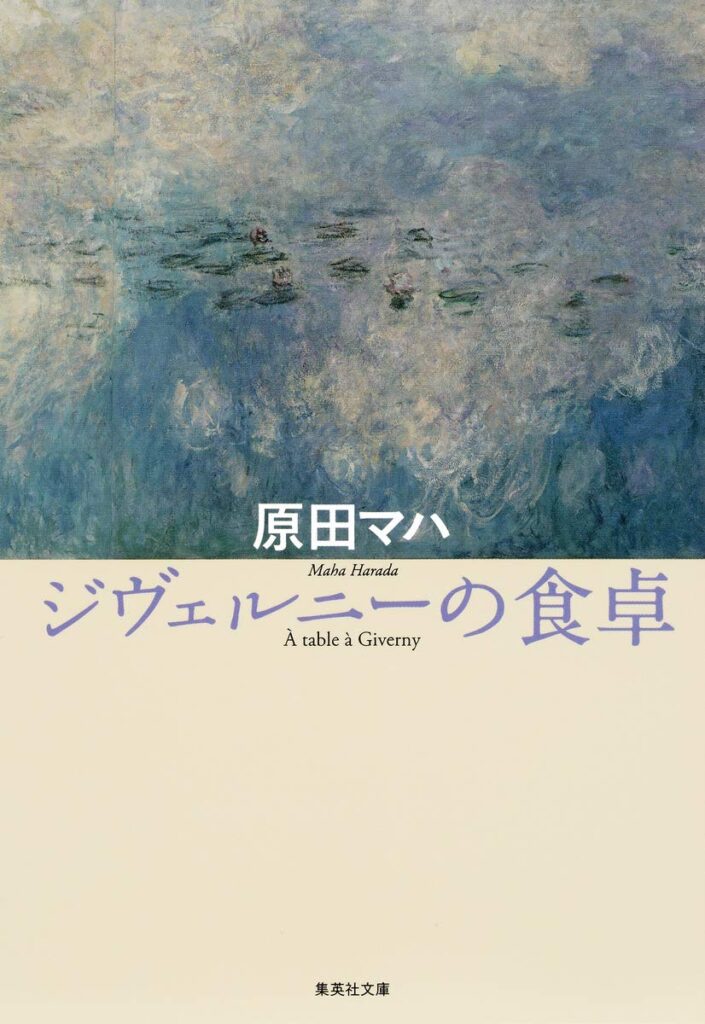
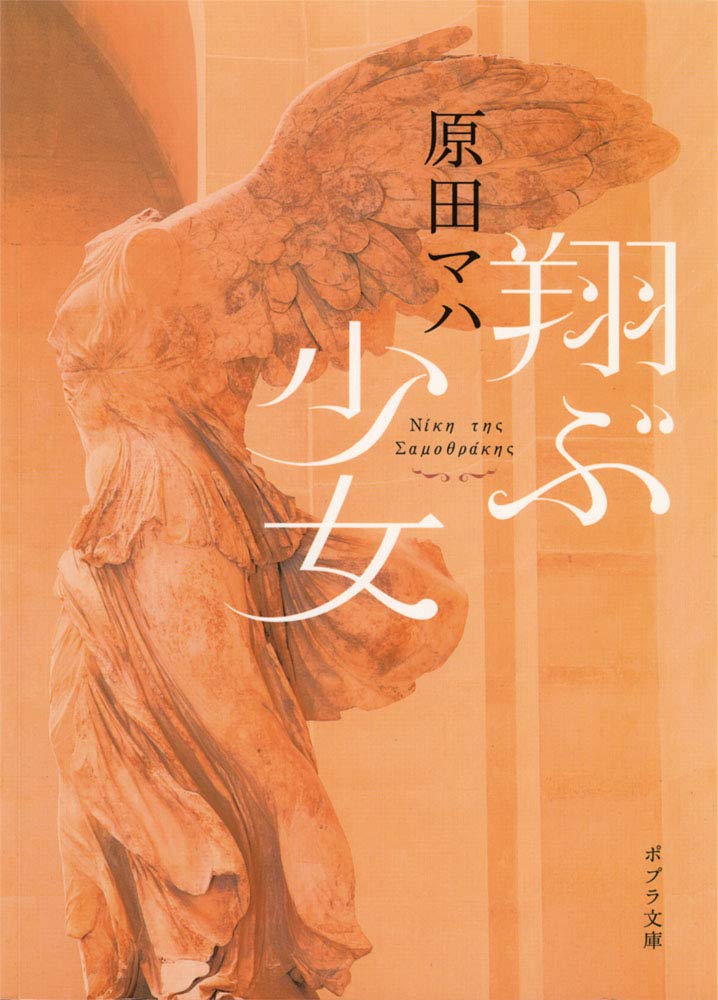
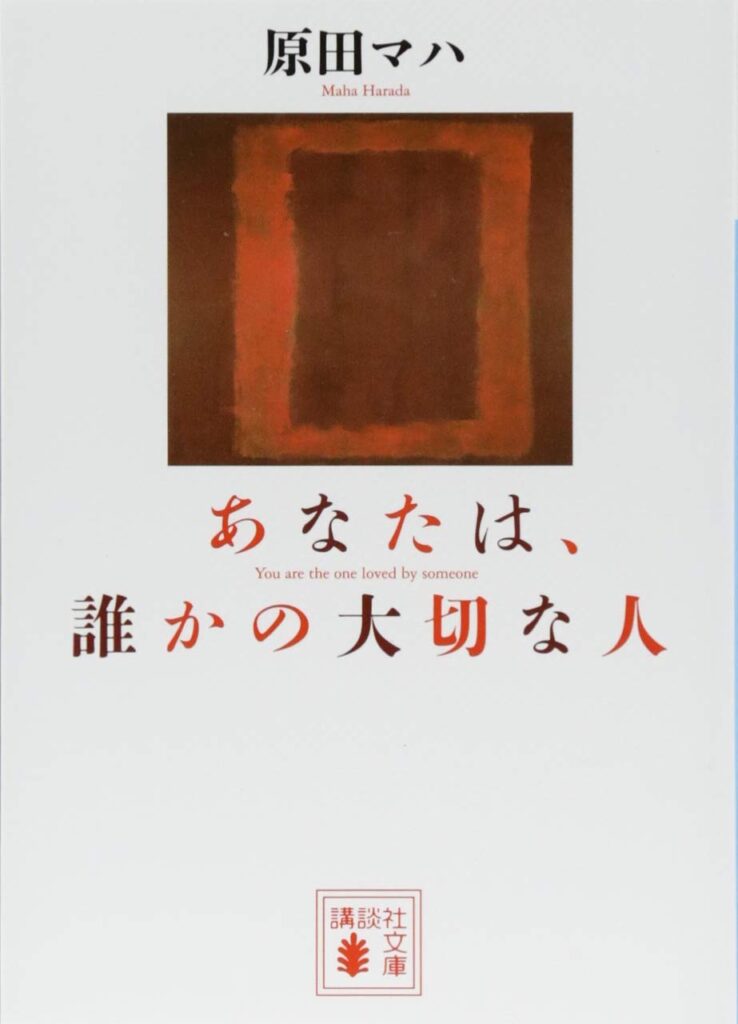
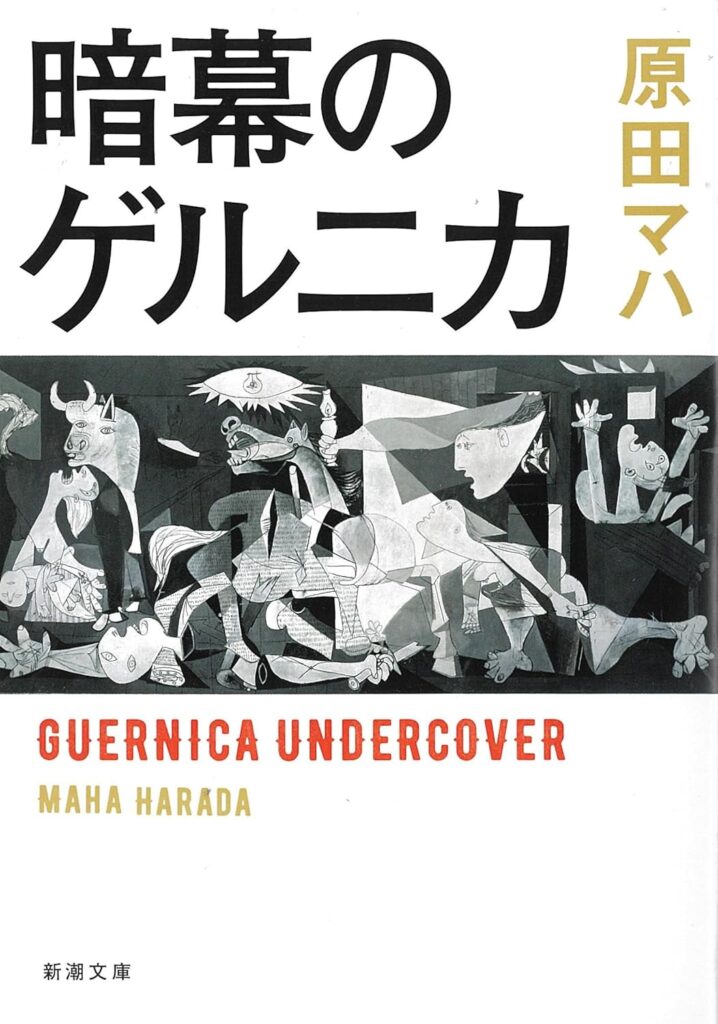
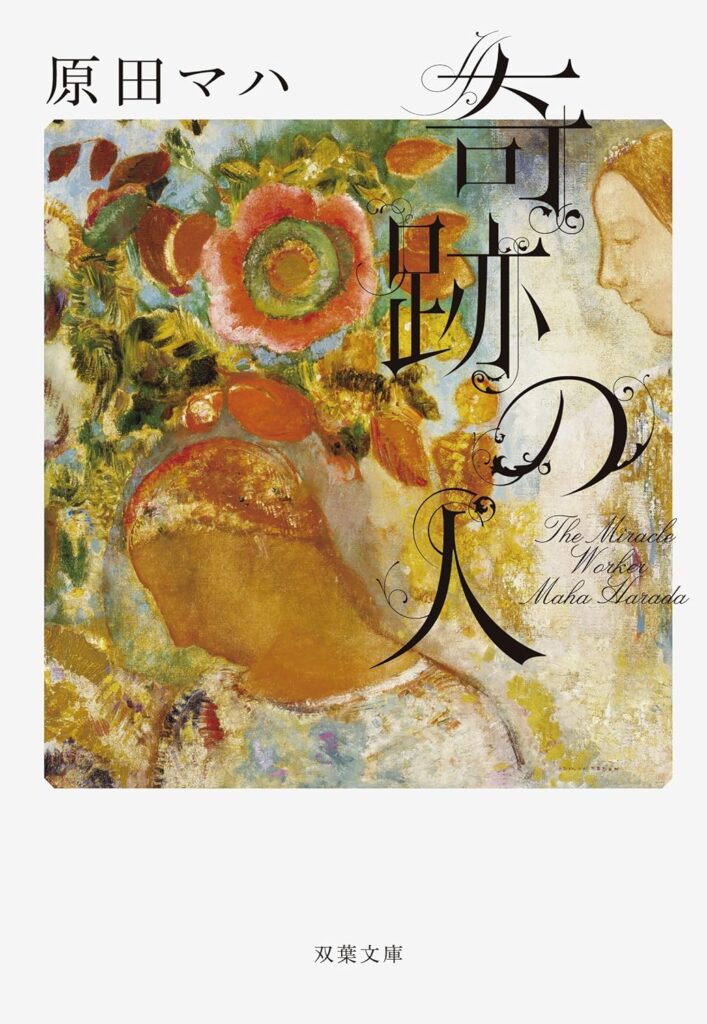
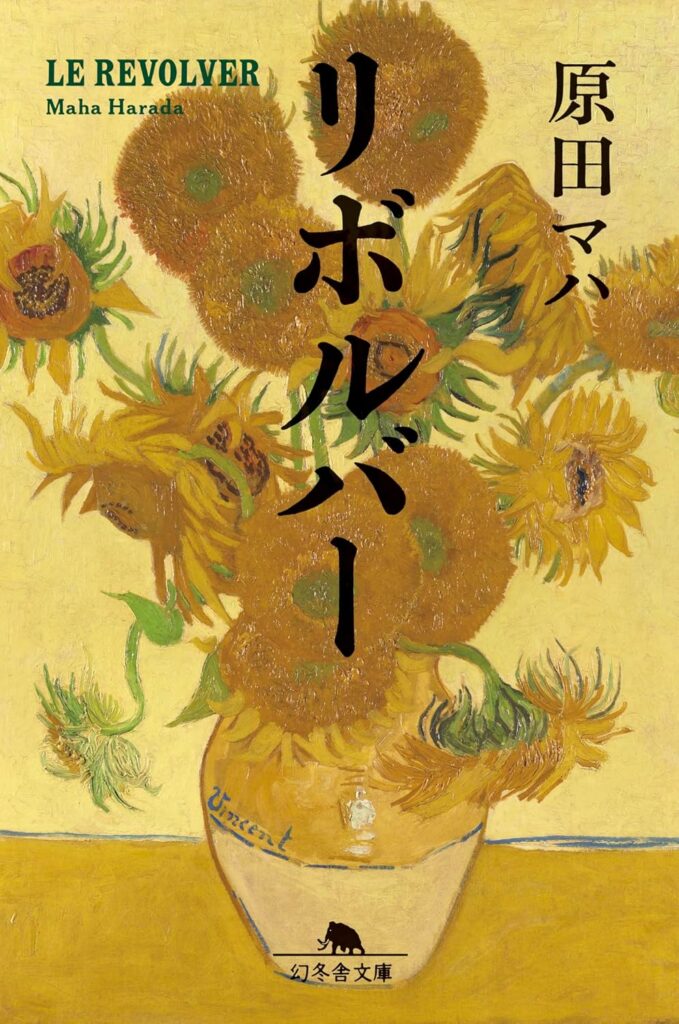
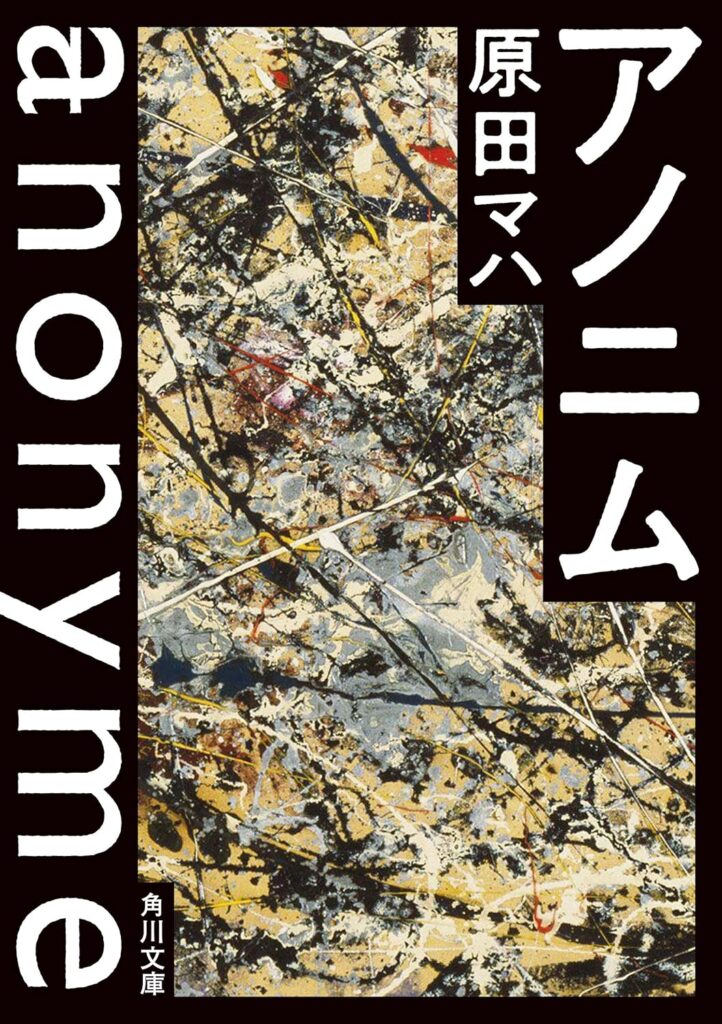
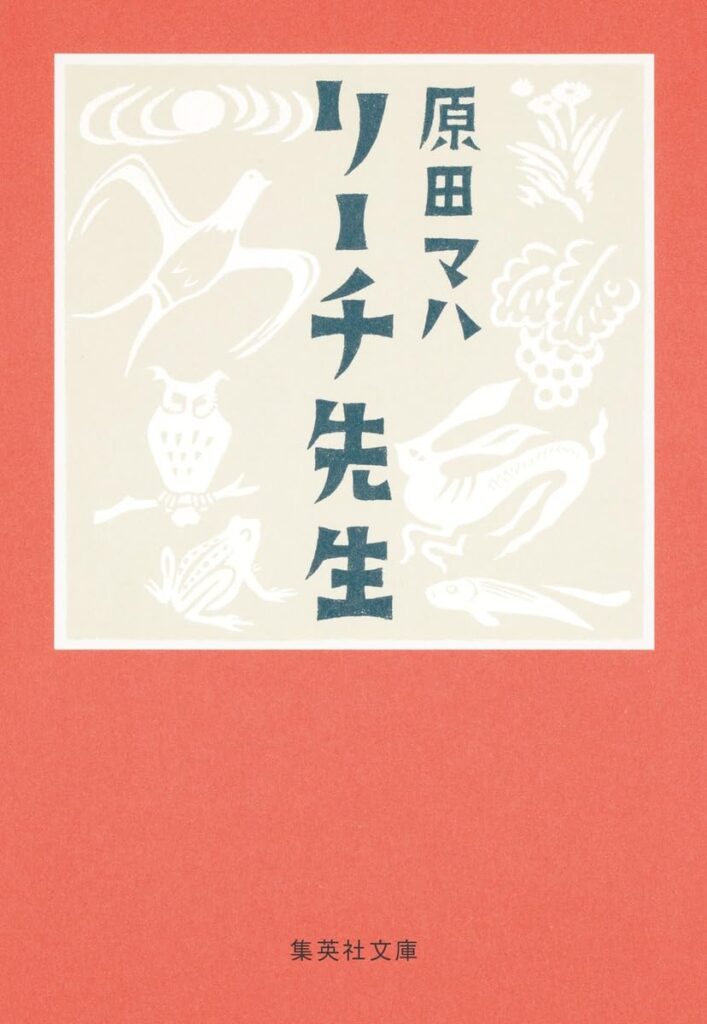
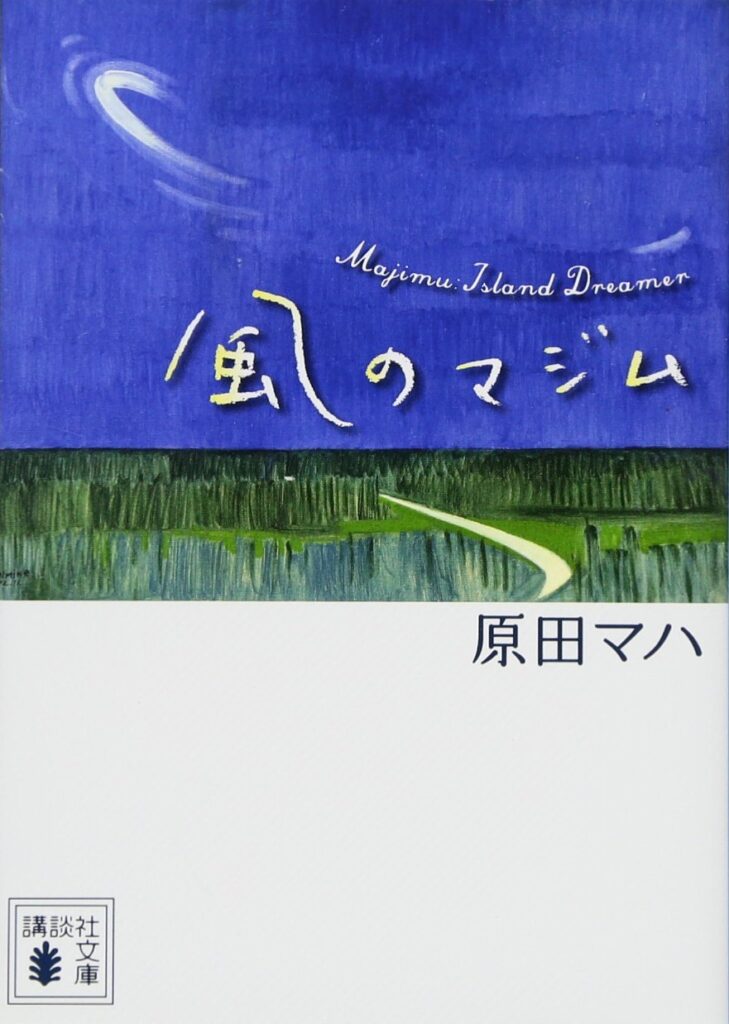
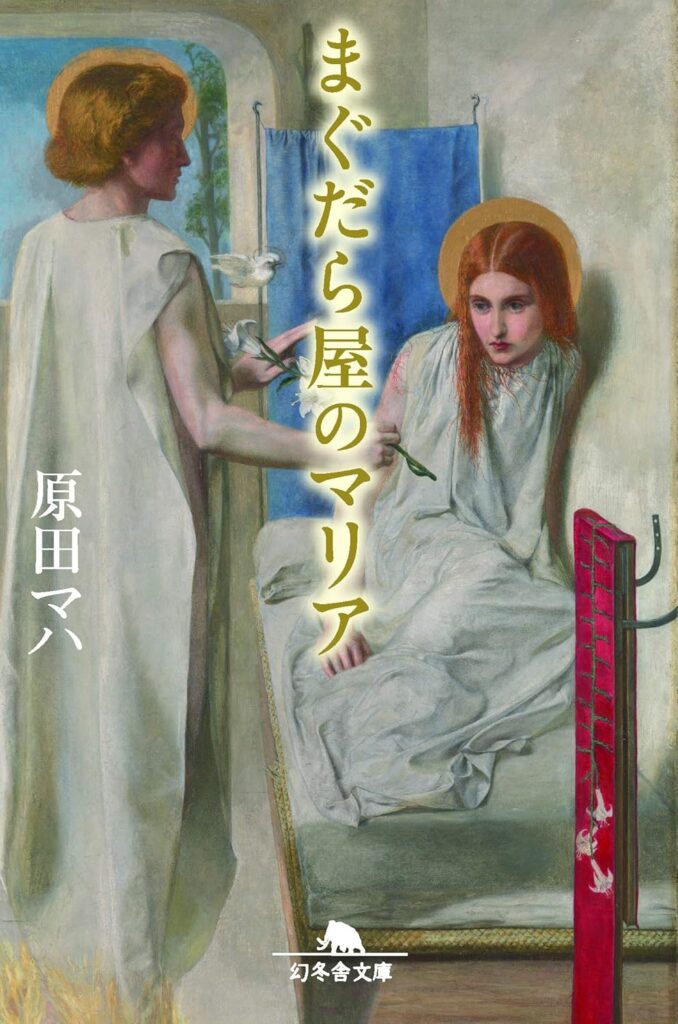
-710x1024.jpg)