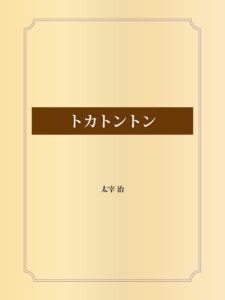 小説「トカトントン」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治が描く、奇妙な幻聴に悩まされる青年の物語は、一度読むと心に深く引っかかり続ける、不思議な魅力を持っています。
小説「トカトントン」のあらすじをネタバレ込みで紹介します。長文感想も書いていますのでどうぞ。太宰治が描く、奇妙な幻聴に悩まされる青年の物語は、一度読むと心に深く引っかかり続ける、不思議な魅力を持っています。
この物語は、ある青年が敬愛する作家へ宛てた手紙という形式で進みます。彼の悩みは深刻で、何かに心を動かされ、感動や意欲が最高潮に達しようとすると、どこからともなく「トカトントン」という金槌で釘を打つような音が聞こえてくるというのです。そして、その音を聞くと、たちまち興が醒め、すべてがどうでもよくなってしまう。
戦後の混乱と虚無感が漂う時代背景の中で、この不可解な音は何を意味するのでしょうか。青年の苦悩は、単なる神経衰弱なのでしょうか、それとももっと深い、時代の病のようなものを映し出しているのでしょうか。この記事では、物語の結末に触れながら、その核心に迫っていきたいと思います。
読み進めていただく中で、もしかしたらあなたの中にも、この「トカトントン」という音に似た感覚を覚える瞬間があるかもしれません。青年の手紙に込められた切実な問いと、それに対する作家の応答を追いながら、この作品が持つ現代的な意味についても考えていきましょう。
小説「トカトントン」のあらすじ
物語は、「拝啓 一つだけ教えてください。困っているのです。」という一文から始まる、ある青年から作家へ宛てた手紙の形でつづられます。差出人の「私」は二十六歳、青森の寺町にある花屋の次男で、中学卒業後、軍需工場勤務、そして四年間の軍隊生活を経て、終戦と共に故郷の焼け跡に戻ってきました。
現在は、父や兄と共に、青森市から少し離れた海岸の部落で、母方の叔父が局長を務める三等郵便局に勤めて一年になります。しかし、「私」は日増しに自分がくだらない人間になっていくような焦燥感に駆られ、悩みを抱えています。彼は、手紙の宛先である「あなた」(作家)の作品を軍需工場時代から愛読しており、作家がかつて自分の故郷近くにいたこと、そして終戦後も近くに住んでいることを知り、強い親近感を覚えています。
「私」の苦悩の中心にあるのが、「トカトントン」という幻聴です。最初にこの音を聞いたのは、終戦の日。玉音放送の後、若い中尉が抗戦と自決を訴え、「私」も死を決意しかけた瞬間でした。背後から聞こえてきた金槌のような音は、彼の悲壮な決意を霧散させ、すべてを白々しく感じさせました。
それ以来、何かに感動したり、奮い立とうとしたりする度に、この「トカトントン」が聞こえ、あらゆる意欲が削がれてしまうようになりました。小説を書いて作家に読んでもらおうと百枚ほど書き進めた時も、完成間近でこの音が聞こえ、原稿を鼻紙にしてしまいました。仕事に打ち込もうとしても、恋愛感情が高まっても、労働者のデモに心を揺さぶられても、駅伝選手の力走に感動しても、必ずこの音が現れて台無しにしてしまうのです。
「私」は、この音の正体と、それから逃れる術を作家に問いかけます。しかし、手紙の最後で衝撃的な告白をします。この手紙を書いている間にも「トカトントン」が聞こえ、あまりのつまらなさに嘘ばかりを書いた気がする、と。恋をした花江という女性も、見たというデモも、その他のことも大部分が嘘かもしれない。ただ、「トカトントン」という音が聞こえることだけは、嘘ではないようだ、と結びます。
この手紙を受け取った作家は、「私」の苦悩を「気取った苦悩」と評し、あまり同情しないと述べます。そして、「私」がいかなる弁明も成立しない醜態、つまり我を忘れて熱中することを恐れ、避けているのだと指摘します。最後に、マタイ伝の一節「身を殺して霊魂(たましい)をころし得ぬ者どもを懼るな、身と霊魂とをゲヘナにて滅し得る者をおそれよ」を引用し、このイエスの言葉に衝撃を受けることができれば、幻聴は止むはずだと返答するのでした。
小説「トカトントン」の長文感想(ネタバレあり)
読後、なんともいえない奇妙な感覚と、重たいような、それでいてどこか乾いたような余韻が残る。それが、太宰治の「トカトントン」を読んだ私の率直な気持ちです。手紙という形式で語られる青年の告白と、それに対する作家の応答。物語はシンプルですが、その中に含まれる問いかけは深く、読む者の心に様々な波紋を広げます。
まず、この物語の核心である謎の幻聴「トカトントン」。この音はいったい何なのでしょうか。単なる青年の神経衰弱の症状と片付けることもできるかもしれません。しかし、この音が鳴るタイミングがあまりにも象徴的です。終戦の詔勅を聞き、死をも覚悟しようとした瞬間。創作への情熱が燃え上がった時。淡い恋心が芽生えた時。社会的な運動に共感を覚えた時。スポーツに純粋な感動を見出した時。人生における重要な局面、感情が高ぶり、何かが変わろうとするその瞬間に、決まってこの乾いた金槌の音が響き、すべてを台無しにしてしまうのです。
これは、戦後の日本が覆われていた虚無感や無力感の象徴と考えるのが自然かもしれません。大義のために命を捧げることを求められた戦争が終わり、信じていた価値観が崩壊した時代。これから何を信じ、何に情熱を傾ければ良いのか分からない。そんな時代の空気が、「トカトントン」という形で青年の内面に響いているのではないでしょうか。何かを始めようとしても、「どうせ無駄だ」「馬鹿馬鹿しい」という冷めた声がどこかから聞こえてくる。それは、彼個人の問題であると同時に、時代の病理でもあったのかもしれません。
主人公である「私」の苦悩について、手紙を受け取った作家は「気取った苦悩」であり、「あまり同情してはいない」と、かなり手厳しい評価を下します。確かに、「私」の語りには、どこか自己憐憫や、自分は特別に繊細な感受性の持ち主なのだ、と言いたげな響きが感じられなくもありません。感動しやすい一方で、その感動を持続させることができず、すぐに冷めてしまう。熱中できない自分、本気になれない自分を、幻聴のせいにして正当化しているようにも見えます。
小説を書こうとしても、恋愛をしようとしても、仕事に打ち込もうとしても、あと一歩のところで「トカトントン」が聞こえてきて挫折する。この繰り返されるパターンは、彼が本質的に「我を忘れる」こと、何かに完全に没入することを恐れている証拠なのかもしれません。作家が指摘するように、「いかなる弁明も成立しない醜態」をさらすことを無意識に避け、幻聴という便利な言い訳を作り出している。そう考えると、作家の指摘は冷たいようでいて、的を射ている部分もあるように思えます。
物語の中で、「私」は郵便局に貯金に来る旅館の女中、花江さんに恋心を抱きます。彼女の境遇を知り、「この人となら、どんな苦労をしてもいい」と決意するのですが、まさにその感動の頂点で「トカトントン」が鳴り響き、彼は「それじゃ、失敬」と冷たく立ち去ってしまう。この場面は、「私」の抱える問題点を端的に示しています。もし花江さんが実在の人物だったとしたら、彼の態度はあまりにも無責任で、相手を深く傷つけるものでしょう。
しかし、手紙の最後で「私」は、花江さんという女性は本当はいないかもしれない、と告白します。デモを見たのも、その他のことも、大部分が嘘かもしれない、と。この告白は、読者をさらに混乱させます。では、この手紙全体が「私」による創作、フィクションだったのでしょうか?もしそうなら、彼の苦悩そのものが、一種の「作り話」だったということになります。トカトントンという音だけは嘘ではない、と言いますが、それすらも疑わしくなってきます。
なぜ「私」は、最後にこのような告白をしたのでしょうか。それは、手紙を書くという行為そのものに対する「トカトントン」だったのかもしれません。自分の苦悩を真剣に訴えようとしたけれど、それすらも「つまらない」「馬鹿馬鹿しい」と感じてしまい、すべてを相対化してしまった。あるいは、作家に対して自分の内面をさらけ出すことへの羞恥心や自己防衛が働いたのかもしれません。または、最初からこの手紙自体を一つの文学作品として構想し、読者を翻弄する仕掛けとしてこの結末を用意したとも考えられます。
そして、この奇妙な手紙に対する作家の返信です。マタイによる福音書の一節、「身を殺して霊魂(たましい)をころし得ぬ者どもを懼るな、身と霊魂とをゲヘナにて滅し得る者をおそれよ」。これは、肉体の死や他人の評価を恐れるのではなく、魂までも滅ぼす力を持つ絶対的な存在(神)を畏れよ、という意味合いで解釈されることが多い言葉です。作家はこれを引用し、「このイエスの言に霹靂(へきれき)を感ずることができたら、君の幻聴は止むはずです」と結びます。
この返信は、「私」にとって救いとなるのでしょうか。作家は、「私」が恐れているのは表面的な失敗や他人の目であり、本当に恐れるべきもの、対峙すべきものから目を背けている、と言いたいのかもしれません。「トカトントン」という自己防衛的な幻聴に逃げ込まず、魂を揺さぶられるような真の体験、たとえそれが破滅につながる可能性があったとしても、それに身を投じる勇気を持て、と。ゲヘナ(地獄)で魂ごと滅ぼされる可能性を恐れるほどの覚悟で、物事にぶつかってみろ、ということでしょうか。
しかし、この返信は非常に難解で、突き放したような印象も与えます。ある意味で、「私」の苦悩の本質を見抜き、厳しいながらも的確なアドバイスを与えているようにも見えますが、一方で、具体的な解決策を示すわけではなく、かえって「私」を混乱させ、さらなる思索の迷宮へと誘い込む可能性も否定できません。この作家の言葉が、「私」にどのような影響を与えたのか、物語はそこまで語ってくれません。
この作品を読む上で、作者である太宰治自身と、手紙の書き手である「私」、そして手紙の受取人である「作家」の関係性も気になるところです。太宰自身、読者からの手紙に触発されてこの作品を書いたと言われています。「私」の抱える苦悩や、熱中と冷却を繰り返す性質には、太宰自身の姿が投影されている部分もあるのかもしれません。また、「作家」の返信には、太宰自身の文学観や人生観、あるいは読者に対するある種の突き放した態度が表れているようにも感じられます。
やはり、この作品の背景にあるのは、敗戦という大きな出来事がもたらした時代の空気です。それまでの価値観が根底から覆され、人々が精神的な支柱を失った時代の虚無感、無力感。「私」が経験する「トカトントン」は、そうした時代精神が生み出した幻影であり、多くの人が程度の差こそあれ、共有していた感覚だったのではないでしょうか。「ミリタリズムの幻影」が剥ぎ取られた後に残った、どうしようもない空虚さ。それを太宰は、この奇妙な幻聴を通して鋭く描き出したのだと思います。
「私」は、虚無感に抗おうと、様々なことに感動し、熱中しようと試みます。しかし、その度に「トカトントン」という内なる声(あるいは外からの音)によって阻まれてしまう。それでも彼は、最終的には嘘かもしれないと断りつつも、自分の苦悩を手紙に書き、作家に送るという行為に及びます。この行為自体が、完全な虚無への抵抗であり、かすかな希望の表れと見ることもできるかもしれません。
手紙とその返信という形式も、この作品の独特な味わいを深めています。読者はまず、「私」の切実な(ように見える)告白に引き込まれ、共感したり、あるいは苛立ちを感じたりします。そして最後の告白で一旦突き放され、さらに作家の難解な返信によって、再び考えさせられる。一方通行のようでいて、読者との間に複雑な対話を生み出すような構成になっています。
そして、この物語は決して過去のものではありません。現代社会においても、「何かを始めたいけれど、どうせ意味がない」「熱くなりたいけれど、冷めた自分がいる」といった感覚、無気力感やシニシズムに囚われてしまうことは、誰にでもあるのではないでしょうか。「トカトントン」という音は、形を変えて現代人の心の中にも響いているのかもしれません。そう考えると、この作品は時代を超えた普遍的なテーマを扱っていると言えるでしょう。
読み終えて改めて思うのは、この作品が持つ多層的な解釈の可能性です。不条理文学のようでもあり、心理描写の巧みな私小説のようでもあり、時代の証言のようでもある。明確な答えや救いが示されるわけではなく、むしろ問いを投げかけられたまま、読者は作品世界から放り出されるような感覚を覚えます。しかし、その割り切れなさ、不可解さこそが、「トカトントン」という作品の抗いがたい魅力なのかもしれません。
太宰治という作家の、人間の弱さや醜さ、そして時代の空気に対する深い洞察力を感じずにはいられません。ただ面白い、感動するというだけでなく、読後にずっしりとした何かを残し、考え続けさせる力を持った作品です。一度読んだだけでは掴みきれない深みがあり、再読するたびに新たな発見があるような気がします。
まとめ
この記事では、太宰治の短編小説「トカトントン」について、結末までの詳しいいきさつと、私なりの考察を交えた感想をお話しさせていただきました。戦後の虚無感を背景に、謎の幻聴「トカトントン」に悩まされる青年の苦悩が、読者からの手紙という形式で描かれています。
物語の中心にある「トカトントン」という音は、単なる幻聴というだけでなく、時代の空気や、何かへの熱中を阻む内なる声、あるいは虚無感そのものの象徴としても解釈できます。主人公「私」が様々な感動や決意の瞬間にこの音を聞き、意欲を失ってしまう描写は、読んでいてやるせない気持ちになります。
また、手紙の最後で「私」が内容の多くが嘘かもしれないと告白する点や、それに対する作家の難解な返信(マタイ伝の引用)は、この物語にさらなる深みと解釈の幅を与えています。「私」の苦悩は本物なのか、作家の言葉は救いなのか。読者は様々な問いを投げかけられたまま、物語の余韻に浸ることになります。
「トカトントン」は、戦後という特定の時代を描きながらも、現代にも通じる無気力感や虚無感といった普遍的なテーマを扱っており、読む者の心に強く訴えかける力を持っています。太宰治の文学に触れる上で、ぜひ読んでいただきたい、考えさせられる一作だと思います。




























































